世界の終わりに、この世の果てまで。
02雨上がりの夜空に
02 雨上がりの夜空に。
町を出てから、かれこれ一時間。私達は国道の沿岸を歩き続けている。
たった一時間歩いただけなのに、辺りの景色からはほとんど生活の臭いは感じられなくなった。
見えるものは、切り立った山の斜面と海だけだ。まだ九時頃だというのに、あまりにも静かすぎる。
「今日中に県境を越えるのは、ちょっと無理かもね」
後ろを歩く繭歌に振り返る。
「うう……そう……だね。そう……かも……だね」
繭歌の額からは、大粒の汗が噴出していた。息もかなりあがっているし、今にも倒れそうなぐらい表情も辛そうだ。
「あのさ……繭歌。私、交代しようか?」
「い、いい。大丈夫。ぜんっぜんだいじょぶだよ」
「なら、良いんだけどさ」
こんなやりとりを、この一時間のうちに、かれこれ10回は繰り返している。
運動部に入っていた私のほうが、繭歌より体力はあるだろうし。体力のあるうちに、繭歌の負担を軽くできるなら、その方が良い。と、私は考えているのだけど……。
なかなか繭歌は交代してくれない。
新しく繭歌についてわかったのは。結構、頑固だって事だ。
「うーん。なんか、良い方法ないかなぁ」
私は思案する。
このままでは、どう考えても隣の県まで繭歌の体力がもたない。
もし途中で私が無理矢理に繭歌から荷物を引き剥がして交代したとしても。やっぱり、朝までに到着するのは難しいと思う。
女の子の二人旅だ。体力勝負の無茶な計画は立てられない。
結局のところ。武器といえるのは、若さとかやる気だけなのだ。
「ねぇ、繭歌」
「なにー……」
掠れた声の繭歌に近づき。私は鞄からミネラルウォーターを取り出す。
キャップを開けて繭歌に渡すと。よっぽど喉が渇いていたのか、凄い勢いで繭歌は飲みはじめた。
「ちょっとさ、考えたんだけど……ヒッチハイクしない?」
「くふ、ヒッチハイクぅ?」
少しむせながら、繭歌は大袈裟に驚いた。
「うん。だってこのまま歩いて移動するのってやっぱ無理があると思うんだ」
「でもさ、でもさ。やっぱ一歩ずつ歩いて行く感じっていうかさ。なんかさ、そういう苦労があったほうが、目的を達成した時の感動っていうかさ。そういうのが大きいのじゃないかなー」
「じゃあ、この先もずっと繭歌はその重い荷物を背負って歩くわけ?」
「べ……べっつにぃ。私はまだまだ余裕だもん」
まだ言うか。
こっちは、繭歌の事心配して言ってるっていうのに。
「ふーん。でも、私は車が止まってくれたら、さっさと乗っちゃうけどね」
「えー……七海ちゃんずるい」
「ずるくないよ。繭歌が勝手に意地張ってるだけでしょ」
「むぅ……七海ちゃんがそう言うなら……」
口を尖らせて。繭歌はくぴくぴとミネラルウォーターに口をつけながら黙ってしまった。
「じゃあ。ここで車が通るの待つからね」
私は地面に腰を下ろす。さっきまで降っていた雨のせいか、アスファルトは少し湿っていた。
走ったり、たくさん歩いたせいで、なんだか足が重い。むくみをとるために、軽くマッサージする。
「う、うんー。わかったよぉ」
拗ねてるようだけど。素直に私に続いて、繭歌も腰を下ろした。大きなリュックを前に置き。クッションのように抱えている。
二人並んで。車が通るのを待つ。けれど、聞こえるのは道路沿いの波音だけで、一向に車がやってくる気配はない。
「読みが甘かったかなぁ」
私も喉が渇いたので、繭歌の持っているペットボトルを取り上げる。
「あー!」
残っていたミネラルウォーターを飲み始めると、繭歌が大きな声をあげた。
「そんな大声出さなくてもいいじゃん。元々、私のなんだからさ」
「そうじゃなくてー。七海ちゃん口つけた」
くち?
繭歌はまじまじと、私の持つボトルの飲み口を見つめている。
ああ、なるほど。繭歌が飲んだ後に私が口を付けたって事か。
「別にいーじゃん。そんなに気にする事じゃないでしょ。女同士なんだしさ」
「それはそうだけどぉ……間接キスって。ちょっと、どきどきしちゃうよねー」
「ちょっと、間接キスとか恥ずかしい事言わないでくれる?」
「だってぇー」
まったく。何が、「だって」なんだか……。
手に持ったペットボトルの飲み口を、まじまじと見てしまう。
本当なら、別に気にするような事じゃないんだけど。繭歌が変な事言うから、なんだか意識してしまう。
結局、私は一口飲んだだけで、ペットボトルに蓋をした。
町を出てから、かれこれ一時間。私達は国道の沿岸を歩き続けている。
たった一時間歩いただけなのに、辺りの景色からはほとんど生活の臭いは感じられなくなった。
見えるものは、切り立った山の斜面と海だけだ。まだ九時頃だというのに、あまりにも静かすぎる。
「今日中に県境を越えるのは、ちょっと無理かもね」
後ろを歩く繭歌に振り返る。
「うう……そう……だね。そう……かも……だね」
繭歌の額からは、大粒の汗が噴出していた。息もかなりあがっているし、今にも倒れそうなぐらい表情も辛そうだ。
「あのさ……繭歌。私、交代しようか?」
「い、いい。大丈夫。ぜんっぜんだいじょぶだよ」
「なら、良いんだけどさ」
こんなやりとりを、この一時間のうちに、かれこれ10回は繰り返している。
運動部に入っていた私のほうが、繭歌より体力はあるだろうし。体力のあるうちに、繭歌の負担を軽くできるなら、その方が良い。と、私は考えているのだけど……。
なかなか繭歌は交代してくれない。
新しく繭歌についてわかったのは。結構、頑固だって事だ。
「うーん。なんか、良い方法ないかなぁ」
私は思案する。
このままでは、どう考えても隣の県まで繭歌の体力がもたない。
もし途中で私が無理矢理に繭歌から荷物を引き剥がして交代したとしても。やっぱり、朝までに到着するのは難しいと思う。
女の子の二人旅だ。体力勝負の無茶な計画は立てられない。
結局のところ。武器といえるのは、若さとかやる気だけなのだ。
「ねぇ、繭歌」
「なにー……」
掠れた声の繭歌に近づき。私は鞄からミネラルウォーターを取り出す。
キャップを開けて繭歌に渡すと。よっぽど喉が渇いていたのか、凄い勢いで繭歌は飲みはじめた。
「ちょっとさ、考えたんだけど……ヒッチハイクしない?」
「くふ、ヒッチハイクぅ?」
少しむせながら、繭歌は大袈裟に驚いた。
「うん。だってこのまま歩いて移動するのってやっぱ無理があると思うんだ」
「でもさ、でもさ。やっぱ一歩ずつ歩いて行く感じっていうかさ。なんかさ、そういう苦労があったほうが、目的を達成した時の感動っていうかさ。そういうのが大きいのじゃないかなー」
「じゃあ、この先もずっと繭歌はその重い荷物を背負って歩くわけ?」
「べ……べっつにぃ。私はまだまだ余裕だもん」
まだ言うか。
こっちは、繭歌の事心配して言ってるっていうのに。
「ふーん。でも、私は車が止まってくれたら、さっさと乗っちゃうけどね」
「えー……七海ちゃんずるい」
「ずるくないよ。繭歌が勝手に意地張ってるだけでしょ」
「むぅ……七海ちゃんがそう言うなら……」
口を尖らせて。繭歌はくぴくぴとミネラルウォーターに口をつけながら黙ってしまった。
「じゃあ。ここで車が通るの待つからね」
私は地面に腰を下ろす。さっきまで降っていた雨のせいか、アスファルトは少し湿っていた。
走ったり、たくさん歩いたせいで、なんだか足が重い。むくみをとるために、軽くマッサージする。
「う、うんー。わかったよぉ」
拗ねてるようだけど。素直に私に続いて、繭歌も腰を下ろした。大きなリュックを前に置き。クッションのように抱えている。
二人並んで。車が通るのを待つ。けれど、聞こえるのは道路沿いの波音だけで、一向に車がやってくる気配はない。
「読みが甘かったかなぁ」
私も喉が渇いたので、繭歌の持っているペットボトルを取り上げる。
「あー!」
残っていたミネラルウォーターを飲み始めると、繭歌が大きな声をあげた。
「そんな大声出さなくてもいいじゃん。元々、私のなんだからさ」
「そうじゃなくてー。七海ちゃん口つけた」
くち?
繭歌はまじまじと、私の持つボトルの飲み口を見つめている。
ああ、なるほど。繭歌が飲んだ後に私が口を付けたって事か。
「別にいーじゃん。そんなに気にする事じゃないでしょ。女同士なんだしさ」
「それはそうだけどぉ……間接キスって。ちょっと、どきどきしちゃうよねー」
「ちょっと、間接キスとか恥ずかしい事言わないでくれる?」
「だってぇー」
まったく。何が、「だって」なんだか……。
手に持ったペットボトルの飲み口を、まじまじと見てしまう。
本当なら、別に気にするような事じゃないんだけど。繭歌が変な事言うから、なんだか意識してしまう。
結局、私は一口飲んだだけで、ペットボトルに蓋をした。
「それにしても、一台も通らないねぇ……」
私の気も知らずに。繭歌は疲れた様子で、リュックにあごを乗せて手をぱたぱたと動かしている。
「国道なんだから、一台ぐらい通ってもいいのにね」
その一台が、私達を乗せてくれるとは限らないけど。
待ち続けて、30分は経っただろうか。
ようやく、遠くから近づく車のヘッドライトの光が見えた。
「七海ちゃん。七海ちゃん。車がきたよー」
「う、うん。わかってるって」
私は立ち上がり、迫ってくる車に向けて大きく手を振った。
けれど、自動車はスピードを緩めない。
ドライバーは。通り過ぎる一瞬、私のほうへ視線を送ったけど。そのまま私達なんて見なかったように、走り去ってしまった。
「行っちゃったね」
遠ざかる車のテールランプを見送りながら。繭歌はぽつりと呟く。
「うん。行っちゃったね」
私もなんだか、一気に疲れが肩にのしかかってきて。力無く呟いた。
最初から上手くいくとは思っていなかったけど。まさか、こんなにノーリアクションで豪快に無視されるなんて。世の中は、やっぱりそんなには甘くないみたいだ。
まだ、一台目なのに。早くも気持ちが折れそうになる。
「どうするぅ?七海ちゃん」
「うーん。もう少しだけ待ってみても……いい?」
自分から言い出した意地もあって。往生際悪く、私は繭歌にくい下がる。
「私は別に待ってもいいけどー」
んー。と、大きく伸びをして。繭歌は再び、リュックの上に体重を預けた。目に見えて退屈しているのがわかる。
「次の車が駄目だったら、私も諦めるから」
「らじゃー」
そして、私達は再び車が通るのを待つ事にした。
けれど、やっぱり。というか、予想通りに車の気配はない。
さっきの車が奇跡の一台なんじゃないか?と思えるぐらいに、国道には私と繭歌以外の気配を感じない。
隣では、退屈を紛らわすためか。繭歌がせわしなく携帯を弄っていた。
かちかちかち、と。携帯電話のキーを押す音が聞こえる。
「繭歌。今からそんなに携帯使ってたら、電池なくなっちゃうよ?」
「うんー。わかってるんだけどさ、ネットの友達のブログとかチャットもチェックしておきたいし。あと、巡回サイトとかコミュとかも更新してないかなーとか気になるじゃん」
「別にいいけどさ。肝心な時に使えない。なんて事ないようにしなよ」
私は、そういうネットの世界には疎いので。繭歌の言う、ブログだとかチャットだとかがどれぐらい大切なのかわからない。
けれど、両親が若い頃には。ネットの中で出会った人達が結婚したり、付き合ったりするのが。流行ったらしい。ネットの中の出会いや繋がりも、現実の繋がりと同じように大事に思える時代だったんだよ。なんてお父さんもお母さんも言ってたっけ。
両親が、そうやってネットで知り合ったカップルなのかは、さすがに怖くて聞けなかったけど……。
そんな話を聞くと、随分ん昔の事のように思うけど。
以前に聞いたクラスメイトの会話を聞く限り、今も昔もネットの使い方なんて、そんなに大きく変っていないと思う。
異性との出会いの場だったり。ゲームソフトや音楽のデータを不正に手に入れて楽しんだり。ブログを開いたり、ネットで自分の声を配信したり……とかとかとか。
まぁ、現代っ子と呼ばれる世代の割に、私はパソコンの使い方がいまいちよくわからないので。
クラスメイトにネットの楽しさを語られても、ピンとこなかったのを覚えている。
「でも、今ってネットとかするのにも制限かかってるんじゃなかったっけ?」
「んー?ああ、それって。世界が終わるかもってニュースで出だした頃の話だよ。運営会社がいくつか潰れちゃったからね。確かに、接続はしにくくなったけど。ネット自体は生きてるから。あんまり関係ないかなー」
テレビ番組とかはどんどんなくなってるのに、ネットの世界は相変わらずって事か。
健全なんだか、不健全なんだか……。
「なんか、繭歌。楽しそうだね」
「そうかな?どうだろ……そりゃあ、町を出てもネットの友達はいつもと変らないからねー。そういう、みんなの会話を見てると、ちょっと安心するっていうのはあるかもかな」
「何?私じゃ不満だって事?」
ちょっと意地悪に聞いてみる。
「や、そういうのじゃなくてさ。えとえと。だから、七海ちゃんは側にいてくれるわけだから。リアルな安心っていうかさ。ネットの友達は、たくさんいるけど……いざって時には頼れないっていうか」
「そんなに必死になんなくてもいいって」
「だってさー。七海ちゃんに嫌われたくないもん」
「や、別にそんな事で嫌いになったりとかしないから」
私には私の付き合いがあるように。繭歌には繭歌の。私の知らない付き合いがあるのは当然だ。
自分だけが誰かの一番だ。なんて、そんな風に思い上がれるほど私は図々しくない。
「うし。おしまい」
キーを打つのを止め。繭歌は携帯を畳むと、リュックのポケットに仕舞った。
「もういいの?」
「うん。ほら、電池とかやばそうだし」
焦ったような、困ったような顔で。繭歌は笑って誤魔化した。私は呆れて溜息を吐く。
「だから言ったじゃん」
「あ、ほら。七海ちゃん、また車がきた」
「もう。そんなにタイミングよく来るわけ……」
繭歌の指すほうを、とりあえず見ると。そこには確かに、ヘッドライトの明りがあった。
随分と大きなライトは多分、大型のトラックか何かだろうか?
遠くからでも聞こえる排気音を立てて、ぐんぐんとこちらに近づいて来る。
今度こそ、逃すわけにはいかない。乗せてくれないとしても、せめて話ぐらいは聞いてくれたっていいはずだ。
体全体を道路側へ大きく乗り出すようにして、私は目一杯、両手を大きく振った。
「おーい。止まってよぉー」
待ちぼうけに飽きていた繭歌も、私に続く形でトラックに手を振っている。
トラックの運転手は、私達を見つけたのか。耳を塞ぎたくなるような大きな音で、何度かクラクションが鳴らされた。
怪獣の鳴き声みたいな音に驚いて、私達は歩道側に飛び退く。
急に大きな音を聞いて、どきどきする胸を押さえながら。私はトラックの後ろ姿を目で追った。
また、駄目だったかぁ。
肩を落としていると、20メートルほど離れた場所に。今、私達の目の前を通り過ぎたばかりのトラックが、ゆっくりと速度を落として停車した。
「七海ちゃん。トラック止まってくれたよ」
「う、うん」
乗せて……もらえるのかな?
でも、止まってくれたという事は、少なくとも私達に興味を持ってくれたって事だろうし……。
「繭歌、行くよ。事情だけでも話してみよ」
「そだよね。ちょっとの距離でも乗せてもらえるかもしれないもんね」
互いに荷物を持って。慌ててトラックに駆け寄る。
大きな荷台を持ったトラックを見上げると、開いた窓から運転手が待ち構えていた。
「なんや、お嬢ちゃんら。いくら広い道路でも、あない道に出てきよったら危ないやないか」 テレビでしか聞いた事の無い関西弁で話しかけられる。
坊主頭に、首には太い金色のネックレス。顔は……お世辞にも優しそうには見えない。 正直に言えば……怖い。
年齢は、私のお父さんと同じぐらいかな?私達から見るとおじさんと呼ぶのがしっくりくる感じだ。
「あの、私達。二人で旅行してるんですけど。良かったら乗せてもらえませんか? その……行けるところまでで良いので」
「良いのでー」
さすがに、世界の果てというなんだか良くわからない場所を目指して、家を抜け出してきた家出少女二人組みです。なんて、馬鹿正直に話すわけにもいかない。なので、多少の嘘を交えつつ私はおじさんに説明する。
繭歌は交渉を私に任せるつもりなのか、隣で愛想笑いだかなんだかよくわからない曖昧な笑顔をおじさんにへらへらと向けている。
「へぇ、こんなご時世に旅行とは。なんや物好きやなぁ……それで、ヒッチハイクっちゅうわけか」
「そうなんです。こんな時だからこそ、せっかくだから見た事の無い場所を見に行こうと思って。見聞を広げたいというか、悔いのないように生きたいというか……」
やばい。自分でも何を言っているのか、わけがわからなくなってきた。さすがに、適当過ぎたかな。
「そうか、そうかぁ。なんや、青春やなぁ。やっぱり若いうちはそれぐらい行動力ないとなぁ」
適当な私の説明を、おじさんはえらく真剣な顔で聞きながら、深く何度も頷く。
そんなに真面目に聞かれると、嘘をついてるだけに、なんとも心苦しい。
「おじさん。乗せてってよぉー。おねがーい」
やたら鼻にかかったような甘い声で、繭歌も会話に参加してくる。
確かに、繭歌の声はもともと高いけれど。それを更に高くしたような、本当にアニメに出てきそうな声だ。わざと作っているのがわかる。
何かのキャラクターの真似……なのだろうか?
「そうやなぁ……」
自分の頭をぱしぱしと叩いて、おじさんは深く目を瞑った。
「駄目……ですか?」
これ以上引き止めるのは、なんだか悪い。
私達の用件は伝えたし、それでも駄目だと言うなら。それは、潔く諦めるしかない。
また、次の車が通るのを待つか。それとも、重い荷物を背負う繭歌を連れて、とにかく県境を徒歩で目指すか。
どちらにせよ。考えるだけで、とても疲れてくる。
「わかった」
癖なのか。自分の頭をまた叩いて、おじさんは目を開けた。
「俺も仕事があるさかい。ほんまに、乗せられるとこまでになるけども。それでええんやったら」
「ほんとですか」
おじさんの返答に、自然と声が弾んでいるのが、自分でもわかる。
「顔は怖いけど、良い人でよかったねー」
「こ、こら」
慌てて、私は繭歌の口を塞いだ。余計な一言でおじさんの機嫌を損ねては、たまったものじゃない。
「ははは。まぁ、顔は怖いてよう言われるわ」
う……おじさんに聞かれてるし。
でも、おじさんは気にしてないのか。大きく口を開けて。豪快に笑っている。
「さ、話は決まったんやし。さっさと出発するで」
トラックのドアをおじさんは開けて、手招きで私達に乗り込むように促す。
ドアの下に付いている足掛けに体重を乗せる。家の車と全然違って、凄く乗りにくい。乗るというより、どちらかというと、登るような感じだ。
「お、お邪魔します」
座席はコンビニの袋だとか、飲み終わったビールの缶だとかが散乱していた。それに、染み付いた煙草の匂いが鼻を突いた。
「ああ、ごめんな。普段は俺だけしかおらんから、散らかってんねん。足元のスペースは適当に自分で作ってな」
「はい……」
そうは言っても。いくらゴミとはいえ、足で蹴るわけにもいかず。私は足元のゴミ袋を少しだけ爪先でずらして、小さなスペースをなんとか確保した。
私も、部屋の掃除とか苦手なほうだけど。さすがに、これは汚すぎると思う。
「うー……七海ちゃん。助けてー……」
繭歌はまだ乗り込めずに、ドアの下でぴょんぴょん跳ねて助けを求めていた。
「もう、何してるのさ。早く乗りなよ。おじさん、待ってくれてるんだから」
「わかってるけどさー。リュ、リュックが。リュックがー」」
ああ、そっか。リュックの重さで繭歌は足掛けから動けないのか。
ほんと、手がかかるんだから。
「ほら、じゃあ。私が先にリュック受け取るから」
「うんー。七海ちゃんありがとね」
後ろに倒れこみそうになりながら、繭歌がリュックを渡してくる。
ずしりとした重みに、腕が引っ張られる。これは確かに重い。
繭歌の事だから、考えもなしに缶詰ばっかり買ったに違いない。そうでなければ、ここまで重くなるはずがない。
とはいえ、これから先。私も繭歌の買った食糧にお世話になるのだから、あまり強くは言えない。
「はぁ、どもども。やっと到着」
乗り込んだ繭歌はリュックを受け取り、足元に強引に押し込めはじめる。
「よっしゃ。ほな、出発するで」
二人が揃ったのを確認して、おじさんはトラックを発車させた。車内が揺れて、ゆっくりと前進をはじめる。
慌ててシートベルトを探して、私と繭歌はそれぞれ装着した。
トラックは国道を黙々と走る。
窓から見える景色は、歩いていた時と変らずとても退屈だ。
それでも、確実に町からは離れている。これで、なんとか最初の難関はなんとかクリアした……かな。
旅はまだ始まったばかりなのに。こんなに苦労するとは思わなかった。
こんな調子で、私達はこれから先。一体どこまで進む事ができるんだろう?
心の中に常に付きまとう不安は晴れない。
「こんな夜に~お前に乗れない、なんてぇ~」
車内は特にこれといった会話もなく、時折思い出したように、それでいて私達に気を遣うように、おじさんが鼻歌を口ずさむ。
知らない曲ではなかったけれど。多分、私達が生まれる前の曲なので、名前までは思い出せなかった。
「俺な。熊田いうねん……お嬢ちゃんらはなんていうん?」
「えっと、七海です」
「繭歌ですです」
鼻歌を中断し、おじさんが急に話しかけてきた。
ずっと沈黙が続いていたので、びっくりしてしまう。
どうやら、おじさんは熊田さんというらしい。
私達も、熊田さんに名前を教える。
「自分の娘ぐらいの歳の子と、何話してええかわからんけど、まぁ……こうやって知り合ったのも何かの縁やろうし、短い間やけど楽しく行こうや」
確かに。
熊田さんの言う通り、せっかく旅の途中で人と会ったのに、黙って外の景色を眺めているだけというのも、なんだか勿体ない気がする。
「熊田さんも娘さんがいるんですか?」
とりあえず、なんでも良いから熊田さんに話を振ってみる。
「おるよ。今年高校二年になったとこかな」
「私達と一緒ですね」
「ははは、まぁ。めっちゃ嫌われてんねんけどな」
「そ、そうなんですか」
私も、お父さんの事を好きじゃないから。複雑な気分だ。
「七海ちゃんはお父さんと仲ええのんか?」
「いえ、あんまり……」
「そうかぁ……」
寂しそうに熊田さんは息と一緒に言葉を吐き出す。
「でも、まぁ……年頃の女の子っていうのはそういうもんなんかもしれへんなぁ」
「みんながそうだとは限らないと思いますけど……」
私がお父さんを嫌いなのは、浮気のせいだし。知り合いの女の子でも、お父さんの事が大好きだと言っている子はたくさんいる。
「ほら、俺ってこんなんやろ?」
熊田さんは自分を指さす。
こんなん。と言われても、熊田さんとはついさっき出会ったばかりなので、よくわからない。
少なくとも、そんなに悪い人には見えないけれど。
「なんちゅーのかな。がさつやし、声でかいし、言葉も……まぁ、汚いしな。おまけに顔もこんなんやし。自分でも、あんまえーとこないなぁって思うんよ。せやから、娘が俺の事嫌いになるんも、わからんでもないわけやな」
「はぁ……」
そういう、ものなのだろうか?そんな理由で、自分のお父さんを嫌いになったりするものなんだろうか?
「熊田さん、優しいのにねー」
いつの間に取り出したのか、ポテトチップをぱりぱりと食べながら、繭歌が口を挟んでくる。思いっきりシートに体を沈め、自分の部屋のように全開でリラックスしていた。
繭歌には遠慮という言葉はないのだろうか?
「ありがとうな。けど、一番嫌われとる理由は。俺がもとヤクザやってとこなんやろな」「えぇ?」
思わず声が裏返る。ヤクザって、あの……ヤクザ?熊田さんが?
そりゃ、顔は確かに怖いけど。まさか、本職の人だったとは……。
人生とは複雑だなぁ。と、それっぽい言葉で納得してみる。
「いや、昔の話やで。今はかカタギやし。ほんまに、ほんまに」
驚く私に気を遣ってか、熊田さんは茶化すように陽気な声で笑って、場を和ませようとする。
「どうして熊田さんはヤクザ屋さんをやめたの?」
私は繭歌の太腿を無言でつねる。
「いたぁっ。何するのさ、七海ちゃん」
「馬鹿じゃないの?あんた馬っ鹿じゃないの?」
「むー、つねられて馬鹿って言われたー」
わけがわからないのか、繭歌はつねられた場所をさすりながら、私を睨んでいる。
「普通、そんな事聞こうと思わないでしょ。空気読みなさいよ」
ひそひそと、繭歌に耳打で叱る。
「そうなの?」
駄目だこりゃ……。
「ごめんなさい」
繭歌に代わって、私は熊田さんに頭を下げる。
「いやいや、かまへんよ。そない気にするような事ちゃうし」
熊田さんは、本当に気にしていないのか。嫌な表情ひとつ見せずに、ひらひらと手を振って笑う。
「なんていうんかな。俺がヤクザやってた頃には、もう仁義も任侠もなくなってるような感じでな。まぁ、それは時代の流れっちゅうやつでしゃーないのかもしれんけど。極道っちゅうよりは、ほんま。ただのチンピラの集まりみたいな感じやったんよ。そやから……その、なんていうんかなぁ。アホらしなったんよね」
「アホらし。ですか」
独特のイントネーション。馬鹿馬鹿しくなった、みたいな意味だろうか?
「誰かの役に立つわけでなし。世間様や家族からは疎まれて、そんなまでして俺何やってんねやろうって。そう思ったんよ」
「それで、運転手さんになったの?」
繭歌はポテトチップスを食べ終わったのか。リュックの中に手を突っ込み。新しいお菓子を探している。
「そやねん。今までの人生を取り戻そう。ほったらかしてた分、これからは家族で旅行に行ったり、娘の学校の行事なんかにもちゃんと顔出そう。親らしいこと、旦那らしい事一杯したろう……そう、思ってたんやけどなぁ……人生ってなかなかうまい事、歯車が噛みあわんもんでなぁ」
熊田さんはそこまで話すと、一旦言葉を区切り。ハンドルの近くに置いてあった煙草の箱に手をかけた。
「一本、ええかな?」
申し訳なさそうに、小さな声で聞かれる。
本当は煙草の煙は苦手だけど。お世話になっている側なので、私は平気な顔を作って頷いた。
繭歌は気にならないのか、もしゃもしゃと相変わらずポテトチップを頬張っている。
窓を大きく開けて、熊田さんは煙草に火をつける。おいしそうに煙を吸ってから、大きく外に向かって吐き出した。
紫煙が風に流されて、景色に溶けていく。
「えーっと。どこまで話したっけな。そう、運送会社に就職も決まってな。これから家族のためにまっとうな金を稼ぐぞって意気込んどったところでな……何が起こったと思う?」
「えっと……」
そんな風に聞かれても。色々と思いつく事はあるけど、下手な事を言えるわけがない。
「娘がな、引き篭もりよってん」
「引き篭もり……ですか」
「俺がヤクザなん学校でバレててな。それで、ずっといじめられとったみたいなんや。俺、そんなんなんも知らんとな。気付いた時には家の中ボロボロになっとったんや。ほんま、アホっちゅーか頭悪すぎて、自分でも笑ってまうよな」
自嘲気味な熊田さんの笑顔を作るけど。その笑顔は見ている私を、どこか悲しい気持にさせた。
「熊田さんの娘さんもさ。味方を作ればいいんだよ。たった一人でも味方がいれば、がんばれると思うんだよね」
ばふっ、と新しいお菓子の袋を開けて。繭歌は良い事を言ったといわんばかりの顔をする。
「誰もがみんな、自分の味方を見つけられるわけじゃないじゃん」
開いたばかりのお菓子の袋に、私は手を突っ込む。繭歌が「あっ」と声をあげたけど、気にせずスナック菓子をニ、三個つまみあげた。
「でもさ、つらい状況だとさ。味方がいないとがんばれないよ。がんばる前に、多分折れちゃうと思うんだよ。私も七海ちゃんがいなかったら折れちゃってたかも」
「え?私?」
まさか、この話の流れで自分の名前が出るなんて思っていなかった。
「そーだよ。私はね、七海ちゃんがいてくれたから学校が楽しくなったし、戦えたんだよ」
照れる事なく、はっきりと言い切る繭歌の言葉に。私が逆に照れてしまう。
「戦えたって……大袈裟に言いすぎだって」
「大袈裟じゃないよ。あの時、七海ちゃんに声をかけてもらうまで、私にとって学校は敵ばっかりだったもん……どこにも、味方なんていなかったもん」
「私は別に何もしてないよ」
私がした事といえば。教室の片隅で、一人で机の上にアニメ雑誌を広げて読んでいた繭歌に声をかけた。
ただ、それだけ。
あの時の私は、好美のグループにいて。その中でも比較的、力をもっていた智子は繭歌の事を毎日のように、気持悪いと愚痴っていたけど。
そんなの、関係なかった。
私が話したいと思った。私が繭歌の事を知りたいと思った。芹沢繭歌の事を知りたいと、私が思ったから。
だから、話しかけた。
繭歌がどう言おうと。どう思っていても。私は何も大した事なんてしていない。
「二人とも仲良しなんやなぁ。でもな、世の中はそんな風に助けてくれる人に恵まれる奴ばっかりと違うんよな」
それは、娘さんの現状と照らし合わせての言葉なんだろう。
深みがあった。
世の中は。自分の居場所に必ず味方がいるなんて限らない。
私の学校にだって、男女問わず大小様々なグループが存在していて。いつも周りには敵しかいないような状況の子だっている。
私も、知らないうちに大きな女子グループに含まれていたけど。見渡したところで、そこには気を許せる子はおろか。味方なんて一人だっていなかった。
ただ、敵意に晒されていなかってっていうだけだ。
大勢に囲まれているからといって、そこが自分の味方ばかりとは限らない。
繭歌は私という味方がいたから大丈夫だったと言った。
でもそんなの。きっと、たまたまで偶然でラッキーなんだと思う。
それは、繭歌と仲良くなれた私自身にだって言える事だし。
だから、繭歌の言ってる事は理想だ。娘さんが一人で部屋に篭ってしまったという現実を見なくてはいけない熊田さんには、残念だけど繭歌の言葉が届くとは思えない。
繭歌に代わって、私は熊田さんに頭を下げる。
「いやいや、かまへんよ。そない気にするような事ちゃうし」
熊田さんは、本当に気にしていないのか。嫌な表情ひとつ見せずに、ひらひらと手を振って笑う。
「なんていうんかな。俺がヤクザやってた頃には、もう仁義も任侠もなくなってるような感じでな。まぁ、それは時代の流れっちゅうやつでしゃーないのかもしれんけど。極道っちゅうよりは、ほんま。ただのチンピラの集まりみたいな感じやったんよ。そやから……その、なんていうんかなぁ。アホらしなったんよね」
「アホらし。ですか」
独特のイントネーション。馬鹿馬鹿しくなった、みたいな意味だろうか?
「誰かの役に立つわけでなし。世間様や家族からは疎まれて、そんなまでして俺何やってんねやろうって。そう思ったんよ」
「それで、運転手さんになったの?」
繭歌はポテトチップスを食べ終わったのか。リュックの中に手を突っ込み。新しいお菓子を探している。
「そやねん。今までの人生を取り戻そう。ほったらかしてた分、これからは家族で旅行に行ったり、娘の学校の行事なんかにもちゃんと顔出そう。親らしいこと、旦那らしい事一杯したろう……そう、思ってたんやけどなぁ……人生ってなかなかうまい事、歯車が噛みあわんもんでなぁ」
熊田さんはそこまで話すと、一旦言葉を区切り。ハンドルの近くに置いてあった煙草の箱に手をかけた。
「一本、ええかな?」
申し訳なさそうに、小さな声で聞かれる。
本当は煙草の煙は苦手だけど。お世話になっている側なので、私は平気な顔を作って頷いた。
繭歌は気にならないのか、もしゃもしゃと相変わらずポテトチップを頬張っている。
窓を大きく開けて、熊田さんは煙草に火をつける。おいしそうに煙を吸ってから、大きく外に向かって吐き出した。
紫煙が風に流されて、景色に溶けていく。
「えーっと。どこまで話したっけな。そう、運送会社に就職も決まってな。これから家族のためにまっとうな金を稼ぐぞって意気込んどったところでな……何が起こったと思う?」
「えっと……」
そんな風に聞かれても。色々と思いつく事はあるけど、下手な事を言えるわけがない。
「娘がな、引き篭もりよってん」
「引き篭もり……ですか」
「俺がヤクザなん学校でバレててな。それで、ずっといじめられとったみたいなんや。俺、そんなんなんも知らんとな。気付いた時には家の中ボロボロになっとったんや。ほんま、アホっちゅーか頭悪すぎて、自分でも笑ってまうよな」
自嘲気味な熊田さんの笑顔を作るけど。その笑顔は見ている私を、どこか悲しい気持にさせた。
「熊田さんの娘さんもさ。味方を作ればいいんだよ。たった一人でも味方がいれば、がんばれると思うんだよね」
ばふっ、と新しいお菓子の袋を開けて。繭歌は良い事を言ったといわんばかりの顔をする。
「誰もがみんな、自分の味方を見つけられるわけじゃないじゃん」
開いたばかりのお菓子の袋に、私は手を突っ込む。繭歌が「あっ」と声をあげたけど、気にせずスナック菓子をニ、三個つまみあげた。
「でもさ、つらい状況だとさ。味方がいないとがんばれないよ。がんばる前に、多分折れちゃうと思うんだよ。私も七海ちゃんがいなかったら折れちゃってたかも」
「え?私?」
まさか、この話の流れで自分の名前が出るなんて思っていなかった。
「そーだよ。私はね、七海ちゃんがいてくれたから学校が楽しくなったし、戦えたんだよ」
照れる事なく、はっきりと言い切る繭歌の言葉に。私が逆に照れてしまう。
「戦えたって……大袈裟に言いすぎだって」
「大袈裟じゃないよ。あの時、七海ちゃんに声をかけてもらうまで、私にとって学校は敵ばっかりだったもん……どこにも、味方なんていなかったもん」
「私は別に何もしてないよ」
私がした事といえば。教室の片隅で、一人で机の上にアニメ雑誌を広げて読んでいた繭歌に声をかけた。
ただ、それだけ。
あの時の私は、好美のグループにいて。その中でも比較的、力をもっていた智子は繭歌の事を毎日のように、気持悪いと愚痴っていたけど。
そんなの、関係なかった。
私が話したいと思った。私が繭歌の事を知りたいと思った。芹沢繭歌の事を知りたいと、私が思ったから。
だから、話しかけた。
繭歌がどう言おうと。どう思っていても。私は何も大した事なんてしていない。
「二人とも仲良しなんやなぁ。でもな、世の中はそんな風に助けてくれる人に恵まれる奴ばっかりと違うんよな」
それは、娘さんの現状と照らし合わせての言葉なんだろう。
深みがあった。
世の中は。自分の居場所に必ず味方がいるなんて限らない。
私の学校にだって、男女問わず大小様々なグループが存在していて。いつも周りには敵しかいないような状況の子だっている。
私も、知らないうちに大きな女子グループに含まれていたけど。見渡したところで、そこには気を許せる子はおろか。味方なんて一人だっていなかった。
ただ、敵意に晒されていなかってっていうだけだ。
大勢に囲まれているからといって、そこが自分の味方ばかりとは限らない。
繭歌は私という味方がいたから大丈夫だったと言った。
でもそんなの。きっと、たまたまで偶然でラッキーなんだと思う。
それは、繭歌と仲良くなれた私自身にだって言える事だし。
だから、繭歌の言ってる事は理想だ。娘さんが一人で部屋に篭ってしまったという現実を見なくてはいけない熊田さんには、残念だけど繭歌の言葉が届くとは思えない。
「じゃあさ。じゃあさ。私が友達になってあげるよー。今なら七海ちゃんもついてるよー」
私の腕を掴んで、なんだかよくわからないアピールを熊田さんにする繭歌。
「繭歌」
短く言って、私は繭歌のおでこに軽くチョップした。
「わぷ。もーなにさー七海ちゃん。つねったり、チョップしたりひどいよー」
騒ぐ繭歌に無言で首を振る。
これ以上は、私達が何かを言うべきじゃない。そう思った。
熊田さんが元ヤクザだとか。娘さんが今でもその事で引き篭もりになっているだとか。
すっごく難しい問題があったとしても。どこまで行っても熊田さんの人生の問題で。
私にも繭歌にも、結局は問題を解決する方法なんてなくて。
話しを聞く事しかできない。何も……できないから。
だから、これ以上は首を突っ込むべきじゃないんだ。
「七海ちゃん、聞いてるー?チョップ凄く痛かったんだよー?」
まだ言ってるし。
「まーゆーか」
今度はチョップではなく。きつく睨んで繭歌を黙らせる。
「いいもん、いいもん。いじわるな七海ちゃんには、お菓子もうわけてあげないもん」
怒られた事で、すっかり繭歌は拗ねてしまった。
熊田さんのトラックに乗せてもらってから。すでに三袋目のおかしを繭歌はあける。細い体のどこにそれだけ収まるのかと感心してしまう。
まぁ、今は良くても。後から響いてくるのだけれども。
男の子にはイマイチ伝わりにくく。女の子にとっては非常にデリケートな問題だ。
「いいよ別に、後でお腹出ても知らないからね」
「うぁ……だ、だいじょうぶだもん」
一瞬ためらったものの。繭歌は結局はおかしを頬張った。しかも、鷲掴みで。
良く見れば。繭歌の持ってるおかしは私が家でも良く食べているやつだ。
自分のお腹の肉を服の上から少しつまんでみる。
陸上部で鍛えていた貯金があるのか。私のお腹はまだお肉をつまめるほどではない。
ん、大丈夫。
チェックも済んだところで。繭歌のお菓子の袋に、遠慮なく手を突っ込んだ。
「あー、七海ちゃんも結局食べるんじゃんかー。さっきも食べたしー」
「さ、さっきは少しだけじゃん。それに、私は陸上部だから大丈夫だし?」
「元でしょー今やってないでしょー」
まぁ、そうなんだけどさ。
気にしない。気にしない。
貯金があるし。
「うーあー七海ちゃんもお腹たぷたぷになってしまえー」
き、気にしない。気にしない……。
「たぷたぷになってしまえー」
「二回も言う必要ないじゃん」
我慢できずに、思わず声が出た。先に二袋も平らげてる繭歌にだけは言われたくない。
たぷたぷなんかになるもんか……多分。
い、いざとなれば、また走ればいいだけだし。
「ははは。なんか楽しいなぁ。いつも一人で走っとるから嬉しいわ」
私達の喧騒を、熊田さんは何本目かの煙草をふかしながら、楽しそうに眺めていた。
正面に、僅かな灯りが見えてきた。トラックは隣町に入ったみたいで、景色に建造物が混じりはじめる。
私達の町とは違い、隣町は観光地として結構有名だった。
もっとも、今では観光しようなんて人は殆んどいないので、どこもまばらな灯りが見えるだけで、寂しい雰囲気が漂っている。
最盛期には、レジャー施設や小さな遊園地もあって。私も小学生の頃に何度か両親に連れてきてもらった記憶がある。でも、私が中学にあがる頃には、その遊園地は経営不振で潰れてしまったのだと、夕飯の支度をしながらお母さんから言っていた。
「この先に、小さいサービスステーションがあるんや。そこでちょっと休憩しよか。トイレとかも済ませとかんとな。次の休憩所まで三時間ぐらい走らなあかんさかい」
熊田さんがそう言うと、車は少し速度を弱めて。車線を変更した。
10分ほど走り続けると、熊田さんの言った通り。夜道の中にサービスエリアの看板がぽつんと、浮び上がってくる。
サービスエリアのガレージに入り、トラックは適当な場所に停車した。
「ほな、しばらく休憩するさかい。適当に休んどってええで。建物の中は自動販売機とかもあるし、うどんとかも食えるしな。ここのうどんめちゃくちゃうまいねん」
ほな。と言って。熊田さんはトイレのある方向へと消えて行った。
「静かだねぇ。七海ちゃん、どうする?」
トラックから降り。大きく後ろに体を伸ばした後、欠伸混じりに繭歌が聞いてきた。
繭歌の言うとおり。サービスエリアは営業中だと思えないほど、水を打ったような静かさだった。
熊田さんのトラック以外にも、数台のトラックや乗用車が停まっていたけど。みんな車内にいるみたいで、人影は私達だけだ。
「とりあえず、私は中で飲み物でも買って休憩する」
ずっと車に乗っていたので、何か飲みながらゆっくり足を伸ばして落ち着きたい。
「トイレいかなくていいの?」
「私は別に後でもいいし」
「七海ちゃんも一緒に行こうよー」
「え?なんで?」
小さな子供じゃないのだから、お手洗いぐらい一人で行けばいいのに。
「だってー。なんか恐いじゃん。それに、トイレ暗そうだし」
熊田さんが向った辺りに視線を移すと、いかにもな雰囲気の薄暗い電灯が点滅している女子トイレが見える。
確かに、ここから見ているだけでもなんだか不気味だ。
古いサービスエリアだから、仕方ないのだろうけど。それにしても、電灯ぐらいはちゃんと交換して欲しいと思う。
「ね、お願い。七海ちゃんついてきてよー」
「しょうがないなぁ……」
私の腕を掴んで、なんだかよくわからないアピールを熊田さんにする繭歌。
「繭歌」
短く言って、私は繭歌のおでこに軽くチョップした。
「わぷ。もーなにさー七海ちゃん。つねったり、チョップしたりひどいよー」
騒ぐ繭歌に無言で首を振る。
これ以上は、私達が何かを言うべきじゃない。そう思った。
熊田さんが元ヤクザだとか。娘さんが今でもその事で引き篭もりになっているだとか。
すっごく難しい問題があったとしても。どこまで行っても熊田さんの人生の問題で。
私にも繭歌にも、結局は問題を解決する方法なんてなくて。
話しを聞く事しかできない。何も……できないから。
だから、これ以上は首を突っ込むべきじゃないんだ。
「七海ちゃん、聞いてるー?チョップ凄く痛かったんだよー?」
まだ言ってるし。
「まーゆーか」
今度はチョップではなく。きつく睨んで繭歌を黙らせる。
「いいもん、いいもん。いじわるな七海ちゃんには、お菓子もうわけてあげないもん」
怒られた事で、すっかり繭歌は拗ねてしまった。
熊田さんのトラックに乗せてもらってから。すでに三袋目のおかしを繭歌はあける。細い体のどこにそれだけ収まるのかと感心してしまう。
まぁ、今は良くても。後から響いてくるのだけれども。
男の子にはイマイチ伝わりにくく。女の子にとっては非常にデリケートな問題だ。
「いいよ別に、後でお腹出ても知らないからね」
「うぁ……だ、だいじょうぶだもん」
一瞬ためらったものの。繭歌は結局はおかしを頬張った。しかも、鷲掴みで。
良く見れば。繭歌の持ってるおかしは私が家でも良く食べているやつだ。
自分のお腹の肉を服の上から少しつまんでみる。
陸上部で鍛えていた貯金があるのか。私のお腹はまだお肉をつまめるほどではない。
ん、大丈夫。
チェックも済んだところで。繭歌のお菓子の袋に、遠慮なく手を突っ込んだ。
「あー、七海ちゃんも結局食べるんじゃんかー。さっきも食べたしー」
「さ、さっきは少しだけじゃん。それに、私は陸上部だから大丈夫だし?」
「元でしょー今やってないでしょー」
まぁ、そうなんだけどさ。
気にしない。気にしない。
貯金があるし。
「うーあー七海ちゃんもお腹たぷたぷになってしまえー」
き、気にしない。気にしない……。
「たぷたぷになってしまえー」
「二回も言う必要ないじゃん」
我慢できずに、思わず声が出た。先に二袋も平らげてる繭歌にだけは言われたくない。
たぷたぷなんかになるもんか……多分。
い、いざとなれば、また走ればいいだけだし。
「ははは。なんか楽しいなぁ。いつも一人で走っとるから嬉しいわ」
私達の喧騒を、熊田さんは何本目かの煙草をふかしながら、楽しそうに眺めていた。
正面に、僅かな灯りが見えてきた。トラックは隣町に入ったみたいで、景色に建造物が混じりはじめる。
私達の町とは違い、隣町は観光地として結構有名だった。
もっとも、今では観光しようなんて人は殆んどいないので、どこもまばらな灯りが見えるだけで、寂しい雰囲気が漂っている。
最盛期には、レジャー施設や小さな遊園地もあって。私も小学生の頃に何度か両親に連れてきてもらった記憶がある。でも、私が中学にあがる頃には、その遊園地は経営不振で潰れてしまったのだと、夕飯の支度をしながらお母さんから言っていた。
「この先に、小さいサービスステーションがあるんや。そこでちょっと休憩しよか。トイレとかも済ませとかんとな。次の休憩所まで三時間ぐらい走らなあかんさかい」
熊田さんがそう言うと、車は少し速度を弱めて。車線を変更した。
10分ほど走り続けると、熊田さんの言った通り。夜道の中にサービスエリアの看板がぽつんと、浮び上がってくる。
サービスエリアのガレージに入り、トラックは適当な場所に停車した。
「ほな、しばらく休憩するさかい。適当に休んどってええで。建物の中は自動販売機とかもあるし、うどんとかも食えるしな。ここのうどんめちゃくちゃうまいねん」
ほな。と言って。熊田さんはトイレのある方向へと消えて行った。
「静かだねぇ。七海ちゃん、どうする?」
トラックから降り。大きく後ろに体を伸ばした後、欠伸混じりに繭歌が聞いてきた。
繭歌の言うとおり。サービスエリアは営業中だと思えないほど、水を打ったような静かさだった。
熊田さんのトラック以外にも、数台のトラックや乗用車が停まっていたけど。みんな車内にいるみたいで、人影は私達だけだ。
「とりあえず、私は中で飲み物でも買って休憩する」
ずっと車に乗っていたので、何か飲みながらゆっくり足を伸ばして落ち着きたい。
「トイレいかなくていいの?」
「私は別に後でもいいし」
「七海ちゃんも一緒に行こうよー」
「え?なんで?」
小さな子供じゃないのだから、お手洗いぐらい一人で行けばいいのに。
「だってー。なんか恐いじゃん。それに、トイレ暗そうだし」
熊田さんが向った辺りに視線を移すと、いかにもな雰囲気の薄暗い電灯が点滅している女子トイレが見える。
確かに、ここから見ているだけでもなんだか不気味だ。
古いサービスエリアだから、仕方ないのだろうけど。それにしても、電灯ぐらいはちゃんと交換して欲しいと思う。
「ね、お願い。七海ちゃんついてきてよー」
「しょうがないなぁ……」
「良かったぁ。一人だとどうしようかと思ったよー」
繭歌に手を引かれ、駐車場の端にあるトイレまで連れていかれる。
女性トイレに入ると、個室のドアは全部開いていて。しばらく利用している人が誰もいないのが、ひと目でわかった。
冷えたタイルと点滅する蛍光灯。それだけで十分に不気味な雰囲気を醸しだしている。
「何か出そうな感じだよねぇ……」
「何かって、何よ」
ただでさえ、気味が悪いというのに。変な事を言わないで欲しい。
ついて行くと行ったは良いけど、私はこういう薄暗くて今にも、その……幽霊とかが出そうな場所は非常に苦手だ。
遊園地のおばけ屋敷でさえ、ずっと目を瞑っていなければ耐えられない。
もちろん、幽霊なんて非科学的で。本当にはいないってわかってるつもりだけど。
それでも、やっぱり恐いものは恐い。
「ほら、繭歌。待っててあげるからさっさと済ませてきちゃいなよ」
「うんー。ちゃんと待っててね?知らないうちに外に出たら嫌だからね?」
個室に入っても、繭歌はなかなかドアを閉めようとせず。しつこく念を押してくる。
「はいはい。わかってるって」
「じゃ、じゃあ……行ってきます」
額に手を直角に当て、敬礼ポーズでおどけて見せた後。繭歌はようやく個室のドアを閉めようとする。
「あ、繭歌」
「なに?」
「わかってると思うけど。ちゃんと最初に水流しなさいよ?外に私いるんだからさ」
「うん、そだね。おしっこの音、聞えちゃうもんね」
「おしっこって……。もうちょっと言い方あるでしょ」
「えと、じゃあ。お花を摘む音とか」
「意味わかんないし」
繭歌がドアを閉めたのを確認すると、私は鏡の設置されている洗面台に移動した。
「ぴゃぁぁぁぁぁっ!」
途端、個室から繭歌の悲鳴が聞える。
肩がびくっと震えた。
「ちょっと、脅かさないでよ。トイレットペーパーでも切れてた?」
「うぅん。それは大丈夫ー」
じゃあ、ゴキブリでも出たのだろうか?あの黒いかさかさと動く生き物を想像しただけで、背筋がぞわぞわと寒くなる。
間違っても幽霊が出たなんて言おうものなら、繭歌には申し訳ないけど走って逃げるしかない。
「なんか、便器の端に茶色いのがついててさ。汚い、汚いよー。」
なんだ、そんな事か。心配して損した。
「それは……しょうがないんじゃない?だって、色んな人が使うわけだし」
建てられたばかりのサービスエリアならともかく。どう見てもここは、ひと時代前からあるっぽいし。駐車場や建物を見る限り、頻繁に清掃業者が入ってるようにも思えない。
女性用トイレとはいえ、使う人が清潔な人ばかりとも限らないわけで。運が悪かったとしか言いようがない。
「嫌なら他のとこ使えばいいじゃん。一杯空いてるんだし」
「うー……もういいよぉ。パンツ下げちゃったし、我慢するよぉ」
めそめそと情け無い声を出しながら。繭歌は諦めたようだった。
ざー、っと。勢い良く水の流れる音がトイレの壁に反響する。
はぁ……何やってるんだろう。ほんと。
水音の残響の中。鏡に映る自分の顔を見ながら、暇つぶしに髪型なんかをチェックする。
湿気があるのか、広がっていた髪を鏡を見ながら、左右から抑え。少し乱れた前髪もヘアピンを外し、手櫛で流れを整えてから、もう一度留めなおした。
一通り髪を触り終えたら、やる事がなくなってしまう。繭歌はまだ出て来る気配はない。
「遅いなぁ……」
「ご、ごめんね。わかってるんだけどね。なんか、緊張しちゃってさー」
独り言のつもりだったけど。声が響いて繭歌に聞えたみたいだ。
申し訳なさそうに、個室から繭歌が返事をしてくる。
「別にいいよ。急かせるつもりで言ったんじゃないし、ゆっくりしなよ」
熊田さんもここで少し休憩するみたいだったし。まだ時間はあるはずだ。
「うん。がんばるー」
トイレでがんばるって……どうなんだろう。さっきもそうだけど、女の子なんだし。もうちょっと恥じらうとかオブラートに包むとかしたほうが良いと思う。
「七海ちゃんさー。怒ったりしてない?」
「どしたの?急に」
「や、ほら。私の我侭に七海ちゃんを巻き込んじゃってるのかなー……なんて」
ここまで来て、なんて今更な話しだろうか。
「トイレしながらする話じゃないと思うけど?」
「あー……うん。まぁ、そうなんだけどね。七海ちゃん、実は迷惑だと思ったりしてるんじゃないかなぁって」
「もし迷惑って言ったらどうするわけ?」
「うー……それはー……泣いちゃうかな?なんちゃって」
へへへ。と笑う声はどこか力がない。繭歌なりに、真剣に気にしているようだ。普段は適当な感じで笑っているくせに、急に繊細な感じを出してくる。
そんな繭歌に、私の心はいつも揺さぶられてばかりだ。
壊れやすい人形みたいで。
だから、放っておけない。一緒にいてあげなくちゃと思ってしまう。
繭歌に手を引かれ、駐車場の端にあるトイレまで連れていかれる。
女性トイレに入ると、個室のドアは全部開いていて。しばらく利用している人が誰もいないのが、ひと目でわかった。
冷えたタイルと点滅する蛍光灯。それだけで十分に不気味な雰囲気を醸しだしている。
「何か出そうな感じだよねぇ……」
「何かって、何よ」
ただでさえ、気味が悪いというのに。変な事を言わないで欲しい。
ついて行くと行ったは良いけど、私はこういう薄暗くて今にも、その……幽霊とかが出そうな場所は非常に苦手だ。
遊園地のおばけ屋敷でさえ、ずっと目を瞑っていなければ耐えられない。
もちろん、幽霊なんて非科学的で。本当にはいないってわかってるつもりだけど。
それでも、やっぱり恐いものは恐い。
「ほら、繭歌。待っててあげるからさっさと済ませてきちゃいなよ」
「うんー。ちゃんと待っててね?知らないうちに外に出たら嫌だからね?」
個室に入っても、繭歌はなかなかドアを閉めようとせず。しつこく念を押してくる。
「はいはい。わかってるって」
「じゃ、じゃあ……行ってきます」
額に手を直角に当て、敬礼ポーズでおどけて見せた後。繭歌はようやく個室のドアを閉めようとする。
「あ、繭歌」
「なに?」
「わかってると思うけど。ちゃんと最初に水流しなさいよ?外に私いるんだからさ」
「うん、そだね。おしっこの音、聞えちゃうもんね」
「おしっこって……。もうちょっと言い方あるでしょ」
「えと、じゃあ。お花を摘む音とか」
「意味わかんないし」
繭歌がドアを閉めたのを確認すると、私は鏡の設置されている洗面台に移動した。
「ぴゃぁぁぁぁぁっ!」
途端、個室から繭歌の悲鳴が聞える。
肩がびくっと震えた。
「ちょっと、脅かさないでよ。トイレットペーパーでも切れてた?」
「うぅん。それは大丈夫ー」
じゃあ、ゴキブリでも出たのだろうか?あの黒いかさかさと動く生き物を想像しただけで、背筋がぞわぞわと寒くなる。
間違っても幽霊が出たなんて言おうものなら、繭歌には申し訳ないけど走って逃げるしかない。
「なんか、便器の端に茶色いのがついててさ。汚い、汚いよー。」
なんだ、そんな事か。心配して損した。
「それは……しょうがないんじゃない?だって、色んな人が使うわけだし」
建てられたばかりのサービスエリアならともかく。どう見てもここは、ひと時代前からあるっぽいし。駐車場や建物を見る限り、頻繁に清掃業者が入ってるようにも思えない。
女性用トイレとはいえ、使う人が清潔な人ばかりとも限らないわけで。運が悪かったとしか言いようがない。
「嫌なら他のとこ使えばいいじゃん。一杯空いてるんだし」
「うー……もういいよぉ。パンツ下げちゃったし、我慢するよぉ」
めそめそと情け無い声を出しながら。繭歌は諦めたようだった。
ざー、っと。勢い良く水の流れる音がトイレの壁に反響する。
はぁ……何やってるんだろう。ほんと。
水音の残響の中。鏡に映る自分の顔を見ながら、暇つぶしに髪型なんかをチェックする。
湿気があるのか、広がっていた髪を鏡を見ながら、左右から抑え。少し乱れた前髪もヘアピンを外し、手櫛で流れを整えてから、もう一度留めなおした。
一通り髪を触り終えたら、やる事がなくなってしまう。繭歌はまだ出て来る気配はない。
「遅いなぁ……」
「ご、ごめんね。わかってるんだけどね。なんか、緊張しちゃってさー」
独り言のつもりだったけど。声が響いて繭歌に聞えたみたいだ。
申し訳なさそうに、個室から繭歌が返事をしてくる。
「別にいいよ。急かせるつもりで言ったんじゃないし、ゆっくりしなよ」
熊田さんもここで少し休憩するみたいだったし。まだ時間はあるはずだ。
「うん。がんばるー」
トイレでがんばるって……どうなんだろう。さっきもそうだけど、女の子なんだし。もうちょっと恥じらうとかオブラートに包むとかしたほうが良いと思う。
「七海ちゃんさー。怒ったりしてない?」
「どしたの?急に」
「や、ほら。私の我侭に七海ちゃんを巻き込んじゃってるのかなー……なんて」
ここまで来て、なんて今更な話しだろうか。
「トイレしながらする話じゃないと思うけど?」
「あー……うん。まぁ、そうなんだけどね。七海ちゃん、実は迷惑だと思ったりしてるんじゃないかなぁって」
「もし迷惑って言ったらどうするわけ?」
「うー……それはー……泣いちゃうかな?なんちゃって」
へへへ。と笑う声はどこか力がない。繭歌なりに、真剣に気にしているようだ。普段は適当な感じで笑っているくせに、急に繊細な感じを出してくる。
そんな繭歌に、私の心はいつも揺さぶられてばかりだ。
壊れやすい人形みたいで。
だから、放っておけない。一緒にいてあげなくちゃと思ってしまう。
「情けない声ださなくても、私はそんな風に思ってないってば」
「ほんとに?」
「じゃなきゃ。繭歌を迎えに行ったりしないって」
「そっかそか……」
嬉しそうに、繭歌は安堵のため息をついた。
会話が終わり、互いに無言になる。室内を無音が支配する。
「じゃあさ、私からも聞いていい?」
繭歌はまだ、トイレからまだ出てきそうにないので。今度はこちらから質問を投げる。
「うん、いいよー。なんでも聞いちゃってよ」
「繭歌の家族ってさ。どんな人なの?」
「あはは。なんだかいきなりだね」
「一緒に旅するわけだし?もっと繭歌の事知っておきたいなって思っただけ」
「そっか。うん、それは嬉しいね。うーん、そうだなぁ。お母さんは普通の人だよ。ちょっと気が弱い感じで……後は、3つ上のお兄ちゃんがいるかな。二人ともちょっと頼りないけど。私は大好きだよ」
「へぇ、繭歌にもお兄ちゃんいるんだ」
「うん。七海ちゃんもお兄さんいるよね」
「あれ?私、話した事あったっけ?」
「クラスじゃ有名だよ。三丁目の交番にいるお巡りさんは七海ちゃんのお兄さんだって」
「そ、そうなんだ。有名なんだ」
は、恥ずかしい。
知らないところで、自分の家族を見られるのってなんだか凄く恥ずかしい。顔から火が出そうになるとはまさにこういう時に使う言葉だろう。
「私も見た事あるけど、良い人そうだよね。頼れるお巡りさんって感じで」
「そうかなぁ。家じゃいつもゲームしたり、ごろごろしてるだけだから」
制服を着たお兄ちゃんと、外で会うのがなんだか恥ずかしくて。私はできるだけお兄ちゃんの勤務する、三丁目には近づかないようにしていた。
だから、家に居る姿以外のお兄ちゃんの事はよく知らない。
家ではだらだらして、事なかれ主義で、結構どうしようもない人だなぁ。と私は思っているけれど。家族以外の人から見れば、それはまた違う風に見えるものなのだろうか?
頼れるおまわりさん、みたいな。
全然イメージわかないけど。
「そういえばさ、お父さんはどんな人なの?」
「お父さん……」
「う、うん」
何気ない、自然な会話の流れの……はずだった。
繭歌の表情はこちらからは見えない。けれど、返事のニュアンスでなんだか微妙な空気になってしまったのがわかる。
もしかしたら、もしかしなくても。私は聞いてはいけない事を聞いてしまったのだろうか? 私の家にも外には言えない事情があるように。繭歌の家にも人には言えない訳ありな事情があったのかもしれない。
迂闊の事聞いちゃったかな。
「あのさ。言いにくい事なら別に無理に言わなくていいよ」
「言いにくいっていうか……うーん。父親はいるんだけど、いないみたいなものっていうか」「いるけど、いない?」
繭歌の言っている事がよくわからない。
「一応いるけどさ……違うんだよね。あいつは父親なんかじゃないよ」
あいつ。自分の父親をそう呼ぶ繭歌の声にはものすごい怒りというか、もっと深いもの。憎しみが込められている気がした。
「あんな奴、さっさと死ねばいいんだ……」
「え?」
私は耳を疑った。一瞬、聞き間違いかとさえ思った。
死ねばいい。その言葉が、凄く衝撃的で。繭歌のイメージからかけ離れてて。
屋上で聞いた、あの声に凄く似ていたから。
どう反応して良いのかわからなかった。
「繭歌?」
とても冷たい繭歌の声に。何かを確認するみたいに、私は不安になって聞き返す。
「ん?なになに?」
またスィッチが切り替わったみたいに、繭歌の声のトーンはいつもの可愛い鈴鳴りのような声に戻っていた。
「あのさ……」
うまく言えない自分がもどかしい。
何か言わなきゃと、焦るほどに言葉は出てこない。
私が何も言い出せずにいると。会話を中断するように、ちょろろ、と水音が一瞬聞えた。
その音が何なのかわかって、緊張感の糸がぷっつりと途切れてしまう。
そこで、この話題はお終いになった。
「ちょ、ちょっと繭歌!」
個室に向って私は叫ぶ。
さっきまでの重苦しい空気が嘘みたいに、ばたばたと騒がしさが戻ってくる。
「あわわわ。出ちゃう、たんまたんまー」
慌てた繭歌の声の後、ざー、と勢いよく水の流れる音が聞える。
「はぁ。間に合ったぁ」
「ほんと、気をつけてよね」
「あはは、ごめごめ。あ、でもでもさ七海ちゃんだから私は恥ずかしくないけどねー」
「私が恥ずかしいってば」
いくら友達とはいえ、用を足す音を聞かされるのは、とても抵抗がある。
もし、逆の立場で自分のトイレの音を繭歌に聞かれたりしたら、きっと恥ずかしくて顔を合わせられない。
からからと、トイレットペーパーを巻きとる音と、衣擦れの音の後。すっきりした顔で個室から出てきた。
「はぁ~すっきりした。七海ちゃん、おまたせー」
「ほんとに?」
「じゃなきゃ。繭歌を迎えに行ったりしないって」
「そっかそか……」
嬉しそうに、繭歌は安堵のため息をついた。
会話が終わり、互いに無言になる。室内を無音が支配する。
「じゃあさ、私からも聞いていい?」
繭歌はまだ、トイレからまだ出てきそうにないので。今度はこちらから質問を投げる。
「うん、いいよー。なんでも聞いちゃってよ」
「繭歌の家族ってさ。どんな人なの?」
「あはは。なんだかいきなりだね」
「一緒に旅するわけだし?もっと繭歌の事知っておきたいなって思っただけ」
「そっか。うん、それは嬉しいね。うーん、そうだなぁ。お母さんは普通の人だよ。ちょっと気が弱い感じで……後は、3つ上のお兄ちゃんがいるかな。二人ともちょっと頼りないけど。私は大好きだよ」
「へぇ、繭歌にもお兄ちゃんいるんだ」
「うん。七海ちゃんもお兄さんいるよね」
「あれ?私、話した事あったっけ?」
「クラスじゃ有名だよ。三丁目の交番にいるお巡りさんは七海ちゃんのお兄さんだって」
「そ、そうなんだ。有名なんだ」
は、恥ずかしい。
知らないところで、自分の家族を見られるのってなんだか凄く恥ずかしい。顔から火が出そうになるとはまさにこういう時に使う言葉だろう。
「私も見た事あるけど、良い人そうだよね。頼れるお巡りさんって感じで」
「そうかなぁ。家じゃいつもゲームしたり、ごろごろしてるだけだから」
制服を着たお兄ちゃんと、外で会うのがなんだか恥ずかしくて。私はできるだけお兄ちゃんの勤務する、三丁目には近づかないようにしていた。
だから、家に居る姿以外のお兄ちゃんの事はよく知らない。
家ではだらだらして、事なかれ主義で、結構どうしようもない人だなぁ。と私は思っているけれど。家族以外の人から見れば、それはまた違う風に見えるものなのだろうか?
頼れるおまわりさん、みたいな。
全然イメージわかないけど。
「そういえばさ、お父さんはどんな人なの?」
「お父さん……」
「う、うん」
何気ない、自然な会話の流れの……はずだった。
繭歌の表情はこちらからは見えない。けれど、返事のニュアンスでなんだか微妙な空気になってしまったのがわかる。
もしかしたら、もしかしなくても。私は聞いてはいけない事を聞いてしまったのだろうか? 私の家にも外には言えない事情があるように。繭歌の家にも人には言えない訳ありな事情があったのかもしれない。
迂闊の事聞いちゃったかな。
「あのさ。言いにくい事なら別に無理に言わなくていいよ」
「言いにくいっていうか……うーん。父親はいるんだけど、いないみたいなものっていうか」「いるけど、いない?」
繭歌の言っている事がよくわからない。
「一応いるけどさ……違うんだよね。あいつは父親なんかじゃないよ」
あいつ。自分の父親をそう呼ぶ繭歌の声にはものすごい怒りというか、もっと深いもの。憎しみが込められている気がした。
「あんな奴、さっさと死ねばいいんだ……」
「え?」
私は耳を疑った。一瞬、聞き間違いかとさえ思った。
死ねばいい。その言葉が、凄く衝撃的で。繭歌のイメージからかけ離れてて。
屋上で聞いた、あの声に凄く似ていたから。
どう反応して良いのかわからなかった。
「繭歌?」
とても冷たい繭歌の声に。何かを確認するみたいに、私は不安になって聞き返す。
「ん?なになに?」
またスィッチが切り替わったみたいに、繭歌の声のトーンはいつもの可愛い鈴鳴りのような声に戻っていた。
「あのさ……」
うまく言えない自分がもどかしい。
何か言わなきゃと、焦るほどに言葉は出てこない。
私が何も言い出せずにいると。会話を中断するように、ちょろろ、と水音が一瞬聞えた。
その音が何なのかわかって、緊張感の糸がぷっつりと途切れてしまう。
そこで、この話題はお終いになった。
「ちょ、ちょっと繭歌!」
個室に向って私は叫ぶ。
さっきまでの重苦しい空気が嘘みたいに、ばたばたと騒がしさが戻ってくる。
「あわわわ。出ちゃう、たんまたんまー」
慌てた繭歌の声の後、ざー、と勢いよく水の流れる音が聞える。
「はぁ。間に合ったぁ」
「ほんと、気をつけてよね」
「あはは、ごめごめ。あ、でもでもさ七海ちゃんだから私は恥ずかしくないけどねー」
「私が恥ずかしいってば」
いくら友達とはいえ、用を足す音を聞かされるのは、とても抵抗がある。
もし、逆の立場で自分のトイレの音を繭歌に聞かれたりしたら、きっと恥ずかしくて顔を合わせられない。
からからと、トイレットペーパーを巻きとる音と、衣擦れの音の後。すっきりした顔で個室から出てきた。
「はぁ~すっきりした。七海ちゃん、おまたせー」
さっぱりした顔で繭歌は個室から出てくると、私の隣に立ち、手を洗いはじめる。
「いやぁ。学校だと誰かがいるの当たり前だけど。七海ちゃんしかいないって思うと、なんか変に意識しちゃうよねー」
すっごい雑な感じで手をすすぐと。あろう事か、そのままスカートでごしごしと手を擦りつけた。
「ちょ、あんた何してんのよ」
「何って、手を洗ったから拭いてるんだよぉ」
いや、そんな。何言ってんのさ、みたいな顔で言われても。
私が言いたいのは、なんで手をスカートで拭くのかという事なわけでさ。
「ハンカチ使いなよ」
「持ってないもん」
はぁ。ほんとにこの子は。
「ほら、貸してあげるから」
ポケットからハンカチを取り出し、繭歌の手に握らせる。
「おー、兎さんだ。七海ちゃんかわいいの好きなんだ。なんか意外だね」
笑いを堪えているのか、ハンカチをまじまじと見つめる繭歌の口の端は今にも緩みそうになっている。
私が兎柄のハンカチを持っているのが、そんなにおかしいのだろうか。
そりゃあ、ちょっとは。自分でも可愛すぎるかなぁ。とか思ってるけどさ。
これぐらいで半笑いになってるようでは、私の部屋に置いてある熊やマンボウの、ふわふわで丸っこいぬいぐるみを見たらきっと繭歌は爆笑してしまう事だろう。
そういえば、お兄ちゃんも笑ってたっけ。
私だってこれでも女の子だ。可愛いものを好きだって……そのぅ……おかしくないと思うのだけど。
「別にいいじゃん。使わないなら返してよ」
「わ、ごめごめ。使う使う」
慌ててハンカチを広げて、繭歌は素早く手を拭いた後で、何故かくしゃくしゃになったハンカチを、そのままポケットに仕舞った。
「こら」
手の平を繭歌に差出し、ハンカチを返すように求める。
「ん?どしたの七海ちゃん」
私の手の平の上に繭歌は首を傾げながら、自分の手を軽く置いた。要するに『お手』のポーズだ。
「いや、そうじゃなくて。ハンカチ返しなさいよ」
「えー。ちゃんと洗って返すよー」
「一度繭歌が使っただけなんだし、そんなに気にしなくていいよ」
「えー……七海ちゃんのハンカチぃ。持ってちゃだめかな?」
繭歌は何故か、ハンカチを返す事を頑なに拒んだ。
どうやら、繭歌は本当にハンカチを返すつもりはないらしい。
私のハンカチなんて、持っていても仕方ないと思うけど。やたらと、繭歌はこだわりを見せる。
「駄目っていうか。一緒にいるわけだし、言ってくれれば別に貸してあげるじゃん」
「そうだけどさー。なんかね、七海ちゃんの持ち物を身につけていたいなぁって」
「芹沢さん。よくわかんないです」
「うぁ。凄い他人行儀だよ。芹沢さんとか言われたし。だからさぁ、私と七海ちゃんのらぶらぶの証にしようかなって」
「ごめん、余計にわかんなくなった。それってつまりどういう事?」
「もー。らぶらぶって事は大好きって事で、愛してるって事でしょー。七海ちゃんは鈍いなぁ」
「鈍いって言われても……」
それって私が悪いのだろうか?
「わかったわよ。そのかわり無くさないでよ?」
「うん。綺麗にして返すねー」
繭歌は満足げにポケットをぱんぱんと叩いた。
「あ、七海ちゃん。あの、さっきの話なんだけどね」
「う、うん」
さっきの。という話しが何を指しているのかはすぐにわかった。
つまり、繭歌のお父さんの話しだ。
どういう事情なのかわからないけど。つまり、繭歌が私に見せたくない心の深い部分の話し。
「なんかさ。変な空気つくっちゃったなぁって思ってさ。んとね、七海ちゃんが変に気にしてなきゃそれでいいんだ」
「私に何ができるのかわかんないけどさ。悩みとか、何かあるならいつでも言いなさいよね」「あー……うん。えとね、あれはそのぅなんていうかさ。七海ちゃんには関係ないっていうかさ」
繭歌に悪気がないのはわかってる。でも、関係ないって言われるのはなんだか寂しい。
私にできる事なんて、たかが知れてるのかも知れない。
それでも、どんなに小さくても。できる事があるあるなら、繭歌の力になってあげたい。そう思う。
「わかった。でも、私は繭歌の味方だからさ。一人で背負い込めなくなる前に相談する事。いい?」
「らじゃだよ。私の中で整理できたら、その時はちゃんと言うから。でも……全部言っちゃったら、今以上に弱くなっちゃって。七海ちゃんにすっごく寄りかかっちゃって、迷惑かけちゃうかもだけど」
「大丈夫。私はちゃんと受け止めるよ」
例えそれがどんな事でも。私は繭歌の事をちゃんと知りたい。
そして、私の事ももっと繭歌に知って欲しいと思う。
繭歌が言ったように。もしも、私が自分の家庭の事を話したら。繭歌はどんな風に思うだろう?
そう考えたら、私もなかなか繭歌に切り出せないのがわかる。
抱えている事情はそれぞれ違うだろうけど。きっと、繭歌が私に話しづらいのは、こんな気持になってしまうからかもしれない。
だから、待つしかない。
だから、今はこれでいい。
「ありがとね、七海ちゃん」
そう言って、繭歌は私に抱きついてきた。
「もう。繭歌ってすぐ抱きついてくるよね」
「うんー。七海ちゃんをぎゅってすると落ち着くのだよだよ」
抱きつくだけでなく、ぐりぐりと頬をすり寄せていた繭歌は、あろう事か。私の頬に唇を押し付けてきた。小さくちゅっと、頬から音がして。繭歌が私の頬を軽く吸ったのがわかる。
「わ、わ、繭歌。何すんのよ」
「ごめごめ。嬉しくてつい」
すこしはにかんで、繭歌は嬉しそうに唇を押さえている。顔もなんだか赤い。
「ついって、あんたね……」
「七海ちゃん怒った?」
「怒ったっていうかさ……」
繭歌の唇の感触が残る頬に手を当てたまま、私は今起こった事にうまく整理がつけられず。呆然と繭歌を見つめる。
つい。とか、たまたま。で、キスなんて普通するものだろうか?
キスの経験がないわけじゃない。けど、それはやっぱり相手は男の子だったわけで。
女の子にキスされるなんて、はじめてだ。
うーん。でも、まぁ頬だし。別に深い意味はないのかも。
繭歌の事だし。きっと悪ふざけが過ぎたに違いない。
そんな風に考えながら、頭の違う部分で別の事を考える私もいる。
好きだとか。愛してるとか。さっき繭歌がそんな事を言うものだから。
だから今のキスも。もしかしたら、実は本気なんじゃないだろうか?なんて思ってしまう。 だからといって、繭歌を嫌いになったりはしないけど。
私と繭歌は女の子同士……なわけで。
「七海ちゃん、行かないの?」
さっきのキスの事なんて、なかったみたいに繭歌はいつも通りの、のほほんとした調子で私を急かすように手を引っ張っている。
また、私だけ勝手にぐるぐると一人で悩んで、気持が取り残されたみたいになる。馬鹿みたいで、恥ずかしい。
自分で納得できる答えが出ないまま。私はもやもやとした気持を抱えたままトイレを後にした。
トイレを出て、熊田さんを探すため、食堂のある建物に入った。
決して広くない食堂で、見渡すまでもなく。真中のテーブルに陣取って、うどんをすすっている熊田さんを発見した。
「お待たせしました」
頭を下げながら、熊田さんの対面に私と繭歌は座った。
「おー。ええよええよ、どうせ一時間ぐらいは休憩するつもりやし。それより二人ともお腹空いてんねやったら、なんか注文してきてええで?俺が払うさかいな」
慣れた手つきで、うどんに七味を足していく熊田さん。どうやらご飯を奢ってくれるみたいだけど、私は夕飯を済ませて出てきているので、そんなにお腹は減っていない。
繭歌もさっきあれだけおかしを食べていたのだから、きっと食べれないだろうし。
「あの。私ご飯食べ……」
「わー。やったね、七海ちゃん。ラッキーだね。熊田さん良い人だね。私、ハンバーグセット食べちゃおうかなぁ」」
「あんた、それ本気で言ってる?」
繭歌のお腹を、ついつい凝視する。
「んん?どしたの七海ちゃん」
「いや、食べすぎなんじゃないかなぁって」
「そんな事ないでしょー。おいしいじゃん、ハンバーグぅ」
そりゃ、おいしいかもしれないけどさ。
おいしいっていうのと、食べられるかはまた別問題だから。
「そやで、若いんやから遠慮する事ないで?この辺は物価安定しとるさかいそない高いわけちゃうし。それに疲れとる時はぎょうさん食べたほうがええよ」
「ほらほらー。熊田さんもこう言ってくれてるんだしさ。食べないほうが失礼ってものだよ」 でも、繭歌みたいにセットでがっつり食べられそうにもないし。
「ほな。これで二人とも好きなもん食べてきいや」
熊田さんは財布から、少しくしゃくしゃになった千円札を取り出し、私の手に握らせた。 「それじゃあ、ごちそうになります……」
渡されたお金返せる雰囲気でもないので。仕方なく、私は繭歌を連れて券売機へと向った。 繭歌は言っていた通り。ハンバーグの定食を。私は飲み物ぐらいしかお腹に入りそうになかったので、オレンジジュースを注文する。
厨房の中のおばさんの手際は驚くほど早く。五分と待たずに注文した料理がトレイに乗せられる。
「お嬢ちゃんたち可愛いからね。これ、おまけしておくね」
そう言っておばさんは、皺だらけの顔をさらにくしゃくしゃにして。にっこり笑ってトレイに二つプリンを乗せてくれた。
「わぁ。ありがとうー。デザートつきなんて豪華だねぇ」
「あ、ありがとうございます。でも、本当に良いんですか?」
おばさんの行為は嬉しいけど。
「いいのよ、いいのよ。最近は若い子なんてほとんど来ないし。残っても、無駄になっちゃうしね。このご時世だし、食べ物を捨てたりするのは気が引けちゃうじゃない」
そう考えたら、私もなかなか繭歌に切り出せないのがわかる。
抱えている事情はそれぞれ違うだろうけど。きっと、繭歌が私に話しづらいのは、こんな気持になってしまうからかもしれない。
だから、待つしかない。
だから、今はこれでいい。
「ありがとね、七海ちゃん」
そう言って、繭歌は私に抱きついてきた。
「もう。繭歌ってすぐ抱きついてくるよね」
「うんー。七海ちゃんをぎゅってすると落ち着くのだよだよ」
抱きつくだけでなく、ぐりぐりと頬をすり寄せていた繭歌は、あろう事か。私の頬に唇を押し付けてきた。小さくちゅっと、頬から音がして。繭歌が私の頬を軽く吸ったのがわかる。
「わ、わ、繭歌。何すんのよ」
「ごめごめ。嬉しくてつい」
すこしはにかんで、繭歌は嬉しそうに唇を押さえている。顔もなんだか赤い。
「ついって、あんたね……」
「七海ちゃん怒った?」
「怒ったっていうかさ……」
繭歌の唇の感触が残る頬に手を当てたまま、私は今起こった事にうまく整理がつけられず。呆然と繭歌を見つめる。
つい。とか、たまたま。で、キスなんて普通するものだろうか?
キスの経験がないわけじゃない。けど、それはやっぱり相手は男の子だったわけで。
女の子にキスされるなんて、はじめてだ。
うーん。でも、まぁ頬だし。別に深い意味はないのかも。
繭歌の事だし。きっと悪ふざけが過ぎたに違いない。
そんな風に考えながら、頭の違う部分で別の事を考える私もいる。
好きだとか。愛してるとか。さっき繭歌がそんな事を言うものだから。
だから今のキスも。もしかしたら、実は本気なんじゃないだろうか?なんて思ってしまう。 だからといって、繭歌を嫌いになったりはしないけど。
私と繭歌は女の子同士……なわけで。
「七海ちゃん、行かないの?」
さっきのキスの事なんて、なかったみたいに繭歌はいつも通りの、のほほんとした調子で私を急かすように手を引っ張っている。
また、私だけ勝手にぐるぐると一人で悩んで、気持が取り残されたみたいになる。馬鹿みたいで、恥ずかしい。
自分で納得できる答えが出ないまま。私はもやもやとした気持を抱えたままトイレを後にした。
トイレを出て、熊田さんを探すため、食堂のある建物に入った。
決して広くない食堂で、見渡すまでもなく。真中のテーブルに陣取って、うどんをすすっている熊田さんを発見した。
「お待たせしました」
頭を下げながら、熊田さんの対面に私と繭歌は座った。
「おー。ええよええよ、どうせ一時間ぐらいは休憩するつもりやし。それより二人ともお腹空いてんねやったら、なんか注文してきてええで?俺が払うさかいな」
慣れた手つきで、うどんに七味を足していく熊田さん。どうやらご飯を奢ってくれるみたいだけど、私は夕飯を済ませて出てきているので、そんなにお腹は減っていない。
繭歌もさっきあれだけおかしを食べていたのだから、きっと食べれないだろうし。
「あの。私ご飯食べ……」
「わー。やったね、七海ちゃん。ラッキーだね。熊田さん良い人だね。私、ハンバーグセット食べちゃおうかなぁ」」
「あんた、それ本気で言ってる?」
繭歌のお腹を、ついつい凝視する。
「んん?どしたの七海ちゃん」
「いや、食べすぎなんじゃないかなぁって」
「そんな事ないでしょー。おいしいじゃん、ハンバーグぅ」
そりゃ、おいしいかもしれないけどさ。
おいしいっていうのと、食べられるかはまた別問題だから。
「そやで、若いんやから遠慮する事ないで?この辺は物価安定しとるさかいそない高いわけちゃうし。それに疲れとる時はぎょうさん食べたほうがええよ」
「ほらほらー。熊田さんもこう言ってくれてるんだしさ。食べないほうが失礼ってものだよ」 でも、繭歌みたいにセットでがっつり食べられそうにもないし。
「ほな。これで二人とも好きなもん食べてきいや」
熊田さんは財布から、少しくしゃくしゃになった千円札を取り出し、私の手に握らせた。 「それじゃあ、ごちそうになります……」
渡されたお金返せる雰囲気でもないので。仕方なく、私は繭歌を連れて券売機へと向った。 繭歌は言っていた通り。ハンバーグの定食を。私は飲み物ぐらいしかお腹に入りそうになかったので、オレンジジュースを注文する。
厨房の中のおばさんの手際は驚くほど早く。五分と待たずに注文した料理がトレイに乗せられる。
「お嬢ちゃんたち可愛いからね。これ、おまけしておくね」
そう言っておばさんは、皺だらけの顔をさらにくしゃくしゃにして。にっこり笑ってトレイに二つプリンを乗せてくれた。
「わぁ。ありがとうー。デザートつきなんて豪華だねぇ」
「あ、ありがとうございます。でも、本当に良いんですか?」
おばさんの行為は嬉しいけど。
「いいのよ、いいのよ。最近は若い子なんてほとんど来ないし。残っても、無駄になっちゃうしね。このご時世だし、食べ物を捨てたりするのは気が引けちゃうじゃない」
おばさんは調理の油と湯気でてかてかと光る顔を手ぬぐいで拭きながら、傍らに置いてあったコップの水を一気に飲み干した。
私達は、もう一度おばさんに頭を下げ。トレイを持って席に戻った。
「あれ、七海ちゃんはジュースとプリンだけでよかったん?」
私達が席に着く頃には、熊田さんはすっかりうどんを平らげて、ずずずっと残った汁をすすっていた。
私は、熊田さんにお釣りの小銭を返す。
「はい。今は飲み物が欲しいなって思って」
「そかそか。まぁ女の子って小食やったりするからなぁ。うちの娘もそやったわ……っていうても小さい頃の話なんやけどな」
「私って、食べる時と食べない時が極端なんですよ」
「そういうもんなんやなぁ」
私はその場をオレンジジュースに口をつける事で誤魔化した。
「七海ちゃん。ハンバーグおいしいよー。デザートもあるしさ、最高だよね」
不器用な箸さばきでハンバーグを切り分けながら、繭歌はハンバーグをゆっくり味わうようにもぐもぐと口を動かしている。その表情はとても幸せそうで、好きなメニューが夕飯に出てきた時の小さな子供を見ているようで、なんだか和んでしまう。
「そうそう。二人ともトラック降りたら次はどこ行くん?」
「え?」
熊田さんのいきなりの質問。
「え、えーと」
しどろもどろになってしまい、うまく答えられない。そもそも繭歌に付き添っているだけの私に答えられるはずがない。
「南に行こうと思ってますです」
私に変わって、繭歌が答えた。口のまわりにハンバーグのソースをたっぷりつけて。
「そうなんや。南いうても乗り物使わんと行ける範囲限られてしまうで?旧沖縄なんて車で行けへんし」
旧沖縄。日本の南端にある街。学校の社会の時間に習ったので場所は知ってるけど。私達の住む街からは遠く離れているし、行った事がないのでどれぐらいかかるのかわからない。
繭歌の事だから、漠然と言ってるだけなのかもしれないけど。
もしも、旧沖縄まで行くことになったとしたら。一体どうやって行けばいいのだろう?
見当もつかない。
「うーん。電車とかバスとか使えればいいんだけどねぇ……」
繭歌は口ではそう言うものの。あまり深く考えていないのがわかる。
事実、会話に参加しているように見えて。繭歌の視線は、目の前のプリンに釘付けだ。
「そやなぁ。ほんまは飛行機でも使えたらええんやろけど、今は飛んでへんし。電車とかも都内ぐらいしかまともに動いとらんからなぁ」
そういう情報は、なんとなく伝え聞いてはいたけど。
私達の街にいた時は遠くで起こってる事みたいで、あまり実感できなかった。
「やっぱ、ヒッチハイクとか歩いたりでがんばるしかないのかなー」
難しい顔でうんうん唸りながら、繭歌はプリンの蓋を開けた。
私も、オレンジジュースのグラスが空になったので。同じように、プリンに手をかける。
プリンの銘柄は、お母さんがよくスーパーで買ってきていたものと同じだった。
「そこはしょうがないんじゃない?少しずつでも、進んでいくしかないよ。無理のない程度にさ」
とても曖昧な言葉になってしまうけど。現実問題として、私達にはそんな方法しか思いつかない。
手持ちのお金にだって限界があるし。なかなか、一気に目的地へ。というわけにはいかないのだ。
「はぁ。そう考えるとなんか心配やわぁ。女の子二人だけでこの先行かせるはなぁ。俺が仕事なかったら付いて行ってやりたいぐらいやで」
割り箸入れの隣に置いてある、安っぽい銀色の灰皿を引き寄せ。熊田さんは煙草を吸い始めた。
「そんな、大丈夫ですよ。
「そうは言うてもなぁ……」
私の言葉を最後まで聞いてから、熊田さんは口を開いた。
「そら七海ちゃんはしっかりしとるように見える。けどな、それでもやっぱり俺から見たら高校生の女の子なんよ。生まれた町から今まで出た事ないんやろ?」
「はい……」
それは、その通りなので。返す言葉がない。
「別に、大人ぶりたいわけちゃうけど。それでもな、君らの住んでた町にもそら悪い奴もおったやろけど。その外側には、比べられんぐらいに悪い事する奴や、悪い大人がおんねん。自分のためやったら、他人なんか平気で踏みにじるような奴が数えられんぐらいおるんよ……」
実体験に基づくものなのか。熊田さんの言葉は、とても静かで。そして、深い。
だけど、熊田さんの言葉は。イメージとしてはなんとなく掴めるけど。あくまでドラマとか映画で今まで見たようなものからしか感じとるしかない。
「そやから、なんて言うかなぁ。こうやって誰かの車に乗せてもらうんかて、ほんまは危ない事やねんで?どこ連れて行かれるかわからんしな」
「でも、熊田さんはちゃんと乗せてくれたよ?」
「そら、俺は……いや、俺の事はどうでもええねん。何が言いたいんかっていうと、これからも旅を続けるんやったら、もっと用心して行かなあかんでって事やねん。」
「うーん。まぁ、とにかくさー。世の中には悪い人もいるけど、熊田さんみたいに良い人もいるって事でしょ?もしかしたら悪い人とも会っちゃうかもだろうけど。そういうのは当たって砕けろーって感じしかないんじゃないかなぁ」
熊田さんの言う。私達の経験の未熟さの話しはともかく。今の繭歌の発言があまりにも楽観的すぎるのだけは、私にもわかる。
さすがに、繭歌のようにその場になってから考えよう。みたいな、ノリだけでこの旅を進めていけるとは私は思っていない。
私達は、もう一度おばさんに頭を下げ。トレイを持って席に戻った。
「あれ、七海ちゃんはジュースとプリンだけでよかったん?」
私達が席に着く頃には、熊田さんはすっかりうどんを平らげて、ずずずっと残った汁をすすっていた。
私は、熊田さんにお釣りの小銭を返す。
「はい。今は飲み物が欲しいなって思って」
「そかそか。まぁ女の子って小食やったりするからなぁ。うちの娘もそやったわ……っていうても小さい頃の話なんやけどな」
「私って、食べる時と食べない時が極端なんですよ」
「そういうもんなんやなぁ」
私はその場をオレンジジュースに口をつける事で誤魔化した。
「七海ちゃん。ハンバーグおいしいよー。デザートもあるしさ、最高だよね」
不器用な箸さばきでハンバーグを切り分けながら、繭歌はハンバーグをゆっくり味わうようにもぐもぐと口を動かしている。その表情はとても幸せそうで、好きなメニューが夕飯に出てきた時の小さな子供を見ているようで、なんだか和んでしまう。
「そうそう。二人ともトラック降りたら次はどこ行くん?」
「え?」
熊田さんのいきなりの質問。
「え、えーと」
しどろもどろになってしまい、うまく答えられない。そもそも繭歌に付き添っているだけの私に答えられるはずがない。
「南に行こうと思ってますです」
私に変わって、繭歌が答えた。口のまわりにハンバーグのソースをたっぷりつけて。
「そうなんや。南いうても乗り物使わんと行ける範囲限られてしまうで?旧沖縄なんて車で行けへんし」
旧沖縄。日本の南端にある街。学校の社会の時間に習ったので場所は知ってるけど。私達の住む街からは遠く離れているし、行った事がないのでどれぐらいかかるのかわからない。
繭歌の事だから、漠然と言ってるだけなのかもしれないけど。
もしも、旧沖縄まで行くことになったとしたら。一体どうやって行けばいいのだろう?
見当もつかない。
「うーん。電車とかバスとか使えればいいんだけどねぇ……」
繭歌は口ではそう言うものの。あまり深く考えていないのがわかる。
事実、会話に参加しているように見えて。繭歌の視線は、目の前のプリンに釘付けだ。
「そやなぁ。ほんまは飛行機でも使えたらええんやろけど、今は飛んでへんし。電車とかも都内ぐらいしかまともに動いとらんからなぁ」
そういう情報は、なんとなく伝え聞いてはいたけど。
私達の街にいた時は遠くで起こってる事みたいで、あまり実感できなかった。
「やっぱ、ヒッチハイクとか歩いたりでがんばるしかないのかなー」
難しい顔でうんうん唸りながら、繭歌はプリンの蓋を開けた。
私も、オレンジジュースのグラスが空になったので。同じように、プリンに手をかける。
プリンの銘柄は、お母さんがよくスーパーで買ってきていたものと同じだった。
「そこはしょうがないんじゃない?少しずつでも、進んでいくしかないよ。無理のない程度にさ」
とても曖昧な言葉になってしまうけど。現実問題として、私達にはそんな方法しか思いつかない。
手持ちのお金にだって限界があるし。なかなか、一気に目的地へ。というわけにはいかないのだ。
「はぁ。そう考えるとなんか心配やわぁ。女の子二人だけでこの先行かせるはなぁ。俺が仕事なかったら付いて行ってやりたいぐらいやで」
割り箸入れの隣に置いてある、安っぽい銀色の灰皿を引き寄せ。熊田さんは煙草を吸い始めた。
「そんな、大丈夫ですよ。
「そうは言うてもなぁ……」
私の言葉を最後まで聞いてから、熊田さんは口を開いた。
「そら七海ちゃんはしっかりしとるように見える。けどな、それでもやっぱり俺から見たら高校生の女の子なんよ。生まれた町から今まで出た事ないんやろ?」
「はい……」
それは、その通りなので。返す言葉がない。
「別に、大人ぶりたいわけちゃうけど。それでもな、君らの住んでた町にもそら悪い奴もおったやろけど。その外側には、比べられんぐらいに悪い事する奴や、悪い大人がおんねん。自分のためやったら、他人なんか平気で踏みにじるような奴が数えられんぐらいおるんよ……」
実体験に基づくものなのか。熊田さんの言葉は、とても静かで。そして、深い。
だけど、熊田さんの言葉は。イメージとしてはなんとなく掴めるけど。あくまでドラマとか映画で今まで見たようなものからしか感じとるしかない。
「そやから、なんて言うかなぁ。こうやって誰かの車に乗せてもらうんかて、ほんまは危ない事やねんで?どこ連れて行かれるかわからんしな」
「でも、熊田さんはちゃんと乗せてくれたよ?」
「そら、俺は……いや、俺の事はどうでもええねん。何が言いたいんかっていうと、これからも旅を続けるんやったら、もっと用心して行かなあかんでって事やねん。」
「うーん。まぁ、とにかくさー。世の中には悪い人もいるけど、熊田さんみたいに良い人もいるって事でしょ?もしかしたら悪い人とも会っちゃうかもだろうけど。そういうのは当たって砕けろーって感じしかないんじゃないかなぁ」
熊田さんの言う。私達の経験の未熟さの話しはともかく。今の繭歌の発言があまりにも楽観的すぎるのだけは、私にもわかる。
さすがに、繭歌のようにその場になってから考えよう。みたいな、ノリだけでこの旅を進めていけるとは私は思っていない。
人生経験が少ないなら少ないなりに想像力だとか、知恵を絞って。目の前の壁とか難しい事とか、そういうあらゆるややこしい事に対処して行かなくちゃいけない。
繭歌が呑気に構えているなら、私がしっかりしなくちゃ……。
「だって、良い人に見えたって。裏では何考えてるかわかんないでしょー?」
「そんなん言い出したら。なんぼ、繭歌ちゃんがええ人や言うてくれても。俺かて腹の中は何考えとるかわからんやん?」
「それはないない。熊田さんは良い人」
繭歌は断言する。まぁ、その自信に根拠なんてないんだろうけど。
でも、熊田さんに限って言えば。私も同じ意見かな。
清廉潔白な人なんて世の中にいないとしても。良い人か悪い人かで言えば、私も熊田さんは良い人だと思う。
「なんや、かなわんなぁ……」
熊田さんは恥ずかしそうに下を向いて、すっかり短くなった煙草をそれでも、すぱすぱと吹かし続けた。
結局、話はそれで終わりになって、熊田さんはとりとめのない世間話に話題を変えた。私達も混じって話しこんでいるうちに、すぐにトラックの出発時刻がやってきた。
食堂から外に出ると、トイレから出た時よりも更に気温が下がっていて。上着を着ていても、肌身が冷たく感じる。
私よりも更に薄着な繭歌は体を丸めて寒さから早く逃げるように、一目散に小走りでトラックに向っていく。
これから、野宿をする事だってあるだろうし。どこかでもうちょっと分厚い上着を買ったほうがいいかもしれない。
私と繭歌が乗り込むのを確認すると、熊田さんはゆっくりとトラックを発車させた。
一台も車の通っていない道路に進入したトラックは、再び目的地へのルートへと戻っていく。
お菓子と。ジュースと。プリンと。お腹はすっかり一杯だ。もう、今日はこれ以上何も食べられそうにない。
大型トラック独特の、ゆったりとした揺れと。エアコンの温かさが、疲れた体に心地よく。緩やかな眠りを誘ってくる。
瞼が何度も重くなり、完全に閉じそうになる度に、なんとか意識を保って瞼をこじ開けるという事を、何度も繰り返す。
トラックがパーキングエリアを出て30分もする頃には、眠気と戦う私とは間逆に。繭歌は私の肩にもたれかかり、静かに寝息を立てていた。
何度か、逆方向に繭歌の体制を持っていこうと考えたけど。幸せそうな寝顔を見てると、それで起こしてしまったら可哀想だなと思い。結局、そのまま我慢する。
「眠かったら、寝とって全然かまへんで?多分、着くのは明け方頃になるさかい」
「あの、でも……熊田さんが起きてるのに、私だけ寝るっていうのは」
「あー。そんなん気にせんでええよ。トラック乗りは夜通し走るなんてしょっちゅうの事やし。なんだかんだで昼間に寝たりしてるさかいな。実はそんなに眠ないねん」
確かに、熊田さんの顔からはあまり疲れを感じない。
トラックの運転手という仕事を、私はよく知らないけれど。昼夜逆転の生活が当たり前のようだ。
「お、そろそろ県境やで。自衛隊の人らが検問張ってはるわ」
前を見ると、熊田さんが言った通り。迷彩服に身を包んだ人達が、何やらものものしい雰囲気で赤い点滅する棒を頭上で真横に構えてトラックに停まるように合図した。
「お仕事ごくろうさんです」
指定された位置にトラックを停めて、エンジンを切った。窓を開けて。熊田さんは自衛隊の人に愛想よく挨拶をした。
「いえ、こちらこそ。お手間をとらせてすいません。免許証の提示と、荷物の確認にご協力をお願いします」
「はいはい。ちょっと待ってくださいね。これ、免許証と積荷のリスト表です」
熊田さんは慣れた手際で免許証を財布から取り出し。数枚のコピー用紙と一緒に自衛隊の人に手渡す。隊員さんは厳しい顔で、免許証と熊田さんの顔を交互に2、3度見比べてから。表情を崩し、熊田さんに免許証を返却した。
「いま荷物のほうを確認しています。もうすぐ終わりますので……あの、失礼ですが。そちらの方達は?」
自衛隊の人の表情が、再び厳しいものに変わる。あからさまに疑いの目を向けられているのがわかった。
確かに自衛隊の人が疑うのもしかたないと思う。こんな時間に、運送トラックに明らかに未成年の私達が
乗っているというのは、どう見てもおかしな状況だ。
とにかく、ここで私達の身元がばれてしまうと。早くも家に連れ戻されかねない。
なんとか、誤魔化さないと……。
「この子らですか?うちの嫁さんの親戚の子で。ばあちゃんのとこまで連れていくんですわ。俺もたまたま今日はこの辺を通る仕事やったんで、ついでにと思いまして」
私が何か言いかける前に。熊田さんは、さも当たり前という調子で、自衛隊の人に説明しはじめた。
あまりにも、自然に話すので。私は熊田さんの言葉に合わせて。できるだけ、それっぽく頷くしかない。
「こんなご時世ですやろ?やっぱり、ばあちゃんにも会える時に子供らに会わせてやりたいですやん」
「なるほど……確かにそうですね。この先どうなるかわからない世の中ですから……」
精悍な顔つきで自衛隊の人は頷く。それ以上は、何も聞かれる事はなく。私達は荷物の検査が終わるまでおとなしく車内で待った。
しばらくすると、トラックの荷台が締まる音が聞える。
自衛隊の人は、胸についているレシーバから聞える声に、何度か頷いてから。再び熊田さんに話しかけた。
「ご協力ありがとうございます。荷物のほうも記載物通り問題ありませんでした。検査は以上ですので、通行してもらって結構です」
「おおきに、お仕事ご苦労さんです」
熊田さんは小さく頭を下げて、シートベルトを締めてから。トラックのエンジンをかける。
「おばあさんに会えると良いですね」
「あ、はい。ありがとうございます」
最後に自衛隊の人が優しく声をかけてくれた。下手な事を言うわけにはいかないので、笑顔を作って、会釈だけを返しておく。
車体の前に置かれていた小さな鉄柵が取り除かれ。自衛隊員の人の誘導に沿ってトラックは検問を通過した。検問を通過して5分も走らないうちに県境を越えた事を示す看板が目に入った。 町を出た時にはどうなる事かと思ったけど。越えてしまえば、どうという事はなく。拍子抜けするぐらいに呆気ないものだった。
「あの、助かりました」
「ん? 俺なんかしたっけ?」
「自衛隊の人に……」
「ああ、あれかいな。あそこは、ああでも言っとかんと俺も困るとこやったし。お互い様みたいなもんや」
それにしたって。咄嗟にあんなにもすらすらと言葉が出るものなんだろうか。
「ほら、俺ヤクザやっとったやろ。誇れる事ちゃうけど……ヤクザっていうのは。人を脅すか騙すかが商売みたいなもんやったから。ああいう嘘もとっさに言えなあかんのんよ」
「そういうものですか」
「そういうもんやなぁ」
熊田さんは真面目な顔で言った。
それから車内は無言になった。道路を走る音と、繭歌の寝息だけが聞える。
寄りかかってる繭歌の口の端から垂れた涎が、私の服の肩口に流れ、小さな染みを作っていた。
お気に入りの服なのに……。
繭歌の馬鹿。私はそっと、繭歌の頭を撫でた。
私も眠気が限界に近づいてきたので。シートに深く体を沈めて瞼を閉じる。
今日一日で、色んな事が起こった。急な変化に、まだ心も体もついていけていない。
とにかく、疲れた。今はゆっくり眠りたい。
周りの音がすぐに遠のき、疲労感が全身を満たしていく。
次に目覚めたら、私の目にはどんな景色が映っているのだろう。
とにかく。今は、おやすみなさい。
*
んー。
疲れた。疲れた。疲れた。疲れた。
なんで私がこんなに走らなくちゃいけないのかな。
すっかり夜になっちゃったし。
おかしい。
星奈は何もしてない。だって、みんながやれっていうからいわれた通りにしただけなのに。 最初はみんなほめてくれたのに。
なんで、急に怒りだしたのかな。
いっぱいいっぱい星奈のこと叩いてさ。すっごく痛くて。だからみんなぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。
ざまーみろだよ。良い気味だよ。
星奈のおしおきなんだよ。
……はぁ。それにしても、たくさん走ったから喉かわいたなぁ。
星奈はお水が無いと元気でないんだよ。どこかでお水をのまないと。
でも、ここどこなんだろ。いっぱいお家がある。
星奈はおうちのまわりしか知らないから。よくわかんない。
「みずー。みずー。冷たくておいしいみずー」
おっきな声で呼んでみるけど、何の変化もなし。
困った。
疲れたし、困ったし。さんざんだよ。
お部屋にいる時は、研究員さんがちゃんとお水を持ってきてくれたけど。自分で見つけるのは凄く大変なんだなぁ。それとも星奈が見つけるの下手なのかなぁ。
研究員さんは凄く嫌いだったけど……お水には感謝だなぁ。
あ、そうだ。もしかしたらお水の匂いがするかも。星奈は結構お鼻良いし。
どうして今まで気付かなかったんだろう。馬鹿だなぁ。
そう思ってお鼻をくんくんさせてみる。
……ん。……んんん?
甘い……匂いがする。甘くておいしい匂い。
水だ。お水の匂いだ。
匂いのするほうに向かって駆け足で向かった。もう我慢できないから全力疾走。
走ったせいで余計に暑くなっちゃったよ。でも、そこにはちゃんとお水があった。
ブランコ、すべり台。全部テレビで観た事がある。公園だ。
星奈より背の小さい子が、みんなで遊ぶ場所。星奈も遊んでみたいけど、今は小さい子いないし。一人だとつまんなさそーだし。また今度かなぁ。残念。
きょろきょろと辺りを見回すと、誰かがお水の出ている前で座っていた。
「何してるのー? 君もお水飲みにきたの?」
近づいて声をかけると、男の子ははびっくりした顔でこっちを見た。
背は星奈より大きい。もしかしたら年上のお兄さんなのかもしれない。
でも、星奈をたたいたり、いっぱい実験した研究者さんよりは年下かな?
「君こそ……その、何してるんだい? こんな時間に」
「んー。星奈はね。喉がからからでね。お水を飲みにきたんだよ。君も喉渇いたの?だったら星奈は順番まつよー。ちゃんと良い子で待つからね」
男の子はじーっと星奈の顔を見る。何か変なのかな?研究員さん達は、「星奈は他の人とは違って特別なんだよ」って言ってたけど。よくわんない。
「……いいよ。君が先に使いなよ」
男の子は、おいしそうな水を星奈に譲ってくれた。うん。良い人だ。きっと。間違いない。「ありがとー。いただきまーす」
たくさんのお水を、ごくごく飲む。
幸せ。飲むだけじゃ足りないから、頭からもたくさんお水をかぶっておこう。
お水が体に染み込んでいく。気持良い。
「あのさ」
「ん?なにー?」
「その、そんな風に浴びたら服にかかっちゃうよ?」
「かかると駄目なの?」
「駄目っていうかさ……」
男の子は星奈の胸の辺りをじぃーっと見る。
たくさん水を浴びたせいでワンピースがすけすけになってた。この事を言いたいのかな?
でも、なんで?
「なんか、変かな」
「色々まずいよ。女の子なんだし」
「そうなんだ。じゃあ次からは気をつけるね」
濡れた服の裾を握って、ぎゅーっと絞って、ぱたぱたと揺らして乾かす。
「だ、だからさ」
「ん?」
「それもまずいと思う。下着、見えちゃってるし」
「そっかー。色々気をつけなきゃいけない事がたくさんあるんだねー」
星奈はずっとお部屋の中にいたから、知らない事がたくさんあるみたいだ。
「もう、良いかな?僕も使いたいんだけど……」
「あ、そっか。ごめんごめん」
そうだね。星奈だけがずっと使っちゃだめだよね。星奈は元気になったから、男の子に変わってあげよう。
「君もたくさん飲むの?」
「僕は別に水を飲みにきたわけじゃないから……」
男の子はなんだか、そわそわしてる。
「えっと……用が済んだなら、できれば違う場所に行って欲しいんだけど……」
「え? なんでー?」
「何でって、言われても」
男の子は後ろに隠した手を凄く気にしてるみたいで、ちらちらと何度もそこばかり見ていた。
何かあるのかな。楽しいものかな?星奈の知らないものかな?
確かめてみよう。面白いものだったら良いなぁ。
「わ、ちょっと。駄目だって。何してるのさ」
「ね、ね。なになに?なに隠してるの?見せて見せて」
「危ないから、ちょっ。ほんと、ちょっと待って」
ぐいぐいと男の子と押し合いになる。星奈も負けないように、力一杯ぐいぐい体を動かして男の子の後ろにまわりこむ。
「あ、みっけ」
「……」
何度か押し合って、やっと男の子が隠してるものを見る事ができた。
んー。でもあんまり面白いものじゃない。
「えっと、それは。えっと。包丁……だよね?お料理に使うやつ」
「……そうだよ」
「なんで隠してたの?ここでお料理するつもりだったの?」
「そうじゃない……けど。理由は言えない」
「内緒なの?」
「そう」
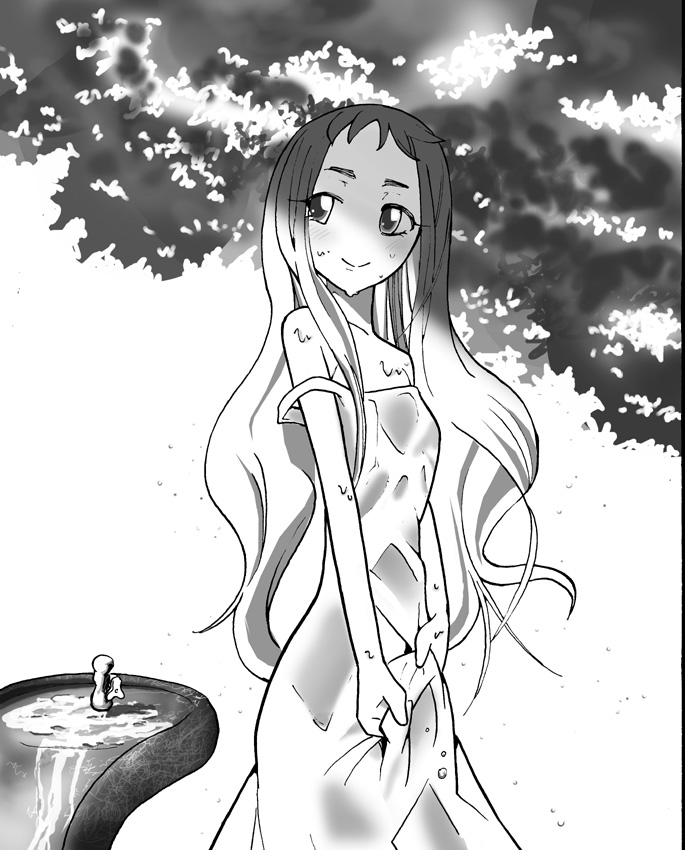
どうして内緒なんだろう?
お外で包丁持ってるのは悪い事なのかな?
だから、男の子は星奈に見られたくなかったのかな?
「あのね。星奈ね、誰にも言ったりしないよ?」
「言わないでくれると、助かるよ」
「うん。やくそくするよ」
やくそくは、ちゃんと守らなきゃいけない事。
だから、この事は男の子と星奈だけの秘密なんだよ。お口チャックだ。
「あ、そだ。ねぇねぇ。さっき包丁についてたのなにー?」
「……っ!」
男の子は星奈を睨んで来た。さっきまで優しかったのに……急に怖い顔になっちゃった。 星奈何か悪い事言ったかな?ごめんなさいしたほうが良いのかな?
「なんか赤いやつがね、べとーってついてた」
「それも見たの?」
「うん。星奈みたよー。包丁にね赤いの一杯ついてた。赤いのは……えっと……」
そうだ。さっき見たところだ。星奈にひどい事してた研究員さんを、ぼきぼきぐしゃーってやった時に、一杯流れてたやつ。お肉がびりーってなったところから、たくさん出てたやつ。「体からたくさん出るんだよね。ぬるぬるで、とろとろで、あったかいんだよね」
「からかってるの?人間の血液だよ……それぐらいわかるだろっ!」
「う、ごめん」
大きな声で怒鳴られた。星奈がちゃんと答えられなかったからかな?。
怒られるのやだなぁ……しゅんってなっちゃうよ。
「そっかぁ。あれは血液っていうんだね。たくさん見たけど、はじめて名前がわかった。
「でもなんで人間の血液が包丁についついてるの?人間をお料理したの?」
「ほんと、変な子だな……」
男の子は怒ったままで、またお水で包丁を洗い始めた。
「何かお手伝いできる事あるー?星奈も手伝いするよ?」
「いいよ、もう終わるし。それよりさ、とりあえず早くどこかに行ってよ」
「星奈の事、嫌い?」
「会って間もないのに好きも嫌いもないだろ。そもそも名前も知らない者同士なのにさ」
「あ、そっか。はじめて会った人にはご挨拶しなきゃいけないんだね」
そうだ。星奈は研究所でいろんな人に会わなきゃいけなかったから、ちゃんと挨拶しなさいってお母さんに言われたんだっけ。
「えーっと。星奈はね、星奈っていうだよ。よろしくお願いします。なんだよ」
頭をぺこりと下げる。うん、お母さんに教えてもらった通りにちゃんと出来た。星奈えらい。お母さんが見てたら絶対褒めてくれたよ。
「あ、そう……」
男の子は星奈の事なんてちっとも気にしないで、ずっと包丁をごしごししている。
「もー。星奈はちゃんとご挨拶したのにー。したのにー」
「そんなのそっちの勝手じゃないか」
「えー。君の名前も教えてよー」
「嫌だ。それに知らないほうが良いよ。君にも迷惑かかるかもしれないし」
「なんで?星奈全然めいわくじゃないよ?」
だって星奈はすっごく知りたい。
星奈はずーっとおっきな白いお部屋の中にいて、いつも一人で。
お母さんはいつも忙しそうだったから、時々しか遊んでくれなくって。
だから、星奈と同じぐらいのお友達がずっと欲しいなーって思ってだんもん。
「……だめ?」
「……」
うぅ……。返事してくれないよ。
やっぱし、星奈の事嫌いなのかなぁ。
せっかくお友達になれるかなーって思ったのになぁ。
星奈はお友達つくるの下手なのかなぁ。
それから、男の子はずーっと星奈とおしゃべりしてくれなくて。
ごしごしごしごし包丁を洗う音だけしかしなくて。
星奈はちょっと……ううん。すっごくすっごく寂しいんだよ。
「……浩平」
包丁をごしごしする音が止まって、男の子はまた星奈に話しかけてくれた。
よかった。星奈の事、忘れてたんじゃなかったんだ。
「え?え?浩平?それが君の名前?」
「……そう」
お名前聞けた。
浩平くん。
はじめてできたお友達のお名前。ちゃんと覚えておかなきゃ。
「教えてくれてありがとーだよ。これで星奈と浩平はお友達だね」
「それは……ちょっと違うと思うけど」
「あのね、あのね。星奈はね。浩平の事の好きだよ」
「何かの冗談?」
「違うよー。浩平はお水飲ませてくれたし。良い人。だから、星奈は浩平が好きなんだよ」 「公園の水なんだから、別に誰が使っても良いんだよ。僕だけのものじゃないし」
「でも浩平は優しいよ。星奈にはわかるんだよ」
「ほんと……単純だね君。よし、これでいいや」
お水を止めて、服で包丁を拭いた浩平は、ぴかぴかになった包丁を見て嬉しそう。
公園の灯りできらきら光る包丁は、小さな三日月みたいでとっても綺麗。
「僕の用事は終わったから、君も早く帰りなよ。家族が心配するよ」
「んー。でも星奈どうやっておうちまで帰っていいかわかんないんだよ」
星奈の住んでた場所はおっきな建物がたくさんあったけど、ここには全然ないし。
多分、研究者さん達の車に乗せられて走ってたから、全然知らないところに来ちゃったのかな。
「迎えに来てもらえば? 携帯とか持ってないの?」
「けーたい?よくわかんないけど、星奈は持ってないよー」
「どこの子か知らないけどさ、世間知らずにもほどがあるでしょ」
「あはは。ごめんだよ、お外の事はよくわかんなくって」
浩平ははぁぁぁーって、大きな息を吐いた。
「はぁ……そうなんだ。とにかく僕はもう行くから。どこか交番で保護してもらうんだね」
すたすたと浩平は公園を出て行こうとする。
あれ?もう行っちゃうのかな?
まだ会ったばっかりなのに。全然おしゃべりもしてないし。全然遊んでないんだよ。
「わ。わ。待ってよー、浩平もう行っちゃうの?せっかくお友達になれたのに?」
「だから、友達じゃないって」
「浩平のお邪魔しないから星奈もついていきたいんだよ」
浩平が行っちゃうのやだから、星奈は浩平の腕にぎゅうってしがみつく。
「ついてくるだけでも邪魔なの」
「途中までだからー」
「腕、腕離してってば。胸が……胸があたってるから」
「あ、ごめんだよ」
浩平は真っ赤になって、汗たらたらで手をばたばたさせてる。
何でなのかわかんないけど、浩平が苦しそうだから手を離してあげた。
「あのさ。僕こういうの苦手だから、やめてくれる?」
「んー?うん、浩平が嫌なら気をつけるよー」
自分の胸をわしわしと触ってみる。ふにふに。やわらかめ。
浩平はふにふにが嫌なのかな?
「そりゃ、僕だって何もなければ君が家に帰れるように手伝ってあげたいけど……今はほんと駄目なんだって……」
「星奈はもう少し浩平と一緒にいたいよ。たくさん遊びたい」
「そんな子供みたいな事言われても……」
「駄目?」
浩平はすごーく難しい顔で、星奈の顔をじぃーっと見た。
「あのね……僕はこれから、急いでこの街を離れなきゃいけない。だから、君とこれ以上一緒にいれないし。遊べない。わかった?」
「う……でもでも」
「わかった?」
「ん……んー」
浩平は凄く真剣で。星奈はとってもお邪魔してるのかな? て思う。
うー。でもでもでも。星奈だって真剣だし。遊びたいって思うけど、でも、それは星奈のわがままだから。やだやだって言って浩平を困らせたくない。
我侭は駄目。
自分の事ばっかりで、我侭な子はみんなに嫌われるわよ。
お母さんが言ってた。
星奈は嫌われたくない。たくさんお友達ほしい。
だから、我侭は言わない。我侭はだめだ。
「……わかった」
星奈がお返事すると、浩平はちょっとだけ頭を下げて「ごめん」って小さく言ってから早足で歩きだした。
後をついて行きたいけど。手をぎゅーって握って我慢、がまん。
浩平の背中がだんだん小さくなっていく。
また、会えるといいなぁ。
浩平の背中に、手を振ってばいばいってする。
ちゃんと……お友達になれたのかな?
でも、一緒に遊んだりできなかったし……。
浩平はお友達って思ってくれてないかも……。
う……。
泣きそうだよ。
胸の奥がきゅってなって。苦しい。
目にたくさん涙が溜まってくる。すぐ泣いちゃうのは星奈のいけないとこだ。
これも、お母さんが駄目って言ってた。
だから、我慢。
大丈夫なんだよ。星奈一人で遊んじゃうんだよ。
誰もいなくても、つまんなくなんて……ないんだよ。
公園を星奈だけが独り占めして、一杯遊んで。後から浩平がやっぱり星奈と遊んでれば良かったーってくやしくなっちゃうかもだよ。
せっかくお外にいるんだし。おうちじゃできない事をたくさんしないとだ。
もし、おうちに戻ったら。今度はいつお外に出れるかわからないし……。
うし、決めた。たくさんあそぼー。
えっと、まず最初は何で遊ぼうかな。あ、あれにしよう。ジャングルジム。
確か一番上まで登って遊ぶんだよね。
まず、低いところに掴まって……わ。なんだかひんやりして気持ち良いんだよ。
いっちに。いっちに。上を目指していく。
競争する人いないのが、やっぱり残念。
ぐいぐいって登って、てっぺんにとーちゃく。
お空にはまんまるお月様だ。
手をうーんと伸ばす。いつもより、ちょっとだけお空が近い。
もっと、もっとおっきなジャングルジムがあったら。お月様まで届くのかな?
てっぺんまで登るの大変そうだけど。いっぱい時間かかるかな。
うーん。それにしても……。
これからどうしよう?
星奈はどうすればいいんだろう?
がんばって、たくさん考えてみる。
うーん。えぇっと。えとえと。
おうち。そう、おうちだ。
とにかく、お母さんのところに戻らなくちゃだけど。
一人でお外を歩いた事ないし……大丈夫かな?
でも、でもでも星奈だってもう子供じゃないし。
道さえわかれば、きっと帰れるはずなんだよ。
……お金とかないけど。でも、歩けば大丈夫だよね。
お水さえちゃんと見つければ、星奈は結構丈夫だし、歩くのだってへっちゃらだし。
なんとか、なる。うん。なるなる。
がんばろう。星奈一人でおうち帰れたら、お母さん褒めてくれるかな。
なんとかなりそうな気がしてきた。
「星奈、がんばるんだよ」
ジャングルジムの上からぴょーんってジャンプする。
上手く着地できたけど、足の裏がぴりぴりって痺れた。
「……ジャングルのジムの頂上から飛び降りるなんて危ないだろ」
「はえ?」
それは、嘘みたいで。星奈、知らない間に寝ちゃってて。夢でも見てるのかなって思った。
だって、だってだってだって。目の前に浩平が立ってたから。
さっきばいばいってして、いなくなっちゃって。寂しいなってなったのに。浩平が目の前にいる。
「こーへーだ。こーへーがいる」
嬉しくて。どんな風に言えば良いのかわからないから、星奈は浩平に思いっきりぎゅってする。
「だからっ!なんで、すぐそうやって抱きつくかな。君は」
「あ、ごめんなんだよ」
そうだった。ぎゅってしたら浩平はヤなんだった。
浩平はまだハジライヲーとか言ってるけど、星奈はよくわかんないや。
「でも、星奈。浩平がいるの気付かなかったんだよ」
「僕は下から何度か呼んだけどね。なんか、上向いてぼーっとしてたから。降りてくるの待ってたんだ」
「ごめんなさい」
「別に……いいんだけどさ」
「えへへー」
「なに?」
浩平は優しいんだなぁ。好きだなぁって思って見てると、浩平はぷいって横を向いた。
「あ、でもでも。浩平は忙しいんじゃなかったっけ?」
「そりゃ、忙しいし。急いでるよ。でも……やっぱり君をほっとくわけにはいかないだろ。こんな時間に女の子を一人で置きざりにするなんて、気になってしょうがないじゃないか」
「そうなんだ。浩平は星奈を心配してくれたんだね。ありがとうなんだよ」
「まぁ、そんなわけだから。とりあえず僕と一緒にくれば。どこまで一緒にいれるかわからないけど……一人でいるよりはましだろ」
「うん、うん」
浩平の手をきゅって掴む。
「ちょっと、何してんのっ!」
「星奈が迷子にならないように、手を握ってて欲しいかもなんだよ」
「あ、あっそう」
浩平が星奈の前を歩いていく。でも、さっきと違って星奈の手をちゃんと握ってくれた。 星奈と浩平なら、なんでもできそうで。どこにだって行けそうだよ。
なんだか、無敵。
いざ、出発なんだよ。

