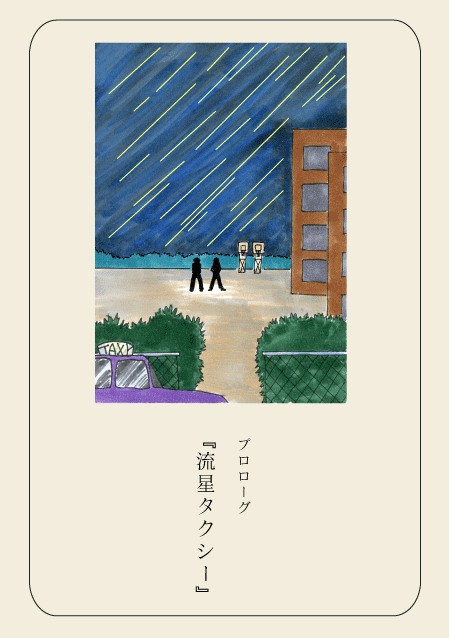月曜の朝はいつも通り、最悪の頭痛から始まる。
ごろりと寝返りを打って、天井を見上げる。黄ばんだ視界の中で、木目がゆらゆらと波打った。自分の呻き声すら、耳鳴りに紛れてどこか遠くから聞こえてくるようだ。
昨日の夜の記憶は、同僚と三件目のスナック「エイリアン」に入ったあたりから途切れている。なんとなく体を探ってみたが、服は特に汚れていない。ママのユウカあたりがうまくやってくれたんだろう。火星人みたいなツラだが、あれでなかなか気が利くヤツだ。
意識ははっきりしてきたが、耳鳴りが消えない……と思ったら、どうやら誰かの声のようだ。痛む節々を気遣いながら体を起こす。
「では、次のニュースです。今日三月三一日に、しぶんぎ座流星群が夜空で観測されます。国立天文台の発表によりますと、今年は例年と比べ、見ごろとなる時期が大幅にずれ込んだほか、流星の元となる塵が観測史上類をみないほど多く飛来するとのこと。ピークとなる午後八時ごろには、一時間に最大四〇〇から五〇〇の流星が見られると予測されており、各地ではそれを見込んだイベントも開催されています。朝は雲がありましたが、昼には青空が広がり、ここ新都市でも多くのファンが――」
俺は手元のリモコンを持ち、テレビの電源を切った。流星群? くだらねえ。星クズが燃えるのを見て、何が楽しいんだってんだ。
せんべい布団から身を引きはがす。枕元の携帯を手にとった。案の定、ユウカからメール。
『将やん、ベロンベロンになってたから、タクシーに押し込んどいたわよ。無事に帰れた? あんたもいい年なんだから、もうちょっと大人らしく飲みなさいよね。☆YU―KA☆ 追伸:タクシーの運転手が毎回タクシーのお世話になるって、面白くない? 持ちネタにしたら、あんたのお気に入りのアヤカちゃんも口説けるかもよ』
うるせえ。無視だ無視。つけっぱなしの腕時計を見ると、そろそろ正午をまわるころだった。そろそろ出勤か。大あくびをして、目頭にこびりついたヤニをほじくり出す。
「ウッス! 将さん、お疲れッス!」
会社にやってきた俺が、殺風景なロッカーで制服に着替えていると、根津がやってきた。
「おーう」
ピョコピョコと頭を下げて、俺の隣のロッカーを開ける。その動きといい、小柄で顎の細い顔立ちといい、相変わらずネズミにそっくりだ。
「いやー昨日は楽しかったっスねー。ごちそうさまでした、本当に!」
それにしても、昨日俺と一緒に飲み明かしたってのに、ずいぶん元気そうだ。確かコイツは今年で二八。で対する俺の方は……。
「どうしたんスか将さん。溜息なんかついて。やっぱ昨日飲みすぎちゃいました?」
「うるっせえな。テメーと違って若くねぇんだよ、俺ぁよ」
「またまたそんなこと言って~。昨日も凄かったッスよ、ほら、あのアヤカちゃんですっけ? 口説きまくってて。四十手前であの積極性、俺も見習いたいッスわ~」
「あんだぁ? てめぇ。今俺のことバカにしただろ、オイ」
着替えながら軽く背中に蹴りを入れてやる。根津は、いでぇ、ちょ、違いますってえとか何とか言って笑っている。慕ってんだか、バカにしてんだか、相変わらずよくわからねえやつだ。
「それはそうと、あのニュース見ました? 将さん」
「あぁ、流星群だっけか?」
俺がそう答えると、根津は目をパチクリさせた。
「……なんだよ」
「いや……将さん、意外とロマンチックなところあるんだなって思って……」
蹴り。
「いでぇ! ちょ、スミマセン冗談ですって。いやそれじゃなくて、ほら。東京で起きた通り魔事件の」
「あぁ」
それなら知っている。三日前、渋谷の大通りで、覆面を被った男が、ナイフで通行人を無差別に斬りつけたってニュースだ。
「全国指名手配したけど、まだ捕まってないんだよな? 確か」
「そうそう。で、ここからが僕の聞いた情報なんスけど……」
根津はそこまで言うと、ほかに誰も聞いてないのに顔を寄せ、声を潜めた。
「どうやらその犯人が、新都市に逃げてきてるらしいんス」
午後四時。俺は田んぼの脇にタクシーを停め、外でタバコを吸っていた。
平日の昼間なんて、流したところでロクに客も捕まらない。無線で時々指示が飛んだが、それだって大した数じゃない。というわけで俺は今、堂々とサボっているというわけだ。
春先の少し冷たい風が、タバコの煙を吹き散らしていく。新都市の市長は、ついこないだ人口二十万人を突破したとか言って自慢してたが、ちっとも都会になった気がしない。駅前から十五分も走りゃ、あるのは住宅地と田んぼばっかりだ。ちょっと横道に入れば、駐禁切符だってロクに切られやしねえ。
タバコの煙を吸い込みながら、昼にロッカーで根津と交わした会話を思い出す。
『実は、あの犯人、新都市の出身らしいんス。しかもどうやらお偉いさんの息子とかなんとかで……。ほらウチも、最近街おこしに力を入れて、知名度も広まってるでしょ。あんまり街のイメージをダウンさせたくないって事で、しばらく匿おうとしてるみたいッス』
『へー』
『なんスか、反応薄いッスね」
『お前の流す噂は話半分に聞けって、カミさんに言われてんだよ』
『将さん、確か独身じゃなかったッスか?』
『うるせえな。そこは正しい情報仕入れなくていいんだよ!』
『いでえ!』
……。
思い出すだに、アホくせえ話だ。
根津の噂好きはいつものことで、毎日どっからか、ワケのわからねえ情報を仕入れてくる。駅前のドーナツ屋がこっそり麻薬を売ってるだの、三丁目の神社に夜な夜な女の幽霊が現れるだの……。こないだなんかは「今、宇宙人を目撃したっていう住民が増えてるんスよ!」とかほざいてて、ありゃもう一種の病気だ。
ただ、毎日くだらない噂を吹いてまわるアイツの気持ちも分からなくはない。
要は、退屈なんだ。
俺も含めて、新都市で働いている人間のほとんどは、ここで生まれ育ったヤツばかりだ。人間関係も、街並みも、誰かとの話題もちっともかわりゃしねえ。
だから、この街に住むヤツはみんな、そんな単調さをどうにかしたくて、どうでもいいことに熱を上げる。
かくて根津はヨタ話の拡散に精を出し、俺は連日酔い潰れては、エイリアン面のババアの世話になるというわけだ。
タクシーの無線機が、不意に声を上げた。
「二一〇号車、二一〇号車、駅前にフリーで一名、どうぞ」
……チッ、仕事か。めんどくせえが、ちょうどタバコも吸い終わっちまった。
「二一〇号車、二一〇号車」
俺は運転席に乗り込み、オウムみたいに繰返す声に応えてやる。
「了解 どうぞ」
それから、車をスタートさせた。
駅までの距離はさほど遠くない。大通りを走ると、すぐに駅が見えた。一昨年くらいに立て直した駅だ。見てくれは城のように立派だが、塗りムラのある薄いピンクの塗装が、どうしようもない安っぽさを醸し出している。そのロータリーのところに、スーツ姿のサラリーマンが一人、立っていた。
中肉中背、いや、ちょっと肥満気味か。だが、顔はどこか病的にやつれている。車に乗り込んでもきょろきょろと落ち着きがない。
その顔に、何故か俺は既視感を抱いた。どこかであったような顔。どこだろう?
「お客さん、どちらまで」
俺が聞くと、男はバックミラー越しに俺の顔を見て、一瞬硬直したようだった。そこからぱくぱくと口を開いて言葉をさがし、やっと掠れるように声を絞り出す。
「い、いやちょっと、行く場所の住所を、ド、ド忘れしちゃって。ハ、ハハ。ちょっと大通りをまっすぐ言ってもらえます?」
そのとき、根津との会話の続きが、ハッキリと脳裏に蘇った。
『いや、ホントですって! 結構特徴もハッキリしてるんスよ。年齢は四十手前くらい。ちょっと肥満で、でも顔は凄くやつれてて骸骨みたいな感じで……』
『そんな大雑把な特徴があるかよ、バカ!』
『いや本当ですって! あ、あとこれ決定的な情報。なんでも、首の後ろに小さい蜘蛛のタトゥーがあるらしいっス』
バックミラー越しに男を見る。正面を向いているので、当然首の後ろは確認できなかった。
……いや、まさか、なあ?
「あ、えっと、たぶんここを右だと思います」
「そうですね。そのまま真っ直ぐ行ってもらえば」
「いやあれ、今度はここを左だったかな?」
俺は黙って男の指示に従いながら、本部にどう連絡したものか迷っていた。
もちろん、強制的に下ろして、警察に通報するって手もある。だが、相手が無差別通り魔事件の犯人かもしれない、と考えると余り気は進まない。最近のタクシーは客席と運転席の間がアクリル板で仕切られているが、俺のタクシーは型が古く、仕切りがないままだ。
男の見た目はヒョロそうだし、俺がもう少し若けりゃ、相手がナイフを持ってようが取り押さえるだろう。だが、正直言って、もう今は体力に自信はない。ましてや、狭い車内で突然襲い掛かられようものなら……。後ろからナイフをブスリとやられる自分を想像して、首筋の毛がチリチリと逆立った。
とはいえ、このままにしておくわけにもいかない。俺はつとめて気楽そうに聞こえるよう気をつけながら、口を開いた。
「お客さんは、どちらからいらっしゃったんで?」
「えっ? あ? ハイ、 あの……東きょ、東京です」
「東京ですかー。こちらにはどのようなご用向きなんですか?」
「あっ、えっ、あの……。その、シュッ、出張です、出張」
「そうですか……。まあ東京と比べると、田舎でしょ、ここも」
「あっ? え、いや……そうですかね」
「そうですよ。僕なんか、ガキのころからずーっとここに住んでますけどね。まあ、いつまでも代わり映えしませんわ、ここは。ハハハ」
「……は、はぁ」
相手はまだ、おどおどながらも、少し落ち着いてきたようだ。よし、いいぞ。いい感じだ。俺は相手に気付かれないように、最寄りの交番に向かってハンドルを切る。
「友達なんかも、もう数十年来の付き合いでね。僕なんてもう三十八にもなるのに、未だに『将やん』なんて呼ばれてますから。あ、本名は将太って言うんですけどね」
「『将やん』ですか……」
男は俺から視線を外し、チラリと窓の外を見た。いかん、気付かれてしまう。
「そうそう。ちょうどここらへんの学校に通ってたんですよ。懐かしいなあ……。こういうのもなんですが、昔は結構ガキ大将でねえ。転校生なんかを小突き回して、イバりちらしてたもんですわ。って、あんまり自慢できた話じゃないですな。ハハ」
「その転校生はどうなったんですか?」
「え? ああ。その子は……中学くらいで転校しちゃいましたね。お父さんが転勤族だったみたいで。おっと、到着しました」
「え?」
あっけにとられた男を尻目に、俺は交番の前に車を停めると、後部座席のドアをロックし、自分は運転席からドアを出た。これでしばらく時間を稼げるはずだ。俺は交番に駆け込む。
「お巡りさん、すいません!」
しかし、返事はこなかった。薄暗い交番の中は、もぬけの殻。目の前のデスクには、簡素な張り紙がしてあった。
『パトロール中です。緊急の場合は下記の番号に……』
「クソが!」
俺は思わず叫び、制服から携帯電話を取り出す。コール音がもどかしい。
「もしもぉーし?」
焦る俺の神経を逆なでするように、間延びしたオッサンの声が電話に応じた。
「あーすいません、どうも不審な男を見つけまして……今交番の前にいるんですが」
「はあーい、了解。ちょっと待っていてくださぁーい」
何だコイツ、酔っ払ってんのか?
「なるべく急ぎで。もしかしたら東京の……」
電話しながら振り返り、俺は思わず声をあげた。
「あっ! コラ!」
男が前の席に移動し、ドアを開けて出ようとしていたのだ。
「どうしました?」と聞いてくる電話を切り、逃げようとする男を追いかける。
「待て、コラ!」
振り返った男は、拳を振り回した。一瞬、ナイフでも持っているかと思ったが、幸い徒手空拳のようだ。俺は気を取り直して男に組み付いた。
「おとなしくしやがれ!」
「やめろ! 離せ!」
相手は必死に手をばたつかせたが、俺が昔習った柔道の大外刈りをかけると、あっけなく地面に叩きつけられた。背中を打った衝撃ではげしく咳きこんでいる。
「おおーい、何してるんだ」
そこに、銀色の自転車に乗った警察官がかけつけてきた。定年前、といった感じの、白髪交じりのジジイだ。まったく、手間をとらせやがって。
男の腕をつかんで引き立たせ、背中にむけて手をねじりあげた。呻く男の耳元で話しかける。
「ここで事件のほとぼりが冷めるまで隠れていようってハラだったんだろうが、お前が通り魔だってことはとっくにバレてんだよ! その証拠に……」
襟を引き、首の後ろを露にする。そこには小さな蜘蛛のタトゥーが……。
なかった。
「あれ?」
困惑する俺に向かって、ようやく息を整えた男が、弱々しく呟く。
「将やん、酷いよ」
「あ?」
「俺だよ、俺。中学で転校した……金丸。覚えてないの?」
「……ああ!」
そこで俺はようやく、最初に男を見たときの既視感の正体に思い当たった。
根津のヨタ話が原因なんかじゃなかったのだ。
「何だい何だい、こいつが怪しい男かい」
自転車をのんびり路肩に停めていた警察官が、最悪のタイミングで話に割り込んでくる。
「いや、あの、これは……」
「新都市に戻ってきたら、あの時のガキ大将が運転手で……。いきなりコレだもん。ひでえよ」
「何だい、ただのケンカかい。ま、いいや。とりあえず話は交番で聞こうか」
「いや、あの俺仕事が……」
弱々しい俺の呟きは、誰にも拾われずに空中に消えていった。
クソ、根津の野郎、覚えとけよ。
「あぁ……、ああ、そうそう。結局勘違いだったんだよ。しかも、そいつが誰だった思う?金丸だよ、金丸。中学校のときの。いやー全然変わってなかったわ。ま、そんなわけで、こっちは問題なさそうだわ。うん、ああ。悪いな。また報告書は明日書くから。うん。お疲れー。あ、あと根津にブチ殺すって伝えといて。じゃな」
俺が電話を切ると、金丸が陰気そうな目で俺を見た。
「今の、誰?」
「ああ? 和田だよ、和田。転校する前、同じクラスだっただろ。アイツ今、俺が働いてるタクシー会社の社長やってんだよ」
「ああ、和田君か……」
「ハハ、お前あいつにも大分パシられてたもんな。あんま良い思い出はないか」
「……久しぶりに帰ってきたのに、いきなり最悪だよ、ほんと」
「ああ? てめえがキョドキョドしてるのが悪いんだろうが。第一、悪いと思ってるから、こうやってメシ食わしてやってんだろ」
午後七時。俺と金丸は、ファミレスでメシを食っている。
コシがまるでないパスタを啜りながら、俺は金丸を睨みつけた。
「俺だっておめえ、無駄に調書とられてよ、今日はもう来なくていいって言われるし、散々だぜ。どうしてくれるんだ」
まあ、実際はサボる口実ができて内心万々歳なんだけどな。
金丸は、本当に悪いと思っているのか、黙ってパスタを啜っている。相変わらず昔から、陰気くさいヤツだ。
その姿を見ながら、俺はさっきから浮かんだ疑問をぶつけることにした。
「なあ、お前、何でここに来たんだ?」
「え?」
「いや、だってお前、里帰りって感じでもねえだろ。小学校の途中から中学校までしかいなかったんだしよ」
「それは……」
「第一お前、今日は平日だぞ? 出張に来たっていうのに、こんな時間になっても会社に連絡一つもとろうとしねえ。第一、お前会ってから今まで、一度も携帯出してないよな?」
「……」
「お前、タクシーに乗った瞬間に、運転手が俺だと気付いたんだろ。もし別人が運転手だったら……本当はどこに行くつもりだったんだ?」
金丸はパスタを啜る手を止め、じっと黙っている。
「答えろよ、オイ」
机を叩き、ドスを利かせて呟くと、金丸はビクッと体をふるわせた。……やがて、絞り出すように呟く。
「……本当は今日、死ぬつもりだったんだ」
それから、ぽつり、ぽつりと話し出した。
転校した先で、酷いイジメにあったこと。
サラリーマンだった父親が仕事をクビになり、離婚した母についていったこと。
大学にも行けず、バイトをして家計を支えていたこと……。
「それでも、そこそこの会社に就職も決まってうまくやれてたんだ。だけど、今年でもうクビさ。母さんだってもういい年さ。これからどうして行けばいいのかわからない」
そう言うと、金丸は頭を抱え込んだ。
「いつだってそうだ! 何でこんなにうまく行かない? 小さいころから親の都合につき合わされて、どこに行っても仲間に入れなかった。君たちの時もそうさ。東京から来たってだけで、ずっとからかわれてた。大学に行こうとしたら両親が離婚して、そろそろ結婚でも、って考えたらクビさ。会社も学校も、東京だってここだってどこだって、みんなが俺を受け入れてくれない。俺が……俺が何をしたっていうんだよ! 畜生!」
激しく叫び、机を叩く。
「挙句の果てには、死のうと思ってやってきたこの街で、昔のガキ大将に再会してこのザマさ。ちゃんと死ぬことさえ、運命が邪魔するんだ。何ひとつ、うまくいった試しがない……」
そう言うと、金丸は泣きだした。騒がしかった店内は、この騒ぎにすっかり静まり返っている。
「お客様、あの、他のお客様のご迷惑となりますので……」
ウェイトレスがやって来て、金丸に話しかける。
「すみません、すみません」
金丸はそう謝りながら、顔を涙でグチャグチャにしていた。
俺は言った。
「おい」
ウェイトレスが振り返る。
「うるせえな、こいつの好きにさせてやれよ」
「えっ?」
「てめえ、こいつの話、聞いてなかったのかよ。今ぐらい好きに泣かせてやれっつってんだ」
「ですが……」
「ああ?」
俺は顔に怒気をはらませて立ち上がる。
「ここじゃあ、死にたいくらい追いつめられてる客を泣かせる自由もねえってのか? 上等だ! 店長呼んでこい!」
「もう、帰るから、ちゃんと降ろしてくれよ!」
「ダメだっつってんだろ? いいから乗ってろ、ボケ」
結局、あのあとゴネまくった俺たちは、メシ代をタダにしてファミレスを出た。
そして、嫌がる金丸を無理矢理タクシーの助手席に乗せ、夜道を走っている。
「どこに連れてく気なんだ。頼むから、もう勘弁してくれ……」
「ダメだ。どうせうまく行ってない人生なんだろ? だったらもう少し俺のワガママに付き合えよ」
そう言い返すと、金丸は諦めたように黙り込んだ。
タクシーは住宅街を行き、田園地帯の路地に入り込んでいく。
都心部を遠く離れたこの場所には、ぽつぽつと数えるほどにしか明りがない。
時刻は七時五十五分。もうすぐ目的地だ。
「え、ここって……」
車を停めたのは、俺たちが通っていた小学校……の裏門。
「よし、入るぞ」
そう言って、車を降りる。
「え、ちょ、入るってここに?」
「そうだよ、ほかにどこがあるってんだ」
「……いや、不法侵入だよ」
「うるせえな。ごちゃごちゃ言ってねえで早く来い!」
助手席を開けて金丸を引きずり出し、「何で四十前にもなってこんなこと……」とブツブツ呟いているケツを蹴り飛ばして校門を乗り越える。
「東京だったら、確実に監視カメラに映ってるね」
「うるせえ、ここは新都市だ、そんな気のきいたもんは、ねえんだよ」
職員室に電気がついていないのを確認して、校庭に出る。
「何だよ、ここに何があるって言うんだ」
「いいからど真ん中まで走れ!」
砂しかない、広いだだっ広い空間を、俺と金丸はよたよたと駆ける。
真ん中につくと、俺はあたりを見回す。遮るものがない、広い空間。上気した体に夜風が心地よい。
ふと遠い昔を思い出した。あのころは、見るもの全てが新しかったっけ。
「もう、何なんだよ、何がしたいんだ」
遅れてついてきた金丸が、肩を激しく上下させて、息をしている。
時計を見る。
時刻は午後八時……ジャスト。
「上だよ、上を見ろ」
「上? 上って空くらいしか……」
視線を上げた金丸が、言葉を失う。
満天の夜空を、白く輝く流星が、滝のように流れ落ちていた。
「おお、思ってたよりすげー眺めじゃねえか、こりゃ」
「……」
金丸は答えない。黙り込み、吸い込まれるように夜空を見上げたままだ。だが、俺は続ける。
「東京の濁った空気じゃ、ここまで綺麗にゃ見えなかっただろうなあ」
「……」
「お前さ、本当は誰かに止めてほしかったんだろ。本当に死にたいんだったら、わざわざ昔住んでた町に来る必要なんて、なかったもんな」
「……」
「お前は賭けたんだ。特に思い出が深いわけでもないこの街に来て、それでも自分を止めてくれる誰かが現れることに」
「……」
「今日この日に、たまたま帰ってきて、たまたま俺に出会って、たまたま俺が今日の流星群のニュースを見てて……。知ってるか? 今日の流星群、今まで中で一番規模がでけえんだってよ。お前は悪い偶然ばっかり重なるっていうが……。これだってすげえ偶然だぜ」
「……」
「世の中、まだけっこう捨てたもんじゃねえな。そうだろ?」
「……うん」
金丸がようやく呟いた返事は、なさけねえ鼻声だった。
ま、いいや。今は気付かないフリをしといてやるよ。
結局、俺たちは流星群がまばらになるまで、小一時間くらい空を眺めていた。バカみてえに口を開けて。
「……俺、帰るよ」
金丸が、ぽつんと呟く。
「帰らなきゃ」
夢から覚めたような目で、俺を見た。
「みんな、心配してるだろうし」
「おう。じゃ、送って行ってやる」
「えっ? ……でも、悪いよ」
「はあ? てめえ、こんなクソ田舎でどうやって俺抜きで駅に行くんだよ。終電逃しちまうぞ」
「本当にいいのかい?」
「うっせえな。ゴチャゴチャ言ってんじゃねえねえよ。黙って乗れや」
肩をどやしつけると、金丸は「痛え」といって笑った。
夜気で冷たくなった校門を再び乗り越え、俺たちはタクシーに戻る。
「……ありがとう、将やん」
ドアを閉めると、金丸が言った。
「うるせえ」
俺は乱暴に車をスタートさせる。
車のデジタル時計の表示は九時十五分。終電の時間を考えると、あんまりチンタラしてもいられねえ。少し大きな通りに出ると、俺はアクセルを強めに踏み込んだ。まばらに立っている街頭が、ミサイルのように後ろへぶっとんで行く。
バックミラーを見る。金丸の中年太りのシルエットが、影絵になってシートに沈んでいた。微かな寝息が聞こえてくる。疲れたのだろうか。
「……なあ」
気付けば口を開いていた。
「恨んでるか? 俺のこと。俺は、いや、あのころの俺たちは、お前が羨ましかったんだ。洒落た服、小綺麗なマンション、優しい両親……俺らのまわりにゃ、どれもないものばかりだった」
何を言ってるんだ、俺は?
「だから、お前にどう接していいか、分かんなかった。嫉妬と憧れと好奇心がごっちゃになって、からかうことしかできなかったんだ」
くだらねえ、こんな昔のことを。だが、言葉は止まらない。
「なあ。俺ぁ結局、この街から出られなかったよ。この街が退屈だ、退屈だって言いながら、知らない世界が怖くて踏み出せねえ。自分の縄張りん中だけで威張り散らす、ガキ大将のまんまさ。いや、あんときよりも悪いかもな。変わらない毎日に退屈して、酒に逃げてばっかりだ。……時々思うよ。もしお前みてえにこの街から出たら、今と違う、もっと楽しい人生を送ってたんだろうか? ってな。だけどそれも、今更どうにもなんねえ話さ」
車は峠道に差し掛かっていた。ここを超えれば、駅前まであと少しだ。
「街に留まれなかったお前と、街から出られなかった俺。何が違ったんだろうな?」
闇を、車のヘッドライトが煌々と切り裂いていく。ふと俺は、このタクシーが流星の一つとなって夜空を駆けているような、そんな空想に捉われた。
「オラ。ついたぞ!」
車をロータリーに停めると、俺は後部シートに座る金丸に声をかける。
金丸は正体不明の呻き声をあげ、もぞもぞと寝返りを打っている。
「チンタラしてんじゃねえ! さっさと降りやがれ!」
俺はシートベルトを外すと、運転席から身を乗り出し、拳骨を食らわせてやった。
「いでぇえ」
悲鳴をあげて飛び起きた金丸は、ようやく目的地についたことを察したらしい。慌ててカバンを手にとり、スーツの内ポケットをゴソゴソと探り出した。
「何してんだてめえ」
「いやだって、お金払わないと……」
「バカか、てめえ。おめえみてえなクソ貧乏人から金を取るほど、俺ぁ落ちぶれてねえってんだ、ボケ!」
「でも……」
「いいから行けってんだ!」
俺がもう一度殴るそぶりを見せると、金丸はひいっと悲鳴をあげ、転がるように車の外に飛び出していった。駅前を歩いていたカップルらが、何事かとこちらを振り返る。
おどおどと周りを見回しながら歩いていくその背中に、俺はパワーウインドウを開けて叫んでやった。
「おい!」
びくりと体を震わせ、金丸がこっちを向く。
「いいか、もうくだらねえ理由で帰ってくるんじゃねえぞ。金が返したきゃ、マトモに暮らせるようになってから返しに来い」
俺が言い終わったあと、金丸は少しあっけに取られたような顔をして、それからちょっと何かを考えてから、口を開いた。
「なあ、将やん」
「なんだよ」
「将やんも、結構細かいことで悩んでるんだな」
「はあ?」
「この街から出られなくても、将やんはガキ大将から、ずいぶん成長したと思うよ、俺は」
そう言って、にやりと笑う。
……この野郎、寝たふりしてやがったのか。
金丸はきびすを返し、そのまま振り返らずに歩いていく。追いかけて一発ぶん殴ってやろうと腰を浮かせ――なんだかアホらしくなって、やめた。シートに沈み込み、小さくなっていく背中に、かわりに「頑張れよ」と呟いてみる。
何だか、毒気を抜かれちまった。
巨人が大きく口を開けたような駅の入口に、あいつの背中が消えたのを見届けると、俺はゆっくりと車をスタートさせた。
開いたままの窓から、心地よい夜気が流れ込んでくる。運転しながら左手でポケットを探り、タバコを取り出した。よれよれのマルボロのパッケージ。一本くわえ、ライターで火をつける。
煙を吐くと、夜空をまた一筋、流星が切り裂いていった。
この街のどのくらいの人が、この流星を見ているのだろう、とふと思う。
そいつはどんな青春を過ごし、どんな仕事につき、どんな気持ちで、夜空を見上げていたのだろう。そいつは今、幸せだろうか?
……ダメだな、何だか今日は、ガラにもないことばっかり考えちまう。
俺は吸いさしのタバコを灰皿にネジ込んで、ハンドルを握りなおした。
明日は嫌でもやってくる。俺にも、あいつにも、名前も知らない誰かにも。
帰ろう。
退屈で愛しい、俺たちの街へ。
210~シェアワールドアンソロジー~
prologue.「流星タクシー」
210 ~シェアワールドアンソロジー~
prologue「流星タクシー」