賭博神話ゼブライト
11.霞野さくみ
虚空に開かれた天蓋から、数多の星星が廃教会を睥睨している。
そのひとつひとつの視線を感じて、霞野さくみは、あれは死者の眼だ、となんとなく思った。
成仏できた幸運な魂は、ああやって天に昇って生者を肴に酒でも酌み交わしているに違いない。のん気なことだ。
少しロマンチズムに過ぎるだろうか。いいやそんなことはない。
なぜなら自分の胸の中に渦巻くこの感情は、決して優雅な死後に対する羨望などではないのだから。
眩むほどの満天に、さくみは思う。
自然の摂理によって退場を喰らった哀れな死人ども。
そこで指をくわえて見ているがいい。
うらやましがるのはてめえらの方だ。
この熱を感じられもしないくせに。
ざまァないじゃないか。
死者なんて、
何もできやしないのだ――。
刺すように刺々しい気配に顔を向けると、陸咲シャガと視線が交錯した。不可視の重力が瞳にのしかかってくるような錯覚。
現在、点差はシャガ五八〇〇、さくみ一四七〇〇。八九〇〇差。
さくみはラス親であるから、シャガはリーヅモチートイ(=五十符三飜ツモ和了)でひっくり返る。ワンチャンス。
びりりっと背骨の中で小さな電撃が弾ける。肌に滲んだ汗が片端から夜気に吸われて消えていく。
この局だ、さくみは夜を肺に流し込む。この局で終わりにしてやる。
六発中四発装填されたロシアンルーレットなど死亡する確率の方が高いのだ。五回戦などないに等しい。
血で汚れた牌を丁寧な手さばきで四人は積む。物音ひとつしない。
誰に向けられたわけでもない最高の技巧。
それが、こんな死しか残らない勝負に捧げられていることが滑稽でもあり、
決して譲りえぬ誇りでもあったのだ。
オーラス、目標はアガり。敗北は四位に逆転されること。
渡りきってやる、この綱――
そのひとつひとつの視線を感じて、霞野さくみは、あれは死者の眼だ、となんとなく思った。
成仏できた幸運な魂は、ああやって天に昇って生者を肴に酒でも酌み交わしているに違いない。のん気なことだ。
少しロマンチズムに過ぎるだろうか。いいやそんなことはない。
なぜなら自分の胸の中に渦巻くこの感情は、決して優雅な死後に対する羨望などではないのだから。
眩むほどの満天に、さくみは思う。
自然の摂理によって退場を喰らった哀れな死人ども。
そこで指をくわえて見ているがいい。
うらやましがるのはてめえらの方だ。
この熱を感じられもしないくせに。
ざまァないじゃないか。
死者なんて、
何もできやしないのだ――。
刺すように刺々しい気配に顔を向けると、陸咲シャガと視線が交錯した。不可視の重力が瞳にのしかかってくるような錯覚。
現在、点差はシャガ五八〇〇、さくみ一四七〇〇。八九〇〇差。
さくみはラス親であるから、シャガはリーヅモチートイ(=五十符三飜ツモ和了)でひっくり返る。ワンチャンス。
びりりっと背骨の中で小さな電撃が弾ける。肌に滲んだ汗が片端から夜気に吸われて消えていく。
この局だ、さくみは夜を肺に流し込む。この局で終わりにしてやる。
六発中四発装填されたロシアンルーレットなど死亡する確率の方が高いのだ。五回戦などないに等しい。
血で汚れた牌を丁寧な手さばきで四人は積む。物音ひとつしない。
誰に向けられたわけでもない最高の技巧。
それが、こんな死しか残らない勝負に捧げられていることが滑稽でもあり、
決して譲りえぬ誇りでもあったのだ。
オーラス、目標はアガり。敗北は四位に逆転されること。
渡りきってやる、この綱――
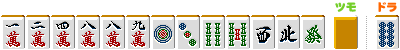
さくみの手はよくない。
役牌ポンも喰いタンの即効も望めない。
最短でミスなくまとめてピンフ。つまらない手だが、今はそのテンパイが欲しい。
しかし、埋まらない。ピンフとはこうも難しい手役だっただろうか。
唇をきつく引き結び、さくみは対面のシャガを見やる。
時折咳き込んでいた最後の修道女は、今はやや小康状態にあるらしかった。息は深く荒いが、眼にはかえって病的な生気がみなぎっている。
こいつ、勝てると思ってやがる――そう思うとさくみの頬がカッと燃えた。
なめられている、そんな気がした。
絶対に負けてたまるか。流局すれば勝つんだ。やつが一六、三二以上の打点をツモりアガらない限りは。
割れんばかりに牌を強くツモる。けれどどんなに祈れどカンチャンが埋まらない。両面さえも。
ヤマにまだあるか、それともどこかに暗刻で持たれているか。
血痕のガン牌などは急ごしらえでほとんど役に立たない。地打ちの感覚に任せるしかなかろう。
ツモ切りを繰り返しながらさくみは、これこそが麻雀なんだ、と思った。笑みさえ浮かぶ。
決して幸福とは呼びがたい人生を送ってきた霞野さくみにとって、勝負の最中に嘲る以外の動機で笑顔を作ることなど、今までは考えられないことだった。
勝てばいい。ただ勝てば。
そうしなければ生きていけないし、なんの意味もない。
その彼女が今、かつてない昂揚を覚えていた。
(おかしいな――追い詰められているっていうのに)
かすかな負けの臭いに酔っているのか、それとも死の恐怖がもたらした錯乱か。
それとも。
さくみにはわからない。
ただ、血を吐きながら打つのをやめないシャガを、麻雀にこだわり続ける烈香を、そして呼吸するように引鉄を引けるシマを見て、思うのだ。
こいつらと卓を囲めてよかった――と。
戦意も殺意も衰えていないのに。この極悪色の感情は、いったいなんなのだろう。
もしもさくみが恵まれていたならば、それが愛だと感じたかもしれない。
歪で刹那的な、むき出しの愛――
それは、十六年間走り続けてきて、ようやく出逢えた敵としか分かち合えない。
そんな心のカタチだったのだ。
シャガが手からヤオチュウ牌ばかり切り出してくる。
よほど手が悪かったのだろう。いまだに不要牌の整理で手がまとまらないらしい。
さくっと烈香やシマがアガってしまってもよい。子のマンガンまでなら振っても逆転されない。
横目に様子を窺うも、烈香はサングラスで両目を覆われ、シマにいたっては飄々として楽しげだ。
一見するとトップ目の余裕に見える。だがさくみたちは知っている。思い知らされている。
こいつは引鉄を自分に向かって引くときも、同じ顔をしているのだ、と。
この自殺麻雀、シマが自らの脳を撃ちぬきかけたのは三回戦だけではなかった。
三回戦とも、彼女はトリガーに指をかけ、その撃鉄は虚空を叩いたのだ。
さくみも命を賭して闘っている身ゆえに、恐怖や不安の殺し方は知っている。
だが、シマから感じるものは、何か違う。
彼女の瞳の中で揺らめくもの、それはまるで――
ああ、そうか。
さくみは急に現実感を取り戻す。
シャガが狙っている手役が唐突に判明した。
脳裏に満ちていたシマの面影は霞がかかったように茫洋とし、脳の隅へと追いやられる。
手牌から九索の暗刻落とし。そこから導き出される手は。
間違いない。
ヤオチュウ牌で構成される役満は国士無双だけではない。
流し満貫――。
どんなクズ手でも満貫逆転を狙える魔法の手、本来の自分の手牌でタンヤオ系統の満貫も狙える二重底。
飲み込む生唾は、泥の味がするのだった。
ところがあっけなくその戦略は破綻してしまう。
「チィ」
ツモ切られた九萬を烈香が喰う。流し満貫は河から鳴き牌が出た瞬間に無効となる。
烈香からすればどちらが三位になってもいい局面、これは明らかにシャガへの攻撃である。
しかしこれはエラーであろう、見守る雨宮はそう思う。
一見すれば烈香の優位は動かないわけであるし、おそらく手牌には安全牌があふれ出さんばかりに溜め込んであるのだろうが、ここではさくみを攻撃すべきなのだ。
なぜか。親番だからだ。
麻雀とは常に親番を苦しめていくゲームである。
親を援護して得するのは連荘してもらってトップを狙うときのみ。
それでさえ親に放銃してしまえばトップ争いから転落してラスを喰う可能性が子よりも大きい。
逆転を目指すシャガを見て、その芽を潰してやろうと動いたのであろうが、烈香にとって何の得にもならないし、ここは静観が正解であったろう。
麻雀打ちとしては熟練でも、狂人としては初心者なのだ。
とはいえまァ――シャガには次の半荘を打つ体力は残っていないだろうから、同じことではあるのだが。
伏せられた眼は穢れたように曇っている。
チィが入ったため、ハイテイはシャガ。
それまでにさくみからの五二直撃か満貫ツモを狙わねばならない。
おそらく手牌には中張牌がたまっているだろうから、ドラの八筒を絡めれば目標の打点は作れるであろう。
しかし残り少ないツモでそれが成るかどうか。
さくみは早々にオリの気配。結局、手にならずにヤオチュウ牌を落としていった。
シマ、打一筒、シャガ三萬、烈香三萬、さくみ九索、シマ五萬、シャガ北、烈香白、さくみ――
打、一筒。
「ロン。ちぇ、低めかぁ」
発声したのはシマ。さくみはほっと息をつく。
かくん、とシャガの手が卓から滑り落ちる。とうとう気力体力ともに絶佳に達し、気絶してしまったのだ。
その様を横目で嘲笑いながら、さくみは手元の点棒入れを漁る。
「へっ、アガらんでも流局したやろ。がめついやっちゃな。いくらや、二千点か?」
そしてふと気がつく。
打一筒はシマの打牌だった。
オーラスをしのいだ安心感で失念していたが、フリテンではないか。
うっ、とさくみの脳裏を思索がめぐる。
ここでチョンボを指摘してはオーラスがやり直されてしまう。
それはまずい、非常に。
(こいつまさか、さっきの見逃しといい……やっぱりあたしを狙ってるのか)
なぜそんな真似を――
「ああ、わたし、チョンボはしてないよ」
さくみの頭の中身を覗き込んだようにシマが言い、ようやく手牌を倒した。ゆっくりと。
シマが二順前に打った牌は――
白。
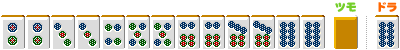
「――清一色平和一盃口ドラドラ。
ええと、いくらかな。わかんないや。大車輪だったらわかったのに。
数えてほしいなさくみちゃん。
計算は、得意なんでしょ?」
子の十飜は一六〇〇〇点。
倍満だった。
ぽかん、とさくみは口を開き、飛び掛った魂をなんとか飲み込んで怒涛のごとく怒り狂った。
やおら勢い込んで立ち上がり、かけていた椅子が倒れ埃が舞い上がる。
「ふ、ふざけるなィ! こんな馬鹿なことが――」
「ふっふっふ」
卓に手をついてシマも腰を上げる。ちょうど背丈が同じほどの二人が、至近距離から見詰め合った。
「ちゃんと見ているつもりでも、敵がひとりと思い込んでいれば他の河なんて見えなくなるよ。見たくないもの。忘れていたいもの。安心したいんだもの。
でもわかっていたはずでしょ?
麻雀は、四人でやるものなんだって」
「おどれ……なんで、こんな無意味なことを……!」
無意味か、と呟くとシマは牌山をじゃらりと崩した。
「無意味やろうが! なんでわざわざあたしを飛ばす必要がある? 弾丸が出る確率は、四人誰でも一緒やろう!」
「一緒じゃないさ。さっきの山越しわかってなかったの?
わたしはこの四回戦、引鉄を引いて弾丸が出るなら、君しかいないと思った。だから――」
「根拠は、根拠はなんや、なんでうちが――」
「根拠?」
「君はそんなつまらないものをあてにして、今まで生きてきたっていうの?」
「――――」
「だったらガッカリだ――引鉄を引く資格もない。お金もいらない。とっとと消え失せてほしいな」
「貴様ァ――」
ゆらり、とさくみが一歩後ずさった。
その手には、月光を鈍く照り返す拳銃が握られている。銃把には、紫色の花の刻印。
震える手つきで、四発目をこめる。シリンダーを回し、その勢いが衰えぬままフレームに手首のスナップだけではめ込む。
銃身をこめかみに当てたとき、さくみの形相は、もはや人のものとは言いがたかった。
眼は吊り上がり充血し、肩を怒らせてする呼吸は荒い。今にも彼女に取り憑く悪霊が背後からぼうっと浮かび上がってきそうだ。
がたん、と意識を失ったシャガがバランスを崩して倒れこむ。
雨宮がとっさに駆け寄り彼女の身体を抱えた。熱い。
それを視界の端に捉えながら、さくみは撃鉄を起こした。
烈香が魅入られたようにその一挙手一投足を注視している。
「あたしは、ニセモノなんかじゃない」
「どうかな」腕を組み、卓にもたれかかったシマの嘲笑にさくみの白目が赤い亀裂を走らせる。
「逃げてもいいと思うよ。わたしは弾丸、出ると思ってるし。なにせ四発も入ってるんだから。君もそう思うなら、わたしはあえて無理強いはしない」
「おい」と烈香が声をあげるのをシマは無視する。
「誰だって生きたい。それは普通のことなんだ。べつに恥ずかしくなんかないって――」
その言葉は甘く、聖者の語る真理のように教会に染み渡っていった。
拳銃を握るさくみの指が、わずかに痙攣する。
それをかき消すように、強く握りなおす。
吹き飛びそうになる心も一緒に、掴みなおしたかったのかもしれない。
「シマ――」さくみの声はすっかり擦り切れていた。
「うちは、逃げてもええんか」
「もちろん。シャガはノックダウンしてるし、烈香はまァ追いかけるかもしれないけど、仕方ないからわたしが止めててあげるよ。サービスしてあげる。百万石へのご祝儀さ」
「ははは――」渇いた笑いが響く。「面白い冗談やな」
「冗談かな」
「ああ、冗談や――逃げるやと? このあたしがか?
あたしをそこらのドグサレと一緒にするな――このあたしを!」
「さくみ」
「引いてやるわ」修羅が嗤う。
「ああ、そうや、我慢がならん。貴様がやってのけたことが、あたしにできへんのんが――うちには許せへんねや!」
「だったら決まりだ」夜叉が嗤う。
「五回戦で会おう、さくみ」
「くそったれ、思ってもいないことを――覚えておきィや、シマ」
トリガーが引き絞られていく。じわじわと。じわじわと。
「次の半荘で殺してやる。絶対に仕留めてやる。ぶっ殺して」
「やるんだ」
狂おしいほどの憎悪が、視界を歪める。
にこやかなシマの表情が凄絶なものへと溶けていく。
黒く甘い憎しみが、さくみの心をかえって冷やしていく。凍えさせていく。
ああ。
次はもっと上手くやろう。次に勝つのは絶対に自分だ。
次さえ訪れてくれたら。
博打なんてものは勝つまでやれば負けようがないのだ。
勝つまでできれば。
だから。
勝つために。
負けないために。
引鉄は、引くためにあるのだ。
起こされていた撃鉄が、解き放たれ――

