賭博神話ゼブライト
Fin.シマウマ
上家の親の手がちょっと大きかった。
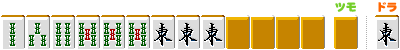
(すべて鳴いた牌)
役ホンイツドラ3。立派な一八〇〇〇だ。
俺は勝負手でもなく、トップ目ということもあり、ベタオリする他なかったのだが、下家にはリーチがかかっていて振る牌がない。
さて困ったというときに、残り五千点でヤケクソになったメタボリックダディがバシンと六索を切ってくれた。親はしかめっ面。
やれやれこれで少しはラクになる、と俺が六索を打つとバタッと親が手を倒した。
「ロン。――」
役ホンイツドラ3。立派な一八〇〇〇だ。
俺は勝負手でもなく、トップ目ということもあり、ベタオリする他なかったのだが、下家にはリーチがかかっていて振る牌がない。
さて困ったというときに、残り五千点でヤケクソになったメタボリックダディがバシンと六索を切ってくれた。親はしかめっ面。
やれやれこれで少しはラクになる、と俺が六索を打つとバタッと親が手を倒した。
「ロン。――」
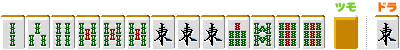
聞きなれぬ語尾は早送りした音声のように茫洋としていたが、ターバンを巻いたひげ面の親が何を求めているかはすぐにわかった。
点棒をくれてやると、一気に箱の中が寂しくなる。
親の河の右端には、五筒が転がっていた。
じろっと見やるとそっぽを向いている。
どうやら俺以外の三人はグル、ということらしい。
ラス家をハコテンにできるのに見逃して俺から取る理由が無い。
恥ずかしながらトリオに囲まれたのはこれが初体験だった。包帯を巻いた左手が意に反して震えていた。
とはいっても、この三人はそれほど強い結びつきはないだろうと踏んでいた。
おそらく普段はお互い敵同士でこの雀荘に巣食っているレギュラーメンバーなのだろうが、どうせ刈り取るなら新参者から奪ってやれ、ということだろう。
糞ッ、とやたらガラガラ勢いをつけて牌をかき混ぜながら、この野郎、と俺は思った。
てめえのトップを確定させねえアガリなんてアガリじゃねえんだ。
不自然な動きをしようとするおっさんの手を軽くひっぱたいて妨害しながら、ちらっと背後を見やる。
砂色のデューンコートを背もたれにひっかけ、嶋あやめは腕を組んで卓上を睨んでいた。
ちょうど俺と背中合わせになる形で別卓に座っている。
向こうの卓の面子はこちらと違って誰もが若い。
十五、六かそこらか。少年が一人に少女が二人。全員兄弟だとしたら言うまでもなくグルだろう。
リーチ、と髪の長い少女が牌を曲げた。
こんな遠くの国でも打点を上げたいときと相手を下ろすときはリーチで通るのだ。
そのうち連荘なんて言葉も万国共通になるのかもしれない。麻雀様様だ。
その麻雀の神様に愛されているのかどうか知らないが、我らがシマの姉御はリーチ者に面子中抜きでドラをぶった切っていた。
三人は顔を見合わせるようにしてシマの打牌をいぶかしんでいる。
しかし、そうやって疑心暗鬼にさせるのがやつの狙いなのかもしれない。あるいは寝不足で六索と九索の区別もつかないか。ありうる。
ぐっと背中に力を入れると、向こうからも押し返してくる気配があった。
お互いの髪が触れるような近さで闘う同士の幸運を祈る暇もなく、俺は新たな局へと進むため、ガチャンとヤマを積み上げた。
点棒をくれてやると、一気に箱の中が寂しくなる。
親の河の右端には、五筒が転がっていた。
じろっと見やるとそっぽを向いている。
どうやら俺以外の三人はグル、ということらしい。
ラス家をハコテンにできるのに見逃して俺から取る理由が無い。
恥ずかしながらトリオに囲まれたのはこれが初体験だった。包帯を巻いた左手が意に反して震えていた。
とはいっても、この三人はそれほど強い結びつきはないだろうと踏んでいた。
おそらく普段はお互い敵同士でこの雀荘に巣食っているレギュラーメンバーなのだろうが、どうせ刈り取るなら新参者から奪ってやれ、ということだろう。
糞ッ、とやたらガラガラ勢いをつけて牌をかき混ぜながら、この野郎、と俺は思った。
てめえのトップを確定させねえアガリなんてアガリじゃねえんだ。
不自然な動きをしようとするおっさんの手を軽くひっぱたいて妨害しながら、ちらっと背後を見やる。
砂色のデューンコートを背もたれにひっかけ、嶋あやめは腕を組んで卓上を睨んでいた。
ちょうど俺と背中合わせになる形で別卓に座っている。
向こうの卓の面子はこちらと違って誰もが若い。
十五、六かそこらか。少年が一人に少女が二人。全員兄弟だとしたら言うまでもなくグルだろう。
リーチ、と髪の長い少女が牌を曲げた。
こんな遠くの国でも打点を上げたいときと相手を下ろすときはリーチで通るのだ。
そのうち連荘なんて言葉も万国共通になるのかもしれない。麻雀様様だ。
その麻雀の神様に愛されているのかどうか知らないが、我らがシマの姉御はリーチ者に面子中抜きでドラをぶった切っていた。
三人は顔を見合わせるようにしてシマの打牌をいぶかしんでいる。
しかし、そうやって疑心暗鬼にさせるのがやつの狙いなのかもしれない。あるいは寝不足で六索と九索の区別もつかないか。ありうる。
ぐっと背中に力を入れると、向こうからも押し返してくる気配があった。
お互いの髪が触れるような近さで闘う同士の幸運を祈る暇もなく、俺は新たな局へと進むため、ガチャンとヤマを積み上げた。
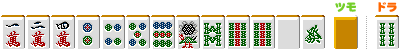
典型的なゴミ手、ここはちょっと無理をしてチャンタ、下の三色へいこう。
そう思って六筒、五索とばすばす切り落としていったのだが、俺にしては珍しいことにすぽすぽカンチャンが埋まっていった。
字牌を暖め、雀頭ないし暗刻にしても構わないと思っていたのだが、九筒がトイツになり、純チャンまで見えてくる。
一筒が二枚枯れたところで一筒を引いてきて四筒と入れ替える。
――上家の親リーを喰らったとき、俺の手はこんな風だった。
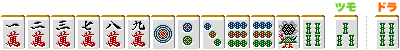
ドラの四索を切れば純チャン三色。ただし二索は場に二枚切れ。
一索を切ればピンフドラ1。実質リーチをかけるから三九の裏が乗ればマンガン。
親に四索は超危険牌。
あなたなら何を切るか。何も迷うことはない。
四索が当たったら卓をひっくり返して逃げ出すつもりだった。
「リーチッ!」
象牙製のまるっこい牌に甲高い悲鳴を上げさせて、四索を打ち出した。
親は今度こそ渋い顔。
下家が安牌ツモ切り、かと思うと対面からもリーチがかかってきた。
親がぎゅっと目をすぼめながら牌をツモる。ツモ切り。
細く長く息を吐きながら俺はツモ山に手を伸ばし――
――ツモ牌を指の腹でなぞったとき、初めて盲牌できてよかったと思った。
案外、実際の麻雀の方が笑ってしまうほど理不尽なものだ。
リーチ一発ツモ、純チャン三色、四千八千。
二索が気持ちよさそうにカンチャンターツに埋まっていた。
メタボダディがすっからかんになったらしくブツブツ言いながら出て行った。
それでその卓はなんとなく解散になり、手持ち無沙汰になった俺はシマのつむじに顎を乗せながら、やつの麻雀を観戦していた。
埃と蜘蛛の巣で汚れた窓から、いつの間にか朝日が射しこんでいる。
シマがうっとうしそうに頭をゆすってくるが気にしない。
オーラス、シマは親番だった。現在三位で、四千オールツモでもまくれない。トップ目からの満貫直撃で逆転だった。
とはいえ手は悪い。カンチャンペンチャンが目立ち、唯一の希望は白のトイツ。
ここから満貫を造れたらすごいな――と思ったその瞬間にシマが白をポン。
続いて鳴きじかけを重ね、あっという間に手牌は四センチ。
一筒と九筒のシャンポン。白のみ、一五〇〇点。
「えーなにそれー」と俺。
「うっさいバーカ」
眠いのかシマの機嫌はあまりよろしくない。
目の縁にクマがうっすらと浮かんでいる。元の肌の白さと相まって、奇人を模した化粧のようだ。
ひょいっと赤五筒を持ってきた。
こんな遠い国でも忌まわしき赤ドラの風習が蔓延っているなんて、と俺は悲しみに包まれた。
シマ、打九筒。ドラが六筒であるため、ドラ含みの面子になってくれれば二千オール。逆転への足がかりとなりうる。
八筒を持ってきたらテンパイに受けるのかなァ――と見ていると今度は七索をツモ。
ちら、と場を見やる気配が顎の下で漂った。
六索は上家の女の子がポンしている。トップ目だ。タンヤオの鳴き仕掛けで積極的にこの半荘を終わらせようとしているらしい。
くりくりした大きな目が忙しなく河をいったりきたりしている。
いい眼だな、と思った。
シマ、打九筒。
次順、知っていたかのように八索ツモ。お、と口をすぼめた。
「隣(九索)が来ると思ってたんだけどね」
打、赤五筒。テンパイ気配ぷんぷんである。
ぴり、と卓の空気が張り詰めた。安いけどね。
髪の長い少女と、人一倍浅黒い肌をした少年がちらちらとトップ目の短髪に視線を送っている。
まだアガれないのか、という悲痛なクエスチョンが俺の耳まで駄々漏れだ。
ぎゅっと唇を噛み締めた短髪が牌をツモる――が引けず。あからさまに向こうもテンパイだ。
しかしシマの手がアガれるかどうか。
九索は場に三枚。残り一枚しかない。おまけに六索は四枚見えていて、短髪の加カンによるチャンカンも期待できない。
ひょいっと次にシマが持ってきたのは白。積極的にカン。
対面の浅黒肌が人差し指でカンドラをめくった。
中。
丸乗りした。
呆然とする三人を尻目に俺とシマはげらげら笑った。
「なにこれ糞ゲー」
「やったねシマさんさすがです」
「でしょーえへへ」
実に嬉しそうだ。日向ぼっこしている猫のような表情になっている。
さすがのシマさんでもドラ4はにやけてしまうらしい。
反対に鬼気迫る顔つきになった三人衆。
差し込める牌がないのか、それともさっきのダディたちと同じく通しまではしていないのか。
「おい早くリンシャン持って来いよ」
「あいよ。よいしょ――と」
ここで九索を引いてこれれば六千オールでケリがつく。
しかしシマは引いてきた牌を見もせずに河に打ち捨ててしまった。
八索。
おや――俺はシマに訝しげな視線を送ったりしないように心を押し殺した。
八索と一筒のシャンポンに受けないのか。
待ち牌は圧倒的にそっちの方が多い。二種とも生牌だから、単純に考えれば四倍アガリやすいはずだ。
ただ、なんとなく俺にはシマのこの待ちの理由がわかる。
なぜってこの待ちは。
「ロン」
――振った相手が、きっとびっくりするだろうから。
「一二〇〇〇。――終わり!」
短髪が捨てた九索を持ってきて、シマは思い切り卓に叩きつけた。
「――どうして」
不気味に色のない顔をして、短髪が呟いた。
「シャンポンにしない――?」
ふふ、とシマはくすぐったそうに笑う。
「その理由は、きっと君が一番よく知ってるよ」
肩で扉を押しのけるようにして、俺とシマは戦場を後にした。
ちらりと後ろを振り返ると、負けた三人が額を寄せ合うようにして、隅の陰の中に埋もれていた――。
異国の空はからり、と晴れていた。日本の空よりも高くて遠い気がする。
そこをうようよと漂うゆがみを、俺は手で払った。
もちろん、やつらは俺の手なんてやすやすと無視しやがるのだが。
ううん――とシマが背伸びをした。ぽへっ、と間抜け面になる。
「疲れたぁ」
「何時間打ってたんだ、俺ら」
「えっと」シマが俺の手を取って時計に目を寄せる。
「二十三時間かな」
「はぁ――どんだけ麻雀好きなんだよ、どいつもこいつも」
背骨がずしっと重たくなったような、徹夜明け特有の倦怠感に包まれて、俺はシマと肩を並べながら歩いていた。
砂漠から生えてきたように突然、道中に現れたその街はシマが買ってきた地図にも載っていなかったので名前もわからない。
それどころか、俺たちは今、地球上のどのあたりにいるのか見当もついていない。
どこをどう間違えたのか、惑星レベルの迷子になってしまっていたのだった。
密航船に乗って上海にあがり、そのときから始まったこの旅の目的地は俺にもシマにもわからないので、まァふらふら彷徨っていればなんとかなるだろうと思っている。
「ま、気まま我がままの風来坊ってところさ――」
「何か言った?」
露店で瑞々しい果物を袋詰めにしてもらっているシマに俺は首を振って答えた。やつは美味そうに果実にかぶりつく。しゃりしゃり。
――その姿だけを眺めていると幸せそうに思えてしまうが、旅を始めたから、シマはいままで俺が見たことのない表情を浮かべることが多くなった。どこか窮屈そうな、それを。
俺といる、他者といる、それがしがらみに思えるときがあるようだった。
ふと視線を感じて横を見ると、こっちをじっと見つめているときがある。無表情に、何かを探るような目つきで。
そういうとき俺は何食わぬ顔をしてそっぽを向いててやり、ひたすら痛くもない腹を探らせてやっている。
もしかしたら、シマは俺のせいで弱くなってしまったのかもしれない。他者のことなんかお構いなしで、猪突猛進していくだけの人生の方がわかりやすかっただろう。それは確かだ。
だが俺は、シマには友達ってやつが必要だと思ったんだ。
綺麗事や理想論ではなく、それを背負ってなお、シマはシマでいられるんじゃないか、と。
何も考えずに闘い続ける戦闘機械じゃなく、シマだけの、嶋あやめという強さを。
ただその輝きを眺めていたかった。
「いこうか」
どこへ、と俺は問い返した。
シマはくるりと軽やかに振り返って、どんなときも枯れることのない笑顔の花を咲かせる。
誰にも期待せず、かといって諦めることもせず。
修羅のように生きていながら、どこまでも人としてあり続けている。
未来は常に揺れ動き、不確定で、ちっとも頼りにならない。
それでもこの『今』を攻撃することなんて、未来の野郎にはできやしないのだ。
だから、勝負の結果が勝ちであろうと負けであろうと、関係ない。
『負けの未来』なんかにびびってたまるか。
勝負はまだついちゃいねえ。
なァ。
そう思うだろ、シマ。
無限の荒野を二人、歩いていく。
シマが少し前を、俺がそれを支えるように。
赤い太陽が俺たちの世界を燃える黄金へと染めあげる。
ああ、シマ。
強くなれ。
どこまでも。
どこまでも。
誰も追いつけないほどに――。
【賭博神話ゼブライト 了】
一索を切ればピンフドラ1。実質リーチをかけるから三九の裏が乗ればマンガン。
親に四索は超危険牌。
あなたなら何を切るか。何も迷うことはない。
四索が当たったら卓をひっくり返して逃げ出すつもりだった。
「リーチッ!」
象牙製のまるっこい牌に甲高い悲鳴を上げさせて、四索を打ち出した。
親は今度こそ渋い顔。
下家が安牌ツモ切り、かと思うと対面からもリーチがかかってきた。
親がぎゅっと目をすぼめながら牌をツモる。ツモ切り。
細く長く息を吐きながら俺はツモ山に手を伸ばし――
――ツモ牌を指の腹でなぞったとき、初めて盲牌できてよかったと思った。
案外、実際の麻雀の方が笑ってしまうほど理不尽なものだ。
リーチ一発ツモ、純チャン三色、四千八千。
二索が気持ちよさそうにカンチャンターツに埋まっていた。
メタボダディがすっからかんになったらしくブツブツ言いながら出て行った。
それでその卓はなんとなく解散になり、手持ち無沙汰になった俺はシマのつむじに顎を乗せながら、やつの麻雀を観戦していた。
埃と蜘蛛の巣で汚れた窓から、いつの間にか朝日が射しこんでいる。
シマがうっとうしそうに頭をゆすってくるが気にしない。
オーラス、シマは親番だった。現在三位で、四千オールツモでもまくれない。トップ目からの満貫直撃で逆転だった。
とはいえ手は悪い。カンチャンペンチャンが目立ち、唯一の希望は白のトイツ。
ここから満貫を造れたらすごいな――と思ったその瞬間にシマが白をポン。
続いて鳴きじかけを重ね、あっという間に手牌は四センチ。
一筒と九筒のシャンポン。白のみ、一五〇〇点。
「えーなにそれー」と俺。
「うっさいバーカ」
眠いのかシマの機嫌はあまりよろしくない。
目の縁にクマがうっすらと浮かんでいる。元の肌の白さと相まって、奇人を模した化粧のようだ。
ひょいっと赤五筒を持ってきた。
こんな遠い国でも忌まわしき赤ドラの風習が蔓延っているなんて、と俺は悲しみに包まれた。
シマ、打九筒。ドラが六筒であるため、ドラ含みの面子になってくれれば二千オール。逆転への足がかりとなりうる。
八筒を持ってきたらテンパイに受けるのかなァ――と見ていると今度は七索をツモ。
ちら、と場を見やる気配が顎の下で漂った。
六索は上家の女の子がポンしている。トップ目だ。タンヤオの鳴き仕掛けで積極的にこの半荘を終わらせようとしているらしい。
くりくりした大きな目が忙しなく河をいったりきたりしている。
いい眼だな、と思った。
シマ、打九筒。
次順、知っていたかのように八索ツモ。お、と口をすぼめた。
「隣(九索)が来ると思ってたんだけどね」
打、赤五筒。テンパイ気配ぷんぷんである。
ぴり、と卓の空気が張り詰めた。安いけどね。
髪の長い少女と、人一倍浅黒い肌をした少年がちらちらとトップ目の短髪に視線を送っている。
まだアガれないのか、という悲痛なクエスチョンが俺の耳まで駄々漏れだ。
ぎゅっと唇を噛み締めた短髪が牌をツモる――が引けず。あからさまに向こうもテンパイだ。
しかしシマの手がアガれるかどうか。
九索は場に三枚。残り一枚しかない。おまけに六索は四枚見えていて、短髪の加カンによるチャンカンも期待できない。
ひょいっと次にシマが持ってきたのは白。積極的にカン。
対面の浅黒肌が人差し指でカンドラをめくった。
中。
丸乗りした。
呆然とする三人を尻目に俺とシマはげらげら笑った。
「なにこれ糞ゲー」
「やったねシマさんさすがです」
「でしょーえへへ」
実に嬉しそうだ。日向ぼっこしている猫のような表情になっている。
さすがのシマさんでもドラ4はにやけてしまうらしい。
反対に鬼気迫る顔つきになった三人衆。
差し込める牌がないのか、それともさっきのダディたちと同じく通しまではしていないのか。
「おい早くリンシャン持って来いよ」
「あいよ。よいしょ――と」
ここで九索を引いてこれれば六千オールでケリがつく。
しかしシマは引いてきた牌を見もせずに河に打ち捨ててしまった。
八索。
おや――俺はシマに訝しげな視線を送ったりしないように心を押し殺した。
八索と一筒のシャンポンに受けないのか。
待ち牌は圧倒的にそっちの方が多い。二種とも生牌だから、単純に考えれば四倍アガリやすいはずだ。
ただ、なんとなく俺にはシマのこの待ちの理由がわかる。
なぜってこの待ちは。
「ロン」
――振った相手が、きっとびっくりするだろうから。
「一二〇〇〇。――終わり!」
短髪が捨てた九索を持ってきて、シマは思い切り卓に叩きつけた。
「――どうして」
不気味に色のない顔をして、短髪が呟いた。
「シャンポンにしない――?」
ふふ、とシマはくすぐったそうに笑う。
「その理由は、きっと君が一番よく知ってるよ」
肩で扉を押しのけるようにして、俺とシマは戦場を後にした。
ちらりと後ろを振り返ると、負けた三人が額を寄せ合うようにして、隅の陰の中に埋もれていた――。
異国の空はからり、と晴れていた。日本の空よりも高くて遠い気がする。
そこをうようよと漂うゆがみを、俺は手で払った。
もちろん、やつらは俺の手なんてやすやすと無視しやがるのだが。
ううん――とシマが背伸びをした。ぽへっ、と間抜け面になる。
「疲れたぁ」
「何時間打ってたんだ、俺ら」
「えっと」シマが俺の手を取って時計に目を寄せる。
「二十三時間かな」
「はぁ――どんだけ麻雀好きなんだよ、どいつもこいつも」
背骨がずしっと重たくなったような、徹夜明け特有の倦怠感に包まれて、俺はシマと肩を並べながら歩いていた。
砂漠から生えてきたように突然、道中に現れたその街はシマが買ってきた地図にも載っていなかったので名前もわからない。
それどころか、俺たちは今、地球上のどのあたりにいるのか見当もついていない。
どこをどう間違えたのか、惑星レベルの迷子になってしまっていたのだった。
密航船に乗って上海にあがり、そのときから始まったこの旅の目的地は俺にもシマにもわからないので、まァふらふら彷徨っていればなんとかなるだろうと思っている。
「ま、気まま我がままの風来坊ってところさ――」
「何か言った?」
露店で瑞々しい果物を袋詰めにしてもらっているシマに俺は首を振って答えた。やつは美味そうに果実にかぶりつく。しゃりしゃり。
――その姿だけを眺めていると幸せそうに思えてしまうが、旅を始めたから、シマはいままで俺が見たことのない表情を浮かべることが多くなった。どこか窮屈そうな、それを。
俺といる、他者といる、それがしがらみに思えるときがあるようだった。
ふと視線を感じて横を見ると、こっちをじっと見つめているときがある。無表情に、何かを探るような目つきで。
そういうとき俺は何食わぬ顔をしてそっぽを向いててやり、ひたすら痛くもない腹を探らせてやっている。
もしかしたら、シマは俺のせいで弱くなってしまったのかもしれない。他者のことなんかお構いなしで、猪突猛進していくだけの人生の方がわかりやすかっただろう。それは確かだ。
だが俺は、シマには友達ってやつが必要だと思ったんだ。
綺麗事や理想論ではなく、それを背負ってなお、シマはシマでいられるんじゃないか、と。
何も考えずに闘い続ける戦闘機械じゃなく、シマだけの、嶋あやめという強さを。
ただその輝きを眺めていたかった。
「いこうか」
どこへ、と俺は問い返した。
シマはくるりと軽やかに振り返って、どんなときも枯れることのない笑顔の花を咲かせる。
誰にも期待せず、かといって諦めることもせず。
修羅のように生きていながら、どこまでも人としてあり続けている。
未来は常に揺れ動き、不確定で、ちっとも頼りにならない。
それでもこの『今』を攻撃することなんて、未来の野郎にはできやしないのだ。
だから、勝負の結果が勝ちであろうと負けであろうと、関係ない。
『負けの未来』なんかにびびってたまるか。
勝負はまだついちゃいねえ。
なァ。
そう思うだろ、シマ。
無限の荒野を二人、歩いていく。
シマが少し前を、俺がそれを支えるように。
赤い太陽が俺たちの世界を燃える黄金へと染めあげる。
ああ、シマ。
強くなれ。
どこまでも。
どこまでも。
誰も追いつけないほどに――。
【賭博神話ゼブライト 了】

