悪魔のミカタ 《777スペシャル》
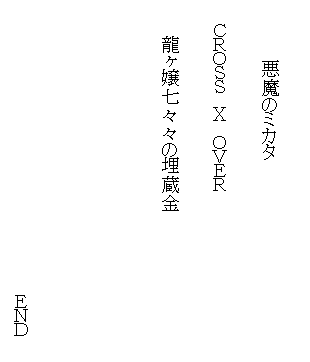
『登場人物』
八真重護……『龍ヶ嬢七々々の埋蔵金』の主人公。盗賊団『祭』の跡継ぎ
壱級天災……名探偵
不義雪姫……『祭』の関係者
戦場緋夜……元・冒険部
唯我一心……三年生。冒険部部長
茨夕……三年生。冒険部。武闘派担当
ゆん……《ゲーム》の進行役
クマ吾郎……ゆんの手下
辻見鉄之進……重護の同級生
龍ヶ嬢七々々……地縛霊
《レプラコーン》……七重島に《七々々コレクション》をばら撒いている正体不明の組織
堂島コウ……悪魔のミカタ
アトリ……見習い悪魔
*
――あの男はいったい、何者だ?
それがその場にいた全員の疑問だったと思う。
俺たちは七々々コレクションを賭けて争う《ゲーム》の最中だった。場所は七重島にある遊園地。その第一ステージをクリアして、遊園地中央にある城へと進もうとしていたところだった。《七々々コレクション》をひそかに島の『遺跡』に流しているという《レプラコーン》、そしてその主催者である『M』(その正体はどっからどー見てもゆんちゃん)も一緒にいる。が、その表情を見れば、俺たちの前にいた男が『想定外の存在』であることを想像することは難くない。
俺は隣にいる自称名探偵・壱級天災に聞いてみた。
「おい、どー思う天災」
「どうやら私の出番のようだな」
元・冒険部の戦場さんや、俺の《実家》の関係者である雪姫姉さんでさえ戸惑っているこの状況で推理権を得た天災はとても嬉しそうに鼻息を荒らげている。「むっふー」とか言ってる。どっから来るんだこの元気。
「まず、あの男は我々と同じくらいの年頃だろう」
「見りゃわかる」
「……。次に、マントのようなものを羽織っている。首からはリングのネックレスを下げている。手をポケット……どこかの高校の制服か? 黄色と紫の随分奇抜なカラーリングだが……とにかく、ポケットに手を突っ込んで、ニヤニヤ笑っているな。ここから導き出される推論は、あの男がとんでもないナルシストだということだ」
「いや、あいつ個人への攻撃は別にいらねえ」
「…………」
「おい見ろ天災! あいつ落ち込んでるぞ!」
「地獄耳も奴のプロファイルに追加しよう。この距離で私の推理を盗み聞きするとは……」
「それは違うぞ天災、お前の声がデカイんだ」
「なんだと重護! 誰がダミ声だ!」
「言ってねーよそんなこと!!」
俺たちがひとしきりギャアギャアやりあった後、いかにも「頃合を見計らってましたよ」とばかりに、謎の男がコホンと咳をした。
「あー、そろそろいいかな?」
「お前は何者なんだぞ!?」
Mことゆんちゃんが、謎の男に詰め寄った。ちなみにゆんちゃんもマントを着けているので、ちょっと相手とペアルックに見える。それが気に入らないのか俺の隣で鉄くんがすんごい闘気を放ち始めている。落ち着きなよ。
ゆんちゃんが顔の中央からズレかかっていたドミノマスク(目元だけを隠す仮面)を直しながら、びしっと謎の男に指を突きつけた。
「ここは《ゲーム》の会場なんだぞ! 参加者以外は入っちゃいけないのだ!」
「いーじゃん固いこと言わなくても」
「固いことじゃないぞ! ルールなんだぞ!」
謎の男はやれやれと肩をすくめてみせる。
「七々々コレクションを持ってればいいんだろ。《レプラコーン》の狙いは七々々コレクションの回収。俺のもついでに回収させてやるよ」
「俺のも……って、七々々コレクションを持っているのか!?」
「あるよ」
謎の男は、首から下げたリングを掴んだ。
最初、誰も何が起こったのかわからなかった。
一番早くそれに気づいたのは俺だろう。
思わず声が出た。
「な、な、な……」
「……? どうした重護」
「……なってる」
「なってる? 何が?」
怪訝そうに眉をひそめる天災の肩を俺はがっくんがっくん揺さぶった。
「なってるんだよ、あいつが!」
「だ、だから何に……」
「女になってるんだよ!!」
「なんだと!!」
男子一同が食い入るように、謎の男……いや謎の女を凝視した。
「いやん」
元から女顔というか、童顔だったから分かりにくかったが、いまや彼(彼女?)の身体にはくびれが出来、凹凸があり、そしてその唇は誘惑するような朱色に染まり――
そして、彼女がリングから手を放すと、
また、彼女は彼に戻っていたのだった。
両手を広げて、手品師のように恭しくお辞儀をする。
「信じて頂けたかな? これが俺の七々々コレクション……えーと、七々々コレクションって、ナンバリングとかあったっけ?」
「ないです、コウにーさん!」
ぴょこん、と。
コウと呼ばれた少年の背中から、黒髪の少女が顔を出した。手をぐーにして握り締め、「イケるぜ、この状況!」みたいな期待に満ちた顔つきで相棒を見上げている。
少年は胸元のリングをいじくっている。
「自己紹介が遅れたな。俺は堂島コウ。悪魔のミカタなんてものをやっている。おい、そこ、可哀想な目で俺を見るな。わかるんだぞ。まったく……よく聞け諸君。
お前らは騙されている。
七々々コレクションってのは、悪魔の道具なんだ」
「……ずいぶん唐突だな」
戦場さんが一歩前に踏み出して、堂島コウに言った。いきなり「七々々コレクションは悪魔の道具だ」とか言い出した奴を、思いっきり罵倒したり嘲笑したりするのかと思ったが、その態度は紳士的。おそらく、戦場さんの頭の中にあるのは、今の俺と同じことだろう。
堂島コウの言っていることが真実であろうとなかろうと、
あの『七々々コレクション』は使える……と。
「いきなり、そんなことを言われても納得できない。危険な悪魔の持ち物だから渡せ、とでも言うつもりか? 生憎と俺たちは七々々コレクションに困らされたこともないし、いまのところ上手くやっているんでね」
「そう来たか」コウは口元を斜めにし、
「ま、そうだよな。こんなこと言われたぐらいでホイホイととっておきを渡してくれるわけねーよな。いいよ。ホントのとこで腹割って話そう。七々々コレクションが全て悪魔の道具ってのは嘘だ。が、その中にいくつか、本物の、呪われたアイテムが混じっている。俺はそれを回収しに来た」
「その呪われたアイテムとは? 目星はついているのか?」
「七々々の剣」
その場が一気に緊張状態に入った。俺も思わずゴクリと生唾を飲み込む。
七々々の剣。
それは、俺たちがこの《ゲーム》に参加した目的とも言っていい、最強の七々々コレクション。どんな能力が秘められた龍ヶ嬢七々々の埋蔵金なのかは不明だが、いま俺の部屋でプリン喰っているであろう七々々ちゃんが自分の名前を冠するぐらいだ。とんでもないコレクションに違いない。
あの堂島コウも、それを狙っているということか。
「話が分かってもらえたかな? ……俺は《七々々の剣》を手に入れ、君たちを悪魔から救いたいんだ! 信じてくれ! みんなあっ!」
涙ながらに訴える堂島コウに「よっ! よっ!」と合いの手を入れてヨイショする黒髪少女。ちなみにスンゲェ格好してる。ボンテージというか、黒と青と赤のベルトで身体を覆っているだけの半裸。第二ステージ進出決定の女性陣たちがひっそりと顔を赤らめているのを見て、俺は拳を握った。グッジョブ、名も知らぬ変態少女。
戦場さんがぺっと唾を吐いた。
「くだらない茶番はやめにしないか。どうせ七々々コレクションを賭けてゲームをすることになるんだ。そうだろ、M」
「えっ、えっ」
両手で顔を隠しつつも指の隙間から黒髪少女を盗み見ているゆんちゃんは咄嗟に答えられない。周りにいる彼女の従者・クマ吾郎たちも「はれんちだよあんなの」と言いたげに俯いている。
「そっ、それは……」
「ゲームの基本原則に違反はしないと思うがな。余っている七々々コレクションがあるなら、誰がそれを手に入れるにしろ、参加枠に入れてやるべきじゃないか? M、あんたがあのリングを手にする可能性だってあるじゃないか」
巧みな話術でMを誘導していく戦場さん。どうやらあの女になれる七々々コレクションがどーしても欲しいらしい。
……いや、これは戦場さんが変態だということではなく。
女になれる七々々コレクションだというだけなら、せいぜい完璧な変装ぐらいにしか使えないが、何も能力があれだけとは限らない。たとえば、屈強な男に変身できたり、背中から翼を生やしたりとかも出来るのかもしれない。その応用性を期待値にかければ、あの七々々コレクションはぜひとも欲しいところだ。俺だって欲しい。
「…………」
「重護」
ジト目で天災が俺を見てくる。
「お前今、ダルクのこと考えてないか?」
「どーした名探偵、珍しく推理が外れてるぜ」
「目が泳いでいるぞ」
ぐっ。
天災の声がデカイせいで俺は雪姫姉さんからまで殺意の視線を受ける羽目になった。いろんな意味で眠れなくなりそう。
「ううう~」
Mはパニックに弱いので、頭を抱えてしゃがみこんでしまったが、やがてミサイルのように勢いよく立ち上がった。
「き、決めたぞ! おい、堂島ショウ!」
「堂島コウです」
「堂島コウ! いまからボーナスステージだ! でもお前はいろいろと策略とかしてきそうだから、簡単なゲームにするぞ!」
「……俺のこのリングをルール無用で奪った奴の勝ち、とか?」
「な、なんで先に言っちゃうのだ~……」
ゆんちゃんはかなりあの堂島コウという男が苦手らしく、半べそで鉄くんの背中に隠れてしまった。鉄くんは目を閉じて久方ぶりの悦楽に浸っている。
堂島コウは指先で自分のリングを弾いた。
「いいぜ、それにしよう。こんな遊園地のど真ん中だしな。わざわざ屋内に入ってポーカーなんてやってたんじゃ地味で仕方ない。ルール無用! いい響きだ。七々々コレクションの使用はどれでもいくらでも無制限。もちろん俺も、手持ちのアイテムはこの腕輪、我が相棒、『グレイテストオリオン』だけじゃない……抵抗させてもらうし、隙あらば、お前らのコレクションを奪わせてもらう。それでいいかな?」
「その女の子は?」
俺が入っている冒険部の三年生・茨先輩が言った。ちなみに冒険部からゲームに参加しているのは、俺と天災と、この茨先輩だ。部長であるクソメガネ……おっといけない、唯我先輩はいろいろあってゆんちゃんに刺され、ゲームの参加権ごと自分の七々々コレクション『モノマネ眼鏡』を茨先輩に託して、入院している。茨先輩は唯我先輩のメガネのにおいを嗅ぎながら、「一心様のために、必ずや七々々の剣を手に入れて見せます!」と息巻いていたが、窓の外を見る唯我先輩はクリスマスの真実を知った子供のような顔をしていた。
そんな茨先輩が言った。
「あたし、あんまり女の子はぶったり蹴ったりしたくないんだけど」
俺とか徒然先輩ならいいんですね、茨先輩。
堂島コウが茨先輩に視線を向ける。
「女の子? ああ、アトリのことか」言って、コウは黒髪の少女の頭をなでなでしてやり、
「こいつは俺のミカタだ。でもまあ、なんか怖いお兄さんがいっぱい睨んでるし、アトリは勝負から除外しよう」
「そんなっ! コウにーさん、あたしだって闘えます!」
「気持ちはありがたいんだけどさ、最近俺って、あんまり知恵比べしてないし、リハビリしたいんだよね。ここで負けてるよーじゃ、《七々々の剣》なんて手に入れられない。だろ?」
「それは……そうかもしれませんけど……」
ぐすっと涙ぐむ少女にコウは微笑む。
「心配するな、俺は負けない。いままでだってずっとそうだったろ? ……ほら、下がってろ」
「コウにーさん……」
少女を建物のそばまで下がらせて、城の門を目前とした円形広場の中央に、
堂島コウは立ちはだかった。
右手に嵌めた指貫グローブを左手で引っ張り直し、パチンと放す。
「じゃ、やろうか」
「そうさせてもらおう!」
まず戦場さんと鉄くんが踊りかかった。鉄くんは日本刀を抜いている。
「はあっ!」
裂帛の気合と共に鉄くんが堂島コウに斬りかかる……が、堂島コウは易々とスウェーバックして、剣をかわす。常人の神経じゃない。鉄くんが優しいとはいえ、刀で斬りかかられて余裕綽々でかわすとは。
だが、戦場さんは優しくない。
鉄くんの背後に巧妙に姿を隠していた戦場さんは、そのまま影に潜れる七々々コレクション『影かき』で鉄くんの影に潜り込んだ。そのままコウのマントが作った影から飛び出し、お得意の連続パンチを繰り出そうとし――
その視界が闇に飲まれた。
「なっ……」
「甘い甘い」
着ていたマントを外したコウが嗤う。
戦場さんは背後を取ったが視界を奪われ、そのパンチは空を切った。慌ててそのマントを引っぺがそうとした時にはもう、堂島コウの右フックが戦場さんのアバラに突き刺さっていた。
「かっ……はっ……」
俺と天災は顔をしかめた。今の一撃で、戦場さんは肋骨をへし折られただろう。もう影かきで息を止め、影に潜ることは出来ない……
あいつ……まさか一瞬で戦場さんの七々々コレクションの特質を見抜いたのか? ネタが分かってる俺だからこそ、鉄くんの背後で戦場さんが息を止めるモーションを見抜くことができたが、初見で、しかも相手が影に潜るという『決め技』を見せないうちに対処策を思いつくなんて、出来るのか?
時間を止めて、その間に考え事でもしていたとしか思えねえ……
「重護」
隣で天災が言う。
「あの男、強いぞ」
「ああ、わかってる」
堂島コウの強さから危険を察してか、かえって自分の七々々コレクションを獲られては仕方ない……と距離を取るメンバーも出てきた。俺と天災もどっちかといえばまだそっち側だ。もちろん、俺は獲りに行くつもりだけど。
正直、俺が持ってきた七々々コレクションはこういう荒事には向いていないので、追加のアイテムが欲しいと思っていたところなのだ。
「糞がァッ!!」
戦場さんが珍しく熱くなって拳を振り回している。影かきの能力が見抜かれている以上、戦場さんに勝ち目がほぼ無いことは戦場さんが一番分かっているのだろう。あの人は嫌な奴だが、馬鹿じゃない。
「どけ、戦場!!」
鉄くんが戦場さんを押しのけるようにして、日本刀を上段から切り下ろした。ちょうどコウは戦場さん向けのバックステップを取った後で、そこからさらに回避しづらい姿勢。これは取ったか、と俺が目を見張った次の瞬間、
がっ……
堂島コウが、
鉄くんの日本刀を鷲づかみにしていた。
「なん、だと……」
刀を振り下ろした姿勢のまま、鉄くんが驚愕に戦慄く。
「ぐあっ!」
堂島コウはそんな鉄くんのがら空きのボディに、膝蹴りを叩き込んで吹っ飛ばした。まだ手に掴んでいた日本刀を背後へ放り捨てる。
「すごい、すごいですコウにーさんっ!!」
「……うん、ありがとうアトリ。でもなんか恥ずかしいから、黙っててくれると嬉しいな……」
ポリポリと頬をかく堂島コウ。確かに「いけいけ」と空中にエアパンチを繰り出す少女は、なんだか運動会でお兄ちゃんを応援する妹のようで、微笑ましい。
「さて」
堂島コウが、跪いた戦場さんに近寄った。
「《七々々コレクション》は、そのブーツか?」
「……っ!」
「おっ。カマかけだったんだけど。当たった?」
コウにはニッと嗤って、
「それじゃ、頂こう」
戦場さんの足に手を伸ばした。
それを見て、戦場さんが笑った。
「おい、お前」
「ん?」
「いまから肺が片方潰れて、とても痛くて動けないぞ」
その瞬間、
俺たちは、堂島コウの肺が潰れる音を聞いた気がした。
「重護、あれは……」
「ああ、俺も『遺跡』でやられた奴だ」
どれが七々々コレクションなのかは分からないが、戦場さんが隠し持っている秘蔵のアイテム。
実際に肺が潰れるわけではないが、それと同じ痛みを与える、催眠術のような七々々コレクションだ。
それをまともに喰らっては、堂島コウもひとたまりもないはず……
「…………」
「…………おい。どうした、痛みで声も出ないか?」
戦場さんが引きつったように笑う。
「なあ、おい」
「…………」
「……おい!!」
コウは答えた。
「いてーよ」
胸をさすり、冷たく赤く輝く目で戦場さんを見下ろし、
「死ぬほどいてぇ。なんだコレ? これも七々々コレクションなのか? くそっ……」
言って、コウは戦場さんの胸倉を掴み、持ち上げ、思い切りぶん殴った。
「がふっ……」
戦場さんは建物脇に幕を張られて隠されていた資材に突っ込み、両足を突き出したまま、動かなくなった。
俺たちは呆然とするしかなかった。
コウはまだ胸をさすっている。
「なんだったんだ? とりあえず気絶させてみたけど……ああ、くそ、痛ぇ。なんかまだ残ってるなあ……嫌な七々々コレクションだ」
「あなたは……」
雪姫姉さんが、次は自分の番だと構えながらも、冷や汗を浮かべている。
「……苦しくなかったのですか? 確かあれは戦場の七々々コレクション……」
「いや、痛かったよ? 普通に。二度と喰らいたくないね」
「では……ただ、『耐えた』と?」
コウは肩をすくめる。
「困ったことに、負けられなくてね。
さ、どうする? 降参するか? 俺を倒さなきゃ、第二ステージへは行けないぜ」
「そうみたいだな……」
「重護、いくのか?」と天災。
「ああ」
俺はチラっと雪姫姉さんと茨先輩にアイコンタクトを送った。茨先輩にはウィンクをしてみたが、殺してきそうな視線が返ってきた。察してくんない? 手を組もーよ……
雪姫姉さんとは、手持ちの七々々コレクションの内訳も分かり合ってるし、意思疎通に問題はない。俺は嫌がる茨先輩の耳元で作戦を伝えた後、盗み聞きしようと近づいてきた(なにをコソコソしてるんですかっ!)黒髪少女のアトリを追い払いながら、堂島コウに宣言した。
「悪いんだけど、君の『グレイテストオリオン』は俺たちが貰うよ、堂島コウ」
「ん? 君は?」
「俺は八真重護」
「なんで《七々々の剣》欲しがってんの?」
俺はちょっとずっこけた。
「いまからやるぞ!」って時にいきなり世間話を振られたら誰でもこーなると思う。
「……いろいろ事情がありまして」
「それを聞いてみたい」
「べつに関係ないでしょ? ……ま、簡単に言うと、助けたい女の子がいまして。もう殺されちゃったんだけど、俺はその犯人を見つけたい……七々々の剣があれば、それが出来るかもしれない。だから俺は……」
「生き返らせれば?」
「え?」
堂島コウはつまらなさそうに立っている。
「犯人探しなんて真面目だなあ。その女の子とやらを生き返らせた方がよくない? ま、生き返って欲しくないならそれでもいいけど」
「……何言ってんだ?」
俺は本気で疑問に思った。
「人が生き返ったりするわけねーだろ」
「そういう七々々コレクションもあるかもしれないぜ? 試してみる価値はある」
「……そういうことじゃねーよ。人が生き返るなんて、あっちゃいけないことだろ。そりゃ、生き返ってくれたら嬉しいけど……でもそれは、間違ってることだと思う。あんたは、そんなことも分からないのか?」
コウは嗤った。
「ああ、わからねーな。わからねーからここまで来たよ」
俺はなんだか無性にイライラしてきた。
それがどうしてなのかは、分からないけど……
「行くよ、雪姫姉さん!」
「はいっ!!」
俺の呼びかけで、雪姫姉さんが堂島コウに飛び掛った。コウはいつの間にか再び黒マントを身に着け、鍛え抜かれた雪姫姉さんの二段蹴りをかわした。しかし、その回避位置はすでに俺にバレている。子供の頃から雪姫姉さんとは一緒に『祭』で鍛えられた間柄だ、同じ標的を仕留める時の呼吸ぐらいは今でも通じる。
「堂島コウ……!!」
「ん」
いかにも渾身の力を入れたように見せた俺のパンチを、堂島コウが身を回転させながらかわした。なんか変な方向に身体が捩れた気がしたが、気のせいだと思いたい。もしくはあの『グレイテストオリオン』の力か……? いずれにせよ、俺たちの作戦はまとめに入っている。
俺は茨先輩に叫んだ。
「茨先輩っ! 次の奴の跳躍位置を……ってあれ!?」
唯我部長から借りてきた《モノマネ眼鏡》で、相手の思考を読めるようになった茨先輩に、堂島コウのトドメを刺してもらう……それが俺たちの作戦だったのだが、茨先輩はコウに殴りかかるどころか、その場にうずくまって頭を抱えていた。あの《モノマネ眼鏡》は、酷使すると頭痛がするとは聞いていたけど……
「茨先輩、普段元気なんだからもうちょっと頑張って!」
「う、うるさい八真! ううっ……」
茨先輩は耐え切れない、とばかりに、なんと愛しの唯我部長のメガネを外して目を覆ってしまった。相当痛そうだ。
「大丈夫スか?」
「そんなわけ……ないでしょ……!! くっ、八真、あいつ……読めなかった……心が……」
「そんな……」
「……八真っ!!」
「えっ?」
影を感じた。
俺は振り返ると同時に、堂島コウに思い切り殴られた。なんとかガードが間に合ったが(七々々ちゃんからの「ゲームしよ?」にも、天災からの「勝負しろ!」にも負けずに続けた、日々の鍛錬に感謝)、妙なパンチだった。右手右足を前に突き出して、全体重を乗せた、下からすくい上げるようなオープンガードから打ち上げるショートアッパー……確か、《スマッシュ》とか言ったような? それが、
骨まで響いた。
俺は吹っ飛ばされて、戦場さんがのびている資材置き場あたりまで転がった。痛ぇ。こればっかりは、鍛えたぐらいじゃどうにもならねえ……
「若っ!」
追撃して欲しかったが、俺を心配して雪姫姉さんが近づいてきてしまった。俺は首を振った。
「雪姫姉さん、俺のことはいいです」
「ですが……」
「……正直、いまので骨、イキました。亀裂ぐらいだと思うけど、もう闘えそうにありません……」
俺はふらふらと、雪姫姉さんに支えてもらいながら立ち上がった。
「申し訳ありません、あの男に《太陽神の楔》を打ち込めなかった……」
雪姫姉さんの言っているのは、相手の動きを封じる七々々コレクションのことだ。以前、俺が見つけて色々あって雪姫姉さんにあげたものだ。ぶん殴られたり巴投げされたりした挙句に渡したから、パッと見にはカツアゲされたものと思われるかもしれないが、自分からあげたのだ。ほんとほんと。
「いや、いいっすよ。茨先輩の一撃が不発に終わった場合の保険だったんで……茨先輩が動けなかった以上、あれで堂島コウを捕縛するのは、無理だったと思います」
「……これから、どうします?」
「いやあ、正直」
俺は頬をかいた。
「策切れッスね」
「……私が破れかぶれで突っ込んでみましょうか」
「いや、もう堂島コウには近づかない方がいいと思います」
俺はそばに転がっていた、鉄くんの刀を雪姫姉さんに見せた。雪姫姉さんが息を呑む。
「……それは」
「黄金になってます。奴の手袋……あれも七々々コレクションなのかもしれません。もしくは、悪魔のアイテム、か」
「《ゴールデンライトアーム》です!」
「……ナンデスッテ?」
俺と雪姫姉さんは、背後を振り返って、アトリを見た。
アトリは腰に手を当てて、薄っい胸を張った。
「あの手袋の名前は《ゴールデンライトアーム》! 由緒正しきゲオルグ・ファウスト博士の手によって生み出された《知恵の実》なのです!」
「……《知恵の実》?」
「それが悪魔のアイテムの名称だよ」
アトリの頭をコツンと叩いて(痛っ!)、コウが言った。
「それと契約すれば、魂と引き換えに、自分の願いを叶えられる……もっともコレにはもう、誰かと契約できる力は残ってないけど」
「……それは、人間も黄金に変えられるのか?」
「ああ、出来る。だから接近戦はやめとけ。最近、悪魔のミカタも金欠でね。消費税も上がったし。彫像にされて売り飛ばされたくないだろ?」
ふふん、とアトリは腕を組む。
ふふん、とコウも腕を組む。
悪魔二人を前にして、俺たちは立ち尽くすしかなかった。
「じゃ、脅迫タイムに入らせてもらおうかな。自分がお宝にされたくなければ、手持ちの七々々コレクションを置いていってもらおーか」
「それはないな」
言ったのは、俺ではなく、
壱級天災だった。
帽子のつばに手をやり、天災は一歩、踏み出した。
「まったく、情けないな、重護。悪魔ごときにやられるとは」
「うっせえ! お前なんも手伝ってねーじゃねーか」
「いまからやる」
「どうする、アトリ。かわい子ちゃんだ。許してあげようか」
「だめです!!」
アトリに怒られ、コウはため息をつき、
「駄目だって」
「そうか。べつにお前に許して貰う必要などない」
「おお、ガッツあるじゃん」コウは嬉しそうに口元を歪め、
「あんたが真打だろうから、名乗り合おうぜ。俺は堂島コウ」
「私は壱級天災。名探偵だ」
「……メータンテー?」
「そうだ」
自信満々に自分を指差し、胸を張る天災。
「私に解けない謎はない!」
パチパチパチパチパチパチ。
拍手したのは、コウ。
「で、名探偵。どうやって悪魔を倒す? いったいどんな策略で、この俺の首から《グレイテストオリオン》を奪う?」
「ふむ」
天災は小さな顎に手をやり、考え込んだ。
「ちょっとした密室トリック、不可能犯罪にも似ているな」
「それって俺のこと褒めてんの?」
「無論だ。私は貴様を強敵として認めている。だから容赦はしない」
「容赦しない、ね。本当にそれが出来るか、名探偵」
「ああ、出来る」
そう言って、天災はどこからともなく、一冊の本を取り出した。
ぞっとするほど黒い本。不思議なことに題名はなく、表紙に金色の紋章が刻印されている。それが、風もないのに天災の手の上でパラララララとめくれ始めた。
天災はニィッと笑った。
「終わりだ、悪魔」
「…………っ!」
コウはバックステップを取ったが、おそらく、その行為に意味はなかった。
「こ、コウにーさん!」
「どうした? アトリ」
「そ、その顔……」
「顔?」
コウは自分の童顔に触れた。次いで、周囲の建物に嵌め込まれているガラスに目をやった。
その目が、ガラスに映った自分の顔に刻まれた、謎の数字の列を認識する。
「……これは?」
「《イゾルデの封印書》」
天災は手の上で本をポンポンと弄んだ。
「七々々コレクションの一つだ」
「天災! お前そんなの持ってたのか!?」
「ふっふっふ、重護。お前、ひょっとして私をただのお隣さんだとでも思っていたのか? 色々とお前の知らないところで、名探偵・壱級天災は大活躍中なのだ」
バタン、と本を閉じて、
「よく聞け、堂島コウ。その顔の刻印は『お前が死ぬまでの時間』だ。この本は死をばら撒く悪魔について記述されていた書物……その文字列が、お前に『刻印の呪い』として刻まれた」
「《グレイテストオリオン》」
コウは動じず、首のリングに手を触れた。
が、刻印は消えない。
「……駄目か」
「やはり、その七々々コレクションは自身を変化させるタイプの能力を持っているようだな」
「ご明察。さすがは名探偵。うーん、このままだと殺されっちまうな。どーしよ」
のんきに考え込んだコウのそばで、「あわわわわわ」とアトリが動揺している。
「な、な、な」
「ななな?」
「なんで、それがここにあるんですか!?」
「ん? なんだ悪魔……アトリとか言ったか。この本がどうかしたか?」
アトリは叫んだ。
「それは《知恵の実》です!!」
驚いたのは、コウ。
「……なんだって? それほんと? アトリ」
「ほんとですほんとです!!」アトリはコウの袖をぐいぐい引っ張った。
「あの本は死をばら撒き、それを『解決』することで未来の死を回避することが出来る……元々は、試練に挑むことで自分の死期を先延ばしにすることが出来る魔導書なんです。シリアルナンバ・二二一、《イゾルデの封印書》……《グレイテストオリオン》と同じ《知恵の実》です!」
「契約は? あの名探偵と」
「契約完了魔力は探知していません。えーとえーと」
アトリはどこからともなく「ポン」と、イゾルデの封印書そっくりの本を空中から出して、それをぺらぺらとめくり始めた。カタログのようなものなのだろうか。
「最後に魂を回収されてからの使用は十三回。物凄く回収効率の悪い《知恵の実》で、ほとんど《廃棄》寸前だったはずなのに……」
「では、その《知恵の実》とやらを、七々々殿が十年前に見つけてコレクションにしていたのだな」
天災が言った。コウが頷く。
「そうらしいな。おい、名探偵。魂を持っていかれる前に、その本を捨てた方がいいぞ」
「断る。というか、これは私に取り付いているようなもので、厳密には私が所有しているわけではない」
「取り付いている?」
「この本と勝負していてな……ま、私の事情など、どうでもいい。そこのヒワイな奴。この本について理解しているなら堂島コウに説明してやったらどうだ?」
ヒワイな奴ってあたしのことですか、ねえあたしのことですか、涙目でコウにすがりつくアトリの頭をコウはポンポンと叩いてやった。
「気にするなアトリ。ヒワイだっていいじゃないか。悪魔なんだし」
「コウにーさん……」
「それで? これから俺はどうすればいい?」
くすん、と一度しゃくり上げて、アトリは語り出した。
「あの本から『刻印の呪い』が発せられたなら、時間が来れば『死』がばら撒かれます。ですが、その前に殺人が起こるはずの『惨劇の未来』へ行って、事件を『解決』できれば、『刻印の呪い』は解除され、惨劇は起こりません……」
「そういうことだ」
天災が言った瞬間、世界が変わった。
血の大河のように赤い空、そしてどこまでも続く灰色の背景。場所こそ遊園地のままだが、その全てから色彩が消え失せている。
そして、堂島コウの足元に誰かが倒れていた。
堂島コウだった。
マントを着たまま、うつ伏せに倒れ、虚ろな眼窩を見開いているそのコウもまた、灰色だった。本物のコウが、自分の死体をそのすぐそばで見下ろしていた。
「これが『惨劇の未来』か……」
血まみれのナイフが一本、天災とコウの中間地点に転がっている。
コウがそれを拾った。
「これが犯行の凶器か」
「だろうな。犯人は私たちの誰かだろう。動機は誰もが同じだ。『刻印の呪い』から発せられる、催眠術のような殺人衝動で、お前を殺し、《グレイテストオリオン》を奪った。この距離だ、誰でも殺せる。お前は『刻印の呪い』に選ばれた『死の対象』であるため、ナイフを回避できなかった……」
天災は笑う。
「さ、どうする? 手がかりゼロだ。お前にこの事件が解決できるかな?
ちなみに、私にはもう解けている」
「……マジかよ、天災」俺が言った。
「……マジかよ、天災」コウが言った。俺は睨んだ。
「マネすんなよ」
「悪い悪い。少しテンパった」
コウは手の中でくるくると血まみれのナイフを回転させた。
「俺が解けなきゃ、俺は死ぬのか」
「ああ、そうだ。解答権は一度きり。だからお前がそれを外せば、助かる道は一つしかない」
「……その心は?」
「《グレイテストオリオン》を捨て、私にこの事件を解決してもらう。
それだけが、推理を外したお前に残された未来だ。もっとも、当てられてしまえば、こちらはそれまで。お前は助かり、私たちは全員まとめてこの《ゲーム》から敗退。第二ステージへは進めないだろう」
天災は腕を組み、いつの間にか現れていた、真っ赤な椅子に腰かける。
「当ててみろ、堂島コウ」
コウはしばらく、手の中のナイフを見ていた。
「コウにーさん、時間が……」
「わかってる」
コウはナイフを振り上げて、
「犯人は、あんただ」
その切っ先を、雪姫姉さんに突きつけた。
雪姫姉さんは、驚いていない。
「……どうだ、名探偵」
天災は答えた。
「外れだ、堂島コウ」
カラン、と。
コウの手からナイフが滑り落ちた。皮肉塗れの顔で笑う。
「向いてねーな、やっぱ、俺に探偵は」
「……ちなみに、なぜ、私だと?」
怪訝そうな雪姫姉さんから、いやあ、とコウは気まずそうに顔を背けた。
「昔馴染みに雰囲気が似てたから、とか? 俺にもわかんねーッスよ。手がかりなかったし。時間もなかったし。畜生、やっちまったな。俺としたことが……」
「そ、そんな……じゃあ、いったい誰がコウにーさんを!」
誰なんですか、いったい誰が、とアトリが天災の肩をゆっさゆっさ揺さぶった。名探偵の顔がブレている。
「よせよせよせ。私は酔うぞ。おうぇ」
「誰が犯人なんですか! なぜ、なんで、どーしてこんなひどいことを!」
天災はチラっとコウを見た。コウは肩をすくめて、首から《グレイテストオリオン》を外し、天災の足元にそれを蹴っ飛ばした。
それを確認して、
「犯人は……」
そして、名探偵は、自分に親指を突きつけた。
「…………この私だ!!」
「あっはっは」
コウが笑い出した。
「ひでぇ名探偵だな。自作自演じゃねーか」
「そんなことはないぞ。なにせ、私はまだ殺っていないのだから」
「かもな」
天災が推理を公開した瞬間、霧が晴れるように、遊園地に色彩が戻り、空が赤から青へとスライドした。
ぽかぽか陽気の晴天を見上げて、コウはため息をつく。
「俺の負けだな」
「そのようだな」
天災が言って、足元の《グレイテストオリオン》に手を伸ばした。それを見て、コウが言う。
「ひとつ忠告しておく。名探偵」
「なんだ?」
「あんまり、自分の頭脳をひけらかすなよ。誰かに殺されてからじゃ遅いぜ?」
「ふん、私は殺されなどしない」
「どうかな」
「……ふん。おい、重護」
「なんだよ? ……わっ」
天災は俺に《グレイテストオリオン》を放り投げてきた。
「……いいのか?」
「そんなものを使って、来年なる予定のスーパー名探偵に私が今なってしまったら、面白くないからな」
「……というか、お前、自分が持ってると本当に『契約』しちゃいそうでビビってんだろ?」
アトリの失言で、俺たちは《グレイテストオリオン》が《知恵の実》であることはもう分かっていた。
「う、うるさい! わ、私は何も聞いてなんかいない、囁かれてなんかいないぞ……!」
ぶるっと身震いした名探偵は、それきり堂島コウには目もくれず、《ゲーム》第二ステージ会場である城を目指して歩き始めた。他の参加者たちも、おのおのがこの突然の乱入者に思うところはあるのだろうが、振り切って歩を進めていく。
コウはその場に大の字になって寝転がっていた。
どーにでもしてくれ、って感じだ。
俺は手の中の《グレイテストオリオン》をポンポン弄んでいたが、最後にちょっと、コウのそばで立ち止まった。
「……残念だったな、堂島コウ」
「ん? いや、べつにいーよ。《グレイテストオリオン》? くれてやるさ。長い付き合いだったけど、それじゃ俺の願いは叶わない。十年前に、実証済みだ」
「……あんたの願い?」
「死んだ恋人を生き返らせること」
「か、彼女持ちだったのか! 男の敵め!」
あっはっは、とコウは笑う。
「いいことばっかじゃねーぞ? 後輩。死なれたら苦しいし」
「……そっか」
「お前にも忠告しておく」コウはぴっと指を立てて見せ、
「その《グレイテストオリオン》は魂回収率ぶっちぎりでナンバーワンの《知恵の実》……叶わない願いは『無い』とまで言われた傑作だ。さっきの名探偵もそうだが、お前にも『声』が聞こえるんじゃないか?」
俺は答えなかった。
「お前が何を夢見ていようが、その《グレイテストオリオン》はいつか必ずお前に囁く。
その時、お前はそれを拒否できるか?
いらないと、突っぱねることが出来るか?
出来なければ、覚えておけ。
俺が必ず、お前の魂を取り立てる」
「……こえーこと言うなっつの」
「ふっふっふ、怖くなったら、いいんだぜ? 誰も見てないし、俺にそれを返してくれても?」
「やっぱ欲しいんじゃねーか!」
「決まってんじゃん、当然だろ」
コウはひらひら手を振った。
「もう行けよ。第二ステージに遅れるぞ」
「……ああ」
俺は最後にちょっと振り返って、動かなくなったコウを見、それから城を目指して走り出した。
○
コウは空を見上げている。
吸い込まれそうな青空だ。
いつか見たのと同じ……
そんな青が、誰かに遮られた。
「久しぶり」
コウは目を細める。
見知らぬ少女が、コウを見下ろしていた。
「……よう」
口元を斜めにし、
「十年ぶりだな、七々々ちゃん」
「あ、やっぱりわかった?」
「取り付いてても、雰囲気は変わらねーよ。ていうか、いいのか? 出てきちゃって」
「コウが出てくるからいけないんだよ。追い出そうと思って飛んできたんだから」
「あー、そうなんだ。悪かったね」
「いいよ、負けてくれたし」
「ひどいなあ」
「……まだ、悪魔のミカタをやってるんだね」
「当然。それが俺の願いだから」
「目的は、やっぱり《七々々の剣》?」
「もちろん」
少女は、ちょっと躊躇ってから、言った。
「せっかく再会できたし、その餞別で教えてあげる。コウ。
《七々々の剣》は、《知恵の実》でも《It》でもないよ」
コウは、黙っていた。
「ねえ、コウ。来てくれて、悪いんだけど、ハッキリ言っとく。
コウの願いは、この島じゃ叶わないと思う。
この島は、若者が誰でも夢を見られるように、私が仲間と作った場所。
あなたのいるべきところじゃない」
「それなら、もっとハッキリ言えばいい」
コウは空を見上げながら言った。
「七々々コレクションの中に、『人を生き返らせる秘宝』は存在しないって、七々々ちゃんの口からハッキリ言ってくれれば、俺はここから出て行く。二度と君の前には現れない」
「……それは、できないよ。ルールがあるから」
「だろ? じゃあ、俺は諦められない。最後まで追いかけるよ。実際、《コレクション》の中に《知恵の実》が混じっているのも真実だし。ヤバイんじゃないの? せめて《知恵の実》だけでも、俺に渡しておきなよ、だいじょうぶ、悪いようにはしないって!」
「夢を追うには、リスクも必要だから」
「交渉決裂、か」
「そうだね」
「ちぇっ」
「……変わらないね、コウは」
「ああ、俺は変わらない。変わらずに、いつか、日奈を生き返らせる。その時まで――」
そしてコウは気づいた。
もう少女はどこにもいない。
最初からいなかったかのように。
コウは、その場に大の字になって寝転がったまま、
やがて独り、笑い出した。