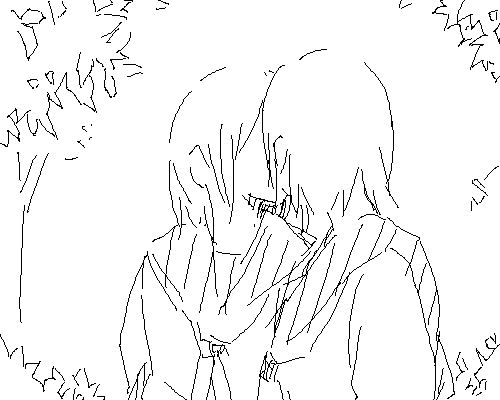凛はいつも笑っていた。
微かに朱を帯びた頬に小さな笑窪を浮かべて。柔らかな木漏れ日が似合うその穏やかな笑顔を、響子は密かに嫉みながらも、凛に夢中になっていた。
そして、それだからこそ気付いた。凛は感情豊かで明朗闊達を絵に描いたような少女だが、実際のところそれは彼女の本質とは恐ろしく乖離した仮面に過ぎないのだと。
響子は金貨を右手でつまみ、差し込む夕日を金貨で受け止めた。反射した光が響子の視界を金色に眩ませる。目の奥に鈍痛が走ったが、そのまま光を眼球に照射し続けた。
こんな目はいらない。この目はただついているだけの役立たずで、ずっと凛を追っていたくせに結局は何も見えていなかったのだから。
しかし響子の意思に反して、彼女の身体はこのささやかな自傷行為を拒絶し、手首を返らせ反射光を赤く染まった教室の天井へ逃がした。
舌打ちをして、天井を見上げる。小刻み揺れる光点をぼんやりと眺めながら響子は、憶えている限りの凛の笑顔を反芻していた。
あの中に、一体いくつの本物があったのだろう。
今となってはもう何もわからなかった。
もしかしたら、全てが―――凛の笑顔など、響子は知らないのかもしれなかった。
二人のカップが空になったのはほぼ同時だった。
河川敷での一件から4日後の土曜日。中途半端に開けた駅前に隣接する、中途半端に大きいショッピングモール。地下1階の隅っこで隠れるように営業している喫茶店で、響子は『お礼』を果たしていた。
紅茶とケーキセットというスタンダードなオーダーだったが、値段の割りにはとても美味しくて、響子はもちろん、凛も満足したようだった。
「いいわね、このお店。今まで気付かなかったわ。こんなところに喫茶店があるなんて」
また来ようかしら。凛がぽつりと漏らしたその言葉に、何故胸がこんなにも高鳴るのだろうと響子は不思議に思った。同時に迷う。「また一緒に」と言って良いものかと。
しかしそんな響子の葛藤は杞憂に終わる。
「ね?」
軽く首を傾げ、凛が響子を覗き込む。退屈しきった猫のようだ、と響子は吹き出しそうになったが、その仕草の意味を正しく理解した途端、頬が火照るのをありありと感じた。
「私と、ですか」
何を萎縮しているのかと、自らの卑屈さに呆れ果てる響子だったが、そう訊かずにはいられなかった。「また」と呟いた凛はその実あまりにも孤独で、そこに他者の入り込む余地はないように響子には感じられたのだった。
「嫌かしら」
「まさか」
そんなわけないです。手を振り振り、思わず声が上擦る。
「染井さんと一緒にお茶ができるなら、私は何よりもそれを優先しますよ」
呆気にとられたように、凛は響子をまじまじと見つめた。あまりにも大げさな響子の表現に戸惑っているらしい。
頬に垂れた髪を耳にかけ直しながら、凛は溜息と共に、
「本当に面白い子よね、なんというか―――そう、私はそんなに重用されるべき人間ではないのよ?」
釣られて凛の言葉も大仰になってしまう。言ってから、凛は例のシャックリのような独特の笑いを漏らした。
「いえ、あの、私にとってはですね。染井さんは恩人なわけですから」
ばつの悪さを誤魔化すように、響子は早口でまくし立てる。恥ずかしさに頬はますます熱くなり、汗が滲み出してきた。
「あのコインは本当に、あれが無くなったら私、きっとどうにかなってしまうくらい大事なものだったんです。だから、あの時染井さんと出会って、コイン探しを手伝ってくれて、見つけてくれて―――嬉しかったんですよ、この上無い程に」
奇跡のようだったと、響子は今になって思った。
途方も無い絶望の淵で出会った、凛はまさしく白騎士だったのだと。あの時の凛を、会ったばかりの響子の為に必死になってくれた凛の姿を思い出す。
今にも暮れそうな夕日の下、うっすらと汗を浮かべた凛の横顔。傷ついた、それでも美しい凛の指先。それだけで眼の奥が熱くなるのだった。。
「言葉なんかじゃ全然足りないくらい感謝しているんです。今の私なら、あなたの為に何だってできるんだわ、きっと。変な子だと思うかもしれないけれど」
ああもう、どうすればいいのかしら。
自らが言ったとおり、言葉とは何て不便なのだろうと響子は地団太を踏んだ。語彙力などとは無関係な次元の問題だった。堪らなくなって、響子は凛の手を取り、強く握り締めた。なんの意味もない行動だったが、それでも何かせずにはいられなかった。
「ごめんなさい、やっぱり変ですよね。でも、どうしても、私」
「変だなんて思ってないわ。少し驚いてはいるけれど―――なんと言えばいいのかしらね、この場合。ありがとう、かしら」
暁に映える朝露でも見たかのように、凛は目を細める。
「でもね、さっきも言ったけれど、そんなに気にしなくて良いのよ。あれは私が好きでやったことなのだし。あんまり買いかぶられても、どうすればいいか分からなくなってしまうわ」
あやすように、凛が響子の手を握り返す。それだけで、響子は奇妙なほど急速に落ち着くのだった。まるで抱きしめられているようだった。
「私は今日あなたとここに来れただけで、心から満足しているけれど。もし、あなたが満足できないと言うならそう言ってちょうだい。あなたのしたいこと、して欲しいこと。私は何でも受け入れるわ」
いつの間にか『お礼』の行き先が変わっていることに響子は気付かなかったが、もはやそれは些事に過ぎなかった。結局のところ、二人の願いは―――微々たる、しかし致命的なズレはあったが―――同じだったのだから。
“ともだち”
どんな関係なのかと、問われた時に二人手を繋ぎ顔を見合わせ微笑んで。
そう答えたい。それだけだった。
「響子と、呼んでください」
「じゃあ凛って呼んでもらおうかしら」
全てが、そのささやかなやり取りで通じた。初めての感覚だった。つい先程まで、言語疎通の不便さに苛まされていたのが嘘のように、触れ合った手の平を通じて凛が響子に沁みわたってくる。
「えへへ」
私はまだこんな笑い方ができたのかと、響子自身が驚くほど自然に笑いがこぼれた。
だらしなく緩んだ響子の口元を見て、凛も「うふふ」と笑う。
凛の笑顔は本当にどこまでも優しくて、柔らかくて、温かかった。
見た者全てを虜にするような、あまりにも魅力的だったその時の凛を、今でも響子は憶えている。
あの時、凛は何を考えていたんだろう。何を思って笑っていたんだろう。
いくら思いをめぐらせても、響子には何一つわからなかった。あの頃の凛は途方も無く深い絶望の底に居たはずで、優しい言葉を求めこそすれ、掛けることなど到底出来ない状態だったろうに。
「あなたに会えて、良かったわ」
あの日の別れ際、そう呟いた凛の横顔に響子は心を奪われた。15年余りの人生で初めて、心から美しいと思えた。
風に揺れる黒髪は嘘みたいに滑らかで、夕日を淡く照り返す肌が眩しくて、そして―――
何もかもが過ぎ去り、取り返しのつかなくなった今だからこそ、響子は確信できた。
凛が髪を掻きあげた、その一瞬ちらりと見えた光は、涙だったのだと。
「響子」
あの日以来、通学路で、廊下で、校門で。響子を見つける度に、凛はそう言って駆け寄ってきた。
名前を呼ばれるだけで、こんなにも嬉しいものなのかと響子は驚く。響子の友人もまた彼女をそう呼ぶのだが、凛とは違い高揚感など全く無いというのに。そしてまた、そんな相手を「凛」と呼べる幸せは眩暈を覚えるほどで、凛の手を、腕を掴んでいなければそのまま倒れてしまうのでは、と響子は怖くなるのだった。
夏休みに入ってからはさらに二人でいることが多くなった。買い物へ、課題をこなすために図書館へ、遊園地へ。驚くほど急速に二人の距離は縮んでいく。
この頃のことを後に思い出す度、響子は激しい後悔に襲われた。あまりにも冷静さを欠いていたと。凛との劇的な出会いと発展に夢中になるあまり、見落としていたものが多すぎたのだと。
しかし当時の彼女は将来の後悔など知るはずも無く、ただただ幸福を謳歌するままに夏休みを終えたのだった。
「今日はどこで食べようかしらね」
昼休み。二人で弁当を持ち、校内を散策する。
彼女達の通う高校は大変に広大な敷地を持ち、校庭や大食堂はもちろん一般に開放している公園まであった。そのため、ほとんどの生徒は昼食を教室外でとる。
「見て、響子。空が真っ青だわ。雲がどこにも無い」
9月も半ばを過ぎ、徐々に秋の空が見え始めていた。とはいえ、日中は未だに日差しが強く気温も高い。しかし、衣替えを待たずに凛は長袖のブラウスを着ていた。暑くないのかと訊く響子に凛は、日陰を選んで歩きながら少し寂しげに笑うのだった。肌が弱いから、直射日光を長時間浴びると真っ赤に焼けてひどく痛むのだと。
陽を浴びながらの散歩は大好きだけれど―――そうなかなか上手くはいかないものよね。いつだったか凛がそう漏らしたのを、響子はぼんやりと思い出す。陽光に照らされ佇む凛はあんなに素敵なのに、その光景が実は痛ましいものなのだと思うと残念でならなかった。
「こういう、雲ひとつ無い空というのも綺麗だけれど、なんだか味気ないわね。やっぱり私、夏の空が好きだわ。というよりも、入道雲が」
手をかざし空を見上げながら、凛は小さく息を吐く。今夏の空を振り返っているのかもしれなかった。
「あぁ、たしかに。入道雲っていいわね」
凛と知り合ってからまだそれほど経っていないにも関わらず、気付けば響子は凛に敬語を使うことをやめていた。凛に促されるまでもなく、それが自然な事のように感じられた。年齢が一つ違うだけで『先輩』と『後輩』に区別されるようになってから、それは初めての経験だった。
「なんていうか、湧いてくる感じ。元気とか、上手くいえないけど、うん―――生きていけるんだって思える」
突拍子もない響子の台詞に、はっとして凛は立ち止まった。微かに頬が紅潮している。
「そう、そうなのよ。なんだか嬉しいわ。今までこの感覚を誰かと共有できたためしが無かったから」
響子の手を取り、にっこりと笑う。
「小さい頃―――本当に、記憶もあやふやなくらいのことだけど。すごく大きくな入道雲を見たの。真っ白に輝いていて、柔らかそうで、ああ、あれに包まって眠れたらどんなにか気持ち良いだろうって、そんな事を考えたわ。とても幸せで、大切な記憶」
凛は小さくかぶりを振り、渇いた洟をすすった。数秒ほど地面を見つめていたが、すぐに顔を上げ、再び空を見上げる。
「ええ、あの頃は幸せだった。別に今を否定するつもりはないけれど、それでも。いつも笑っていたわ。怖いものなんて、お化けくらいで。それに父はとても優しくて、夏休みだったと思うけど、遊園地を二人で手を繋いで歩き回ったわ。どんな我が侭も笑って聞いてくれた。そうね、あの頃は世界の全てが優しかった。何ものにも否定されず、何ものも否定せずに全てが上手く廻っていた―――今になって思えば、それは信じられないことだけど。でも、だからかも知れないわ。入道雲を見ると、あの頃に戻った気がする。あの頃に戻れる気がするの」
凛は社交的な少女だが、しかしこれほどに朗々と語る姿を響子は知らなかった。堰を切ったように次から次へと、言葉が溢れて止まらないようだった。
彼女の言う『感覚』は響子のそれとは全く別のモノだったが―――響子にとっての入道雲は夏の豊かな生気の象徴だった―――切実と言っていいほどの凛の想いに頷くことしかできなかった。嫌われたらどうしようとか、そういった次元の問題ではなく、「私の感覚とは違う」などと凛を否定することで何か取り返しのつかない事態を招く予感がしたからだった。
「でもね」
不意に凛は言葉を切り、深呼吸してから響子に向き直る。
光線の関係か、輪郭がぼやけて、すぐ目の前にいるはずなのに表情が全く読めなかった。恐らく笑っているのだろうと、響子は自らに言い聞かせる。凛はいつも笑っているのだから。今もあの柔らかい微笑みを浮かべているに違いないのだ。
「同時に思い知るの。時は二度と戻らないって。どんなに素敵で、幸せな時代があったとしても、過ぎてしまったらそれはただの記憶。もし今が辛いのだとしたら、それはむしろ毒にしかならないんだわ」
響子は眩暈を覚えた。低く僅かに掠れた凛の声が頭の奥を痺れさせている。言葉の意味は殆ど理解できなかったが、この上なく気持ちよかった。
「だから頑張れるのよ、きっと。今を不幸だと思った瞬間、あの美しい光景が苦痛でしかなくなってしまうから。そんなの嫌じゃない?入道雲を見ると、力が湧いてくる。やってみせようじゃないって、奮起できるのね」
それは凛が初めて見せた、素顔の欠片だった。闘志に満ち満ちた獰猛な瞳が響子を射抜く。普段の響子なら怯えたかもしれないが、茫洋とした意識と快楽の中、それは心地よい刺激として感じられた。
「うふふ」
不意打ちのように発せられた凛の笑い声に、響子は一瞬で覚醒する。先程までの痺れが嘘のようだった。微かな痛みを感じるほどに、咽喉が渇ききっている。
今では凛の笑顔が鮮明に認識できた。やっぱり笑っていたのだと安堵したが、凛に握られた右手はじっとり汗ばんでいた。不思議だった。今しがた感じた不安がなんだったのか、よく思い出せない。
「あら、もうこんな時間だわ」
腕時計に目をやり、凛は驚いたように呟いた。昼休みは20分程しか残されていない。
急ぎましょう。そう言って凛は歩き出す。適当な木陰にベンチを見つけ、響子を手招きした。
「響子と話していると、本当に時間を忘れてしまうわね」
弁当を膝の上に広げながら、くすくすと笑う。
「こんなの初めてよ。馬鹿みたいな話だけれど、今までは誰と話しても退屈しか感じなかったの。あなたと彼らの何が違うのかわからないけれど、でも」
「褒められてるのかしら、それ。なんだか変な子呼ばわりされてる気がするわ」
「あら、最初に自分を変な子って言ったのはあなたでしょう?」
いつだって、凛との食事は楽しい。普段なら見向きもしない話題もこの時だけは最高の肴になるのだった。そんな他愛も無いお喋りに、響子の中に沈殿していた不安の名残が溶け消えていく。
―――そうだ、これが全てなのだ。私がいて、凛がいる。それだけでいい。それさえ見失わなければ、何があろうと私達は大丈夫なのだ。
変な子だなんて、本当に面白い表現よね。そう言って屈託無く微笑む凛を見つめながら、そんなこと思う。徐々に早くなる動悸に戸惑いながらも。
「そういえばそうだったかしら。まあいいわ。私といて楽しいって思ってくれるなら、こんなに嬉しいことはないもの」
「楽しいわよ、本当に。あなたといると、色んなことに気付かされる。そんなこと今まで無かったから―――あなたは私に感謝してるって言っていたけれど、それは私だって同じ。分かってもらえるかしら、この気持ち。例えば―――そうね、何だと思う?私が一番、あなたに感謝していること」
「え、なんだろう。凛の前じゃ変なことしちゃった覚えしかないから。お礼言われるようなことしたかな」
顎に手を当てしばし考えるが、見当もつかなかった。うーんと唸る響子を可笑しそうに凛が見ている。
「ごめん、全然わからないわ。何だったの?」
「それはね」
開いたまま手を付けていない弁当箱に視線を落としながら、凛は躊躇するように言葉を切った。それは、ともう一度繰り返してから、今度は正面から響子を見る。
「私のような人間でも、誰かを愛せるのだと気付かせてくれたこと」
そう言って、凛は響子の唇に唇を重ねた。
視界が光で溢れる。眩しくて、何も見えなかった。
しかし唇の感触と間近に聞こえる凛の息遣いと微かな匂いが、響子に悟らせた。
恋をしていたのだと。出会ったその瞬間から、凛しか見えていなかったのだと。
愛している。
そう凛は言ってくれました。
私は信じています。彼女の言葉は―――数々の嘘に塗れていたことは否定しませんが―――愛していると言ってくれたあの時だけは、それでも真実だった。
だからこそ、悔やむのです。
凛は精一杯の勇気をもって助けを求めてくれたのに。
舞い上がるばかりだった私は、何も理解することなく、しようともせず、凛の想いに応えているつもりで、結局のところ彼女を裏切り続けました。
凛の失望がどれほどのものだったのか―――今となっては、確かめる術もありません。
だいにわ 『☆だいこんらん☆』