塔から脱出するゲーム2
15.???の塔
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 超能力者の塔 X
X X
X 難易度:NOLMAL X
X X
X プレイヤー:ホッシーナ(タイムトラベラー) X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 超能力者の塔 X
X X
X 難易度:NOLMAL X
X X
X プレイヤー:ホッシーナ(タイムトラベラー) X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 内部エラーを検知しました。『超能力者の塔』を実行できません X
X X
X 不明なモジュールが強制実行されました X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 内部エラーを検知しました。『超能力者の塔』を実行できません X
X X
X 不明なモジュールが強制実行されました X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 難易度:皆殺し X
X X
X プレイヤー:ホッシーナ(タイムトラベラー) X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 難易度:皆殺し X
X X
X プレイヤー:ホッシーナ(タイムトラベラー) X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X X
X X
X 「あの女、許さない」 X
X X
X X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X X
X X
X 「あの女、許さない」 X
X X
X X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 狩場の屋上 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
タイムトラベル以外に「平行世界を移動できる」という、どこぞの大統領のような能力を持っているホッシーナにとって、この世界はまだマトモなほうだった
移動した世界がとっくに壊滅していて、残された人類が自分と自我を失った超能力者だけ――というのが、これまで渡り歩いてきた中でぶっちぎりに最低な世界。そんなホッシーナからすれば『目が覚めると見知らぬ塔の屋上』は、「少々インパクトに欠けるスタート地点ですね」と軽口を叩けるほど平和である。
(それにしても、どうして私はこんな格好を……)
ホッシーナは服を着ていなかった。ただ全裸というわけでもなく、なぜか水着を着ていたのだ。しかもビキニなので肌の露出が多く、メリハリのついた体型にコンプレックスを持っているホッシーナからすれば、それは野外露出にも等しい。
生地が白色というところだけが、かろうじて救いだった。これで黒色だったらもはや痴女でしかない。
(まあ誰も見ていませんので、別にいいのですが――)
ぐるりと周囲を確認したとき、それを見つけてしまった。
数メートル先に設置された『ある物』。さすがのホッシーナも驚いてしまった。
固定式の砲台。仕組みはわからなかったが、チキチキチキという音が聞こえることから次の瞬間にでも発射されるのだろう。
何が発射されるのだろう。ホッシーナが予想するよりも早く、それは発射された。
ヒュンと風を切って飛び出した、矢。いかにも砲弾を発射しそうなこの砲台は意外に原始的らしく、先ほどのチキチキチキという音は内部で弦が引かれている音だったらしい。
「どんな構造になっているんでしょうか、あの砲台」
砲台をちらりと見て、次に矢に注目する。
「あらあら、この矢じり、すごく鋭いじゃあないですか。こんなの当たったら死んじゃいますよ」
まるでカタツムリが進む速度で宙に浮く矢を、ホッシーナは軽く撫でたあとにポキリとへし折った。
人は死ぬ間際に一生の記憶が一瞬で再生されるらしい。それは走馬灯という現象であるが、ホッシーナはそれを見たわけではない。
時間加速。タイムトラベラーの能力を使用し、自分の時間を数倍に加速することで本来流れている時間を引き伸ばした――わかりやすく言えば、超高速で動いたのだ。
砲台からの直線上から外れ、時間加速を解除する。すると気だるい疲労が全身に降りかかり、クラリと立ちくらみを起こした。
(これさえなければ、最高の能力なのですが……)
タイムトラベルは使用者に大きな負担を与える。ホッシーナはこれを代償と割り切っていたが、この世界では少しわけが違う。ホッシーナは今までどおり『疲労』と思っていたが、正しくは『身体能力の低下』だった。
運動能力と五感、思考能力が減少し、一度失ったそれは巻き戻るまで回復することはない。もちろん今のホッシーナはそのことに気づくはずがない。
(今さらウダウダと文句を言うつもりはありませんが……)
カチカチカチ
(どうして、次から次へと!)
どういうカラクリになっているのか、足元の石畳の1つが横にスライドし、丸い筒が現れた。
その筒からは、ゴポゴポと何かの液体が沸き出していた。ホッシーナはその液体の正体を知るはずもないが、ただ、ガソリンのような異臭がしていることにはすぐ気づいた。
(これは……! 時間、停止!)
周囲が白黒になる――なんてことは当然ないが、異臭がしない。まるで最初からなかったように、異臭は消えていた。
ふらふらと不安定な足取りでその場から、用心して十数メートルほど離れる。
――ドォン!
時間停止を解除すると、足元に筒があったところから巨大な火柱が生まれ、爆音、爆風と共に周辺を吹き飛ばした。
予想以上の爆発と身体能力の低下に、ホッシーナは立っていられなくなり座り込んでしまう。キンキンと耳鳴りがしていた。火柱の熱がちりちりと顔を焼き、吹き飛ばされた石畳の破片が小雨のように降りかかる。
(まるで狙い澄ましたようなトラップの配置……ここまで悪意を感じる世界は初めてですね……)
時間加速に続き、間を置かずに時間停止。身体能力低下も著しく、もはや立つことさえままならない。
ホッシーナはこれを疲労と思い込んでいるため、少し休めば大丈夫だろうと気楽に考えていた。
(ただ、それまでに何もなければいいのですが……ん?)
しばらく休もうと這うように横になったとき、手を伸ばせば届くところに宝箱が置いてあることに気づいた。
ロールプレイングゲームなどでよく見かける、手に収まるほどの宝箱。だが、ホッシーナの表情は硬い。
(こんなのありましたっけ……?
この流れからすると、どうせトラップに違いありません。透視が使えればいいのですが、あいにく私は時間操作しか――)
パカッ
宝箱は勝手に開いた。
赤や青などの多くの配線に、なんとなくその正体の予想がついてしまう数本の黒い筒。そしてデジタル式の時計が、残り5秒からカウントダウンを始めていた。
(ああ、なんてひどい……)
4、
3、
2、
1、
――爆発。
先ほどの爆発と比べると小規模ではあったが、人一人を吹き飛ばすには十分すぎた。
(……私じゃなかったら、死んでましたね)
ホッシーナは爆発による怪我や焦げが一つもなく、何事もなかったようにそこに寝転がっていた。
時間加速、停止をしたところで動くことができない。なので、カウントダウンに合わせて数秒、『未来に飛んだ』。
爆発する直前から爆発後の時間、その場にホッシーナはいなかった。タイムトラベルでその瞬間だけ跳躍し、九死に一生を得たのだ。
けれど代償も大きかった。動くこともできず、大の字に寝転がって呼吸するのが精一杯であった。
(それにしても……)
ホッシーナは休みながらも、ここまでのトラップを思い出していた。
固定式の砲台。
埋込型の大型爆弾。
宝箱型の小型爆弾。
用意周到に設置されていたと思った。が、よくよく考えると妙だ。どうも詰めが甘いように感じられた。1つ1つの起動の間にタイムラグがあり、その結果能力を使って逃げることができた。
もっと良い配置ができたのでは? または、もっと効果的なトラップがあったのでは? 詰将棋のように追い込んで殺すぐらい、この塔の悪趣味さなら可能ではないのだろうか。
これは、まるで――
(私が能力を使うよう、仕組まれていたような……)
それは思いつく限りで最悪な想像。なぜなら「この塔を管理している者は、自分がここに来ることを知っていて、それを前提にトラップを設置している」ということだからだ。
(……成るように成るだけですね)
これまでに死を覚悟したことはなかったわけでもない。そんなとき、ホッシーナは運に委ねることにしていた。
体力が戻るまでにトラップ等が起動してしまったら、それまで。そうでなければ見苦しくても生きてみよう。ホッシーナは空を見ながら考えた。
(でも、わざわざ殺さずに追い詰めたとして、何の意味があるんだろう)
その疑問の答えはすぐわかることになった。
太陽の光が眩しくて細めていた視界に、影が覆った。
ゆっくりと首をひねると、そこには腰にボロ布をまとい、手には大きな棍棒を持った緑色の人でない生物。
(ゲームとかでは定番の……ゴブリン、のようですね……)
運がなかった。潔く諦め、目を閉じた。
どうせ死ぬなら一瞬で、なるべく痛みを感じないように死にたい。全身の力を抜き、呼吸を落ち着かせ、そのときを待った。
が、そのときが来ない。しばらく待ってはみたものの遅すぎる。
首に力を入れて頭を持ち上げ、目を開いた。
ゴブリンはホッシーナの足元にしゃがみ込んで、すんすんと鼻で呼吸をしていた。
嗅いでいる。この醜い異形が――――の臭いを、嗅いでいる! ホッシーナの怒りの沸点は一瞬で振り切った。
「何を、しているんですかっ!」
「ギャァッ」
抵抗しようと動かした脚が思っていた以上に動き、ゴブリンの顔を蹴り抜いた。当たりどころが良かったのか、軽い音と共にゴブリンは石畳に飛ばされ、ゴロゴロと転がった。
(しまった、こういう単細胞な生物は変に刺激したら……!)
極めて的確な見解だった。起き上がったゴブリンはとても言語化できそうにない唸り声を発し、威嚇のために大きく開いた口からは鼻が曲がりそうな異臭がする唾液を垂れ流している。
そして手に持った棍棒を高く振り上げながら、近づいてきた。
「ごめ、ごめんなさい! わざとじゃないんです、でもあなただって悪いんですよ、あんな――」
――ゴッ! ぼきンッ
「イ゛!」
言い訳なんて通じるはずがない。ゴブリンはホッシーナの脚に棍棒を振り下ろた。鈍い音が響き、折れる音。
ホッシーナは次に叫ぶための空気を思いっきり吸い込んでいた。
「イギャアアアアアアッ! あし、あジがぁぁぁぁぁ!!!!!!」
喉が枯れるほどの悲鳴。目尻に溜まることなく涙がこぼれ、叫んだ拍子に口内を切ってしまったのか、血と唾液を吐き出しゴブリンに浴びせていた。
「ギャ、ギャギャギャ!」
――メギッ! ばきっ!
「グギャ、がっ! アガっ! ああああ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛っ!」
右脚の次は、左肩。その次は左腕。
そこから先は、めちゃくちゃにホッシーナを殴りつけた。
殴られた場所は赤く、青く、不気味なほどに黒い紫へと変色していく。
ゴブリンの手が止まるころ、ホッシーナはあまりに無残な姿になっていた。元々生地の少ない水着は破れ全裸状態、本来曲がるはずがない方向に腕が曲がり、顔は涙や唾液やらでぐちゃぐちゃに汚れていた。
ゴブリンは棍棒を投げ捨て、ホッシーナにのしかかった。体臭、唾液の悪臭から顔を背けようにも、ホッシーナはそれすらできないほどに瀕死だった。
(早く殺して……もう、苦しいの、嫌だ……)
生への諦めは、死の懇願への変わっていた。だが舌を噛み切るほどの勇気はなく、結局最期の一撃はゴブリン頼みだった。
しかし、ゴブリンはその願いを叶える気は少しもないようだった。
ゴブリンはホッシーナのことを「外敵」と見なしていた。そして傷めつけたあとは「もう放っておいても勝手に死ぬ」と判断した。
けれど、瀕死のホッシーナから何かを感じ取ったのだろう。
股間を高く、硬く反り立たせていた
「うそ、そんな……」
脚と脚の間に移動するゴブリンを見て、ホッシーナは死ぬ以上の絶望を感じていた。
このゴブリンに、「雌」と思われている。これから行われるだろうそれは、自分が人間だということを否定されてしまう。いや、ゴブリンからすれば、すでに自分は同じ種族かそれ以下なのだ!
「やめて、おねがい……それ、だけは……」
ホッシーナは処女であったが、さして大事にしているわけではなく、ただタイミングがなかっただけ。こんな別の生物に差し出すわけではない、それなのに――
グイッ
「ひっ!」
当たっている。凶悪な、それが。
まったく潤いのないそこを、ぐいぐいと押してきている。針を刺すような痛みと未知への体験の恐怖と絶望に、ホッシーナは気が狂いそうになっていた。
グイッ、グイッ
「ダメ、ぜったい……いやだ、いやです! やめ――」
必死に身体を揺らし抵抗するが、ゴブリンを大きく開いた両脚をつかんでそれを封じる。
残酷な現実が訪れた。
ぶちんっ
「――――――――!」
【ホッシーナは非処女になりました】
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 狩場の屋上 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
タイムトラベル以外に「平行世界を移動できる」という、どこぞの大統領のような能力を持っているホッシーナにとって、この世界はまだマトモなほうだった
移動した世界がとっくに壊滅していて、残された人類が自分と自我を失った超能力者だけ――というのが、これまで渡り歩いてきた中でぶっちぎりに最低な世界。そんなホッシーナからすれば『目が覚めると見知らぬ塔の屋上』は、「少々インパクトに欠けるスタート地点ですね」と軽口を叩けるほど平和である。
(それにしても、どうして私はこんな格好を……)
ホッシーナは服を着ていなかった。ただ全裸というわけでもなく、なぜか水着を着ていたのだ。しかもビキニなので肌の露出が多く、メリハリのついた体型にコンプレックスを持っているホッシーナからすれば、それは野外露出にも等しい。
生地が白色というところだけが、かろうじて救いだった。これで黒色だったらもはや痴女でしかない。
(まあ誰も見ていませんので、別にいいのですが――)
ぐるりと周囲を確認したとき、それを見つけてしまった。
数メートル先に設置された『ある物』。さすがのホッシーナも驚いてしまった。
固定式の砲台。仕組みはわからなかったが、チキチキチキという音が聞こえることから次の瞬間にでも発射されるのだろう。
何が発射されるのだろう。ホッシーナが予想するよりも早く、それは発射された。
ヒュンと風を切って飛び出した、矢。いかにも砲弾を発射しそうなこの砲台は意外に原始的らしく、先ほどのチキチキチキという音は内部で弦が引かれている音だったらしい。
「どんな構造になっているんでしょうか、あの砲台」
砲台をちらりと見て、次に矢に注目する。
「あらあら、この矢じり、すごく鋭いじゃあないですか。こんなの当たったら死んじゃいますよ」
まるでカタツムリが進む速度で宙に浮く矢を、ホッシーナは軽く撫でたあとにポキリとへし折った。
人は死ぬ間際に一生の記憶が一瞬で再生されるらしい。それは走馬灯という現象であるが、ホッシーナはそれを見たわけではない。
時間加速。タイムトラベラーの能力を使用し、自分の時間を数倍に加速することで本来流れている時間を引き伸ばした――わかりやすく言えば、超高速で動いたのだ。
砲台からの直線上から外れ、時間加速を解除する。すると気だるい疲労が全身に降りかかり、クラリと立ちくらみを起こした。
(これさえなければ、最高の能力なのですが……)
タイムトラベルは使用者に大きな負担を与える。ホッシーナはこれを代償と割り切っていたが、この世界では少しわけが違う。ホッシーナは今までどおり『疲労』と思っていたが、正しくは『身体能力の低下』だった。
運動能力と五感、思考能力が減少し、一度失ったそれは巻き戻るまで回復することはない。もちろん今のホッシーナはそのことに気づくはずがない。
(今さらウダウダと文句を言うつもりはありませんが……)
カチカチカチ
(どうして、次から次へと!)
どういうカラクリになっているのか、足元の石畳の1つが横にスライドし、丸い筒が現れた。
その筒からは、ゴポゴポと何かの液体が沸き出していた。ホッシーナはその液体の正体を知るはずもないが、ただ、ガソリンのような異臭がしていることにはすぐ気づいた。
(これは……! 時間、停止!)
周囲が白黒になる――なんてことは当然ないが、異臭がしない。まるで最初からなかったように、異臭は消えていた。
ふらふらと不安定な足取りでその場から、用心して十数メートルほど離れる。
――ドォン!
時間停止を解除すると、足元に筒があったところから巨大な火柱が生まれ、爆音、爆風と共に周辺を吹き飛ばした。
予想以上の爆発と身体能力の低下に、ホッシーナは立っていられなくなり座り込んでしまう。キンキンと耳鳴りがしていた。火柱の熱がちりちりと顔を焼き、吹き飛ばされた石畳の破片が小雨のように降りかかる。
(まるで狙い澄ましたようなトラップの配置……ここまで悪意を感じる世界は初めてですね……)
時間加速に続き、間を置かずに時間停止。身体能力低下も著しく、もはや立つことさえままならない。
ホッシーナはこれを疲労と思い込んでいるため、少し休めば大丈夫だろうと気楽に考えていた。
(ただ、それまでに何もなければいいのですが……ん?)
しばらく休もうと這うように横になったとき、手を伸ばせば届くところに宝箱が置いてあることに気づいた。
ロールプレイングゲームなどでよく見かける、手に収まるほどの宝箱。だが、ホッシーナの表情は硬い。
(こんなのありましたっけ……?
この流れからすると、どうせトラップに違いありません。透視が使えればいいのですが、あいにく私は時間操作しか――)
パカッ
宝箱は勝手に開いた。
赤や青などの多くの配線に、なんとなくその正体の予想がついてしまう数本の黒い筒。そしてデジタル式の時計が、残り5秒からカウントダウンを始めていた。
(ああ、なんてひどい……)
4、
3、
2、
1、
――爆発。
先ほどの爆発と比べると小規模ではあったが、人一人を吹き飛ばすには十分すぎた。
(……私じゃなかったら、死んでましたね)
ホッシーナは爆発による怪我や焦げが一つもなく、何事もなかったようにそこに寝転がっていた。
時間加速、停止をしたところで動くことができない。なので、カウントダウンに合わせて数秒、『未来に飛んだ』。
爆発する直前から爆発後の時間、その場にホッシーナはいなかった。タイムトラベルでその瞬間だけ跳躍し、九死に一生を得たのだ。
けれど代償も大きかった。動くこともできず、大の字に寝転がって呼吸するのが精一杯であった。
(それにしても……)
ホッシーナは休みながらも、ここまでのトラップを思い出していた。
固定式の砲台。
埋込型の大型爆弾。
宝箱型の小型爆弾。
用意周到に設置されていたと思った。が、よくよく考えると妙だ。どうも詰めが甘いように感じられた。1つ1つの起動の間にタイムラグがあり、その結果能力を使って逃げることができた。
もっと良い配置ができたのでは? または、もっと効果的なトラップがあったのでは? 詰将棋のように追い込んで殺すぐらい、この塔の悪趣味さなら可能ではないのだろうか。
これは、まるで――
(私が能力を使うよう、仕組まれていたような……)
それは思いつく限りで最悪な想像。なぜなら「この塔を管理している者は、自分がここに来ることを知っていて、それを前提にトラップを設置している」ということだからだ。
(……成るように成るだけですね)
これまでに死を覚悟したことはなかったわけでもない。そんなとき、ホッシーナは運に委ねることにしていた。
体力が戻るまでにトラップ等が起動してしまったら、それまで。そうでなければ見苦しくても生きてみよう。ホッシーナは空を見ながら考えた。
(でも、わざわざ殺さずに追い詰めたとして、何の意味があるんだろう)
その疑問の答えはすぐわかることになった。
太陽の光が眩しくて細めていた視界に、影が覆った。
ゆっくりと首をひねると、そこには腰にボロ布をまとい、手には大きな棍棒を持った緑色の人でない生物。
(ゲームとかでは定番の……ゴブリン、のようですね……)
運がなかった。潔く諦め、目を閉じた。
どうせ死ぬなら一瞬で、なるべく痛みを感じないように死にたい。全身の力を抜き、呼吸を落ち着かせ、そのときを待った。
が、そのときが来ない。しばらく待ってはみたものの遅すぎる。
首に力を入れて頭を持ち上げ、目を開いた。
ゴブリンはホッシーナの足元にしゃがみ込んで、すんすんと鼻で呼吸をしていた。
嗅いでいる。この醜い異形が――――の臭いを、嗅いでいる! ホッシーナの怒りの沸点は一瞬で振り切った。
「何を、しているんですかっ!」
「ギャァッ」
抵抗しようと動かした脚が思っていた以上に動き、ゴブリンの顔を蹴り抜いた。当たりどころが良かったのか、軽い音と共にゴブリンは石畳に飛ばされ、ゴロゴロと転がった。
(しまった、こういう単細胞な生物は変に刺激したら……!)
極めて的確な見解だった。起き上がったゴブリンはとても言語化できそうにない唸り声を発し、威嚇のために大きく開いた口からは鼻が曲がりそうな異臭がする唾液を垂れ流している。
そして手に持った棍棒を高く振り上げながら、近づいてきた。
「ごめ、ごめんなさい! わざとじゃないんです、でもあなただって悪いんですよ、あんな――」
――ゴッ! ぼきンッ
「イ゛!」
言い訳なんて通じるはずがない。ゴブリンはホッシーナの脚に棍棒を振り下ろた。鈍い音が響き、折れる音。
ホッシーナは次に叫ぶための空気を思いっきり吸い込んでいた。
「イギャアアアアアアッ! あし、あジがぁぁぁぁぁ!!!!!!」
喉が枯れるほどの悲鳴。目尻に溜まることなく涙がこぼれ、叫んだ拍子に口内を切ってしまったのか、血と唾液を吐き出しゴブリンに浴びせていた。
「ギャ、ギャギャギャ!」
――メギッ! ばきっ!
「グギャ、がっ! アガっ! ああああ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛っ!」
右脚の次は、左肩。その次は左腕。
そこから先は、めちゃくちゃにホッシーナを殴りつけた。
殴られた場所は赤く、青く、不気味なほどに黒い紫へと変色していく。
ゴブリンの手が止まるころ、ホッシーナはあまりに無残な姿になっていた。元々生地の少ない水着は破れ全裸状態、本来曲がるはずがない方向に腕が曲がり、顔は涙や唾液やらでぐちゃぐちゃに汚れていた。
ゴブリンは棍棒を投げ捨て、ホッシーナにのしかかった。体臭、唾液の悪臭から顔を背けようにも、ホッシーナはそれすらできないほどに瀕死だった。
(早く殺して……もう、苦しいの、嫌だ……)
生への諦めは、死の懇願への変わっていた。だが舌を噛み切るほどの勇気はなく、結局最期の一撃はゴブリン頼みだった。
しかし、ゴブリンはその願いを叶える気は少しもないようだった。
ゴブリンはホッシーナのことを「外敵」と見なしていた。そして傷めつけたあとは「もう放っておいても勝手に死ぬ」と判断した。
けれど、瀕死のホッシーナから何かを感じ取ったのだろう。
股間を高く、硬く反り立たせていた
「うそ、そんな……」
脚と脚の間に移動するゴブリンを見て、ホッシーナは死ぬ以上の絶望を感じていた。
このゴブリンに、「雌」と思われている。これから行われるだろうそれは、自分が人間だということを否定されてしまう。いや、ゴブリンからすれば、すでに自分は同じ種族かそれ以下なのだ!
「やめて、おねがい……それ、だけは……」
ホッシーナは処女であったが、さして大事にしているわけではなく、ただタイミングがなかっただけ。こんな別の生物に差し出すわけではない、それなのに――
グイッ
「ひっ!」
当たっている。凶悪な、それが。
まったく潤いのないそこを、ぐいぐいと押してきている。針を刺すような痛みと未知への体験の恐怖と絶望に、ホッシーナは気が狂いそうになっていた。
グイッ、グイッ
「ダメ、ぜったい……いやだ、いやです! やめ――」
必死に身体を揺らし抵抗するが、ゴブリンを大きく開いた両脚をつかんでそれを封じる。
残酷な現実が訪れた。
ぶちんっ
「――――――――!」
【ホッシーナは非処女になりました】

事切れたように、ホッシーナの動きは止まった。受け入れがたい現実に、思考が停止してしまったのだ。
「グギャ、ギャギャギャギャギャ」
ゴブリンは己の性欲を満たすためだけに、腰を打ちつけた。乱暴に扱われるホッシーナのそこから、明らかに破瓜とは違う血が流れ出ていた。
他を弄ぶ余裕が出てきたのだろう、ゴブリンはホッシーナの豊満な乳房を力いっぱい鷲掴みにした。伸び過ぎた爪が食い込み、じわりと血がにじみ始めた。
(もう、やだ……誰か、助けて……)
抵抗することで逆鱗に触れ、殺してもらおうとした。だが散々痛みつけられた身体はもう動かない。ただただ蹂躙を受け入れるしかなかった。
「ギャ、ギャ! ギャ! ギャギャ!」
大きく声を上げ、ゴブリンは動きを止めた。
ドクンドクンと、体内でゴブリンのそれを脈打っている。ホッシーナはそれが意味するところを知っている。
(出された……こんな、こんなモンスターに……)
人間ではなくなってしまった。こんなモンスターと同格になってしまった。ホッシーナは処女を散らされたことよりも、行為そのものに悲しみを抱いた。
ゴブリンは血や体液で汚れたそれを引き抜いて、転がっていた棍棒を拾った。
そして、ホッシーナの頭を狙うように振り上げた。
(あっ、やっと死)
グチャンッ!
棍棒はホッシーナの顔を粉砕した。
【ゲームオーバー】
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 大賢者“ナツメ”と使い魔“アカネ” X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ホッシーナがゴブリンに強姦、撲殺されていたころ――
大賢者“ナツメ”は使い魔“アカネ”に押し倒されていた。
順を追って説明すると、ナツメとアカネの2人はホッシーナよりも早く塔に招かれていた。
ナツメはすぐに、この塔の主が救世主ということに気づいた。自分が呼び出した救世主とはまた別の存在だったが、こうして巻き込まれている以上文句の一つでも言ってやらないと気が済まなかった。なので救世主に小言を言うためだけ2人は探索(アカネはずっと嫌がっていたが、ナツメは無理やり引っ張って)を始めた。
大賢者“ナツメ”。
彼女を一言で表すとしたら『全知全能』、これに尽きる。別の世界軸から同一人物を召喚することができるほど知と才を兼ね備えた稀代の賢者なのだ。
ただ典型的な魔法使いのステータスゆえ肉弾戦は苦手としていたが、そもそも近づく間もなく魔法で殲滅させることができるため、実質弱点は存在しない。
ただ1つ、ボーイッシュな外見(胸とか腰とかが少々残念)だけが彼女の不満な点であったが、塔の探索にはまったく影響はない(それにそういった需要も確実に存在する。別に気にすることではない)。
使い魔“アカネ”。
彼女は無能なサキュバスである。ただ名誉のために言っておくと、サキュバスとしての能力が無能(女性なら誰もが羨むだろうスタイルなのだが、処女。なぜなら異性に興味がないからだ。同性はもっと興味がない。興味があるのは男性同士の耽美な官能シーンだけ)であり、それ以外(家事手伝いや戦闘面)は極めて優秀なのだ。
何か特技があるわけでもなく、素手ゴロのパワーファイターとしてナツメを護衛するのが今の役目であった。
能力、スタイルがまったく逆の2人は相性が良く、何ら苦労することなく塔を降りて行った。
階段を降りるにつれ、ひしひしと感じられる救世主の気配。だが、ナツメはこの塔の救世主がその昔自分が呼び出した救世主と比べ、遥かに格下だということを感じ取っていた。
そもそも塔の探索も、2人にしてみれば子供向けのアトラクションの延長程度。注意力は散漫し、慢心が生まれ始めていた。
「アカネ、この塔出たら何かおいしいもの食べよう」
「いいですね、カレーとか食べたいです」
こんな散歩気分なまま探索が続いていたとき、2人は、本来存在してはいけない“彼”から、あってはならない介入を受けた。
『使い魔“アカネ”、サキュバスとして覚醒しろ』
ナツメは、はっきりとその声を聞いた。あまりに鮮明な声だったので背後に誰かがいる、そう錯覚さえしてしまった。
ナツメは魔力を撒き散らし、ソナーの要領で周囲を警戒した。だが、人どころか鼠一匹、それに引っかかることはなかった。
「もしかしたら聞き間違いか?」ともナツメは考えたが、それにしては妙に存在感のある声だった。まるで“神様に命令する”かのような、不思議な力が感じられた。
「アカネ、変わりはない?」
「はい、特に何も」
「本当に?」
「ほ、本当ですよ~」
念のため注意深く反応をうかがってみたが、本人が言っているように何も問題なさそうに見えた。
そんなとき、ふと、アカネに目が止まった。
アカネは自身の希望でやや大きめのローブを着込んでいた。自分の体型、特に胸が目立たないようにするためと聞いていたが、アカネのずぼらな性格もあり、すっかり着崩れてインナーが丸見え。その結果、胸がこぼれてしまっていた。
(……なぜ凝視しているんだ、私は)
普段なら気にも留めない、もはや見慣れてしまっているアカネの身体(そういう意味ではなくて。日常の風景的な意味で)。今さらまじまじと見てしまったことに違和感を覚えた。
「(まあいいか。そんなときもあるのかな)なら行こう。飽きてきたから、ちょっと急ぐよ」
「は、はいっ」
すたすたと歩き始めるナツメ、それを追うアカネ。これは普段どおりの立ち位置だったが、ここでアカネは思いも寄らない行動に出る。
「……アカネ?」
先に行くナツメを、アカネは背後から抱き締めた。身長差があるため、ナツメはアカネの腕の中にすっぽりと埋まった。
こういったスキンシップはめずらしいことではない。ナツメはたびたびアカネに抱き締められていたが、こんな空気を読まないタイミングは初めてだった。
「こらアカネ、今はそんなときじゃないだろう?」
子供を躾けるように言ってみるものの、変わりはない。
(なぜだろう……変な、気分だ)
抱きつかれることには慣れている。それなのに、頭に当たる柔らかな感触がいつにも増して気持ちがいい。それにとても良い香りがしていた。甘ったるい、花の蜜ような匂い。
(あ、イケナイ……これ以上は、マズい)
ナツメはふつふつと興奮し始めていることに気づいた。大賢者とはいえ一人の女、性的に催すことぐらいはある。ただほんのちょっと火がつきやすく、理性が飛びやすい、そんな自分の欠点をナツメはしっかりと知っていた。
「アカネ、早く離すんだ」
「ナツメさん」
「いい加減にしないと怒るよ?」
「ナツメさん」
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 大賢者“ナツメ”と使い魔“アカネ” X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ホッシーナがゴブリンに強姦、撲殺されていたころ――
大賢者“ナツメ”は使い魔“アカネ”に押し倒されていた。
順を追って説明すると、ナツメとアカネの2人はホッシーナよりも早く塔に招かれていた。
ナツメはすぐに、この塔の主が救世主ということに気づいた。自分が呼び出した救世主とはまた別の存在だったが、こうして巻き込まれている以上文句の一つでも言ってやらないと気が済まなかった。なので救世主に小言を言うためだけ2人は探索(アカネはずっと嫌がっていたが、ナツメは無理やり引っ張って)を始めた。
大賢者“ナツメ”。
彼女を一言で表すとしたら『全知全能』、これに尽きる。別の世界軸から同一人物を召喚することができるほど知と才を兼ね備えた稀代の賢者なのだ。
ただ典型的な魔法使いのステータスゆえ肉弾戦は苦手としていたが、そもそも近づく間もなく魔法で殲滅させることができるため、実質弱点は存在しない。
ただ1つ、ボーイッシュな外見(胸とか腰とかが少々残念)だけが彼女の不満な点であったが、塔の探索にはまったく影響はない(それにそういった需要も確実に存在する。別に気にすることではない)。
使い魔“アカネ”。
彼女は無能なサキュバスである。ただ名誉のために言っておくと、サキュバスとしての能力が無能(女性なら誰もが羨むだろうスタイルなのだが、処女。なぜなら異性に興味がないからだ。同性はもっと興味がない。興味があるのは男性同士の耽美な官能シーンだけ)であり、それ以外(家事手伝いや戦闘面)は極めて優秀なのだ。
何か特技があるわけでもなく、素手ゴロのパワーファイターとしてナツメを護衛するのが今の役目であった。
能力、スタイルがまったく逆の2人は相性が良く、何ら苦労することなく塔を降りて行った。
階段を降りるにつれ、ひしひしと感じられる救世主の気配。だが、ナツメはこの塔の救世主がその昔自分が呼び出した救世主と比べ、遥かに格下だということを感じ取っていた。
そもそも塔の探索も、2人にしてみれば子供向けのアトラクションの延長程度。注意力は散漫し、慢心が生まれ始めていた。
「アカネ、この塔出たら何かおいしいもの食べよう」
「いいですね、カレーとか食べたいです」
こんな散歩気分なまま探索が続いていたとき、2人は、本来存在してはいけない“彼”から、あってはならない介入を受けた。
『使い魔“アカネ”、サキュバスとして覚醒しろ』
ナツメは、はっきりとその声を聞いた。あまりに鮮明な声だったので背後に誰かがいる、そう錯覚さえしてしまった。
ナツメは魔力を撒き散らし、ソナーの要領で周囲を警戒した。だが、人どころか鼠一匹、それに引っかかることはなかった。
「もしかしたら聞き間違いか?」ともナツメは考えたが、それにしては妙に存在感のある声だった。まるで“神様に命令する”かのような、不思議な力が感じられた。
「アカネ、変わりはない?」
「はい、特に何も」
「本当に?」
「ほ、本当ですよ~」
念のため注意深く反応をうかがってみたが、本人が言っているように何も問題なさそうに見えた。
そんなとき、ふと、アカネに目が止まった。
アカネは自身の希望でやや大きめのローブを着込んでいた。自分の体型、特に胸が目立たないようにするためと聞いていたが、アカネのずぼらな性格もあり、すっかり着崩れてインナーが丸見え。その結果、胸がこぼれてしまっていた。
(……なぜ凝視しているんだ、私は)
普段なら気にも留めない、もはや見慣れてしまっているアカネの身体(そういう意味ではなくて。日常の風景的な意味で)。今さらまじまじと見てしまったことに違和感を覚えた。
「(まあいいか。そんなときもあるのかな)なら行こう。飽きてきたから、ちょっと急ぐよ」
「は、はいっ」
すたすたと歩き始めるナツメ、それを追うアカネ。これは普段どおりの立ち位置だったが、ここでアカネは思いも寄らない行動に出る。
「……アカネ?」
先に行くナツメを、アカネは背後から抱き締めた。身長差があるため、ナツメはアカネの腕の中にすっぽりと埋まった。
こういったスキンシップはめずらしいことではない。ナツメはたびたびアカネに抱き締められていたが、こんな空気を読まないタイミングは初めてだった。
「こらアカネ、今はそんなときじゃないだろう?」
子供を躾けるように言ってみるものの、変わりはない。
(なぜだろう……変な、気分だ)
抱きつかれることには慣れている。それなのに、頭に当たる柔らかな感触がいつにも増して気持ちがいい。それにとても良い香りがしていた。甘ったるい、花の蜜ような匂い。
(あ、イケナイ……これ以上は、マズい)
ナツメはふつふつと興奮し始めていることに気づいた。大賢者とはいえ一人の女、性的に催すことぐらいはある。ただほんのちょっと火がつきやすく、理性が飛びやすい、そんな自分の欠点をナツメはしっかりと知っていた。
「アカネ、早く離すんだ」
「ナツメさん」
「いい加減にしないと怒るよ?」
「ナツメさん」

「掌握(サキュバス式拘束術)」
「え……?」
アカネが放ったそれはナツメから自由を奪った。口は動く、思考は回る、それなのに首から下の神経が途絶えてしまったように、身体は言うことを聞いてくれない。
「これ、どうですか? 睡眠(サキュバス式子守唄)でも良かったのですが、やっぱり意識がはっきりしている相手をどうこうする、というのが燃えますよね。反応がないなんて人形を相手にしているのと変わりませんからね。その点、掌握(サキュバス式拘束術)は最高です。何しろ嫌がる表情、拒絶する声を堪能することができるんですから」
「何を言っている……?」
「つまり、こういうことですよ」
後ろにいたアカネが、ナツメの前に回り込んだ。
「今から、ナツメさんをレイプします」
そのアカネのことを、ナツメは知らなかった。ナツメとアカネの付き合いは長い、それなのに初めて見るアカネがそこにいた。
妖艶。まさにその一言。仕草や雰囲気が妙にネットリとしていて絡みついてくる。見慣れたスタイルのはずなのにゴクリと生唾を飲んでしまった。
それ以上に瞳。ピンクに染まり、潤った瞳はゆらゆらと揺れている。
「アカネ、お前……」
「そうなると、私の処女はナツメさんに捧げることになりますね。よろしくお願いします~」
「よろしくしない! さてはあの声だな……!」
「まあまあ、何だっていいじゃないですか」
今度は前から抱き締めた。顔と顔がぶつかりそうになるほど近づく。もちろんナツメは掌握(サキュバス式拘束術)によって動けない。
アカネの吐息がナツメの顔を撫でた。ぺたり、ぺたりと温かなアカネの指、手のひらが這いまわる。
ナツメは、嫌な気分はしなかった。それどころか――
「ドキドキします?」
「そん、そんなこと……」
「無理しなくてもいいですよ。今の私は勝手に魅了(サキュバス式チャーム)が発動しているんですよ」
「なんだそれは……」
「言ってしまえば催淫アロマみたいなものですね。そこらのバニーとは比較にならないほど濃いものですが。
ですのでナツメさん、ムラムラしちゃうのは自然なのですよ」
「自然……?」
「そうですよー。だから、素直になってもいいんですよー」
アカネはナツメの目を覗きこんだ。ナツメは目を逸らせない。そのピンクに光る瞳に吸い込まれてしまう。
素直になってもいい。素直になればいい。ナツメの理性は瓦解していく。
ぼぅっとするナツメに、アカネはニタリと笑う。そしてローブ、インナーを脱ぎ、床に投げ捨てた。黒いレースのキャミソールとショーツだけになったアカネは、投げ捨てた衣服の上にナツメを押し倒した。
ここで話は冒頭に繋がる。
「さてナツメさん。私はあなたの使い魔です、どんな命令にでも従いましょう」
「どんな、命令も?」
「ええ、なんなりと。やめろと言われればやめます、死ねと言われれば死にましょう。
さあ、言ってください。
ナツメさんが、
今、
一番、
私にさせたいことを」
「して、ほしい」
ナツメは間髪入れず言った。
それは命令ではなく、懇願だった。
「ナツメさん、それだけじゃあわかりません。
私は、あなたを、どうすればいいんです?」
「めちゃくちゃに、して」
「めちゃくちゃ、と言いますと?」
「ひどいこと、されたいの。いっぱい叩かれて、嫌なことを言われて、傷つきたいのっ。
いっぱい、いっぱい! 苛めて、ほしい!」
やけになったように吠えるナツメ。アカネはそれを、冷たく見つめる。
「腕を叩かれて気持ち良さそうにしていたので、もしかしたらと思っていましたが……やっぱりマゾだったんですね」
アカネは服の上から、ナツメの慎ましい膨らみを鷲掴みにした。ギリギリと力をこめていくたびに、ナツメの表情は歓喜に満ちていく。
「マゾの人を苛める趣味はありませんが、これは命令ですからね。しっかりたっぷり、堕としてあげますよ」
アカネはナツメに顔を寄せる。ナツメは自然と目を閉じた。
小さく口を開き、アカネは頬張るようにナツメの唇を奪った。
「んっ、んん……」
もごもごとナツメの口内で暴れるアカネの舌。それはとても乱暴な動きだったが、ナツメにはそれが心地良いものだった。
「ん……ンンッ!」
突然、ナツメは苦痛に顔を歪める。冷たく笑いながらアカネが離れると、つうぅっと、唾液に混じって赤い液体がこぼれ落ちた。
「ごめんなさい。ナツメさんの舌、とっても柔らかかったので噛んじゃいました。
痛かったですか? もうやめたほうがいいですか?」
返ってくる答えはわかりきっている。アカネはあえて、ナツメ自身に理解させるように問う。
ナツメはアカネの予想通りに、首を振った。涙を浮かべながらも、笑顔を作っていた。
その様子に、アカネは満足して微笑む。
「ふふ……いらっしゃい、こちら側の世界へ」
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 大賢者“ナツメ” ―> サキュバス“ナツメ” X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 成り立てサキュバスの領域 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「……うぅ」
ホッシーナが目を覚ましたとき、天井が見えた。
先ほどまで屋上にいたはずなのに……と、薄ぼんやりとした記憶を掘り起こす。
たしかに自分は屋上にいた。が、『屋上にいた』という記憶しかなくて、そこで起こった出来事については何も覚えていなかった。
あいかわらずこっ恥ずかしい水着を着ている。もちろん怪我はない――が。
「いたっ……」
立って歩こうとすると、途端に下半身に痛みが走る。いや下半身ではない、これはもっと別のところ。まるで両側から皮膚を引っ張られるような、裂けてしまいそうな痛み。
しかしホッシーナは屋上での記憶が何一つない。なのであの惨劇を覚えていない。それが幸か不幸かはわからないが。
止まっていても始まらない。ホッシーナは内股気味に探索を始めた。
・
・
・
・
・
ホッシーナは自分の『時間操作』について考えた。
どうやら使用したあとの気だるさは『疲労』ではないらしい。どれだけ休んでも回復することはなかった。
おそらく回復しない何か――そう、言ってしまえば『身体能力の低下あるいは喪失』なのだろう。
となると、乱用するわけにはいかない。『時間操作』は最後の手段として、自力で解決できる困難には立ち向かわなければならない。
けれど「まだ大丈夫」と思って能力の使用を渋った結果、どうなってしまうのか。
「あ、あ゛ー……」
ホッシーナは腹に突き刺さった鉄の棒にうつろな目を向けていた。どくどくと溢れる血は棒を伝い、ぼたぼたと床に落ちて溜まっていく。
このフロアもトラップが多く存在した。特に握りこぶし大の投石がびゅんびゅんと飛び交い、最初は運動神経だけで避けていたが次第に疲労が溜り、動きに鈍くなったホッシーナに容赦なく石は襲いかかった。
頭からは流血し、身体中に擦り傷と青あざだらけ。もはや時間を停止させても逃げることが困難な状態。そんなホッシーナを、鉄の棒がどこからか発射され貫いた。
もっと早くに能力を使っていれば。ホッシーナはそう思いながら息絶えた。
・
・
・
・
・
また目が覚めると天井が見えた。
記憶を整理すると、ここは屋上から2つ下のフロア。そして、先ほどのフロアの記憶がない。
妙にお腹が痛い。これは腹痛というよりは、何か物理的な、まるで前から後ろを貫くような痛みだった。
(まったくもう、何が何やら)
どうやらこの世界は勝手が違うらしく、ホッシーナは不自由さを感じていた。能力の使用制限もあるが、『塔からの脱出(もしかしたら塔内に探している超能力者がいるかもしれないが)』が目的になっている節がある。
まるで得体の知れない何かに遊ばれているような――
「あれ? キミもここに迷い込んだ人?」
――と考えていると、すぐ目の前に人がいた。
この塔では少々場違いな、ピシっと正装(まるでハスラーのような格好)をしている、人。ベストをきっちりと着こなした、隙のない姿。けれど性別がわからなかった。胸の膨らみはほとんどない、背はやや低めだがどちらでもあっても不自然ではない。
声の感じからすれば女性だろうか。中性的だがどこかツヤが感じられた。
「……あなたは?」
「キミと同じ境遇をたどる者だよ、水着のお嬢さん」
「…………っ!」
「ハハハ、怒らないでほしいな。同性じゃないか。
私は名前はナツメ。よろしくね」
どうやら同性らしいが、それでも肌を晒すのが恥ずかしかった。
べたべたと、舐めるような視線を感じる。ホッシーナは思わず、腕を組んで身を守ろうとした。
「ははは、ごめんごめん。どうせその様子なら苦労しているんじゃない? だったらさ、お互い協力しようよ」
「…………」
「悪くない話だろう?」
たしかにデメリットはない(と思われる)。けれど、言いようのない不安があった。
目の前の(男性のように見える)女性。どう見ても人間なのだが、人間ではないような気がした。
もちろん“なんとなく”の範疇であったが、ホッシーナはその“なんとなく”を信じるようにしていた。
なので、ここでの返事はたった1つ。
「ごめんなさい。無理です」
「そっか。残念」
意外にもあっさりと引き下がった。ホッシーナは安堵に胸を撫で下ろそうとして――
「じゃあ、力づくだな」
身構えるよりも、能力を使用するよりも早く、その女はホッシーナの首を締め上げ、頭を床に叩きつけていた。
脳が揺れ、目の前が暗転し、意識が飛びかかってしまう。そんな状態で、首を締めつける相手と目が合った。
あっという間に叩き伏せられていた。
「乱暴してごめんね。だってこうでもしないと、逃げちゃうでしょ?」
「ぐ、ウグッ」
「あんまり抵抗されるのも面倒だし、ちょっとイタズラさせてもらうね」
「魔眼(サキュバス式イビルアイ)」
ギラリと目が光ったように見えた。その瞬間、身体中に電流が走ったように痺れた、ホッシーナはそう感じた。
が、そんな生易しいものではなかった。
手が勝手に上に伸び、ナツメを抱き締めようとした。
「ふふふ、熱烈だね」
「そんな、これは違っ」
「うん、知ってる。魔眼(サキュバス式イビルアイ)は、相手を好き勝手に操ることができる。ただ至近距離で目を合わせなくちゃダメなんだけど……キミも、満更じゃなかったのかな?」
否定しようにも口が動かない。腕はナツメの背中に回り、ぎゅっと抱き締めてしまう。
身体と身体が密着する。ナツメの体温が服越しから肌に伝わってくる。魅了(サキュバス式チャーム)がかけられているわけでもないので性的な興奮はなかったが、ドキドキと胸が高鳴ってしまう。
「感じるよ、キミの鼓動。どきどきしているね」
「離しなさい、今なら、許してあげるから」
「まだ自分の立場をわかっていないようだね。私の意思一つで死んじゃうんだよ?」
「ぐっ……」
「冗談だよ。そんなことするわけないじゃない。
……私はね、もう我慢できそうにないの」
そう言ってするすると服を脱ぎ捨てたナツメの股、下半身は、滴るほどに濡れていた。
ナツメの匂いが周囲に充満した。
「アカネにも散々遊んでもらったけど、ぜんぜん足りないんだ。キミの名前、教えてくれる?」
「斉藤、星奈(言いたくないのに……! 口が勝手に……!)」
「ふぅん、星奈さん、か。それじゃあ星奈さん、これからキミに、素敵な体験をさせてあげよう」
ナツメはホッシーナにとってショーツの代わりの水着を引き裂いた。
あらわになったそこに、そっと手をかざす。
「擬態 (サキュバス式極悪トランスフォーム)」
「あ、あっ、ああああああああっ!?」
まるで木が育つように、ホッシーナから男性特有のそれが生えた。
それは丸太を思わせるように太く、びくん、びくんと脈打っていた。
「なにこれ、何これ、何これっ!?」
「ナニって、見たことぐらいあるだろう、非処女に匂いがするぐらいだし。
女性が男性の悦びを知ることができる、素敵な魔法だよ」
両手で覆うように、太い竿に触れた。その瞬間、
「あ、あっあっあっ、アッ!」
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 成り立てサキュバスの領域 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「……うぅ」
ホッシーナが目を覚ましたとき、天井が見えた。
先ほどまで屋上にいたはずなのに……と、薄ぼんやりとした記憶を掘り起こす。
たしかに自分は屋上にいた。が、『屋上にいた』という記憶しかなくて、そこで起こった出来事については何も覚えていなかった。
あいかわらずこっ恥ずかしい水着を着ている。もちろん怪我はない――が。
「いたっ……」
立って歩こうとすると、途端に下半身に痛みが走る。いや下半身ではない、これはもっと別のところ。まるで両側から皮膚を引っ張られるような、裂けてしまいそうな痛み。
しかしホッシーナは屋上での記憶が何一つない。なのであの惨劇を覚えていない。それが幸か不幸かはわからないが。
止まっていても始まらない。ホッシーナは内股気味に探索を始めた。
・
・
・
・
・
ホッシーナは自分の『時間操作』について考えた。
どうやら使用したあとの気だるさは『疲労』ではないらしい。どれだけ休んでも回復することはなかった。
おそらく回復しない何か――そう、言ってしまえば『身体能力の低下あるいは喪失』なのだろう。
となると、乱用するわけにはいかない。『時間操作』は最後の手段として、自力で解決できる困難には立ち向かわなければならない。
けれど「まだ大丈夫」と思って能力の使用を渋った結果、どうなってしまうのか。
「あ、あ゛ー……」
ホッシーナは腹に突き刺さった鉄の棒にうつろな目を向けていた。どくどくと溢れる血は棒を伝い、ぼたぼたと床に落ちて溜まっていく。
このフロアもトラップが多く存在した。特に握りこぶし大の投石がびゅんびゅんと飛び交い、最初は運動神経だけで避けていたが次第に疲労が溜り、動きに鈍くなったホッシーナに容赦なく石は襲いかかった。
頭からは流血し、身体中に擦り傷と青あざだらけ。もはや時間を停止させても逃げることが困難な状態。そんなホッシーナを、鉄の棒がどこからか発射され貫いた。
もっと早くに能力を使っていれば。ホッシーナはそう思いながら息絶えた。
・
・
・
・
・
また目が覚めると天井が見えた。
記憶を整理すると、ここは屋上から2つ下のフロア。そして、先ほどのフロアの記憶がない。
妙にお腹が痛い。これは腹痛というよりは、何か物理的な、まるで前から後ろを貫くような痛みだった。
(まったくもう、何が何やら)
どうやらこの世界は勝手が違うらしく、ホッシーナは不自由さを感じていた。能力の使用制限もあるが、『塔からの脱出(もしかしたら塔内に探している超能力者がいるかもしれないが)』が目的になっている節がある。
まるで得体の知れない何かに遊ばれているような――
「あれ? キミもここに迷い込んだ人?」
――と考えていると、すぐ目の前に人がいた。
この塔では少々場違いな、ピシっと正装(まるでハスラーのような格好)をしている、人。ベストをきっちりと着こなした、隙のない姿。けれど性別がわからなかった。胸の膨らみはほとんどない、背はやや低めだがどちらでもあっても不自然ではない。
声の感じからすれば女性だろうか。中性的だがどこかツヤが感じられた。
「……あなたは?」
「キミと同じ境遇をたどる者だよ、水着のお嬢さん」
「…………っ!」
「ハハハ、怒らないでほしいな。同性じゃないか。
私は名前はナツメ。よろしくね」
どうやら同性らしいが、それでも肌を晒すのが恥ずかしかった。
べたべたと、舐めるような視線を感じる。ホッシーナは思わず、腕を組んで身を守ろうとした。
「ははは、ごめんごめん。どうせその様子なら苦労しているんじゃない? だったらさ、お互い協力しようよ」
「…………」
「悪くない話だろう?」
たしかにデメリットはない(と思われる)。けれど、言いようのない不安があった。
目の前の(男性のように見える)女性。どう見ても人間なのだが、人間ではないような気がした。
もちろん“なんとなく”の範疇であったが、ホッシーナはその“なんとなく”を信じるようにしていた。
なので、ここでの返事はたった1つ。
「ごめんなさい。無理です」
「そっか。残念」
意外にもあっさりと引き下がった。ホッシーナは安堵に胸を撫で下ろそうとして――
「じゃあ、力づくだな」
身構えるよりも、能力を使用するよりも早く、その女はホッシーナの首を締め上げ、頭を床に叩きつけていた。
脳が揺れ、目の前が暗転し、意識が飛びかかってしまう。そんな状態で、首を締めつける相手と目が合った。
あっという間に叩き伏せられていた。
「乱暴してごめんね。だってこうでもしないと、逃げちゃうでしょ?」
「ぐ、ウグッ」
「あんまり抵抗されるのも面倒だし、ちょっとイタズラさせてもらうね」
「魔眼(サキュバス式イビルアイ)」
ギラリと目が光ったように見えた。その瞬間、身体中に電流が走ったように痺れた、ホッシーナはそう感じた。
が、そんな生易しいものではなかった。
手が勝手に上に伸び、ナツメを抱き締めようとした。
「ふふふ、熱烈だね」
「そんな、これは違っ」
「うん、知ってる。魔眼(サキュバス式イビルアイ)は、相手を好き勝手に操ることができる。ただ至近距離で目を合わせなくちゃダメなんだけど……キミも、満更じゃなかったのかな?」
否定しようにも口が動かない。腕はナツメの背中に回り、ぎゅっと抱き締めてしまう。
身体と身体が密着する。ナツメの体温が服越しから肌に伝わってくる。魅了(サキュバス式チャーム)がかけられているわけでもないので性的な興奮はなかったが、ドキドキと胸が高鳴ってしまう。
「感じるよ、キミの鼓動。どきどきしているね」
「離しなさい、今なら、許してあげるから」
「まだ自分の立場をわかっていないようだね。私の意思一つで死んじゃうんだよ?」
「ぐっ……」
「冗談だよ。そんなことするわけないじゃない。
……私はね、もう我慢できそうにないの」
そう言ってするすると服を脱ぎ捨てたナツメの股、下半身は、滴るほどに濡れていた。
ナツメの匂いが周囲に充満した。
「アカネにも散々遊んでもらったけど、ぜんぜん足りないんだ。キミの名前、教えてくれる?」
「斉藤、星奈(言いたくないのに……! 口が勝手に……!)」
「ふぅん、星奈さん、か。それじゃあ星奈さん、これからキミに、素敵な体験をさせてあげよう」
ナツメはホッシーナにとってショーツの代わりの水着を引き裂いた。
あらわになったそこに、そっと手をかざす。
「擬態 (サキュバス式極悪トランスフォーム)」
「あ、あっ、ああああああああっ!?」
まるで木が育つように、ホッシーナから男性特有のそれが生えた。
それは丸太を思わせるように太く、びくん、びくんと脈打っていた。
「なにこれ、何これ、何これっ!?」
「ナニって、見たことぐらいあるだろう、非処女に匂いがするぐらいだし。
女性が男性の悦びを知ることができる、素敵な魔法だよ」
両手で覆うように、太い竿に触れた。その瞬間、
「あ、あっあっあっ、アッ!」

まるで火山の噴火のように、黄色がかった粘っこい体液が吹き出し、ナツメに降りかかった。
「わ、すごい量……ねばねばして、とても臭う……それに、この味……すっごく、濃い」
顔や服についた精液を拭い、ぺろりぺろりと舐めとるナツメ。その表情は、とても妖艶だ。
一方ホッシーナは、嫌悪に満ちていた表情とは打って変わって、放心しているようだった。
「星奈、どうだった?」
意地悪そうにナツメは尋ねる。
「ど、どうって……」
「男性のエクスタシー、すごいでしょう? 体内で弾けるようなそれとは違って、外に放出する感覚。病みつきになったんじゃない?」
「そんなこと……」
と言うホッシーナの口調は弱い。ナツメの言うとおり、ホッシーナは男性のエクスタシーとやらに火がついてしまっていた。
「ふふふ、いじらしい顔しちゃって、かわいいなぁ。なあに大丈夫さ、擬態 (サキュバス式極悪トランスフォーム)は1回程度じゃ収まらないよ。
それに、私も愉しみたい。もう、ダメ……興奮してきた」
ナツメの呼吸は荒くなっていた。ホッシーナのことなんてまるで眼中にないようで、そそり立つそれをまたぐように腰を置いた。
「あぁ、ある。すぐ下に、星奈のぶっといペニスが、ある。ねえ、入れていいよね? もう、入れるよ?」
「ダメ、そんなのされたら、私……!」
「無理、無理むり、もう入れるから!」
ずぼりっ。ナツメは勢い良く腰を落とした。
その衝撃に、ホッシーナは耐えれない。
「アッ、ウァッ!」
先ほどと同じか、それ以上に精液を噴出した。ナツメの膣内を満たし、収まりきらずにどくどくと溢れ出した。
「~~~~~~! あぁん、こんなに、出して……お腹いっぱいになっちゃうよ……!」
ぶちゅ、ぶちゅ。上下に動くたび精液が絡む音が響く。
ホッシーナに生えたそれは、2度目の射精のあとでも硬さを失っていない。ホッシーナの表情は快楽に負け、溶け始めていた。
「たったの2回でもう堕ちちゃったのかな? まだまだこれからだよ?
さて、何回遊べるかな……?」
【ゲームオーバー】
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 1階、待ち続ける彼女 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“救世主”はずっと、あの忌々しい超能力者――伊藤月子を待ち続けていた。
裏切られて塔の主に仕立て上げられてから、どれぐらい経ったことだろう。何秒、何分、何時間、何日、何年……途中から数えることをやめてしまったが、“救世主”は一瞬足りとも伊藤月子への恨みを忘れたことはなかった。
あるときから、塔の屋上に人(以降は侵入者と呼ぶことにする)の気配が感じるようになった。
“救世主”の胸は踊った。
姿まではわからなかったが、その中の誰かが伊藤月子かもしれない、そう思うだけで居ても立ってもいられなくなった。
しかし塔の主の制約なのか、1階より上のフロアに行くことができなかった。なので待つことしかできなかった。
“救世主”は何とも歯がゆい思いをしたが、じっと我慢した。
まるで遠距離恋愛中の恋人と久しく会う日のような心地。“救世主”にとってそれは『恋愛感情』ではなく『殺意』ではあったが。
結論から言えば、“救世主”の我慢が報われることはなかった。侵入者が伊藤月子ではなかったからだ。
“救世主”は落胆したまま侵入者を殺し、待ち、殺しては、待ち、殺しては――ずっとこのサイクル繰り返した。
そして、今回も――
“救世主”は2階に通じる階段の前で新たな侵入者を待っていた。
もう何人目かわからない。「どうせ今回も違うに決まっている」と思いながらも、「今回こそは――」とすがるように願っていた。
「よう“救世主”殿。ひさしぶりだなぁ」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “戦士(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
“救世主”の願いはあっさりと砕かれた。そこにいたのは、やけに露出度の高い鎧(ビキニアーマー)を着て、刀身がぬらりと輝く剣を持った“戦士”だった。
その“戦士”は、まるで鏡を見ているように“救世主”と瓜二つだった。その素性が少し気にはなったが、結局は伊藤月子ではない。“救世主”は「またハズレか」とため息をついた。
「ん、今ハズレって言った? おいおい、つれないなぁ。
こっちはあのとき――ゴブリンに……されたときの恨み、溜まってるんだからなぁ!」
剣を片手で振り回し“救世主”を挑発する“戦士”。それとは対照的に“救世主”の気分はどんどんと盛り下がっていく。なにせ、『まったく記憶にない』からだ。
ハズレ相手に余計な労力を割きたくない、これがいつもの本音。けれど今回はちょっと違った。目の前の“戦士”は、剣技だけなら自分より上だったのだ。
魔法などを駆使すれば何ら問題のない相手だが、近距離戦ならこちらが不利……という判断だった。
「……面倒だから、魔法で終わらせることにするわ」
「ははは、いいねぇ。前と同じ戦略ってわけか。悪くないと思うんだけどさぁ……
私が、何の対策をしていないとでも?」
ボンッ!
“戦士”の背後から飛来した火の玉が、魔力を溜めていた“救世主”の右手を焼き焦がした。
炭となった右手はボロボロと、粉末となって床に落ちていく。それは“救世主”にとって、さしたるダメージではない。けれど、この魔法の使用者だけが気がかりだった。
間違いなく、自分より格上の魔力が感じられたのだ。
「あらら、ウェルダンを通り過ぎて焦がしちゃった……ミディアムレアが好みなんだけどなぁ」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “魔法使い(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
真っ赤なローブ、三角帽子の、こちらも“救世主”とよく似た“魔法使い”が“戦士”の後ろから顔を出した。
「遊んでいる余裕はない、そう言っただろう?」
「そうだけどさー……せめて腕の一本ぐらいは、ね?」
(2人もいたなんて……)
“戦士”に続いて“魔法使い”。しかもこの“魔法使い”も自分のそれより強力。考えるまでもなく分が悪い。
油断している隙に――と、“救世主”は左手を握って『生成』し始める。
あの2人を確実に仕留めるためのフラグ(破片手榴弾)。知識を総動員してその構造などを思い出していたが――ふと、『嫌な予感』がして、身体を右にずらした。
激しい銃撃音を同時に、“救世主”の左肩から先が吹き飛んだ。
「うー、耳が痛い……なんて騒々しいモノでしょう……」
「ほほー、なかなかの威力だなぁ」
「これはアンチマテリアルライフル。武器というよりは兵器。剣や魔法の一歩、いえ数万歩も先を行く戦力ですよ。
……にしても、この至近距離で避けるなんて」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “学者(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
セーラー服に白衣を羽織り、眼鏡をかけた“学者”は“戦士”と“魔法使い”の足元で寝転がり、アンチマテリアルライフルのトリガーを引いていた。
「くっ……これは……」
目の前の、自分によく似た得体の知れない3人。今のままではあまりに不利、“救世主”は一旦退却することを考えた。
1人1人ならまだ相手にすることができる。まずは傷を癒すことが先決――という考えも、とっくに対策が練られていた。
「魅了(チャーム)」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “バニー(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「うふふ、逃・が・さ・な・い」
3人の後ろから現れた“バニー”は、“救世主”に向けてウィンク、そしてペロリと舌を出した。
(ん、あれ……? 身体、が熱っ……動け、ない)
それは甘く、危険な罠だった。“救世主”の身体は痺れ、動くことができなくなった。
そしてトドメと言わんばかりに、“救世主”の両目にナイフが突き刺さる。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “盗賊(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「……“バニー”のこと、あんまり見ないで」
「あらー、“盗賊”ったら嫉妬? かーわいー」
「あいつ嫌い。だってあいつは、バニーの前で、私を……!」
「怒っちゃダメ。あの子、あのときの“救世主”とは違うみたいよ?」
「おい、乳繰り合うのは後にしておけ……よっと!」
視覚が失われ、棒立ちになっていた“救世主”を、戦士”は振りかぶった剣の腹で叩き端の壁まで吹き飛ばした。
「お前、残機があるんだってな? だからそれがなくなるまで、私たちが丁寧に殺してやるよ」
「え? 私はこんがり焼いて食べたいんだけど。食欲的な意味で」
「研究したいから、食べちゃダメ。排泄物だと正確なデータが取れない」
「私は性的に食べたいなぁ。女性としても、擬似的な男性としても」
「“バニー”!!!! 許さないからね!!!!!」
「……お前たち」
苛立った様子の“戦士”に、4人はびくりと震えて口を塞ぐ。
そんな様子に満足し、“戦士”は“救世主”に向き直る。
「まあ目的はどうあれ、私たちは皆、お前に復讐がしたいってことだ。
さあお前たち、声高らかにあの言葉を言おうじゃないか。
……せーの!」
「「「「「さあ、私たちが相手だ」」」」」
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 1階、待ち続ける彼女 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“救世主”はずっと、あの忌々しい超能力者――伊藤月子を待ち続けていた。
裏切られて塔の主に仕立て上げられてから、どれぐらい経ったことだろう。何秒、何分、何時間、何日、何年……途中から数えることをやめてしまったが、“救世主”は一瞬足りとも伊藤月子への恨みを忘れたことはなかった。
あるときから、塔の屋上に人(以降は侵入者と呼ぶことにする)の気配が感じるようになった。
“救世主”の胸は踊った。
姿まではわからなかったが、その中の誰かが伊藤月子かもしれない、そう思うだけで居ても立ってもいられなくなった。
しかし塔の主の制約なのか、1階より上のフロアに行くことができなかった。なので待つことしかできなかった。
“救世主”は何とも歯がゆい思いをしたが、じっと我慢した。
まるで遠距離恋愛中の恋人と久しく会う日のような心地。“救世主”にとってそれは『恋愛感情』ではなく『殺意』ではあったが。
結論から言えば、“救世主”の我慢が報われることはなかった。侵入者が伊藤月子ではなかったからだ。
“救世主”は落胆したまま侵入者を殺し、待ち、殺しては、待ち、殺しては――ずっとこのサイクル繰り返した。
そして、今回も――
“救世主”は2階に通じる階段の前で新たな侵入者を待っていた。
もう何人目かわからない。「どうせ今回も違うに決まっている」と思いながらも、「今回こそは――」とすがるように願っていた。
「よう“救世主”殿。ひさしぶりだなぁ」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “戦士(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
“救世主”の願いはあっさりと砕かれた。そこにいたのは、やけに露出度の高い鎧(ビキニアーマー)を着て、刀身がぬらりと輝く剣を持った“戦士”だった。
その“戦士”は、まるで鏡を見ているように“救世主”と瓜二つだった。その素性が少し気にはなったが、結局は伊藤月子ではない。“救世主”は「またハズレか」とため息をついた。
「ん、今ハズレって言った? おいおい、つれないなぁ。
こっちはあのとき――ゴブリンに……されたときの恨み、溜まってるんだからなぁ!」
剣を片手で振り回し“救世主”を挑発する“戦士”。それとは対照的に“救世主”の気分はどんどんと盛り下がっていく。なにせ、『まったく記憶にない』からだ。
ハズレ相手に余計な労力を割きたくない、これがいつもの本音。けれど今回はちょっと違った。目の前の“戦士”は、剣技だけなら自分より上だったのだ。
魔法などを駆使すれば何ら問題のない相手だが、近距離戦ならこちらが不利……という判断だった。
「……面倒だから、魔法で終わらせることにするわ」
「ははは、いいねぇ。前と同じ戦略ってわけか。悪くないと思うんだけどさぁ……
私が、何の対策をしていないとでも?」
ボンッ!
“戦士”の背後から飛来した火の玉が、魔力を溜めていた“救世主”の右手を焼き焦がした。
炭となった右手はボロボロと、粉末となって床に落ちていく。それは“救世主”にとって、さしたるダメージではない。けれど、この魔法の使用者だけが気がかりだった。
間違いなく、自分より格上の魔力が感じられたのだ。
「あらら、ウェルダンを通り過ぎて焦がしちゃった……ミディアムレアが好みなんだけどなぁ」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “魔法使い(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
真っ赤なローブ、三角帽子の、こちらも“救世主”とよく似た“魔法使い”が“戦士”の後ろから顔を出した。
「遊んでいる余裕はない、そう言っただろう?」
「そうだけどさー……せめて腕の一本ぐらいは、ね?」
(2人もいたなんて……)
“戦士”に続いて“魔法使い”。しかもこの“魔法使い”も自分のそれより強力。考えるまでもなく分が悪い。
油断している隙に――と、“救世主”は左手を握って『生成』し始める。
あの2人を確実に仕留めるためのフラグ(破片手榴弾)。知識を総動員してその構造などを思い出していたが――ふと、『嫌な予感』がして、身体を右にずらした。
激しい銃撃音を同時に、“救世主”の左肩から先が吹き飛んだ。
「うー、耳が痛い……なんて騒々しいモノでしょう……」
「ほほー、なかなかの威力だなぁ」
「これはアンチマテリアルライフル。武器というよりは兵器。剣や魔法の一歩、いえ数万歩も先を行く戦力ですよ。
……にしても、この至近距離で避けるなんて」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “学者(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
セーラー服に白衣を羽織り、眼鏡をかけた“学者”は“戦士”と“魔法使い”の足元で寝転がり、アンチマテリアルライフルのトリガーを引いていた。
「くっ……これは……」
目の前の、自分によく似た得体の知れない3人。今のままではあまりに不利、“救世主”は一旦退却することを考えた。
1人1人ならまだ相手にすることができる。まずは傷を癒すことが先決――という考えも、とっくに対策が練られていた。
「魅了(チャーム)」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “バニー(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「うふふ、逃・が・さ・な・い」
3人の後ろから現れた“バニー”は、“救世主”に向けてウィンク、そしてペロリと舌を出した。
(ん、あれ……? 身体、が熱っ……動け、ない)
それは甘く、危険な罠だった。“救世主”の身体は痺れ、動くことができなくなった。
そしてトドメと言わんばかりに、“救世主”の両目にナイフが突き刺さる。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “盗賊(レベル99)”の立川はるかが現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「……“バニー”のこと、あんまり見ないで」
「あらー、“盗賊”ったら嫉妬? かーわいー」
「あいつ嫌い。だってあいつは、バニーの前で、私を……!」
「怒っちゃダメ。あの子、あのときの“救世主”とは違うみたいよ?」
「おい、乳繰り合うのは後にしておけ……よっと!」
視覚が失われ、棒立ちになっていた“救世主”を、戦士”は振りかぶった剣の腹で叩き端の壁まで吹き飛ばした。
「お前、残機があるんだってな? だからそれがなくなるまで、私たちが丁寧に殺してやるよ」
「え? 私はこんがり焼いて食べたいんだけど。食欲的な意味で」
「研究したいから、食べちゃダメ。排泄物だと正確なデータが取れない」
「私は性的に食べたいなぁ。女性としても、擬似的な男性としても」
「“バニー”!!!! 許さないからね!!!!!」
「……お前たち」
苛立った様子の“戦士”に、4人はびくりと震えて口を塞ぐ。
そんな様子に満足し、“戦士”は“救世主”に向き直る。
「まあ目的はどうあれ、私たちは皆、お前に復讐がしたいってことだ。
さあお前たち、声高らかにあの言葉を言おうじゃないか。
……せーの!」
「「「「「さあ、私たちが相手だ」」」」」

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 1階、瀕死の彼女 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「……つまらない」
“戦士”は剣を床に突き刺し、心底呆れた様子でつぶやいた。
足元にはボロ布のように無残に、血や泥、吐瀉物で汚れた“救世主”が横たわっていた。ひゅうひゅうとか細い呼吸が、彼女が瀕死であることを伝えていた。
立川はるかたちもこの“救世主”が脅威でないことをわかったのだろう。“学者”は壁に寄りかかって本を読み、読み終えたページからムシャムシャと咀嚼し、“バニー”と“盗賊”は部屋の隅で女の子同士の恋愛を愉しんでいた。
そして貧乏くじを引いたように、“戦士”と“魔法使い”が“救世主”の処理の担当になっていた。
「つまらないって……楽に越したことはないでしょう?」
「たしかにそうだけど……悲しいかな、やはり苦戦を強いられることを望んでしまっているようだ」
「ふーん、よくわからない。結局、どう食べるかが重要だと思うけどなぁ」
“魔法使い”はどろどろとヨダレを垂らしてた。そんな“魔法使い”に、やはり“戦士”は呆れてしまう。2人に限ったことではない、皆が皆、他の自分の性癖は理解し難いものだった。
「で、どーするの? 2人はさすがにきついんだけど……」
「あの3人は命をどうこうすることには興味がないからな…… なに、私たちだけで楽しめばいいだろう」
「えー、きついよー……それに私、誰かを殺すってあんまり好きじゃないし……」
「ものは考えようだぞ? 処理の最中に……腕が1本なくなったところで、何の疑問もあるまい」
「(ごくり)……あらあらそれは。うふふふふ」
「アハハハハハ。腕1本だけだぞ?」
「ふふふふふふふ」
「ハハハハハハハ」
その後、『10回復活するごとに交代』という約束で、“戦士”と“魔法使い”の2人は“救世主”を殺し合うことにした。
「さてと、私は勿体ぶってなぶり殺す趣味もないから、手っ取り早くいこうかな」
指先に魔力を込め、集中させる。その収縮された魔力が自分をたやすく殺し得るものだということを、“救世主”は焦点の定まっていない目で見て、わかってしまう。
しかし動くことができない。回復も追いつかない。“救世主”はこの先の末路を気づいてしまった。
「それじゃ1回目。ばいばーい」
ピィン!
ビームとなって発射された魔法は、“救世主”の頭を撃ち抜いた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
即死だった。“魔法使い”、そして“戦士”はその様子に何も感じない。すでに作業と認識していたからだ。
「さー、次々」
「急かさないでよ。このレベルの魔法、チャージが大変なんだから」
『立川はるかに救済処置を与えろ』
「ん?」
“魔法使い”は、聞き慣れない男の声に周囲をキョロキョロと見渡した、それは“戦士”も同じで、合わせるように顔を動かしていた。
「“戦士”、何か言った?」
「いや。“魔法使い”が言ったんじゃなかったのか」
他の3人の声でもない。間違いなく、この場にいない誰かの声だった。
「まあいい。ほら、早くチャージするんだ」
「はーい」
再びチャージに戻ると、“救世主”の復活は始まっていた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:255→254 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「お、始まったー復活」
「ここからが長い戦いだな」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「「え?」」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル50→55 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル50→55 ◆
◆ 学者の知識 レベル50→55 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル50→55 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル50→55 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
単なる復活ならどうでも良かった。が、事態はあまりに悪い。
復活と共に、脅威が増した。“救世主”のすべての能力が向上している――“戦士”と“魔法使い”は肌でそれを感じていた。
「なに、何なのよ、こいつ!」
「待て、“魔法使い”!」
“戦士”の静止も聞かず、“魔法使い”は両手に溜めた巨大な火の玉を“救世主”に投げつけ、一瞬で黒焦げにした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:254→253 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル55→60 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル55→60 ◆
◆ 学者の知識 レベル55→60 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル55→60 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル55→60 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
さらに脅威を増した“救世主”は、ついに回復を終えて立ち上がった。
半ばパニックに陥った“魔法使い”。だが“戦士”は冷静だった。
これ以上殺してはいけない。研ぎ澄まされた警戒心がそう告げていた。
「待て、待て!」
しかし“戦士”の忠告は遅すぎた。
――ぷつんっ
“魔法使い”の腕は、高らかに舞い上がった。
「ふぇ……?」
肩から先はドバドバと血を吹き出していた。“魔法使い”はそれに気づかない。
ようやく異変に気づいたとき、“救世主”の腕が“魔法使い”の身体を貫いていた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “魔法使い”は死亡しました ◆
◆ ◆
◆ このフロアでは復活はしません ◆
◆ ◆
◆ 【ゲームオーバー】 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
“魔法使い”は“救世主”同様、即死だった。ただ違う点は、“魔法使い”は復活しなかった。
「熱い……それにこの血の香り……食欲が、そそる」
腕を突き刺したまま、“救世主”は“魔法使い”の肉に齧りつく。そしてムシャムシャと食べ始めた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”は“魔法使い”を殺しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は救済処置により、“魔法使い”のステータスを引き継ぎます ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル60 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル60→159 ◆
◆ 学者の知識 レベル60 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル60 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル60 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「ま、“魔法使い”……?」
一瞬の出来事。あまりにあっけないその最期に、“戦士”は放心していた。それがいかに危険なことか、普段の“戦士”ならわかりきっているはずなのに。
このまま、“戦士”の末路も決定したかのように思えた。が、それを1人の立川はるかが救った。
鼓膜を破るかのような音と同時に、“救世主”の首から上が吹き飛んだ。
「“戦士”、逃げて!」
“学者”はアンチマテリアルライフルのスコープから目を離し、叫んだ。その声に我に返った“戦士”は、剣を掴んで部屋から飛び出した。
・
・
・
・
・
どこをどう走ったのか、“戦士”は覚えていなかった。体力の限界が訪れ、ぜいぜいと息を切らしながら小さな部屋の中で座り込んだ。
“救世主”のことを考えていた。やはり、バケモノだった。規格外のバケモノ、自分たちの手ではとうて負えそうにもない。
一矢報いたい。“魔法使い”の敵を討ってやりたい。けれど勝算がまったく見えなかった。
「“戦士”」
いつの間にか“学者”がいた。一応気を張っていたつもりなのに、声をかけられるまで気づかなかった。
それに後から追いかけて来たわりに、まったく息が乱れていない。“戦士”は“盗賊”ほどではないにしろ、体力は備わっているほうである。少なくとも“学者”なんかには負けるはずがない。
なのに、どうして?“戦士”の中で疑問が生まれる。
「“学者”……“バニー”と、“盗賊”は?」
「……一度しか言わないから、よく聞いてね」
「死んじゃった“魔法使い”の気配、感じる?」
「……感じない。どこにいるんだろう」
「たぶん、どこにもいない。変だよね、私たちは、他の私たちのことが以心伝心のようにわかるはずなのに。
おそらく、ここでは巻き戻りは起こらない。推測だけど……きっとこれは正しい」
「……お前が言うんだ、間違いないだろうな……」
「あのときの声、覚えてる?」
「『立川はるかに救済処置を与えろ』、だっけ? そうだ、あれがそもそもおかしかったんだ」
「うん、そうだね。理屈はわからないけど、あれが元凶。“救世主”がバケモノとなったトリガーなんだと思う」
「それが、何だって言うんだよ」
「で、これが大事なことなんだけどね」
「なんだよ」
「“バニー”と“盗賊”は、ここに来る前にわたしが撃ち殺した」
「…………!!!!!!!」
その瞬間“戦士”の理性は弾け飛び、握った拳を振り上げた。
「魅了(チャーム)」
拳は、“学者”に届くことはなかった。高く挙げた拳を、ゆるゆると下げていった。
「お前、それ……」
「やっと気づいた? 脳筋なんだから……『立川はるかに救済処置を与えろ』、というのは、何も“救世主”だけに適用されるわけじゃないみたい」
「それじゃあ……!」
「うん。でね、私の結論はとしては」
「“戦士”。私を、殺して」
「きっと私じゃあ、勝てない。だって私は“学者”だもの。そういう命のやりとりとか不慣れだから……
でも“戦士”は違う。私じゃできないことを、“戦士”はできるはず」
「そんな……買いかぶりすぎだろ……」
「最期ぐらい買いかぶらせてよ……ねえ、お願い。私の、最期のお願い」
“学者”は目を閉じた・
“戦士”は“学者”の覚悟が伝わっていた。それを鼻で笑うような性格を、“戦士”はしていない。
“戦士”の両手で剣を持った。
“学者”の身体を縦に切り裂いた。
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 1階、瀕死の彼女 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「……つまらない」
“戦士”は剣を床に突き刺し、心底呆れた様子でつぶやいた。
足元にはボロ布のように無残に、血や泥、吐瀉物で汚れた“救世主”が横たわっていた。ひゅうひゅうとか細い呼吸が、彼女が瀕死であることを伝えていた。
立川はるかたちもこの“救世主”が脅威でないことをわかったのだろう。“学者”は壁に寄りかかって本を読み、読み終えたページからムシャムシャと咀嚼し、“バニー”と“盗賊”は部屋の隅で女の子同士の恋愛を愉しんでいた。
そして貧乏くじを引いたように、“戦士”と“魔法使い”が“救世主”の処理の担当になっていた。
「つまらないって……楽に越したことはないでしょう?」
「たしかにそうだけど……悲しいかな、やはり苦戦を強いられることを望んでしまっているようだ」
「ふーん、よくわからない。結局、どう食べるかが重要だと思うけどなぁ」
“魔法使い”はどろどろとヨダレを垂らしてた。そんな“魔法使い”に、やはり“戦士”は呆れてしまう。2人に限ったことではない、皆が皆、他の自分の性癖は理解し難いものだった。
「で、どーするの? 2人はさすがにきついんだけど……」
「あの3人は命をどうこうすることには興味がないからな…… なに、私たちだけで楽しめばいいだろう」
「えー、きついよー……それに私、誰かを殺すってあんまり好きじゃないし……」
「ものは考えようだぞ? 処理の最中に……腕が1本なくなったところで、何の疑問もあるまい」
「(ごくり)……あらあらそれは。うふふふふ」
「アハハハハハ。腕1本だけだぞ?」
「ふふふふふふふ」
「ハハハハハハハ」
その後、『10回復活するごとに交代』という約束で、“戦士”と“魔法使い”の2人は“救世主”を殺し合うことにした。
「さてと、私は勿体ぶってなぶり殺す趣味もないから、手っ取り早くいこうかな」
指先に魔力を込め、集中させる。その収縮された魔力が自分をたやすく殺し得るものだということを、“救世主”は焦点の定まっていない目で見て、わかってしまう。
しかし動くことができない。回復も追いつかない。“救世主”はこの先の末路を気づいてしまった。
「それじゃ1回目。ばいばーい」
ピィン!
ビームとなって発射された魔法は、“救世主”の頭を撃ち抜いた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
即死だった。“魔法使い”、そして“戦士”はその様子に何も感じない。すでに作業と認識していたからだ。
「さー、次々」
「急かさないでよ。このレベルの魔法、チャージが大変なんだから」
『立川はるかに救済処置を与えろ』
「ん?」
“魔法使い”は、聞き慣れない男の声に周囲をキョロキョロと見渡した、それは“戦士”も同じで、合わせるように顔を動かしていた。
「“戦士”、何か言った?」
「いや。“魔法使い”が言ったんじゃなかったのか」
他の3人の声でもない。間違いなく、この場にいない誰かの声だった。
「まあいい。ほら、早くチャージするんだ」
「はーい」
再びチャージに戻ると、“救世主”の復活は始まっていた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:255→254 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「お、始まったー復活」
「ここからが長い戦いだな」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「「え?」」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル50→55 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル50→55 ◆
◆ 学者の知識 レベル50→55 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル50→55 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル50→55 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
単なる復活ならどうでも良かった。が、事態はあまりに悪い。
復活と共に、脅威が増した。“救世主”のすべての能力が向上している――“戦士”と“魔法使い”は肌でそれを感じていた。
「なに、何なのよ、こいつ!」
「待て、“魔法使い”!」
“戦士”の静止も聞かず、“魔法使い”は両手に溜めた巨大な火の玉を“救世主”に投げつけ、一瞬で黒焦げにした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:254→253 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル55→60 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル55→60 ◆
◆ 学者の知識 レベル55→60 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル55→60 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル55→60 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
さらに脅威を増した“救世主”は、ついに回復を終えて立ち上がった。
半ばパニックに陥った“魔法使い”。だが“戦士”は冷静だった。
これ以上殺してはいけない。研ぎ澄まされた警戒心がそう告げていた。
「待て、待て!」
しかし“戦士”の忠告は遅すぎた。
――ぷつんっ
“魔法使い”の腕は、高らかに舞い上がった。
「ふぇ……?」
肩から先はドバドバと血を吹き出していた。“魔法使い”はそれに気づかない。
ようやく異変に気づいたとき、“救世主”の腕が“魔法使い”の身体を貫いていた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “魔法使い”は死亡しました ◆
◆ ◆
◆ このフロアでは復活はしません ◆
◆ ◆
◆ 【ゲームオーバー】 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
“魔法使い”は“救世主”同様、即死だった。ただ違う点は、“魔法使い”は復活しなかった。
「熱い……それにこの血の香り……食欲が、そそる」
腕を突き刺したまま、“救世主”は“魔法使い”の肉に齧りつく。そしてムシャムシャと食べ始めた。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”は“魔法使い”を殺しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は救済処置により、“魔法使い”のステータスを引き継ぎます ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル60 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル60→159 ◆
◆ 学者の知識 レベル60 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル60 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル60 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「ま、“魔法使い”……?」
一瞬の出来事。あまりにあっけないその最期に、“戦士”は放心していた。それがいかに危険なことか、普段の“戦士”ならわかりきっているはずなのに。
このまま、“戦士”の末路も決定したかのように思えた。が、それを1人の立川はるかが救った。
鼓膜を破るかのような音と同時に、“救世主”の首から上が吹き飛んだ。
「“戦士”、逃げて!」
“学者”はアンチマテリアルライフルのスコープから目を離し、叫んだ。その声に我に返った“戦士”は、剣を掴んで部屋から飛び出した。
・
・
・
・
・
どこをどう走ったのか、“戦士”は覚えていなかった。体力の限界が訪れ、ぜいぜいと息を切らしながら小さな部屋の中で座り込んだ。
“救世主”のことを考えていた。やはり、バケモノだった。規格外のバケモノ、自分たちの手ではとうて負えそうにもない。
一矢報いたい。“魔法使い”の敵を討ってやりたい。けれど勝算がまったく見えなかった。
「“戦士”」
いつの間にか“学者”がいた。一応気を張っていたつもりなのに、声をかけられるまで気づかなかった。
それに後から追いかけて来たわりに、まったく息が乱れていない。“戦士”は“盗賊”ほどではないにしろ、体力は備わっているほうである。少なくとも“学者”なんかには負けるはずがない。
なのに、どうして?“戦士”の中で疑問が生まれる。
「“学者”……“バニー”と、“盗賊”は?」
「……一度しか言わないから、よく聞いてね」
「死んじゃった“魔法使い”の気配、感じる?」
「……感じない。どこにいるんだろう」
「たぶん、どこにもいない。変だよね、私たちは、他の私たちのことが以心伝心のようにわかるはずなのに。
おそらく、ここでは巻き戻りは起こらない。推測だけど……きっとこれは正しい」
「……お前が言うんだ、間違いないだろうな……」
「あのときの声、覚えてる?」
「『立川はるかに救済処置を与えろ』、だっけ? そうだ、あれがそもそもおかしかったんだ」
「うん、そうだね。理屈はわからないけど、あれが元凶。“救世主”がバケモノとなったトリガーなんだと思う」
「それが、何だって言うんだよ」
「で、これが大事なことなんだけどね」
「なんだよ」
「“バニー”と“盗賊”は、ここに来る前にわたしが撃ち殺した」
「…………!!!!!!!」
その瞬間“戦士”の理性は弾け飛び、握った拳を振り上げた。
「魅了(チャーム)」
拳は、“学者”に届くことはなかった。高く挙げた拳を、ゆるゆると下げていった。
「お前、それ……」
「やっと気づいた? 脳筋なんだから……『立川はるかに救済処置を与えろ』、というのは、何も“救世主”だけに適用されるわけじゃないみたい」
「それじゃあ……!」
「うん。でね、私の結論はとしては」
「“戦士”。私を、殺して」
「きっと私じゃあ、勝てない。だって私は“学者”だもの。そういう命のやりとりとか不慣れだから……
でも“戦士”は違う。私じゃできないことを、“戦士”はできるはず」
「そんな……買いかぶりすぎだろ……」
「最期ぐらい買いかぶらせてよ……ねえ、お願い。私の、最期のお願い」
“学者”は目を閉じた・
“戦士”は“学者”の覚悟が伝わっていた。それを鼻で笑うような性格を、“戦士”はしていない。
“戦士”の両手で剣を持った。
“学者”の身体を縦に切り裂いた。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 1階、彼女たちの決着 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「よう“救世主”殿」
外へと通じる扉の前で座っていた“救世主”の前に、“戦士”は現れた。
不敵な笑みを浮かべ、自信に満ちた様子。心なしかエロティックな雰囲気さえ感じられた。
「…………」
“救世主”は立ち、ぽんぽんと服の汚れを払い、扉の横に移動した。
「出てってええで。ハズレには興味ないし」
「お前、さっき1人殺したじゃないか……」
「アレはちょっとした腹いせ。本当は平和主義者やねんで? ほら、気が変わらないうちにさっさと出てけ」
「おいおい、つれないなぁ。これで、ちょっとはやる気出してくれないか?」
“戦士”は小さな筒のようなものを、“救世主”に放り投げた。
“救世主”がそれに気づいたときには、周囲に激しい閃光が走った。“救世主”は目を閉じるだけに留まらず、身体を折り曲げ反射的に身体を守った。
その閃光の中で、“戦士”は“救世主”に詰め寄りヘソから上下に切断した。
「フラッシュバン。“学者”はこういう小道具作るのが上手だなぁ」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:252→251 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル65→70 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル164→169(引き継ぎあり) ◆
◆ 学者の知識 レベル65→70 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル65→70 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル65→70 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「ああ、身体が軽い。これがあいつの身体能力なのか。はは、良いなぁ、実に良い」
「……他のヤツらがいないと思ったら、そういうことか」
「いないって? たしかに姿はないけど、私の中にはしっかり残っている。
だからもう一度、言わせてもらおう」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “戦士(レベル99)”の立川はるか ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル99 ◆
◆ 学者の知識 レベル99(引き継ぎあり) ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル99(引き継ぎあり) ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル99(引き継ぎあり) ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「さあ、私たちが相手だ」
・
・
・
・
・
“学者”の知識、知性を引き継いだ“戦士”は、この戦いの終わり方がわかっていた。けれど、それを承知で“救世主”に挑んでいた。
それはきっと、彼女の、“戦士”特有の性癖によるものだったのだろう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:246→245 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル95 →100 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル194→199(引き継ぎあり) ◆
◆ 学者の知識 レベル95 →100 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル95 →100 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル95 →100 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「あっ」
“救世主”の短剣は、“戦士”の手から剣が弾き飛ばした。
そのまま首元に刃を突きつける。
「……あーあ、ここまでか」
“戦士”は肩をすくめた。その顔に未練などなく、どこか満足気だった。
「なんや、案外諦めがええんやね」
「救済処置とやらで、いずれ追い抜かれるのはわかっていたからな。
お前、ズルすぎだよ。どんなチートだよ」
苦笑いを浮かべる“戦士”に、ますます“救世主”は困惑する。
「死ぬの、怖くないん?」
「そりゃあ怖いよ。けど、もう無理だろう」
「まあ、だから」
――ガチンッ
“戦士”の口の中で、金属音が鳴った。
「“学者”の切り札だ。これ、爆弾らしいぞ?」
“戦士”は歯型のついた小さな球を吐き出した。
「じゃあな、バケモノ」
―――――――――――――――――――――――――
粉々に消し飛んだ“救世主”は、小さな粘土が寄り集まって人の形を作るように、元の姿に戻った。
最後の最後で自爆した“戦士”を思い出していた。殺されれば引き継がれてしまう、だからこそ自爆。
結果的には自分の勝ち。けれど戦略としては完全に敗北。“救世主”は自分が許せなかった。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:245→244 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置の効果は終わりました ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル100 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル199(引き継ぎあり) ◆
◆ 学者の知識 レベル100 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル100 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル100 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 1階、彼女たちの決着 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「よう“救世主”殿」
外へと通じる扉の前で座っていた“救世主”の前に、“戦士”は現れた。
不敵な笑みを浮かべ、自信に満ちた様子。心なしかエロティックな雰囲気さえ感じられた。
「…………」
“救世主”は立ち、ぽんぽんと服の汚れを払い、扉の横に移動した。
「出てってええで。ハズレには興味ないし」
「お前、さっき1人殺したじゃないか……」
「アレはちょっとした腹いせ。本当は平和主義者やねんで? ほら、気が変わらないうちにさっさと出てけ」
「おいおい、つれないなぁ。これで、ちょっとはやる気出してくれないか?」
“戦士”は小さな筒のようなものを、“救世主”に放り投げた。
“救世主”がそれに気づいたときには、周囲に激しい閃光が走った。“救世主”は目を閉じるだけに留まらず、身体を折り曲げ反射的に身体を守った。
その閃光の中で、“戦士”は“救世主”に詰め寄りヘソから上下に切断した。
「フラッシュバン。“学者”はこういう小道具作るのが上手だなぁ」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:252→251 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル65→70 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル164→169(引き継ぎあり) ◆
◆ 学者の知識 レベル65→70 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル65→70 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル65→70 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「ああ、身体が軽い。これがあいつの身体能力なのか。はは、良いなぁ、実に良い」
「……他のヤツらがいないと思ったら、そういうことか」
「いないって? たしかに姿はないけど、私の中にはしっかり残っている。
だからもう一度、言わせてもらおう」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “戦士(レベル99)”の立川はるか ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル99 ◆
◆ 学者の知識 レベル99(引き継ぎあり) ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル99(引き継ぎあり) ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル99(引き継ぎあり) ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「さあ、私たちが相手だ」
・
・
・
・
・
“学者”の知識、知性を引き継いだ“戦士”は、この戦いの終わり方がわかっていた。けれど、それを承知で“救世主”に挑んでいた。
それはきっと、彼女の、“戦士”特有の性癖によるものだったのだろう。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:246→245 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置により、“救世主”のレベルが上がります ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル95 →100 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル194→199(引き継ぎあり) ◆
◆ 学者の知識 レベル95 →100 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル95 →100 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル95 →100 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「あっ」
“救世主”の短剣は、“戦士”の手から剣が弾き飛ばした。
そのまま首元に刃を突きつける。
「……あーあ、ここまでか」
“戦士”は肩をすくめた。その顔に未練などなく、どこか満足気だった。
「なんや、案外諦めがええんやね」
「救済処置とやらで、いずれ追い抜かれるのはわかっていたからな。
お前、ズルすぎだよ。どんなチートだよ」
苦笑いを浮かべる“戦士”に、ますます“救世主”は困惑する。
「死ぬの、怖くないん?」
「そりゃあ怖いよ。けど、もう無理だろう」
「まあ、だから」
――ガチンッ
“戦士”の口の中で、金属音が鳴った。
「“学者”の切り札だ。これ、爆弾らしいぞ?」
“戦士”は歯型のついた小さな球を吐き出した。
「じゃあな、バケモノ」
―――――――――――――――――――――――――
粉々に消し飛んだ“救世主”は、小さな粘土が寄り集まって人の形を作るように、元の姿に戻った。
最後の最後で自爆した“戦士”を思い出していた。殺されれば引き継がれてしまう、だからこそ自爆。
結果的には自分の勝ち。けれど戦略としては完全に敗北。“救世主”は自分が許せなかった。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “救世主”の立川はるかは死亡しました ◆
◆ ◆
◆ “救世主”は残機を1消費して復活します ◆
◆ ◆
◆ 残機:245→244 ◆
◆ ◆
◆ 救済処置の効果は終わりました ◆
◆ ◆
◆ 戦士の剣技 レベル100 ◆
◆ 魔法使いの魔法 レベル199(引き継ぎあり) ◆
◆ 学者の知識 レベル100 ◆
◆ 盗賊の身体能力 レベル100 ◆
◆ バニーガールの魅力 レベル100 ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 対峙する2人 +1 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ホッシーナはそのフロアが1階、つまり出口があるということに気がついた。
どこからか風が流れてきている。今まで窓はあっても壁と一体になっていて、押しても引いてもピクリとも動かない。えて銃弾すら弾き返しそうな分厚い代物で、太陽の光は差し込んでも風が通る余地は少しもなかった。
それほど厳重に封鎖されている塔内に、風を感じるのだ。
たしかに、贔屓目に見ても塔の出口が開いているというのはあまりに無用心。けれど閉め切られていた窓がこのフロアに限って開いているというのは、それ以上に不自然すぎる。
なのでホッシーナは自分の都合の良いようにとらえることにした。
どこかに出口がある。
そこから脱出できる。
そして今回こそ、伊藤月子を助けることができるかもしれない。
ホッシーナは、とにかく前向きに物事を考えた。
――目の前の絶望と向き合うまでは。
「なに、これ……」
突然話しは変わるが、ホッシーナは比較的ゲームを嗜むほうである。
特に好き嫌いはなく『贅沢な暇つぶし』ぐらいのつもりだったが、それなりに遊んでいたので『それ』については直感でわかってしまった。
典型的なロールプレイングゲームを考えていただこう。ダンジョンの最奥には何がいるかはご存知だろう。
次に典型的なアクションゲームを考えていただこう。画面がスクロールして音楽が変わったら、そこから起こる展開を予想することなんて容易なことだろう。
……いい加減脱線するのも興が冷めるので、そろそろ本文に戻るとする。
ホッシーナは目の前にいる『それ』に、言葉を失っていた。
『それ』に対してホッシーナが抱いた感想は『怖い』だとか『住む世界の違う生物』などではなく、『美しい』という意外で、かつボキャブラリーの乏しいものだった。
まず目に入ったものが、『それ』が着ている毒々しい程に赤いドレス。綺麗に染まっているわけではなくムラもあればまだらもある(元々は淡いライトグリーンのドレスであったが、幾人もの血を吸い込み変色してしまったのだ。もちろんホッシーナはそのことを知るよしもない)。
ところどころ破れてほつれて、お世辞にも良品とは言いがたい。なのに魅入ってしまう。『それ』が着る小汚い赤いドレスが、何にも勝る召し物に感じられた。
そんな赤いドレスに隠された身体。胸元はドレスをはち切れんばかりに盛り上げ、それとは対照的に腰は引き締まり、くびれている。そして縦に破れたスカートの隙間からは、むっちりと弾力のある脚がちらちらと見え隠れしていた。
「……また、ハズレか」
『それ』が口を開いた。ようやくホッシーナは『それ』と目を合わせた。
一見童顔、けれど必要以上に甘ったるく、なのに陰気で、ところが艶やかで、一転憎しみで歪んでいるように見えた。
かなり失礼なことを言われたにもかかわらず、ぽそぽそと動いた唇に思わずゴクリと、ホッシーナは生唾を飲んでしまった。
「めんどうやし……これで、えっか」
『それ』はゆっくりと、右手をホッシーナに突き出した。すると手のひらの周囲の空気がゆらゆらと揺れる。
「時間――」
このホッシーナの判断、行動は理性的なものではない。
「停止!!!」
反射的に、なるべく温存しておきたかった能力を使用した。
さして戦闘慣れしていないホッシーナでも感じられるほど『それ』から殺気が放出され、ホッシーナの本能を痛いほどに刺激したのだ。
ホッシーナは床を蹴り、駆けた。『それ』の隣りを通り過ぎ、振り返ることなくがむしゃらに部屋から飛び出した。
「…………あれ?」
しばらくして時間停止の効果が切れて『それ』――“救世主”は目の前のハズレがいなくなったことに疑問を抱いた。
“救世主”はハズレが『消えた』と結論づけた。今さら超高速で動かれても見逃すはずがない。それにこの部屋は2階からの階段と、自分のすぐ後ろにしか出る扉がない。2階に戻るということは塔のシステム上、不可能。
そうなるとハズレは後ろの出口からしか逃げることはできない、しかも自分に気づかれずに。もちろんこれも不可能。
そこで思い出した、「時間停止」という言葉。
まるでお伽話のようだが、もしあのハズレが言葉の通りに時間を止めることができるなら、不可能と思えたことも可能になる。
時間と止めるだなんて科学や腕力ではもちろんできない。そんな都合の良い魔法だって存在しない。
となると一つの可能性が思い浮かぶ。
「……超能力者、か……!」
魔法や科学ではない、未知の、超常的な能力。身が焦がれるほどに待ち続けている『あいつ』と同種の存在!
“救世主”は自分でも久しいと感じるほどに、笑みを漏らしていた。
・
・
・
・
・
走って、走って、できる限り時間と止めたまま走り続けたホッシーナは、糸が切れたようにガクリと体勢を崩して床に膝を着けた。
ずいぶん無理をして時間を止めてしまった。走ったことによる疲労以上に、時間停止の代償がホッシーナを降りかかる。
重い。身体が、とても重い。のろのろと立ち上がり、ずしり、ずしりと一歩ずつ脚を踏み出す。
もたもたしているとあのバケモノに追いつかれてしまう。幸い、風の吹く方向から出口のある場所は何となくわかる。身体は重いがあと一回ぐらいなら時間停止もできるだろう。
何の対策もなくもう一度会えば、その時点で死亡がほぼ確定する。が、まだこちらに分がある。悲観するところではない、とにかく、出口を目指すのだ。
「伊藤、月子さん……」
歩くことさえ表情を歪ませるホッシーナ。そんな彼女が、ぽつりと名前をつぶやいた。
伊藤月子という女性。その女性こそが、ホッシーナがどうしても助けたい人物だった。
平行世界を行き来できる(この塔ではなぜか使用できないが)ホッシーナは、何人もの伊藤月子を出会ってきた。そしてすべての伊藤月子が、自身の強大すぎる超能力に悩み、苛まれ、ある世界では忌み嫌われ、ある世界では暴走し自我を失う――悲惨な結末を迎えていた。
ホッシーナは、伊藤月子を救いたかった。最初こそ、ただただ伊藤月子から逃げるためだけに平行世界を移動していた。けれど少しずつ情が湧き、いざ触れ合ってみると自分と何ら変わりない女の子ということもわかった(スタイルはだいぶ違うが)。
いつしか、伊藤月子と自分が平穏に暮らせる世界を探そうとしていた。だから、この塔から脱出することが目的ではない。脱出は単なる通過点で、この世界の伊藤月子を助けること、自分が伊藤月子の『救世主』となることが、ホッシーナの真の目的だった。
頬を撫でる風が一層強くなっていく。ヒュウヒュウと耳元で音が鳴る。曲がり角を曲がるたびに風が湿っていくようで、心が踊った。
「あ、ああ」
ようやく光が見えた。突き当たりの部屋から入り込む光がとても眩しくてよく見えない。けれど、ある。出口がそこにある!
「やった、やった……!」
あれだけ重かった身体が軽く感じられた。脚を踏み出す速度も上がっていく。進む、進む、歩が進む。長い廊下を進み、出た先はエントランスホール。広くて、煌々と明かりも灯っている。
その先、広いエントランスホールの向かいに光源、出口があった。もう身体は限界だった。代償によりボロボロになった身体に鞭を打っていたため、疲労も限界を迎えていた。それでも、たとえ這ってでも突き進んでやる、ホッシーナからはそんな気がいさえ感じられた。
まあもちろん、ホッシーナの脱出劇は呆気無く幕を閉じる。
「はい、おつかれさーん」
ホッシーナは背後から肩をつかまれた。
あの声。あのバケモノ――“救世主”の声だった。
「あんたさぁ、『アキレスと亀』って知ってる? 屁理屈言ってアキレスはいつまで経っても亀に追いつけないっていう、アレ。ウチ、まさにアキレスの気分やったわ。
お前遅すぎ。ウチがその気になれば、200回ぐらいは死んでたで?」
脚が震え、冷や汗が垂れ、奥歯がカチカチ鳴っている。すぐ後ろのバケモノは、まるでドアノブを捻って開けるぐらいに簡単な気持ちで殺すことだろう。
ホッシーナは時間停止のタイミングを図っていた。自分以外のすべてが停止する以上、肩をつかまれているとそこで固定され、身動きが取れなくなってしまう。
身体が離れた一瞬。それに賭けるしかなかった。
「あなたは、何者?」
「誰が質問してええて言うた?」
ギチッ
「あうっ!」
肩をつかむ手に力が込められ、ホッシーナは苦痛に顔を歪める。
みしみしと軋んでいる。折るだの外すだの、そんな甘いものではない。あと1回機嫌を損ねれば、その瞬間粉砕してしまうほどの力だ。
「あんたはウチの質問に答えるだけ。ええな?」
「…………」
「黙るなや。ちゃんと答えてくれるなら、ここから出してあげるで?」
「……本当に?」
思わず聞き返してしまう。だがこれを質問とは受け取られなかったらしく、「ほんまほんま、ハズレには興味ないし」と軽い口調で返ってきた。
もしも(だいぶ希望は薄いが)本当なら、これほど楽なことはない。たとえ(おそらくこちらが本命)嘘だったとしても、とりあえず時間を稼ぐことはできるし、気を逸らすチャンスも生まれるかもしれない。
「最初の……というよりは確認やけど、あんた、時間を止めることができるな?」
「…………」
「『時間停止!』なんて叫んだら誰だってわかるで。そこから辿ると、あんた自身は戦力があらへん。時間を止めることで相手が無抵抗になるのに、攻撃した形跡がなかった、ただ逃げることだけを優先した。
出口があることを知ってたかもしれへんけど、障害を排除したほうが確実に安全、でもしなかった。どうや?」
「……ご名答(本当は時間停止だけじゃないけど、わざわざ言うこともない……)」
「まあそんなことはどうでもええ。ここからが本題。
あんた、超能力者?」
「ええ、そうよ」
時間停止がバレているのなら秘密にすることもないだろう。ホッシーナのこの考えはあまりに浅はかだったのかもしれない。
「なら、伊藤月子ってヤツ、知ってる?」
その名前に、びくんと身体を震わせてしまった。それは肯定したも同じ、“救世主”はニンマリと笑う。
「その反応、知ってるな? あの貧相な身体つきの、性悪超能力者のことを」
「性悪?」
「ウチは昔、その伊藤月子に騙されてここに閉じ込められるようになったんや。だから言うなれば、復讐したいねん。簡単には殺さず、殺してって懇願するところまで虐め抜いてやりたいんや。楽しいやろなぁぁ」
ヒシヒシと殺気、怒気が伝わってきていた。どれほどの恨みを抱いているのか、肌で感じることができた。
「そこでや、あんたが知ってる伊藤月子のこと、教えろや。あいつも超能力者なんやろ?」「…………んっ!」
ホッシーナは違和感を感じた。下半身――ヘソから下が、冷たい。氷のように、とか、恐怖で固まって、などといったチープな表現ではなく、血が通っていない(これもチープな表現ではあるが)ように冷たかった。
「これ、は……?」
自分の身体を見て、ホッシーナは思考が止まってしまうほどに驚いた。冷たいと感じていたヘソから下が石化、無機質なグレー色へと変わり、石になっていたのだ。
「ようやくアイツの手がかりが見つかったんや、逃さへんで」
「この石化な、全身に広がったらもう戻れへん。そこで終わりや」
「でも今ならまだ間に合う」
「伊藤月子のこと、全部教えてくれたら戻してやる」
「それで、さっさとここから出てけばええで」
「さあ」
「お? し? え? て?」
そんなこと、悩むまでもなかった。
「――時間停止」
最後の時間停止を、ホッシーナは使用した。そして下半身は動かないまま、上半身を捻って肘を“救世主”にぶつける。何度も何度も、骨が悲鳴を上げ、筋肉がパンパンに腫れてしまっても、それでも何度も何度も。
「……解除」
代償によって意識を保つことさえままならないホッシーナと、きょとんと目をパチパチさせる“救世主”。
「妙にヒリヒリするんやけど……お前、やったな?」
「ええ、しましたよ。時間止めて、男性たちが好みそうなその身体を殴ってやりました。それが何か? これが、私の答えです」
「お前、自分がどうなるかわかってんのか?」
「わかってますよ。バカじゃないんですから。
もちろん怖いです。生きたいに決まってます。
ですが、私は伊藤月子さんを裏切らない。
あなたは性悪と言った。たしかに、そういう世界の伊藤月子さんはいました。
ですが、ほとんどの世界の伊藤月子さんは、とても優しい。でも他の人たちが彼女の存在を許さない。あなたも、その一人だ」
「言いたいことは、それだけか?」
石化は首元まで進行していた。
ホッシーナは、とっくに覚悟ができていた。
「私はここで終わりでしょうね。
もしかしたら、あなたは伊藤月子さんと会ってしまうかもしれない。
でも、あの人があなたなんかに負けるはずが」
ついに口まで石化し、ホッシーナの言葉が途切れた。
(ごめんなさい……私は、もう)
『ホッシーナ、すべてを思いだせ』
(…………! 伊藤先輩、伊藤)
――ピシリ
ホッシーナの全身はグレーに染まった。
呼吸もない、体温もない。ホッシーナは単なる石像になってしまった。
「はい、バイバイ」
――トンッ
“救世主”が軽く押すと、ホッシーナは倒れ――音と立てて砕け、粉々になった。
【ホッシーナ(タイムトラベラー)――バッドエンド:脱出失敗】
・
・
・
“救世主”は不満だった。
すぐ後ろにいる、得たいの知れない男。その存在が不愉快で堪らなかった。
「で、お前は誰やねん」
「ん、僕? 僕は、そうだなぁ……単なるストーリーテラーだよ」
すたすたと無警戒に“救世主”の隣りを通り過ぎていく。
貧弱すぎる。これが“救世主”の感想。その気になればいくらでも殺せるような相手、それなのに、できない。まるで『何かに命令されているかのように』殺す気が起きなかったのだ。
「ちょっと干渉しすぎたからね、そろそろ僕は退場するよ。すべてが終わるまで、ね」
「すべてが終わる?」
「ああそうだよ。もうすぐ、キミの待ち人が現れる。そのときが、終わりさ」
「さあ、いよいよクライマックスだ」
得たいの知れない男は、軽く手を振って外へと出て行った。
“救世主”は煮え切れない気持ちで、その背中を眺めることしかできなかった。
X X
X 救世主の塔 X
X X
X 対峙する2人 +1 X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ホッシーナはそのフロアが1階、つまり出口があるということに気がついた。
どこからか風が流れてきている。今まで窓はあっても壁と一体になっていて、押しても引いてもピクリとも動かない。えて銃弾すら弾き返しそうな分厚い代物で、太陽の光は差し込んでも風が通る余地は少しもなかった。
それほど厳重に封鎖されている塔内に、風を感じるのだ。
たしかに、贔屓目に見ても塔の出口が開いているというのはあまりに無用心。けれど閉め切られていた窓がこのフロアに限って開いているというのは、それ以上に不自然すぎる。
なのでホッシーナは自分の都合の良いようにとらえることにした。
どこかに出口がある。
そこから脱出できる。
そして今回こそ、伊藤月子を助けることができるかもしれない。
ホッシーナは、とにかく前向きに物事を考えた。
――目の前の絶望と向き合うまでは。
「なに、これ……」
突然話しは変わるが、ホッシーナは比較的ゲームを嗜むほうである。
特に好き嫌いはなく『贅沢な暇つぶし』ぐらいのつもりだったが、それなりに遊んでいたので『それ』については直感でわかってしまった。
典型的なロールプレイングゲームを考えていただこう。ダンジョンの最奥には何がいるかはご存知だろう。
次に典型的なアクションゲームを考えていただこう。画面がスクロールして音楽が変わったら、そこから起こる展開を予想することなんて容易なことだろう。
……いい加減脱線するのも興が冷めるので、そろそろ本文に戻るとする。
ホッシーナは目の前にいる『それ』に、言葉を失っていた。
『それ』に対してホッシーナが抱いた感想は『怖い』だとか『住む世界の違う生物』などではなく、『美しい』という意外で、かつボキャブラリーの乏しいものだった。
まず目に入ったものが、『それ』が着ている毒々しい程に赤いドレス。綺麗に染まっているわけではなくムラもあればまだらもある(元々は淡いライトグリーンのドレスであったが、幾人もの血を吸い込み変色してしまったのだ。もちろんホッシーナはそのことを知るよしもない)。
ところどころ破れてほつれて、お世辞にも良品とは言いがたい。なのに魅入ってしまう。『それ』が着る小汚い赤いドレスが、何にも勝る召し物に感じられた。
そんな赤いドレスに隠された身体。胸元はドレスをはち切れんばかりに盛り上げ、それとは対照的に腰は引き締まり、くびれている。そして縦に破れたスカートの隙間からは、むっちりと弾力のある脚がちらちらと見え隠れしていた。
「……また、ハズレか」
『それ』が口を開いた。ようやくホッシーナは『それ』と目を合わせた。
一見童顔、けれど必要以上に甘ったるく、なのに陰気で、ところが艶やかで、一転憎しみで歪んでいるように見えた。
かなり失礼なことを言われたにもかかわらず、ぽそぽそと動いた唇に思わずゴクリと、ホッシーナは生唾を飲んでしまった。
「めんどうやし……これで、えっか」
『それ』はゆっくりと、右手をホッシーナに突き出した。すると手のひらの周囲の空気がゆらゆらと揺れる。
「時間――」
このホッシーナの判断、行動は理性的なものではない。
「停止!!!」
反射的に、なるべく温存しておきたかった能力を使用した。
さして戦闘慣れしていないホッシーナでも感じられるほど『それ』から殺気が放出され、ホッシーナの本能を痛いほどに刺激したのだ。
ホッシーナは床を蹴り、駆けた。『それ』の隣りを通り過ぎ、振り返ることなくがむしゃらに部屋から飛び出した。
「…………あれ?」
しばらくして時間停止の効果が切れて『それ』――“救世主”は目の前のハズレがいなくなったことに疑問を抱いた。
“救世主”はハズレが『消えた』と結論づけた。今さら超高速で動かれても見逃すはずがない。それにこの部屋は2階からの階段と、自分のすぐ後ろにしか出る扉がない。2階に戻るということは塔のシステム上、不可能。
そうなるとハズレは後ろの出口からしか逃げることはできない、しかも自分に気づかれずに。もちろんこれも不可能。
そこで思い出した、「時間停止」という言葉。
まるでお伽話のようだが、もしあのハズレが言葉の通りに時間を止めることができるなら、不可能と思えたことも可能になる。
時間と止めるだなんて科学や腕力ではもちろんできない。そんな都合の良い魔法だって存在しない。
となると一つの可能性が思い浮かぶ。
「……超能力者、か……!」
魔法や科学ではない、未知の、超常的な能力。身が焦がれるほどに待ち続けている『あいつ』と同種の存在!
“救世主”は自分でも久しいと感じるほどに、笑みを漏らしていた。
・
・
・
・
・
走って、走って、できる限り時間と止めたまま走り続けたホッシーナは、糸が切れたようにガクリと体勢を崩して床に膝を着けた。
ずいぶん無理をして時間を止めてしまった。走ったことによる疲労以上に、時間停止の代償がホッシーナを降りかかる。
重い。身体が、とても重い。のろのろと立ち上がり、ずしり、ずしりと一歩ずつ脚を踏み出す。
もたもたしているとあのバケモノに追いつかれてしまう。幸い、風の吹く方向から出口のある場所は何となくわかる。身体は重いがあと一回ぐらいなら時間停止もできるだろう。
何の対策もなくもう一度会えば、その時点で死亡がほぼ確定する。が、まだこちらに分がある。悲観するところではない、とにかく、出口を目指すのだ。
「伊藤、月子さん……」
歩くことさえ表情を歪ませるホッシーナ。そんな彼女が、ぽつりと名前をつぶやいた。
伊藤月子という女性。その女性こそが、ホッシーナがどうしても助けたい人物だった。
平行世界を行き来できる(この塔ではなぜか使用できないが)ホッシーナは、何人もの伊藤月子を出会ってきた。そしてすべての伊藤月子が、自身の強大すぎる超能力に悩み、苛まれ、ある世界では忌み嫌われ、ある世界では暴走し自我を失う――悲惨な結末を迎えていた。
ホッシーナは、伊藤月子を救いたかった。最初こそ、ただただ伊藤月子から逃げるためだけに平行世界を移動していた。けれど少しずつ情が湧き、いざ触れ合ってみると自分と何ら変わりない女の子ということもわかった(スタイルはだいぶ違うが)。
いつしか、伊藤月子と自分が平穏に暮らせる世界を探そうとしていた。だから、この塔から脱出することが目的ではない。脱出は単なる通過点で、この世界の伊藤月子を助けること、自分が伊藤月子の『救世主』となることが、ホッシーナの真の目的だった。
頬を撫でる風が一層強くなっていく。ヒュウヒュウと耳元で音が鳴る。曲がり角を曲がるたびに風が湿っていくようで、心が踊った。
「あ、ああ」
ようやく光が見えた。突き当たりの部屋から入り込む光がとても眩しくてよく見えない。けれど、ある。出口がそこにある!
「やった、やった……!」
あれだけ重かった身体が軽く感じられた。脚を踏み出す速度も上がっていく。進む、進む、歩が進む。長い廊下を進み、出た先はエントランスホール。広くて、煌々と明かりも灯っている。
その先、広いエントランスホールの向かいに光源、出口があった。もう身体は限界だった。代償によりボロボロになった身体に鞭を打っていたため、疲労も限界を迎えていた。それでも、たとえ這ってでも突き進んでやる、ホッシーナからはそんな気がいさえ感じられた。
まあもちろん、ホッシーナの脱出劇は呆気無く幕を閉じる。
「はい、おつかれさーん」
ホッシーナは背後から肩をつかまれた。
あの声。あのバケモノ――“救世主”の声だった。
「あんたさぁ、『アキレスと亀』って知ってる? 屁理屈言ってアキレスはいつまで経っても亀に追いつけないっていう、アレ。ウチ、まさにアキレスの気分やったわ。
お前遅すぎ。ウチがその気になれば、200回ぐらいは死んでたで?」
脚が震え、冷や汗が垂れ、奥歯がカチカチ鳴っている。すぐ後ろのバケモノは、まるでドアノブを捻って開けるぐらいに簡単な気持ちで殺すことだろう。
ホッシーナは時間停止のタイミングを図っていた。自分以外のすべてが停止する以上、肩をつかまれているとそこで固定され、身動きが取れなくなってしまう。
身体が離れた一瞬。それに賭けるしかなかった。
「あなたは、何者?」
「誰が質問してええて言うた?」
ギチッ
「あうっ!」
肩をつかむ手に力が込められ、ホッシーナは苦痛に顔を歪める。
みしみしと軋んでいる。折るだの外すだの、そんな甘いものではない。あと1回機嫌を損ねれば、その瞬間粉砕してしまうほどの力だ。
「あんたはウチの質問に答えるだけ。ええな?」
「…………」
「黙るなや。ちゃんと答えてくれるなら、ここから出してあげるで?」
「……本当に?」
思わず聞き返してしまう。だがこれを質問とは受け取られなかったらしく、「ほんまほんま、ハズレには興味ないし」と軽い口調で返ってきた。
もしも(だいぶ希望は薄いが)本当なら、これほど楽なことはない。たとえ(おそらくこちらが本命)嘘だったとしても、とりあえず時間を稼ぐことはできるし、気を逸らすチャンスも生まれるかもしれない。
「最初の……というよりは確認やけど、あんた、時間を止めることができるな?」
「…………」
「『時間停止!』なんて叫んだら誰だってわかるで。そこから辿ると、あんた自身は戦力があらへん。時間を止めることで相手が無抵抗になるのに、攻撃した形跡がなかった、ただ逃げることだけを優先した。
出口があることを知ってたかもしれへんけど、障害を排除したほうが確実に安全、でもしなかった。どうや?」
「……ご名答(本当は時間停止だけじゃないけど、わざわざ言うこともない……)」
「まあそんなことはどうでもええ。ここからが本題。
あんた、超能力者?」
「ええ、そうよ」
時間停止がバレているのなら秘密にすることもないだろう。ホッシーナのこの考えはあまりに浅はかだったのかもしれない。
「なら、伊藤月子ってヤツ、知ってる?」
その名前に、びくんと身体を震わせてしまった。それは肯定したも同じ、“救世主”はニンマリと笑う。
「その反応、知ってるな? あの貧相な身体つきの、性悪超能力者のことを」
「性悪?」
「ウチは昔、その伊藤月子に騙されてここに閉じ込められるようになったんや。だから言うなれば、復讐したいねん。簡単には殺さず、殺してって懇願するところまで虐め抜いてやりたいんや。楽しいやろなぁぁ」
ヒシヒシと殺気、怒気が伝わってきていた。どれほどの恨みを抱いているのか、肌で感じることができた。
「そこでや、あんたが知ってる伊藤月子のこと、教えろや。あいつも超能力者なんやろ?」「…………んっ!」
ホッシーナは違和感を感じた。下半身――ヘソから下が、冷たい。氷のように、とか、恐怖で固まって、などといったチープな表現ではなく、血が通っていない(これもチープな表現ではあるが)ように冷たかった。
「これ、は……?」
自分の身体を見て、ホッシーナは思考が止まってしまうほどに驚いた。冷たいと感じていたヘソから下が石化、無機質なグレー色へと変わり、石になっていたのだ。
「ようやくアイツの手がかりが見つかったんや、逃さへんで」
「この石化な、全身に広がったらもう戻れへん。そこで終わりや」
「でも今ならまだ間に合う」
「伊藤月子のこと、全部教えてくれたら戻してやる」
「それで、さっさとここから出てけばええで」
「さあ」
「お? し? え? て?」
そんなこと、悩むまでもなかった。
「――時間停止」
最後の時間停止を、ホッシーナは使用した。そして下半身は動かないまま、上半身を捻って肘を“救世主”にぶつける。何度も何度も、骨が悲鳴を上げ、筋肉がパンパンに腫れてしまっても、それでも何度も何度も。
「……解除」
代償によって意識を保つことさえままならないホッシーナと、きょとんと目をパチパチさせる“救世主”。
「妙にヒリヒリするんやけど……お前、やったな?」
「ええ、しましたよ。時間止めて、男性たちが好みそうなその身体を殴ってやりました。それが何か? これが、私の答えです」
「お前、自分がどうなるかわかってんのか?」
「わかってますよ。バカじゃないんですから。
もちろん怖いです。生きたいに決まってます。
ですが、私は伊藤月子さんを裏切らない。
あなたは性悪と言った。たしかに、そういう世界の伊藤月子さんはいました。
ですが、ほとんどの世界の伊藤月子さんは、とても優しい。でも他の人たちが彼女の存在を許さない。あなたも、その一人だ」
「言いたいことは、それだけか?」
石化は首元まで進行していた。
ホッシーナは、とっくに覚悟ができていた。
「私はここで終わりでしょうね。
もしかしたら、あなたは伊藤月子さんと会ってしまうかもしれない。
でも、あの人があなたなんかに負けるはずが」
ついに口まで石化し、ホッシーナの言葉が途切れた。
(ごめんなさい……私は、もう)
『ホッシーナ、すべてを思いだせ』
(…………! 伊藤先輩、伊藤)
――ピシリ
ホッシーナの全身はグレーに染まった。
呼吸もない、体温もない。ホッシーナは単なる石像になってしまった。
「はい、バイバイ」
――トンッ
“救世主”が軽く押すと、ホッシーナは倒れ――音と立てて砕け、粉々になった。
【ホッシーナ(タイムトラベラー)――バッドエンド:脱出失敗】
・
・
・
“救世主”は不満だった。
すぐ後ろにいる、得たいの知れない男。その存在が不愉快で堪らなかった。
「で、お前は誰やねん」
「ん、僕? 僕は、そうだなぁ……単なるストーリーテラーだよ」
すたすたと無警戒に“救世主”の隣りを通り過ぎていく。
貧弱すぎる。これが“救世主”の感想。その気になればいくらでも殺せるような相手、それなのに、できない。まるで『何かに命令されているかのように』殺す気が起きなかったのだ。
「ちょっと干渉しすぎたからね、そろそろ僕は退場するよ。すべてが終わるまで、ね」
「すべてが終わる?」
「ああそうだよ。もうすぐ、キミの待ち人が現れる。そのときが、終わりさ」
「さあ、いよいよクライマックスだ」
得たいの知れない男は、軽く手を振って外へと出て行った。
“救世主”は煮え切れない気持ちで、その背中を眺めることしかできなかった。
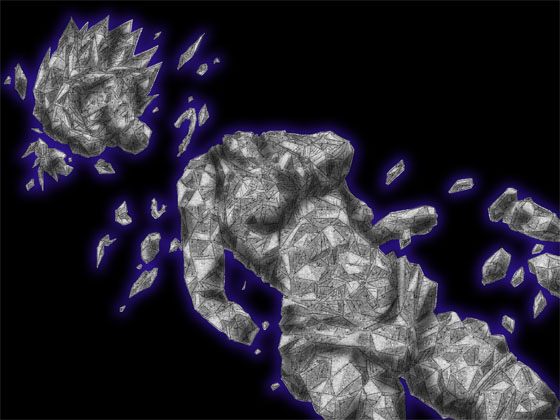
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ “超能力者(レベル1)”の伊藤月子が現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「長かったなぁ……」
“救世主”は、今までにない気配を屋上から感じていた。
いる。屋上に『アイツ』がいる。間違いない、ハズレではない。これまでのハズレたちとはまったく違う、別格のオーラを醸し出している。
“救世主”は、自分が激しく高揚していることに気がついた。
これまで侵入者に対して“戦士”と“バニー”、“魔法使い”の性癖を発散させたこともあった。“学者”の知識で世の理を解明もした。“盗賊”の俊敏さで塔内を駆け巡りもした。どれも自分を興奮させてくれた。けれど所詮は『アイツ』を待つだけの暇つぶし。すぐに虚しさを覚えたものだった。
けれど、今回は違う。胸の鼓動がいつもよりも早い。ドクンと一度鳴るごとに身体が揺れるようで、呼吸も苦しく、体温もやけに高く感じられた。
そう、これはまるで、恋。しかも、初恋のよう……。
相手を想い続け身を焦がす気持ちで待っていたことを考えると、まぁ、恋と言っても過言ではないだろう。
ただ、向けられた感情はひどく混濁、歪曲、邪悪なものだったが。
“救世主”はふと、思う。
――もし伊藤月子を殺したら、自分は何をすればいいのだろう。
考えたことがなかった。復讐心に駆られ、それしか生きる目的がなかった。この長きにわたる復讐劇が終わったとして、塔から脱出できるとは限らない。むしろ出れないだろう(という推測)。
――どうしよう。
改めて思う。
が。
――まあいいや。とりあえず殺そう、そのあとに考えればいいや。
次の瞬間どうでもよくなっていた。
◆ ◆
◆ “超能力者(レベル1)”の伊藤月子が現れました ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「長かったなぁ……」
“救世主”は、今までにない気配を屋上から感じていた。
いる。屋上に『アイツ』がいる。間違いない、ハズレではない。これまでのハズレたちとはまったく違う、別格のオーラを醸し出している。
“救世主”は、自分が激しく高揚していることに気がついた。
これまで侵入者に対して“戦士”と“バニー”、“魔法使い”の性癖を発散させたこともあった。“学者”の知識で世の理を解明もした。“盗賊”の俊敏さで塔内を駆け巡りもした。どれも自分を興奮させてくれた。けれど所詮は『アイツ』を待つだけの暇つぶし。すぐに虚しさを覚えたものだった。
けれど、今回は違う。胸の鼓動がいつもよりも早い。ドクンと一度鳴るごとに身体が揺れるようで、呼吸も苦しく、体温もやけに高く感じられた。
そう、これはまるで、恋。しかも、初恋のよう……。
相手を想い続け身を焦がす気持ちで待っていたことを考えると、まぁ、恋と言っても過言ではないだろう。
ただ、向けられた感情はひどく混濁、歪曲、邪悪なものだったが。
“救世主”はふと、思う。
――もし伊藤月子を殺したら、自分は何をすればいいのだろう。
考えたことがなかった。復讐心に駆られ、それしか生きる目的がなかった。この長きにわたる復讐劇が終わったとして、塔から脱出できるとは限らない。むしろ出れないだろう(という推測)。
――どうしよう。
改めて思う。
が。
――まあいいや。とりあえず殺そう、そのあとに考えればいいや。
次の瞬間どうでもよくなっていた。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 塔から脱出するゲーム2 X
X X
X The LAST GAME X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 塔から脱出するゲーム2 X
X X
X The LAST GAME X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
伊藤月子は、わけがわからないまま塔から降り続けた。
途中から階数を数えることを諦め、進んでは休み、進んでは休みを繰り返し、時には心が折れかかりうずくまってしまったこともがあった。
けれど大切な恋人、そしてタイムトラベラーの友人を思い出し、どうにか自分を震え立たせ、やっと、ようやく、そのフロアに降り立った。
そこには“救世主”がいた。
「一日千秋の想いとは、まさにこのこと」
“救世主”はどこか演技がかった口調で伊藤月子に語りかけた。
ここはすでに1階。“救世主”はあえてモンスターやトラップを配置せず、無傷で伊藤月子を降ろしていた。
理由は2つ。まず、モンスター討伐によるレベルアップを防ぎたかったのだ。負ける気はさらさらないものの、“救世主”は念には念を入れておきたかったからだ。
そして残りの1つが、伊藤月子を殺すのは唯一自分だけ、という奇妙な独占欲。処女性を重んじる思想と似ていなくもないが、やはり少し、奇妙。
(結果だけで言えば“救世主”は伊藤月子の命を何度か救っていることになる。レベル1の超能力者ではこの塔をクリアすることは無理ゲーだからだ)
「ほんまに、どれぐらい待ったんやろか……もう思い出せへんぐらいや」
「あの、あなたは……?」
「忘れたとは言わせへんで。よくもまぁ、ウチをこっぴどく裏切ってくれたもんやなぁ」
(……ぜんぜん知らないし。年下……だよね? 見覚えのない顔だなー……)
と、伊藤月子が困惑するのも無理はない。やさしい塔の伊藤月子と、ここにいる伊藤月子はまったくの別人だからだ(皆さんのよく知る伊藤月子が後者)。
(誰かと勘違いしてる? そんなに私と似てるのかな……?
逆恨みもいいところだけど、この子は……)
伊藤月子は勘違い女(“救世主”のことをそう呼ぶことにした)に出会ってから、ずっと警戒を解いていなかった。
単なる人間ではないとすぐ気づいた。もしかしたら人間というくくりには入らない、別次元の生物かもしれない、そんなファンタジーめいたことを思った。
表情や声のトーンから伝わる感情は実に友好的なものだ。今すぐにでも友人になっていっしょにお風呂に入れそうなほど、明るくて懐っこい、魅力的な少女に見えた。
けれどテレパシーを使ったことでわかる、勘違い女の心中。殺気、憎悪、憤怒……それらがグチャグチャに混ざり洪水のように押し寄せ、ひさしぶりに吐き気を催してしまった。
伊藤月子はこの塔に来てから、ずっと懸念していることがあった。良くも悪くも特技である超能力のコンディションがいまひとつなのだ。
質も精度も全盛期と比べると十万分の1ほどで、もし勘違い女が危害を加えようと襲いかかってきたとしても、身を守る自信がなかった。
「ん? まだ知らんフリするんかいな。そろそろイラってしてきたで?」
なので穏便に事を済ませたいと思っていたのだが、それはどうにも無理に思えた。
(誤解を解く……のは、難しいだろうし、テレポートか、念動力で押さえつけて逃げる、どっちかかな)
「知らんふり続けるんやったら、同じことさせたるからな」
まるで手品のように、“救世主”の右手に短剣が現れた。
「最初は、これやったな」
まばたき以上の速度で、あっという間に詰め寄って伊藤月子の腹に突き刺した。
「は、ぁ?」
一瞬の出来事に伊藤月子の理解が追いついていない。だが痛覚すら届いていない頭は、腹に短剣が刺さっていることだけは認識しているようだった。
“救世主”は刺さった短剣をぐるりと時計方向に捻り、それを引き抜き――
「回復(ヒーリング)」
伊藤月子は短剣を刺される前と何ら変わりがなかった。傷もなければ痛みもない。だが“救世主”が握る、べっとりと血のついた短剣が幻覚でもなんでもない、『刺された』ということが事実だと証明していた。
「はっ、ハッ、ハッ、ハッ、はっ……」
伊藤月子は過呼吸気味に息を鳴らしていた。
まるで目を閉じるように、自然な状態で刺してきた。そしてショック死、体力出血、どちらが早いかわからないが間違いなく死ぬ、その寸前で助けられた。
「どお? 思い出した?」
ニコリと、屈託のない笑みを見て伊藤月子は確信する。
こいつは、異常だ。
しかも重度の。
「ごめんなさい……あなたのこと、本当に、知らないの……」
「次はアレやっけ? 蟲の産卵。でもこればっかりはできひんしなぁ。魔法で生命生み出すのは禁忌やし」
“救世主”は伊藤月子の左手をつかんだ。伊藤月子はその凄まじい握力を振り払えず、刺された動揺、パニックが続いていて超能力を使うこともできない。
「綺麗なお手々やなぁー。小さくって、すべすべしてて……この爪なんて、すごくキラキラしてる」
「離して、痛いっ!」
「知らんぷりする悪い子は、ちょぉっとお灸を据えんとあかんよなぁ」
“救世主”は、伊藤月子の薬指の爪をつまんだ。
「ちょ、ちょっと……!」
これから起こることがわかってしまい、伊藤月子は顔を青くする。
普通なら「そんなことするはずがない」と高をくくれるようなことも、目の前の相手なら平気で行うからだ。
「なーに、まだ一枚目や。せーの」
――ベリッ
「ぎっ」
爪が、剥がれた。あいかわらず状況だけは冷静に見ることができた。
「ぎゃああああああっ!」
先ほどとは違い、痛みは指から脳内へ一気に駆け抜ける。
なんとも汚い声で叫び泣き喚く伊藤月子。常々超能力で身を守ってきた伊藤月子には耐え難い激痛、倒れてしまいそうになったが、腕をつかむ“救世主”がそれを許さない。
“救世主”は剥がした爪をまじまじと見て、それを口の中に放り込んだ。
ポリ、ポリ。何度か咀嚼したのち、顔を渋くして床に吐き出した。
「見た目はスライスアーモンドなのに不味いこと不味いこと。食欲失せてもうたわ」
(イカれてる……狂ってる!)
今は遊ばれているだけで、その気になれば呆気無く殺される。
(もう、やるしか……)
伊藤月子は自らがずっと封じ込めていた、『ある目的』のために超能力を使う覚悟を決めた。
ミシッ
「お?」
“救世主”は首に違和感を覚えた。
締まる。荒縄をグルグルに巻かれたように、締まっていく。それも、凄まじい力で!
「なんだ、これ……え、うええええエエエエ」
首を締める正体、それは伊藤月子の念動力。
超能力で命を奪う。これこそが、伊藤月子がずっと禁じていた超能力の用途だった。
「おおお、グオオオ、オ」
締めるだけでなく、ねじ切って確実に息の根を止めようとしていた。“救世主”はたまらず伊藤月子の手を離し、両手で頭を抑えた。伊藤月子は“救世主”から距離を取りながらも、睨んだまま念動力を発し続ける。
見えない一進一退の攻防。それは程なくして決着がついた。
「そんな……なんで……」
伊藤月子は力尽きたように、床に崩れ落ちる。“救世主”はというと、首筋がひどくうっ血していたがニタニタと笑うほどの余裕はあるようだった。
「いやぁ、危なかった。あとちょっと、ほんのちょっとだったのになぁ。紙一重だぁ……何キロメートルぐらいあるかなぁ、この紙一重」
楽しそうに、愉快だと言わんばかりに、伊藤月子を見下ろす“救世主”。伊藤月子はそれを睨み返す体力さえなかった。
せめて全盛期で千分の1でもあれば――と、伊藤月子は思ってしまう。
「なあ、起きろよ」
「い゛、いたいっ!」
黒髪をぐいっと引っ掴み、“救世主”は伊藤月子を引き起こした。ぶちぶちと痛々しい音が聞こえるが、気にするはずもない。
伊藤月子はたまらず、震える脚でどうにか立ち上がった。
「お前、もっとその気になれや。でないと張り合いないやろぉ?」
「どうして、こんなこと……!」
「だーかーらー、あのときの復讐やん」
会話も成立しない。
超能力も通じない。
なら。
――べちっ
「あたっ」
逃げるしかない。
伊藤月子が振り払った平手は“救世主”の顔面に当たった。
ダメージはなかったものの“救世主”は反射的に目を閉じてしまった。その瞬間、髪を掴んでいた手がふっと軽くなった。
「……ん?」
残っていたのは一束の黒髪。伊藤月子はどこかへ消えていた。
「そうか、逃げたか」
自ら髪を切って、逃げた(おそらくテレポートで)。髪とはいえ、かなり捨て身の逃走だ。
「それぐらい頑張ってもらわないとなぁ」
逃げ場所の目星はついている。ゆっくり、ゆっくり追い詰めよう。そしてその間に処刑方法を考えよう。
“救世主”の笑いは止まらない。
・
・
・
・
・
「はぁっ……はぁっ……」
咄嗟にテレポートしたため、床よりやや高い位置に現れてしまいそのまま落下してしまった。幸いケガはなかったが、初心者のようなミスをしてしまうほど焦っていたのだろう。
もともとテレポートは負担の大きい能力の1つで、床に倒れたまま起き上がれなくなってしまった。
逃げたい気持ちだけが先行してしまっている。出口がどこにあるかもわからないし、今どこにいるかもわからない。それに勘違い女がどこまで迫っているかさえも……
「はぁ……はぁ……」
伊藤月子はぐったりと伏せてしまう。ひそかな自慢だった髪を切ってまで逃げたが、そこから先のことを考えていなかった。
ひとまずは、勘違い女がやってこないことを祈るしかない。
――それにしても。
伊藤月子は、床に散らばる小石がやけに気になった。大小それぞれの石が、そこら中にばらばらと撒き散らされているのだ。
寝転がっているため、チクチクと肌に食い込んで痛い。
ふと、目の前にあった小石を握った。
――バチンッ
『私は伊藤月子さんを裏切らない』
静電気が走ったかと思えば、ある光景が脳裏に過ぎった。
よく知る女性が、身体の半分が石になりながらも勘違い女に啖呵を切る、そんな光景。
これはサイコメトリー。物体の残留思念を読み取るという能力。
勝手に発動したことは不思議だったが、そんなことはどうでも良い。伊藤月子は、目に見えた光景の女性に驚きを隠せなかった。
「ホッシーナ……!」
見覚えのある女性――それは、同じ超能力者のホッシーナだった。
半身が石化していたホッシーナ、そして散らばった石。それは簡単に結びついた。
「やだ、そんな……」
『これが、私の答えです』
『ほとんどの世界の伊藤月子さんは、とても優しい』
『あの人があなたなんかに負けるはずが』
触れるたびに光景が再生され、最悪の瞬間――完全に石化し、倒れて砕けてしまうシーン――も見てしまい。伊藤月子は涙を抑えることができなかった。
やや離れたところに、一際大きな石の塊があった。
顔。
顔が転がっている。
「ホッシーナ……」
小石で身体が傷つくことも忘れ、這って進む。
石となったホッシーナの首から上が、そこにあった。
――バチンッ
『伊藤先輩……できれば、これをサイコメトリーしていないことを祈っています』
声だけが聞こえていた。おそらく、目を閉じて最期を迎えたのだろう。
『おそらく、私はもう石像になっていることでしょう……もしかしたら、粉々にされているのかもしれません。
これが遺言になると思うと、とても悲しいです……』
『伊藤先輩。これを見ているとき、あなたはあのバケモノに出会ったと思います。
あのバケモノは、伊藤先輩に凄まじい憎しみを抱いています』
『もし伊藤先輩が、私と同じように万全の状態でなければ……逃げてください。まだ扉が開いているかわかりませんが、このサイコメトリーを解いて、脱出してください』
『私はダメでしたが……どうか、伊藤先輩だけは……
……こんな私のメッセージ、聞いてくれてありがとうございました。
さようなら、伊藤先輩』
ここで、声は止まった。
けれど伊藤月子は手を離さない。
「ウソ。ホッシーナ、ウソついてる」
伊藤月子が知るホッシーナはこんなしおらしく女性ではない。狡猾で、自分の身体の魅力を理解していて、恋人を横取りしようとする悪女(演技ではあったが)なのだ。
そんな女が、メソメソと引き下がるはずがない。むしろ別の言葉を残すはずだ。
サイコメトリーを解かないまま、待った。
すると、フフッと、ホッシーナの笑い声が続いた。
『伊藤先輩には敵いませんね……さっさと逃げちゃってくださいよ……』
「ダメだよそんなの……私は、ホッシーナの言葉を最後まで聞きたい」
『伊藤先輩……私は、悔しい。あのバケモノにいいようにされて、こんなことになってしまいました……復讐は何も生みません、同じことを考えているだけ、それぐらいのこと、わかります。
でも、すごく、悔しい』
「私も許せないよ……でも……」
今のままではどうしようもない。全力の念動力でさえ通じなかった。
そんな伊藤月子を慰めるように、ホッシーナの言葉は続いた。
『私の時間操作の能力を、少しだけ残しておきました。
さあ、あのときまで戻りましょう、伊藤先輩』
……あのとき?
伊藤月子はその言葉にピンと来ない。
ただ、なんとなくわかる。
ここに来る前の、自分と、恋人と、ホッシーナと、あと誰か1人がいたお話の時だ。
『私の知る伊藤先輩は、ときどき怖くもありましたが、とても優しい人でした。
あなたは、あんなバケモノになんて負けない。ぜったいに、負けません』
『思い出して』
・
・
・
・
・
「ここに来るまでに、考えてみた」
エントランスホールの入口で“救世主”は言った。
伊藤月子は背を向けたまま、一本の棒のように立ち尽くしていた。
「もしかしたらお前は、ウチの知る伊藤月子じゃないのかもしれない」
出口は完全に封鎖していた。伊藤月子がここにいることも、“救世主”は最初からわかっていた。
身体の芯まで恐怖を植えつけたい、そんな歪んだ想いで“救世主”はあえてゆっくり来たのだ。
「もしかしたらお前は、このへんに転がってる石の超能力者が言うように、いいヤツなのかもしれない」
ぴくりと、伊藤月子の指が動いた。その反応に“救世主”は嬉しさを堪え切れない。
「たとえば、いっしょにご飯を食べたり、遊んだり……そうやなぁ、お風呂とか入ったりしたら楽しいかもしれない。
案外、すごく仲良くなって良い友達になれるかもしれない」
「――でも、殺す」と、“救世主”は間髪入れずに言う。
「ウチは、どうやってもお前のことが」
ぷつんっ
「アッ?」
“救世主”の右腕が、鋭利な刃物を使ったように斬れ、落ちた。
ぶつんっ!
次は首。あれだけ頑丈だった“救世主”の首が、まるで紙を引き裂くように軽々と宙に浮いた。
「……おいおいおい、おい」
すぐに復活した“救世主”は問う。その表情は、まるで子供のように無邪気で、どこか残酷だった。
「お前、どうしたんだ? まるで別人のようじゃないか!? それも超能力の1つなのか!?」
「私は、私だよ」
ぶつんっ!
また、浮いた。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 伊藤月子は本来の自分を思い出しました X
X X
X 超能力が元に戻りました X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X 伊藤月子は本来の自分を思い出しました X
X X
X 超能力が元に戻りました X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「私は、こんなことに超能力を使いたくない。
でも、あなただけは許さない。許せない!」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ 伊藤月子 ◆
◆ ◆
◆ “超能力者(レベル1)” → “超能力者(レベル99999)” ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆ ◆
◆ 伊藤月子 ◆
◆ ◆
◆ “超能力者(レベル1)” → “超能力者(レベル99999)” ◆
◆ ◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「はぁっ――」
“救世主”の首から上が復活した瞬間、彼女から見える景色は線になった。
超高速で動いているときのような、周囲の光景が糸のように細くなり消えていく、そんな感覚。
ただ違う点があるとすれば、自分で動いているわけではない、誰かの力で動かされている――コンマ数秒の中で“救世主”は状況を把握した。
ドンッ!!!
「……んなっ」
止まった景色が上下左右前後にガタガタと揺れ、続いて左半身に激痛が走った。手や脚、脇腹に肩、通常なら動かすことのできる骨、筋肉などの部位は木っ端微塵に壊れてしまっているようだった。
だが『そんな程度』の負傷は、わざわざ“救世主”が心配するほどのものではない。“救世主”からすれば取るに足らない軽傷だからだ。
ただ、取るに足る問題が“救世主”を驚愕させ言葉を失わせていた。
塔の壁が、大きくえぐれている。
凄まじい力で壁に激突させられたのだろう。そして、その力を働きかけた存在は目の前にいるブチギレた超能力者。
(ウチが、あれだけぶっ叩いても傷一つつかなかった壁が、こうも簡単に壊れる、だと……!?)
――ミシッ
「うっ、ぐぅぅぅぅ!」
さらに右半身から力がかかり、壁に押しつけられた。すでにズタボロの左半身は壁と同化するようにグチャグチャとすり潰されていく。
「お前の足元、ホッシーナの破片があるから、ちょっと移動してもらったよ」
伊藤月子は“救世主”に人差し指を向け、冷たく言い放った。
突きつける人差し指を右に動かすほど、“救世主”はどんどんと壁に埋まっていった。
「ぐはっ、この、このぉぉぉぉ!!」
「あまり騒がないで、うるさいから。それとも、こんな“指遊び”が苦しいのかな?」
「……こ、のっ!」
不可視の力に逆らうほど、無傷な右半身にも傷を負っていく。けれど伊藤月子の言葉が癪に触ったのだろう、“救世主”は身体の損壊を気にもしない。
「うぐぉ、うお、うおおおおおっ!」
ついに念動力を押しのけ、“救世主”は壁から離れることができた。左半身は当然のこと、右半身も粉砕してほぼ元の姿を残していない。
しかし先ほども言ったとおり、このぐらいの負傷は取るに足らない問題なのだ。まるで逆再生のように身体は癒え、あっという間に元通り。
“救世主”が回復している間、伊藤月子は人差し指を折り曲げ、今度は手を大きく開き、手のひらを向けていた。
「はは、たいした超能力やないか。おもしろぉなってき」
――ぐちゃっ
伊藤月子が手を握ると同時に、“救世主”の上半身はペースト状に変化した。べとべと、ドロドロな極赤の、苺ジャムにも見えないことのない“元”上半身は床に降り注ぎ、そこにできた血だまりに残った下半身はベチャリと倒れた。
さすがにここまでの破損は深刻な問題なのだろう、“救世主”が復活するまで少々の時間を要した。時間にすれば数秒、これまで一瞬で回復、復活していたことを考えると、このダメージがいかに深刻なものだったかを物語っている。
「……おい、さすがにこれはキツかったで。いつもより復活が大変やったやないか」
「ふーん、やっぱり」
「あ?」
「いろいろと『視て』みたんだけど、やっぱりお前、人間じゃない。特に魂の数……ウジャウジャと、どれだけあるんだろう。見当もつかない。
普通なら致命傷、即死するようなダメージも、その魂を消費して回復しているんだね」
「(なんや、見えるって……残機が見える? 形として、見てるって言うんか?)」
「もしも不死身で、いくらでも復活するのならすぐに脱出したけど……でも、そうじゃないみたいだね。確実に、魂の数が減ってる。
ということは、底はある。いずれ魂のストックがゼロになるときがくる。だから」
「お前が完全にくたばるまで、殺し続けることにするよ」
この伊藤月子の言葉に“救世主”は違和感を覚えた。
身体が芯から冷たくなっていくような、感覚。楽しいと思っていたことが、ふと冷静になってみれば実にくだらない、幼稚なことだったと自覚してしまう――そんな、心のブレ。
(頭に上っていた血が下りてきたんかな。なら、ここからやな)
“救世主”は両手にハンドガンを創り、伊藤月子に向けて発砲。伊藤月子はそれを念動力で受け止め、弾丸は着弾する寸前で宙で止まり、ギュルギュルと回ったのちに完全に停止した。
1発だけでなく、何発も何発も撃ち込む。ノータイムでいくらでも弾丸を創り出すので途切れることがない。もはや両手にアサルトライフルを持っているような“救世主”。ただ“救世主”にとって、これはめくら撃ちみたいなものだった。とりあえず狙いはするものの、当たるはずがない、どうせ超能力で防がれるだろう、ぐらいの攻撃だった。
ただほんの一瞬、気を逸らすことができれば良かったのだ。
「…………っ」
弾丸はカーテンように敷き詰まり、伊藤月子の視界からは“救世主”が見えなくなった。
そう、“救世主”はこの瞬間を待っていた。
「ハッハッー! いただき!」
“盗賊”の身体能力で接近、“魔法使い”の最大火力の魔法を至近距離で伊藤月子に放つ。
いや、放とうとした。
「ハー……!」
魔力を溜め込んだ両手が、手首さら先が、なくなっていたのだ。後ろでボトンと、重量感のある音が聞こえた。
きっと、消えた両手が落ちた音なのだろう。両手首からざぶざぶと溢れる血を見て、“救世主”は思った。
「『透視』。通常なら死角だったかもしれないけど、私には視えるよ。全部ね」
弾丸のカーテンの向こうから声が聞こえた。
「これ、返すね」
そう言って、宙に静止していた弾丸のすべてが“救世主”に向き、初速のまま“救世主”へ帰った。
隙間なく、しかもすべて同じ速度の弾丸のカーテンは壁となり、“救世主”を欠片も残さず消し飛ばした。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X
X “救世主”は消滅しました X
X X
X 残機を10消費して復活します X
X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
「なんやねん、いったい……」
減った残機の数はなんとなくわかる。けれど残機の数まで“救世主”は把握していなかった。
先ほどの身体の芯から冷たくなるような感覚もそうだったが、“救世主”は致命的な感情が欠落していた。
・
・
・
・
・
“救世主”は『恐怖』を知らない。
『身体が芯から冷たくなっていくような、感覚』。あれは、伊藤月子に対して心底恐怖していたのだ(敗北感と言っても良い)。
『恐怖』を知らないから、残機の総数を把握しない。相手を警戒することもない。相手の力量に白旗を上げる発想も生まれない。もっと言うなら、相手の攻撃に対して防御する、という反応さえお粗末なもの。
まあ、“救世主”はこれまで敵らしい敵に会ったことがなく、5人の平行世界の自分たちにも(援護はあったものの)勝利し、恐怖を覚えるタイミングなんてなかったのだ。
「アア、ああああああああ!!!!!」
念動力で浮かされた“救世主”は、バリバリと縦に引き裂かれた。
ある時は発火能力で炭となり、ある時は超電磁砲で撃ち抜かれる。物理的に殴られ首から上が吹き飛んだこともあった。
傍から見れば、“救世主”の勝機なんて一厘もなかった。剣技も、魔法も身体能力も戦略も、どれ一つとして伊藤月子の超能力には及ばない。伊藤月子は汗一つかかず、まるで作業のように“救世主”に攻撃し続けていた。
これだけワンサイドゲームになっているにもかかわらず、“救世主”は自分が遥かに劣っていること、万に一つ勝てる可能性がないこと、(伊藤月子が見逃すとは思えないが)ずいぶん前に逃亡しなければならなかったこと、それらに気づくよしもなかった。
「少しずつ、回復する速度が落ちてきたね。魂ももう、数えるほどになってきた」
「(残機が、そんなに……!?)」
ケガの治癒が追いついていないことは自覚していた。が、残機が数えることができるほど減っていたことに驚きを隠せない。
今まで、残機があったから復活できていた。それがなくなれば――
「死んじゃうだろうね」
伊藤月子は“救世主”の心中の続きを言った。
次にオーバーキル(過剰なダメージのこと)を受ければ、一度に残機を大量に消費する。もしかしたら、もうオーバーキルに耐え切れるほど残機が残っていないかもしれない。
「あとね、4つ。今までの感じからだと、身体の三分の二に致命傷が与えられたら、それで終わり」
『終わり』=『死』
“救世主”はようやく自覚する。
もしかしたら、死ぬかもしれない、と。
「……さて」
がしっ。伊藤月子の手が“救世主”の顔をつかむ。
伊藤月子自体はさして握力はない。しかし、超能力が加わりミシミシと、“救世主”の顔を万力のように締めつける。
「さっきも言ったとおり、私はあなたを許さない。気は乗らないけど、殺す。
……死んじゃう前に、何か一言ぐらい、聞いておいてあげる」
伊藤月子は、決して驕っていたわけではない。もともと殺戮のために超能力を使用することに躊躇し、いざ使ってみれば一方的な虐殺となってしまった。この『何か一言』は、伊藤月子なりの情けだった。
「……ウチ、もうこれで終わりなん?」
「終わりだよ。もう、ここまで。呆気無く感じるけど、私は、それでいい」
「はー、そっか。そやなぁ……信じてくれるかわからへんけど、一言、謝っておきたい。手、離してくれる?」
伊藤月子は言われるがまま、掴んでいた手を離した。そのとき、“救世主”と目が合った。
じーっと見つめる“救世主”に、伊藤月子もつい目を合わせてしまい、逸らせなくなってしまう。
“救世主”は、伊藤月子に対してニコリと、笑みを向けた。
「魅了(チャーム)」
「そんなことだろうと思った」
“救世主”が魅了(チャーム)を放つよりも早く、伊藤月子は目を閉じていた。
「なん……何で、わかるんだよ!? ウチの行動を、回避の仕方を!」
「『テレパシー』。対象の心理を読み取る超能力だよ。油断させようって魂胆が丸聞こえだったよ。もっとも、これは最初っから使っていたけどね」
これで、“救世主”が持つすべてのスキルが通用しなかったことになる。
がしっ。伊藤月子の手が再び“救世主”の顔をつかむ。
“救世主”は、抵抗もしない。
ようやく、心が折れた。
――ボンッ!
【立川はるか(救世主)――ハッピーエンド:安らかな眠りを】

