駃騠を放棄
ケッテイヲホウキ
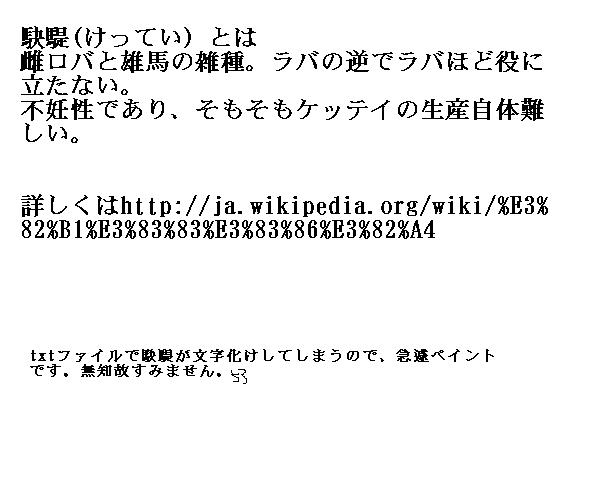
高校生活は、無駄極まりない。つまりは、俺のような人間にとって学校は無駄な時間を消費させられる場所でしかないのだ。クラスで話す人間が居ない、身の置き場がない、勉強なんか自習の方が捗る、部活に所属していない。そんな人間に学校は厳しい場所だ。下衆しか居ない場所なんか俺の居場所じゃない。掃き溜めに鶴とまでは言わないけれど、烏合と交わり合いたくなんかない。
早く高校生活を終えて大学に行きたい。大学だったらもう少しマトモな人間に絞られるだろうと、希望を持つことで今を生きる。
イヤホンから今度歌おうと思っている歌が流れてくる。多少早口な所があるから、滑舌と音程に気を付けて、ここのハモリはどうするか、とぼんやり考える。周りから朝なのにテンションの高い声が聞こえる。ガチで、やべぇ、うける、お前らは言葉を三つくらいしか知らないのかよと溜息をつく。高血圧なのだとしたら、全員脳出血で死んでしまえ。
歌うという一点において、俺は俺を保っている。某動画サイトで歌い手という奴になって早数ヶ月、凄いマイリス数を記録した一動画を機に、俺の名前は多少周知された。それで生放送をやってみたり、ツイッターをやってみたりしたところ、多くの人が俺に声をかけてくれるようになった。学校で爪弾きに合っているのに、学校ではほとんど喋れないのに、俺の声を聞いて好きになってくれる人間が大勢居る場所、それが俺の本当の居場所だった。だからこそ、学校はゴミで、屑で、下らなくて、無駄だ。
十月上旬。後期も始まって一ヶ月経ち、夏休みボケも冷めてきた頃。丁度体育祭も終わり普段に戻り始めた頃、俺のクラスに季節外れの転校生が来た。
前日から話題になっていたそいつは、先生に連れられて教卓の横に立った。
「平田理沙です。よろしくお願いします」
簡素な自己紹介の後、にこっと笑っただけでクラス中が沸き立つのがわかった。
平田理沙という名前の美少女だったからだ。全てのパーツが小さく、白いのに目だけ大きく、整った顔をしていた。細長い足は短いスカートに似合っていた。クラスのブス共はあれを見て何か感じてくれないものか。お前らの大根足なんて見苦しさしかない。
担任のハゲは平田さん視力は大丈夫かな、と幼稚園児に話しかけるような声で聞き、一番後ろの端、俺の隣に彼女を配置した。一気に視線がこちら、いや俺じゃなくて彼女だろうが、に集まる。
「よろしくね、えっと、名前教えて?」
「…………内間」
ぼそっと呟くと、彼女はよろしく内間君と再度挨拶をした。俺は無言で会釈をした。
確かに美人だ、芸能人で居そうな顔をしている。何だっけ、よくまとめサイトとかで取り上げられている子。その子に似ている。ただ俺とは関わりあうことは無いだろう。隣の席ってだけで因縁つけられる可能性だってある。理不尽な話だ。
そのまま特に会話は続かなくて、授業が始まった。俺はぼんやりと先生の話を右から左に聞き流しながら、ノートに歌詞を書いた。歌う予定のやつだ。歌詞は暗記しないと。その歌詞を消して、今度は落書きをした。某キャラクター、所謂俺の嫁というやつだ。書きなれたそれは当初に比べれば幾分か上手くなった。
チャイムが鳴って、俺は急いでそれを消した。さらば嫁。結構上手く書けたのに。
休み時間になると俺の隣、彼女の席に男女それぞれ派手な奴等が群がった。どこから来たのー、部活どこ入るのーだとか、それ知ってどうすんだよと悪態を吐きたい質問が続き、机から立ち上がった。騒がれるすぐ横に居るのは不快だ。トイレ行って多少時間潰して来よう。
トイレに向かって歩いている途中、後ろから、ねぇ、待って、という声が聞こえた後、内間君という声と共に肘の辺りの制服を、それと共に肘の肉を掴まれた。一瞬腕が、全身が震えた。
振り向くと、平田理沙が立っていた。廊下を歩いている生徒の多くがこちらを見てくる。何の用だ、お前に声をかけられることで俺まで注目を浴びてしまうじゃないか。
「あの、内間君って、東方とか好き?もしかしてニコニコとかイケる人!?」
笑顔でそう聞かれて、何を言っているかわからなかった。彼女のような人間から飛び出す言葉じゃないものが飛び出してきた。必死に頷くと、彼女はマジで!と笑顔で喜んだ。
何が起きているのかよくわからなかった。何故この女は俺に話しかけているのか、何故笑顔なのか、何故話しかけて喜んでいるのか。廊下で固まっている俺は周囲から奇異な目で見られているだろう。
「あのね!私もニコニコ好きなの!ニコ厨と出会えてガチで嬉しい!」
彼女はそんな俺の様子も気にせず一方的に話しかけてくる。だから嫌なんだよこういう系の女は。俺はこう注目されるのが嫌いなのに。
彼女が興奮して色々話しかけてくる言葉に相槌をうっていたら、急にごめんねと言って俺は解放された。周囲の目も少し離れたところで、バツが悪いながらもトイレに向かう。用を足している間は気が気じゃなかった。どう教室で避けるかが問題だと思った。
俺だってあんな可愛い子に近づいて来られれば嬉しいが、教室での立ち位置を考えると、微妙だ。彼女と共にうざい奴らが俺を囲ったりしたら不愉快この上ないことになる。あいつらの思考回路は理解不能だから近寄りたくすらない。
「あー俺はDクラ羨ましいけどなー。何あの可愛い子、久しぶりに三次元良いかもって思いそーになった」
「思ってねーんだ?」
「思ってねー」
高原康友は笑って前歯をむき出しにした。彼の前歯は彼の顔に似合わずはみ出ている。矯正すりゃいいのにと思うが口にはしない。
結局あの後平田理沙は終始クラスの奴らに囲まれて、俺の元に来る事は無かった。放課後には他の女に引きずられるように体育館に向かっていた。えー理沙バスケしてたのー?、じゃー一緒一緒ー、マジで、平田バスケ部入んの?俺もバスケ部!、セージうっさい、こいつガチでうぜーから気ぃ付けなよ理沙ー。数時間で呼び捨てにまで進化するあいつらは凄い、新人類、未知生物だ。イヤホンの隙間から聞こえる雑音に溜息をついて立ち上がって、康友と一緒に学校を出た。
俺が学校で話す唯一の友達。クラスは隣で体育とかは一緒になるがそれ以外は別々だ。一年の時も隣のクラスで仲良くなって、二年の文理選択時に別れてしまったが、結局は隣のクラスになった。朝と夕方、駅までの十五分は何かお互いに予定が無い限り一緒に帰る。俺も康友もクラスに友達は居ない。康友は話す奴くらいは居るみたいだが。二人共帰宅部で、二次元が好きで、ゲームが好きで、ネットが好きで、要するに引きこもり体質だ。
きっと康友も何かで自分を保っているんだろうと勝手に思っている。康友にさえ歌い手の事は言っていなかった。ただ互いに知っている。俺は良い声をしている事、康友は凄いギターが上手い事。友達が居ないためにカラオケには行かず康友以外知らないこと、他に目付けられるのが嫌でギターを学校には持ち込まず俺以外知らないこと。
「ガチいい加減にして欲しいんだよな、明日話しかけて来たらどーすりゃいいんだよ。俺の立ち位置壊すなつー話だよ」
「ああいうリア充は理解してくんねーよ、聖也ごしゅーしょーさま」
「おはよう、内間君!」
昨日の懸念通り、席に着いてすぐ話しかけてきたのは平田理沙だった。俺が来たのを見計らって女の集団から抜け出て来たみたいだ。大人しく会釈すると、彼女はちょっとだけ物怖じして、一呼吸くらい空白があってから、笑顔に戻った。廊下で付けたイヤホンを外す。
「ねぇねぇ、内間君はどんな音楽聞く感じ?何聞いてたの?理沙は懐古厨だからさーやっぱ名曲最高って感じで!うん、で内間君どんなの聞く?ボカロ?アニソン?東方?それともロキノン系のやつとか?」
「……まぁ、全般的に……」
こんな所でボカロとかアニソンとかいう単語口に出す神経がわからない。目を机に向けて鞄から教科書を取り出しながら答えると、右端にスカートがちらちらと見える。
「そっか、全体的にわかる感じ?最近ハマってるのとかある?」
「いや……特には」
俺が広がりようのない返答をしておいたのに、彼女は次々と話しかける。適当に相槌のようなものを打っているだけで、話は広がっていく。彼女の今はまっているボカロ曲、好きなP名、今期チェックしているアニメ、東方の好きなキャラ、すらすら出てくるその姿に本当に好きなんだなと疑いを捨てる。鞄の中身を出し終え、席に座った俺は目を反らす道具が無くなって、彼女の首元を見つめる。流石に目は合わせられないし、胸元を見ていたらキモい等言われかねないからだ。白い首が面白いように動く。彼女は机に手を付いて、覗き込むように話を続けた。
「でね!マイリス管理して……ってごめんね、何か凄い理沙ばっかり喋ってるね、もうすぐ予鈴だし!つい嬉しくて!今度遊ぼうよ、アキバとか行こう!」
「……はい、機会があれば」
「うん、また声かけるね!」
女の集団に戻っていく姿だけ見れた。笑顔で手を振っていて、そんなに俺との会話が楽しかったのかと、とりあえず解放されたことに一先ず安心する。すぐにイヤホンを付け直した。ボリュームを上げる。絶対あの女集団が俺の事を何か言っているのがわかるから。ヲタクキモくないとか、暗いとか、デブとか、不細工だとか、随分な事を言ってくれているに違いない。うるせぇよ公衆便器の性格ブスが。
次の日の休み時間も平田理沙は来た、好きな歌い手の話をした。その次の日も平田理沙は声をかけてきた。その次も、その次も、その次も。俺は平田理沙の好みと携帯とフェイスブックのアドレスと癖を把握した。流石に土日はメールを何通かやり取りをするだけだった。絵文字が沢山入ったメールは今まで見たどのメールよりも輝いていた。そんな彼女に捕まって、大分学校での生活は様変わりしてしまったのだが、学校のある間はあまり呟かないようにしていたのなんかが幸いして、俺のオンでの活動に支障は無かった。
土日はそんなメッセージを横目に録音をして、新曲をアップした。直ぐに数十のマイリスが付いて、徐々にマイリス数は増えた。これから先の休み時間なんかは再生数とマイリス数の確認、通知メールで少しは楽しみが出来る。
早く高校生活を終えて大学に行きたい。大学だったらもう少しマトモな人間に絞られるだろうと、希望を持つことで今を生きる。
イヤホンから今度歌おうと思っている歌が流れてくる。多少早口な所があるから、滑舌と音程に気を付けて、ここのハモリはどうするか、とぼんやり考える。周りから朝なのにテンションの高い声が聞こえる。ガチで、やべぇ、うける、お前らは言葉を三つくらいしか知らないのかよと溜息をつく。高血圧なのだとしたら、全員脳出血で死んでしまえ。
歌うという一点において、俺は俺を保っている。某動画サイトで歌い手という奴になって早数ヶ月、凄いマイリス数を記録した一動画を機に、俺の名前は多少周知された。それで生放送をやってみたり、ツイッターをやってみたりしたところ、多くの人が俺に声をかけてくれるようになった。学校で爪弾きに合っているのに、学校ではほとんど喋れないのに、俺の声を聞いて好きになってくれる人間が大勢居る場所、それが俺の本当の居場所だった。だからこそ、学校はゴミで、屑で、下らなくて、無駄だ。
十月上旬。後期も始まって一ヶ月経ち、夏休みボケも冷めてきた頃。丁度体育祭も終わり普段に戻り始めた頃、俺のクラスに季節外れの転校生が来た。
前日から話題になっていたそいつは、先生に連れられて教卓の横に立った。
「平田理沙です。よろしくお願いします」
簡素な自己紹介の後、にこっと笑っただけでクラス中が沸き立つのがわかった。
平田理沙という名前の美少女だったからだ。全てのパーツが小さく、白いのに目だけ大きく、整った顔をしていた。細長い足は短いスカートに似合っていた。クラスのブス共はあれを見て何か感じてくれないものか。お前らの大根足なんて見苦しさしかない。
担任のハゲは平田さん視力は大丈夫かな、と幼稚園児に話しかけるような声で聞き、一番後ろの端、俺の隣に彼女を配置した。一気に視線がこちら、いや俺じゃなくて彼女だろうが、に集まる。
「よろしくね、えっと、名前教えて?」
「…………内間」
ぼそっと呟くと、彼女はよろしく内間君と再度挨拶をした。俺は無言で会釈をした。
確かに美人だ、芸能人で居そうな顔をしている。何だっけ、よくまとめサイトとかで取り上げられている子。その子に似ている。ただ俺とは関わりあうことは無いだろう。隣の席ってだけで因縁つけられる可能性だってある。理不尽な話だ。
そのまま特に会話は続かなくて、授業が始まった。俺はぼんやりと先生の話を右から左に聞き流しながら、ノートに歌詞を書いた。歌う予定のやつだ。歌詞は暗記しないと。その歌詞を消して、今度は落書きをした。某キャラクター、所謂俺の嫁というやつだ。書きなれたそれは当初に比べれば幾分か上手くなった。
チャイムが鳴って、俺は急いでそれを消した。さらば嫁。結構上手く書けたのに。
休み時間になると俺の隣、彼女の席に男女それぞれ派手な奴等が群がった。どこから来たのー、部活どこ入るのーだとか、それ知ってどうすんだよと悪態を吐きたい質問が続き、机から立ち上がった。騒がれるすぐ横に居るのは不快だ。トイレ行って多少時間潰して来よう。
トイレに向かって歩いている途中、後ろから、ねぇ、待って、という声が聞こえた後、内間君という声と共に肘の辺りの制服を、それと共に肘の肉を掴まれた。一瞬腕が、全身が震えた。
振り向くと、平田理沙が立っていた。廊下を歩いている生徒の多くがこちらを見てくる。何の用だ、お前に声をかけられることで俺まで注目を浴びてしまうじゃないか。
「あの、内間君って、東方とか好き?もしかしてニコニコとかイケる人!?」
笑顔でそう聞かれて、何を言っているかわからなかった。彼女のような人間から飛び出す言葉じゃないものが飛び出してきた。必死に頷くと、彼女はマジで!と笑顔で喜んだ。
何が起きているのかよくわからなかった。何故この女は俺に話しかけているのか、何故笑顔なのか、何故話しかけて喜んでいるのか。廊下で固まっている俺は周囲から奇異な目で見られているだろう。
「あのね!私もニコニコ好きなの!ニコ厨と出会えてガチで嬉しい!」
彼女はそんな俺の様子も気にせず一方的に話しかけてくる。だから嫌なんだよこういう系の女は。俺はこう注目されるのが嫌いなのに。
彼女が興奮して色々話しかけてくる言葉に相槌をうっていたら、急にごめんねと言って俺は解放された。周囲の目も少し離れたところで、バツが悪いながらもトイレに向かう。用を足している間は気が気じゃなかった。どう教室で避けるかが問題だと思った。
俺だってあんな可愛い子に近づいて来られれば嬉しいが、教室での立ち位置を考えると、微妙だ。彼女と共にうざい奴らが俺を囲ったりしたら不愉快この上ないことになる。あいつらの思考回路は理解不能だから近寄りたくすらない。
「あー俺はDクラ羨ましいけどなー。何あの可愛い子、久しぶりに三次元良いかもって思いそーになった」
「思ってねーんだ?」
「思ってねー」
高原康友は笑って前歯をむき出しにした。彼の前歯は彼の顔に似合わずはみ出ている。矯正すりゃいいのにと思うが口にはしない。
結局あの後平田理沙は終始クラスの奴らに囲まれて、俺の元に来る事は無かった。放課後には他の女に引きずられるように体育館に向かっていた。えー理沙バスケしてたのー?、じゃー一緒一緒ー、マジで、平田バスケ部入んの?俺もバスケ部!、セージうっさい、こいつガチでうぜーから気ぃ付けなよ理沙ー。数時間で呼び捨てにまで進化するあいつらは凄い、新人類、未知生物だ。イヤホンの隙間から聞こえる雑音に溜息をついて立ち上がって、康友と一緒に学校を出た。
俺が学校で話す唯一の友達。クラスは隣で体育とかは一緒になるがそれ以外は別々だ。一年の時も隣のクラスで仲良くなって、二年の文理選択時に別れてしまったが、結局は隣のクラスになった。朝と夕方、駅までの十五分は何かお互いに予定が無い限り一緒に帰る。俺も康友もクラスに友達は居ない。康友は話す奴くらいは居るみたいだが。二人共帰宅部で、二次元が好きで、ゲームが好きで、ネットが好きで、要するに引きこもり体質だ。
きっと康友も何かで自分を保っているんだろうと勝手に思っている。康友にさえ歌い手の事は言っていなかった。ただ互いに知っている。俺は良い声をしている事、康友は凄いギターが上手い事。友達が居ないためにカラオケには行かず康友以外知らないこと、他に目付けられるのが嫌でギターを学校には持ち込まず俺以外知らないこと。
「ガチいい加減にして欲しいんだよな、明日話しかけて来たらどーすりゃいいんだよ。俺の立ち位置壊すなつー話だよ」
「ああいうリア充は理解してくんねーよ、聖也ごしゅーしょーさま」
「おはよう、内間君!」
昨日の懸念通り、席に着いてすぐ話しかけてきたのは平田理沙だった。俺が来たのを見計らって女の集団から抜け出て来たみたいだ。大人しく会釈すると、彼女はちょっとだけ物怖じして、一呼吸くらい空白があってから、笑顔に戻った。廊下で付けたイヤホンを外す。
「ねぇねぇ、内間君はどんな音楽聞く感じ?何聞いてたの?理沙は懐古厨だからさーやっぱ名曲最高って感じで!うん、で内間君どんなの聞く?ボカロ?アニソン?東方?それともロキノン系のやつとか?」
「……まぁ、全般的に……」
こんな所でボカロとかアニソンとかいう単語口に出す神経がわからない。目を机に向けて鞄から教科書を取り出しながら答えると、右端にスカートがちらちらと見える。
「そっか、全体的にわかる感じ?最近ハマってるのとかある?」
「いや……特には」
俺が広がりようのない返答をしておいたのに、彼女は次々と話しかける。適当に相槌のようなものを打っているだけで、話は広がっていく。彼女の今はまっているボカロ曲、好きなP名、今期チェックしているアニメ、東方の好きなキャラ、すらすら出てくるその姿に本当に好きなんだなと疑いを捨てる。鞄の中身を出し終え、席に座った俺は目を反らす道具が無くなって、彼女の首元を見つめる。流石に目は合わせられないし、胸元を見ていたらキモい等言われかねないからだ。白い首が面白いように動く。彼女は机に手を付いて、覗き込むように話を続けた。
「でね!マイリス管理して……ってごめんね、何か凄い理沙ばっかり喋ってるね、もうすぐ予鈴だし!つい嬉しくて!今度遊ぼうよ、アキバとか行こう!」
「……はい、機会があれば」
「うん、また声かけるね!」
女の集団に戻っていく姿だけ見れた。笑顔で手を振っていて、そんなに俺との会話が楽しかったのかと、とりあえず解放されたことに一先ず安心する。すぐにイヤホンを付け直した。ボリュームを上げる。絶対あの女集団が俺の事を何か言っているのがわかるから。ヲタクキモくないとか、暗いとか、デブとか、不細工だとか、随分な事を言ってくれているに違いない。うるせぇよ公衆便器の性格ブスが。
次の日の休み時間も平田理沙は来た、好きな歌い手の話をした。その次の日も平田理沙は声をかけてきた。その次も、その次も、その次も。俺は平田理沙の好みと携帯とフェイスブックのアドレスと癖を把握した。流石に土日はメールを何通かやり取りをするだけだった。絵文字が沢山入ったメールは今まで見たどのメールよりも輝いていた。そんな彼女に捕まって、大分学校での生活は様変わりしてしまったのだが、学校のある間はあまり呟かないようにしていたのなんかが幸いして、俺のオンでの活動に支障は無かった。
土日はそんなメッセージを横目に録音をして、新曲をアップした。直ぐに数十のマイリスが付いて、徐々にマイリス数は増えた。これから先の休み時間なんかは再生数とマイリス数の確認、通知メールで少しは楽しみが出来る。
十一月になった。最初は怪訝な目で見られていた平田理沙の俺への対応は、皆慣れたらしく日常の光景になっていた。
放課後、いつものように彼女が俺に近寄って来た。
「内間君、内間君、今度の土日どっちか暇ある?」
「まぁ」
「この前ね、結衣亜達とカラオケ行ったときに半額チケ貰ったの!店員のお兄さんがガチ良い人で学割フリータイムでもコレ見せたら半額にしてくれるって!でね、土日だったら居るから声かけてーって言ってくれてさ、内間君と是非行こう!!って思って。流石に何人もで行ったら迷惑かなーって思うじゃんねー」
確かに普通の半額チケットの裏にペンで店員の名前が丸で囲んで書いてある。特別優待ってか、下心が丸見えだってのと鼻で笑う。優待した女が男連れて来るなんて、最高にコイツ惨めじゃんと加虐心が頭を擡げて、いいねと返事した。
土日の予定は動画巡りとかゲームとか次の歌の練習と録音とかあるけれど、別に二日丸々かかるわけじゃないし、差し迫った予定でもない。
「やったぁ!理沙ちょー内間君の歌声聞きたいし、ヲタカラしたくてうずうずしてたんだよね!……結衣亜達の前でアニソンなんか歌えないもん。じゃあどっちにしよっか!日曜どうかな?土曜午前は部活あるんだ、フリータイムだから時間ギリギリ使いたいし」
「どっちでもいいけど……」
「じゃあ日曜!日曜十一時ね!」
「わかった。あ、あと……土日だから時間ずっとは無理じゃないかな」
「そっかーー!!満室なったら追い出されるかーーー!!忘れてた!!そうだよねー、流石内間君!土日のフリータイムならって孔明の罠だわ!!」
「いや、別にそんなつもりじゃないだろうと思うけど……てか平田さんネタ古っ」
そう言って笑うと、彼女も笑った。今ではある程度会話も双方向だし、こうやって顔を見て笑うことも出来る。
そこに江夏結衣亜が、理沙ー、部活行こー!と声をかけて、平田理沙に抱きついた。勢いが良過ぎて平田理沙の身体が俺の机に打つかって少し机が動く。俺は何事も無かったかのように机を直した。
「痛いって結衣亜!ごめんね、じゃあまた!」
「うん」
江夏結衣亜は平田理沙の友人でリア充グループに属している人間だ。多分一番偉い位置に居るんじゃないかと思う。女子の関係性はよくわからないけれど。黒くウェーブした長い髪の毛と大きな胸、短いスカートに濃い化粧が目立つ女子だ。
その江夏は俺の横を通り抜けながら、聞こえるか聞こえないかわからない声で、調子乗んなよデブと言った。
聞き間違いじゃない。絶対に言った。俺の身体は硬直した。
平田理沙は全く気付いていない様子で、自分の机に戻って部活に行く準備をしていた。
イヤホンを付けて立ち上がると教科書を鞄に詰めてすぐに教室を出た。いつもならCクラスの前に康友が居て、いや居なかったら俺が廊下で待っているんだが、康友の姿が確認出来なくてもすぐ玄関に向かった。出来る限り早くこの場所から立ち去りたかった。
何であんな事言われなきゃなんねぇんだ。外に出てから音楽のボリュームを上げる。
いつ俺が調子乗ったよ、そりゃあデブかもしれねぇけどそれでいつお前に迷惑かけたかよ。勝手に平田理沙が来るんだから仕方ねぇだろうがよ。
駅までの道のりでイラつきと傷ついた心は少しだけ落ち着いて、電車を待つ間に康友にメールを送る。電車の列に並んでいると、四人組の女が大声で喋りながら白線の内側を歩く。もうすぐ電車来んだから後ろ歩けよと関係の無いそいつらにもムカつく。
何で女ってあんな五月蝿くて意味わかんなくて自分が一番偉いと勘違いしてんだ。気持ち悪ぃ。イケメンや金持ちにばっかり擦り寄って、どうせ歌い手の俺を応援してくれてる女共も俺の顔を晒せば一気に離れるんだろう。本当に醜く身勝手な生き物だ。中古便器スイーツ脳が俺を見下すんじゃねぇよ。
その日はイライラしながらツイッターに書き込んだり、生放送をしたりして心を静めた。Lサイズのポテトチップスを食べ、冷蔵庫にあったプリンとアイスを食べ、チョコレート菓子を食べ、夕食を食べてストレス発散をした。はけ口があるというのは、救いなのかもしれないと生放送後にベッドに倒れこむ。
皆のリクに答えて歌を歌って、感想をリアルタイムで聞けて、多少恥ずかしい言葉を呟いて。それで皆が俺のことを慕ってくれるのであれば、俺の存在価値を認めてくれるのであれば、そこが俺の居場所だ。
寝返りをうつと枕元に置いていた携帯を取る。平田理沙からメールが来ていた。何も知らないのであろう彼女は暢気に日曜の再確認をしている。
ふと怖くなる。日曜、彼女の言う通りの時間に行ったとして、彼女は一人で待っているのか。江夏なんかが付いて来て俺を笑いに来るのではないか。罠ではないのか。
そこまで考えて急に胃が苦しくなって、手元にあるコーラを飲んだ。その炭酸のせいかこみ上がって来る物を感じ、トイレに駆け込んで嘔吐した。飲んだばかりのコーラを筆頭にチョコと夕食の一部が吐き出された。涙と鼻水と胃液、唾液に汚れた顔を洗うと、瞳孔と唇が開いたままで自分の顔ながら怖かった。あの女達のせいで胃が不調になっている。洗面台の鏡を割りたい衝動に駆られたが、ぐっと堪えた。
色々考えても、平田理沙の一ヶ月近く俺を慕ってくれた態度は嘘偽りないわけだから、何かあっても対処出来る心構えはして、大人しくカラオケに行こうと思った。わかってるよ、と簡素なメールを返して風呂に向かった。
結局カラオケの前に居たのは平田理沙だけだった。私服の彼女は制服と同じくらい可愛らしく、女の流行はわからないがよく見るような格好だった。思ったより胸がある。
俺は無難にGパンとユニクロで没個性的だったが、彼女は開口一番にそのジーンズ良いねと言ってくれた。Gパンだけはこだわっているんだ、俺のサイズで好みを探すのは結構大変で、それが認められた気がした。
カラオケの受付で彼女は前言っていた名前の男を呼び出して、チケットを出した。俺を見る男の目線が冷たい。それでも彼女の前では良い格好をして、学割半額でフリータイムをしてくれて、部屋にまで案内してくれた。フリーのドリンクが来るまでの間、彼女はコートを脱いで、俺のジャケットも一緒にかけてくれて、はしゃいでいる様子だった。俺は烏龍茶、彼女はカルピスソーダを頼んだ。
「ドリンク来たよ!もうこれで邪魔者は居ないね内間君!思う存分歌おう!」
「邪魔者って……」
「熱唱出来ないじゃん!一番手どうするー?理沙行こうかー?」
「ん、お願いします」
笑ってマイクを渡すと、彼女も笑ってくれる。彼女は今クールやっているアニメのオープニングを入れると、歌い始めた。
普通、至って普通だ。声を張ると音程を外す程度で普通に上手い。歌声はいつもの声よりも高く、ふにゃふにゃしている。鼻にかかった感じだ。ぼんやりと彼女が歌うのを見つめていると、間奏の時に内間君曲入れてよーと促される。
やっぱり歌わないとダメか。
実際問題、彼女の知識からすると俺の歌い手としての存在を知っているか知らないか微妙なところだ。バレるのは嫌だ。教室なんかで話されたら困るし、ネットで何か暴露されても困る。声だけでバレなきゃいいんだが、と一先ず動画としてアップしていない曲を入れる。
「あ、理沙もこの曲好きだよー!」
画面に次の曲として出た曲名に反応して返事をくれる。
彼女の曲が終わって、一応拍手をすると、ありがとうと言われた。マイクがパスされる。この曲は声出しに最適なんだ、前奏が始まって彼女は次の曲を探そうとしたのか、俺の前からデンモクが消える。
歌いだして、間奏になっても全く次曲が入らないから、視線を画面から移すと、彼女はデンモクを持ったまま固まっていた。
「平田、さん?大丈夫?どうしたの?」
「ちょ、凄!!え!?ガチで上手過ぎるよ内間君!!ヤバイ耳レイプ!!いや、そんなんじゃなくて、ああ始まっちゃう!歌って!!」
歌詞が現れたのに反応して、彼女は俺に前を向くように促した。気のせいかもしれないが、頬が赤かったように思う。
歌い終わっても、新しい曲は入っていなかった。マイクを渡そうと振り返ると、すぐそばに平田理沙が居た。歌うのに夢中で気がつかなかった、いつの間に移動していたんだ。
「凄い!!凄いよ内間君!!理沙感動した!!てか、えと、あの……」
「ん?……と、とりあえず、ありがとう?」
彼女が言葉を濁すから、よくわからないけれどお礼を言ってマイクを置く。そのまま烏龍茶を口に含んだ。
そんな事よりこの距離感は何なんだろう。すぐ横に平田理沙が居る。数センチ手を伸ばせば触れられる距離。歌って上がっただけじゃない脈拍が五月蝿いほど耳に響く。
「あの、あのね!理沙、内間君好きになっちゃったかも……」
「は?」
烏龍茶を持ってストローに口をつけたまま固まった。
目の前では耳まで真っ赤にした平田理沙が俺を至近距離で見つめている。何が、何が起きた今、何て言った、好きに、なっちゃった、かも、かもって何だ。
ぎぎぎと音がしそうな不自然さで俺は烏龍茶をテーブルに戻した。
「あの、次、歌う?」
正常な思考回路はどこかへ行った。無言が続く部屋で俺が出した声は全くそぐわないものだった。真っ赤な彼女は、え、と目を見開いて固まったままだった。
今すぐ選択肢出て来い。頭の中で選択肢を探しても何も出てこない、大体どうして彼女は黙ったままなんだ、次喋れよ。カラオケの曲紹介のような音楽だけが響く。
「歌う、けど、あの、そっか、失敗か。ごめんね、変な雰囲気にして。違うの、今日本当は理沙デートのつもりだったの。内間君とデート出来るって思ってたの。一緒にカラオケしてもっと親しくなれたら嬉しいなって思ってたの」
彼女は言葉を繋ぐ。俺はただ首を振るだけだったが、彼女は俺から目を反らさずに一語一語確認するように発音する。
「そしたら内間君ガチで歌上手くて、低音ボイスで、歌声も凄いエロくて、いや、エロいとか、ああもう理沙のバカ!!艶っぽい、色っぽい?とにかく!そんな感じで、ドストライクで、好きって気持ちが抑えきれなくなって、つい近づいちゃって、つい告白しちゃって、うん……ごめんなさい」
「いや、謝らなくて……いいし」
「内間君!理沙の事嫌いじゃない!?」
「あ、はい」
「あのっ!理沙とお付き合いして下さい!声だけじゃないよ、理沙のヲタ話聞いてくれるし、楽しいし、優しいし、内間君と話すの楽しみになってたの。……今フラれてもそんな傷つかないし、ど、どうかな?」
「どう、とは…………えっと、付き合うのは、特に、問題ないから……」
何とか搾り出した声は震えていた。それでも彼女の告白に答える事が出来て、彼女を笑顔に出来た。彼女はありがとう!と軽くガッツポーズをした。
俺は彼女居ない歴イコール年齢を今この瞬間に断ち切った。降って湧いたような出来事だ。未だ脳内処理が追いついていない。目の前の可愛い女の子が友達から彼女に進化した。いや、レベル上げとは違う。
その後、二人で笑い合って、カラオケに戻った。彼女のリクエストに答えたり、一緒に歌ったりして、初めてのデートを楽しんだ。
そう、平田理沙は俺の恋人になった。そして俺も平田理沙の恋人になった。呼び名も平田さんから理沙へ、内間君から聖也へ変わった。
学校ではいつも通りで、付き合いはバレたら話すという取り決めだったから俺達が付き合っているのが周知されたのはもう十二月に入ろうとしている時だった。一応付き合い出した次の週に康友には伝えた。彼の家に遊びに行った時にゲームをしながら、何の気なく伝えると、康友は驚いて、その後祝福してくれた。
「裏切り者め、リア充爆発しろ。非童貞にゲーム貸さねぇからな。まぁ、よし、祝いに一曲弾いてやろう」
「あははっ、じゃあまだ借りれるな。何弾いてくれんの?」
康友はギターを本棚に入っているアンプに繋ぐと、軽くチューニングしてボス戦に使われていたゲーム音楽を弾き始めた。キーボで弾かれるはずのメロディーラインが康友の細い指で奏でられる。
祝いがギター演奏なんてナルシストのような気もするが、彼なりの最大の祝福なのだろうと大人しく演奏を見つめる。俺はギターに詳しくないからよくわからないが、真っ赤で鋭利な形をしたギターはストラップが短く、康友の胸と肋骨辺りに抱えられて、見目はあまりカッコ良いものではない。ただ、狂いの無い音とリズムに、時折歪ませられるトーンは正確過ぎて美しい。物が少ない整然とした康友の部屋はギターの音が響きやすく、澄んでいる。
弾き終えた康友にありがとうと言って、二人でゲームに戻った。それから先はいつもの二人で、そんなに会話もせずにゲームを攻略していった。
放課後、いつものように彼女が俺に近寄って来た。
「内間君、内間君、今度の土日どっちか暇ある?」
「まぁ」
「この前ね、結衣亜達とカラオケ行ったときに半額チケ貰ったの!店員のお兄さんがガチ良い人で学割フリータイムでもコレ見せたら半額にしてくれるって!でね、土日だったら居るから声かけてーって言ってくれてさ、内間君と是非行こう!!って思って。流石に何人もで行ったら迷惑かなーって思うじゃんねー」
確かに普通の半額チケットの裏にペンで店員の名前が丸で囲んで書いてある。特別優待ってか、下心が丸見えだってのと鼻で笑う。優待した女が男連れて来るなんて、最高にコイツ惨めじゃんと加虐心が頭を擡げて、いいねと返事した。
土日の予定は動画巡りとかゲームとか次の歌の練習と録音とかあるけれど、別に二日丸々かかるわけじゃないし、差し迫った予定でもない。
「やったぁ!理沙ちょー内間君の歌声聞きたいし、ヲタカラしたくてうずうずしてたんだよね!……結衣亜達の前でアニソンなんか歌えないもん。じゃあどっちにしよっか!日曜どうかな?土曜午前は部活あるんだ、フリータイムだから時間ギリギリ使いたいし」
「どっちでもいいけど……」
「じゃあ日曜!日曜十一時ね!」
「わかった。あ、あと……土日だから時間ずっとは無理じゃないかな」
「そっかーー!!満室なったら追い出されるかーーー!!忘れてた!!そうだよねー、流石内間君!土日のフリータイムならって孔明の罠だわ!!」
「いや、別にそんなつもりじゃないだろうと思うけど……てか平田さんネタ古っ」
そう言って笑うと、彼女も笑った。今ではある程度会話も双方向だし、こうやって顔を見て笑うことも出来る。
そこに江夏結衣亜が、理沙ー、部活行こー!と声をかけて、平田理沙に抱きついた。勢いが良過ぎて平田理沙の身体が俺の机に打つかって少し机が動く。俺は何事も無かったかのように机を直した。
「痛いって結衣亜!ごめんね、じゃあまた!」
「うん」
江夏結衣亜は平田理沙の友人でリア充グループに属している人間だ。多分一番偉い位置に居るんじゃないかと思う。女子の関係性はよくわからないけれど。黒くウェーブした長い髪の毛と大きな胸、短いスカートに濃い化粧が目立つ女子だ。
その江夏は俺の横を通り抜けながら、聞こえるか聞こえないかわからない声で、調子乗んなよデブと言った。
聞き間違いじゃない。絶対に言った。俺の身体は硬直した。
平田理沙は全く気付いていない様子で、自分の机に戻って部活に行く準備をしていた。
イヤホンを付けて立ち上がると教科書を鞄に詰めてすぐに教室を出た。いつもならCクラスの前に康友が居て、いや居なかったら俺が廊下で待っているんだが、康友の姿が確認出来なくてもすぐ玄関に向かった。出来る限り早くこの場所から立ち去りたかった。
何であんな事言われなきゃなんねぇんだ。外に出てから音楽のボリュームを上げる。
いつ俺が調子乗ったよ、そりゃあデブかもしれねぇけどそれでいつお前に迷惑かけたかよ。勝手に平田理沙が来るんだから仕方ねぇだろうがよ。
駅までの道のりでイラつきと傷ついた心は少しだけ落ち着いて、電車を待つ間に康友にメールを送る。電車の列に並んでいると、四人組の女が大声で喋りながら白線の内側を歩く。もうすぐ電車来んだから後ろ歩けよと関係の無いそいつらにもムカつく。
何で女ってあんな五月蝿くて意味わかんなくて自分が一番偉いと勘違いしてんだ。気持ち悪ぃ。イケメンや金持ちにばっかり擦り寄って、どうせ歌い手の俺を応援してくれてる女共も俺の顔を晒せば一気に離れるんだろう。本当に醜く身勝手な生き物だ。中古便器スイーツ脳が俺を見下すんじゃねぇよ。
その日はイライラしながらツイッターに書き込んだり、生放送をしたりして心を静めた。Lサイズのポテトチップスを食べ、冷蔵庫にあったプリンとアイスを食べ、チョコレート菓子を食べ、夕食を食べてストレス発散をした。はけ口があるというのは、救いなのかもしれないと生放送後にベッドに倒れこむ。
皆のリクに答えて歌を歌って、感想をリアルタイムで聞けて、多少恥ずかしい言葉を呟いて。それで皆が俺のことを慕ってくれるのであれば、俺の存在価値を認めてくれるのであれば、そこが俺の居場所だ。
寝返りをうつと枕元に置いていた携帯を取る。平田理沙からメールが来ていた。何も知らないのであろう彼女は暢気に日曜の再確認をしている。
ふと怖くなる。日曜、彼女の言う通りの時間に行ったとして、彼女は一人で待っているのか。江夏なんかが付いて来て俺を笑いに来るのではないか。罠ではないのか。
そこまで考えて急に胃が苦しくなって、手元にあるコーラを飲んだ。その炭酸のせいかこみ上がって来る物を感じ、トイレに駆け込んで嘔吐した。飲んだばかりのコーラを筆頭にチョコと夕食の一部が吐き出された。涙と鼻水と胃液、唾液に汚れた顔を洗うと、瞳孔と唇が開いたままで自分の顔ながら怖かった。あの女達のせいで胃が不調になっている。洗面台の鏡を割りたい衝動に駆られたが、ぐっと堪えた。
色々考えても、平田理沙の一ヶ月近く俺を慕ってくれた態度は嘘偽りないわけだから、何かあっても対処出来る心構えはして、大人しくカラオケに行こうと思った。わかってるよ、と簡素なメールを返して風呂に向かった。
結局カラオケの前に居たのは平田理沙だけだった。私服の彼女は制服と同じくらい可愛らしく、女の流行はわからないがよく見るような格好だった。思ったより胸がある。
俺は無難にGパンとユニクロで没個性的だったが、彼女は開口一番にそのジーンズ良いねと言ってくれた。Gパンだけはこだわっているんだ、俺のサイズで好みを探すのは結構大変で、それが認められた気がした。
カラオケの受付で彼女は前言っていた名前の男を呼び出して、チケットを出した。俺を見る男の目線が冷たい。それでも彼女の前では良い格好をして、学割半額でフリータイムをしてくれて、部屋にまで案内してくれた。フリーのドリンクが来るまでの間、彼女はコートを脱いで、俺のジャケットも一緒にかけてくれて、はしゃいでいる様子だった。俺は烏龍茶、彼女はカルピスソーダを頼んだ。
「ドリンク来たよ!もうこれで邪魔者は居ないね内間君!思う存分歌おう!」
「邪魔者って……」
「熱唱出来ないじゃん!一番手どうするー?理沙行こうかー?」
「ん、お願いします」
笑ってマイクを渡すと、彼女も笑ってくれる。彼女は今クールやっているアニメのオープニングを入れると、歌い始めた。
普通、至って普通だ。声を張ると音程を外す程度で普通に上手い。歌声はいつもの声よりも高く、ふにゃふにゃしている。鼻にかかった感じだ。ぼんやりと彼女が歌うのを見つめていると、間奏の時に内間君曲入れてよーと促される。
やっぱり歌わないとダメか。
実際問題、彼女の知識からすると俺の歌い手としての存在を知っているか知らないか微妙なところだ。バレるのは嫌だ。教室なんかで話されたら困るし、ネットで何か暴露されても困る。声だけでバレなきゃいいんだが、と一先ず動画としてアップしていない曲を入れる。
「あ、理沙もこの曲好きだよー!」
画面に次の曲として出た曲名に反応して返事をくれる。
彼女の曲が終わって、一応拍手をすると、ありがとうと言われた。マイクがパスされる。この曲は声出しに最適なんだ、前奏が始まって彼女は次の曲を探そうとしたのか、俺の前からデンモクが消える。
歌いだして、間奏になっても全く次曲が入らないから、視線を画面から移すと、彼女はデンモクを持ったまま固まっていた。
「平田、さん?大丈夫?どうしたの?」
「ちょ、凄!!え!?ガチで上手過ぎるよ内間君!!ヤバイ耳レイプ!!いや、そんなんじゃなくて、ああ始まっちゃう!歌って!!」
歌詞が現れたのに反応して、彼女は俺に前を向くように促した。気のせいかもしれないが、頬が赤かったように思う。
歌い終わっても、新しい曲は入っていなかった。マイクを渡そうと振り返ると、すぐそばに平田理沙が居た。歌うのに夢中で気がつかなかった、いつの間に移動していたんだ。
「凄い!!凄いよ内間君!!理沙感動した!!てか、えと、あの……」
「ん?……と、とりあえず、ありがとう?」
彼女が言葉を濁すから、よくわからないけれどお礼を言ってマイクを置く。そのまま烏龍茶を口に含んだ。
そんな事よりこの距離感は何なんだろう。すぐ横に平田理沙が居る。数センチ手を伸ばせば触れられる距離。歌って上がっただけじゃない脈拍が五月蝿いほど耳に響く。
「あの、あのね!理沙、内間君好きになっちゃったかも……」
「は?」
烏龍茶を持ってストローに口をつけたまま固まった。
目の前では耳まで真っ赤にした平田理沙が俺を至近距離で見つめている。何が、何が起きた今、何て言った、好きに、なっちゃった、かも、かもって何だ。
ぎぎぎと音がしそうな不自然さで俺は烏龍茶をテーブルに戻した。
「あの、次、歌う?」
正常な思考回路はどこかへ行った。無言が続く部屋で俺が出した声は全くそぐわないものだった。真っ赤な彼女は、え、と目を見開いて固まったままだった。
今すぐ選択肢出て来い。頭の中で選択肢を探しても何も出てこない、大体どうして彼女は黙ったままなんだ、次喋れよ。カラオケの曲紹介のような音楽だけが響く。
「歌う、けど、あの、そっか、失敗か。ごめんね、変な雰囲気にして。違うの、今日本当は理沙デートのつもりだったの。内間君とデート出来るって思ってたの。一緒にカラオケしてもっと親しくなれたら嬉しいなって思ってたの」
彼女は言葉を繋ぐ。俺はただ首を振るだけだったが、彼女は俺から目を反らさずに一語一語確認するように発音する。
「そしたら内間君ガチで歌上手くて、低音ボイスで、歌声も凄いエロくて、いや、エロいとか、ああもう理沙のバカ!!艶っぽい、色っぽい?とにかく!そんな感じで、ドストライクで、好きって気持ちが抑えきれなくなって、つい近づいちゃって、つい告白しちゃって、うん……ごめんなさい」
「いや、謝らなくて……いいし」
「内間君!理沙の事嫌いじゃない!?」
「あ、はい」
「あのっ!理沙とお付き合いして下さい!声だけじゃないよ、理沙のヲタ話聞いてくれるし、楽しいし、優しいし、内間君と話すの楽しみになってたの。……今フラれてもそんな傷つかないし、ど、どうかな?」
「どう、とは…………えっと、付き合うのは、特に、問題ないから……」
何とか搾り出した声は震えていた。それでも彼女の告白に答える事が出来て、彼女を笑顔に出来た。彼女はありがとう!と軽くガッツポーズをした。
俺は彼女居ない歴イコール年齢を今この瞬間に断ち切った。降って湧いたような出来事だ。未だ脳内処理が追いついていない。目の前の可愛い女の子が友達から彼女に進化した。いや、レベル上げとは違う。
その後、二人で笑い合って、カラオケに戻った。彼女のリクエストに答えたり、一緒に歌ったりして、初めてのデートを楽しんだ。
そう、平田理沙は俺の恋人になった。そして俺も平田理沙の恋人になった。呼び名も平田さんから理沙へ、内間君から聖也へ変わった。
学校ではいつも通りで、付き合いはバレたら話すという取り決めだったから俺達が付き合っているのが周知されたのはもう十二月に入ろうとしている時だった。一応付き合い出した次の週に康友には伝えた。彼の家に遊びに行った時にゲームをしながら、何の気なく伝えると、康友は驚いて、その後祝福してくれた。
「裏切り者め、リア充爆発しろ。非童貞にゲーム貸さねぇからな。まぁ、よし、祝いに一曲弾いてやろう」
「あははっ、じゃあまだ借りれるな。何弾いてくれんの?」
康友はギターを本棚に入っているアンプに繋ぐと、軽くチューニングしてボス戦に使われていたゲーム音楽を弾き始めた。キーボで弾かれるはずのメロディーラインが康友の細い指で奏でられる。
祝いがギター演奏なんてナルシストのような気もするが、彼なりの最大の祝福なのだろうと大人しく演奏を見つめる。俺はギターに詳しくないからよくわからないが、真っ赤で鋭利な形をしたギターはストラップが短く、康友の胸と肋骨辺りに抱えられて、見目はあまりカッコ良いものではない。ただ、狂いの無い音とリズムに、時折歪ませられるトーンは正確過ぎて美しい。物が少ない整然とした康友の部屋はギターの音が響きやすく、澄んでいる。
弾き終えた康友にありがとうと言って、二人でゲームに戻った。それから先はいつもの二人で、そんなに会話もせずにゲームを攻略していった。
十二月の入りたてに初めて理沙と手を繋いだ。隠す必要が無くなった時から彼女は積極的になってきていた。
テストを乗り越えたり、彼女と遊びに行ったり、一緒に帰って駅で話したりしているうちに俺の生活は少しずつ彼女中心に動き出した。朝は康友と登校するが、帰りは二回に一回は別々に帰る、彼女に時間を割くから必然的に歌い手としての活動が疎かになる、彼女を介してクラスの他の男と喋る機会が増える。
最初は彼女と一緒に居たリア充グループの奴が面白半分で話しかけてきて、死ぬほどウザかったが、普通の奴らにも一目置かれるようになったのか挨拶程度はするようになった。
俺はクラスの立ち位置を変えようとしていた。俺の力ではなく彼女の力ではあったが。
「なーなーお前平田とどーなの?」
「……どーなの、とは?」
リア充グループに引き連れられて屋上で昼飯を食べるはめになった。このクソ寒い中屋上にたむろするなんてバカとしか思えない。どうして俺がこいつらのジュースを買いに走らせられたのか。イラついて仕方ないが、ジュースを手渡し終わると急に肩を組まれた。一瞬身体がびくつく。こういう奴らの過剰スキンシップは気持ち悪くてどうしようもない。
「わっかんねーわけねぇだろ?どこまでやったんだって話だよ」
「いや、やってないよ」
「マジで?じゃあまだお前童貞?もう一ヶ月くらい経ってね?ああ、あれか、クリスマスにってやつ?」
「……別に、んなつもりじゃねーし」
肩を組まれているせいですぐ横にある薄笑いを浮かべた表情には、周りの男の同じような顔には、下劣で反吐が出る。大体何故お前らにそんな事を話さなければならない。何のメリットが俺にある。
言葉を濁した俺に興味を無くしたのか、話題は違う奴に移る。所在の無さが浮き彫りになったまま、大人しく弁当を摘み、脳内で音楽を流した。最近は色々振り回されて新曲のチェックも十分に出来ていないし、投稿も出来ていない。
「な、内間!」
「え?あ、ああ、え?」
「って聞いてろよー、寝てんの?お前起きてんのか寝てんのかわかんねぇ目してるしなー」
バカ笑いの横で苦笑いをする。触るな、話しかけてくんな、どっか行け、俺は理沙と付き合ってるだけでお前らの友達じゃねぇんだよ。雨でも降ってこの場がお開きになってしまえばいいのに、空はバカと同じくらい何も無い青だった。ああ寒ぃ。
「最近よくセージ達とご飯食べてるね!仲良くなったの?」
「いや、まぁ、向こうから一方的に話してくるつーか、俺は話合わせてるだけで」
「そっかー……、理沙もね、そんな感じ、せーやと話してる方が楽しいし」
帰り道の間は、手を繋ぎたいという彼女の要望とそれは恥ずかしいという俺の懇願の間を取って、俺の鞄の持ち手を彼女が掴むという形になった。彼女に合わせて歩幅を狭くして、ゆっくり歩く。途中のコンビニで買ったからあげクンを二人で食べ合いながら、適当に会話をする。
駅に着くと、彼女の使っていた路線が止まっていた。事故か何かがあったらしく、人がごった返していた。
「うっそーーー、いつ動くんだろ。えーーー」
「どっかで時間潰そうか、ここ居ても動きそうにないし」
ツイッターで情報を確認しても有益なモノが特に無かったから、彼女と二人で駅を出る。道中からあげを食べてしまったので、何か食べるという気にならなかったのは彼女も同じらしく、駅近くのデパートのベンチででも座っていようということになった。けれど、エスカレーターの近くにあるベンチもトイレの近くにあるベンチも全て埋まっていて、結局最上階の階段のところに腰掛けることになった。
「寒くない?」
「うん、ごめんね、せーやも帰るの遅くなっちゃって」
座っている距離が近い気がする。彼女は俺の鞄の持ち手を掴んだままだ。近い、身体が、顔が。脈拍が上がる。
「そういやさ、クリスマスどうする?理沙予定ある?」
「ん?せーやとデートする予定あるよ。どこ行こうか、綺麗な場所が良いよねー」
「じゃあちょっとググるわ」
そう言って携帯を見る。画面を開いて、調べようとした俺の画面を彼女が覗き込む。左側が一気に暖かくなる。
検索をかけて、上の方にあった特集ページを開く。色々出てきて、彼女に見えるように画面を動かす。彼女が、ねぇねぇと俺のコートを引っ張った。
「ん?」
「誰も居ないよ」
「うん?何が?」
「……今日何日かわかってる?」
「え、わかる、けど?」
「理沙達付き合いだして一ヶ月記念だよ、もうせーやのバカっ!!」
「いや、それはわかってるけど、えっと、ごめん。ごめん、だけど、何を怒っているの?記念日だから特別な事すべきだったかな、だったらごめんね」
とりあえず頭を下げて謝る。記念日とか大事にしなきゃいけなかったのか、変に意識すると俺一人湧き立っているようで恥ずかしいから抑えていたのに。
頭を上げて彼女の顔を見ると、困ったような怒ったような顔で眉を八の字に歪ませていた。そのまま彼女は目を閉じた。
「し、しても、え、いいの?え、するよ?」
「うん」
彼女は目を閉じたまま短く答えた。どうしたらいいのかわからないから、誰も居ないことをもう一度確かめると、自分の唇を彼女の唇にくっ付けた。キス、というのには程遠いような接触だった。一瞬触れるとすぐに離した。
目を開いた彼女は頬を赤くして、抱きついてきた。恥ずかしい、だけれども愛おしい。俺も彼女の背中に手を回した。きっと俺の方も真っ赤になっているだろう。小さな彼女の背中は俺の両手にすっぽりと入り込む。
手を離して、彼女から身体を離すともう一度口付けた。今度は先ほどに比べてゆっくりと彼女の唇を味わう。柔らかくて、小さかった。口を離した後にもう一度、もう一度と続けて、五度ほど続けた時に彼女が逃げるように俺の胸に頭を寄せた。息が荒い。
「急……にっ……待って」
俺の胸の中で彼女が大きく呼吸をして俺のコートを掴む。大丈夫、と背中を撫でてやると、彼女一度びくと震えた後に顔を上げた。涙目で頬が赤くて唇が開いていて、今まで見た中で一番可愛かった。
「ごめん、心臓が持たなくて……」
「いや、俺もごめん……」
「あの、耳元で囁かないで……」
「え?」
「……せーやの声、かっこ良過ぎるから」
その答えに思わず笑いが零れて、そうなんだ、と少し作ったような低音で囁く。彼女はまた震えて、俺の胸を拳で軽く叩いた。
「うーーーー、いじわる!」
笑いながら、涙目な彼女にもう一度キスをした。
それから俺も少し積極的に彼女の身体に触れた。柔らかい彼女の身体に触れ、誰も触れたことのない場所に触れ、誰も聞いた事のない声を聞いた。
「今週の土日暇ある?またカラオケ行かね?」
目的は歌うことじゃないのだが、空き教室で弁当を食べながら彼女を誘う。本当はカラオケなんかじゃなくて家に呼びたいけれど、親が居る家に彼女を呼べるわけはない。
彼女が自分で弁当を作ってきた日は、空き教室を見つけて、彼女が作った弁当と俺の親が作った弁当を交換して食べるようになった。二人で椅子を並べて食べる手料理は美味い。空き教室には前の時間に授業でも無い限り暖房が効いておらず、それを口実に二人で身体を寄せ合った。
「日曜なら大丈夫!カラオケかー、久しぶりだねー、せーやの歌声聞きたい!」
「んーそれもあるけど、なんつーか」
隣に座っている彼女の耳に唇を寄せると、ひゃぁと変な声が彼女から漏れる。もっと理沙といちゃつきたいし?と呟く。彼女が俺の声に弱いことはわかってきて、それを活用することを覚えた。
耳も頬も赤くした彼女が、小声で何かを呟く。
「え?何?」
「……じゃ、じゃあ、家、来る?うちの親、昼居ないし……」
「え!?」
思った以上に大きな声が出た。空き教室にそれは響き渡り、彼女は真っ赤な顔で俺の顔を見た。何度か口を動かして、じゃあ行く、行くよと繰り返す。
それから先の弁当の味はあまり覚えていない。何とか咀嚼をして、彼女の言葉に返答をして、平静を装って教室に戻った。
授業の内容もあまり入って来なかった。日曜までにどうやってコンドームを準備したらいいのかとか、帰ったらやり方を調べなければとか、実際理沙は処女なのかとか、色々な考えが頭を駆け巡った。それでも、先生に指されなかったりしたのは日頃の素行の賜物だと思う。あいつらは成績さえ良ければ何も言ってこない。
日曜は午後から彼女の家に向かった。結局コンドームは買えなかった。コンビニとドラックストアで四回も挑戦したが、どうも逡巡してしまい、コンドームの棚を行き来するだけで手に取る事も出来なかった。大体何で自販機が近場に無いんだ、恥ずかしいだろあんな物を人の手を通して買うなんて。通販も考えたが、この日数では無理だった。それに俺は親のクレカで通販しているのだから、万一バレたりしたら大事だ。
そんな事を言い訳しながら彼女の家の最寄り駅に降り、彼女と落ち合った。
どうでもいい会話をしながら手袋越しに手を繋ぐ。これだったら俺の手が緊張で湿っぽいことも、動悸が激しいことも気付かれないだろう。いつもより彼女も俺も口数が少ない。
彼女の家は駅から歩いて十五分程のマンションだった。母親と二人暮らしであることをエレベーターの中で聞いた。モデルハウスのようなすっきりと物の無いリビングを通り、彼女の部屋に入った。入った瞬間に何か良い匂いがした。彼女の部屋もあまり物が無く、本棚は教科書や参考書といった本がほとんどを占めて一区画ずつ文庫本と漫画が置かれていた。クローゼットがあるから、もしかしたらそこに色々入っているのかもしれない。
とりあえずコートを脱いで、ローテーブルの横のクッションに腰を下ろした。
「……お茶、持って来るね」
「うん、あ、これ」
左手に持ちっぱなしだった菓子を彼女に渡す。康友の家に行くときも、俺の家に康友が来るときも手土産なんて無かったが、流石に女の子の家に上がるときには持ってきた。
その菓子とお茶をテーブルに並べて、隣に並んで無言で食べた。すぐ後ろにベッドがある。彼女のお茶が無くなるのをじっと見つめる。無くなったら押し倒そうと自分に言い聞かせた。
「せーや、お茶、美味しくなかった?」
「え?」
彼女のお茶を見るのに必死で自分のお茶を少しも飲んでいないことに気付いた。勢いよくコップを掴むと一気に飲み干す。
「ごめん!」
そのまま彼女の身体を引き上げて、ベッドに押し倒した。驚いた顔をした彼女に口付ける。そして彼女のニットワンピースを捲り上げた。下にインナーを着ていたようで、それもずり上げた。白地に水色のチェック柄の下着が見えた。ホックを外すために背中に手をまわそうとして、彼女の太ももにGパン越しだが勃起した物が触れた。
「っ!!やだ!!待って、怖い!!」
それまで制止していた彼女が急に動き出して、インナーもワンピースを戻して起き上がると、ベッドの上で壁に寄りかかり体育座りのような格好になった。急な行動に驚いたが、俺はゆっくりと側に寄る。
「ごめん、怖かった?」
「こっち、こそ、ごめん」
顔を両腕に埋めて、震えているような彼女に触れていいのかわからなくて、隣に同じように座る。性急過ぎたかと反省すると同時に、失敗したな、今日無理かもなと落胆する。目の前の本棚にある文庫本の題名を見る。目に入った星新一、きまぐれロボットって今の彼女だなと溜息をついた。
彼女が伏せていた顔を上げて、もう一度ごめんと呟いた。少し涙目だ。
「あの、せーやの、やつが当たって、こんな……大きくて固いんだって思って、急に何か怖くなって、ごめん。理沙臆病者だね。もう、大丈夫だから」
震えながら、俺に抱きつく彼女の頭を撫でた。丁度今の格好なら当たる心配がないので、抱きつかれたまましばらく頭を撫で続けた。少しずつ震えは収まって、俺と彼女が同じくらいの体温になっていく気がした。
彼女が俺の肩から頭を上げた。
「……しよ?」
その言葉に頷いて、ゆっくりと彼女を布団の上に押し倒した。舌を舐めあって、そのまま耳や首を舐めて、さっきとは違ってワンピースを全部脱がせた。インナーも脱がせると、下着とニーハイだけになる。
服越しに何度か触れたことのある胸は白く盛り上がっていて、薄く青い血管が見える。腹は特に真っ白で緩やかな曲線は、綺麗だった。
「……あんまり、見ないで……」
彼女が両手で胸を隠して背中を丸める仕草をしたから、浮き上がった背中に手を伸ばして何とかホックを外した。
「え!せーやマジ知能犯じゃん!!」
「ぶっ、知能犯!!笑わせんなって!」
つい笑ってしまって、二人で笑う。笑いながらも、ブラを取り外して、直接胸に触れる。生の胸はしっとりとして柔らかく、ふわふわしていたのに乳首だけ芯を持っている感じだった。
乳首を舐めたり、吸ったりすると高い声が上がる。右手でパンツに触れると彼女の身体がびくっと震えた。気にせずに下ろして足から引き抜く。彼女が伸ばした手を退かせてそこに触れた。陰毛は薄くて、濡れていることがわかった。
「やっ……あ、あっ、ぅ」
何度か指を往復させて、入り込める穴を見つけてゆっくりと押し入った。温かくぬるついていて、指が痛いくらい狭い。
「痛い?」
「……だい、じょう、ぶ……あっ」
狭い中で指を動かすと声が上がって、奥から液体が出てくる。すげぇ、と呟いて、指を増やした。二本の指を何度か往復させて引き抜いた、俺ももう限界だった。
手早くニットとシャツを脱いで、ベルトを外し、Gパンとボクサーパンツを下ろすと竿を彼女の入り口に付けた。
「あっ」
「入れるよ、痛かったら言って」
力を入れると、濡れた側面を滑った。指を引き抜いたことで閉じてしまったように、何度か滑ってしまって入らなかった。焦っていた俺の手の上に彼女の手が重なった。
彼女の顔を見ると真っ赤で涙目だったし、手も震えていたけれど、誘導されて力を込めると押し入る感覚があって、生暖かい中に入り込んだ。
「っーーーーー!!……入っ、た?」
「うん、うん、やべぇ、何だこれ、あ!痛くない?」
「うん、いいよ」
眉間に皺がよっていたから痛いんだろうなと思って、彼女の身体を抱きしめた。しっとりとして温かい。細いのに柔らかい。動いていないのに出そうだ。
身体を少し離して、腰を動かした。
「あっ、あ、あっ、っ、せーやっ、すきっ、あっ、あ」
「っ、ぅ」
彼女の喘ぎと中の気持ち良さでもう持たなかった。射精のタイミングを見計らって引き抜くと、彼女の腹の上に出した。へその付近に精液が飛び散った。
股の下の布団に少し血液が付いていて、俺の竿の根元にも血液が付いていた。言っていた通り本当に処女だったのかと、そして童貞を卒業したことに感動した。けれど案外呆気ないものだった。暖房が効いていて裸なのに暑い。
立ち上がって、ティッシュを取って彼女の腹を拭く。
「ごめん、早くて……」
「そう、なの?理沙わかんない……」
後処理をして彼女の横に寝転がった。彼女がしがみ付いてくる。ぼんやりとした意識の俺に何度もキスをしてきた。
「好き、せーやの初めて奪っちゃった」
「俺も、奪っちゃった」
笑って抱き寄せる。彼女の裸も恥ずかしそうに笑う顔を本当に綺麗で、可愛くて、最高だった。抱きしめると胸が当たって、萎えた物がもう一度勃起し出した。
そしてその後二回ほどやって、一度眠ってから彼女の家を出た。帰りの電車で名実共に平田理沙が俺の女になって、俺は大人になって童貞共とは違うんだと実感した。魔法使いとかバカだろ、人生損してやがる。不思議な選民意識を抱いて、電車を降りた。
俺は初めて中止を願わないクリスマスを過ごし、新年を迎えた。
テストを乗り越えたり、彼女と遊びに行ったり、一緒に帰って駅で話したりしているうちに俺の生活は少しずつ彼女中心に動き出した。朝は康友と登校するが、帰りは二回に一回は別々に帰る、彼女に時間を割くから必然的に歌い手としての活動が疎かになる、彼女を介してクラスの他の男と喋る機会が増える。
最初は彼女と一緒に居たリア充グループの奴が面白半分で話しかけてきて、死ぬほどウザかったが、普通の奴らにも一目置かれるようになったのか挨拶程度はするようになった。
俺はクラスの立ち位置を変えようとしていた。俺の力ではなく彼女の力ではあったが。
「なーなーお前平田とどーなの?」
「……どーなの、とは?」
リア充グループに引き連れられて屋上で昼飯を食べるはめになった。このクソ寒い中屋上にたむろするなんてバカとしか思えない。どうして俺がこいつらのジュースを買いに走らせられたのか。イラついて仕方ないが、ジュースを手渡し終わると急に肩を組まれた。一瞬身体がびくつく。こういう奴らの過剰スキンシップは気持ち悪くてどうしようもない。
「わっかんねーわけねぇだろ?どこまでやったんだって話だよ」
「いや、やってないよ」
「マジで?じゃあまだお前童貞?もう一ヶ月くらい経ってね?ああ、あれか、クリスマスにってやつ?」
「……別に、んなつもりじゃねーし」
肩を組まれているせいですぐ横にある薄笑いを浮かべた表情には、周りの男の同じような顔には、下劣で反吐が出る。大体何故お前らにそんな事を話さなければならない。何のメリットが俺にある。
言葉を濁した俺に興味を無くしたのか、話題は違う奴に移る。所在の無さが浮き彫りになったまま、大人しく弁当を摘み、脳内で音楽を流した。最近は色々振り回されて新曲のチェックも十分に出来ていないし、投稿も出来ていない。
「な、内間!」
「え?あ、ああ、え?」
「って聞いてろよー、寝てんの?お前起きてんのか寝てんのかわかんねぇ目してるしなー」
バカ笑いの横で苦笑いをする。触るな、話しかけてくんな、どっか行け、俺は理沙と付き合ってるだけでお前らの友達じゃねぇんだよ。雨でも降ってこの場がお開きになってしまえばいいのに、空はバカと同じくらい何も無い青だった。ああ寒ぃ。
「最近よくセージ達とご飯食べてるね!仲良くなったの?」
「いや、まぁ、向こうから一方的に話してくるつーか、俺は話合わせてるだけで」
「そっかー……、理沙もね、そんな感じ、せーやと話してる方が楽しいし」
帰り道の間は、手を繋ぎたいという彼女の要望とそれは恥ずかしいという俺の懇願の間を取って、俺の鞄の持ち手を彼女が掴むという形になった。彼女に合わせて歩幅を狭くして、ゆっくり歩く。途中のコンビニで買ったからあげクンを二人で食べ合いながら、適当に会話をする。
駅に着くと、彼女の使っていた路線が止まっていた。事故か何かがあったらしく、人がごった返していた。
「うっそーーー、いつ動くんだろ。えーーー」
「どっかで時間潰そうか、ここ居ても動きそうにないし」
ツイッターで情報を確認しても有益なモノが特に無かったから、彼女と二人で駅を出る。道中からあげを食べてしまったので、何か食べるという気にならなかったのは彼女も同じらしく、駅近くのデパートのベンチででも座っていようということになった。けれど、エスカレーターの近くにあるベンチもトイレの近くにあるベンチも全て埋まっていて、結局最上階の階段のところに腰掛けることになった。
「寒くない?」
「うん、ごめんね、せーやも帰るの遅くなっちゃって」
座っている距離が近い気がする。彼女は俺の鞄の持ち手を掴んだままだ。近い、身体が、顔が。脈拍が上がる。
「そういやさ、クリスマスどうする?理沙予定ある?」
「ん?せーやとデートする予定あるよ。どこ行こうか、綺麗な場所が良いよねー」
「じゃあちょっとググるわ」
そう言って携帯を見る。画面を開いて、調べようとした俺の画面を彼女が覗き込む。左側が一気に暖かくなる。
検索をかけて、上の方にあった特集ページを開く。色々出てきて、彼女に見えるように画面を動かす。彼女が、ねぇねぇと俺のコートを引っ張った。
「ん?」
「誰も居ないよ」
「うん?何が?」
「……今日何日かわかってる?」
「え、わかる、けど?」
「理沙達付き合いだして一ヶ月記念だよ、もうせーやのバカっ!!」
「いや、それはわかってるけど、えっと、ごめん。ごめん、だけど、何を怒っているの?記念日だから特別な事すべきだったかな、だったらごめんね」
とりあえず頭を下げて謝る。記念日とか大事にしなきゃいけなかったのか、変に意識すると俺一人湧き立っているようで恥ずかしいから抑えていたのに。
頭を上げて彼女の顔を見ると、困ったような怒ったような顔で眉を八の字に歪ませていた。そのまま彼女は目を閉じた。
「し、しても、え、いいの?え、するよ?」
「うん」
彼女は目を閉じたまま短く答えた。どうしたらいいのかわからないから、誰も居ないことをもう一度確かめると、自分の唇を彼女の唇にくっ付けた。キス、というのには程遠いような接触だった。一瞬触れるとすぐに離した。
目を開いた彼女は頬を赤くして、抱きついてきた。恥ずかしい、だけれども愛おしい。俺も彼女の背中に手を回した。きっと俺の方も真っ赤になっているだろう。小さな彼女の背中は俺の両手にすっぽりと入り込む。
手を離して、彼女から身体を離すともう一度口付けた。今度は先ほどに比べてゆっくりと彼女の唇を味わう。柔らかくて、小さかった。口を離した後にもう一度、もう一度と続けて、五度ほど続けた時に彼女が逃げるように俺の胸に頭を寄せた。息が荒い。
「急……にっ……待って」
俺の胸の中で彼女が大きく呼吸をして俺のコートを掴む。大丈夫、と背中を撫でてやると、彼女一度びくと震えた後に顔を上げた。涙目で頬が赤くて唇が開いていて、今まで見た中で一番可愛かった。
「ごめん、心臓が持たなくて……」
「いや、俺もごめん……」
「あの、耳元で囁かないで……」
「え?」
「……せーやの声、かっこ良過ぎるから」
その答えに思わず笑いが零れて、そうなんだ、と少し作ったような低音で囁く。彼女はまた震えて、俺の胸を拳で軽く叩いた。
「うーーーー、いじわる!」
笑いながら、涙目な彼女にもう一度キスをした。
それから俺も少し積極的に彼女の身体に触れた。柔らかい彼女の身体に触れ、誰も触れたことのない場所に触れ、誰も聞いた事のない声を聞いた。
「今週の土日暇ある?またカラオケ行かね?」
目的は歌うことじゃないのだが、空き教室で弁当を食べながら彼女を誘う。本当はカラオケなんかじゃなくて家に呼びたいけれど、親が居る家に彼女を呼べるわけはない。
彼女が自分で弁当を作ってきた日は、空き教室を見つけて、彼女が作った弁当と俺の親が作った弁当を交換して食べるようになった。二人で椅子を並べて食べる手料理は美味い。空き教室には前の時間に授業でも無い限り暖房が効いておらず、それを口実に二人で身体を寄せ合った。
「日曜なら大丈夫!カラオケかー、久しぶりだねー、せーやの歌声聞きたい!」
「んーそれもあるけど、なんつーか」
隣に座っている彼女の耳に唇を寄せると、ひゃぁと変な声が彼女から漏れる。もっと理沙といちゃつきたいし?と呟く。彼女が俺の声に弱いことはわかってきて、それを活用することを覚えた。
耳も頬も赤くした彼女が、小声で何かを呟く。
「え?何?」
「……じゃ、じゃあ、家、来る?うちの親、昼居ないし……」
「え!?」
思った以上に大きな声が出た。空き教室にそれは響き渡り、彼女は真っ赤な顔で俺の顔を見た。何度か口を動かして、じゃあ行く、行くよと繰り返す。
それから先の弁当の味はあまり覚えていない。何とか咀嚼をして、彼女の言葉に返答をして、平静を装って教室に戻った。
授業の内容もあまり入って来なかった。日曜までにどうやってコンドームを準備したらいいのかとか、帰ったらやり方を調べなければとか、実際理沙は処女なのかとか、色々な考えが頭を駆け巡った。それでも、先生に指されなかったりしたのは日頃の素行の賜物だと思う。あいつらは成績さえ良ければ何も言ってこない。
日曜は午後から彼女の家に向かった。結局コンドームは買えなかった。コンビニとドラックストアで四回も挑戦したが、どうも逡巡してしまい、コンドームの棚を行き来するだけで手に取る事も出来なかった。大体何で自販機が近場に無いんだ、恥ずかしいだろあんな物を人の手を通して買うなんて。通販も考えたが、この日数では無理だった。それに俺は親のクレカで通販しているのだから、万一バレたりしたら大事だ。
そんな事を言い訳しながら彼女の家の最寄り駅に降り、彼女と落ち合った。
どうでもいい会話をしながら手袋越しに手を繋ぐ。これだったら俺の手が緊張で湿っぽいことも、動悸が激しいことも気付かれないだろう。いつもより彼女も俺も口数が少ない。
彼女の家は駅から歩いて十五分程のマンションだった。母親と二人暮らしであることをエレベーターの中で聞いた。モデルハウスのようなすっきりと物の無いリビングを通り、彼女の部屋に入った。入った瞬間に何か良い匂いがした。彼女の部屋もあまり物が無く、本棚は教科書や参考書といった本がほとんどを占めて一区画ずつ文庫本と漫画が置かれていた。クローゼットがあるから、もしかしたらそこに色々入っているのかもしれない。
とりあえずコートを脱いで、ローテーブルの横のクッションに腰を下ろした。
「……お茶、持って来るね」
「うん、あ、これ」
左手に持ちっぱなしだった菓子を彼女に渡す。康友の家に行くときも、俺の家に康友が来るときも手土産なんて無かったが、流石に女の子の家に上がるときには持ってきた。
その菓子とお茶をテーブルに並べて、隣に並んで無言で食べた。すぐ後ろにベッドがある。彼女のお茶が無くなるのをじっと見つめる。無くなったら押し倒そうと自分に言い聞かせた。
「せーや、お茶、美味しくなかった?」
「え?」
彼女のお茶を見るのに必死で自分のお茶を少しも飲んでいないことに気付いた。勢いよくコップを掴むと一気に飲み干す。
「ごめん!」
そのまま彼女の身体を引き上げて、ベッドに押し倒した。驚いた顔をした彼女に口付ける。そして彼女のニットワンピースを捲り上げた。下にインナーを着ていたようで、それもずり上げた。白地に水色のチェック柄の下着が見えた。ホックを外すために背中に手をまわそうとして、彼女の太ももにGパン越しだが勃起した物が触れた。
「っ!!やだ!!待って、怖い!!」
それまで制止していた彼女が急に動き出して、インナーもワンピースを戻して起き上がると、ベッドの上で壁に寄りかかり体育座りのような格好になった。急な行動に驚いたが、俺はゆっくりと側に寄る。
「ごめん、怖かった?」
「こっち、こそ、ごめん」
顔を両腕に埋めて、震えているような彼女に触れていいのかわからなくて、隣に同じように座る。性急過ぎたかと反省すると同時に、失敗したな、今日無理かもなと落胆する。目の前の本棚にある文庫本の題名を見る。目に入った星新一、きまぐれロボットって今の彼女だなと溜息をついた。
彼女が伏せていた顔を上げて、もう一度ごめんと呟いた。少し涙目だ。
「あの、せーやの、やつが当たって、こんな……大きくて固いんだって思って、急に何か怖くなって、ごめん。理沙臆病者だね。もう、大丈夫だから」
震えながら、俺に抱きつく彼女の頭を撫でた。丁度今の格好なら当たる心配がないので、抱きつかれたまましばらく頭を撫で続けた。少しずつ震えは収まって、俺と彼女が同じくらいの体温になっていく気がした。
彼女が俺の肩から頭を上げた。
「……しよ?」
その言葉に頷いて、ゆっくりと彼女を布団の上に押し倒した。舌を舐めあって、そのまま耳や首を舐めて、さっきとは違ってワンピースを全部脱がせた。インナーも脱がせると、下着とニーハイだけになる。
服越しに何度か触れたことのある胸は白く盛り上がっていて、薄く青い血管が見える。腹は特に真っ白で緩やかな曲線は、綺麗だった。
「……あんまり、見ないで……」
彼女が両手で胸を隠して背中を丸める仕草をしたから、浮き上がった背中に手を伸ばして何とかホックを外した。
「え!せーやマジ知能犯じゃん!!」
「ぶっ、知能犯!!笑わせんなって!」
つい笑ってしまって、二人で笑う。笑いながらも、ブラを取り外して、直接胸に触れる。生の胸はしっとりとして柔らかく、ふわふわしていたのに乳首だけ芯を持っている感じだった。
乳首を舐めたり、吸ったりすると高い声が上がる。右手でパンツに触れると彼女の身体がびくっと震えた。気にせずに下ろして足から引き抜く。彼女が伸ばした手を退かせてそこに触れた。陰毛は薄くて、濡れていることがわかった。
「やっ……あ、あっ、ぅ」
何度か指を往復させて、入り込める穴を見つけてゆっくりと押し入った。温かくぬるついていて、指が痛いくらい狭い。
「痛い?」
「……だい、じょう、ぶ……あっ」
狭い中で指を動かすと声が上がって、奥から液体が出てくる。すげぇ、と呟いて、指を増やした。二本の指を何度か往復させて引き抜いた、俺ももう限界だった。
手早くニットとシャツを脱いで、ベルトを外し、Gパンとボクサーパンツを下ろすと竿を彼女の入り口に付けた。
「あっ」
「入れるよ、痛かったら言って」
力を入れると、濡れた側面を滑った。指を引き抜いたことで閉じてしまったように、何度か滑ってしまって入らなかった。焦っていた俺の手の上に彼女の手が重なった。
彼女の顔を見ると真っ赤で涙目だったし、手も震えていたけれど、誘導されて力を込めると押し入る感覚があって、生暖かい中に入り込んだ。
「っーーーーー!!……入っ、た?」
「うん、うん、やべぇ、何だこれ、あ!痛くない?」
「うん、いいよ」
眉間に皺がよっていたから痛いんだろうなと思って、彼女の身体を抱きしめた。しっとりとして温かい。細いのに柔らかい。動いていないのに出そうだ。
身体を少し離して、腰を動かした。
「あっ、あ、あっ、っ、せーやっ、すきっ、あっ、あ」
「っ、ぅ」
彼女の喘ぎと中の気持ち良さでもう持たなかった。射精のタイミングを見計らって引き抜くと、彼女の腹の上に出した。へその付近に精液が飛び散った。
股の下の布団に少し血液が付いていて、俺の竿の根元にも血液が付いていた。言っていた通り本当に処女だったのかと、そして童貞を卒業したことに感動した。けれど案外呆気ないものだった。暖房が効いていて裸なのに暑い。
立ち上がって、ティッシュを取って彼女の腹を拭く。
「ごめん、早くて……」
「そう、なの?理沙わかんない……」
後処理をして彼女の横に寝転がった。彼女がしがみ付いてくる。ぼんやりとした意識の俺に何度もキスをしてきた。
「好き、せーやの初めて奪っちゃった」
「俺も、奪っちゃった」
笑って抱き寄せる。彼女の裸も恥ずかしそうに笑う顔を本当に綺麗で、可愛くて、最高だった。抱きしめると胸が当たって、萎えた物がもう一度勃起し出した。
そしてその後二回ほどやって、一度眠ってから彼女の家を出た。帰りの電車で名実共に平田理沙が俺の女になって、俺は大人になって童貞共とは違うんだと実感した。魔法使いとかバカだろ、人生損してやがる。不思議な選民意識を抱いて、電車を降りた。
俺は初めて中止を願わないクリスマスを過ごし、新年を迎えた。
冬休みはほぼ毎日学校に行くと言って理沙の家に入り浸っていた。宿題をやって、セックスをして、少し話してセックスをした。俺は完全にセックスの虜になっていて、コンドームも買えるようになった。童貞を捨てたことで、内気が少し治った気がした。
理沙は軽く拒むこともあったが、強く押すと大抵の場合は流されてセックスに応じた。女なんて緩いもんだなと思った。まんこに触れるといつも濡れていて、淫乱なのか俺が上手いのかどちらとしても出来ればどうでも良かった。
毎日昼は理沙とセックスをして、夜は疲れて少しだけ動画をチェックしたりしてすぐ眠った。新作の投稿は数週間出来ていなくて、ツイッターで体調が悪く声が出ない素振りを見せた。顔の見えないファンの女よりも目の前の彼女だ、ベッドに横たわりながら携帯を横に置いて目を閉じた。
「んっ、あの、せーや、再来週の土日暇ある?」
一回やって、理沙の胸を後ろから揉んでいると彼女が振り向きながら声をかけてきた。胸を揉みながら、あるよと短く答える。
「結衣亜、達と、っ、ディズニー行こうって、言っててっ……もう!せーやストップ!」
揉んでいた手をぱしんと叩かれる。そのまま理沙が身体を反転させて向かい合う形になる。顔が赤く、目が潤んでいた。
「はいはいディズニーでしょ、江夏さんと誰?俺行っていいの?」
「結衣亜とのんちゃんと二人の彼氏と六人で行こうって言ってるの。ガチリア充計画でしょ!」
「んー何ー俺と一緒じゃリア充じゃねぇの?」
肋骨の辺りから腰骨までのラインを撫でながら言うと、理沙は脹れる。なだらかなこのラインは理沙のパーツの中でもお気に入りの部位だ。脹れた頬を指で突いて、笑うと理沙も笑う。
「じゃあ、結衣亜達と計画進めちゃうね、一月学生安いらしいんだよね。ふふっ、楽しみだね!」
「つか俺江夏さんに嫌われてる気すんだけど行って大丈夫?」
嫌な事を思い出しながら何でもない風に聞く。行った後に不快な気分になるのは嫌だ。
「え?何で?結衣亜から言い出した計画だよ?せーやの勘違いじゃない?嫌いな人と行こうなんて言わないでしょ」
全く無垢な顔で返事をされて、そうかと呟く。
ディズニーは一度理沙と行ってみたかった場所だが、理沙以外よくわからないメンバーで行くとなると話は違ってくる。それでも彼女の言う通り、言いだしっぺが嫌いな人選をするわけがないだろうし、男が他に二人も来るなら何とかやっていけそうな気がする。
理沙が喋らない俺の顔を掴んでキスをしてくる。額に、眉毛に、鼻に、頬に、もみあげに。耳の横の毛に触れた後に唇を毛先にまで動かす。
「せーや大分髪の毛伸びたね、ふわふわしてて可愛い」
「あーそろそろ切らねぇとな」
「切っちゃうの?勿体無い、理沙髪直毛だからせーやの髪の毛羨ましいよー、いい感じでふわふわー」
身体を少し上げて理沙は俺の髪に顔を埋めた。理沙の胸に俺も顔を埋めた。そのまま前戯を始めて結局もう一度セックスをした。
爛れた生活をしていた冬休みが終わって、久しぶりに朝早く起きて寒い中を歩いた。手袋を忘れて、両手をコートのポケットに突っ込みながら駅を降りて学校に向かって歩いていると康友の姿が前方に見えた。声をかけると、変わらないダルそうな顔で挨拶を返してきた。
「だりー久しぶりーガチ寒ぃわ、康友休み何してた?」
「寝正月。ゲームしてネットしてギター弾いてー、あ、お年玉入ったか?新作出んのタイミング狙ってるよな!」
「は?」
「は、って。…………お前チェックしてねぇの?」
怪訝な顔で康友は俺を見る。チェックする暇なんて無かったつうの、毎日理沙と一緒だったんだからよ。
「悪ぃ。新作って何?やっべー見てねぇー」
「ほら延期になったやつ、来週の土曜発売だってよ。土曜とかやべぇよな、まさかゲーム発売日が土日来るとは思わなかったわ。頭沸いてんだろ。本気出して並ばねぇと!」
「来週土曜?マジかーーーーー、あーーーー俺無理」
康友は、は?とさっき俺が出したのと同じ声を出して驚いた。怪訝な顔が何故だかわからないけれど俺の良心を抉る。康友の顔は口から下がマフラーに覆われていて口元は見えないが、目だけで十分に俺への非難を語っている。
「何、何か用事あんのか?」
「その日理沙達とディズニー行くんだよな」
「はぁ?マジかよ、発売日より女かよ。はーーーリア充なっちまったなーー」
「違ぇよ、あいつだけだったら断れるけどそれ以外も居るから無理なんだよ」
あまりにも攻め立てられているような物言いに腹が立ってきて吐き捨てるように返す。一瞬変な雰囲気が流れたが、康友がじゃあしゃあねぇなと呟いて顔を普通に戻した。俺もそれを見て気を緩ませる。
康友の言う通り仕方ない。俺の身体は一つだから理沙に時間を割いたら他に時間は割けなくなる。康友といつもの通学路を少し早い速度で学校まで向かった。二人で攻略速度の賭けの話をしていつもの雰囲気に戻った。
そうこうしている内にディズニーの日になった。一度だけ行くメンバーと学校で集まったことがあったが、江夏さんの一個上の彼氏はスポーツ推薦が決まっている話の合わなそうなイケメンだったし、のんちゃんという人の彼氏は他校生らしく姿を見ることはなかった。その場は江夏さんが仕切って事務的な連絡をして終わった。帰り際に江夏さんの彼氏がにやにやしながら、せーや君よろしくーと間延びした声で挨拶してきて不快だった。その時は適当に挨拶をしておいたが、ここまで来ると断るわけにも、ドタキャンをするわけにもいかず、
もう開き直った気持ちで集合場所に向かった。
いつもの癖で早めに行くと来ていたのは江夏さんの彼氏と理沙だった。
「おーせーや君ー、おはよー」
「おはよー、せーや」
「あ、おはようございます」
一応年上だから敬語を使う。江夏さんの彼氏の格好がどう見てもガイヤがとかあの系の雑誌に載っていそうな格好で笑いそうになったのを耐えた。でも根がイケメンだから何を着ても似合う。
「先輩早いですね、まだ十分前なのに」
「あー俺サッカー部だったからそーゆー時間的なのはしっかりしてんだよねー。てかあれかー二人で早く来ようって約束してた?じゃあ邪魔してごめんねー」
悪気の無さそうな、けれどもあまり好きではない笑顔で言われて、いやと首を振る。俺が言葉に詰まっていると理沙がフォローのように会話に入って来る。
結局理沙と先輩の二人で話が盛り上がっているうちに他のメンバーも集まってきてディズニーに向かった。初めて見たのんちゃんの彼氏は先輩とは顔見知りらしく、会った瞬間にハイタッチのような事をしていた。馴れ馴れしい挨拶に世界が違うなと感じる。そんなに寒くない日だったのに背筋がぞくっとした。
チケットを購入して園内に入ると目の前にディズニーキャラクターが数体居て女共がはしゃいだ。江夏さんが走って行って、キャラクターを捕まえると皆で写真を撮る流れになった。周りがデジカメを取り出したので、俺も親から借りてきた物を取り出す。
「えー!内間君のちょー良いやつじゃない?」
のんちゃんと言う人が俺のデジカメを見て馬鹿みたいに騒ぎ出す。確かに最新型のやつだ、少し前までCMもやっていたカメラだ。俺が、いや、そんなと口篭っていると、江夏さんが嫌な顔で笑った。
「じゃあさー、内間君のカメラ使わせてもらっちゃおうよ!だってうちらのカメラ安物だもん、それで後で皆で分けようよ、ね、内間君良いよね?」
「え、あ、良いけど……」
「わーガチ内間君良い人なんだけどーー!」
江夏さんが俺の手からカメラを取り上げてキャストの人にそれを渡す。固まっているうちに皆と同じようにキャラクターの隣に並ばされて写真を撮った。ありがとうございまーすと馬鹿みたいな大声で俺以外が挨拶をして俺がキャストからカメラを受け取る。
何となく不快だが、俺のカメラが周りのゴミみたいなデジカメより優れているのは事実だからカメラ係りは仕方ないと自分に言い聞かせた。理沙がすっと俺の隣に来て小声で囁く。
「せーやごめんね、結衣亜結構自己中だからさ、嫌な事は嫌って言っていいよ」
「別に嫌じゃないよ、俺のカメラが高性能だからしゃーねーじゃん」
「まぁせっかく撮るんなら良いカメラが良いもんね、絶対二人の写真撮ろうね!」
理沙がぎゅっと腕にしがみ付いて来て、びっくりして押しのけた。彼女は一瞬困惑した顔をした後に照れ屋ーと笑って隣を歩いた。
その後は皆でファストパスを取りに走り、パスの取れなかったアトラクションの列に並んだ。二列ずつ並んでいる時は楽だったが、それ以外の数になると男同士で組まされたりして話題に困った。周り中がこの非日常の雰囲気を楽しんでいるようなのに、俺一人知らない人とパーティを組まされて初めてのダンジョンを縛りプレイさせられているような気分だ。こんな事なら康友の言うゲーム発売の列に並んだ方が何倍も楽しいかもしれない。
ぼんやりと隠れミッキーを探す。せっかくディズニーに来ているのに女共は学校の話や新作の化粧品の話を、男共は俺の知らない奴の話をしていて、俺が昨日ネットで仕入れた知識など何の役も立たない。
「せーや君、なーにぼーっとしてんのー?」
「あ、いや、隠れミッキーを……」
「マジで!?見つかった?どれどれー」
先輩に肩を捕まれて、舌打ちしたい気持ちを抑えてある部分を指すと、先輩はわっかんねーと笑った。三つ丸が並んだやつだと説明しても、笑うだけで意思疎通が図れない。
「あんなんミッキーじゃなくね?てかそんなん言ったら全部ミッキーじゃね?あははは、せーや君面白いなー」
「えーっと、隠れミッキーってそういう物ですから……」
俺が引き下がりながら言っても先輩はずっと笑っている。何が面白いのかわからない。馬鹿は箸転がっても面白いのかもしれない、と冷めた目をして携帯で時間を確認した。まだ来てから一時間程度しか経っていなくて、苦痛の時間が続くことに溜息をついた。
数十分並んで乗ったアトラクションは数分で終了して、効率の悪さに嫌気がする。待ち時間がさして面白いわけでもなく、馬鹿話が続くだけで忍耐力が試されているのかと思った。アトラクションの前でも俺のカメラを使って皆で写真を撮って、不快感は募る。
それからファストパスを使ってアトラクションに乗り、早めの昼食にした。先輩と江夏さんが食べ終わった人の席を素早く奪って何とか六人で座れて、こういう所は使えて頼もしいなと笑う。料理が並ぶと江夏さんが俺に声をかけた。
「内間君撮って撮って!」
料理に手を付けずに江夏さん達がポーズを作る。一瞬何のことかと思ったが、素早くカメラを取り出して席から少し離れて全員を撮った。俺の席はぽっかりと空いている。俺がまるでこのメンバーに入っていないみたいだ。
撮って席に戻る前に江夏さんは食べようと言って料理に手を付けた。俺を入れての写真を撮り直す気は無いのか、と俺も席について食べだした。隣の席の理沙は俺の変化に気付かないように笑いながら食べている。食べている間は理沙と会話したり、料理を交換したりして楽しかった。
食べ終わるとまたファストパスを取りに行き、アトラクションの列に並んだ。同じ事の繰り返し、これがあと数時間続くのかと思うと嫌になる。せっかく夢の国なのに。
「あーーー何か喉渇いた!」
「ん、俺も。あ、せーや君悪いんだけどさー、俺ら並んどくから飲み物買って来てくんね?ここ出た先にあっただろ」
「え?」
「結衣ペプシねー、のんちゃんどうする?」
「普通にお茶でいいよー」
俺が了承していないのに次々と注文を口にされる。待てよ、何で俺が一人で行かなきゃいけねぇんだよ、この人数のコップ持てるわけねぇだろと呆気に取られる。
「待って、理沙も行くよ。ペプシ二つとお茶とコーヒーね。行こう、せーや」
「え、理沙ちゃん行かなくて良くね?せーや君一人で大丈夫だよねー?」
「あ、はい」
「もー先輩空気読んで下さい、理沙せーやと二人っきりになりたいんですー。じゃー行って来ます。てか普通に出口で待ってます。あと数分で乗れるでしょ?じゃーあとでねー」
理沙が俺の腕を引っ張って列から抜けて歩き出す。掴む力が少し強くて二人で無言で薄暗いアトラクション内を抜けた。
「はーーーーーっ、もう飲み物渡して二人で違うところ行こうよ!」
「え、理沙怒ってるの?」
「怒ってるよ!何あれ!せーや優しすぎ!!ガチでウザイ!!」
「え、ごめん。いや、普通に仲良くしようよ」
理沙が感情を露にするせいで俺は思っていた事と反対の事を口走る。アトラクションの前で顔を赤くして怒る彼女を宥める彼氏の立ち位置になってしまった。俺の言葉に彼女は困ったような顔をして腕に抱きついて来た。コート越しに柔らかい身体が当たる。
彼女がこっちこそごめんね、と呟いて何となく彼女にもイラついた。何を謝っているんだ、俺はお前に謝られるような事になっていない。お前が俺を哀れむなと思ったが、表面には出さずに二人で皆の飲み物を買った。肌寒い中二人で腕を組んで並ぶのは、室内のアトラクションの列より温かく感じた。
二人で出て来たメンバーにその飲み物を渡すと理沙が個別行動を切り出して、パレードまでばらばらになることとなった。二人で歩くディズニーは楽しくて、やっと本来の目的が達成出来たと安堵する。二人で写真を撮ったり、チュロスを半分こして食べたりと心から笑う事が出来た。
結局パレードの時間には全員が集まった。皆パレードに夢中だったのでカメラの面で不快になることはあったが、他の奴等の強引さのお陰で良い場所も取れたので公平なやり取りだと思った。二人で手を繋ぎながら見るパレードは綺麗だったし、嫌な事もあったが楽しい一日だと自分を納得させた。
ディズニーから帰った後、お土産を家族に渡して自室に入ったが、何となく興奮したままだったので久しぶりに生放送をすることにした。疲れは残るものの、明日は日曜で休みだし、枠を確保するとツイッターに告知を書き込む。色々嫌な事をされた部分を発散させる意味もあった。
のど飴を数粒舐めて、水を飲んで喉を整えると生放送の準備をする。ツイッターには数名のリプが来た。いきなりだからあまり来ないかもな、と何歌うかと最近の曲を探る。難しそうな曲が多く、一つだけ練習しているうちに告知した時間になって生放送を始めた。
久しぶりです、と声を作って話すと待っていましたーと文字が流れる。横の視聴者数を見ると以前に比べてあまり伸びない。リクエストを受ける前に練習した曲を即興で披露する。簡単に練習しただけだったので自分でも粗が目立つなと思ったが、声質でカバーをした。称賛の声が流れる中、リクエストを受け付けた。知らない曲名が半分ほど流れて、知っている物を採用して歌った。歌い終わって水を飲む。称賛ばかりの文字列の中で、最近の曲あまりわからないんですか?といった言葉が流れる。
「あー、最近ちょっと巡れてなくて……ごめんなさい」
素直に謝ると、お忙しそうですよねー、お気になさらずーと文字が流れる。でも一方で引退?等という文字も流れる。始まって結構な時間が経っているのに視聴者数は伸びない。
引退については否定して、以前やっていたように言って欲しい言葉を募ってそれを喋って、最後に一曲歌って生放送は終了した。ツイッターに書き込んで、全てを終えて深呼吸をする。横にあった携帯は理沙からのメールが来ていて、今日は楽しかったねと絵文字で光っていた。そのままデジカメのデータを確認すると俺以外派手な格好をした奴等が笑顔で写っていて、俺はぎこちない笑顔をしている。理沙と二人で写った写真も顔の大きさが結構違っていて、理沙の笑顔が眩しかった。
いきなり胃液がこみ上げて来てトイレに走り、嘔吐した。大分消化されていた夕食は酷い酸性の臭いを放ち、その臭いに飲まれて再度嘔吐をした。胃の中が空になる。ひくひくと痙攣するような胃を押さえて洗面台で顔を洗う。鏡に映った顔はデジカメの中の顔より悲惨だった。
何かわからない所在の無さへの恐怖が足元から背中を駆け巡った。
デジカメのデータを紙媒体に人数分刷りだして、月曜日には一緒に行ったメンバーに渡した。朝に渡した理沙は素直に喜び、彼氏と二人分の写真を渡したのんちゃんという人は案外優しく、仕事早いねありがとうとお礼を言ってチョコ菓子と請求した金額をくれた。個別に話すと存外良い人なのかもしれない。
江夏さんとは何故かタイミングが合わず、今日中は無理かもしれないと思いながら理沙と一緒に帰るために一人教室に残っていた放課後、彼女がジャージで教室に入ってきた。部活の途中なのか少し汗をかいて、学校の指定じゃない籠球部と書かれたジャージを着ている。自分の机を探ると何かを取り出してポケットに入れた。
彼氏と二人分の写真を入れた封筒を持って声をかける。この時、どうして俺は理沙に渡すのを託さなかったのか後悔することになるのに。
「あ、あの江夏さん!」
「ん?何?」
「これ、土曜の写真、それで印刷料なんだけどさ……」
「はぁ?結衣印刷してなんて頼んでないし」
「は?」
まさかの言葉に固まった。お前が俺のデジカメで撮って後で分けようと言ったのではないのか。江夏さんは固まっている俺の手から封筒を取るとその場で写真を見始めた。
この時期夕方のこの時間ではもう外が薄暗い。ぱらぱらと写真を見て彼女は溜息をついた。
「てか結衣ガチブスに写ってるしー。あのキャスト写真撮るの下手過ぎんだけど。ああ、でも……」
ふっと彼女は鼻で笑って、俺を見た。馬鹿にしたような、卑下するような目に、固まったまま声が出ない。薄暗い中で彼女の派手な顔がより陰影を濃くしている。
「あんたも酷いよねー、よく理沙の隣に写れるつーか。ふふふっ。あんた居ることでうちらのグループの顔レベル急に下がるの、もう逆にウケるわ」
「え……」
「結衣があんただったらあんな子と付き合えないー、住む世界違うもん、よく卑屈にならずに居れるよねー、彼氏言ってたよーせーや君マジリスペクトだって」
固まっている俺の横を彼女は通り抜ける。何も言い返せない。今すぐこの場から逃げ出したかった。教室のドアが開く音がする。
「彼氏が言ってたの、あんた達美女と野獣だって。でもさ、結衣閃いたんだけど、美女と野獣って野獣が元は王子様だったからハッピーエンドなわけじゃん。美女と野獣だってカエルの王子様だって、王子に戻らなきゃハッピーエンドじゃなくね?」
くすくす笑う音と共にドアが閉まった。
俺は鞄を掴むと走って廊下を抜け、駅まで全力疾走した。駅に着いた瞬間に吐き気が込み上げて、駅の汚い便器に嘔吐した。一月の寒波が俺の身体も心も全て冷やした。
理沙は軽く拒むこともあったが、強く押すと大抵の場合は流されてセックスに応じた。女なんて緩いもんだなと思った。まんこに触れるといつも濡れていて、淫乱なのか俺が上手いのかどちらとしても出来ればどうでも良かった。
毎日昼は理沙とセックスをして、夜は疲れて少しだけ動画をチェックしたりしてすぐ眠った。新作の投稿は数週間出来ていなくて、ツイッターで体調が悪く声が出ない素振りを見せた。顔の見えないファンの女よりも目の前の彼女だ、ベッドに横たわりながら携帯を横に置いて目を閉じた。
「んっ、あの、せーや、再来週の土日暇ある?」
一回やって、理沙の胸を後ろから揉んでいると彼女が振り向きながら声をかけてきた。胸を揉みながら、あるよと短く答える。
「結衣亜、達と、っ、ディズニー行こうって、言っててっ……もう!せーやストップ!」
揉んでいた手をぱしんと叩かれる。そのまま理沙が身体を反転させて向かい合う形になる。顔が赤く、目が潤んでいた。
「はいはいディズニーでしょ、江夏さんと誰?俺行っていいの?」
「結衣亜とのんちゃんと二人の彼氏と六人で行こうって言ってるの。ガチリア充計画でしょ!」
「んー何ー俺と一緒じゃリア充じゃねぇの?」
肋骨の辺りから腰骨までのラインを撫でながら言うと、理沙は脹れる。なだらかなこのラインは理沙のパーツの中でもお気に入りの部位だ。脹れた頬を指で突いて、笑うと理沙も笑う。
「じゃあ、結衣亜達と計画進めちゃうね、一月学生安いらしいんだよね。ふふっ、楽しみだね!」
「つか俺江夏さんに嫌われてる気すんだけど行って大丈夫?」
嫌な事を思い出しながら何でもない風に聞く。行った後に不快な気分になるのは嫌だ。
「え?何で?結衣亜から言い出した計画だよ?せーやの勘違いじゃない?嫌いな人と行こうなんて言わないでしょ」
全く無垢な顔で返事をされて、そうかと呟く。
ディズニーは一度理沙と行ってみたかった場所だが、理沙以外よくわからないメンバーで行くとなると話は違ってくる。それでも彼女の言う通り、言いだしっぺが嫌いな人選をするわけがないだろうし、男が他に二人も来るなら何とかやっていけそうな気がする。
理沙が喋らない俺の顔を掴んでキスをしてくる。額に、眉毛に、鼻に、頬に、もみあげに。耳の横の毛に触れた後に唇を毛先にまで動かす。
「せーや大分髪の毛伸びたね、ふわふわしてて可愛い」
「あーそろそろ切らねぇとな」
「切っちゃうの?勿体無い、理沙髪直毛だからせーやの髪の毛羨ましいよー、いい感じでふわふわー」
身体を少し上げて理沙は俺の髪に顔を埋めた。理沙の胸に俺も顔を埋めた。そのまま前戯を始めて結局もう一度セックスをした。
爛れた生活をしていた冬休みが終わって、久しぶりに朝早く起きて寒い中を歩いた。手袋を忘れて、両手をコートのポケットに突っ込みながら駅を降りて学校に向かって歩いていると康友の姿が前方に見えた。声をかけると、変わらないダルそうな顔で挨拶を返してきた。
「だりー久しぶりーガチ寒ぃわ、康友休み何してた?」
「寝正月。ゲームしてネットしてギター弾いてー、あ、お年玉入ったか?新作出んのタイミング狙ってるよな!」
「は?」
「は、って。…………お前チェックしてねぇの?」
怪訝な顔で康友は俺を見る。チェックする暇なんて無かったつうの、毎日理沙と一緒だったんだからよ。
「悪ぃ。新作って何?やっべー見てねぇー」
「ほら延期になったやつ、来週の土曜発売だってよ。土曜とかやべぇよな、まさかゲーム発売日が土日来るとは思わなかったわ。頭沸いてんだろ。本気出して並ばねぇと!」
「来週土曜?マジかーーーーー、あーーーー俺無理」
康友は、は?とさっき俺が出したのと同じ声を出して驚いた。怪訝な顔が何故だかわからないけれど俺の良心を抉る。康友の顔は口から下がマフラーに覆われていて口元は見えないが、目だけで十分に俺への非難を語っている。
「何、何か用事あんのか?」
「その日理沙達とディズニー行くんだよな」
「はぁ?マジかよ、発売日より女かよ。はーーーリア充なっちまったなーー」
「違ぇよ、あいつだけだったら断れるけどそれ以外も居るから無理なんだよ」
あまりにも攻め立てられているような物言いに腹が立ってきて吐き捨てるように返す。一瞬変な雰囲気が流れたが、康友がじゃあしゃあねぇなと呟いて顔を普通に戻した。俺もそれを見て気を緩ませる。
康友の言う通り仕方ない。俺の身体は一つだから理沙に時間を割いたら他に時間は割けなくなる。康友といつもの通学路を少し早い速度で学校まで向かった。二人で攻略速度の賭けの話をしていつもの雰囲気に戻った。
そうこうしている内にディズニーの日になった。一度だけ行くメンバーと学校で集まったことがあったが、江夏さんの一個上の彼氏はスポーツ推薦が決まっている話の合わなそうなイケメンだったし、のんちゃんという人の彼氏は他校生らしく姿を見ることはなかった。その場は江夏さんが仕切って事務的な連絡をして終わった。帰り際に江夏さんの彼氏がにやにやしながら、せーや君よろしくーと間延びした声で挨拶してきて不快だった。その時は適当に挨拶をしておいたが、ここまで来ると断るわけにも、ドタキャンをするわけにもいかず、
もう開き直った気持ちで集合場所に向かった。
いつもの癖で早めに行くと来ていたのは江夏さんの彼氏と理沙だった。
「おーせーや君ー、おはよー」
「おはよー、せーや」
「あ、おはようございます」
一応年上だから敬語を使う。江夏さんの彼氏の格好がどう見てもガイヤがとかあの系の雑誌に載っていそうな格好で笑いそうになったのを耐えた。でも根がイケメンだから何を着ても似合う。
「先輩早いですね、まだ十分前なのに」
「あー俺サッカー部だったからそーゆー時間的なのはしっかりしてんだよねー。てかあれかー二人で早く来ようって約束してた?じゃあ邪魔してごめんねー」
悪気の無さそうな、けれどもあまり好きではない笑顔で言われて、いやと首を振る。俺が言葉に詰まっていると理沙がフォローのように会話に入って来る。
結局理沙と先輩の二人で話が盛り上がっているうちに他のメンバーも集まってきてディズニーに向かった。初めて見たのんちゃんの彼氏は先輩とは顔見知りらしく、会った瞬間にハイタッチのような事をしていた。馴れ馴れしい挨拶に世界が違うなと感じる。そんなに寒くない日だったのに背筋がぞくっとした。
チケットを購入して園内に入ると目の前にディズニーキャラクターが数体居て女共がはしゃいだ。江夏さんが走って行って、キャラクターを捕まえると皆で写真を撮る流れになった。周りがデジカメを取り出したので、俺も親から借りてきた物を取り出す。
「えー!内間君のちょー良いやつじゃない?」
のんちゃんと言う人が俺のデジカメを見て馬鹿みたいに騒ぎ出す。確かに最新型のやつだ、少し前までCMもやっていたカメラだ。俺が、いや、そんなと口篭っていると、江夏さんが嫌な顔で笑った。
「じゃあさー、内間君のカメラ使わせてもらっちゃおうよ!だってうちらのカメラ安物だもん、それで後で皆で分けようよ、ね、内間君良いよね?」
「え、あ、良いけど……」
「わーガチ内間君良い人なんだけどーー!」
江夏さんが俺の手からカメラを取り上げてキャストの人にそれを渡す。固まっているうちに皆と同じようにキャラクターの隣に並ばされて写真を撮った。ありがとうございまーすと馬鹿みたいな大声で俺以外が挨拶をして俺がキャストからカメラを受け取る。
何となく不快だが、俺のカメラが周りのゴミみたいなデジカメより優れているのは事実だからカメラ係りは仕方ないと自分に言い聞かせた。理沙がすっと俺の隣に来て小声で囁く。
「せーやごめんね、結衣亜結構自己中だからさ、嫌な事は嫌って言っていいよ」
「別に嫌じゃないよ、俺のカメラが高性能だからしゃーねーじゃん」
「まぁせっかく撮るんなら良いカメラが良いもんね、絶対二人の写真撮ろうね!」
理沙がぎゅっと腕にしがみ付いて来て、びっくりして押しのけた。彼女は一瞬困惑した顔をした後に照れ屋ーと笑って隣を歩いた。
その後は皆でファストパスを取りに走り、パスの取れなかったアトラクションの列に並んだ。二列ずつ並んでいる時は楽だったが、それ以外の数になると男同士で組まされたりして話題に困った。周り中がこの非日常の雰囲気を楽しんでいるようなのに、俺一人知らない人とパーティを組まされて初めてのダンジョンを縛りプレイさせられているような気分だ。こんな事なら康友の言うゲーム発売の列に並んだ方が何倍も楽しいかもしれない。
ぼんやりと隠れミッキーを探す。せっかくディズニーに来ているのに女共は学校の話や新作の化粧品の話を、男共は俺の知らない奴の話をしていて、俺が昨日ネットで仕入れた知識など何の役も立たない。
「せーや君、なーにぼーっとしてんのー?」
「あ、いや、隠れミッキーを……」
「マジで!?見つかった?どれどれー」
先輩に肩を捕まれて、舌打ちしたい気持ちを抑えてある部分を指すと、先輩はわっかんねーと笑った。三つ丸が並んだやつだと説明しても、笑うだけで意思疎通が図れない。
「あんなんミッキーじゃなくね?てかそんなん言ったら全部ミッキーじゃね?あははは、せーや君面白いなー」
「えーっと、隠れミッキーってそういう物ですから……」
俺が引き下がりながら言っても先輩はずっと笑っている。何が面白いのかわからない。馬鹿は箸転がっても面白いのかもしれない、と冷めた目をして携帯で時間を確認した。まだ来てから一時間程度しか経っていなくて、苦痛の時間が続くことに溜息をついた。
数十分並んで乗ったアトラクションは数分で終了して、効率の悪さに嫌気がする。待ち時間がさして面白いわけでもなく、馬鹿話が続くだけで忍耐力が試されているのかと思った。アトラクションの前でも俺のカメラを使って皆で写真を撮って、不快感は募る。
それからファストパスを使ってアトラクションに乗り、早めの昼食にした。先輩と江夏さんが食べ終わった人の席を素早く奪って何とか六人で座れて、こういう所は使えて頼もしいなと笑う。料理が並ぶと江夏さんが俺に声をかけた。
「内間君撮って撮って!」
料理に手を付けずに江夏さん達がポーズを作る。一瞬何のことかと思ったが、素早くカメラを取り出して席から少し離れて全員を撮った。俺の席はぽっかりと空いている。俺がまるでこのメンバーに入っていないみたいだ。
撮って席に戻る前に江夏さんは食べようと言って料理に手を付けた。俺を入れての写真を撮り直す気は無いのか、と俺も席について食べだした。隣の席の理沙は俺の変化に気付かないように笑いながら食べている。食べている間は理沙と会話したり、料理を交換したりして楽しかった。
食べ終わるとまたファストパスを取りに行き、アトラクションの列に並んだ。同じ事の繰り返し、これがあと数時間続くのかと思うと嫌になる。せっかく夢の国なのに。
「あーーー何か喉渇いた!」
「ん、俺も。あ、せーや君悪いんだけどさー、俺ら並んどくから飲み物買って来てくんね?ここ出た先にあっただろ」
「え?」
「結衣ペプシねー、のんちゃんどうする?」
「普通にお茶でいいよー」
俺が了承していないのに次々と注文を口にされる。待てよ、何で俺が一人で行かなきゃいけねぇんだよ、この人数のコップ持てるわけねぇだろと呆気に取られる。
「待って、理沙も行くよ。ペプシ二つとお茶とコーヒーね。行こう、せーや」
「え、理沙ちゃん行かなくて良くね?せーや君一人で大丈夫だよねー?」
「あ、はい」
「もー先輩空気読んで下さい、理沙せーやと二人っきりになりたいんですー。じゃー行って来ます。てか普通に出口で待ってます。あと数分で乗れるでしょ?じゃーあとでねー」
理沙が俺の腕を引っ張って列から抜けて歩き出す。掴む力が少し強くて二人で無言で薄暗いアトラクション内を抜けた。
「はーーーーーっ、もう飲み物渡して二人で違うところ行こうよ!」
「え、理沙怒ってるの?」
「怒ってるよ!何あれ!せーや優しすぎ!!ガチでウザイ!!」
「え、ごめん。いや、普通に仲良くしようよ」
理沙が感情を露にするせいで俺は思っていた事と反対の事を口走る。アトラクションの前で顔を赤くして怒る彼女を宥める彼氏の立ち位置になってしまった。俺の言葉に彼女は困ったような顔をして腕に抱きついて来た。コート越しに柔らかい身体が当たる。
彼女がこっちこそごめんね、と呟いて何となく彼女にもイラついた。何を謝っているんだ、俺はお前に謝られるような事になっていない。お前が俺を哀れむなと思ったが、表面には出さずに二人で皆の飲み物を買った。肌寒い中二人で腕を組んで並ぶのは、室内のアトラクションの列より温かく感じた。
二人で出て来たメンバーにその飲み物を渡すと理沙が個別行動を切り出して、パレードまでばらばらになることとなった。二人で歩くディズニーは楽しくて、やっと本来の目的が達成出来たと安堵する。二人で写真を撮ったり、チュロスを半分こして食べたりと心から笑う事が出来た。
結局パレードの時間には全員が集まった。皆パレードに夢中だったのでカメラの面で不快になることはあったが、他の奴等の強引さのお陰で良い場所も取れたので公平なやり取りだと思った。二人で手を繋ぎながら見るパレードは綺麗だったし、嫌な事もあったが楽しい一日だと自分を納得させた。
ディズニーから帰った後、お土産を家族に渡して自室に入ったが、何となく興奮したままだったので久しぶりに生放送をすることにした。疲れは残るものの、明日は日曜で休みだし、枠を確保するとツイッターに告知を書き込む。色々嫌な事をされた部分を発散させる意味もあった。
のど飴を数粒舐めて、水を飲んで喉を整えると生放送の準備をする。ツイッターには数名のリプが来た。いきなりだからあまり来ないかもな、と何歌うかと最近の曲を探る。難しそうな曲が多く、一つだけ練習しているうちに告知した時間になって生放送を始めた。
久しぶりです、と声を作って話すと待っていましたーと文字が流れる。横の視聴者数を見ると以前に比べてあまり伸びない。リクエストを受ける前に練習した曲を即興で披露する。簡単に練習しただけだったので自分でも粗が目立つなと思ったが、声質でカバーをした。称賛の声が流れる中、リクエストを受け付けた。知らない曲名が半分ほど流れて、知っている物を採用して歌った。歌い終わって水を飲む。称賛ばかりの文字列の中で、最近の曲あまりわからないんですか?といった言葉が流れる。
「あー、最近ちょっと巡れてなくて……ごめんなさい」
素直に謝ると、お忙しそうですよねー、お気になさらずーと文字が流れる。でも一方で引退?等という文字も流れる。始まって結構な時間が経っているのに視聴者数は伸びない。
引退については否定して、以前やっていたように言って欲しい言葉を募ってそれを喋って、最後に一曲歌って生放送は終了した。ツイッターに書き込んで、全てを終えて深呼吸をする。横にあった携帯は理沙からのメールが来ていて、今日は楽しかったねと絵文字で光っていた。そのままデジカメのデータを確認すると俺以外派手な格好をした奴等が笑顔で写っていて、俺はぎこちない笑顔をしている。理沙と二人で写った写真も顔の大きさが結構違っていて、理沙の笑顔が眩しかった。
いきなり胃液がこみ上げて来てトイレに走り、嘔吐した。大分消化されていた夕食は酷い酸性の臭いを放ち、その臭いに飲まれて再度嘔吐をした。胃の中が空になる。ひくひくと痙攣するような胃を押さえて洗面台で顔を洗う。鏡に映った顔はデジカメの中の顔より悲惨だった。
何かわからない所在の無さへの恐怖が足元から背中を駆け巡った。
デジカメのデータを紙媒体に人数分刷りだして、月曜日には一緒に行ったメンバーに渡した。朝に渡した理沙は素直に喜び、彼氏と二人分の写真を渡したのんちゃんという人は案外優しく、仕事早いねありがとうとお礼を言ってチョコ菓子と請求した金額をくれた。個別に話すと存外良い人なのかもしれない。
江夏さんとは何故かタイミングが合わず、今日中は無理かもしれないと思いながら理沙と一緒に帰るために一人教室に残っていた放課後、彼女がジャージで教室に入ってきた。部活の途中なのか少し汗をかいて、学校の指定じゃない籠球部と書かれたジャージを着ている。自分の机を探ると何かを取り出してポケットに入れた。
彼氏と二人分の写真を入れた封筒を持って声をかける。この時、どうして俺は理沙に渡すのを託さなかったのか後悔することになるのに。
「あ、あの江夏さん!」
「ん?何?」
「これ、土曜の写真、それで印刷料なんだけどさ……」
「はぁ?結衣印刷してなんて頼んでないし」
「は?」
まさかの言葉に固まった。お前が俺のデジカメで撮って後で分けようと言ったのではないのか。江夏さんは固まっている俺の手から封筒を取るとその場で写真を見始めた。
この時期夕方のこの時間ではもう外が薄暗い。ぱらぱらと写真を見て彼女は溜息をついた。
「てか結衣ガチブスに写ってるしー。あのキャスト写真撮るの下手過ぎんだけど。ああ、でも……」
ふっと彼女は鼻で笑って、俺を見た。馬鹿にしたような、卑下するような目に、固まったまま声が出ない。薄暗い中で彼女の派手な顔がより陰影を濃くしている。
「あんたも酷いよねー、よく理沙の隣に写れるつーか。ふふふっ。あんた居ることでうちらのグループの顔レベル急に下がるの、もう逆にウケるわ」
「え……」
「結衣があんただったらあんな子と付き合えないー、住む世界違うもん、よく卑屈にならずに居れるよねー、彼氏言ってたよーせーや君マジリスペクトだって」
固まっている俺の横を彼女は通り抜ける。何も言い返せない。今すぐこの場から逃げ出したかった。教室のドアが開く音がする。
「彼氏が言ってたの、あんた達美女と野獣だって。でもさ、結衣閃いたんだけど、美女と野獣って野獣が元は王子様だったからハッピーエンドなわけじゃん。美女と野獣だってカエルの王子様だって、王子に戻らなきゃハッピーエンドじゃなくね?」
くすくす笑う音と共にドアが閉まった。
俺は鞄を掴むと走って廊下を抜け、駅まで全力疾走した。駅に着いた瞬間に吐き気が込み上げて、駅の汚い便器に嘔吐した。一月の寒波が俺の身体も心も全て冷やした。
あの日理沙に勝手に帰ったことを詫びるメールを入れることで精一杯だった。月を跨いで二月になってもあの女の言葉が耳に残って離れなかった。理沙には何でもないように振舞ったが、積極的に自分から触れることが出来なくなった。
今二人で並んで歩いている姿も全ての人間から笑われているのかもしれない。今まで理沙が勝手に注目を集めているのだと、俺の彼女可愛いだろ、羨ましいだろと思っていたが、嘲笑の的として視線を集めていたのかもしれない。疑心暗鬼は俺を苦しめて、理沙と一緒に居る時間が減って康友との時間が前と同じくらいにまでなりそうだった。
それでも毎日学校に行けば同じクラスにあの女が居て、否応なしに視界に入って、俺の事を見て笑っているように見えた。五月蝿い、うるせぇよクソビッチが。俺がお前に何をした、何で俺がお前の言葉でこんなに振り回されなきゃいけねぇんだ。
日曜に行った理沙の家では理沙を手酷く抱いた。後ろから背中を押さえつけてセックスをすると、加虐心が満たされてゴムを着けずに理沙の尻に射精した。理沙は涙に濡れた顔で俺を見て笑った。
「最近せーやドSだね、理沙もMなのかな、せーやなら何されても気持ち良いよ」
終わった後抱き付いてくる理沙を見て、こっちが泣きそうになった。頭をかき抱いて顔を合わせるのを防いだ。理沙の家の天井が見える。シミ一つない綺麗な天井に女特有の良い匂いがして、理沙の頭からシャンプーの匂いがした。綺麗で、綺麗で、隙のない空間。
理沙がするりと拘束を抜けて顔を上げた。床に落ちている俺のシャツを拾い上げて着ると、部屋の外に出て行き、紫色にピンクの紐が付いた紙袋を持って帰ってきた。何故か冷たいそれを身体を起こした俺に手渡す。
「ちょっと早いけどバレンタイン。学校に持って行くと溶けちゃうかなって思って」
「……すっげー冷えてる」
紙袋の中に入っていた小さな箱はショッキングピンクでリボンを外すとトリュフが三個入っていた。詳しくは知らないが絶対に高いやつだと思った。甘い匂いと酒の香りがする。
俺がそれを見てぼんやりとしていると、理沙が一つを取り出して口に咥えた。ん、と短い声を出して目を閉じて咥えたチョコレートを差し出す。
骨格に沿った綺麗な髪に白い肌、閉じているのに大きいと判る瞳、すっと通った鼻筋、チョコレートを咥えた小さな口、俺のシャツをだぼだぼに着こなす細くて白い身体。見下ろしたその姿にぞっとした。あの言葉が巡る。住んでいる世界が、違う。
「うっ……ごめん!」
口を抑えてもう場所を覚えてしまっているトイレに駆け込んだ。吐き出すものがなかったから胃液だけが喉を伝って口元に留まる。必死に嗚咽を堪えた。
あの日駆け込んだ場所とは違う掃除の行き届いたトイレ、ラベンダーの芳香剤の香り。全てが俺を拒絶しているようで再度吐き気が込みあがる。必死に耐えているとトイレの扉をノックされた。
「あの、せーや、大丈夫?体調悪かった?もしかしてチョコ苦手?あの、お酒が体質的に無理とかだった?ごめんね、大丈夫?お水持って来ようか?」
「…………いや、大丈夫だから」
レバーを引いて流水音で掻き消して口の中の物を吐き出す。幸いにもトイレ内に洗面台が備え付いていたから軽く口をすすいでトイレから出た。心配そうな顔で理沙が立っていた。
「悪い、ちょっと酒の匂い苦手で……」
「そう、なんだ。ごめんなさい。理沙も口洗うね。このままじゃせーやとチュー出来ないし。バレンタインまでには新しいの買っておくね!」
「あ、いや、いいよ。ごめん、俺もう帰るわ。マジごめん」
嘘を付いて理沙の顔を見ずにさっさと服を着ると立ち去った。吐き気が治まらない。彼女の家の最寄り駅のトイレでもう一度胃液を吐き出した。脈打つのは心臓だけでなく胃もだ。駅の汚いトイレは寛容に俺を受け入れてくれる。
結局その後家に帰ってから発熱をした。もしかしたらあの吐き気は風邪から来るものだったのかもしれない。熱は夜になっても、一晩眠っても下がらず、次の日学校を休んだ。
カーテンから日差しが入り、見上げる天井は薄汚く汚れていて、一晩中かいた汗で布団も身体も臭かった。両親が共働きの家には誰も居ないが、母親が昼飯や薬、飲み物等の用意はしておいてくれたようだ。重い身体を引きずってシャワーを浴びてから、お粥を温め卵を入れて食べて、薬を飲んだ。頭が痛い、節々が痛い、胃も何もかもが痛いのだ。
携帯には理沙からの心配するようなメールが届いていたが無視をした。お粥の入っていた土鍋とレンゲ、コップを水につけるとベッドに戻った。
玄関のインターフォンの音で目が覚めた。時計を見ると昼飯を食べてから二時間くらいしか経っていない。何度も響くそれは諦めろよと悪態をつきたいしつこさだった。ゆっくりと立ち上がりリビングの画面を見ると理沙が映っていた。何故だ、と驚きながら簡単に髪を撫で付けて、よれている服を整えて玄関に出た。
「何してんのっ!?」
「せーや!ごめん、メール返って来なかったから、共働きだって言ってたし心配なっちゃって!良かった、倒れてたりしたらどうしようって思って、それで、理沙……」
時間を考えても学校を抜け出して来ているのがわかった。必死な様子と手にコンビニの袋を下げている姿に嬉しさを感じたが同時に劣等感も感じる。彼氏のために授業を抜け出して看病の準備をこなす可愛い彼女。理沙はどこにも欠点が無い。
とりあえず彼女を玄関に入れて、扉を閉めた。
「俺は大丈夫だから、学校戻りなよ」
「いいの!結衣亜達にノートとか言い訳頼んで来たから。熱あるの、ごめんね寝てる時に。何か食べた?一応おうどんとか買ってきたんだけど、食べたならいいし。あーっと冷蔵庫はどこかな、アイスとか飲み物冷やしたい」
「……こっち」
理沙をキッチンに案内する。無言の俺に対して理沙も無言で後ろを付いてくる。
身体が弱っているせいか、不満が吹き出る。あの女の名前なんか出すなよ。謝るんなら来るんじゃねぇよ。寝てるってわかってんのに嫌がらせかよ。つか弱ってるとこ見せたくねぇのに何なんだよ。偽善ぶってんじゃねぇよ。この時間まで食べてねぇとかあるわけねぇだろ、俺の親何も出来ないって馬鹿にしてんのか。共働きでも家事や料理の準備くらいはやってくれるっての。普通に会社休んでくれて母親と鉢合わせとか想像しねぇのかよ。まぁキッチンだってリビングだって理沙の家よりは汚ぇよ。見るんじゃねぇよ、俺をこれ以上苦しめんなよ。大体親に何て説明すりゃいいんだよ理沙の持ってきた物をよ。
冷蔵庫に物を仕舞う理沙を見る。ぎちぎちに詰まった冷蔵庫の隙間を作って理沙が物を入れていく。無理矢理ではなく、さっと整理して入れる仕草に俺の領域が侵害されている感じがする。
会いたかったのに会いたくない。
「せーやのお部屋どこ?横になった方がいいよ、ごめんね邪魔しに来ちゃって」
「いや、いいよ。でも寝るから、えっと……」
帰って、という言葉が言い出せない。けれども実際帰って欲しい。こんな弱った姿をずっと見られるのも、俺の部屋を見られるのも、側に居られるのも、帰ってきた親に何か言われるのも全部嫌だ。苦しんでいる姿なんか彼女に見られたくない。
「眠れないなら理沙が添い寝してあげる、理沙にうつしちゃっていいよ」
笑いながら抱きついてくる彼女を跳ね除けた。部屋の中という二人きりの空間で彼女を拒絶したのは初めてだ。目を見開く彼女を見て目を反らした。
「…………もう、止めろ」
「え?」
「止めろよ、悪いけど、俺マジでだりぃから、悪い、帰って」
「……あ、うん、わかった。……ごめんなさい」
彼女は薄く涙目になりながら鞄を持って立ち去った。その場に立ち竦んでいると吐き気がまた込み上げてきてトイレで嘔吐した。食べた卵粥は吐き出され、涙と鼻水で顔が濡れた。
何故吐き気が込み上げるのかもわからない。何が不快でどうしようもないのか、彼女への苛立ちは何なのかよくわからない。どうして俺はこんなに弱くなってしまったのか。
顔と口を洗って水をラッパ飲みして胃を落ち着かせると再び布団に入った。
翌日には熱が下がって学校に向かった。通学路で康友と会って軽く話す。この時間が気楽で落ち着ける。
教室の前で別れて、室内に入ると理沙が駆け寄ってきた。周囲の目線がこちらに突き刺さる。今までどうして普通で居れたのだろう。過去の俺は鈍感で盲目で何もわかっちゃいない。
「おはようせーや、昨日はごめんね。大丈夫?ノートのコピー昼休みに渡すね」
「……はよ、あ、今日も弁当作って来たんだ」
「うん、栄養あるものばっかりだから元気出ると思う!」
あっそ、俺の親のは栄養考えてねぇ出来損ないの弁当かよ。今まで感じなかった理沙の言葉への反感が生まれる。
無言で頷くと理沙は俺の席に居座って担任が来るまで話を続けた。机に両肘をかけて、その上に胸を置くようにして俺に話しかける。いつもの光景、いつもの仕草、変わったのは俺の心の中だけなのかもしれない。吸い込まれそうな彼女の瞳は俺を確実に映していて、話の端々で笑って瞳を隠した。
昼休みに理沙と二人で空き教室で弁当を食べた。理沙が作ってきたカラフルな弁当と俺の親が作った茶色っぽい弁当を交換して食べる。理沙がくれたノートのコピーはいかにも女らしい丸っこい文字が不規則に離れた文字列を成していて、気持ち悪かった。
何事も無く食べ終えたところに理沙が箱を取り出した。
「病み上がりであれだけどチョコ。これは手作りだからお酒なんか入ってないよ。ね、開けてみて!」
「ん、ありがとう」
リボンを解いて箱を開けると四角形のチョコレートの上に絵が描いてあった。俺が前言っていた東方の好きなキャラクター五人だ。感動すると共に、絵の上手さに軽く引く。俺が何度も練習してある程度描けるようになったレベルとは全然違う。カラフルなその姿に華やかさを感じる。
「あ、もしかして可愛くて食べられないとか!?理沙昨日ガチ頑張ったんだよ、ググってチョコの上にカラーイラスト描く方法見つけてさ、失敗したやつはお母さんと自分用ってことにしてー」
理沙の声が遠くに聞こえた。
どうしようか、心臓が握りつぶされそうだ。
チョコが嬉しいのは事実、二次元嫁の姿に感動したのも事実、理沙の事を好きなのも事実、だけれど、一挙一動に劣等感を感じて死にたくなるのも事実だ。
「……せーや?」
「もう、こういうの、止めよう」
必死に捻り出した声は震えていた。チョコの箱を机に置いて、理沙に頭を下げた。彼女の顔は見えないけれど、驚いているのは雰囲気でわかる。
空き教室の寒い空気が更に温度を下げた。こつこつと雨が窓を叩いて音を立てる。今まで雨が降っていたことにも気付かなかった。
「止め、ようって、どういうこと?バレンタインが嫌ってこと、それとも……理沙が、嫌ってこと?」
「……どっちも。ごめん。俺、これ以上付き合えない」
「やだっ!!」
急に理沙が大声を上げた。初めて聞く大きな声だった。
顔を上げると彼女が目に涙を溜めて真っ赤にしていて、両手を胸元で握っていた。手に力が強くかかっているようで指先は白く、腕は震えている。
「理沙は、やだよ。ど……こが、嫌?理沙、直す、から……」
彼女は目に溜っていた涙を零して、こちらを見つめる。痛々しい。眉が下がって、唇が震えている。歯を噛み締めているのがわかる。
何故か手が伸びて彼女の目尻を拭った。指先が涙で濡れる。その手に彼女が手を重ねてきて、指先に唇が触れた。
「こういうの、嫌?もう、したくない?」
「………………え」
じゃあ、と彼女は呟いて俺の膝に跨って首に手をまわした。固まっている状態でキスをされる。唇がふわふわと触れ合う。目を開けたまま口付けを受けていると、首を強く抱かれて舌を入れられた。驚いて舌で押し返したが、その舌を舐めあげられる。
唾液が押し返している舌と唇の間から落ちた。一瞬だけ顎に触れて彼女のスカートに落ちる。長いキスに勃ちそうになって、彼女の腰を両手で持って身体を離そうとした。首に回された腕に力がこもる。
大人しくなされるがままにしていると、首の拘束が取れて顔が離れた。荒い息をして彼女がこちらを見つめる。
「嫌、だった?」
「………………」
「触って……お願い、理沙を、拒絶しないで」
彼女が俺の右手を自分の腰から胸に持って行った。カーディガンの手触りと奥にある胸の柔らかさを感じる。初めは感じなかった脈拍が掌から伝わってきた。早い。少し力を込めるとぐにゃっと形が変わった。
俺の手の上にあった彼女の手が動いてカーディガンのボタンを外し始めた。
「え、何して……?」
俺の声には答えずに彼女の指はブラウスのボタンに掛かった。胸に置いていた手を外して彼女の脱衣を止めるようにカーディガンの前を閉じた。これ以上俺を誘惑しないで欲しい。もう少しで昼休みも終わる、こんな場所で、こんな時間で何を始めようとしているのか。必死にカーディガンを押さえて見える肌を消す。
「もう戻ろう、昼休み終わるよ」
「やだ、ねぇ、しようよ、理沙したい。お願い」
「俺ゴム持ってないし、こんな場所で何を考えているの?授業もあるし、落ち着いて」
「やだ、今離れたら本当に離れちゃう気がする、やだ、ぎゅっとしてよせーや」
ぼろぼろと涙を零して俺に抱きついてくる姿に心が痛む。押し黙っていると、彼女が俺のベルトに手をかけた。その手首を掴んだが、彼女の手は止まらずにベルトを外されチャックが下ろされる。先ほどの行為で少し勃起しかけていた物に下着越しに指が触れる。
下着から出されて彼女が身体を下ろして口を付けた。一瞬腰を引いたが彼女が根元を掴んで口の中に含んだ。生暖かい口内で先端を弄られる。
俺の脚の間で行われている行為に正常な思考回路が働かない。水音がして扱かれている間に昼休みの終了を告げるチャイムが鳴った。どこか遠くで感じるそれと、彼女のフェラ姿に身体が弛緩していく。完全に勃起したのを確認して彼女がスカートの下に手を入れてパンツを脱いだ。そのまま俺の上に跨る。
「……理沙?」
「っ、んん……いっ…………ぁんっ」
あまり濡れていない中に入り込む。温かく柔らかいけれど、潤滑液が少ないから少し痛い。入れ終わった彼女を抱きしめてキスをした。中が微かに動いて奥の方から液体を排出してくる。
彼女が不安定に動く。肌蹴ている胸元を更に開いて顔を埋めた。柔らかい胸とブラの生地が顔に擦れる。彼女が自分の二の腕に口を押し当てて声を殺している。ぐもった声と動いて鳴る椅子の音がする。全体重ではないとはいえ、二人の体重を支えているのは辛い。下から強く押し上げると彼女はびくんと反り返って、そのまま激しくすると声が漏れた。
「ぁ……、あ、っ……」
出す前にティッシュを持とうと思って、顔を胸元から外して机の上に置かれていたティッシュの袋に手を伸ばした。それを見た彼女が足を俺の腰に絡めた。全体重が俺の太ももと腰にかかる。
「な、離して」
「やだ、このままする、中出して」
外そうとしても足は外れなかった。くそ、と小さく舌打ちをして腰を振った。彼女の望み通りに膣内に射精した。中出しは今までの射精の中で一番気持ち良かったが、終わった後の倦怠感が半端なかった。
俺が出したのを感じたのか、彼女は足を緩めた。身体を離してふらふらと自分の元使っていた椅子に戻っていく。俺も疲れて景色が霞んで見える。思えば病み上がりだった。
「理沙は、せーやのためだったら何でも出来るの。覚えておいて、理沙はせーやが一番好きで大事だよ。せーやと理沙を離すのは例えせーやでも認めないから……」
満足そうな顔でそう言う理沙を見て、今した行為にぞっとした。顔が青ざめたのか、彼女が慌てて言葉を付け足す。
「いや、えっと、あのね、理沙を捨てないで欲しいの。お願い、せーやの言う事何でも聞くよ、嫌なところは言って貰えれば絶対直すし。理沙はせーや大好きだから、ね」
椅子から立ち上がって俺の頬を撫でる手に大人しく頷いた。
何、こいつ、怖ぇ。固まった状態で何度も首を縦に振った。頬を撫でる手は柔らかく俺の髪に移り、そのまま下に行って首を撫でる。無言で俺に触れる手に借りてきた猫のように大人しく従っていた。
それから先は出来る限りで理沙を避けた。あからさまでない程度に、何かと理由をつけて一緒に居る時間を少なくした。一人で勉強したい、康友、ゲーム、ネット、アニメ、とにかく有りとあらゆる言い訳を駆使した。クラスの男ともなるべく話さないように心がけた。最初は罪悪感に苛まれたが、徐々にそれも薄くなっていった。それでも節々に理沙を思い出すことはあった。理沙と離れることで嘔吐衝動は治まりつつあった。
「聖也明日暇?」
「ん、暇暇、週末課題今日中に終わらす予定だから」
「おーじゃあ明日聖也ん家ってことで。まだ攻略してねぇんだろ?俺横で見てるわ」
「いや意味わっかんねーから、まぁいいけど」
康友と喋りながら下校している時だった。後ろからせーや、と声をかけられた。振り向くと理沙が神妙な顔つきで立っていて、俺と康友は気まずい雰囲気を感じた。
久しぶりに正面からきちんと見た彼女はファーの耳あてとバーバリーのマフラー、Pコートを着て上は完全防備しているのに、下はこの寒い中ミニスカートに生足で足が赤っぽくなっていた。
「何?」
「ごめん、ちょっと時間いいかな」
「あ、いいよ、いいよ、俺先帰るから。じゃあ聖也また明日な」
康友が慌てた様子で声を張り上げて逃げるように歩いていってしまった。二人きりにされるとどうしようもなく、黙っていると彼女が俺の鞄を掴んだ。
「理沙の家、来て」
「今から?無理だよ、帰るの何時になるか。話ならどこか入ろうか?」
「……わかった、カラオケでいい?」
その言葉に頷いて彼女に鞄を掴まれたままカラオケに向かった。二人でカラオケに入るのは久しぶりだ、あの付き合いだした時とその後一回行ったのと。一番最初に行ったのと同じ店に入って、彼女がカードを出して今度は女の店員に案内された。
終始無言で、店員が飲み物を持ってくる間、コートを脱ぐ間も無言だった。俺はコーラで彼女は烏龍茶を頼んだ。彼女が喋らなければ俺達の間はこんなに無言が続くものなのかと思った。コーラに手を伸ばすと、彼女が口を開いた。
「もう、理沙のこと、嫌い?」
「嫌いじゃないよ」
「じゃあ何で避けるの、理沙達付き合っているんだよね?」
理沙が泣きそうな顔で俺の右腕を掴んだ。右腕に柔らかい感触がして、彼女の匂いと整った顔が近づいてきた。一気に侵食されそうなその行為に、背筋が冷たくなった。
どうして寒気がするのか、この女は俺の彼女じゃないのか、俺はこの女が好きなのではないのか。怖い、この生き物が。俺のどす黒い感情も醜態も全て浄化しそうな女が。もうこれ以上俺に違いを感じさせて惨めにしないで欲しい。純粋に俺を慕う心が憎い。
俺に、お前との、格の違いを目の当たりにさせるな。
「ごめんっ!」
思い切り彼女を突き飛ばして部屋を出た。以前来た時に覚えているトイレまで小走りで駆け込む、便器の前に来ると思い切り嘔吐した。嫌な声が響いて、胃がせり上がって中身を吐き出す。臭い、汚い、醜い。
胃の中を吐き出すとトイレットペーパーで軽く口や顔を拭いて出た。口と手を洗って部屋に戻る。戻りたくはないが戻る以外に術は無いのだ。カラオケの廊下が歪んで見えた。
ドアを開けると彼女は心配そうな目で見てきて、俺は大丈夫と小さな声を出した。その声を聞いて彼女はぼろぼろと涙を零した。俺がうろたえていると、涙を垂れ流した状態で俺の髪に手を伸ばした。
「紙、付いてる。これトイレットペーパーだよね、せーやの髪の毛、っ、伸びたから。っそんなに、理沙に触れられるの嫌?吐く、ほど?っ、ごめんね」
「いや、違うから、理沙に触れられるのが嫌ってわけじゃなくて……」
「ごめんね、苦しめてごめん。そうだよね、せーや別れたいって言ってたもんね。その時理沙凄い卑怯な手使ったもん。嫌われて当然だよね」
いつも俺の目を見て話していた彼女が俯いて喋り続けている。俺は自分の彼女を苦しめているのにそれを解消する手段を持たない。いや、持っているがそれが俺が彼女以上に傷つく方法なのだ。何も出来なくてただ目の前の光景を見ていた。彼女の泣き声と知らない音楽が響いていた。
一頻り泣いた彼女は涙を拭くと笑って、ありがとう聖也と言った。何にお礼を言われているのかわからなかったが、彼女に促されてカラオケを後にした。
その先、俺と理沙が二人きりで会話することは卒業式まで無かった。四月の進級でクラスも離れ離れになって、顔を見ることも少なくなった。卒業式、最後の最後に彼女が第二ボタンを貰いに来て、無言で渡した。痛々しい笑顔をしていたのが、最後に見た彼女の顔だった。結局はあのカラオケの後、彼女が冷却期間だと周りに言ったらしく、あまり騒がれることなく自然消滅していった。康友との会話、日々の不満、歌い手としてのそこそこの人気、俺は俺に舞い戻った。
今二人で並んで歩いている姿も全ての人間から笑われているのかもしれない。今まで理沙が勝手に注目を集めているのだと、俺の彼女可愛いだろ、羨ましいだろと思っていたが、嘲笑の的として視線を集めていたのかもしれない。疑心暗鬼は俺を苦しめて、理沙と一緒に居る時間が減って康友との時間が前と同じくらいにまでなりそうだった。
それでも毎日学校に行けば同じクラスにあの女が居て、否応なしに視界に入って、俺の事を見て笑っているように見えた。五月蝿い、うるせぇよクソビッチが。俺がお前に何をした、何で俺がお前の言葉でこんなに振り回されなきゃいけねぇんだ。
日曜に行った理沙の家では理沙を手酷く抱いた。後ろから背中を押さえつけてセックスをすると、加虐心が満たされてゴムを着けずに理沙の尻に射精した。理沙は涙に濡れた顔で俺を見て笑った。
「最近せーやドSだね、理沙もMなのかな、せーやなら何されても気持ち良いよ」
終わった後抱き付いてくる理沙を見て、こっちが泣きそうになった。頭をかき抱いて顔を合わせるのを防いだ。理沙の家の天井が見える。シミ一つない綺麗な天井に女特有の良い匂いがして、理沙の頭からシャンプーの匂いがした。綺麗で、綺麗で、隙のない空間。
理沙がするりと拘束を抜けて顔を上げた。床に落ちている俺のシャツを拾い上げて着ると、部屋の外に出て行き、紫色にピンクの紐が付いた紙袋を持って帰ってきた。何故か冷たいそれを身体を起こした俺に手渡す。
「ちょっと早いけどバレンタイン。学校に持って行くと溶けちゃうかなって思って」
「……すっげー冷えてる」
紙袋の中に入っていた小さな箱はショッキングピンクでリボンを外すとトリュフが三個入っていた。詳しくは知らないが絶対に高いやつだと思った。甘い匂いと酒の香りがする。
俺がそれを見てぼんやりとしていると、理沙が一つを取り出して口に咥えた。ん、と短い声を出して目を閉じて咥えたチョコレートを差し出す。
骨格に沿った綺麗な髪に白い肌、閉じているのに大きいと判る瞳、すっと通った鼻筋、チョコレートを咥えた小さな口、俺のシャツをだぼだぼに着こなす細くて白い身体。見下ろしたその姿にぞっとした。あの言葉が巡る。住んでいる世界が、違う。
「うっ……ごめん!」
口を抑えてもう場所を覚えてしまっているトイレに駆け込んだ。吐き出すものがなかったから胃液だけが喉を伝って口元に留まる。必死に嗚咽を堪えた。
あの日駆け込んだ場所とは違う掃除の行き届いたトイレ、ラベンダーの芳香剤の香り。全てが俺を拒絶しているようで再度吐き気が込みあがる。必死に耐えているとトイレの扉をノックされた。
「あの、せーや、大丈夫?体調悪かった?もしかしてチョコ苦手?あの、お酒が体質的に無理とかだった?ごめんね、大丈夫?お水持って来ようか?」
「…………いや、大丈夫だから」
レバーを引いて流水音で掻き消して口の中の物を吐き出す。幸いにもトイレ内に洗面台が備え付いていたから軽く口をすすいでトイレから出た。心配そうな顔で理沙が立っていた。
「悪い、ちょっと酒の匂い苦手で……」
「そう、なんだ。ごめんなさい。理沙も口洗うね。このままじゃせーやとチュー出来ないし。バレンタインまでには新しいの買っておくね!」
「あ、いや、いいよ。ごめん、俺もう帰るわ。マジごめん」
嘘を付いて理沙の顔を見ずにさっさと服を着ると立ち去った。吐き気が治まらない。彼女の家の最寄り駅のトイレでもう一度胃液を吐き出した。脈打つのは心臓だけでなく胃もだ。駅の汚いトイレは寛容に俺を受け入れてくれる。
結局その後家に帰ってから発熱をした。もしかしたらあの吐き気は風邪から来るものだったのかもしれない。熱は夜になっても、一晩眠っても下がらず、次の日学校を休んだ。
カーテンから日差しが入り、見上げる天井は薄汚く汚れていて、一晩中かいた汗で布団も身体も臭かった。両親が共働きの家には誰も居ないが、母親が昼飯や薬、飲み物等の用意はしておいてくれたようだ。重い身体を引きずってシャワーを浴びてから、お粥を温め卵を入れて食べて、薬を飲んだ。頭が痛い、節々が痛い、胃も何もかもが痛いのだ。
携帯には理沙からの心配するようなメールが届いていたが無視をした。お粥の入っていた土鍋とレンゲ、コップを水につけるとベッドに戻った。
玄関のインターフォンの音で目が覚めた。時計を見ると昼飯を食べてから二時間くらいしか経っていない。何度も響くそれは諦めろよと悪態をつきたいしつこさだった。ゆっくりと立ち上がりリビングの画面を見ると理沙が映っていた。何故だ、と驚きながら簡単に髪を撫で付けて、よれている服を整えて玄関に出た。
「何してんのっ!?」
「せーや!ごめん、メール返って来なかったから、共働きだって言ってたし心配なっちゃって!良かった、倒れてたりしたらどうしようって思って、それで、理沙……」
時間を考えても学校を抜け出して来ているのがわかった。必死な様子と手にコンビニの袋を下げている姿に嬉しさを感じたが同時に劣等感も感じる。彼氏のために授業を抜け出して看病の準備をこなす可愛い彼女。理沙はどこにも欠点が無い。
とりあえず彼女を玄関に入れて、扉を閉めた。
「俺は大丈夫だから、学校戻りなよ」
「いいの!結衣亜達にノートとか言い訳頼んで来たから。熱あるの、ごめんね寝てる時に。何か食べた?一応おうどんとか買ってきたんだけど、食べたならいいし。あーっと冷蔵庫はどこかな、アイスとか飲み物冷やしたい」
「……こっち」
理沙をキッチンに案内する。無言の俺に対して理沙も無言で後ろを付いてくる。
身体が弱っているせいか、不満が吹き出る。あの女の名前なんか出すなよ。謝るんなら来るんじゃねぇよ。寝てるってわかってんのに嫌がらせかよ。つか弱ってるとこ見せたくねぇのに何なんだよ。偽善ぶってんじゃねぇよ。この時間まで食べてねぇとかあるわけねぇだろ、俺の親何も出来ないって馬鹿にしてんのか。共働きでも家事や料理の準備くらいはやってくれるっての。普通に会社休んでくれて母親と鉢合わせとか想像しねぇのかよ。まぁキッチンだってリビングだって理沙の家よりは汚ぇよ。見るんじゃねぇよ、俺をこれ以上苦しめんなよ。大体親に何て説明すりゃいいんだよ理沙の持ってきた物をよ。
冷蔵庫に物を仕舞う理沙を見る。ぎちぎちに詰まった冷蔵庫の隙間を作って理沙が物を入れていく。無理矢理ではなく、さっと整理して入れる仕草に俺の領域が侵害されている感じがする。
会いたかったのに会いたくない。
「せーやのお部屋どこ?横になった方がいいよ、ごめんね邪魔しに来ちゃって」
「いや、いいよ。でも寝るから、えっと……」
帰って、という言葉が言い出せない。けれども実際帰って欲しい。こんな弱った姿をずっと見られるのも、俺の部屋を見られるのも、側に居られるのも、帰ってきた親に何か言われるのも全部嫌だ。苦しんでいる姿なんか彼女に見られたくない。
「眠れないなら理沙が添い寝してあげる、理沙にうつしちゃっていいよ」
笑いながら抱きついてくる彼女を跳ね除けた。部屋の中という二人きりの空間で彼女を拒絶したのは初めてだ。目を見開く彼女を見て目を反らした。
「…………もう、止めろ」
「え?」
「止めろよ、悪いけど、俺マジでだりぃから、悪い、帰って」
「……あ、うん、わかった。……ごめんなさい」
彼女は薄く涙目になりながら鞄を持って立ち去った。その場に立ち竦んでいると吐き気がまた込み上げてきてトイレで嘔吐した。食べた卵粥は吐き出され、涙と鼻水で顔が濡れた。
何故吐き気が込み上げるのかもわからない。何が不快でどうしようもないのか、彼女への苛立ちは何なのかよくわからない。どうして俺はこんなに弱くなってしまったのか。
顔と口を洗って水をラッパ飲みして胃を落ち着かせると再び布団に入った。
翌日には熱が下がって学校に向かった。通学路で康友と会って軽く話す。この時間が気楽で落ち着ける。
教室の前で別れて、室内に入ると理沙が駆け寄ってきた。周囲の目線がこちらに突き刺さる。今までどうして普通で居れたのだろう。過去の俺は鈍感で盲目で何もわかっちゃいない。
「おはようせーや、昨日はごめんね。大丈夫?ノートのコピー昼休みに渡すね」
「……はよ、あ、今日も弁当作って来たんだ」
「うん、栄養あるものばっかりだから元気出ると思う!」
あっそ、俺の親のは栄養考えてねぇ出来損ないの弁当かよ。今まで感じなかった理沙の言葉への反感が生まれる。
無言で頷くと理沙は俺の席に居座って担任が来るまで話を続けた。机に両肘をかけて、その上に胸を置くようにして俺に話しかける。いつもの光景、いつもの仕草、変わったのは俺の心の中だけなのかもしれない。吸い込まれそうな彼女の瞳は俺を確実に映していて、話の端々で笑って瞳を隠した。
昼休みに理沙と二人で空き教室で弁当を食べた。理沙が作ってきたカラフルな弁当と俺の親が作った茶色っぽい弁当を交換して食べる。理沙がくれたノートのコピーはいかにも女らしい丸っこい文字が不規則に離れた文字列を成していて、気持ち悪かった。
何事も無く食べ終えたところに理沙が箱を取り出した。
「病み上がりであれだけどチョコ。これは手作りだからお酒なんか入ってないよ。ね、開けてみて!」
「ん、ありがとう」
リボンを解いて箱を開けると四角形のチョコレートの上に絵が描いてあった。俺が前言っていた東方の好きなキャラクター五人だ。感動すると共に、絵の上手さに軽く引く。俺が何度も練習してある程度描けるようになったレベルとは全然違う。カラフルなその姿に華やかさを感じる。
「あ、もしかして可愛くて食べられないとか!?理沙昨日ガチ頑張ったんだよ、ググってチョコの上にカラーイラスト描く方法見つけてさ、失敗したやつはお母さんと自分用ってことにしてー」
理沙の声が遠くに聞こえた。
どうしようか、心臓が握りつぶされそうだ。
チョコが嬉しいのは事実、二次元嫁の姿に感動したのも事実、理沙の事を好きなのも事実、だけれど、一挙一動に劣等感を感じて死にたくなるのも事実だ。
「……せーや?」
「もう、こういうの、止めよう」
必死に捻り出した声は震えていた。チョコの箱を机に置いて、理沙に頭を下げた。彼女の顔は見えないけれど、驚いているのは雰囲気でわかる。
空き教室の寒い空気が更に温度を下げた。こつこつと雨が窓を叩いて音を立てる。今まで雨が降っていたことにも気付かなかった。
「止め、ようって、どういうこと?バレンタインが嫌ってこと、それとも……理沙が、嫌ってこと?」
「……どっちも。ごめん。俺、これ以上付き合えない」
「やだっ!!」
急に理沙が大声を上げた。初めて聞く大きな声だった。
顔を上げると彼女が目に涙を溜めて真っ赤にしていて、両手を胸元で握っていた。手に力が強くかかっているようで指先は白く、腕は震えている。
「理沙は、やだよ。ど……こが、嫌?理沙、直す、から……」
彼女は目に溜っていた涙を零して、こちらを見つめる。痛々しい。眉が下がって、唇が震えている。歯を噛み締めているのがわかる。
何故か手が伸びて彼女の目尻を拭った。指先が涙で濡れる。その手に彼女が手を重ねてきて、指先に唇が触れた。
「こういうの、嫌?もう、したくない?」
「………………え」
じゃあ、と彼女は呟いて俺の膝に跨って首に手をまわした。固まっている状態でキスをされる。唇がふわふわと触れ合う。目を開けたまま口付けを受けていると、首を強く抱かれて舌を入れられた。驚いて舌で押し返したが、その舌を舐めあげられる。
唾液が押し返している舌と唇の間から落ちた。一瞬だけ顎に触れて彼女のスカートに落ちる。長いキスに勃ちそうになって、彼女の腰を両手で持って身体を離そうとした。首に回された腕に力がこもる。
大人しくなされるがままにしていると、首の拘束が取れて顔が離れた。荒い息をして彼女がこちらを見つめる。
「嫌、だった?」
「………………」
「触って……お願い、理沙を、拒絶しないで」
彼女が俺の右手を自分の腰から胸に持って行った。カーディガンの手触りと奥にある胸の柔らかさを感じる。初めは感じなかった脈拍が掌から伝わってきた。早い。少し力を込めるとぐにゃっと形が変わった。
俺の手の上にあった彼女の手が動いてカーディガンのボタンを外し始めた。
「え、何して……?」
俺の声には答えずに彼女の指はブラウスのボタンに掛かった。胸に置いていた手を外して彼女の脱衣を止めるようにカーディガンの前を閉じた。これ以上俺を誘惑しないで欲しい。もう少しで昼休みも終わる、こんな場所で、こんな時間で何を始めようとしているのか。必死にカーディガンを押さえて見える肌を消す。
「もう戻ろう、昼休み終わるよ」
「やだ、ねぇ、しようよ、理沙したい。お願い」
「俺ゴム持ってないし、こんな場所で何を考えているの?授業もあるし、落ち着いて」
「やだ、今離れたら本当に離れちゃう気がする、やだ、ぎゅっとしてよせーや」
ぼろぼろと涙を零して俺に抱きついてくる姿に心が痛む。押し黙っていると、彼女が俺のベルトに手をかけた。その手首を掴んだが、彼女の手は止まらずにベルトを外されチャックが下ろされる。先ほどの行為で少し勃起しかけていた物に下着越しに指が触れる。
下着から出されて彼女が身体を下ろして口を付けた。一瞬腰を引いたが彼女が根元を掴んで口の中に含んだ。生暖かい口内で先端を弄られる。
俺の脚の間で行われている行為に正常な思考回路が働かない。水音がして扱かれている間に昼休みの終了を告げるチャイムが鳴った。どこか遠くで感じるそれと、彼女のフェラ姿に身体が弛緩していく。完全に勃起したのを確認して彼女がスカートの下に手を入れてパンツを脱いだ。そのまま俺の上に跨る。
「……理沙?」
「っ、んん……いっ…………ぁんっ」
あまり濡れていない中に入り込む。温かく柔らかいけれど、潤滑液が少ないから少し痛い。入れ終わった彼女を抱きしめてキスをした。中が微かに動いて奥の方から液体を排出してくる。
彼女が不安定に動く。肌蹴ている胸元を更に開いて顔を埋めた。柔らかい胸とブラの生地が顔に擦れる。彼女が自分の二の腕に口を押し当てて声を殺している。ぐもった声と動いて鳴る椅子の音がする。全体重ではないとはいえ、二人の体重を支えているのは辛い。下から強く押し上げると彼女はびくんと反り返って、そのまま激しくすると声が漏れた。
「ぁ……、あ、っ……」
出す前にティッシュを持とうと思って、顔を胸元から外して机の上に置かれていたティッシュの袋に手を伸ばした。それを見た彼女が足を俺の腰に絡めた。全体重が俺の太ももと腰にかかる。
「な、離して」
「やだ、このままする、中出して」
外そうとしても足は外れなかった。くそ、と小さく舌打ちをして腰を振った。彼女の望み通りに膣内に射精した。中出しは今までの射精の中で一番気持ち良かったが、終わった後の倦怠感が半端なかった。
俺が出したのを感じたのか、彼女は足を緩めた。身体を離してふらふらと自分の元使っていた椅子に戻っていく。俺も疲れて景色が霞んで見える。思えば病み上がりだった。
「理沙は、せーやのためだったら何でも出来るの。覚えておいて、理沙はせーやが一番好きで大事だよ。せーやと理沙を離すのは例えせーやでも認めないから……」
満足そうな顔でそう言う理沙を見て、今した行為にぞっとした。顔が青ざめたのか、彼女が慌てて言葉を付け足す。
「いや、えっと、あのね、理沙を捨てないで欲しいの。お願い、せーやの言う事何でも聞くよ、嫌なところは言って貰えれば絶対直すし。理沙はせーや大好きだから、ね」
椅子から立ち上がって俺の頬を撫でる手に大人しく頷いた。
何、こいつ、怖ぇ。固まった状態で何度も首を縦に振った。頬を撫でる手は柔らかく俺の髪に移り、そのまま下に行って首を撫でる。無言で俺に触れる手に借りてきた猫のように大人しく従っていた。
それから先は出来る限りで理沙を避けた。あからさまでない程度に、何かと理由をつけて一緒に居る時間を少なくした。一人で勉強したい、康友、ゲーム、ネット、アニメ、とにかく有りとあらゆる言い訳を駆使した。クラスの男ともなるべく話さないように心がけた。最初は罪悪感に苛まれたが、徐々にそれも薄くなっていった。それでも節々に理沙を思い出すことはあった。理沙と離れることで嘔吐衝動は治まりつつあった。
「聖也明日暇?」
「ん、暇暇、週末課題今日中に終わらす予定だから」
「おーじゃあ明日聖也ん家ってことで。まだ攻略してねぇんだろ?俺横で見てるわ」
「いや意味わっかんねーから、まぁいいけど」
康友と喋りながら下校している時だった。後ろからせーや、と声をかけられた。振り向くと理沙が神妙な顔つきで立っていて、俺と康友は気まずい雰囲気を感じた。
久しぶりに正面からきちんと見た彼女はファーの耳あてとバーバリーのマフラー、Pコートを着て上は完全防備しているのに、下はこの寒い中ミニスカートに生足で足が赤っぽくなっていた。
「何?」
「ごめん、ちょっと時間いいかな」
「あ、いいよ、いいよ、俺先帰るから。じゃあ聖也また明日な」
康友が慌てた様子で声を張り上げて逃げるように歩いていってしまった。二人きりにされるとどうしようもなく、黙っていると彼女が俺の鞄を掴んだ。
「理沙の家、来て」
「今から?無理だよ、帰るの何時になるか。話ならどこか入ろうか?」
「……わかった、カラオケでいい?」
その言葉に頷いて彼女に鞄を掴まれたままカラオケに向かった。二人でカラオケに入るのは久しぶりだ、あの付き合いだした時とその後一回行ったのと。一番最初に行ったのと同じ店に入って、彼女がカードを出して今度は女の店員に案内された。
終始無言で、店員が飲み物を持ってくる間、コートを脱ぐ間も無言だった。俺はコーラで彼女は烏龍茶を頼んだ。彼女が喋らなければ俺達の間はこんなに無言が続くものなのかと思った。コーラに手を伸ばすと、彼女が口を開いた。
「もう、理沙のこと、嫌い?」
「嫌いじゃないよ」
「じゃあ何で避けるの、理沙達付き合っているんだよね?」
理沙が泣きそうな顔で俺の右腕を掴んだ。右腕に柔らかい感触がして、彼女の匂いと整った顔が近づいてきた。一気に侵食されそうなその行為に、背筋が冷たくなった。
どうして寒気がするのか、この女は俺の彼女じゃないのか、俺はこの女が好きなのではないのか。怖い、この生き物が。俺のどす黒い感情も醜態も全て浄化しそうな女が。もうこれ以上俺に違いを感じさせて惨めにしないで欲しい。純粋に俺を慕う心が憎い。
俺に、お前との、格の違いを目の当たりにさせるな。
「ごめんっ!」
思い切り彼女を突き飛ばして部屋を出た。以前来た時に覚えているトイレまで小走りで駆け込む、便器の前に来ると思い切り嘔吐した。嫌な声が響いて、胃がせり上がって中身を吐き出す。臭い、汚い、醜い。
胃の中を吐き出すとトイレットペーパーで軽く口や顔を拭いて出た。口と手を洗って部屋に戻る。戻りたくはないが戻る以外に術は無いのだ。カラオケの廊下が歪んで見えた。
ドアを開けると彼女は心配そうな目で見てきて、俺は大丈夫と小さな声を出した。その声を聞いて彼女はぼろぼろと涙を零した。俺がうろたえていると、涙を垂れ流した状態で俺の髪に手を伸ばした。
「紙、付いてる。これトイレットペーパーだよね、せーやの髪の毛、っ、伸びたから。っそんなに、理沙に触れられるの嫌?吐く、ほど?っ、ごめんね」
「いや、違うから、理沙に触れられるのが嫌ってわけじゃなくて……」
「ごめんね、苦しめてごめん。そうだよね、せーや別れたいって言ってたもんね。その時理沙凄い卑怯な手使ったもん。嫌われて当然だよね」
いつも俺の目を見て話していた彼女が俯いて喋り続けている。俺は自分の彼女を苦しめているのにそれを解消する手段を持たない。いや、持っているがそれが俺が彼女以上に傷つく方法なのだ。何も出来なくてただ目の前の光景を見ていた。彼女の泣き声と知らない音楽が響いていた。
一頻り泣いた彼女は涙を拭くと笑って、ありがとう聖也と言った。何にお礼を言われているのかわからなかったが、彼女に促されてカラオケを後にした。
その先、俺と理沙が二人きりで会話することは卒業式まで無かった。四月の進級でクラスも離れ離れになって、顔を見ることも少なくなった。卒業式、最後の最後に彼女が第二ボタンを貰いに来て、無言で渡した。痛々しい笑顔をしていたのが、最後に見た彼女の顔だった。結局はあのカラオケの後、彼女が冷却期間だと周りに言ったらしく、あまり騒がれることなく自然消滅していった。康友との会話、日々の不満、歌い手としてのそこそこの人気、俺は俺に舞い戻った。
十月に出会い(長らく不在の神が降りて来た)、
十一月に恋人に(霜は溶かされ)、
十二月に触れ合って(走り出したい程の幸福が)、
一月に溺れて(睦言は甘かったのに)、
二月にさようなら(まるで夢の如く)、
それから先は土の中と同じ。

