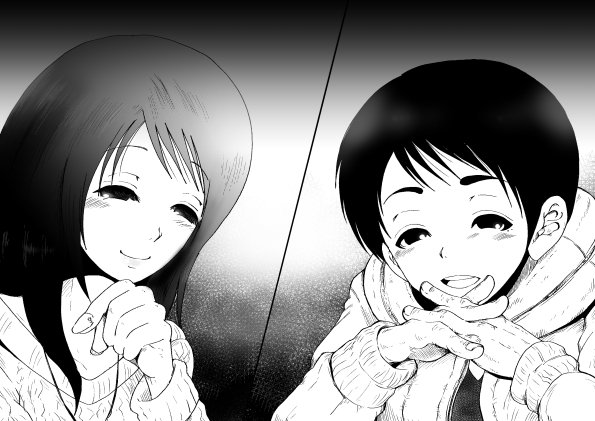用法用量を守って正しいストーキングを。
9
****は、自分の名前をひどく嫌っていた。
嫌悪を抱くきっかけは覚えていない。ただ物心ついた時点で不快だと感じていたことだけは記憶にある。
その名前を口にされないようにある時から*****は自分のことを瀬賀と名乗った。名前をもじったような、けれど直接的でない抽象的な単語の組み合わせだ。考えついた名前の中で、最も馴染んでもらえそうな渾名だと彼は思った。
目論見通りその【あだ名】は定着し、今では彼を*****や*****と呼ぶ友人はほとんどいなくなった。みんな「瀬賀」をちゃんと使ってくれている。その名前がどう伝わったのか誰も知らないし、きっかけも覚えていない。ただなんとなく周りが呼ぶから瀬賀。それは、彼の執念じみた努力の賜物だった。
「瀬賀、なんかあったの?」
通話を終え、画面から顔を上げると瀬賀は目を細めて笑う。いつものとっつきやすく柔和な、人を”不快にさせない”顔を浮かべると、大したことじゃないと伝えた。
瀬賀のとっつきやすいフリは、潮の取り繕った姿や森のとぼけたフリとはまた違った類で、その精度は二人の比べ物にならないほど精密に組み上げられている。だから、これを不自然だと思う人はいない。
「瀬賀も物好きだよな」
「物好き?」
学友の言葉に瀬賀は首を傾げる。週刊誌をぺらぺらと捲る彼の顔は、とても退屈そうだった。
「ほら、小波だっけか。アイツちょっと気味悪いのによく付き合うなって思ってさ」
「そうかなあ……。案外付き合ってみると良い奴だよ。今度話してみる?」
「遠慮しとく。瀬賀のコミュ力ほんとすげーよなあ。お前が合わない奴とか想像できないし」
「俺にだって苦手な人はいるよ」
「例えば?」
「んー、すぐには思い浮かばないけど」
「ほら」
ケラケラ笑う学友の反応に、瀬賀は困ったように苦笑する。
講義室の席から人が消えていく。暗幕でも垂れたみたいに暗くなった窓の外の風景に、講義室と瀬賀たちの姿が映っているのが見える。瀬賀はしばらく自分の姿をじっと見つめ、やがて鞄を肩に提げて席を立った。
「今日は用事ありなのか? さっきの電話って女?」
学友の問いかけに瀬賀はそうなんだ、と困り顔を作る。
「うちの従姉妹、なんかあったみたいでさ。また明日ね」
「お前も大変だな、色んな奴の面倒見てさ。恋人作る暇もないんじゃねえの?」
彼はそう言いながら手元から薬包を瀬賀に差し出す。いつも悪いね、と言いつつ瀬賀はそれを受け取ると、鞄にしまった。
「今は全然そんなの考えてないよ~。あー、でも……いや、なんでもないかな」
曖昧な返答と同時に目を逸らす。それだけで学友は簡単に釣れた。彼は目を輝かせて瀬賀を見る。
「なんだよ、なんか気になる奴でもいるのか?」
「いやいや、でも俺には高嶺の花だからさ……。ほら、糸杉さんとか」
「あー……」
学友は同情にも似た目を瀬賀に向け、肩に手を置いた。やっぱり、そうだよね、と瀬賀が小さく呟くと、彼はゆっくり頷いた。
「諦めろ、ありゃ流石の瀬賀でも無理だ」
●
学友と別れ、大学を出てしばらく帰路を歩く。周囲を気にしながら人気のない小道に入ると、鞄の中にしまった薬包を見た。なんてことはない、少し効きの良い睡眠薬だ。ここ最近眠りが浅いという理由を告げたら、彼がこっそりとくすねてきてくれたものだった。彼はたまにそういった類のものを裏から回してくれる。といってもできて睡眠薬とか風邪薬とか、それくらいだ。
瀬賀は彼が手を置いていた肩を何度か払った後、鞄を閉じて再び歩き出した。
街灯が円形に照らす光の下をいくつも潜りながら、閑寂とした住宅街の片隅まで瀬賀は歩く。しばらくすると、マンションが見えてきた。四階建て、ベージュ色に塗装された細長い建物。瀬賀はここで一人で暮らしている。そのほうが都合が良いのだ。何をするにしても。
玄関口の自動扉を通ると、オートロックの前に愛美の姿を見つけた。
「ただいま」
「瀬賀ちゃん」
顔を上げた愛美は、雨に濡れた小動物みたいだった。よほど掴んだ情報がショックだったのだろう。やっぱり、あざみに関する情報を調べさせて正解だった。
「あざみちゃんをなんとかしなくちゃ」
「愛美、落ち着いて。話は部屋で聞くから」
オートロックを開け、奥のエレベーターに乗って三階へ。暖色のライトが照らす廊下を奥まで歩いて、角部屋へ辿り着くと瀬賀は愛美を入れた。
固い扉を閉じて、鍵をかける。バーも下ろした。
これで、この部屋は愛美と瀬賀の二人だけだ。愛美は靴を脱ぐと電気を付け、四帖のキッチンルームを抜けて、八帖のワンルームまで入っていく。
瀬賀の部屋は非常に簡素な部屋だ。特徴といえばウォークインクローゼットが広いくらいで、あとはベッドに小型のローテーブルとテレビ。書棚も一応あるが大して数は入っていない。
ローテーブルの上にはノートブックが置かれ、その奥、窓際の片隅に小さな丸型のラグ・カーペットが置かれている。
愛美の部屋に比べたら何もないようなものだ。瀬賀は鞄をベッドに置いて縁に腰掛けた。窓際に目を向けると、愛美はラグカーペットの上に正座している。自分の身体がはみ出ない丁度いい大きさのカーペットに、彼女はすっぽりと収まっていた。
「何か飲む?」
「うん……」
キッチンルームに置かれたケトルに水を注ぎ、スイッチを入れる。その間にマグカップにティーバッグを入れてトレーに載せた。ああ、と瀬賀は小さく呟いて棚を開ける。愛美が好きだったチョコチップクッキーがまだ一パック残っていたのを思い出したのだ。
「それで、あざみさんについて調べてどうだったの?」
ノートブックを片付けてトレーを置く。ラグカーペットの中で愛美は不安げな顔を浮かべたまま黙っている。これだから、ドン臭いのは嫌いなんだ。瀬賀は不満げな顔を浮かべて彼女を睨んだ。愛美はその顔を見て慌てて何か喋ろうとするが、あ、とかう、とか言葉になっていない声しか出ず、身体も緊張で強張っていく。
瀬賀は愛美に歩み寄り、しゃがむと束ねられた髪を一房掴んで思い切り持ち上げるように引っ張る。痛、と小さな声が聞こえたが、その悲鳴を聞いて瀬賀は顔をしかめる。
「愛美、聞かれたことは?」
「……すぐに答える」
強く髪を引かれた愛美の陶器のように白い首筋が見える。肌にはらり、と零れた髪が流れ落ちていく。
愛美はあざみの話を始めた。彼の機嫌を損ねないように、丁寧に、丁寧に。
その情報を聞きながら、あの女も大概だな、と瀬賀は肩を竦めた。恐らく森とルナの件も彼女が一枚噛んでいるに違いない。といってそれを追求をするつもりもなければ、する理由もないので森の件は構う必要はないだろう。
愛美は喋り疲れたのか、深い呼吸をする。唇のぷっくりとした柔らかな唇と、頬から顎にかけての柔らかなライン。その輪郭に乗る色艶のある毛先を瀬賀は何の毛無しに指で掬い取ってみる。全く、怖気がするほどなめらかな触り心地だった。
「愛美は、潮が好き?」
「好き」
「でもこのままだとあざみさんに取られちゃうよ」
「そんなの嫌!」
「じゃあ、沢山アプローチしなくちゃいけないよね」
愛美の頭を撫でる。
何故神様は、彼女にばかり甘いのだろう。どれだけ嫉妬しても手に入らない自分に比べて、彼女ははじめからなんでも持っていた。
なんでも持っているくせに、何故欲しがるのか。
全くもって不平等だ。
「愛美は本当に駄目な子だよね。俺が手助けしないと何も決められないんだからさ」
愛美の潤んだ眼差しを見下しながら、瀬賀は皮肉げに笑う。
幼い頃誰もがこの縋るような眼差しに従った。彼女の興味を惹きたくて、頼りがいのある男を目指した。でも、彼女の愛に応えられた男は、一人もいなかった。
彼女の頬に触れ、下唇を親指で押す。口内の生ぬるい吐息が指にかかる。
気持ちが悪い。
「本当に、愛美は何だったら自分でできるんだろうね」
愛美は、喋る人形だ。何があっても、どこまでいっても瀬賀の言葉を一番に動く人形。
彼女のことならなんでも知っている。嫌いな物も、好きなものも、身体の洗い方から髪の維持、得意な髪型、胸のサイズ、生理の周期、使っている美容液。瀬賀が全て決めてきた。導いてきた。
そして今も、瀬賀が見つけさせた潮にアプローチを続けている。
「あざみさんの件は俺に任せてよ。もしかしたら、愛美にとって都合のいい流れにできるかもしれない」
「本当?」
愛美の顔が驚きと喜びに満ちる。瀬賀は満面の笑みで頷いた。
「だから安心して、俺が愛美に間違ったことを教えたこと、ある?」
「ない。*****ちゃんはいつだって正しーー」
「その名前で呼ぶなって、何度言ったっけ?」
愛美の言葉が止まる。いや、止めさせた。彼女の頬を挟むように掴んだ瀬賀は穏やかな顔のまま愛美を見つめ、首を傾げた。
「ほら、ちゃんと言って。せが、でしょ?」
「せ、瀬賀くん」
よくできました。瀬賀は払うように愛美を左へ放った。床に転がった愛美は自分の頬を撫でながら、目に涙を浮かべ、ごめんなさい、と弱々しく呟く。その姿を見下ろしながら、瀬賀は思わず口元に笑みを浮かべてしまう。
摘みたい、という気持ちを抑えることがこんなにも苦しいことだとは思わなかった。だが、我慢の先には快楽が待っている。焦らされ、切なさに塗れた末の射精の瞬間のように、きっと愛美が壊れる瞬間は、甘美に違いない。
瀬賀はしゃがむと、愛美の髪をひと束摘み上げる。
そろそろかな、と小さな声で呟くと、潤んだ目で見上げる愛美の前で人差し指と中指を立てて、彼女の髪を挟む。
「長くなってきたね、コレ」
「ーー!」
瀬賀は一瞬、自分が何をされたのか分からなかった。
気がついた時、彼は床に転がっていた。テーブルの角にぶつかったのだろう、右腕に一筋の赤い痛みがあった。瀬賀はその傷と、愛美とをしばらく交互に見ていた。
愛美は、自分がしてしまったことに気がつくと急いで立ち上がり、そして「ごめんなさい」と一言残して部屋を逃げるように出ていった。部屋に残された瀬賀はその突然の拒絶をしばらく呑み込めず呆然としていたが、やがて、深く一度息を吸って、吐いた。
「恩知らずが」
思わず口から出た言葉を聞いて、瀬賀は頭を振る。この感情は、駄目だ。表に出すべきではないものだ。
内に秘めて、ゆっくりと馴染ませるべきものだ。
瀬賀は深呼吸をすると立ち上がり、ウォークインクローゼットを開く。目の前に置かれた姿見に、瀬賀の全身が映っている。
姿見の奥には、いくつもの服が掛けられている。丁寧にビニールで覆われ、防虫剤や消臭剤も置かれ、厳重に保管してされたそれらを見て、瀬賀は口元に笑みを浮かべた。
クローゼットの中を見たら、きっと誰もが目を疑うだろう。彼の表の顔との差に、何の冗談かと思うかもしれない。
ここには、瀬賀の秘密がしまわれている。
見られてはいけない、秘められた想いの全て詰め込まれている。
瀬賀は衣服と下着を脱ぎ捨てた。姿見には、一人の白く華奢で頼りない、しかし肩幅や腰骨だけしっかりとしている男の裸があった。
*****は、クローゼット奥の抽斗を開けて、淡い緑のショーツとブラジャーを取り出す。*****のお気に入りの花の刺繍の入ったそれを身につけると、身が震えた。自分が矯正されていく。正しい方へ。この間隔を味わっている瞬間、*****は心穏やかな気持ちになれた。
ビニールで包まれた中から一着取り出し、ビニールを丁寧に剥がす。無地の黒の上に赤青黄の花があしらわれたベルスリーブタイプのワンピース。そのゆったりとした着心地を肌で感じながら、*****は一度くるりと回ってみせた。ふわりと広がるスカートのふくらみがとても美しかった。最後に黒いソックスと、卸したての黒いハイカットスニーカーを身に着けて出来上がり。
鏡の前に、ワンピースを身に付けた男の姿が映る。*****はにっこりと笑うと姿見に近づいて、鏡の中の自分の頬をそっと撫でた。
「ほんと……こんな可愛いのに、みんな、センスが終わってる」
あとはウィッグが欲しい。綺麗で、繊細で、触れると溶けてしまいそうな緩やかな髪でできたウィッグが。
*****は、出来上がりたかった。
育てた実を摘むと同時に、自分も出来上がる。その瞬間を、ずっと待っている。
だから、その実に拒絶されたことが、*****を不愉快にさせた。でも彼女はまだ壊せない。この苛立ちを、不快感を、彼女にまだぶつけてはいけない。
なら、他で代用するしかない。
*****は携帯を手に取ると、彼女からの連絡を改めて見た。高飛車で、自分の美しさを疑うことのない、愛されたがりの依存女のアカウント。*****はそれを見て微笑む。
●
「お待たせ、糸杉さん」
カフェの中央の席に座り、携帯を弄っていたあざみは顔を上げて、そこに目的の異性を見つけると嬉しそうにはにかみ、それからどこか不安そうな笑みに表情を変えた。
瀬賀はそれを見て、穏やかな笑みを浮かべた。ごめん遅れちゃって、と一言添えて向かいの席に座ると、彼女は首を横に振った。
「突然ごめんね、迷惑じゃなかった?」
「そんな、糸杉さんにお茶を誘ってもらえるなんて思ってなかったからびっくりしたよ」
瀬賀の返答に気を良くしたのか、それとも容易い男だと思ったのか、あざみは覗き込むように瀬賀を見て、助けてほしいの、と弱々しい声で呟く。
「何か……あったの?」
「実はね、潮くんのことで……」
大切な友人の名前をきっかけに、二人の対話は、始まった。