女子小学生だって悩みますっ・文系
じゃんけん
莉々ちゃんは北欧っぽいところからやって来た。ブロンドの髪に透き通るような肌を持った莉々ちゃんは黙って立っていれば人形のようだ。
そんな莉々ちゃんが鏡の前でじゃんけんしてる。お昼休みの時間に図書館へと向かう途中に目撃した出来事だった。
鏡の中の自分と自分の目を合わせて、グーを出したりチョキを出したりパー出したり。試合前のボクサーが仮想する相手に向かってこぶしを繰り出す姿にも似ている。
学校の中の廊下、壁に貼り付けられた大きな鏡。これを見て自分自身を顧みましょうと、言わんかばかりの鏡。日頃何気なく見ている鏡でも、莉々ちゃんが前に立てばちょっとしたイベントだ。金色の髪をぶんぶんと振りまきながら、莉々ちゃんのじゃんけんは続く。
「あっ。聖子ちゃん、現れたなっ。どこいくの」
「図書館だよ」
「今日は負けないかんねっ」
今日は?
「この間はさんざんだったけど、今度こそはっ」
この間?
わたしの中の記憶をたどってゆくと、一昨日の帰り道のことを思い出した。莉々ちゃんとじゃんけんをしたもっとも新しい記憶はその時だったからだ。
「聖子ちゃんと別れる信号まで、全戦全勝することを誓いますっ」
「ランドセルじゃんけんのことだよね」
「どんな試合でもたゆまず、正々堂々と挑むぞっ」
「力の入れようがすごいね」
そんな莉々ちゃんが鏡の前でじゃんけんしてる。お昼休みの時間に図書館へと向かう途中に目撃した出来事だった。
鏡の中の自分と自分の目を合わせて、グーを出したりチョキを出したりパー出したり。試合前のボクサーが仮想する相手に向かってこぶしを繰り出す姿にも似ている。
学校の中の廊下、壁に貼り付けられた大きな鏡。これを見て自分自身を顧みましょうと、言わんかばかりの鏡。日頃何気なく見ている鏡でも、莉々ちゃんが前に立てばちょっとしたイベントだ。金色の髪をぶんぶんと振りまきながら、莉々ちゃんのじゃんけんは続く。
「あっ。聖子ちゃん、現れたなっ。どこいくの」
「図書館だよ」
「今日は負けないかんねっ」
今日は?
「この間はさんざんだったけど、今度こそはっ」
この間?
わたしの中の記憶をたどってゆくと、一昨日の帰り道のことを思い出した。莉々ちゃんとじゃんけんをしたもっとも新しい記憶はその時だったからだ。
「聖子ちゃんと別れる信号まで、全戦全勝することを誓いますっ」
「ランドセルじゃんけんのことだよね」
「どんな試合でもたゆまず、正々堂々と挑むぞっ」
「力の入れようがすごいね」
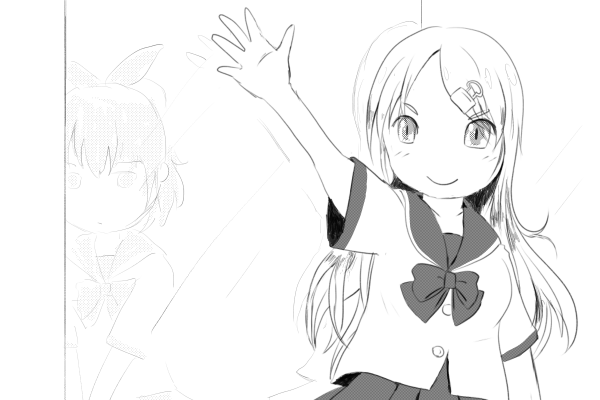
じゃんけんの敗北者は二人分のランドセルを前後に持つ。重さは莉々ちゃんの表情で容易に想像できるが、莉々ちゃんは勝負を楽しむかのように笑っていた記憶が。教科書にノート、筆入れ。水筒にタブレットにその他もろもろ。昨今の女子小学生をなめちゃいけない。八甲田山の行軍にも負けず劣らずの装備を強いられて、わたしたちは学び舎へと毎日向かうのだから。わたしとしては重い荷物を抱え込むことを考えると、あんまり負けたくない。どうでもいいけど。
振り上げた莉々ちゃんの小さなガッツポーズ。わたしはこれまでこんなにかわいいガッツポーズを見たことはない。ガッツというフレーズが名前負けするレベルだし。
帰り道のランドセルじゃんけんに、これほど心血を注ぐ女子小学生はどこにいようか。
グーを出す速度、チョキを出す腕の角度、パーを出す足のベクトル。全てを完璧の境地にまで高めんと、莉々ちゃん手は武者震いをしていたのはちょっと感動。
ランドセルじゃんけんは小学生の間にだけ許された遊びだ。勝者は敗者をこき使うようにランドセルを持たせる。運。運が全てを解決させる。
中学生ならばまだ微笑ましく、高校生ならばSNS映えを意識させられる。だが、大人になってからのランドセルじゃんけんなどは、痛々しい以外の表現が見つからない。ましてや、YouTuberの企画ならばなおさらだし。逆を言うならば、子どものうちに全力で楽しむのが吉じゃないか。しかし、子どもだということを担保に遊びじゃくるのも、ちょっとわたしには子どもすぎると思う。だって、もう小学六年だし。
そろそろオトナを意識したいお年頃、オトナって何に向かって進むのだろう。身近なオトナを思い浮かべても、オトナがオトナに見えてこない。
そういえば、うそうそ時の週末には、毎度毎度とオトナの女性がじゃんけんを仕掛けてくるし、時代をときめくアイドルたちもじゃんけんに我が身の運命を託す大会を催しているし。だから、わたしたち女子小学生だってじゃんけんに願いをのせても不思議じゃない。莉々ちゃんはあいかわらず鏡の中の自分とじゃんけんの特訓を繰り返し、わたしは目的の部屋へと向かった。
図書館の児童たちはまばらだった。さんさんと太陽輝くお昼休み、お年頃の子たちは外で遊ぶのがおあつらえってことなんだろか。
昨今の公園には遊具がない、というか、昭和の頃には当たり前だった遊具が危ないからという理由で撤去されたらしい。それをオトナたちは「最近の子どもたちは外で遊ばなくなった」と嘆いているらしい。遊具がないなら、ないなりに遊ぶことを工夫しなければいけないわたしたちの責務でもある。ここでオトナに向かって牙向くのは一種の思考の停止だと思う。与えられないならば、作ったら?わたしは図書館に行くけど。
小さな低学年の為に背の高い六年生が高い位置の本を取ってあげていた。同じクラスの越智ちゃんだった。
彼女はモデルのようにスタイルがいい。女子小学生なのに。
お兄ちゃんがいるらしく、その影響なのか大人びている。女子小学生なのに。
百四十センチあるかないかのわたしからすれば、その背の高さは犯罪的だ。女子小学生なのに。
取ってあげた本を小さな低学年の子に手渡すと、たんぽぽのように微笑む。女子小学生なのに。
オトナの振る舞いが自然に身に着けている越智ちゃん。女子小学生なのに。
小リスのステップで受付カウンターに向かう低学年の子が手にしている本は夢野久作の「ドグラ・マグラ」だった。女子小学生なのに。
誰かのためにわが身を削る、ただその行為は至極当然なこと。だが、越智ちゃんはさらりとそつなくこなす、まるでオトナのよう。女子小学生なのに。
多分、越智ちゃんはランドセルじゃんけんなどしないだろう。わたしの妄想だけど。
まだまだわたしはオトナになりきれてない。女子小学生だし。
一冊だけ本を借りて図書館をあとに、鏡の場所を再び訪れると莉々ちゃんはじゃんけんの練習を続けていた。何の本を借りたかって?人のことを詮索するのはオトナじゃないなぁ。
下校時間、莉々ちゃんを待たせてしまった。
理由と言えば、お話にするでもない些細なことだったので省きたい。約束の巌流島へ向かう宮本武蔵の気持ちが分かる……訳がない。前言撤回。それほど、わたしは焦っているし。
莉々ちゃんのことだからきっとやきもきしながらわたしが来るのを待っているはず。わたしの予想は裏切らなかった。
「遅いぞっ、聖子ちゃんっ」
威勢だけは佐々木小次郎の莉々ちゃんが、にこにこしながらわたしが来るのを待っていたのだ。ぴょんと跳ね上がり、手にしていた靴を床に解き放つように落とすと、乾いた音がそこら中に響いていた。がちゃっと莉々ちゃんの水色のランドセルが背中で音をさせていた。
「よーし。勝負だぞっ」
「ちょっと、待って……」
じゃんけんの準備運動をしながら、莉々ちゃんは健闘を誓った。じゃんけんの準備運動って、何?それほど、わたしは焦っていたし。
「じゃんけんぽん!!」
グーを突き出したわたしの対面の手は平和のシンボルを示していた。
石ころを突き出したわたしの真正面はハサミを差し出していた。
北欧少女の目つぶしはわたしの鉄拳にて潰された。
「……ふふふ。わたし、破れたりっ」
ストップモーションで莉々ちゃんはパーの姿で固まっていた。
「うん。約束だよね」
「あれだけ練習をしたのにっ」
勝負の世界の厳しさは子どもオトナ関係なく平等。いくら練習を積んでも目の前の結果はゆるぎない。結果が出せなかったと悔やむのならば、結果を正直に認めるのがオトナだと思う。
わたしは背負った赤いランドセルをおろし、莉々ちゃんの前に差し出した。
莉々ちゃんは素直にわたしのランドセルを抱え込むように前にかけると仔猫のような顔をした。
「か、軽いっ?聖子ちゃんのランドセルっ」
「うん。中のもの、全部出してみた」
帰り間際、ランドセルの中身をすべて教室に置いてきた。ぎりぎりの軽量化を目標にこっそりわたしの机の中に置いてきた。当然、先生たちには隠匿しなければいけないけど。だから、ちょっと教室を出るまで時間がかかったのは莉々ちゃんには内緒だ。誰かのためにわが身を削る、ただその行為は至極当然なこと。遊ぶことを工夫しなければいけないという、わたしたちの責務。やってることはまるでオトナのよう。違うかも。
「聖子ちゃん……オトナだねっ」
うん。違うね。
振り上げた莉々ちゃんの小さなガッツポーズ。わたしはこれまでこんなにかわいいガッツポーズを見たことはない。ガッツというフレーズが名前負けするレベルだし。
帰り道のランドセルじゃんけんに、これほど心血を注ぐ女子小学生はどこにいようか。
グーを出す速度、チョキを出す腕の角度、パーを出す足のベクトル。全てを完璧の境地にまで高めんと、莉々ちゃん手は武者震いをしていたのはちょっと感動。
ランドセルじゃんけんは小学生の間にだけ許された遊びだ。勝者は敗者をこき使うようにランドセルを持たせる。運。運が全てを解決させる。
中学生ならばまだ微笑ましく、高校生ならばSNS映えを意識させられる。だが、大人になってからのランドセルじゃんけんなどは、痛々しい以外の表現が見つからない。ましてや、YouTuberの企画ならばなおさらだし。逆を言うならば、子どものうちに全力で楽しむのが吉じゃないか。しかし、子どもだということを担保に遊びじゃくるのも、ちょっとわたしには子どもすぎると思う。だって、もう小学六年だし。
そろそろオトナを意識したいお年頃、オトナって何に向かって進むのだろう。身近なオトナを思い浮かべても、オトナがオトナに見えてこない。
そういえば、うそうそ時の週末には、毎度毎度とオトナの女性がじゃんけんを仕掛けてくるし、時代をときめくアイドルたちもじゃんけんに我が身の運命を託す大会を催しているし。だから、わたしたち女子小学生だってじゃんけんに願いをのせても不思議じゃない。莉々ちゃんはあいかわらず鏡の中の自分とじゃんけんの特訓を繰り返し、わたしは目的の部屋へと向かった。
図書館の児童たちはまばらだった。さんさんと太陽輝くお昼休み、お年頃の子たちは外で遊ぶのがおあつらえってことなんだろか。
昨今の公園には遊具がない、というか、昭和の頃には当たり前だった遊具が危ないからという理由で撤去されたらしい。それをオトナたちは「最近の子どもたちは外で遊ばなくなった」と嘆いているらしい。遊具がないなら、ないなりに遊ぶことを工夫しなければいけないわたしたちの責務でもある。ここでオトナに向かって牙向くのは一種の思考の停止だと思う。与えられないならば、作ったら?わたしは図書館に行くけど。
小さな低学年の為に背の高い六年生が高い位置の本を取ってあげていた。同じクラスの越智ちゃんだった。
彼女はモデルのようにスタイルがいい。女子小学生なのに。
お兄ちゃんがいるらしく、その影響なのか大人びている。女子小学生なのに。
百四十センチあるかないかのわたしからすれば、その背の高さは犯罪的だ。女子小学生なのに。
取ってあげた本を小さな低学年の子に手渡すと、たんぽぽのように微笑む。女子小学生なのに。
オトナの振る舞いが自然に身に着けている越智ちゃん。女子小学生なのに。
小リスのステップで受付カウンターに向かう低学年の子が手にしている本は夢野久作の「ドグラ・マグラ」だった。女子小学生なのに。
誰かのためにわが身を削る、ただその行為は至極当然なこと。だが、越智ちゃんはさらりとそつなくこなす、まるでオトナのよう。女子小学生なのに。
多分、越智ちゃんはランドセルじゃんけんなどしないだろう。わたしの妄想だけど。
まだまだわたしはオトナになりきれてない。女子小学生だし。
一冊だけ本を借りて図書館をあとに、鏡の場所を再び訪れると莉々ちゃんはじゃんけんの練習を続けていた。何の本を借りたかって?人のことを詮索するのはオトナじゃないなぁ。
下校時間、莉々ちゃんを待たせてしまった。
理由と言えば、お話にするでもない些細なことだったので省きたい。約束の巌流島へ向かう宮本武蔵の気持ちが分かる……訳がない。前言撤回。それほど、わたしは焦っているし。
莉々ちゃんのことだからきっとやきもきしながらわたしが来るのを待っているはず。わたしの予想は裏切らなかった。
「遅いぞっ、聖子ちゃんっ」
威勢だけは佐々木小次郎の莉々ちゃんが、にこにこしながらわたしが来るのを待っていたのだ。ぴょんと跳ね上がり、手にしていた靴を床に解き放つように落とすと、乾いた音がそこら中に響いていた。がちゃっと莉々ちゃんの水色のランドセルが背中で音をさせていた。
「よーし。勝負だぞっ」
「ちょっと、待って……」
じゃんけんの準備運動をしながら、莉々ちゃんは健闘を誓った。じゃんけんの準備運動って、何?それほど、わたしは焦っていたし。
「じゃんけんぽん!!」
グーを突き出したわたしの対面の手は平和のシンボルを示していた。
石ころを突き出したわたしの真正面はハサミを差し出していた。
北欧少女の目つぶしはわたしの鉄拳にて潰された。
「……ふふふ。わたし、破れたりっ」
ストップモーションで莉々ちゃんはパーの姿で固まっていた。
「うん。約束だよね」
「あれだけ練習をしたのにっ」
勝負の世界の厳しさは子どもオトナ関係なく平等。いくら練習を積んでも目の前の結果はゆるぎない。結果が出せなかったと悔やむのならば、結果を正直に認めるのがオトナだと思う。
わたしは背負った赤いランドセルをおろし、莉々ちゃんの前に差し出した。
莉々ちゃんは素直にわたしのランドセルを抱え込むように前にかけると仔猫のような顔をした。
「か、軽いっ?聖子ちゃんのランドセルっ」
「うん。中のもの、全部出してみた」
帰り間際、ランドセルの中身をすべて教室に置いてきた。ぎりぎりの軽量化を目標にこっそりわたしの机の中に置いてきた。当然、先生たちには隠匿しなければいけないけど。だから、ちょっと教室を出るまで時間がかかったのは莉々ちゃんには内緒だ。誰かのためにわが身を削る、ただその行為は至極当然なこと。遊ぶことを工夫しなければいけないという、わたしたちの責務。やってることはまるでオトナのよう。違うかも。
「聖子ちゃん……オトナだねっ」
うん。違うね。

