食いタンのみのタモツ
第十話「短かった黄金時代」
Mよ、昨日のひややかな青空が
剃刀の刃にいつまでも残っているね。
だがぼくは、何時何処で
きみを見失ったのか忘れてしまったよ。
短かった黄金時代――
活字の置き換えや神様ごっこ
「それが、ぼくたちの古い処方箋だった」と呟いて……
(鮎川信夫『死んだ男』より)
時は二万年前に遡る。まだ僅かに生き残っていたネアンデルタール人の末裔が、木の実を集めて戯れに遊んでいる最中に、「ロン」と呟いた。自分の発した言葉の意味もわからないまま彼は何だか愉快な気持ちになり、じゃらじゃらと木の実をかき混ぜる。しかし残念ながらこの偶然が麻雀という遊戯に繋がることはなく、彼は子孫を残せないまま、クロマニョン人の一人に頭を割られて死んだ。
そんなこととは一切関係なく、時は現在から二十年遡り、舞台は千葉県にある公団住宅の一室に移る。表札には「畑中」とあり、普段は母子二人だけが住んでいるその部屋には、もう一組の家族が訪れていた。近々一つの家族となる予定の桜木一家である。外は冬の寒さが厳しさを増す時節だというのに、部屋の中は柔らかく暖かな空気に包まれている。
「開けていーい?」
畑中家の一人娘、純が返答を待たずにプレゼントの包装紙をびりびりと破る。今日は彼女の五歳の誕生日を祝うために皆が集まっているのだ。
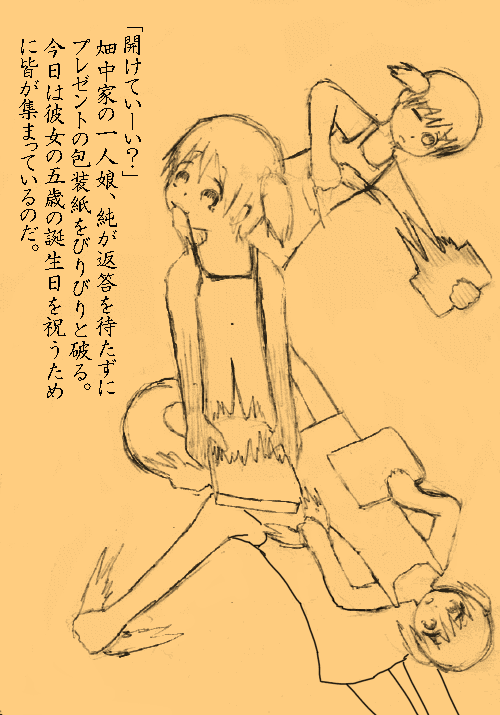
「まーじゃんぱいー」純は手をたたいて喜ぶ。
「あら、こんな高価なものを」純の母親、畑中張子(はたなか・ちゃんこ)が、近い将来の夫、桜木道夫の顔を窺う。
「いいんだ、みんなで遊べるものだし。小さい頃から麻雀に親しんでいるといろいろ役に立つしね」
「例の大会の規模、年々大きくなってるわね、そういえば」
親たちの会話そっちのけで、純と真一郎は麻雀牌の入っている箱を争うように開け、牌や点棒を、バースデーケーキの生クリームのついた手で、遠慮なく思い思いにべたべたと触る。
子供用に優しく書かれた麻雀ルールの解説書を、頬すり合わせて覗き込んでいた子供たちは、次々に驚きの声をあげる。
「純チャンって役がある! これあたし専用!」
「ダブルリーチって必殺技っぽくってかっけー」
「やりたいよー、やろーよー」
「四人でやるんだって」
「おじさんも一緒にあそぼー」
「え、でも今からだと帰りが遅くなってしまうけど……」
「今日はもう泊まっていらっしゃったら」
「そうだよ泊まってってー」
「泊まろ泊まろー」
「そうだな」道夫は満ち足りた気分で答える。
「もう、家族だもんな」正確にはまだ婚姻届を出してはいないが、道夫と張子は、お互い連れ合いを早くに亡くしてしまった同士、傷を舐め合う目的以上に惹かれ合っていた。子供たちも仲良く打ち解け、理想的な再婚生活を送ることが出来る、そう信じていた。こたつに移動し、子供たちを座らせ、麻雀卓を囲む準備をする。
「ねえねえおじさんてお母さんと結婚するんでしょー」
無邪気に訊ねる純の言葉に道夫と張子は「えと」「あの」と言葉を詰まらせる。
「あたしがおっきくなったら、あたしも一緒にお嫁さんにしてね、おじさん」
「何言ってんだよそんなの無理だよ!」真一郎が横で激昂する。
「純ちゃんは僕のお嫁さんになるんだから!」
大胆発言を連発する子供たちを、二人の親は苦笑しながら羨ましそうに眺める。将来顔を赤らめて思い出すことになるような言葉を、恥ずかしがることもなく言える時代に彼らはいる。その笑顔がいつまでも続くように、出来れば大きく育っても純真さを消さないでいて欲しいと願っている。
子供たちを大人しく座らせ、親決めをすると、道夫が親になった。
「私が親だな」
「知ってるよ! 僕ら子供!」
「いやそういうことじゃなくて、ゲームをする上での決まりでな……」
「おじさんが親? じゃあねじゃあねじゃあね、お父さん、って呼んでいーい?」
道夫と張子は一瞬顔を見合わせた後、純に負けないような笑顔を浮かべる。
「ああ、いいよ、純ちゃん。今から私は君のお父さんだ」
「へへー、やったー」
一人きょとんとしている真一郎は「早く始めよーよー」と卓を叩く。子供たちに丁寧に教えながら道夫は牌を配り、理牌(リーパイ 牌を種類順、数順に並び替えること)してやる。
「まあとりあえず最初はよくわかんないだろうから、役は気にせず、三つ同じ牌か、数が続きになっているのを集めていこう」
「ダブルリーチ!」
わけのわからないままに真一郎はそう叫んで牌を倒す。
「純チャン!」
負けじと純も続く。
「いやいや、まず親からだからね。さて、と……」
ようやく自分の配牌を見たところで道夫は一瞬固まってしまう。何度も見直す。捨てる牌は一つも見あたらない。つまり、天和(テンホウ 親の配牌で既にアガっている状態の役。役満で48000点)であった。
「こんなことってあるんだな……」道夫はこの天運を、自分たちの前に輝かしい未来が開けた証左と受け止めた。
「すごいよ、お父さんもうアガっちゃってる。いきなりこれじゃ勝負にならないな、もう一回やり直そう」
わけがわからないままぶーぶーと言う子供らを宥めながら、もう一度牌を混ぜ、配り直す。純と真一郎は再び「ダブルリーチ!」「純チャン!」を繰り返す。それを見ながら、(これが幸せというものか)と感じ入っていた道夫の呼吸が、自分の配牌を見た瞬間に一瞬止まる。
「また、天和……」
「道夫さん?」この日初めて張子が不安げな表情を浮かべた。
「あら、こんな高価なものを」純の母親、畑中張子(はたなか・ちゃんこ)が、近い将来の夫、桜木道夫の顔を窺う。
「いいんだ、みんなで遊べるものだし。小さい頃から麻雀に親しんでいるといろいろ役に立つしね」
「例の大会の規模、年々大きくなってるわね、そういえば」
親たちの会話そっちのけで、純と真一郎は麻雀牌の入っている箱を争うように開け、牌や点棒を、バースデーケーキの生クリームのついた手で、遠慮なく思い思いにべたべたと触る。
子供用に優しく書かれた麻雀ルールの解説書を、頬すり合わせて覗き込んでいた子供たちは、次々に驚きの声をあげる。
「純チャンって役がある! これあたし専用!」
「ダブルリーチって必殺技っぽくってかっけー」
「やりたいよー、やろーよー」
「四人でやるんだって」
「おじさんも一緒にあそぼー」
「え、でも今からだと帰りが遅くなってしまうけど……」
「今日はもう泊まっていらっしゃったら」
「そうだよ泊まってってー」
「泊まろ泊まろー」
「そうだな」道夫は満ち足りた気分で答える。
「もう、家族だもんな」正確にはまだ婚姻届を出してはいないが、道夫と張子は、お互い連れ合いを早くに亡くしてしまった同士、傷を舐め合う目的以上に惹かれ合っていた。子供たちも仲良く打ち解け、理想的な再婚生活を送ることが出来る、そう信じていた。こたつに移動し、子供たちを座らせ、麻雀卓を囲む準備をする。
「ねえねえおじさんてお母さんと結婚するんでしょー」
無邪気に訊ねる純の言葉に道夫と張子は「えと」「あの」と言葉を詰まらせる。
「あたしがおっきくなったら、あたしも一緒にお嫁さんにしてね、おじさん」
「何言ってんだよそんなの無理だよ!」真一郎が横で激昂する。
「純ちゃんは僕のお嫁さんになるんだから!」
大胆発言を連発する子供たちを、二人の親は苦笑しながら羨ましそうに眺める。将来顔を赤らめて思い出すことになるような言葉を、恥ずかしがることもなく言える時代に彼らはいる。その笑顔がいつまでも続くように、出来れば大きく育っても純真さを消さないでいて欲しいと願っている。
子供たちを大人しく座らせ、親決めをすると、道夫が親になった。
「私が親だな」
「知ってるよ! 僕ら子供!」
「いやそういうことじゃなくて、ゲームをする上での決まりでな……」
「おじさんが親? じゃあねじゃあねじゃあね、お父さん、って呼んでいーい?」
道夫と張子は一瞬顔を見合わせた後、純に負けないような笑顔を浮かべる。
「ああ、いいよ、純ちゃん。今から私は君のお父さんだ」
「へへー、やったー」
一人きょとんとしている真一郎は「早く始めよーよー」と卓を叩く。子供たちに丁寧に教えながら道夫は牌を配り、理牌(リーパイ 牌を種類順、数順に並び替えること)してやる。
「まあとりあえず最初はよくわかんないだろうから、役は気にせず、三つ同じ牌か、数が続きになっているのを集めていこう」
「ダブルリーチ!」
わけのわからないままに真一郎はそう叫んで牌を倒す。
「純チャン!」
負けじと純も続く。
「いやいや、まず親からだからね。さて、と……」
ようやく自分の配牌を見たところで道夫は一瞬固まってしまう。何度も見直す。捨てる牌は一つも見あたらない。つまり、天和(テンホウ 親の配牌で既にアガっている状態の役。役満で48000点)であった。
「こんなことってあるんだな……」道夫はこの天運を、自分たちの前に輝かしい未来が開けた証左と受け止めた。
「すごいよ、お父さんもうアガっちゃってる。いきなりこれじゃ勝負にならないな、もう一回やり直そう」
わけがわからないままぶーぶーと言う子供らを宥めながら、もう一度牌を混ぜ、配り直す。純と真一郎は再び「ダブルリーチ!」「純チャン!」を繰り返す。それを見ながら、(これが幸せというものか)と感じ入っていた道夫の呼吸が、自分の配牌を見た瞬間に一瞬止まる。
「また、天和……」
「道夫さん?」この日初めて張子が不安げな表情を浮かべた。

