いん!
Sadistic!
求める物は、すべて手に入れてきた。これまでも、これからも。
わたくしは生まれた時から完璧だった。わたくし以外の存在は屑だった。
魔法学園アカデミーに入学後も、常に頂点の座に収まってきた。人望、成績、容姿、全てにおいて完璧であるわたくしに、愚民共は平伏せねばいけませんわ。
いいですこと? 貴方達の生き方は、己の身の程を知ることが全て。生命とは対等でないことを学び、それを魂の細部にまで刻みつけなさい。
どこまでも卑しく忠実に、主であるわたくしへ、頭を垂れなさい、尻尾を振りなさい。わたくしの一言で、自らの喉元を切り裂く程度のことは、息を吸うようにやりなさい。
従いなさい、愚民共。
わたくし『レアナ・クレッシェント・ニルヴァーナ』の前に、平伏しなさい。
愚民が嫌なら、奴隷になればよろしいわ。今なら首輪をプレゼントして差し上げますからね。なにも考えず、首を絞めて、楽におなりなさい。さぁさぁ、わたくしの前に跪いて受け取るのですよ。可愛いければ喉元ぐらいは撫でてあげるし、甘いお菓子も少しだけ分けあげるから。
わたくし、小煩い蠅が大嫌いですの。目の前を横切られるのは、どうしても許せない性質ですの。叩き潰して、地に堕として、もがいている様子を見下ろすのは大好きですけれど。
だから、とっても目触りなのよ、貴女。フィノ・トラバント。
何故、わたくしの前を横切ろうとするのかしら。わたくしなんて、眼中に入っていないとでも言いたいのね? そういうのって、とっても迷惑。だけど嫌いではなくってよ。むしろ好ましいわ。
「フィノ・トラバント、わたくし、貴方が好きよ」
好き、好き、大好きだわ。フィノ・トラバント。
愛おしくて、もう狂ってしまいそう。貴女を壊してさしあげる夢を、なんども見た。
その両目に、わたくしだけが映っていた。
貴女の悲鳴を聞きながら、両目を抉ってさしあげた。
舌を絡めて、わたくしだけを感じていた。
虚ろな貴女を見つめつつ、舌を噛みちぎってあげた。おいしかったわ。
声にならない貴女の悲鳴はとっても甘美。
汗と血の匂いが、それと混ざってさらに色濃くしてくれる。
貴女はなにも見えず、なにも言えず、そしてなにも聞こえなくなった。
そんな貴女を、隅々まで舐めつくした。最後に、強く貫いた。
小さな心臓の鼓動が、ゆっくり消えていく。
それを感じて、わたくしも、ついに果ててしまったわ。
夢の中、わたくしだけが、貴女を支配していた。
素晴らしかった。とても素晴らしかった。
いつも、いつも、いつも、いつも、いつも……気がつけば、貴女のことを、考えていますわ。
今日の夢に、また貴方が出てきたわ。次はどうやって、調理してさしあげようって考えた。
このわたくしが。たった一人の愚民のことを、ずっと考え続けているのですよ。どうして頂けるのかしら? 貴女の姿が、わたくしの心に、影となって焼きついてしまって、離れないの。
ねぇ……フィノ・トラバント。
子生意気な貴女の視線が、すべてわたくしのために集えば、どれほどに気持ちがいいのかしらね。完膚なきまでに従属させたいわ。わたくし以外、なにも映さない、なにも感じない、専用の特別な子犬に調教してさしあげたい。そう思っていましてよ。
「(……まずは、そうねぇ。手始めに、昼夜問わず一日中ベッドの上に鎖で縛りつけてあげましょうか。身体の自由が利かないのはもちろん、瞼を目隠しで覆って、口にはアレを強く押し込めて、耳元でずっと甘い言葉を囁き続けてあげましょう。ゆっくりと自我の壊れるお薬をあんなところやこんなところに突き刺しながら……空いた手で『ためつすがめつ』するように……全身を撫でまわして砂糖菓子のように甘い誘惑と理性の鎖を断ち切ってしまいたくなるような困惑に意識が平常と限界を朦朧と彷徨い続け始めたところで少しずつ頂いていきましょうか素材に舌鼓を打つようにしてねどこの液体なのだか分からないぐらいぐちゃぐちゃに蕩けきっている貴女を見つめながらゆっくりゆっくり貴女の身体と心を私の望む色に染めあげていくのよあぁ素敵だわあぁ駄目もう食べたい貴女を今すぐ食べたい食べさせてお願い食べさせて味わい尽くさせて全部全部全部っ!)……今すぐにっ!」
「えっ! お姉さま?」
あら、いけない。
「――――こほん」
今、ここがどこで、どのような状況なのかを思い出して、咳ばらいで誤魔化すわたくし。
「ごめんなさいね。先を続けて頂ける?」
空想の世界へ飛び立っていた楽しい一時は、終わりを告げた。あぁ面倒くさいわ。このつまらない現実の時間へ引き戻されて、なにが楽しいのかしら。とにかく、目の前で揺らめく紅茶に口付けて、気を落ち着かせましょう。
「あの……お姉さま……」
「なにかしら?」
「来月に行われる、学園パーティーの提案書、私の企画……ダメですか……?」
「いいえ、そんなことはないわよ」
今すぐ、そこの開けた窓から投げ捨てたいわ。出来の悪い、お前の脳みそと一緒に。
言葉は、紅茶と共に喉の奥へ溶けていく。その代わり、冷めた紅茶の湯気のように、笑って見せた。
「貴女の考え、とても独創的で魅力的だわ」
「……ほ、本当ですか?」
「えぇ、続けて説明して頂戴」
「は、はいっ!」
ようやく愛らしく見えてきた駄犬に、一つ微笑みを投げかける。あらあら、顔を真っ赤にして。
誰にも見られないように溜息を一つこぼして、思考を切り替えた。
フィノ・トラバント。貴女はわたくしの私物。でも最近、貴女に付きまとっている女がいるわね。しかもその女、貴女の使い魔なんですってね。そういうのって、とっても迷惑。
早いうちに叩き潰してあげなくてはね。
ちょうど良かったのかもしれませんわ。わたくしも、夢の貴女を愛でるだけでは、そろそろ我慢出来なくなってきたところ。
フィノ・トラバント、お待ちになっていて。今日にでも、貴女を一番のお気に入りにしてさしあげましょう。
わたくしは生まれた時から完璧だった。わたくし以外の存在は屑だった。
魔法学園アカデミーに入学後も、常に頂点の座に収まってきた。人望、成績、容姿、全てにおいて完璧であるわたくしに、愚民共は平伏せねばいけませんわ。
いいですこと? 貴方達の生き方は、己の身の程を知ることが全て。生命とは対等でないことを学び、それを魂の細部にまで刻みつけなさい。
どこまでも卑しく忠実に、主であるわたくしへ、頭を垂れなさい、尻尾を振りなさい。わたくしの一言で、自らの喉元を切り裂く程度のことは、息を吸うようにやりなさい。
従いなさい、愚民共。
わたくし『レアナ・クレッシェント・ニルヴァーナ』の前に、平伏しなさい。
愚民が嫌なら、奴隷になればよろしいわ。今なら首輪をプレゼントして差し上げますからね。なにも考えず、首を絞めて、楽におなりなさい。さぁさぁ、わたくしの前に跪いて受け取るのですよ。可愛いければ喉元ぐらいは撫でてあげるし、甘いお菓子も少しだけ分けあげるから。
わたくし、小煩い蠅が大嫌いですの。目の前を横切られるのは、どうしても許せない性質ですの。叩き潰して、地に堕として、もがいている様子を見下ろすのは大好きですけれど。
だから、とっても目触りなのよ、貴女。フィノ・トラバント。
何故、わたくしの前を横切ろうとするのかしら。わたくしなんて、眼中に入っていないとでも言いたいのね? そういうのって、とっても迷惑。だけど嫌いではなくってよ。むしろ好ましいわ。
「フィノ・トラバント、わたくし、貴方が好きよ」
好き、好き、大好きだわ。フィノ・トラバント。
愛おしくて、もう狂ってしまいそう。貴女を壊してさしあげる夢を、なんども見た。
その両目に、わたくしだけが映っていた。
貴女の悲鳴を聞きながら、両目を抉ってさしあげた。
舌を絡めて、わたくしだけを感じていた。
虚ろな貴女を見つめつつ、舌を噛みちぎってあげた。おいしかったわ。
声にならない貴女の悲鳴はとっても甘美。
汗と血の匂いが、それと混ざってさらに色濃くしてくれる。
貴女はなにも見えず、なにも言えず、そしてなにも聞こえなくなった。
そんな貴女を、隅々まで舐めつくした。最後に、強く貫いた。
小さな心臓の鼓動が、ゆっくり消えていく。
それを感じて、わたくしも、ついに果ててしまったわ。
夢の中、わたくしだけが、貴女を支配していた。
素晴らしかった。とても素晴らしかった。
いつも、いつも、いつも、いつも、いつも……気がつけば、貴女のことを、考えていますわ。
今日の夢に、また貴方が出てきたわ。次はどうやって、調理してさしあげようって考えた。
このわたくしが。たった一人の愚民のことを、ずっと考え続けているのですよ。どうして頂けるのかしら? 貴女の姿が、わたくしの心に、影となって焼きついてしまって、離れないの。
ねぇ……フィノ・トラバント。
子生意気な貴女の視線が、すべてわたくしのために集えば、どれほどに気持ちがいいのかしらね。完膚なきまでに従属させたいわ。わたくし以外、なにも映さない、なにも感じない、専用の特別な子犬に調教してさしあげたい。そう思っていましてよ。
「(……まずは、そうねぇ。手始めに、昼夜問わず一日中ベッドの上に鎖で縛りつけてあげましょうか。身体の自由が利かないのはもちろん、瞼を目隠しで覆って、口にはアレを強く押し込めて、耳元でずっと甘い言葉を囁き続けてあげましょう。ゆっくりと自我の壊れるお薬をあんなところやこんなところに突き刺しながら……空いた手で『ためつすがめつ』するように……全身を撫でまわして砂糖菓子のように甘い誘惑と理性の鎖を断ち切ってしまいたくなるような困惑に意識が平常と限界を朦朧と彷徨い続け始めたところで少しずつ頂いていきましょうか素材に舌鼓を打つようにしてねどこの液体なのだか分からないぐらいぐちゃぐちゃに蕩けきっている貴女を見つめながらゆっくりゆっくり貴女の身体と心を私の望む色に染めあげていくのよあぁ素敵だわあぁ駄目もう食べたい貴女を今すぐ食べたい食べさせてお願い食べさせて味わい尽くさせて全部全部全部っ!)……今すぐにっ!」
「えっ! お姉さま?」
あら、いけない。
「――――こほん」
今、ここがどこで、どのような状況なのかを思い出して、咳ばらいで誤魔化すわたくし。
「ごめんなさいね。先を続けて頂ける?」
空想の世界へ飛び立っていた楽しい一時は、終わりを告げた。あぁ面倒くさいわ。このつまらない現実の時間へ引き戻されて、なにが楽しいのかしら。とにかく、目の前で揺らめく紅茶に口付けて、気を落ち着かせましょう。
「あの……お姉さま……」
「なにかしら?」
「来月に行われる、学園パーティーの提案書、私の企画……ダメですか……?」
「いいえ、そんなことはないわよ」
今すぐ、そこの開けた窓から投げ捨てたいわ。出来の悪い、お前の脳みそと一緒に。
言葉は、紅茶と共に喉の奥へ溶けていく。その代わり、冷めた紅茶の湯気のように、笑って見せた。
「貴女の考え、とても独創的で魅力的だわ」
「……ほ、本当ですか?」
「えぇ、続けて説明して頂戴」
「は、はいっ!」
ようやく愛らしく見えてきた駄犬に、一つ微笑みを投げかける。あらあら、顔を真っ赤にして。
誰にも見られないように溜息を一つこぼして、思考を切り替えた。
フィノ・トラバント。貴女はわたくしの私物。でも最近、貴女に付きまとっている女がいるわね。しかもその女、貴女の使い魔なんですってね。そういうのって、とっても迷惑。
早いうちに叩き潰してあげなくてはね。
ちょうど良かったのかもしれませんわ。わたくしも、夢の貴女を愛でるだけでは、そろそろ我慢出来なくなってきたところ。
フィノ・トラバント、お待ちになっていて。今日にでも、貴女を一番のお気に入りにしてさしあげましょう。
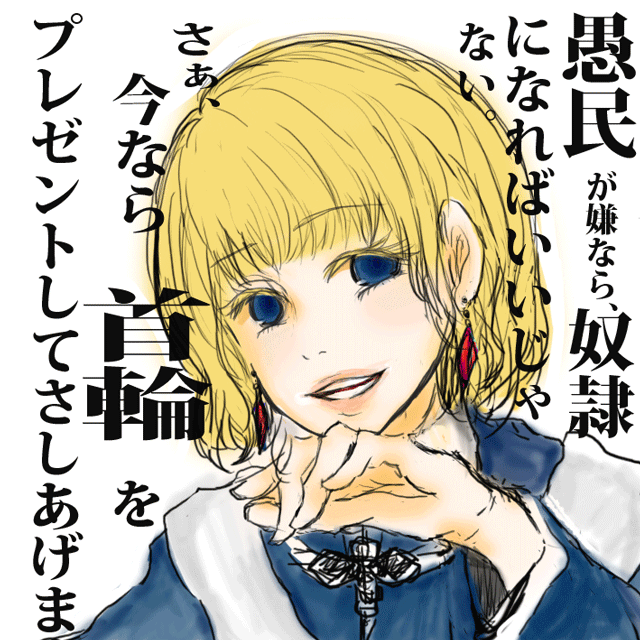
最も古い旧校舎の図書室。別世界のように静かだった。
人気のない場所は嫌いじゃない。世界が夕焼けから、夜に変わっていくのも好き。けど、不意に背筋がふるえた。
「くしゅん! ……やだ、風邪でもひいたのかしら」
椅子から立ち上がって窓を閉め、席に戻り、もう一度辞書のように分厚い研究書物に目を通す。
「……ここ、記述が間違ってる。こっちも前項と内容が矛盾してる」
これはいくらなんでも、ダメだ。本を閉じ、内容を記録していたメモ用紙を、ゴミ箱の中に投げ捨てる。他の書物を紐解くと、それもまた難解で、把握するには時間がかかりそうだった。
この図書室に置いてある書物は、著名でない研究家が記した専門書がほとんどだ。読みづらく、実用性があるのか、そもそも正しい事が記されているのか、疑わしいところを挙げればきりがない。
部屋に掛けられた時計が、カチ、カチ、と音を立てて刻んでいく。夜の気配が強くなってきた。
「そろそろ帰らないと……」
新校舎には、立派で快適で、正当性が重視された資料が揃っていた。古い図書室を好んで利用する生徒は、私以外にはいなかった。
「……えぇと、まとめておく必要があるのは、これと、これと……」
一人でいるのは嫌いじゃない。でもあえて、この図書室を選んでいるのには理由がある。
理解の困難な資料には、さりげなく、古代の禁術が、暗号を用いて隠されていたりするのだ。偶然それに気がついてから、人目につかない書物を読むことが多くなった。
「結果としては、人生最大の汚点になったわけだけど……」
あの時、アイリスを呼び出した禁術も、ここで見つけた書物が発端だ。
かわいくて、素直な使い魔が欲しかった。欲を言えば、今度の試験の成績をあげるために『術者と魔力を共有出来る』使い魔が欲しかった。だけど、私の言葉を聞き届けてくれたのは、どちらでもない変態だった。
「禁術って、恐ろしいわ……」
安易に力を使ってしまったことを、海よりも深く反省した。
もう二度と、悲劇は起こすものではない。これ以上、変態が増えてはいけない。
一匹でも手に負えないのに、それが二匹も側にいたらと考えると……。
「ご機嫌よう、こんなところにいましたのね。フィノ・トラバント」
聞いたことのある声が後ろから聞こえた。入り口に、人好きのする笑みを浮かべた魔女がいた。同じクラスメイトだった。
「レアナじゃない、どうしたの?」
「ふふ、少し貴女に用事がありまして、探していましたのよ」
彼女は優等生だった。筆記試験の点数は私と同じく、常に満点。そのうえ実技試験も一位ときてる。さらには、このアカデミーを統括する生徒会長に選ばれていた。
長いアカデミーの歴史でも、彼女ほどの実力と実績をそなえた魔女は稀らしい。すでにあちこちから声がかかっているのを、噂で聞いた。
父様の魔導騎士団はどうなのか知らないけど……面白い話じゃない。
「なにか用事? たいしたことじゃないなら、はやく出て行ってよね。忙しいんだから」
「あらあら、手厳しいわね?」
レアナが後ろ手に、教室の扉を閉めた。
「放課後に一人、こんなところでお勉強会とは、熱心なことね」
「私は、必要だと思うことをやっているだけ。貴女と違って、秀でた能力がないからね」
「その一途なところ、好きよ。生徒会の役員に入ってみない?」
「お断りよ。役員の仕事には興味ないわ」
「ふふ、そういう素直な答え方は敵を作るわよ。嫌いじゃないけれど」
優秀な彼女は、秀でた外見の容姿ともあわさって、学園で最も名の知れた魔女だろう。だけどそれを鼻にかけることもなく、誰とでも平等に接していた。
おせっかい焼きで、クラスメイトと言い争っているのを、仲裁してくれたこともある。それは、まぁ、感謝してる。
「貴女はいつも一人よね」
「そういうレアナこそ、いつもの取り巻きがいないじゃない」
嫌味ではなかった。私たちは、正反対の立ち位置にいると思っていた。
「わたくしだって、一人でいたい時もありますわ」
「それなら帰って」
「あら、お邪魔かしら? わざわざ貴女を求めて、探していたというのに」
「さっきも言ったけど、なにか用があるなら、はやく済ませて」
「……うふふ、かわいい子」
妙な言い方に、眉をひそめて振り返る。
レアナの整った表情、怒るどころか、嬉しそうに。
「フィノ・トラバント」
「……なによ」
近づいて来る。靴が床を踏みしめると、コツ、と高い音がした。
嫌な予感がして、席を立つ。正面から彼女を見据える。
コツ、コツ、コツ。ボリュームのある金髪が、床を踏みしめる度に、わずかに揺れた。
深海のような蒼の瞳。波打つように微笑んで、見つめてくる。
「最近、妙な噂を聞きましたの」
「……噂?」
「貴女の使い魔、お元気かしら?」
「…………!?」
心臓が、ぎゅっと縮まった。アイリスのことは、誰にも話してないのに。……だって、あんな変態と一緒に暮らしているなんて、知れるの絶対嫌。でもそれより、一人で禁術を利用したことが致命的だった。誰かに知れたら、退学処分だ。
口の中が渇く。冷や汗が流れて、心臓が飛び跳ねる。落ち着いて、大丈夫。
「あら? 聞こえませんでしたの? 貴女の使い魔、お元気ですかと、お尋ねしたのですよ」
「わざわざ嫌味を言いに来たの? この前の試験で使い魔を呼び出せなかったこと、知ってるでしょ」
「存じてあげていますわよ。入学以来、実技試験が、ことごとく無得点の魔女のこと」
「うるさいっ!」
「――けれど、少し小耳に挟みましたの。最近、貴女の側に、見なれない女性がいるとね」
「それは、私のメイドよ。最近雇ったの」
「うふふ。そう、メイドでしたの。それは知りませんでしたわ」
裏に言葉を隠した微笑みで、レアナは笑った。
「ほんと、知りませんでしたわ。最近のメイドって、黒い翼と尻尾が、生えていらっしゃるのね」
「……!!」
マズい、バレてる。
学園の生徒達の中で、最も高い権限を持つ彼女の笑みは、言い得ぬ圧迫感に満ちていた。
「貴女のメイド。今、どちらにいらっしゃるの?」
「い、家で仕事をしてるに決まってるでしょ。メイドなんだから……!」
「そうよね。家でお仕事をしていらっしゃるはずですわね。ところで、メイドのお名前は?」
「……アイリス」
「よい名前だわ。それにしても名前って、大切ですわよね。名前があるからこそ、この世界の全ての存在は認識される。まずは名を与えること。それが契約の証であり、使い魔と共存する、唯一の手段である。……と、古めかしい教科書の一節にもありますものね?」
「……ぅ」
レアナがにっこり微笑んだ。
草食動物が、肉食動物に追い詰められた時、こんな気持ちになるのだろうか。彼女は明らかに真実を知っている。
退学処分を言い渡されることは、父様への道が断たれるのも同じ。そんなの、絶対嫌っ!
「……暗くなってきたから、今日は帰るわね」
お願いだから黙ってて、なんて言ったところで、通じる相手じゃない。それなら、残る手段は一つだけ。大急ぎで家に帰って、メイドを土の中に埋めてやるっ!
思えば、短い付き合いだった。いつか、こんな日が来るんじゃないかって思ってた。
さよなら、アイリス。今までご苦労様。
「……逃げるのね?」
「うるさいっ! そこどいてっ!」
「あらあら、怒ったところが、やっぱり一番かわいいわね。……おいしそう」
「……え?」
「ゆっくり、わたくしの物にしようと思っていたのだけど。もう、我慢なんて出来ない……」
「…………え?」
白くて、細い両腕が伸びてくる。手首が捕まる。
「な、なにするの……!?」
「うふふふふふ。せいぜい抵抗なさって。今日は、お家には帰さないから」
レアナの両手、薬指に嵌められた小さな指輪から、淡い緑色の光が溢れだす。
その光が馴染みのある魔力だと分かり、背筋が冷えた。掴まれた両腕を振りほどこうとしたが、遅かった。万力のように固められた指は、びくともしない。
「もう、逃がさない」
「離してっ!」
レアナが用いたのは、身体能力を高める基礎的な魔術だ。でも展開が速すぎる。詠唱すら必要とせず、指輪程度の品で魔力を媒介するなんて。そんな芸当が出来るのは、学園の教師でもあやしい。
「この……っ!」
感情を必死に高め、内なる魔力を呼び醒ます。
抵抗しろ! 彼女の力を弾き飛ばせ!
歯を食いしばって、必死に足掻いた。
「……哀れね」
出来の悪い人形を蔑むように、笑っていた。心に鋭く、突き刺さった。
「抵抗が無意味なことは、よくご存じでしょう? ……落ちこぼれさん?」
「だ、黙――――!?」
平手打ち。頬が熱い。痛い。
「うるさい下僕は嫌いよ。メイドのこと、学園長にお話されたくなければ、口を閉じなさい」
「……くっ!」
「ふふ、その顔はいいわよ。もっともっと、反抗的な表情で、静かに、黙って、わたくしを睨んでいなさい……」
「!?」
容赦はなかった。力いっぱいに、床上に押し倒される。背中を強く打ちつけて、息が止まる。
身悶える暇なんてない。ほっそりした指が、たわむれるように、私の首に絡みつく。
息を吸いたいのに、馬乗りされて、お腹が動かない! 苦しい、苦しい、苦しいっ!!
「どう……? 気持ちいいでしょう……?」
ゆらゆら揺れる、深海の瞳。
「調理の時間よ、フィノ・トラバント。貴女が望むのは、どんな味……?」
頬を染めあげた。極上の素材が手に入った、調理人のように。
「うふふふふ、まぁ、ゆっくりいきましょう」
「――――けほっ! けほっ!」
指が離れた。埃っぽい室内の空気をいっぱいに吸い込んで、むせ返ってしまう。
必死に空気を求めていると、不意に、冷たい、鉄の匂いがした。
「……な、なによそれ!」
「手錠ですわ。魔術で縛ってもいいのですけど、やっぱり実物の方が、楽しいでしょう?」
「楽しいわけあるかっ!」
「心配しないで。これから "楽しく感じるように" なりますから」
「……い、いやーーーっ!?」
暴れても無意味だった。強化魔術の力は凄まじく、私の両手を片手で抑えつける。残る片手は重い机の足をつかんで、平然と引き寄せた。
硬質な鉄の音。両手首が、机の脚と繋がった。
「……ほら、やっぱり思った通り。貴女って、こういうのがぴったりね」
「全然嬉しくないんだけどっ!?」
「……ゆっくり、躾をしてあげましょうね……うふふ……うふふふふふ!」
「ヘンタイーッ!」
「あら、失礼ですわね。これから貴女は、自分から望んでお願いする立場になるのよ?」
「――――!!」
うっとりと、蕩けるような微笑みに、背筋が凍る。
本気だ。本気で私を『そういう風』にしようとしてる。
人気のない場所は嫌いじゃない。世界が夕焼けから、夜に変わっていくのも好き。けど、不意に背筋がふるえた。
「くしゅん! ……やだ、風邪でもひいたのかしら」
椅子から立ち上がって窓を閉め、席に戻り、もう一度辞書のように分厚い研究書物に目を通す。
「……ここ、記述が間違ってる。こっちも前項と内容が矛盾してる」
これはいくらなんでも、ダメだ。本を閉じ、内容を記録していたメモ用紙を、ゴミ箱の中に投げ捨てる。他の書物を紐解くと、それもまた難解で、把握するには時間がかかりそうだった。
この図書室に置いてある書物は、著名でない研究家が記した専門書がほとんどだ。読みづらく、実用性があるのか、そもそも正しい事が記されているのか、疑わしいところを挙げればきりがない。
部屋に掛けられた時計が、カチ、カチ、と音を立てて刻んでいく。夜の気配が強くなってきた。
「そろそろ帰らないと……」
新校舎には、立派で快適で、正当性が重視された資料が揃っていた。古い図書室を好んで利用する生徒は、私以外にはいなかった。
「……えぇと、まとめておく必要があるのは、これと、これと……」
一人でいるのは嫌いじゃない。でもあえて、この図書室を選んでいるのには理由がある。
理解の困難な資料には、さりげなく、古代の禁術が、暗号を用いて隠されていたりするのだ。偶然それに気がついてから、人目につかない書物を読むことが多くなった。
「結果としては、人生最大の汚点になったわけだけど……」
あの時、アイリスを呼び出した禁術も、ここで見つけた書物が発端だ。
かわいくて、素直な使い魔が欲しかった。欲を言えば、今度の試験の成績をあげるために『術者と魔力を共有出来る』使い魔が欲しかった。だけど、私の言葉を聞き届けてくれたのは、どちらでもない変態だった。
「禁術って、恐ろしいわ……」
安易に力を使ってしまったことを、海よりも深く反省した。
もう二度と、悲劇は起こすものではない。これ以上、変態が増えてはいけない。
一匹でも手に負えないのに、それが二匹も側にいたらと考えると……。
「ご機嫌よう、こんなところにいましたのね。フィノ・トラバント」
聞いたことのある声が後ろから聞こえた。入り口に、人好きのする笑みを浮かべた魔女がいた。同じクラスメイトだった。
「レアナじゃない、どうしたの?」
「ふふ、少し貴女に用事がありまして、探していましたのよ」
彼女は優等生だった。筆記試験の点数は私と同じく、常に満点。そのうえ実技試験も一位ときてる。さらには、このアカデミーを統括する生徒会長に選ばれていた。
長いアカデミーの歴史でも、彼女ほどの実力と実績をそなえた魔女は稀らしい。すでにあちこちから声がかかっているのを、噂で聞いた。
父様の魔導騎士団はどうなのか知らないけど……面白い話じゃない。
「なにか用事? たいしたことじゃないなら、はやく出て行ってよね。忙しいんだから」
「あらあら、手厳しいわね?」
レアナが後ろ手に、教室の扉を閉めた。
「放課後に一人、こんなところでお勉強会とは、熱心なことね」
「私は、必要だと思うことをやっているだけ。貴女と違って、秀でた能力がないからね」
「その一途なところ、好きよ。生徒会の役員に入ってみない?」
「お断りよ。役員の仕事には興味ないわ」
「ふふ、そういう素直な答え方は敵を作るわよ。嫌いじゃないけれど」
優秀な彼女は、秀でた外見の容姿ともあわさって、学園で最も名の知れた魔女だろう。だけどそれを鼻にかけることもなく、誰とでも平等に接していた。
おせっかい焼きで、クラスメイトと言い争っているのを、仲裁してくれたこともある。それは、まぁ、感謝してる。
「貴女はいつも一人よね」
「そういうレアナこそ、いつもの取り巻きがいないじゃない」
嫌味ではなかった。私たちは、正反対の立ち位置にいると思っていた。
「わたくしだって、一人でいたい時もありますわ」
「それなら帰って」
「あら、お邪魔かしら? わざわざ貴女を求めて、探していたというのに」
「さっきも言ったけど、なにか用があるなら、はやく済ませて」
「……うふふ、かわいい子」
妙な言い方に、眉をひそめて振り返る。
レアナの整った表情、怒るどころか、嬉しそうに。
「フィノ・トラバント」
「……なによ」
近づいて来る。靴が床を踏みしめると、コツ、と高い音がした。
嫌な予感がして、席を立つ。正面から彼女を見据える。
コツ、コツ、コツ。ボリュームのある金髪が、床を踏みしめる度に、わずかに揺れた。
深海のような蒼の瞳。波打つように微笑んで、見つめてくる。
「最近、妙な噂を聞きましたの」
「……噂?」
「貴女の使い魔、お元気かしら?」
「…………!?」
心臓が、ぎゅっと縮まった。アイリスのことは、誰にも話してないのに。……だって、あんな変態と一緒に暮らしているなんて、知れるの絶対嫌。でもそれより、一人で禁術を利用したことが致命的だった。誰かに知れたら、退学処分だ。
口の中が渇く。冷や汗が流れて、心臓が飛び跳ねる。落ち着いて、大丈夫。
「あら? 聞こえませんでしたの? 貴女の使い魔、お元気ですかと、お尋ねしたのですよ」
「わざわざ嫌味を言いに来たの? この前の試験で使い魔を呼び出せなかったこと、知ってるでしょ」
「存じてあげていますわよ。入学以来、実技試験が、ことごとく無得点の魔女のこと」
「うるさいっ!」
「――けれど、少し小耳に挟みましたの。最近、貴女の側に、見なれない女性がいるとね」
「それは、私のメイドよ。最近雇ったの」
「うふふ。そう、メイドでしたの。それは知りませんでしたわ」
裏に言葉を隠した微笑みで、レアナは笑った。
「ほんと、知りませんでしたわ。最近のメイドって、黒い翼と尻尾が、生えていらっしゃるのね」
「……!!」
マズい、バレてる。
学園の生徒達の中で、最も高い権限を持つ彼女の笑みは、言い得ぬ圧迫感に満ちていた。
「貴女のメイド。今、どちらにいらっしゃるの?」
「い、家で仕事をしてるに決まってるでしょ。メイドなんだから……!」
「そうよね。家でお仕事をしていらっしゃるはずですわね。ところで、メイドのお名前は?」
「……アイリス」
「よい名前だわ。それにしても名前って、大切ですわよね。名前があるからこそ、この世界の全ての存在は認識される。まずは名を与えること。それが契約の証であり、使い魔と共存する、唯一の手段である。……と、古めかしい教科書の一節にもありますものね?」
「……ぅ」
レアナがにっこり微笑んだ。
草食動物が、肉食動物に追い詰められた時、こんな気持ちになるのだろうか。彼女は明らかに真実を知っている。
退学処分を言い渡されることは、父様への道が断たれるのも同じ。そんなの、絶対嫌っ!
「……暗くなってきたから、今日は帰るわね」
お願いだから黙ってて、なんて言ったところで、通じる相手じゃない。それなら、残る手段は一つだけ。大急ぎで家に帰って、メイドを土の中に埋めてやるっ!
思えば、短い付き合いだった。いつか、こんな日が来るんじゃないかって思ってた。
さよなら、アイリス。今までご苦労様。
「……逃げるのね?」
「うるさいっ! そこどいてっ!」
「あらあら、怒ったところが、やっぱり一番かわいいわね。……おいしそう」
「……え?」
「ゆっくり、わたくしの物にしようと思っていたのだけど。もう、我慢なんて出来ない……」
「…………え?」
白くて、細い両腕が伸びてくる。手首が捕まる。
「な、なにするの……!?」
「うふふふふふ。せいぜい抵抗なさって。今日は、お家には帰さないから」
レアナの両手、薬指に嵌められた小さな指輪から、淡い緑色の光が溢れだす。
その光が馴染みのある魔力だと分かり、背筋が冷えた。掴まれた両腕を振りほどこうとしたが、遅かった。万力のように固められた指は、びくともしない。
「もう、逃がさない」
「離してっ!」
レアナが用いたのは、身体能力を高める基礎的な魔術だ。でも展開が速すぎる。詠唱すら必要とせず、指輪程度の品で魔力を媒介するなんて。そんな芸当が出来るのは、学園の教師でもあやしい。
「この……っ!」
感情を必死に高め、内なる魔力を呼び醒ます。
抵抗しろ! 彼女の力を弾き飛ばせ!
歯を食いしばって、必死に足掻いた。
「……哀れね」
出来の悪い人形を蔑むように、笑っていた。心に鋭く、突き刺さった。
「抵抗が無意味なことは、よくご存じでしょう? ……落ちこぼれさん?」
「だ、黙――――!?」
平手打ち。頬が熱い。痛い。
「うるさい下僕は嫌いよ。メイドのこと、学園長にお話されたくなければ、口を閉じなさい」
「……くっ!」
「ふふ、その顔はいいわよ。もっともっと、反抗的な表情で、静かに、黙って、わたくしを睨んでいなさい……」
「!?」
容赦はなかった。力いっぱいに、床上に押し倒される。背中を強く打ちつけて、息が止まる。
身悶える暇なんてない。ほっそりした指が、たわむれるように、私の首に絡みつく。
息を吸いたいのに、馬乗りされて、お腹が動かない! 苦しい、苦しい、苦しいっ!!
「どう……? 気持ちいいでしょう……?」
ゆらゆら揺れる、深海の瞳。
「調理の時間よ、フィノ・トラバント。貴女が望むのは、どんな味……?」
頬を染めあげた。極上の素材が手に入った、調理人のように。
「うふふふふ、まぁ、ゆっくりいきましょう」
「――――けほっ! けほっ!」
指が離れた。埃っぽい室内の空気をいっぱいに吸い込んで、むせ返ってしまう。
必死に空気を求めていると、不意に、冷たい、鉄の匂いがした。
「……な、なによそれ!」
「手錠ですわ。魔術で縛ってもいいのですけど、やっぱり実物の方が、楽しいでしょう?」
「楽しいわけあるかっ!」
「心配しないで。これから "楽しく感じるように" なりますから」
「……い、いやーーーっ!?」
暴れても無意味だった。強化魔術の力は凄まじく、私の両手を片手で抑えつける。残る片手は重い机の足をつかんで、平然と引き寄せた。
硬質な鉄の音。両手首が、机の脚と繋がった。
「……ほら、やっぱり思った通り。貴女って、こういうのがぴったりね」
「全然嬉しくないんだけどっ!?」
「……ゆっくり、躾をしてあげましょうね……うふふ……うふふふふふ!」
「ヘンタイーッ!」
「あら、失礼ですわね。これから貴女は、自分から望んでお願いする立場になるのよ?」
「――――!!」
うっとりと、蕩けるような微笑みに、背筋が凍る。
本気だ。本気で私を『そういう風』にしようとしてる。
「……それじゃ、まずは下拵えから」
ひんやりした掌が、ゆっくり、熱を持った顔をなでていく。
瞼の上を、鼻梁の横を、頬を、唇を。優しく、なで下ろしていく。
「……ひぅっ!?」
吐息がつまった喉元。くすぐるみたいに、指が踊る。
「……ぁ、やだ、だめ、お願いっ!」
くすぐったい。背筋がぞくぞくする。
両手に絡まった手錠が、じゃらじゃらと音を立てて、自分が身悶えているのが分かる。
やだ、いやだ、こんなの。
「だ……だれか……たすけ……て!」
「そうそう、忘れていましたわね」
レアナが片腕を持ち上げて、パチンと指を鳴らす。部屋全体が、薄緑色のなにかで覆われた。
「簡易的な結界ですわ。これであえぐ声はおろか、わたくし達の気配すら、外には通じません。世界で二人きり……うふふ……とっても素敵な響きよね」
「い、いい加減にしてっ!」
「まだそんなことをおっしゃるのね。はやく受け入れた方が楽ですわよ?」
「絶対に嫌っ!!」
「そう? それならちょっと、強引にいきましょうか」
言って、懐から取り出したもの。
白いガーゼ。透明な液体の入った注射器。
「なによ、それっ!?」
「素直になれるお薬よ。最初はちくっとしますけど、明日になれば、これが欲しくて、欲しくて、涎を垂らしてお願いするようになりますからね」
「いやーっ!? 父様助けてーっ!!」
「あらあら、これは予想外ね。もしかしてファザコン?」
「ファザコン言――――!?」
彼女の舌先が、うなじをなでた。ねばついて、ざらついた感触。熱い。
「や、やだ……!」
細いしなやかな指が、制服のスカーフを解いて、ボタンを外していく。
「……ちょ、ちょっと、お願いだから、やめてよっ……!」
「わたくしに、お願いが通じると思っているの……?」
はだけさせられた鎖骨の上。ゆっくり、指がなぞっていく。
触れられたそこはひどく熱いのに、頭の芯は鋭く冷たい。
ぞくぞくする。身体の奥、なにかが殻を破って―――。
『あらあらあらぁ? たのしいことなってるわね。
もしかして、犯されちゃう? 犯されちゃうの?
あはっ! ほらほら、もっと力抜いて。委ねなさい。
食べられちゃいなさい』
ねばつくように、甘い声。
快楽から逃れるように、強く目を閉じた。
だけど暗闇が逆に、彼女の舌先を強く感じてしまう。
「……っ、ぁ、はぁっ!」
生々しい赤い舌先が、何度も、何度も、なであげている。怖いと思った時には違う、ぞくぞくする感覚が、身体の奥から溢れだしてくる。やだ、いやだ。気持ちがいい。
「いやぁ……っ!」
甘い声がこぼれそうになるのを、唇を噛んで必死に耐えた。
「……いい顔……もっと、見せて……わたくしにだけ、見せて……」
レアナの人差し指に、再び魔力が集う光が見えた。赤の閃光を伴った細い指が、身体の中心を、すぅとなでていく。感触はなかったのに、制服と下に着ていたシャツが、綺麗に切り裂かれる。
剥き出しになった自分の肌を、じっと見つめる二つの目。恥辱と恐怖で、身体が痺れたように動かない。
「おいしそう……」
舌舐めずりをする猫のように、彼女の顔が降りてくる。私の胸元に。
「あああああぁぁっ!?」
熱い吐息を感じるのと一緒に、彼女の舌が蠢いていた。残された下着と大切なところを、上から舐めとられた。耐えきれず、あえいだ声が出ちゃう。やだ、こんなのいやっ!
「もっともっと……気持ちよくしてあげる……」
「……やめ……っ!」
ちぅ、と音がする。口付けて、吸われてる。
絡みあうように混じった指先、嫌で仕方がないのに、怖いぐらいに気持ちがいい。
「やめてよぅ……! お願いだから……もうやめてよぅっ!」
「うふふ。貴女って攻められると弱いのね……」
降り注ぐ、キスの雨。頬へ、喉へ、瞼の上へ。
「そろそろ、邪魔な物を取り払ってしまいましょう」
下着が外された。胸の膨らみを隠す物はなくなって、彼女の前に。
「見ないでっ……!」
じゃら、じゃららん。激しい手錠の音がする。
怖い、怖いのに、なにかを期待してる自分がいる。
「さぁ、お薬の時間ですよ……」
「やだ……やだっ!」
首筋を、消毒液の香りのするガーゼが、つたっていく。
注射器の針を覆っていた蓋が、外れる。
「やだぁ……っ!」
ごくん、と唾を飲み込む音が、妙に生々しく聞こえた。
(助けてください……父様っ!)
私の身体は、父様の物って決めてたのにっ!
初めての相手も、父様だって決めてたのにっ!!
まだ、キスまでしか…………あ、やだ、馬鹿、やめて、やめて、やめてーーーっっ!?
『ガシャーーーーーーン!!』
魂の叫び。なにかが砕ける音がした。
周辺を覆っていた薄緑色の結界が砕け散っていく。破片が、無数の砂礫となって消えていく。まさか、本当に、父様が来てくれたっ!?
「ご主人様から、今すぐ離れなさーいっ! この変態っ!!」
違った。結界を破った先にいたのは、見知った一匹の変態だった。結界と同時に、窓の硝子も無視して飛び込んできたみたいだ。陽に反射する破片が、頭に突き刺さっているのが見える。どくどくと、血が流れている。大丈夫かしらと思った矢先、
「きゃうんっ!?」
本棚の角にしたたかに頭を打ちつけた。ぴゅーっと、噴水のように血が溢れ出す……が、倒れない。「変態は死なないもん!」と息まいていたが、確かに丈夫に出来てるわね。
なんてしぶとい。
「助けにきましらよぅ~。ごひゅひんひゃまぁ」
「……」
「あれぇ、なんらか、くらくらしまふへぇ。うへへへへ……」
「……」
耐久性能にも、限界があるみたいだ。壊れちゃった。ただでさえ厄介で面倒なのに。
「アレが、あなたのメイド……?」
「違うわ、違うわよ! 断じて違うわよっ!!」
認めてなるものか。アレの主人だなんて、嫌すぎる。
変態は、自前のエプロンで頭の血を拭っていく。清潔感が第一の白いエプロンが、瞬く間に赤く染まった。
「ふわ~、綺麗になりましたぁ。……えぇと、そこの、サディスティックな変態さん。ご主人様を離してくださいよぅ」
「貴女が彼女の使い魔ね。なるほど、変態だわ」
「変態に変態って言われるのは、心外ですぅ。――あ、ご主人様は別ですから。もっと罵ってくださいね」
「私を変態の仲間扱いしないでよっ!」
拘束されてなければ、思いっきり殴ってやるのに。でも、こうして助けに来てくれたことが嬉しい。なんだかんだで、役に立つ。あとで褒めてあげても……いいかな?
「それにしても変態メイド。どうしてこちらにいらっしゃるのかしら。家でご主人様の帰りを待っていたのではなかったのかしら?」
「ふっふん、甘いですねぇ。ほっぺにちゅーぐらい甘いですねぇ!」
アイリスは得意気に、大きな胸を逸らす。そして、胸元にある収納ポケットから、なにか小さな物を取り出した。なんだろう、あれ。
魔法の力が発展した、ウルスラ王国では滅多に見る事のない、機械?
「これはですねぇ、盗聴機と呼ばれるものですよぅ。いつ! いかなる時も! ご主人様のお声が拝聴出来る、すばらしー代物なのですっ!」
「と、とうちょうき?」
「はいっ! ご主人様がおでかけしている間、さっきゅんはこれを使って、お家で悶えているのです! うっかりこぼされた欠伸の声とか、本当にもう……たまりませんっ!!」
……え。
「驚きましたわ。まさか同じ考えの方がいらっしゃるなんて」
レアナが立ちあがる。懐から、アイリスが取り出した物と、全く同じ機械が現れる。
「うふふ……欠伸の時の、無防備に甘い声色もかわいいけれど、最高の瞬間はやっぱり……」
「ちょっと待てッ! そこの変態共ッ!! まさか、まさかとは思うけどっ! 四六時中、私の声を聞いてたわけじゃ……!」
「そうですよ。だからご主人様のピンチを知って、かけつけて来たんですぅ!」
「死ねっ! 今すぐ舌噛んで死ねっ! 馬鹿ーーーーーッッ!!」
『死ねっ! 今すぐ舌噛んで死ねっ! 馬鹿ーーーーーッッ!!』
叫ぶと、二人の手元にある機械からも、エコーがかかる。すると二人は示し合せたかのように、『保存、保存』と呟いて、機械を操作する。
「はふぅ~、これでまた一つ、オカズが増えたですぅ。えへへ……」
「そうね。彼女の手足を切断して、大切な物を目の前で凌辱してさしあげたりとか……考えるだけで、濡れてしまいそうだわ」
「貴女ってば、本当にサディストですねぇ……。この場合は、ご主人様に逢引がバレちゃって、涙目でさっきゅんのことを罵っている様子を想像すべきですよぅ」
「つまらない。マゾヒストの考えは理解出来ないわ」
「別に理解してもらおうとは、思わないもん」
「ふふ、貴女とは未来永劫、仲良くなれそうにないわね」
「さっきゅんもですよぅ。気が合いますねぇ」
「……あんた達……いい加減にしてよね……」
殴り飛ばしたい。何故かお互いを好敵手と認め合っているような、シニカルな表情の変態二人を殴り飛ばしたい。というか、この恥ずかしい格好を、早くどうにかしたい。寒いし。
「変態メイド、中々やりますわね。存じあげてはいますけど、一応、名前を聞いておきましょうか」
「アイリスですよぅ。ご主人様から頂いた、大事な大事な、私だけの名前です」
「単なる淫魔が、過ぎた名前を頂いたものね。わたくしの名前は、レアナ・クレッシェント・ニルヴァーナ。覚えておきなさい、淫魔」
「そんな長い名前、覚える気にもなりませんよぅ。それより早く、ご主人様の拘束を解いてもらえませんか? 私達はこれから愛の巣に帰って、それはもうイチャイチャパラダイスですから」
「お断りするわ。彼女はこれから、かわいい子犬にするために、調教させなくてはいけませんもの」
「ダメですよぅ。それは、さっきゅんのお仕事だもん」
「貴女の仕事は終わりよ。後はわたくしに引き継がせて、異界に帰りなさい」
「やです。ご主人様と、ご主人様のぱんつは、誰にも渡さないのですぅ」
「あら、わたくし、自分の犬に下着をはかせるつもりはなくってよ。むしろ別の物を入れてあげるけど」
「ははぁ、それもいやらしくて、中々素敵ですねぇ」
「そうでしょう。彼女のような高慢な犬に似合うのは、やっぱり辱めの方がいいと思うの」
「いやいや、でも幼女体型のご主人様には、見られて困るような、愛らしさも必要ですしぃ」
「そうねぇ……」
その後も、延々と二人の会話は続いた。こいつら、死んでしまえばいいのに。
父様、私、もう頑張れないかもしれません。お家に帰りたいです。
ひんやりした掌が、ゆっくり、熱を持った顔をなでていく。
瞼の上を、鼻梁の横を、頬を、唇を。優しく、なで下ろしていく。
「……ひぅっ!?」
吐息がつまった喉元。くすぐるみたいに、指が踊る。
「……ぁ、やだ、だめ、お願いっ!」
くすぐったい。背筋がぞくぞくする。
両手に絡まった手錠が、じゃらじゃらと音を立てて、自分が身悶えているのが分かる。
やだ、いやだ、こんなの。
「だ……だれか……たすけ……て!」
「そうそう、忘れていましたわね」
レアナが片腕を持ち上げて、パチンと指を鳴らす。部屋全体が、薄緑色のなにかで覆われた。
「簡易的な結界ですわ。これであえぐ声はおろか、わたくし達の気配すら、外には通じません。世界で二人きり……うふふ……とっても素敵な響きよね」
「い、いい加減にしてっ!」
「まだそんなことをおっしゃるのね。はやく受け入れた方が楽ですわよ?」
「絶対に嫌っ!!」
「そう? それならちょっと、強引にいきましょうか」
言って、懐から取り出したもの。
白いガーゼ。透明な液体の入った注射器。
「なによ、それっ!?」
「素直になれるお薬よ。最初はちくっとしますけど、明日になれば、これが欲しくて、欲しくて、涎を垂らしてお願いするようになりますからね」
「いやーっ!? 父様助けてーっ!!」
「あらあら、これは予想外ね。もしかしてファザコン?」
「ファザコン言――――!?」
彼女の舌先が、うなじをなでた。ねばついて、ざらついた感触。熱い。
「や、やだ……!」
細いしなやかな指が、制服のスカーフを解いて、ボタンを外していく。
「……ちょ、ちょっと、お願いだから、やめてよっ……!」
「わたくしに、お願いが通じると思っているの……?」
はだけさせられた鎖骨の上。ゆっくり、指がなぞっていく。
触れられたそこはひどく熱いのに、頭の芯は鋭く冷たい。
ぞくぞくする。身体の奥、なにかが殻を破って―――。
『あらあらあらぁ? たのしいことなってるわね。
もしかして、犯されちゃう? 犯されちゃうの?
あはっ! ほらほら、もっと力抜いて。委ねなさい。
食べられちゃいなさい』
ねばつくように、甘い声。
快楽から逃れるように、強く目を閉じた。
だけど暗闇が逆に、彼女の舌先を強く感じてしまう。
「……っ、ぁ、はぁっ!」
生々しい赤い舌先が、何度も、何度も、なであげている。怖いと思った時には違う、ぞくぞくする感覚が、身体の奥から溢れだしてくる。やだ、いやだ。気持ちがいい。
「いやぁ……っ!」
甘い声がこぼれそうになるのを、唇を噛んで必死に耐えた。
「……いい顔……もっと、見せて……わたくしにだけ、見せて……」
レアナの人差し指に、再び魔力が集う光が見えた。赤の閃光を伴った細い指が、身体の中心を、すぅとなでていく。感触はなかったのに、制服と下に着ていたシャツが、綺麗に切り裂かれる。
剥き出しになった自分の肌を、じっと見つめる二つの目。恥辱と恐怖で、身体が痺れたように動かない。
「おいしそう……」
舌舐めずりをする猫のように、彼女の顔が降りてくる。私の胸元に。
「あああああぁぁっ!?」
熱い吐息を感じるのと一緒に、彼女の舌が蠢いていた。残された下着と大切なところを、上から舐めとられた。耐えきれず、あえいだ声が出ちゃう。やだ、こんなのいやっ!
「もっともっと……気持ちよくしてあげる……」
「……やめ……っ!」
ちぅ、と音がする。口付けて、吸われてる。
絡みあうように混じった指先、嫌で仕方がないのに、怖いぐらいに気持ちがいい。
「やめてよぅ……! お願いだから……もうやめてよぅっ!」
「うふふ。貴女って攻められると弱いのね……」
降り注ぐ、キスの雨。頬へ、喉へ、瞼の上へ。
「そろそろ、邪魔な物を取り払ってしまいましょう」
下着が外された。胸の膨らみを隠す物はなくなって、彼女の前に。
「見ないでっ……!」
じゃら、じゃららん。激しい手錠の音がする。
怖い、怖いのに、なにかを期待してる自分がいる。
「さぁ、お薬の時間ですよ……」
「やだ……やだっ!」
首筋を、消毒液の香りのするガーゼが、つたっていく。
注射器の針を覆っていた蓋が、外れる。
「やだぁ……っ!」
ごくん、と唾を飲み込む音が、妙に生々しく聞こえた。
(助けてください……父様っ!)
私の身体は、父様の物って決めてたのにっ!
初めての相手も、父様だって決めてたのにっ!!
まだ、キスまでしか…………あ、やだ、馬鹿、やめて、やめて、やめてーーーっっ!?
『ガシャーーーーーーン!!』
魂の叫び。なにかが砕ける音がした。
周辺を覆っていた薄緑色の結界が砕け散っていく。破片が、無数の砂礫となって消えていく。まさか、本当に、父様が来てくれたっ!?
「ご主人様から、今すぐ離れなさーいっ! この変態っ!!」
違った。結界を破った先にいたのは、見知った一匹の変態だった。結界と同時に、窓の硝子も無視して飛び込んできたみたいだ。陽に反射する破片が、頭に突き刺さっているのが見える。どくどくと、血が流れている。大丈夫かしらと思った矢先、
「きゃうんっ!?」
本棚の角にしたたかに頭を打ちつけた。ぴゅーっと、噴水のように血が溢れ出す……が、倒れない。「変態は死なないもん!」と息まいていたが、確かに丈夫に出来てるわね。
なんてしぶとい。
「助けにきましらよぅ~。ごひゅひんひゃまぁ」
「……」
「あれぇ、なんらか、くらくらしまふへぇ。うへへへへ……」
「……」
耐久性能にも、限界があるみたいだ。壊れちゃった。ただでさえ厄介で面倒なのに。
「アレが、あなたのメイド……?」
「違うわ、違うわよ! 断じて違うわよっ!!」
認めてなるものか。アレの主人だなんて、嫌すぎる。
変態は、自前のエプロンで頭の血を拭っていく。清潔感が第一の白いエプロンが、瞬く間に赤く染まった。
「ふわ~、綺麗になりましたぁ。……えぇと、そこの、サディスティックな変態さん。ご主人様を離してくださいよぅ」
「貴女が彼女の使い魔ね。なるほど、変態だわ」
「変態に変態って言われるのは、心外ですぅ。――あ、ご主人様は別ですから。もっと罵ってくださいね」
「私を変態の仲間扱いしないでよっ!」
拘束されてなければ、思いっきり殴ってやるのに。でも、こうして助けに来てくれたことが嬉しい。なんだかんだで、役に立つ。あとで褒めてあげても……いいかな?
「それにしても変態メイド。どうしてこちらにいらっしゃるのかしら。家でご主人様の帰りを待っていたのではなかったのかしら?」
「ふっふん、甘いですねぇ。ほっぺにちゅーぐらい甘いですねぇ!」
アイリスは得意気に、大きな胸を逸らす。そして、胸元にある収納ポケットから、なにか小さな物を取り出した。なんだろう、あれ。
魔法の力が発展した、ウルスラ王国では滅多に見る事のない、機械?
「これはですねぇ、盗聴機と呼ばれるものですよぅ。いつ! いかなる時も! ご主人様のお声が拝聴出来る、すばらしー代物なのですっ!」
「と、とうちょうき?」
「はいっ! ご主人様がおでかけしている間、さっきゅんはこれを使って、お家で悶えているのです! うっかりこぼされた欠伸の声とか、本当にもう……たまりませんっ!!」
……え。
「驚きましたわ。まさか同じ考えの方がいらっしゃるなんて」
レアナが立ちあがる。懐から、アイリスが取り出した物と、全く同じ機械が現れる。
「うふふ……欠伸の時の、無防備に甘い声色もかわいいけれど、最高の瞬間はやっぱり……」
「ちょっと待てッ! そこの変態共ッ!! まさか、まさかとは思うけどっ! 四六時中、私の声を聞いてたわけじゃ……!」
「そうですよ。だからご主人様のピンチを知って、かけつけて来たんですぅ!」
「死ねっ! 今すぐ舌噛んで死ねっ! 馬鹿ーーーーーッッ!!」
『死ねっ! 今すぐ舌噛んで死ねっ! 馬鹿ーーーーーッッ!!』
叫ぶと、二人の手元にある機械からも、エコーがかかる。すると二人は示し合せたかのように、『保存、保存』と呟いて、機械を操作する。
「はふぅ~、これでまた一つ、オカズが増えたですぅ。えへへ……」
「そうね。彼女の手足を切断して、大切な物を目の前で凌辱してさしあげたりとか……考えるだけで、濡れてしまいそうだわ」
「貴女ってば、本当にサディストですねぇ……。この場合は、ご主人様に逢引がバレちゃって、涙目でさっきゅんのことを罵っている様子を想像すべきですよぅ」
「つまらない。マゾヒストの考えは理解出来ないわ」
「別に理解してもらおうとは、思わないもん」
「ふふ、貴女とは未来永劫、仲良くなれそうにないわね」
「さっきゅんもですよぅ。気が合いますねぇ」
「……あんた達……いい加減にしてよね……」
殴り飛ばしたい。何故かお互いを好敵手と認め合っているような、シニカルな表情の変態二人を殴り飛ばしたい。というか、この恥ずかしい格好を、早くどうにかしたい。寒いし。
「変態メイド、中々やりますわね。存じあげてはいますけど、一応、名前を聞いておきましょうか」
「アイリスですよぅ。ご主人様から頂いた、大事な大事な、私だけの名前です」
「単なる淫魔が、過ぎた名前を頂いたものね。わたくしの名前は、レアナ・クレッシェント・ニルヴァーナ。覚えておきなさい、淫魔」
「そんな長い名前、覚える気にもなりませんよぅ。それより早く、ご主人様の拘束を解いてもらえませんか? 私達はこれから愛の巣に帰って、それはもうイチャイチャパラダイスですから」
「お断りするわ。彼女はこれから、かわいい子犬にするために、調教させなくてはいけませんもの」
「ダメですよぅ。それは、さっきゅんのお仕事だもん」
「貴女の仕事は終わりよ。後はわたくしに引き継がせて、異界に帰りなさい」
「やです。ご主人様と、ご主人様のぱんつは、誰にも渡さないのですぅ」
「あら、わたくし、自分の犬に下着をはかせるつもりはなくってよ。むしろ別の物を入れてあげるけど」
「ははぁ、それもいやらしくて、中々素敵ですねぇ」
「そうでしょう。彼女のような高慢な犬に似合うのは、やっぱり辱めの方がいいと思うの」
「いやいや、でも幼女体型のご主人様には、見られて困るような、愛らしさも必要ですしぃ」
「そうねぇ……」
その後も、延々と二人の会話は続いた。こいつら、死んでしまえばいいのに。
父様、私、もう頑張れないかもしれません。お家に帰りたいです。
笑顔で互いをみやる変態二人組。その異質な雰囲気は、しかし階下から聞こえてきた足音によって、収まっていく。
「――先生、こっちです! さっき、凄い音が聞こえて……っ!」
アイリスが部屋に侵入した際の、ガラスの破裂音を耳にした生徒がいたのだろう。あれだけ派手にやれば、バレない方がおかしい。足音からここへ向かっているのは数人か、慌てて階段を上ってくる音が聞こえてくる。
「……無粋な連中ね。残念ですけれど、貴女との決着は持ち越しですわ。変態メイド」
「別に構いませんよぅ。どうしようもなくなったら、ご主人様と、愛の逃避行をするだけですしぃ」
「私を巻き込むなっ! レアナも早く、この手錠を解きなさいよっ!」
「どうして? とってもそそるのに、その姿」
「こっち見るなっ! さっきやろうとしたこと、洗いざらいぶちまけるわよっ!!」
「仕方がありませんわね。その代わり、わたくしも変態メイドのことを黙っておきますから、おあいこですわよ」
レアナはくつくつ笑いながら、悠然と鍵束を取り出した。かちゃん、と小さな解錠の音がする。急いで起き上がり、変態二人から距離を取る。
「……あれぇ? ご主人様。そこは普通、こっちへ逃げて来るべきですよぅ」
「黙りなさい! 一人の方が、よっぽど、安全だわっ!」
「ふふ、随分嫌われてるじゃない。変態メイド」
「あれはご主人様の、照れ隠しなんですよぅ」
「そんなわけあるかっ!」
お互いに距離をとり、綺麗な正三角形が完成する。その間に、足音はこの階まで辿り着いたようだ。緊迫した息使いと焦りの声が、この部屋へと向かってくる。
「一芝居打つといたしましょう。ここはシンプルに、わたくし達は、謎の変質者に襲われたという設定で」
「仕方ありませんねぇ、その話、乗ってあげますよぅ」
「ふざけるなっ! そこの変質者二名っ!!」
指を突きつけて叫ぶ。しかし二人は示し合せたように、
「もう大丈夫ですよ、ご主人様。怖い人はもう、どこかへ行ってしまいましたからね」
「フィノ・トラバント、ご安心なさって。ここにはもう、わたくし達しかいないのですから、ね?」
「それ、一番危険よねっ!?」
偽りの笑顔が、二人から浮かんだその直後、図書室の扉が開かれた。
その後のことは、あまり思いだしたくない。扉が開かれた瞬間に、飛びかかってきた二人に抱きしめられて、どさくさに紛れて、あんなところやそんなところを触られた。正直、少し死にたくなった。
駆けつけてくれた教師と生徒に、この二人こそが変態であり、諸悪の根源であることを伝えようとした。しかし、アイリスとレアナの猫被りの上手さには、叶わなかった。
「ご主人様。こんなに錯乱なされて……!」
「あぁ、なんて可哀想な、フィノ・トラバント。もう大丈夫ですからね!」
二人は口を揃えて、凶悪な変質者のことを、語りに語った。
腐った中身に相応しい醜悪な男。外見通りの非道な真似を、平然と行った、らしい。
なるほど、外見が美しいだけの変態よりも、確かに聞こえがいいわね。
いい加減にしろ、貴様ら。
「分かりました。もうそれ以上はおっしゃらないで。強く、強く生きるのですよ」
「騙されないでくださいっ! 本当の変態は、まだここにいますっ!!」
「よちよち、ご主人様。とっても怖かったんでちゅねー。でも、もう大丈――あふんっ!?」
「触らないでよ! 馬鹿っ!」
「先生、ご覧のように、フィノ・トラバントの傷は、随分と深いご様子。警備体制の強化をお願いいたしますわ」
「わかりました。すぐに他の教師を集めて、相談しましょう」
「お心遣い、感謝いたしますわ」
てきぱきと、勝手に話が進んでいく。
「……もうやだ、帰りたい」
怒る気力も萎え、なるようになれとあきらめた。その隙を、狙われてしまった。
別れ際、レアナが悠然と微笑んで、耳元で囁いた。
「今日は楽しかったわ。また、二人きりでお会いしましょうね」
「……っ!」
それは正しく、悪魔の囁きだった。
ぬるりと湿った熱の感触。心に刻まれた。
「――先生、こっちです! さっき、凄い音が聞こえて……っ!」
アイリスが部屋に侵入した際の、ガラスの破裂音を耳にした生徒がいたのだろう。あれだけ派手にやれば、バレない方がおかしい。足音からここへ向かっているのは数人か、慌てて階段を上ってくる音が聞こえてくる。
「……無粋な連中ね。残念ですけれど、貴女との決着は持ち越しですわ。変態メイド」
「別に構いませんよぅ。どうしようもなくなったら、ご主人様と、愛の逃避行をするだけですしぃ」
「私を巻き込むなっ! レアナも早く、この手錠を解きなさいよっ!」
「どうして? とってもそそるのに、その姿」
「こっち見るなっ! さっきやろうとしたこと、洗いざらいぶちまけるわよっ!!」
「仕方がありませんわね。その代わり、わたくしも変態メイドのことを黙っておきますから、おあいこですわよ」
レアナはくつくつ笑いながら、悠然と鍵束を取り出した。かちゃん、と小さな解錠の音がする。急いで起き上がり、変態二人から距離を取る。
「……あれぇ? ご主人様。そこは普通、こっちへ逃げて来るべきですよぅ」
「黙りなさい! 一人の方が、よっぽど、安全だわっ!」
「ふふ、随分嫌われてるじゃない。変態メイド」
「あれはご主人様の、照れ隠しなんですよぅ」
「そんなわけあるかっ!」
お互いに距離をとり、綺麗な正三角形が完成する。その間に、足音はこの階まで辿り着いたようだ。緊迫した息使いと焦りの声が、この部屋へと向かってくる。
「一芝居打つといたしましょう。ここはシンプルに、わたくし達は、謎の変質者に襲われたという設定で」
「仕方ありませんねぇ、その話、乗ってあげますよぅ」
「ふざけるなっ! そこの変質者二名っ!!」
指を突きつけて叫ぶ。しかし二人は示し合せたように、
「もう大丈夫ですよ、ご主人様。怖い人はもう、どこかへ行ってしまいましたからね」
「フィノ・トラバント、ご安心なさって。ここにはもう、わたくし達しかいないのですから、ね?」
「それ、一番危険よねっ!?」
偽りの笑顔が、二人から浮かんだその直後、図書室の扉が開かれた。
その後のことは、あまり思いだしたくない。扉が開かれた瞬間に、飛びかかってきた二人に抱きしめられて、どさくさに紛れて、あんなところやそんなところを触られた。正直、少し死にたくなった。
駆けつけてくれた教師と生徒に、この二人こそが変態であり、諸悪の根源であることを伝えようとした。しかし、アイリスとレアナの猫被りの上手さには、叶わなかった。
「ご主人様。こんなに錯乱なされて……!」
「あぁ、なんて可哀想な、フィノ・トラバント。もう大丈夫ですからね!」
二人は口を揃えて、凶悪な変質者のことを、語りに語った。
腐った中身に相応しい醜悪な男。外見通りの非道な真似を、平然と行った、らしい。
なるほど、外見が美しいだけの変態よりも、確かに聞こえがいいわね。
いい加減にしろ、貴様ら。
「分かりました。もうそれ以上はおっしゃらないで。強く、強く生きるのですよ」
「騙されないでくださいっ! 本当の変態は、まだここにいますっ!!」
「よちよち、ご主人様。とっても怖かったんでちゅねー。でも、もう大丈――あふんっ!?」
「触らないでよ! 馬鹿っ!」
「先生、ご覧のように、フィノ・トラバントの傷は、随分と深いご様子。警備体制の強化をお願いいたしますわ」
「わかりました。すぐに他の教師を集めて、相談しましょう」
「お心遣い、感謝いたしますわ」
てきぱきと、勝手に話が進んでいく。
「……もうやだ、帰りたい」
怒る気力も萎え、なるようになれとあきらめた。その隙を、狙われてしまった。
別れ際、レアナが悠然と微笑んで、耳元で囁いた。
「今日は楽しかったわ。また、二人きりでお会いしましょうね」
「……っ!」
それは正しく、悪魔の囁きだった。
ぬるりと湿った熱の感触。心に刻まれた。
今夜から学園の周辺に、非常体制が敷かれることになったらしい。だけどそれで、変質者を捕まえられるとは思わない。
変質者は既に学園の中にいるのだから。さらに言えば、今、ここにいるのだから。
「はぁ~ん、お腹空きましたねぇ、ご主人様ぁ」
「…………」
服を着替え、学園内にある自宅に帰りついた時には、陽はすっかり落ちていた。アイリスも血塗れのメイド服を取り換えて、外見だけは清楚で、つつましいメイド姿に戻っている。
「無駄に長い一日だったわね……」
そして無駄に疲れた。がっくり両肩を落としながら、自宅の鍵を手に取った。
「ご主人様、しっかりと鍵をかけておきましょうね。いつ、変質者がやってくるか分かりませんからねっ!」
「ご忠告ありがとう、アイリス。確かにその通りだわ」
「えへへ、褒められちゃった」
アイリスもたまにはいい事を言う。確かに変質者と同じ屋根の下なんて、危険すぎる。
私は頷いた。頷いて、一人で家に入った。
「……あれ?」
「おやすみ。変質者一号さん」
「い、いや~~んっ!? ご、ご主人様ぁ、お外暗いよぅ、怖いよぅ! 一人にしちゃイヤ~~!!」
扉の向こう側、必死になって、ドアノブを回す音が聞こえてくる。無視して靴を脱ごうとした時だ。
ア・ケ・テ・ク・ダ・サ・イ………オ・ネ・ガ・イ……デ・ス・ヨ・ゥ……
ア・ケ・テ・ア・ケ・テ……コ・コ・ヲ・ア・ケ・テ・ェェェェ!!!
変態が、怨念を込めて、扉をひっかいていた。魔力の波動を感じる。
不気味な、闇の奥深くから這い上がってくるような気配。
「やめなさいーーッ!!」
扉を開けた。すぐ正面に立っていた変態の鼻面に激突。
「いたいですぅ……くすんくすん……ひどいよぅ……」
「お願いだから、呪術的な魔術には、手を出さないでっ!」
「だしませんからぁ、お家にいれてぇー!」
アイリスは小動物のように、扉の僅かな隙間から身を潜らせてくる。そこをすかさず、
「きゅうっ!?」
「うん、ごめんね」
玄関を閉める際、適度にアイリスを扉に挟めて、鬱憤を晴らしておくことを忘れない。なにをするんですかと、軽く涙目で訴えてくる紅い瞳に向けて、笑顔を返してあげた。
「今日は助かったわ、アイリス。結果的にはだけどね。ありがとう」
「あぁんっ! 腹黒いご主人様の笑顔も素敵……っ! そのお顔で、踏んでぇ……っ!」
「やかましい。反省する気ないの?」
「え~? でもさっきゅん、悪いこと、なぁんにもしてないですよ?」
「…………へぇ?」
無邪気に笑うその顔を見て、耐えていた理性の線が切れた。怒りを通り越して、全身が冷たくなる。
「もういいわ――――貴女との契約は、打ち切りよ」
「……えっ?」
疲れていたこともあって、かなり苛立っていた。契約を打ち切ることを、心の底から本気で言ったわけじゃない。けど、いい加減にしてほしかった。
「う、嘘ですよね? ご主人様?」
「黙れ。言う事を聞かない使い魔なんて必要ないわ。帰りなさい、サキュバス。二度とその顔を見せないで」
「……い、いやですっ!!」
アイリスの口から悲痛な声が飛び出した。予想以上の反応で、これでしばらく、大人しくなるかと思ったのに。
「ちょっとっ!」
押し倒されそうな勢いで、胸に飛び込んでくる。両腕が回されて、背骨が折れてしまいそうなぐらい、強く、強く、抱きしめられる。
「お願い、捨てないでっ! なんでもしますからぁ!」
「しなくていいから!」
「さっきゅんのこと、捨てないでっ!!」
「ちょっとっ!?」
「いやですっ、けーやく打ち切るの、いやですぅ! やだっ、やだっ、やっっ!!」
「アイリス、痛いっ! 離して!」
「やーんっ!」
「うるさいっ!」
思いっきり、両頬を横に引っ張ってやる。ぎりぎりと抓ってやると、やっと静かになった。
真っ赤になった頬と、涙で潤んだ紅い瞳で、じっと私を見ている。飼い主に見捨てられた猫のよう。
「……ご主人様ぁ」
「そ、そんな目で見ないでよっ! 大体ねっ、無断で盗聴機をつけるなんて、無茶苦茶よ」
「ごめんなさい。でも、アレがなかったら、今日は本当に危なかったじゃないですかぁ。学園にあんな変態が紛れ込んでるなんて、油断なりませんっ!」
「……貴女が言える立場じゃないでしょ」
「さっきゅんは、いいんです」
「よくないわよ」
「いいんだもん。だって、ご主人様の使い魔なんだから」
拗ねたように、頬を膨らませる。眼尻から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
「ご主人様が見えてないと、不安なんです。寂しいんです。心細いんです。ずっと、ずっと、お側にいたいのに……どうして、許してくれないの……」
「仕方ないでしょ、私は学校があるんだし。一日中側にいるなんて無理よ」
「でも、せめて、声だけでも聞いていたいじゃないですか……」
「……だからって」
「だから内緒で、盗聴機をパンツの生地の中に……ふにゃあああぁぁっ! ほっへひっはらないへええええぇぇっ!!」
「常識を学びなさい! この変態!」
「あ~んっ!」
再び強く抱きしめられた。アイリスの表情が見えなくなる。
「離してよ」
「嫌です。私だけの、たった一人のご主人様。怒られても、罵られても、殴られても、蹴られても、踏みつけられても、転がされても、痺れさせられても。なにがあっても、貴女を離しません」
「……マゾなの?」
「違います。貴女のことが好きなんです。お願い、わかって……」
「わかるわけ……」
柔らかな彼女の肢体は、甘くて、淫らな花の匂いがした。息を吸うだけで、心が跳ねる。
くらりと頭が揺れて、喉が乾いていく。
「アイリス、いい加減に離して」
なにを言ったところで、私達は契約を交わした、主人と使い魔なのだ。使い魔は、けっして主人に抗えない。自由奔放過ぎるアイリスを見ていると、自信がなくなるけれど。
「…………ぅー」
不本意だと言うように、アイリスはゆっくりと、拘束を解いていく。
ようやく向き合った時、頬には沢山の涙のあとが出来ていた。不安に揺れる眼は、さらに心細そうで、今にも大声で泣き出しそう。
「ごしゅじんさまぁ……」
潤んだ眼差しで、じっと私を見つめる彼女。
心臓の音が、大きく脈打つ。血が昇っていく。
身体が、なにかを求めてざわめいた。
なにが欲しいの。言って。
わたしは、
「――――アイリス」
喉が渇いていた。渇きを満たす水を求めてた。忘れられないぐらい、どろりとした、濃い味の。
強くなにかを求めてる。強くなにかを欲してる。
(……なに、これ。私、どうしちゃったの……?)
危ないよ。それ以上考えると、戻れなくなるよ。内から響く、誰かの声。
二つの感情がせめぎ合う。すぐに大きく傾いた。
アイリスが、胸元へと、綺麗な顔を押し付けていた。
「ご主人様……離さないで……」
声のする方へ、心が落ちていく。
「……けーやく、打ち切らないでください……お側にいてください……」
布越しに感じられる、腹が立つぐらいに大きな胸の膨らみ。その奥にある、心臓の音。
とく、とく、動いてる。音がしてる。その音に重なりたい。一緒になりたい。
「ご主人様、ご主人様、ご主人様……」
苦しい。心臓が、急く。
「もう、どこにも行かないで……っ!」
繰り返し、繰り返し、誰かの名前を呼んだ。不思議と分かった。
彼女が呼んでいるのは、私じゃない。彼女が求めているのは、私じゃない。
「アイリス……」
息が苦しい。胸が切り裂かれていく。
どうして、私じゃないの。
貴女が呼んでいる『ご主人様』って、誰なの。
「ご主人様、お願いです。お願いですからぁ……!」
「うるさいっ!」
名前を呼んで。私の名前を呼んで。
どこの誰だか知らない『ご主人様』じゃなくて、貴女が契約をした、私の名前を呼んで!
「アイリスのバカっ! 大っ嫌い!!」
頭に白い霧が浮かびあがっていた。
耐えきれず、彼女の背に爪を立てた。声を押し殺して、首筋に噛みついた。
苦しくて、息がままならない。
「……!? い、いたいですっ……っ!」
どうして、私を呼んでくれないの。貴女は、誰を呼んでるの。
紅い瞳、甘い花の香り、ゆっくりと揺れ落ちてくる、アイリスの長い黒髪。
縋るように抱きしめた。いつもと大きく異なる気持ち。悲しい。辛い。
分からなくなってくる。なにを求めているのか。
分からなくなってくる。彼女をどうしたいのか。
分からなくなってくる。私が、分から
『ムズカシイ事、考える必要あるの?
食べたければ、食べればいいじゃない。
飲みたければ、飲めばいいじゃない。
ねぇ、はやくぅ。迷ってるなら、私が代わってあげるわよ?』
地面がぐらりと揺れた。力が入らない。意識と理性が追い付かない。
頭が、割れるように痛い。
全身を巡る血が、失敗をして、恥をかいてしまった時のように、熱い。
「あ、あの……? ご主人様、大丈夫ですか?」
「……うる、さ、い……」
大丈夫なはず、ないじゃない。誰のせいだと思ってるの。
「今日はごめんなさい。疲れてますよね。お薬持っていきますから、寝室でお休みになってください」
「……いい、平気だから……」
「とても平気に見えません。足元ふらふらしてますよ。ベッドまで歩けますか?
ひどい。でも、かわいい。ずっとそうして、見つめていて。私だけを、見つめていて。
紅い瞳が、私を見るためだけに、あればいい。
赤い唇が、私の名前を呼ぶためだけに、あればいい。
私の声以外、聞いてはダメ。私の物以外、触れてはダメ。私の事以外、考えてはダメ。
鎖で縛りつけたい。
二人きりで、いつまでも触れあっていたい。
食べたい。
なに、これ。
わたし、どうして、そんなに、だって、しんぱい、ちがう、おいしい、なに、だれ、
なんなの、だいじな、ちがう、なにが、ほしいの、あたえて、たべてよ、
だれなの、あなた、しらない、こたえて、わたしは、だれなの、
わたしは、あなた――――
同じよ。私たちは、同じ。
「……ご、ご主人様?」
「――――――なぁに?」
心臓の音が激しく急いた。喉が鳴る。心が滾る。
身体が求めて、魂がそれに応えてる。『たべたい。たべたいよ。たべてしまいたい』
『そうそう。ぜんぶ、私たちの物なのよ。跡形も残さずに、隅々まで存分に味わうの』
『でも、父様が許してくださらないわ』
『いいじゃない。内緒にしておけば平気よ。それに一番は変わりないんでしょ。私たちは、彼女のご主人様なのよ。いじめるのも、可愛がるのも、思いのまま』
『そうかな。でも……』
『ご主人様は、なにをしてもいいの。なにをしても許される。彼女だって、きっと受け入れてくれるわ。ほら、みて。私たちのこと、あんな眼で見てる』
『かわいい。とっても……』
『おいしそうでしょ? あぁ、駄目、もう、はやく食べたい』
『うん、食べよう。どこから食べればいいかな?』
『前菜は軽く済ませたいわね。やっぱりメインデイッシュを楽しまないと』
『デザートは?』
『あまいクリームが、たっぷり乗ってるのがいいわね。食べ終わった時、お口の周り、ベタベタしてるかも』
『お行儀悪いと、怒られない?』
『平気よ。私たちがご主人様なんだもの。ずっと、ずっと、ずぅーっと、二人っきり。あの子を気が済むまで食べちゃえばいいの。いっぱい、いっぱい、命令してあげるのよ』
『いじめるの? 壊しちゃってもいい?』
『もういいよって言うまでは、壊しちゃ、だめ。いっぱい、いっぱい、おねだりさせてあげるの。その時の顔をよく見てね。とってもおいしそうに、蕩けてるはずだから』
『うん。じゃあ、食べていい?』
『もちろん』
彼女に触れる。それからしばらく、お互いを静かに見つめていた。
「――――おいしい……」
触れた唇を、自分の舌で舐めとった。
彼女の甘い味が脳髄まで通じて、それだけで我慢が出来なくなる。
気が狂っちゃいそう。でも、壊しちゃいけないって言われたから、我慢。
「………………ぇ」
彼女のてっぺんから、真っ白な蒸気が立ち上った。綺麗な顔が真っ赤に染まっていって、触れたばかりの唇を、細くてしなやかな掌で覆う。いつもは見せてくれない、恥じらいを含んだその姿が、すごくかわいい。
「おいしかった?」
「……ご、ご、ご、ご主人様!? 気は確かですかっ!?」
「うん。アイリスが好き。とっても、大好き」
「衛生兵ーーッ! 重傷者一名ーーーッ!!」
「うるさいなぁ」
わけの分かんないことを言う口を、もう一回黙らせる。そのまま、今度は前菜を求めた。
彼女の耳朶は、口に含むと、予想以上に柔らかくておいしい。軽く歯で噛んであげると、固い骨が、びくりと震えた。その反応が心地良くて、つい、ねっとりした舌先で探ってしまう。
「……んぅ……」
駄目だ。すごくおいしい。私の方が壊れちゃいそう。
両手を頭の後ろに回す。もっと深く、ちょうだい。
「あ、あの、その、えと、えぇと、はわわ、はわわわ、はわわわわわ……っ!?」
「どうしたの? なんで止めるの?」
「なんでって、なんでって、なんでってえええぇぇ!?」
活きの良い魚のように、口をパクパクさせる。変な子。
「今、ものすごく心臓ドキドキしてるんですけどっ! いろんな意味でっ!!」
「私も。ねぇ、続きしよ?」
「……でもこれ以上進むと、十八歳未満は、閲覧禁止になっちゃいますよ?」
「ダメ?」
「……本当にどうしちゃったんですか。失礼ですけど、おつむ大丈夫ですか?」
「別にどうもしないわ。……そろそろ、続けてもいい?」
「いやーんっ! ご主人様が壊れちゃったよおおおぉぉーーっ!!」
「うるさい」
私よりも少しだけ、背の高い彼女。赤い唇が、とても綺麗。
逃げようとする顔を、しっかり抑えつけてやる。
吸い寄せられるように、顔を近づけた。
足りない距離は、踵を、床から離すだけで、事足りた。
触れたのは、本当に、一瞬だけ。
もう一度、笑ってあげる。
「ご主人様……」
紅い瞳の中に、私が見えた。
「本当に、いいんですか?」
「うん」
「……目を、閉じていてもらますか?」
「うん」
静かに目を閉じた。アイリスの一番深いところは、どんな味がするんだろう。
私に、私だけに、教えて。全部受け止めてあげるから――――――。
『――――はい、そこまで。それ以上は、フィノにはまだ早いよ。離れなさい』
だけどその時、また、声が聞こえた。
いやらしく笑う、淫らな声じゃない。
世界で一番、聞き覚えのある素敵な声。貫く棘を添えて、突き刺された。
瞼の中に映るその人は、私のすべて。いつもより険しい顔を浮かべて、怒ってる。
『君はまだ、羽化する時じゃない。もう少しだけ、子供でいなさい』
暗闇の中で光る怜悧な眼差しが、私を見てる。あぁ……ごめんなさい。私、悪い子でした。許してください、お父様。いい子にするから、だから、嫌わないで。
目を開けて、寸前まで迫っていた唇を押し退けた。
頭の中に浮かんでいた、白い靄が消え去って、身体が冷たくなっていく。耳鳴りが止んで、心臓の音も少しずつ、穏やかになってくる。
しばらくなにも考えられず、ぼんやり、天井だけを見つめていた。
「ご、ご主人様ぁっ! そんなに焦らされたら……もう、我慢が――――ごふっ!?」
間近に迫っていた変態の鼻面を、なにも考えず、ぐーで殴った。
見事に半円を描き、床に倒れ伏した変態。なにも考えず踏みつける。
「なんでこうなるのおおおおぉぉぉぉ!?」
「う、うるさあいっ!」
踏みつける。踏みつける。踏みつける。踏みつける。
踏み続ける。体力の続く限り!
踏まれろ! 潰れろ! 肉塊と化せ! 変態!!
「ご、ご主人様ぁっ! これは踏まれて気持ちいいというレベルを超えてますっ!」
「死ね、死ね、死ねっ!!」
「あぁーーーっ!? ヒットポイントがなくなっちゃうううぅぅぅっ!!」
アイリスの断末魔。いつものように、頭が冴えてきた。だけど自分がしたことが消えるはずもなくて、私の方が、恥ずかしさで死んでしまいそう。
「アイリスなんて、大っ嫌い!」
アイリスの頭をぐりぐり押し潰して、気持ちをどうにか抑えつける。「今のなしだからねっ! ノーカウントっ!」
「そ、そんなっ!? ご主人様から誘っておいて……むぎゅーーーー!?」
這い上がる死者に、脳天チョップ!
「さっきのは違うの! 間違いっ!」
「えーーっ!?」
「あんたのことなんて、好きじゃないんだからねっ!!」
「……だけど、瑞々しかった唇の柔らかさは、強く脳裏に焼きついてしまったのです。あの瞬間、爛れ落ちる寸前の、甘い果実の味。それが忘れられな……ぐふぅっ!?」
「妙な語りを入れるなっ!」
飛び膝蹴りが、鳩尾に綺麗におさまった。吐血した。
やめてよね。制服が汚れるじゃない。
「……ま、負けませんよぅ……っ!」
「しぶといわねっ! えいっ! えいっ! このぉっ!」
「がふっ!? こ……ここで……諦めてなるものかああぁぁぁ!!」
変態が三度崩れ落ちつつ、がしっ! としがみ付いてきた。
「今のは絶対、フラグ立ってたもんっ! もうちょっと、もうちょっとで、十八歳未満禁止のイベントが、さっきゅんの目の前に開かれていたはずなのですっ! しかし、なんということでしょうっ! 選択肢らしい選択肢が出現せず、気がつけばフルボッコ一択っ! プレイヤーの期待を散々煽っておいて、オチがそれってひどくないですか! ……はっ! もしやさっきゅん自身のパラメーターが足りなかったというのですかっ! そんな馬鹿なことがあってたまりますかっ! お手軽なエロシチュが売りの業界で、そんな面倒なものは不必要なんですうぅぅぅーーー!!」
「うるさいっ! 意味のわからないことを喚くなっ!」
もうなにがなにやら。
気持ちを無理やり抑えつけるために、手近にあった物を、全力で引っ張ってやった。
「ひあっ!? ご主人様、そんなとこ引っ張っちゃ……」
ぎゅうううう……っ!
「らめえええええええええっ!? ちぎれちゃう、ちぎれちゃう、ちぎれちゃうううううううううううーーーーーー!?!?」
「黙りなさい! 私の話を聞きなさいっ!」
「聞きますから、やめてえぇぇーーっ!!」
「さっきのは、今日の夕方に助けてくれたお礼なのっ!! けっして深い意味はないのよっ!! わかった!? わかったわね!? わかりましたって言え―ッ!!」
「わかりましたああ! だからお願い、もうやめてえええええええ!!」
この夜、彼女の弱点を見つけた。普段は服の中に隠している尻尾。
次に変なコトしたら、この尻尾、引き抜いてやるんだからっ!
変質者は既に学園の中にいるのだから。さらに言えば、今、ここにいるのだから。
「はぁ~ん、お腹空きましたねぇ、ご主人様ぁ」
「…………」
服を着替え、学園内にある自宅に帰りついた時には、陽はすっかり落ちていた。アイリスも血塗れのメイド服を取り換えて、外見だけは清楚で、つつましいメイド姿に戻っている。
「無駄に長い一日だったわね……」
そして無駄に疲れた。がっくり両肩を落としながら、自宅の鍵を手に取った。
「ご主人様、しっかりと鍵をかけておきましょうね。いつ、変質者がやってくるか分かりませんからねっ!」
「ご忠告ありがとう、アイリス。確かにその通りだわ」
「えへへ、褒められちゃった」
アイリスもたまにはいい事を言う。確かに変質者と同じ屋根の下なんて、危険すぎる。
私は頷いた。頷いて、一人で家に入った。
「……あれ?」
「おやすみ。変質者一号さん」
「い、いや~~んっ!? ご、ご主人様ぁ、お外暗いよぅ、怖いよぅ! 一人にしちゃイヤ~~!!」
扉の向こう側、必死になって、ドアノブを回す音が聞こえてくる。無視して靴を脱ごうとした時だ。
ア・ケ・テ・ク・ダ・サ・イ………オ・ネ・ガ・イ……デ・ス・ヨ・ゥ……
ア・ケ・テ・ア・ケ・テ……コ・コ・ヲ・ア・ケ・テ・ェェェェ!!!
変態が、怨念を込めて、扉をひっかいていた。魔力の波動を感じる。
不気味な、闇の奥深くから這い上がってくるような気配。
「やめなさいーーッ!!」
扉を開けた。すぐ正面に立っていた変態の鼻面に激突。
「いたいですぅ……くすんくすん……ひどいよぅ……」
「お願いだから、呪術的な魔術には、手を出さないでっ!」
「だしませんからぁ、お家にいれてぇー!」
アイリスは小動物のように、扉の僅かな隙間から身を潜らせてくる。そこをすかさず、
「きゅうっ!?」
「うん、ごめんね」
玄関を閉める際、適度にアイリスを扉に挟めて、鬱憤を晴らしておくことを忘れない。なにをするんですかと、軽く涙目で訴えてくる紅い瞳に向けて、笑顔を返してあげた。
「今日は助かったわ、アイリス。結果的にはだけどね。ありがとう」
「あぁんっ! 腹黒いご主人様の笑顔も素敵……っ! そのお顔で、踏んでぇ……っ!」
「やかましい。反省する気ないの?」
「え~? でもさっきゅん、悪いこと、なぁんにもしてないですよ?」
「…………へぇ?」
無邪気に笑うその顔を見て、耐えていた理性の線が切れた。怒りを通り越して、全身が冷たくなる。
「もういいわ――――貴女との契約は、打ち切りよ」
「……えっ?」
疲れていたこともあって、かなり苛立っていた。契約を打ち切ることを、心の底から本気で言ったわけじゃない。けど、いい加減にしてほしかった。
「う、嘘ですよね? ご主人様?」
「黙れ。言う事を聞かない使い魔なんて必要ないわ。帰りなさい、サキュバス。二度とその顔を見せないで」
「……い、いやですっ!!」
アイリスの口から悲痛な声が飛び出した。予想以上の反応で、これでしばらく、大人しくなるかと思ったのに。
「ちょっとっ!」
押し倒されそうな勢いで、胸に飛び込んでくる。両腕が回されて、背骨が折れてしまいそうなぐらい、強く、強く、抱きしめられる。
「お願い、捨てないでっ! なんでもしますからぁ!」
「しなくていいから!」
「さっきゅんのこと、捨てないでっ!!」
「ちょっとっ!?」
「いやですっ、けーやく打ち切るの、いやですぅ! やだっ、やだっ、やっっ!!」
「アイリス、痛いっ! 離して!」
「やーんっ!」
「うるさいっ!」
思いっきり、両頬を横に引っ張ってやる。ぎりぎりと抓ってやると、やっと静かになった。
真っ赤になった頬と、涙で潤んだ紅い瞳で、じっと私を見ている。飼い主に見捨てられた猫のよう。
「……ご主人様ぁ」
「そ、そんな目で見ないでよっ! 大体ねっ、無断で盗聴機をつけるなんて、無茶苦茶よ」
「ごめんなさい。でも、アレがなかったら、今日は本当に危なかったじゃないですかぁ。学園にあんな変態が紛れ込んでるなんて、油断なりませんっ!」
「……貴女が言える立場じゃないでしょ」
「さっきゅんは、いいんです」
「よくないわよ」
「いいんだもん。だって、ご主人様の使い魔なんだから」
拗ねたように、頬を膨らませる。眼尻から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
「ご主人様が見えてないと、不安なんです。寂しいんです。心細いんです。ずっと、ずっと、お側にいたいのに……どうして、許してくれないの……」
「仕方ないでしょ、私は学校があるんだし。一日中側にいるなんて無理よ」
「でも、せめて、声だけでも聞いていたいじゃないですか……」
「……だからって」
「だから内緒で、盗聴機をパンツの生地の中に……ふにゃあああぁぁっ! ほっへひっはらないへええええぇぇっ!!」
「常識を学びなさい! この変態!」
「あ~んっ!」
再び強く抱きしめられた。アイリスの表情が見えなくなる。
「離してよ」
「嫌です。私だけの、たった一人のご主人様。怒られても、罵られても、殴られても、蹴られても、踏みつけられても、転がされても、痺れさせられても。なにがあっても、貴女を離しません」
「……マゾなの?」
「違います。貴女のことが好きなんです。お願い、わかって……」
「わかるわけ……」
柔らかな彼女の肢体は、甘くて、淫らな花の匂いがした。息を吸うだけで、心が跳ねる。
くらりと頭が揺れて、喉が乾いていく。
「アイリス、いい加減に離して」
なにを言ったところで、私達は契約を交わした、主人と使い魔なのだ。使い魔は、けっして主人に抗えない。自由奔放過ぎるアイリスを見ていると、自信がなくなるけれど。
「…………ぅー」
不本意だと言うように、アイリスはゆっくりと、拘束を解いていく。
ようやく向き合った時、頬には沢山の涙のあとが出来ていた。不安に揺れる眼は、さらに心細そうで、今にも大声で泣き出しそう。
「ごしゅじんさまぁ……」
潤んだ眼差しで、じっと私を見つめる彼女。
心臓の音が、大きく脈打つ。血が昇っていく。
身体が、なにかを求めてざわめいた。
なにが欲しいの。言って。
わたしは、
「――――アイリス」
喉が渇いていた。渇きを満たす水を求めてた。忘れられないぐらい、どろりとした、濃い味の。
強くなにかを求めてる。強くなにかを欲してる。
(……なに、これ。私、どうしちゃったの……?)
危ないよ。それ以上考えると、戻れなくなるよ。内から響く、誰かの声。
二つの感情がせめぎ合う。すぐに大きく傾いた。
アイリスが、胸元へと、綺麗な顔を押し付けていた。
「ご主人様……離さないで……」
声のする方へ、心が落ちていく。
「……けーやく、打ち切らないでください……お側にいてください……」
布越しに感じられる、腹が立つぐらいに大きな胸の膨らみ。その奥にある、心臓の音。
とく、とく、動いてる。音がしてる。その音に重なりたい。一緒になりたい。
「ご主人様、ご主人様、ご主人様……」
苦しい。心臓が、急く。
「もう、どこにも行かないで……っ!」
繰り返し、繰り返し、誰かの名前を呼んだ。不思議と分かった。
彼女が呼んでいるのは、私じゃない。彼女が求めているのは、私じゃない。
「アイリス……」
息が苦しい。胸が切り裂かれていく。
どうして、私じゃないの。
貴女が呼んでいる『ご主人様』って、誰なの。
「ご主人様、お願いです。お願いですからぁ……!」
「うるさいっ!」
名前を呼んで。私の名前を呼んで。
どこの誰だか知らない『ご主人様』じゃなくて、貴女が契約をした、私の名前を呼んで!
「アイリスのバカっ! 大っ嫌い!!」
頭に白い霧が浮かびあがっていた。
耐えきれず、彼女の背に爪を立てた。声を押し殺して、首筋に噛みついた。
苦しくて、息がままならない。
「……!? い、いたいですっ……っ!」
どうして、私を呼んでくれないの。貴女は、誰を呼んでるの。
紅い瞳、甘い花の香り、ゆっくりと揺れ落ちてくる、アイリスの長い黒髪。
縋るように抱きしめた。いつもと大きく異なる気持ち。悲しい。辛い。
分からなくなってくる。なにを求めているのか。
分からなくなってくる。彼女をどうしたいのか。
分からなくなってくる。私が、分から
『ムズカシイ事、考える必要あるの?
食べたければ、食べればいいじゃない。
飲みたければ、飲めばいいじゃない。
ねぇ、はやくぅ。迷ってるなら、私が代わってあげるわよ?』
地面がぐらりと揺れた。力が入らない。意識と理性が追い付かない。
頭が、割れるように痛い。
全身を巡る血が、失敗をして、恥をかいてしまった時のように、熱い。
「あ、あの……? ご主人様、大丈夫ですか?」
「……うる、さ、い……」
大丈夫なはず、ないじゃない。誰のせいだと思ってるの。
「今日はごめんなさい。疲れてますよね。お薬持っていきますから、寝室でお休みになってください」
「……いい、平気だから……」
「とても平気に見えません。足元ふらふらしてますよ。ベッドまで歩けますか?
ひどい。でも、かわいい。ずっとそうして、見つめていて。私だけを、見つめていて。
紅い瞳が、私を見るためだけに、あればいい。
赤い唇が、私の名前を呼ぶためだけに、あればいい。
私の声以外、聞いてはダメ。私の物以外、触れてはダメ。私の事以外、考えてはダメ。
鎖で縛りつけたい。
二人きりで、いつまでも触れあっていたい。
食べたい。
なに、これ。
わたし、どうして、そんなに、だって、しんぱい、ちがう、おいしい、なに、だれ、
なんなの、だいじな、ちがう、なにが、ほしいの、あたえて、たべてよ、
だれなの、あなた、しらない、こたえて、わたしは、だれなの、
わたしは、あなた――――
同じよ。私たちは、同じ。
「……ご、ご主人様?」
「――――――なぁに?」
心臓の音が激しく急いた。喉が鳴る。心が滾る。
身体が求めて、魂がそれに応えてる。『たべたい。たべたいよ。たべてしまいたい』
『そうそう。ぜんぶ、私たちの物なのよ。跡形も残さずに、隅々まで存分に味わうの』
『でも、父様が許してくださらないわ』
『いいじゃない。内緒にしておけば平気よ。それに一番は変わりないんでしょ。私たちは、彼女のご主人様なのよ。いじめるのも、可愛がるのも、思いのまま』
『そうかな。でも……』
『ご主人様は、なにをしてもいいの。なにをしても許される。彼女だって、きっと受け入れてくれるわ。ほら、みて。私たちのこと、あんな眼で見てる』
『かわいい。とっても……』
『おいしそうでしょ? あぁ、駄目、もう、はやく食べたい』
『うん、食べよう。どこから食べればいいかな?』
『前菜は軽く済ませたいわね。やっぱりメインデイッシュを楽しまないと』
『デザートは?』
『あまいクリームが、たっぷり乗ってるのがいいわね。食べ終わった時、お口の周り、ベタベタしてるかも』
『お行儀悪いと、怒られない?』
『平気よ。私たちがご主人様なんだもの。ずっと、ずっと、ずぅーっと、二人っきり。あの子を気が済むまで食べちゃえばいいの。いっぱい、いっぱい、命令してあげるのよ』
『いじめるの? 壊しちゃってもいい?』
『もういいよって言うまでは、壊しちゃ、だめ。いっぱい、いっぱい、おねだりさせてあげるの。その時の顔をよく見てね。とってもおいしそうに、蕩けてるはずだから』
『うん。じゃあ、食べていい?』
『もちろん』
彼女に触れる。それからしばらく、お互いを静かに見つめていた。
「――――おいしい……」
触れた唇を、自分の舌で舐めとった。
彼女の甘い味が脳髄まで通じて、それだけで我慢が出来なくなる。
気が狂っちゃいそう。でも、壊しちゃいけないって言われたから、我慢。
「………………ぇ」
彼女のてっぺんから、真っ白な蒸気が立ち上った。綺麗な顔が真っ赤に染まっていって、触れたばかりの唇を、細くてしなやかな掌で覆う。いつもは見せてくれない、恥じらいを含んだその姿が、すごくかわいい。
「おいしかった?」
「……ご、ご、ご、ご主人様!? 気は確かですかっ!?」
「うん。アイリスが好き。とっても、大好き」
「衛生兵ーーッ! 重傷者一名ーーーッ!!」
「うるさいなぁ」
わけの分かんないことを言う口を、もう一回黙らせる。そのまま、今度は前菜を求めた。
彼女の耳朶は、口に含むと、予想以上に柔らかくておいしい。軽く歯で噛んであげると、固い骨が、びくりと震えた。その反応が心地良くて、つい、ねっとりした舌先で探ってしまう。
「……んぅ……」
駄目だ。すごくおいしい。私の方が壊れちゃいそう。
両手を頭の後ろに回す。もっと深く、ちょうだい。
「あ、あの、その、えと、えぇと、はわわ、はわわわ、はわわわわわ……っ!?」
「どうしたの? なんで止めるの?」
「なんでって、なんでって、なんでってえええぇぇ!?」
活きの良い魚のように、口をパクパクさせる。変な子。
「今、ものすごく心臓ドキドキしてるんですけどっ! いろんな意味でっ!!」
「私も。ねぇ、続きしよ?」
「……でもこれ以上進むと、十八歳未満は、閲覧禁止になっちゃいますよ?」
「ダメ?」
「……本当にどうしちゃったんですか。失礼ですけど、おつむ大丈夫ですか?」
「別にどうもしないわ。……そろそろ、続けてもいい?」
「いやーんっ! ご主人様が壊れちゃったよおおおぉぉーーっ!!」
「うるさい」
私よりも少しだけ、背の高い彼女。赤い唇が、とても綺麗。
逃げようとする顔を、しっかり抑えつけてやる。
吸い寄せられるように、顔を近づけた。
足りない距離は、踵を、床から離すだけで、事足りた。
触れたのは、本当に、一瞬だけ。
もう一度、笑ってあげる。
「ご主人様……」
紅い瞳の中に、私が見えた。
「本当に、いいんですか?」
「うん」
「……目を、閉じていてもらますか?」
「うん」
静かに目を閉じた。アイリスの一番深いところは、どんな味がするんだろう。
私に、私だけに、教えて。全部受け止めてあげるから――――――。
『――――はい、そこまで。それ以上は、フィノにはまだ早いよ。離れなさい』
だけどその時、また、声が聞こえた。
いやらしく笑う、淫らな声じゃない。
世界で一番、聞き覚えのある素敵な声。貫く棘を添えて、突き刺された。
瞼の中に映るその人は、私のすべて。いつもより険しい顔を浮かべて、怒ってる。
『君はまだ、羽化する時じゃない。もう少しだけ、子供でいなさい』
暗闇の中で光る怜悧な眼差しが、私を見てる。あぁ……ごめんなさい。私、悪い子でした。許してください、お父様。いい子にするから、だから、嫌わないで。
目を開けて、寸前まで迫っていた唇を押し退けた。
頭の中に浮かんでいた、白い靄が消え去って、身体が冷たくなっていく。耳鳴りが止んで、心臓の音も少しずつ、穏やかになってくる。
しばらくなにも考えられず、ぼんやり、天井だけを見つめていた。
「ご、ご主人様ぁっ! そんなに焦らされたら……もう、我慢が――――ごふっ!?」
間近に迫っていた変態の鼻面を、なにも考えず、ぐーで殴った。
見事に半円を描き、床に倒れ伏した変態。なにも考えず踏みつける。
「なんでこうなるのおおおおぉぉぉぉ!?」
「う、うるさあいっ!」
踏みつける。踏みつける。踏みつける。踏みつける。
踏み続ける。体力の続く限り!
踏まれろ! 潰れろ! 肉塊と化せ! 変態!!
「ご、ご主人様ぁっ! これは踏まれて気持ちいいというレベルを超えてますっ!」
「死ね、死ね、死ねっ!!」
「あぁーーーっ!? ヒットポイントがなくなっちゃうううぅぅぅっ!!」
アイリスの断末魔。いつものように、頭が冴えてきた。だけど自分がしたことが消えるはずもなくて、私の方が、恥ずかしさで死んでしまいそう。
「アイリスなんて、大っ嫌い!」
アイリスの頭をぐりぐり押し潰して、気持ちをどうにか抑えつける。「今のなしだからねっ! ノーカウントっ!」
「そ、そんなっ!? ご主人様から誘っておいて……むぎゅーーーー!?」
這い上がる死者に、脳天チョップ!
「さっきのは違うの! 間違いっ!」
「えーーっ!?」
「あんたのことなんて、好きじゃないんだからねっ!!」
「……だけど、瑞々しかった唇の柔らかさは、強く脳裏に焼きついてしまったのです。あの瞬間、爛れ落ちる寸前の、甘い果実の味。それが忘れられな……ぐふぅっ!?」
「妙な語りを入れるなっ!」
飛び膝蹴りが、鳩尾に綺麗におさまった。吐血した。
やめてよね。制服が汚れるじゃない。
「……ま、負けませんよぅ……っ!」
「しぶといわねっ! えいっ! えいっ! このぉっ!」
「がふっ!? こ……ここで……諦めてなるものかああぁぁぁ!!」
変態が三度崩れ落ちつつ、がしっ! としがみ付いてきた。
「今のは絶対、フラグ立ってたもんっ! もうちょっと、もうちょっとで、十八歳未満禁止のイベントが、さっきゅんの目の前に開かれていたはずなのですっ! しかし、なんということでしょうっ! 選択肢らしい選択肢が出現せず、気がつけばフルボッコ一択っ! プレイヤーの期待を散々煽っておいて、オチがそれってひどくないですか! ……はっ! もしやさっきゅん自身のパラメーターが足りなかったというのですかっ! そんな馬鹿なことがあってたまりますかっ! お手軽なエロシチュが売りの業界で、そんな面倒なものは不必要なんですうぅぅぅーーー!!」
「うるさいっ! 意味のわからないことを喚くなっ!」
もうなにがなにやら。
気持ちを無理やり抑えつけるために、手近にあった物を、全力で引っ張ってやった。
「ひあっ!? ご主人様、そんなとこ引っ張っちゃ……」
ぎゅうううう……っ!
「らめえええええええええっ!? ちぎれちゃう、ちぎれちゃう、ちぎれちゃうううううううううううーーーーーー!?!?」
「黙りなさい! 私の話を聞きなさいっ!」
「聞きますから、やめてえぇぇーーっ!!」
「さっきのは、今日の夕方に助けてくれたお礼なのっ!! けっして深い意味はないのよっ!! わかった!? わかったわね!? わかりましたって言え―ッ!!」
「わかりましたああ! だからお願い、もうやめてえええええええ!!」
この夜、彼女の弱点を見つけた。普段は服の中に隠している尻尾。
次に変なコトしたら、この尻尾、引き抜いてやるんだからっ!

