天ノ雀――アマノジャク――
01.天馬の麻雀
その頃、麻雀が流行っていた。というのも深夜アニメで麻雀を題材にしたものが二つ放映され、また十数年近く続いた麻雀漫画が大団円を迎えて完結したりと、不意に麻雀という言葉を耳にする機会が多かった。徹夜なし煙草なし賭けなしの健康麻雀が認められてきたということもあっただろう、女性や子供向けの小ぶりな牌が発売された。三大少年誌のすべてで麻雀漫画が連載され始め、馬場天馬はそれらを毎週欠かさず読んでいた。
「賭けねえ麻雀なんか面白くねえよ。調子に乗った初心者が来たらカモってやろうぜ」
渡り廊下でマットを広げている同級生たちがそう嘲笑ってはしゃいでいるのを見て、ふむ、と天馬は思った。
そうして、見てみぬフリをしようかと思ったが、急に例の気狂いが起こってきて、気がつくと彼は四人の少年を見下ろしていた。
「やあ――」
それまで和気藹々と打っていた四人が、無機質な顔で一斉に天馬を見上げた。気の弱いものならそれだけで怯んでしまうところだが、馬場天馬はその年の春以来その手の圧迫に対して不感症の男になっていた。
「儲かってるかい」
「おまえには関係ねえ――とっとと消えろ」
「寂しいこというなよ。せっかくカモってやろうと思ったのに」
いつの間にか、昼食を食べていた周りの人影が消えている。
上家に座っていた険しい顔をした少年のピアスがキラリと光った。
「賭けねえ麻雀がつまらねえだと? こんな低いレートで賭けも糞もあるか。遊びだよ、こんなもん」
「おまえ――」
「まだ初心者の方がマシだぜ。一生懸命打つからな。そもそも麻雀は賭けには向いてねえんだ。徹夜したって低いレートじゃ一万負けたか勝ったかって勝負だからな。誰もハコテンになんかなりゃしねえ」
どけ、と天馬は足元の茶髪の少年を押しのけて座った。三人の視線が天馬を刺した。
「最近びくびくしなくなったと思ったが、何様になったつもりなんだ、馬場――」とピアスがいった。
「裸にして屋上から晒してやろうか」
「黙ってろ、穴ぼこ野郎」天馬は押しのけた茶髪の首をぐいっと掴んで引き寄せた。
「おい、見てろよ、この手をアガってやる」
「この手を――?」と思わず茶髪は怪訝な顔をした。だってその手は、
「賭けねえ麻雀なんか面白くねえよ。調子に乗った初心者が来たらカモってやろうぜ」
渡り廊下でマットを広げている同級生たちがそう嘲笑ってはしゃいでいるのを見て、ふむ、と天馬は思った。
そうして、見てみぬフリをしようかと思ったが、急に例の気狂いが起こってきて、気がつくと彼は四人の少年を見下ろしていた。
「やあ――」
それまで和気藹々と打っていた四人が、無機質な顔で一斉に天馬を見上げた。気の弱いものならそれだけで怯んでしまうところだが、馬場天馬はその年の春以来その手の圧迫に対して不感症の男になっていた。
「儲かってるかい」
「おまえには関係ねえ――とっとと消えろ」
「寂しいこというなよ。せっかくカモってやろうと思ったのに」
いつの間にか、昼食を食べていた周りの人影が消えている。
上家に座っていた険しい顔をした少年のピアスがキラリと光った。
「賭けねえ麻雀がつまらねえだと? こんな低いレートで賭けも糞もあるか。遊びだよ、こんなもん」
「おまえ――」
「まだ初心者の方がマシだぜ。一生懸命打つからな。そもそも麻雀は賭けには向いてねえんだ。徹夜したって低いレートじゃ一万負けたか勝ったかって勝負だからな。誰もハコテンになんかなりゃしねえ」
どけ、と天馬は足元の茶髪の少年を押しのけて座った。三人の視線が天馬を刺した。
「最近びくびくしなくなったと思ったが、何様になったつもりなんだ、馬場――」とピアスがいった。
「裸にして屋上から晒してやろうか」
「黙ってろ、穴ぼこ野郎」天馬は押しのけた茶髪の首をぐいっと掴んで引き寄せた。
「おい、見てろよ、この手をアガってやる」
「この手を――?」と思わず茶髪は怪訝な顔をした。だってその手は、
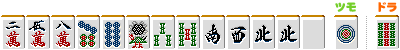
という有様だったから。この手をまとめるのは無理かな、と茶髪は思っていた。親番でもないし無理することはない。
「バカいうな――」と天馬は笑った。
「どんな手でもやれることをやんだよ」
そういってバシッと二萬を叩き切った。続いて八萬。五萬。親番のピアスが嫌そうな顔を見せた。
流局間際、天馬はツモ牌を置いて静かに手牌を開けた。
「バカいうな――」と天馬は笑った。
「どんな手でもやれることをやんだよ」
そういってバシッと二萬を叩き切った。続いて八萬。五萬。親番のピアスが嫌そうな顔を見せた。
流局間際、天馬はツモ牌を置いて静かに手牌を開けた。
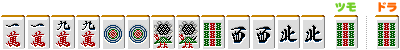
「ツモ。三千六千だな。ふん、ま、ツモがよかっただけだが、親は国士、染め手傾向の南家を警戒せざるを得ないし、早いリーチがかかっても字牌でしのげる。なによりアガれば高い。な? ピンフなんかに持ってかなくてよかったろ」
茶髪はぐうの音も出ずに沈黙していた。すっと天馬が立ち上がった時、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
ピアスも同時に立ち上がり、腰の入った一発を天馬にぶちかました。
どう、っと天馬がリノリウムに倒れこみ、茶髪がびっくりしたように身をすくめた。
「偉そうに麻雀講座ができてよかったな、馬場。でも麻雀じゃ身を守れないぜ」
「そうだな――」と天馬は口元の血を拭って身体を起こした。笑っている。
「だからおまえも、最初からこうすればよかったんだ。麻雀はおまえには難しすぎるよ。大勢で囲んで小銭をむしってるのがおまえにはお似合いさ。一生そうやって地べたを這い回っているといい」
「てめえ――」とピアスが拳を振り上げた。
どど、と駆け足でその場に白垣真が現れ、全員ぴたっと動きを止めた。
「やあやあ、揉め事だっていうから授業をサボって駆けつけたよ」
「おい白垣、おまえ会長のくせにそんなことしていいのかよ」と天馬。
「いいのさ。だって僕は会長だもの。――三村、すまないね、馬場が何かまたひねたことをいったんだろう」
ピアスこと三村は拳を開き、天馬から一歩離れた。
「会長、このブタに二度と人間様に口答えするなってしつけてくれよ。胸糞悪くて仕方ねえ」
「三千六千で腹を立ててるからいつまで経っても麻雀が上手くならねえんだ」
「なんだと!」
そのやり取りで白垣は事のおおよそを察知したらしい。また拳を天高く突き上げかけた三村と天馬の間に割って入り、どうどうと手で二人を押さえ、
「そんなに話がこじれちゃったんなら、麻雀で勝負をつければいいじゃないか」
といった。
もうすぐ夏休みが始まる、暑くけだるい午後だった。
「――ということになったんだ」
「天馬」
「なんだい」
「バカじゃないんですか?」
「おう、そこがオレの――」
「いいところ、でしょう。聞き飽きました、このバカ」
そういって加賀見空奈はいつもよりやや早い仕草で弁当を突き始めた。卵焼きがするすると口の中に消えていく。
例の一件から一日明け、今日から夏休みであった。放課後であったが二人は居残って屋上で昼食を採っている。ペントハウスの陰にいればそれほど暑くもない。冷えたコンクリートが心地よいくらいであった。
「誰がどんな麻雀を打とうが放っておけばいいでしょう。何もわざわざ自分から喧嘩を売るなんて、自業自得です」
「別に。ただ苦しそうな手牌のやつがいたから代打ちしてやっただけだ。むしろあの茶髪には感謝してほしいくらいだぜ」
ごくっ、と天馬は水筒のお茶を飲んだ。
「で、カガミ、おまえも来るか。楽しいぜ。レートはリャンピン(千点二百円)だ。小遣い稼ぎにゃちょうどいいだろ」
「犯罪ですよ、そのレートからは」
「白垣んちでやるから治外法権さ。麻雀打ちにいくんだか、あいつんちにクーラー浴びにいくんだかわかんねえや」
巷の雀荘はたいてい千点五十円から百円が普通である。そこまでは慣習として見逃されるが、二百円からは警察が摘発することもあるという。順位点がワンツーの場合、ハコって一万円が出て行く計算となる。ワンゲームだけなら遊びで済むが、
「三日間、寝ずに食わずのデスマーチだ。体力勝負になるかもな」
三日も連続敢行すれば負け頭の損失がどれほどになるか、高校生の財布の事情からすれば決して笑える額ではなくなってくる。
カガミは額を押さえて頭を振った。
「負けたお金はどこから出てくるんですか。天馬、働いてないでしょう」
「勝つから平気だよ」
「私、貸しませんよ」
「うん、わかってる。貸してくれるっていっても突っ返すさ」
「だから」カガミは空になった弁当箱を見つめている。「負けたらどうするのって聞いてるんです」
天馬は黙った。
「殺されることはなくたって、あなたが負けて殴られたりするのは嫌です」
「じゃ、こうしよう。オレは負けがひどくなったら白垣に頼んでこっそり逃げ出す」
「本当ですか」
「ああ――最悪の時はな」
カガミは、ふう、と息をついて空を見上げた。からりと晴れた不気味なほど青い空だ。
「わかりました。好きにしてください」
「言われなくてもそうする。ってわけで、悪いな、しばらく一緒にいられない」
そういってカガミの目を見た時、ずきっと天馬の胸が痛んだ。殴られるよりもひどかったが、いまさら勝負から退くわけにもいかない。
(今回限りで、麻雀なんかやめよう。こいつと一緒にいる方がいい)
実際に、天馬は近頃ほとんど打つことがなかった。たまり場にしている生徒会室でもケンに回ることが多く、風邪でも引いてるんじゃないかと噂されていた。
それがどういうわけか、今回に限って、性欲にも等しい麻雀への欲求が湧いてきたのだ。
なぜだかわからない、しかし打たねばならない気がした。
誰かに呼ばれているような、そんな気がして――
「天馬」
不意に呼ばれて振り返ると、カガミが手を前で組んでじっと俯いていた。夏の日差しを頭からかぶって、その輪郭がぼやけている。
「どうした?」
「――なんでも、ない、です」
天馬には彼女のかすかな表情の変化が読み取れる。しかしその日のそれは、彼にも判断つきかねる無色の顔だった。
茶髪はぐうの音も出ずに沈黙していた。すっと天馬が立ち上がった時、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
ピアスも同時に立ち上がり、腰の入った一発を天馬にぶちかました。
どう、っと天馬がリノリウムに倒れこみ、茶髪がびっくりしたように身をすくめた。
「偉そうに麻雀講座ができてよかったな、馬場。でも麻雀じゃ身を守れないぜ」
「そうだな――」と天馬は口元の血を拭って身体を起こした。笑っている。
「だからおまえも、最初からこうすればよかったんだ。麻雀はおまえには難しすぎるよ。大勢で囲んで小銭をむしってるのがおまえにはお似合いさ。一生そうやって地べたを這い回っているといい」
「てめえ――」とピアスが拳を振り上げた。
どど、と駆け足でその場に白垣真が現れ、全員ぴたっと動きを止めた。
「やあやあ、揉め事だっていうから授業をサボって駆けつけたよ」
「おい白垣、おまえ会長のくせにそんなことしていいのかよ」と天馬。
「いいのさ。だって僕は会長だもの。――三村、すまないね、馬場が何かまたひねたことをいったんだろう」
ピアスこと三村は拳を開き、天馬から一歩離れた。
「会長、このブタに二度と人間様に口答えするなってしつけてくれよ。胸糞悪くて仕方ねえ」
「三千六千で腹を立ててるからいつまで経っても麻雀が上手くならねえんだ」
「なんだと!」
そのやり取りで白垣は事のおおよそを察知したらしい。また拳を天高く突き上げかけた三村と天馬の間に割って入り、どうどうと手で二人を押さえ、
「そんなに話がこじれちゃったんなら、麻雀で勝負をつければいいじゃないか」
といった。
もうすぐ夏休みが始まる、暑くけだるい午後だった。
「――ということになったんだ」
「天馬」
「なんだい」
「バカじゃないんですか?」
「おう、そこがオレの――」
「いいところ、でしょう。聞き飽きました、このバカ」
そういって加賀見空奈はいつもよりやや早い仕草で弁当を突き始めた。卵焼きがするすると口の中に消えていく。
例の一件から一日明け、今日から夏休みであった。放課後であったが二人は居残って屋上で昼食を採っている。ペントハウスの陰にいればそれほど暑くもない。冷えたコンクリートが心地よいくらいであった。
「誰がどんな麻雀を打とうが放っておけばいいでしょう。何もわざわざ自分から喧嘩を売るなんて、自業自得です」
「別に。ただ苦しそうな手牌のやつがいたから代打ちしてやっただけだ。むしろあの茶髪には感謝してほしいくらいだぜ」
ごくっ、と天馬は水筒のお茶を飲んだ。
「で、カガミ、おまえも来るか。楽しいぜ。レートはリャンピン(千点二百円)だ。小遣い稼ぎにゃちょうどいいだろ」
「犯罪ですよ、そのレートからは」
「白垣んちでやるから治外法権さ。麻雀打ちにいくんだか、あいつんちにクーラー浴びにいくんだかわかんねえや」
巷の雀荘はたいてい千点五十円から百円が普通である。そこまでは慣習として見逃されるが、二百円からは警察が摘発することもあるという。順位点がワンツーの場合、ハコって一万円が出て行く計算となる。ワンゲームだけなら遊びで済むが、
「三日間、寝ずに食わずのデスマーチだ。体力勝負になるかもな」
三日も連続敢行すれば負け頭の損失がどれほどになるか、高校生の財布の事情からすれば決して笑える額ではなくなってくる。
カガミは額を押さえて頭を振った。
「負けたお金はどこから出てくるんですか。天馬、働いてないでしょう」
「勝つから平気だよ」
「私、貸しませんよ」
「うん、わかってる。貸してくれるっていっても突っ返すさ」
「だから」カガミは空になった弁当箱を見つめている。「負けたらどうするのって聞いてるんです」
天馬は黙った。
「殺されることはなくたって、あなたが負けて殴られたりするのは嫌です」
「じゃ、こうしよう。オレは負けがひどくなったら白垣に頼んでこっそり逃げ出す」
「本当ですか」
「ああ――最悪の時はな」
カガミは、ふう、と息をついて空を見上げた。からりと晴れた不気味なほど青い空だ。
「わかりました。好きにしてください」
「言われなくてもそうする。ってわけで、悪いな、しばらく一緒にいられない」
そういってカガミの目を見た時、ずきっと天馬の胸が痛んだ。殴られるよりもひどかったが、いまさら勝負から退くわけにもいかない。
(今回限りで、麻雀なんかやめよう。こいつと一緒にいる方がいい)
実際に、天馬は近頃ほとんど打つことがなかった。たまり場にしている生徒会室でもケンに回ることが多く、風邪でも引いてるんじゃないかと噂されていた。
それがどういうわけか、今回に限って、性欲にも等しい麻雀への欲求が湧いてきたのだ。
なぜだかわからない、しかし打たねばならない気がした。
誰かに呼ばれているような、そんな気がして――
「天馬」
不意に呼ばれて振り返ると、カガミが手を前で組んでじっと俯いていた。夏の日差しを頭からかぶって、その輪郭がぼやけている。
「どうした?」
「――なんでも、ない、です」
天馬には彼女のかすかな表情の変化が読み取れる。しかしその日のそれは、彼にも判断つきかねる無色の顔だった。

