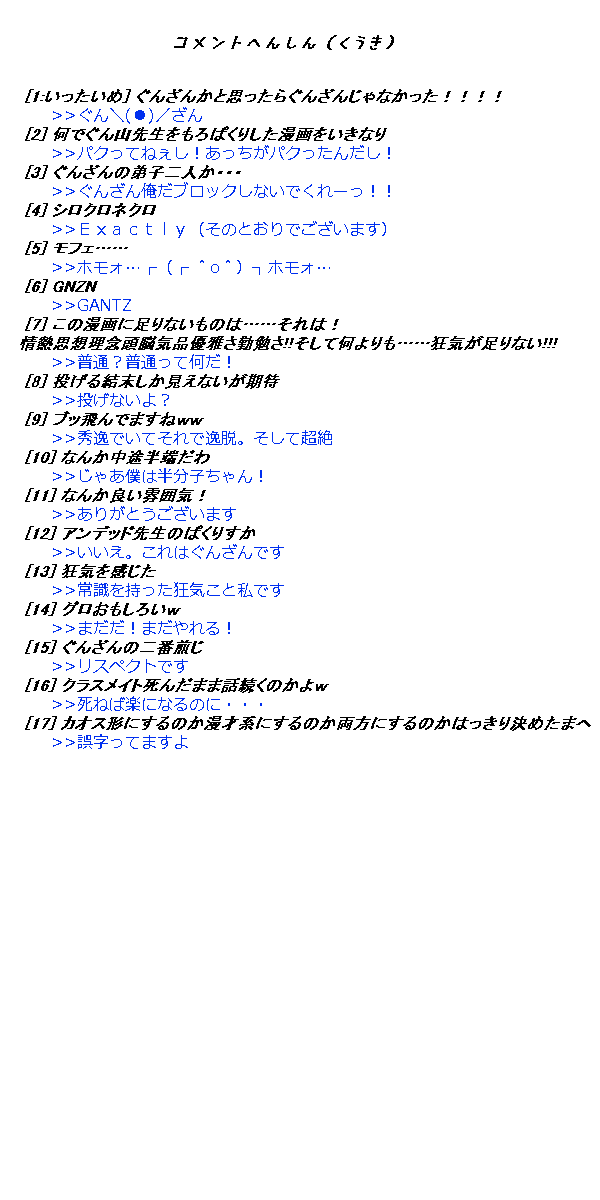あるところに一人の魔女がいました。
魔女は永く、とても永く生きすぎたので毎日が暇まで仕方ありませんでした。
今までなら、新しい魔術の研究や永遠の美の追求について研究していましたがそれも何十、何百年という間に飽きてしまいました。もとより、この魔女は飽きっぽい性格なのでひとつのことが長続きしたためしがないのも暇をつぶせないひとつの理由でした。
「311,040,000、311,040,001、311,040,002」
結果、魔女はその日も暇で暇で「どこまで数字を数えることが出来るか」なんて面白みの無いことをしていました。31,104,000秒が大体一年ですから、365日、閏年を含めずに考えると魔女はもう十年近く数字を数え続けていることになります。
「311,040,011、311,040,012……飽きた」
唐突に言うと魔女は日に当たらずに白くなった細い足を近くの椅子に投げ出し、十年間のいう努力を「飽きた」その一言で片付けてしまう。魔女はそんな人でした。
あるいは、この魔女からすれば今まで生きていた年数から数えてみれば十年なんていうのは一瞬だったのかもしれません。とにかく、数える事をやめた魔女は新しい暇つぶしの方法を考えなくてはならなくなりました。
「ごはん……」
最初に思いついたのは十年ぶりの食事でした。魔女は食べなくても生きていける体でしたが、食べることが嫌いなわけではありませんでした。
「でも面倒」
しかし魔女は面倒くさがりでした。どれくらい面倒くさがりなのかというと、十年も何も食べていないのに面倒の一言で食事を作らないほどの面倒くさがりでした。
「でも久しぶりに料理もしたいわ」
魔女はこの数千年という間に古今東西ありとあらゆる料理をしていました。と、いっても魔女は飢えや渇きからは程遠い存在なので、食べる行為よりも作るということが好きなだけでした。特に食べさせる相手も無く、そして食べる必要も無い。それなのに料理、などと思いついたのはわずかに残っていた魔女の人間らしさかもしれません。
「マーティス」
ふと次に魔女が思いついたのは飼い猫のマーティスのことでした。
「マーティス?」
しかし、マーティスは普通の黒猫でした。
「マーティス……」
魔女は丸々と太り、いつも膝の上でぬくぬくだった、細く冷たくなったマーティスを拾い上げてため息をつきました。餌はあげるのが面倒だからといって開発した魔術器具で自動的に与え続けていたので餓死の心配はありませんでしたが、残念なことにマーティスは普通の猫でした。なので冷たくなっていたのです。
しかし、今回のマーティスは実に恵まれていました。なにせ、まだきちんと形が残っていたのですから。
あるときのマーティスは骨だけになっていました。またあるときのマーティスはガリガリにやせ細っていました。
魔女は実に面倒くさがりだったのです。
「もう走り回ってはくれないのね」
マーティスはもともと走り回るよりはご飯を食べてごろごろとしているのが好きな猫でしたが、それでも魔女はもう走り回る事の出来なくなったマーティスを抱いたままトボトボと裏庭へと続く扉を開けました。
そこに広がっていたのは無数のマーティスと書かれた十字架でした。魔女は十字架の立てられていない一角に行くと、杖を取り出して軽く一振りし小さな穴を掘り、冷たくなったマーティスを横たえさせ魔法で優しく土をかけていきます。魔女はもう何度目になるかわからないマーティスの埋葬式を今回も一人で行います。魔女は千回目まではメモに残していましたが、今はメモをどこかになくしてしまったのでもうこれが何回目かなんて事は覚えていません。
ただ、どんな形になっても必ずマーティス達は最後にはここに連れてこられます。魔女は面倒くさがりでしたが、きちんと自分の決めたルールを守る魔女でした。
「さよならマーティス」
魔女は最後にマーティスのお墓に真っ白な十字架をさし、持っていた杖で「マーティス」と魔法で十字架に刻んでから家へと戻っていきました。
「また一人になってしまったわ」
魔女の言うとおり、部屋にはもう魔女の姿しかありません。愛しのマーティスは土の中。
しかし魔女は寂しがる様子も見せず「お腹が減った」だの「暇だ」などと誰も聞いていないのはずなのにずっと独り言を言っていました。誰も聞いてくれないとわかっていても自分の思っていることを口に出していないと寂しさに耐えられそうに無かったのです。心で思っているだけよりも、声に出して、それが自分の耳に入れば自分だけは聞いているという妙な自信につながっていたのです。
魔女の力をもってすれば永遠の命なんてものも簡単に作れますが、魔女はそれを嫌っていました。尽きることの無い命、終わりの無い人生。
終わりがあるから始まるというのに、終わりを消してしまっては始まる意味があるのだろうか。そう魔女は考えていました。と、言うのも魔女自身が終わりをなくしてしまった存在だったので終わらないという事のつらさは十分にわかっていました。
二人ならこのつらさを解消できるかもしれないと思ったこともありますが、面倒くさがりの魔女にずっとずっとずっと何もいわずについてきてくれる人などきっと魔女が一生かけても見つけることが出来ないだろうとあきらめていました。
「あぁ、愛しのマーティス……マーティス」
そして魔女が望んだのは限りある命。それも何も文句を言わない動物でした。魔女はもともとそういった弱い立場になりたくない。その一心で研究を始めたのでしたが、今ではその弱い弱いものに戻りたいと思うようになっていました。なんとも皮肉なものです。まさに青い鳥は家にいた。というようなものです。
「マーティス」
魔女はふらふらと立ち上がり、部屋のすみにかけてあった十年分のほこりにまみれボロボロになった真っ赤なコートに手をかけ、軽くほこりを払ってからそれを羽織りました。
「チチンプイプイ」
魔女がそうコートに杖を向けてどこかの安っぽい絵本の三流魔女が言いそうな魔法を唱えると、ほこりまみれのボロボロだったコートが新品のようなぴかぴかのコートへとはや変わりしました。
「うん」
魔女はそのほかにも持っていたものに魔法をかけ、その出来を確認するように鏡の前でうれしそうにうなずいてから家から出ました。
魔女が身に着けたのは真っ赤なコートに真っ赤なハイヒール。サングラスにブランド物のバッグ。もはやこれでは「魔女」というより「悪女」といったいでたちで魔女は愛車へと歩み寄っていきました。
魔女の愛車はコートと同じ真っ赤なスポーツカーで、ここだけ見るともはやこの魔女が魔女だなんてことはひとかけらも思うことが出来ません。ただ、その異常なほどに透き通った美しい白い肌と、蟲惑的なまでに真っ赤な口紅、そして整ったプロポーションと腰まで伸びた吸い込まれるような漆黒のストレートを見れば、「魔法でもかけられたように美しいな」とは思うかもしれません。ただそれだけです。
「さて」
十年間自分の部屋以外の世界を見ていなかったかので、魔女はいったいどんな変化があったのだろうかと少しわくわくしていました。
「馬車が車になってたときくらいの面白いことは無いかしら」
魔女は今乗っている車というものが発明されたときのことを思い出し、少し笑ってからまた考え込みました。
「でも、あの災害のときのようにボロボロになった街を見るのは面白くなさそうね」
今度はため息をつきながら昔見た瓦礫の町を思いだしました。
走る道は整地などされていない山道。それにもかかわらず魔女のスポーツカーは大きなゆれを見せることなくすいすいと走っていました。普通なら通れるはずの無い木々の間も難なく猛スピードで駆け抜けていきます。それは、魔女のドライブテクニック云々より木々達が、土達が魔女のために道を作っているかのようでした。と、いうより実際そうでした。魔女が近づけ付けば木はその根っこごと道を譲り、道端に転がる大きな石もするすると横によけていきます。そして魔女が通り過ぎればまた最初の位置へと戻っていくのです。魔女がよければいいのですがそれを魔女は嫌がりました。
なぜなら魔女は面倒くさがりだったのです。
「遠野さん! 遠野さんじゃないですか!」
町についた魔女はしばらくの間あたりを観光がてらにとぶらぶらとしていましたが、一人の青年の声でその足を止めました。
「覚えていますか遠野さん。僕ですよパン屋の息子のコリンです」
魔女を遠野と呼んで笑いかけたのは、魔女より少しだけ大きな青年でした。青年は、魔女を見てたいそう興奮した様子で話しかけていましたが、魔女は思い出せないといった様子で首を傾げました。
するとコリンと名乗った青年は残念そうにため息をつき、「じゃあ、あの約束も覚えていないんでしょうね」といって魔女に背を向けました。
魔女はやっぱり思い出せなかったようでしばらくその場でうんうんとうなっていました。何せ十年も前の話ですので魔女の記憶には新しいはずなのですが、数をずっと数えていたせいか余計なことは忘れてしまったようだったのです。しかし、コリンの悲しそうな顔を見たら、魔女は本当にコリンが余計なことだったのだろうかと思い始めたしまったのです。
「あぁ、あれね」
魔女は唐突にポンと手を叩き、何度もうなづきましたが、それ以上は何もしませんでした。ただ、クスリと微笑んでからまた歩き出しました。もちろん、コリンを探すことはしませんでした。なぜなら魔女は面倒くさがりだからです。
「すいません。子猫を一匹売ってもらいたいのですが」
魔女は一軒のペットショップにより、そこで黒い子猫を飼いました。途中、お金を払おうと思って十年前の紙幣を出したところ「革命がおきたからそんな古いお金は使えない」といわれてしまいましたが、魔女が杖を一振りすると使えなかったお金は使えるお金にかわりました。店主は目を天にして驚きましたが、魔女が「どうですか? 私のマジック」というと「すばらしい。いい物を見たからこのボールを一緒につけて差し上げます」と子猫と一緒にボールをくれました。
「得しちゃったわね」
魔女はうれしそうに黒い子猫を抱え真っ赤なスポーツカーへと戻っていきました。子猫の名前はもう決まっています。
マジで生きた
しんだ