賭博神話ゼブライト
09.ALL I NEED IS...
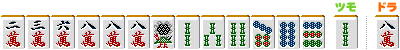
南一局、二本場――七順目。
シマの手である。何を切るか。
もっともテンパイ枚数が多いのは六萬切り。テンパイ受け入れは一二三四萬、一二三五索。
ペン三索待ちになると苦しいが、親番であり、即リーをかければ三者ベタオリもありえる。それでツモればなおよし。
現在、シャガは残り一七〇〇点。
ツモれば容赦なくハコテンである。四回戦の装弾数は四発。
三分の二で死ぬ、あいこで負けるじゃんけんを課せられることになる。
(親だし、ここはテンパイを優先して打六萬かな――)
そう雨宮が結論づけたのを待ち構えていたかのように、止まっていたシマの指が閃いた。
打、一索。
ふ――と雨宮は息をついた。
シマも人が悪い。
打六萬では最終テンパイは役なし確定。リーチしなければ出アガリできない。
どの道シマがこの打点をテンパイすればシャガは絶対絶命だが、リーチとくればシャガはオリて流局か、あるいは全面抗争に踏み出てシマとリーチを打ち合い、シマの待ちがペン三索あたりの愚形なら打ち勝つことも難しくない。
リーチをかければ、もはや奇襲はできない。
ヤミテン一二〇〇〇を狙えるのは、一索打ち出しの――
シマの細長い指先が、ツモ牌をそろそろと露にしていく。
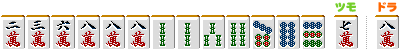
――七萬引き、一四萬待ちのピンフ――
当然、牌を曲げるそぶりさえない。打二索。
勝ったな、と雨宮は思った。
この流れでは振るのはおそらく――
そのとき、シャガにはもうとっくに怜悧な思考は残っていなかったのかもしれない。
ただ自分の中に流れる何かに従っていただけで。
打、一萬――あっけない、だがそれも博打の一面だ。いや、それこそが、というべきだろう。
どんなにがんばろうと、どんなに美しかろうと、負けるときは負ける。ドラマティックな展開などありはしない、笑ってしまうほど無様にだ。
神と同列に扱われた少女の最期はまァ、病死ではなく戦死に終わっただけマシというところだろう。
だがこの時、シマあやめに見えていたのは、
そんな結末ではなかったのだ。
シマ、動かず。
烈香がツモる。ツモ切り。
さくみがツモる。一萬あわせ打ち。同順フリテンでアガれない。
シマがツモる。北ツモ切り。
雨宮、ただただ呆然――。
なぜ、勝利を見逃す。なぜ。
四回戦を引き伸ばすことに意味なんてない。これは千点いくらのレート麻雀ではない、誰かが死に絶えた時、そいつの亡骸を残った三人で喰い合う麻雀。
雨宮は眼球だけめぐらせて、シマの横顔に答えを探す。
情けをかけているのか、この哀れな最後の殉教者に。
だとしたらシマ――雨宮の顔から表情が消えていく。
負けるのは、きっとおまえだぜ。
そんな優しさなんて持つ資格、
おまえにはないんだから。
「ロン」
「――ピンフ、ドラ3。一二〇〇〇は一二六〇〇」
さくみはびっくりしたようにぱちぱちと瞬きをした。
一萬のトイツ落としを狙われた形だったのだが、当然彼女も気づいている。シマの北がツモ切りであったことを。
シャガを殺せていたことを。
「おまえ、何がしたいんや――」
衝撃覚めやらぬさくみの問いに、シマは伏せていた顔を持ち上げた。
これが本当にさっきまでへらへら笑い呆けていた少女と同一人物なのだろうか。
檻のように垂れた前髪の奥で、燦々と輝く瞳から、誰も視線を逸らせない。縛られたように。
「何ってもちろん」
嗤う。
「勝ちにいくんだ」
おまえにとって――勝つとはなんだ。
なんなんだ。
いったいおまえには、何が視えているんだ。
雨宮はその問いを、とうとう胸に仕舞いこんだまま、封印してしまった。
どうせわかりはしないのだ。自分にも、誰にも。
わかったなどと自惚れることこそ、おこがましいのだ。
人の心なんてものは……。
シマが放り上げた百点棒が月に重なり、重力の糸に引かれて堕ちる。
点棒の尻が卓を叩いたのを合図に、四人の手が、牌の残骸にぬうっと伸びた。
南一局、三本場。
当然、牌を曲げるそぶりさえない。打二索。
勝ったな、と雨宮は思った。
この流れでは振るのはおそらく――
そのとき、シャガにはもうとっくに怜悧な思考は残っていなかったのかもしれない。
ただ自分の中に流れる何かに従っていただけで。
打、一萬――あっけない、だがそれも博打の一面だ。いや、それこそが、というべきだろう。
どんなにがんばろうと、どんなに美しかろうと、負けるときは負ける。ドラマティックな展開などありはしない、笑ってしまうほど無様にだ。
神と同列に扱われた少女の最期はまァ、病死ではなく戦死に終わっただけマシというところだろう。
だがこの時、シマあやめに見えていたのは、
そんな結末ではなかったのだ。
シマ、動かず。
烈香がツモる。ツモ切り。
さくみがツモる。一萬あわせ打ち。同順フリテンでアガれない。
シマがツモる。北ツモ切り。
雨宮、ただただ呆然――。
なぜ、勝利を見逃す。なぜ。
四回戦を引き伸ばすことに意味なんてない。これは千点いくらのレート麻雀ではない、誰かが死に絶えた時、そいつの亡骸を残った三人で喰い合う麻雀。
雨宮は眼球だけめぐらせて、シマの横顔に答えを探す。
情けをかけているのか、この哀れな最後の殉教者に。
だとしたらシマ――雨宮の顔から表情が消えていく。
負けるのは、きっとおまえだぜ。
そんな優しさなんて持つ資格、
おまえにはないんだから。
「ロン」
「――ピンフ、ドラ3。一二〇〇〇は一二六〇〇」
さくみはびっくりしたようにぱちぱちと瞬きをした。
一萬のトイツ落としを狙われた形だったのだが、当然彼女も気づいている。シマの北がツモ切りであったことを。
シャガを殺せていたことを。
「おまえ、何がしたいんや――」
衝撃覚めやらぬさくみの問いに、シマは伏せていた顔を持ち上げた。
これが本当にさっきまでへらへら笑い呆けていた少女と同一人物なのだろうか。
檻のように垂れた前髪の奥で、燦々と輝く瞳から、誰も視線を逸らせない。縛られたように。
「何ってもちろん」
嗤う。
「勝ちにいくんだ」
おまえにとって――勝つとはなんだ。
なんなんだ。
いったいおまえには、何が視えているんだ。
雨宮はその問いを、とうとう胸に仕舞いこんだまま、封印してしまった。
どうせわかりはしないのだ。自分にも、誰にも。
わかったなどと自惚れることこそ、おこがましいのだ。
人の心なんてものは……。
シマが放り上げた百点棒が月に重なり、重力の糸に引かれて堕ちる。
点棒の尻が卓を叩いたのを合図に、四人の手が、牌の残骸にぬうっと伸びた。
南一局、三本場。

