T=〃レヽ∋ωゎ
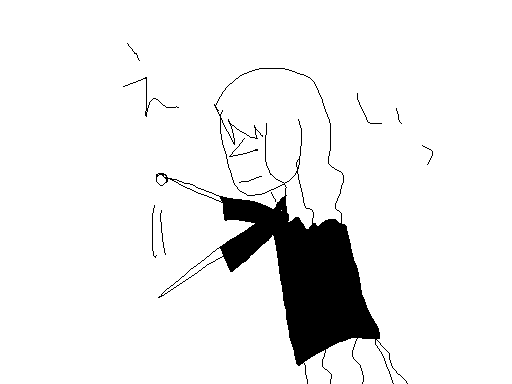
そのとき、僕は初めて『頭の中が真っ白になる』という現象を体験した。
圧力の無い突風が全てを吹き飛ばしてしまったような。巨大な滝に打たれ体が霧散し水と溶け合ってしまったような。
梢さんが僕を見ている。梢さんの感情が流れ込んでくる。
彼女に感じた奇妙な一体感。シンパシー。
なんのことはない。
僕と同じだったのだ。梢さんは、あの時からずっと。
僕と同じことを感じ、傷つき、生きてきた。
そして互いをずっと、ずっと愛してきた。
どうすればいいのだろう。
砕けたびい玉を、ヒビ一つ無く澄んだ真球に戻すことは出来るのだろうか。
新しく生まれつつある世界を殺し、再び過去を蘇らせることが。
でもそれはきっと、してはいけないことだ。
一度崩れたものは二度と元通りにはならない。
どこかで必ず、致命的なひずみが生まれてしまうから。
そんなこと、嫌というほど知っている。
だから―――
「気の迷いです、それは」
梢の目を見据えたまま、言った。
目を逸らすことは出来なかった。何があっても、自らの気持ちを覚られてはいけないと思った。
「違うわ」
はっきりと梢は否定した。巳貴は首を振り、
「あなたが見ているのは6年前の俺です。こんなこと言いたくないけど、それでも言います」
無意識に手を握る。不思議と汗は滲まなかった。
「梢さんが俺に抱いている感情は、過去への妄執です。愛とか恋とか、そういう類のものじゃない」
「違う。私は『あなた』を見てるんだわ。過去や現在なんて――――そんなの関係ない」
「あの幸せに溢れた時間と、別れの痛みが心に焼き付いて・・・錯覚しているだけです」
胸が痛んだ。確かな痛みを感じた。
茫洋とした、気味の悪い感触だった。
「だから、あなたはそんな事を言っちゃいけない。俺なんかを気にするのは馬鹿げてます」
「どうせ私は馬鹿よ!」
思わず大声が出た。唇が震えた。目の奥が熱を持つ。それでも梢は下を向かなかった。
「私だってわかってるの。結婚するんだもの。こんなところに来て良いはずが無い。あなたに会いたくて、我慢できずに。そんなの許されない。あの人を愛していないなんて、そんなこと―――」
息が詰まる。
「どうして・・・」
どうして言ってしまったのか。どうして巳貴がこんなにも愛しいのだろう。
6年という月日は、人の心を変えるには十分な時間だ。特に十代の彼らにとって、それは途方も無く長い。それこそ子供から大人へと変貌するほどに。
その一瞬毎で消えていく未来、感情、記憶。そして生まれる新たな瞬き。全てが混沌と渦巻き流れ弾ける中で、わけもわからず、しかし確実にその想いだけは消えずに残っていた。
「言い訳なんて出来ない。許してもらおうとも思わない」
今、私は何を言っているのだろうか。何を言おうとしているのだろうか。
梢にはわからなかった。
ただ、巳貴が好き―――。
その一点で思考は止まり、しかし振り返ることも無く、行くあての無い憐れな言葉だけがひたすら増殖を続ける。
「取り戻したいのよ、私は。あの頃、当たり前に存在していた温もりを。匂いを、光を」
幼い頃の休日。カーテンの隙間から差し込む穏やかな朝陽。身体を包む布団はひたすらに柔らかくて、頬を撫でる髪が金色に輝き、母の操る包丁がリズミカルにまな板を叩く。その音を聞きながら、呟く。「ああ、きっと今日も素晴らしい一日になるんだわ」―――
ふと、あまりにも懐かしい光景が脳裏をよぎり、ぎくりとした。
「無理ですよ」
梢の動揺を突くように、巳貴は言い放った。
「終わってしまったんです。壊してしまったんです。僕が、あの時」
梢を拒絶したあの瞬間、選択してしまった。確かに在ったであろう、二人が共に生きられる路を捨て、決して交わることの無い丁字路を。
「そんなことない。終わってなんかいない」
梢は頑なだった。混乱しきった頭のなかで、それでも今目の前に巳貴がいる。それが全てだった。
「だって、私たちはまた逢えたじゃない。昨日あなたがあの公園を通らなければ、再会することなんてなかった。そうしたら私はきっと諦めて帰っていたわ、あの人の所へ」
本当にそうだろうか。せめて巳貴を一目見ようと、彼の家まで行ってしまったのではないだろうか。
ふと浮かんだそんな考えを振り払うように、小さく頭を振る。
「でも、あなたは居た。奇跡のようなタイミングで、あそこに―――」
「逢っただけです」
力を入れすぎた拳は、既に真っ白だった。ぎりぎりと心臓が捻り潰されようとしている。まるで、自らの握り固めた拳が直接心臓を締め付けているかのように。
「そこから先に繋がる路は無いんですよ。たまたま僕たちは交差してしまったけれど、向かっている先は全くの別方向なんです」
一昨日までの世界が嘘のようだった。もう、まるで変わってしまっている。何もかもが。
こんなにも梢を愛していたなんて、知らなかった。知る必要も無かった。
「だから立ち止まらないでください。振り返らないで下さい。あなたは幸せになるんだ。幸せになれるんだ。このまま、僕のことなんか綺麗さっぱり忘れてあなたの場所へ帰ってください。それが一番です。そうでなければいけないんです」
声が掠れた。咽喉が渇ききっている。巳貴は指先の震えを覚られないよう慎重に、ティーカップへ手を伸ばした。
効き過ぎた冷房のためか、血管ごと拳を握っていたためか、或いはその両方かもしれない、すっかり冷え切った巳貴の手を、唐突に暖かい何かが包む。
引きつったように、思わず巳貴は身を硬くした。
梢の手だった。巳貴の目を真っ直ぐ見つめたまま、梢の両手が、巳貴の半端に差し出された右手を握っている。
その貌からは、梢が今何を思っているのか見当もつかない。
無表情、というわけではなかった。その逆―――行き場の無いあらゆる感情が梢の中で爆発し、混ざり合っていた。
シャボン玉のような危うさが瞳の奥で揺れている。
「あなたの言うとおりなのよ、きっと。でも駄目なの。もう気付いてしまったから」
握る手に力が入る。
指が擦れ、左薬指に嵌められた指輪の感触がありありと感じられた。
ほんの何十時間か前まで、それは近い将来訪れるはずの幸せを象徴する存在だった。
生涯の伴侶として自らを選んでくれた男の愛が詰まった、かけがえの無い宝物。
かすかな違和感を抱きながらも、梢は確かにその指輪を、それが意味するものを受け入れていた。
しかし今はもう、梢の体温を吸ってほのかに熱を帯びているはずの指輪は何故か、恐ろしく冷たいのだった。
どうしようもなく愚かで、醜く、なにもかもを裏切ろうとしている自分を罰するための剣のように。
―――きっと私は全てを失うだろう。
梢は確信していた。
婚約者を裏切るような人間を、巳貴が愛してくれるはずなどない。あの人を捨て、巳貴には愛想を尽かされ、その後には何も残らない。
それでいいと思った。ほかに方法が無かった。
「私はたぶん一生かかっても、あの人を、あの人が思うような形で愛せない。だってあの人を見る度に私はあなたを思い出してしまうもの。彼があなただったら良かったのにって、絶対にそう考えてしまうわ。だから、もう駄目なのよ」
「そんな簡単に言わないで下さい」
巳貴は梢の手を振り払おうとしたが、力が入らなかった。
今このつながりを断ってしまったら、永遠に戻らない。そんな気がした。
手遅れなのだろうか。
もう後戻りできないところまで、事態は進んでしまったのか。
たとえそうだとして、巳貴に何が出来るのだろう。
わからなかった。
巳貴には、何も。
夏の強い日差しが目に痛い。
すっかり冷めてしまった紅茶を一口に飲み干し、「出ましょう」と梢は言った。
穏やかで心地よいこの店の雰囲気を自分が台無しにしているような気がして、急に居たたまれなくなったのだった。
店を一歩出たところで、手で傘を作り、通りの先にある公園の鮮やかに茂った木々を眺める。全てが眩しくて、清々しくて、しかし梢は全く高揚を覚えなかった。見せ付けられているように思えた。惨めだった。
「日傘、差さないんですか」
心配そうに、巳貴が言う。
日光を反射し輝く梢の真っ白な肌はこれ以上ない程に美しかったが、同時に堪らなく痛々しく巳貴の目には映った。
「日傘」
―――あの人からのプレゼントだ。白い肌の女が好きなあの人が私にくれた、最初の贈り物。
瞼が弱々しく痙攣した。「梢にはいつも綺麗でいて欲しいからね」そんな言葉が蘇る。
目頭を押さえ、静かに深呼吸した。
「差さないわ。必要ないもの」
梢の口調に頑ななものを感じ取り、巳貴は「そうですか」とだけ言った。
これから梢はどうするつもりなのだろう。
出来ることなら、今すぐにでも婚約者の所へ帰って欲しかった。
それは梢との断絶を意味するのだろうが、それでも願わずにはいられない。
梢が、幸せであるようにと。
しかし彼女は言ったのだ。
巳貴のいない幸せなど無いのだと。巳貴がいて、初めて梢の幸せは成立するのだと。
嬉しかった。それはもう、掛け値なしに。
だがその言葉を利用できるほど巳貴は大人ではなかったし、また無邪気に受け入れられるような幼さも残っていなかった。
閉塞している、と思わずにはいられなかった。
「少し、歩かない?」
巳貴に背を向けたままで、梢が呟く。
「ええ」
行く当てなど無かった。ただこの混乱しきった現状を打破すべく―――出口の無い迷路の出口を探すがごとく―――とにかく動かなければ湧き上がる焦燥に狂ってしまいそうだった。
先を歩く梢の歩調はしっかりしていたが、どこか上の空だった。空いている左手の指を、しきりに動かしている。
指輪を気にしているのだ、と巳貴は気付いた。親指で薬指の腹をさすっている。
意識しているのかいないのか、巳貴にはわからなかったが、ひどく不安定に見えた。
気付けば、あの公園にいた。柔らかい土に薄く芝生の生えた広場は、舗装された道路よりも遥かに涼しかった。
はっとしたように梢が立ち止まる。
そこはまさしく2日前、巳貴と再会した場所だった。こんなところに来るつもりなど無かったのに。
「ねえ、巳貴くん」
梢は振り向けなかった。これから訊こうとしている事はあまりにも最低で、巳貴がどんな反応を示すかと怖れていた。
「なんですか」
しかし、抑えきれなかった。どうしても訊きたかった。たとえどんな答えが返ってこようとも。
「巳貴くん」
薬指に嵌められた指輪に右手を伸ばす。外そうと力を込めたが、びくともしなかった。
指輪が意思を持ってそれを拒んでいるかのようだった。
「なんですか」
再び巳貴が言った。やや戸惑いながら。
その低いトーンは、巳貴が怒っているからだと、梢には思えた。でも、と自らに言い聞かせる。顎に力が入り、奥歯が軋んだ。
空を見上げる。気味が悪いほどに青く澄んでいた。
「私のこと、好き?」
するり、と指輪が抜けた。
それまでの抵抗が嘘のように、あっさりと。