第八話「リトルバスターズ」
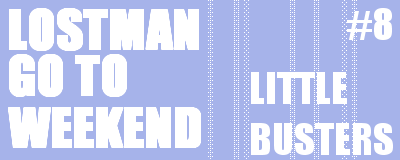
上体を逸らして横薙ぎの攻撃をかわし、返す刀で鳴海は奏汰の腹部に一撃を叩き込む。
宙に叩き上げられた奏汰を見上げ、鳴海は低い姿勢を取り、両手で握り締めたベースを後ろに構え、跳躍する。奏汰へと真っ直ぐ向かう鳴海と奏汰の目が合った。
「っの野郎!」
鳴海の振る一撃に合わせるように、奏汰はギターを振った。宙で重なりあう二つの音と衝撃で、二人は弾き飛ばされ、鳴海は地面に激突する寸前にベースを地面に叩きつけて勢いを殺して着地すると、すぐに顔を上げた。
距離の空いた互いの空間を鳴海は目を細めて見つめる。奏汰もまた、対等に渡り合ってくる彼の姿を見つめていた。あれほど打ち負かされ、顕現されたベースもへし折られ、圧倒的に力量を見せつけたはずなのに、彼は立ち上がってきた。それもさっきとはまるで別人だ。
「ロストマン、だったか。お前はどうして、そうまでして彼女に拘る?」
奏汰の言葉に、鳴海は首を傾げる。
「あいつは現実で成功している。そんな奴がこんなところにいる必要が無いだろう。ここは鬱屈とした感情を抱えている奴らの掃き溜めなんだから」
「……掃き溜め?」
「あいつは現実で飛べる。飛べない俺達とは比べ物にならないくらい遥か遠くに、だ。だから、俺はムーンマーガレットの名を殺すんだ」
「……あんたには、彼女の【音】が聴こえていない」
だから、あんなに寂しくて、刺々しい音が出せるんだ。
そして律花も、きっと自分を隠し続けているから、音が出ないんだ。
鳴海は駆ける。
構えたベースは軽く、一から十まで全てを教えてくれる。どう扱えばどう【鳴って】くれるのかが頭に流れ込んでくる。
これなら、いける。
ギターを構える奏汰に唐竹、右袈裟、左袈裟と次々に斬りこんでいく。リーチの長いベースはギターに比べて少々振りが遅いが、それでも一撃一撃の威力はギターよりも優れているらしい。鳴海から繰り出される攻撃を受け止め、しかし奏汰はじりじりと圧されていく。
「いい加減に、しろぉ!」
逆袈裟を振り上げた隙にギターを順手に持ち替え、奏汰は引き千切るように掻き鳴らす。奏汰を中心に周囲を囲うように音撃が形成される。目の前に迫る衝撃波に鳴海は即座にベースを持ち変えた。
一から十まで、できることは全て分かった。
だから、この【音撃】にどう接するべきかも、鳴海は理解していた。
周囲のブッキングを見ながらずっと思っていたことだ。
何故皆、あんなに音をぶつけ合うのだろう。
音はもっと綺麗にできるものだ。重ねる音を選べばどこまでも透き通った和音にすることだって出来る。
右手の人差指で四弦をハジく。まるでアンプを通したような低音が這いずりまわる。
ベースが生み出す低音は、基本の音。
バスドラムに低音を重ねる。バッキング、リードギター、メロディ。多彩なギターサウンドをバンドとして集約するための核であり、影の薄い裏の功労者。
全ての音を一つに繋げる為に。
あらゆる人を受け止める為に。
鳴海が求めたのは、弾き飛ばす力じゃない。受け止め、調音する力だ。
迫る音撃の波を読み取る。ファズがかったノイジーな音だ。よく聴かないとコードすら分からない程潰れてしまった音。シューゲイズなんてレベルじゃない程の擦れた嫉妬に塗れた音に鳴海は潜り込んでいく。
――潜れ。
――探れ。
――もっと深く。
――もっと探れ。
――彼の音を識れ。
――感覚を尖らせろ。
手にした弦に指を掛け、フレットに左の指を滑らせる。低音から高音へ一度スライド。深い低音が唸る。
探れ。探れ。語らない彼の感情を探って、|コード《苦しみ》を見つけろ。
――ノイズの先の音が聴こえた。
鳴海はベースを鳴らす。
深い低音がギターノイズの中に潜り込む。敵意に満ちたギターサウンドが、彼の目の前で柔らかな和音へと変わっていく。ふわり、とギターからノイズが溶けて消えていく。
奏汰は唖然とした。観衆も、目を疑った。
彼の圧倒的とまで謳われた音撃が、鳴海の音に掻き消されて消えていった。本来ならば弾き飛ばされる筈の彼は、得意気な顔をして、奏汰を見つめていた。
「なんだよ、それ……そんなの俺は、知らない……」
自信を打ち砕かれた事も理由にあった。だが、それ以上に鳴海の基本スペックが奏汰を徐々に上回り始めている。彼のベースが、馴染み始めている。
レモンドロップスはキャンディを舐めながらその光景を見て、ひっそりと笑う。
「なるほど、鳴海君は確かに特殊なプレイヤーだ」
ジョニーは、腕を組みながら鳴海の戦闘を見ていた。弾くのではなく、受け入れる。そんな音撃の出し方を、このモッシュピットで見たのは彼も始めてだった。
「彼は、自分の思い通りにいかない世界との摩擦を解消している。ここに来た時点でね。だからこそ、僕達とは違ってマイナスのない、ゼロのプレイヤーだった」
だから、彼は顕現が出来なかった。ジョニーは目を細める。
「でも今、彼は戦う理由を見つけた。きっとそれは、私達とは違うベクトルの力なんでしょうね。仮に私達が鬱屈とした感情や満たされない焦燥感、言わばマイナスの力を使っているとするなら、彼はプラスの力を使っている」
「だから、弾くことしか出来ない音撃を、無力化できると……そういうわけか」
「無力化、じゃないですよきっと」
ジョニーがレモンドロップスを見た。彼女は舐め終えたキャンディの棒を前に突き出すと、片目を閉じて目を凝らすようにして鳴海に重ねる。
「彼は全部背負うって言った。だから、相手の音を打ち消すなんて、そんなナンセンスなことはしていません」
眉を顰めながらジョニーは再び鳴海を見た。奏汰の音撃に自分の音を当てては和音にして衝撃をかき消している。そうか、と彼は納得するように呟いた。
「彼は、受け止めているのか」
ならばきっと、彼はこのモッシュピットで唯一の異端になるに違いない。
「週末のロストマン、ね」
彼はやはり、ラスト・ホリデイの最大の対抗馬になるかもしれない。
ジョニーは去っていった男の背中を脳裏に浮かべながら、そう思った。鳴海君なら、彼を止められるかもしれない。
身を削り続ける彼の悲しい強さへの執着から、彼を救ってくれるかもしれない、と……。
・
雪彦は、唖然として鳴海を見ていた。戦況をひっくり返した彼の猛攻を見ながら、彼がここへ来る前に言っていた事を思い出す。
――俺は、勝利を諦めない。
彼は追いついたんだ。彼が憧れていた存在と同じプレイヤーの世界へ足を踏み入れ、彼女のピンチに颯爽とヒーローのように立ち臨み、そして今こうして戦っている。
自分もこんな風になれるだろうか。
雪彦は自らの両手を眺める。この手で、もう一度立ち上がって、戦う事が自分にも出来るだろうか。
想いは形に、形は力へと変わっていく。
雪彦の両手の中に、一振りのギターが現れる。黒と白に交互にペイントされたボディのストラトタイプのギター。スクワイア・サイクロン。
鳴海が何もかもを受け止めて戦うと決めたように、自分は彼女の為に強くなりたいと、そう思った。彼に比べたらこれはきっと小さな理由になるだろうか。
それでも、雪彦も、立ち上がろうと思った。
目の前でブッキングに興じる彼を見て、冷め切っていた胸元に、火が灯るのを感じた。
・
奏汰は、律花が嫌いというわけでは無かった。
ただ、自分の挫折と、自分に成り代わろうとする妹の姿が重なって、彼女との接し方がまるで分からなくなってしまっただけだ。自分が出来無かったことを、彼女はいともたやすくこなしていく。
そうして気が付けば、出来る妹に対して奏汰は嫉妬を覚え、嫉妬すればするほど自分が堕ちていくのを感じた。
堕落していく中で見つけたモッシュピットは、とても心地が良かった。
ここでは挫折も関係ない。ひりついた自分の感情をぶつけるだけで世界が反転した。憧れと畏怖、嫉妬。溢れそうなフラストレーションを瓶ごとブチ壊してくれる。
だから、そんな空間に、妹がいることに、彼はとても驚いた。
奏汰に出来なかった事を全て乗り越え、現実で成功を重ねるのに、これ以上何を不満に思っているのか。こんな泥まみれの世界に浸って汚れる必要なんて彼女には無い。
だから、救おうと思ったのだ。
お前の居場所はここには無いと、お前は現実で生きるべきだと。
「なのに、なんでお前は邪魔をするんだッ!」
防戦一方の中に見つけた微かな反撃の機会を奏汰は見逃さない。腹部に叩きつけられ身体をくの字に曲げる鳴海に蹴りの追撃を見舞い、弦を引き千切るように奏でる。
渾身のノイズサウンド。
だがそれを、吹き飛ばされながら低音を鳴らすことで鳴海は和音に変えてしまう。
不思議と彼が中和した音は、奏汰に気分を良く、身体の負担を軽くさせた。良い音だと思った。だが、そんな音では勝てない。
モッシュピットは心を折る戦いなのだから。
「俺の邪魔をするなァ!」ギターを手に奏汰は駆ける。
「てめえの邪魔なんて知るか!」受け身をとった鳴海は叫ぶ。
「何も知らないくせに!」振り被ったギターを弾き飛ばされ、しかし奏汰は構わず空いた手を握り締めると、鳴海の右頬を殴りつける。
殴られた鳴海は、ベースから手を離すと、奏汰の顔面に拳を叩き付けた。
「知らないさ、言わなきゃ何も分からないしどうしようもないだろうがッ! お前がムーンマーガレットに何を思っているかなんて分かるかよ! でも、例えお前が好意で彼女を叩きのめしたとしても、その好意は全く伝わらなかった。だから彼女は泣いたんだ」
視界の端に律花を見た。
彼女は、流した涙を拭って、立ち上がっていた。
「あんたが何をしたいのか、音が教えてくれたよ。でも、そんなひりついた音で何が伝わるって言うんだ。何故彼女の音が出ないのか、その理由を俺はずっと考えてきた。お前は彼女の事を知っているんだろう? なら、なんで彼女の悲鳴を聞かない?」
なあ、律花、お前はなんでそんなに強いのに、ここに来ちまったんだ。
両肩を掴まれ、腹に鳴海の膝がめり込む。迫り上がるような吐き気に奏汰は絞りだすように悲鳴を吐き出す。
「そんな歪みきった音をぶつけあったって、分かり合えるわけがないだろうが! だから俺は、アンタの音を調音する! 吐き出したいほどの想いがあるんなら、もっとハッキリとした音を使って伝えてやれよ!」
そんな事できてたら、苦労しない。
目の前の彼は真剣な眼差しで奏汰の事を見つめていた。自分や他のプレイヤーとは違った、敵意のない、強い眼差し。
顔面に、鋭いのを一発貰った。
そういえば、律花とマトモに話したのは、いつが最後だっただろう。
小さい頃はいつも兄さんと愉しげに後ろをついてきたものだ。
「……兄さん!」
妹の声がして、奏汰は思わず顔を向けた。
キャップ帽を脱いだムーンマーガレット、白部律花の姿をそこに見つけた。
顔を隠すようにしてかぶっていたキャップを右手に持ち、左手には、再び顕現したギターを持っている。一度へし折った筈なのに、ギターは確かにそこに再び存在していた。
月の光を浴びて、真紅に輝くギブソンSG。
「律花……」
「帰ったら、改めてちゃんと話そうよ……兄さん」
そう言って彼女はにっこりと笑うと、ギターを構える。
追撃の為にベースを拾い上げた鳴海は、律花と奏汰の対峙を見て微笑むと、構えようとしていたベースを下ろし、身を引いた。
律花は、ムーンマーガレットは、弦に触れる。一度も出せなかった音撃。どうしてとずっと考えてきたが、答えがどうしても出なかった。けれど、今なら出せる気がした。
私はムーンマーガレットであり、白部律花だ。彼が全てを受け止めようとしたように、私もまた私自身をちゃんと受け入れてあげなくちゃいけない。
好戦的なムーンマーガレットも。
優秀な白部律花も。
受け入れて、一歩前に進みたい。
手にしたピックで六本の弦を垂直に鳴らす。
クランチサウンドのパワーコードが鳴り響き、その音撃は奏汰目掛けて飛んで行く。
奏汰はマスクを外した。
隠した素顔を曝け出した奏汰の表情は、とても穏やかなものだった。
ブッキング結果。
・週末のロストマン○
・デッド・オブ・ナイト●
扉を開けると、そこにはいつもの玄関と、廊下があった。玄関先に靴が二足。父の大きな革靴と、母の小さな靴が左隅に綺麗に並べられている。右から奏汰、律花、父、母と必ず並べられている。いつからだろう。けれど白部家にとってそれは当たり前で、こうして摩擦を感じるようになっても、この並びだけは変わったことがなかった。
律花はしばらく、玄関に足を踏み入れることを躊躇っていた。たった数日、されど数日。自分はこの家を逃げるように出ていった。父に反抗して、学校だって休んでしまった。今までそんな大それたことなんてしたことがなかったから、父がどんな反応をするのか、正直怖かった。
見限られてしまうかもしれないという想いが、何よりも律花の心を縛っていた。
たった一歩が、怖くてたまらなかった。
「律花」
その声に、律花は振り返る。
奏汰はぎこちなく笑って、律花の肩に手をかけると、諦めろ、と言った。でもそれはここ数年の嫌味じみたものではなくて、もっと、幼い頃に見たことのある穏やかな表情だった。
――一緒に怒られてやるから、諦めろ。
ああ、と律花は声を漏らす。そういえば、私が何かしてしまった時、父や母に怒られる時、必ずそばに兄の姿があった。どうして忘れてしまっていたのだろう。
「ねえ」
律花の声に、奏汰がなんだ、と言った。
「……昔みたいに、お兄ちゃんって、呼んでも、いいかな?」
俯いたままぼそり、と律花は言った。恥ずかしくて、奏汰の顔を直視できない。服の裾をぎゅっと握りしめてしまう。落ち着かなくて体を揺らしてしまう。それくらい、律花にとってその一言は照れくさくて、勇気の要る一言だった。
奏汰はしばらくもじもじと動く妹の姿を見ていたが、やがて呆れたように笑うと肩を竦め、彼女の頭を撫でながら、いいよ、と答えた。
久しぶりの手の感触に、律花は心地よさを感じていた。
「律花!」
びくり、と律花は体を硬直させてしまう。とても大きな声だった。ここ数年、そんな張り上げるような声を聞いた覚えがなかった。
律花は恐る恐る、振り返って玄関の先に目を向ける。
そこには、父と母の姿があった。
いつも食卓で憮然としている父の表情が、ほんの少しだけ、怒りに満ちているのが律花には分かった。
もしかしたら、父は普段からこんな風に微かに表情を変えていたのではないだろうか、と律花は彼の姿に怯えながら思った。
何も見ていなかったのは、私も同じなのかもしれない。
父は強い歩調で床を鳴らしながらやってくると、裸足のまま玄関を踏み越えて律花の前にやってくると、彼女の頬を強く打った。
乾いた音と、無音。その後、滲むような痛みが頬に走る。
打たれた頬に手をやりながら呆然とする律花を父はじっと見つめ、それから、彼女の体に腕を回すと、ぎゅう、と強く抱き締める。律花は抱き締められながら、自分の置かれた状況にひどく混乱していた。
手を振り上げる父の姿なんて、想像したことがなかった。
抱きしめられるなんて、予想すらしていなかった。
冷たい目で見られて、終わるだけだと、思っていたのに。
「一体どこに行っていた」
律花は何も言えなかった。何か言おうと思うのだが、喉がぎゅっと堰き止められていて何も出てこなかった。
「一体どこに行っていたんだ」
二度、問いかけられて、律花はあ、と声を漏らした。蛇口を捻るようにして、言葉が生まれる。父の大きな胸に顔を埋めたまま、律花は、自然と湧いてきた一言を、絞りだすようにして、口にした。
「……ごめん、なさい」
どうして今、自分は泣いているのだろう。
どうして、父は抱きしめてくれているのだろう。
父の匂いを嗅ぎながら、律花は堰を切って溢れだした涙を嗚咽と共に彼の背中に手を回す。ごめんなさい、ごめんなさい、と彼女は繰り返すように謝り続けた。
耳元でギターの心地よい音が聞こえた。澄んだ、なんのエフェクトも掛かっていないクリーンサウンド。
この音は、多分私だ。
律花はそう思った。
・
グリーンの制服に身を包み、律花は廊下を歩いていた。リノリウムの床を上履きで鳴らしながら歩く彼女の姿は、どこか嬉しそうにも見えた。
「白部、ちょっと頼んでもいいか?」
ステップを踏むように歩く律花に怪訝な表情を浮かべながら、一人の教師が彼女に声をかけた。律花は振り向くと小さくお辞儀をして、今日は急いでるから無理です、と返事を返すとにっこり笑い、踵を返すとそのまま廊下奥の階段を降りて行ってしまった。
断られた教師は呆然とした表情のまま、律花の消えていった廊下を眺めていた。
「白部さんが断るなんて珍しいね」
「それになんだかいつもより明るくなった気がする……」
偶然その光景を見ていた生徒達が不思議そうに話していた。
教師もまた、彼女の小さな変化に戸惑いながら、手にしていた書類をと廊下とを眺めていた。
律花にとっては小さな変化だったかもしれないそれは、しかしこれまでの白部律花を知っている人間からすれば戸惑いを覚えるようなレベルのもので、彼女が何か変わったという噂は校内に広がった。
様々な理由が噂される中で最も出たのは、恋人が出来たのではないかというものだった。だがそれを真に受けて尋ねた男子生徒どもはこぞってはぐらかされ、恋話に恋する年頃の女子生徒達は誤魔化され、気が付けば彼女の話術に乗って自身の愚痴や相談をさせられてしまっていた。
品行方正、成績優秀。
しかし余裕のある姿勢だった。
何より、白部律花は今、とても楽しそうに笑うのだ。
保健室を開けると、ベッドに横になっていた弦子が起き上がって手を振る。律花は彼女を見て困ったように顔をしかめると、横の丸椅子に座った。
「やあ律花ちゃん」
「本当に弦子、キャラ変わったよね」
「それはあなただって同じじゃない、ムーンマーガレットちゃん?」
目を細めてからかうように笑う彼女に、律花は不機嫌そうに眉をひそめる。
「くたばればいいのに」
「いやあ、だってもうバレちゃったし、今更猫被る必要はないでしょう?」
そういって弦子はくわえていたキャンディバーを手に取って律花に向ける。先についた黄色い飴玉は、彼女のお気に入りのレモン味だ。
ブッキングの後、律花はキャップを外し、自分の顔を曝した。今更隠していてもしょうがないことのように思えたし、何より自分よりも目立ち、美味しい思いをする鳴海が許せなかったということもあった。
まあ、そんなものは全部こじつけた理由に過ぎないのだが。
その際二人をねぎらうようにして近づいてきたのが、ジョニー・ストロボと、目の前にいるレモンドロップスこと調沢弦子だった。
「本当にあの時はびっくりした」
「ごめんね、でも隠していたのは律花も一緒なんだから、オアイコってことでいいじゃない」
「良くないわよ! アンタは気づいていたんでしょ? おまけにお兄……兄までけしかけて……。今回の件で分かったけど、あなた、本当に性格悪いわ」
「あ、分かっちゃった?」
悪びれもせずに笑う弦子を見て、律花は溜息を吐いた。
ただ、それでも彼女を憎めないのは、多分、それが結果として自分を含めた人間にきっかけを与えたからなのだろう。律花は内に秘めた想いを吐き出し奏汰や家族と改めて会話をする機会を得た。鳴海は、今度こそ本当のプレイヤーとして覚醒することができた。
一歩間違えばどうなっていたのか分からない。そんな状況の中、弦子は、レモンドロップスはその状況を仕組んだのだ。
「最近はお兄ちゃんって呼んでるんだ?」
「うるさいわね」
「おお、怖い怖い。でもいい顔してるよ、今」
寝転がって足をばたつかせながら、弦子は律花にいたずらっぽく笑いかけるとそう言った。言われた律花は少し恥ずかしそうに顔を伏せて、それから怒った顔で彼女の額に一発デコピンをお見舞いする。
「痛っ!」
「今回の件は、これで許してあげる。どうせジョニー・ストロボのほうからもっと手痛い罰食らったんでしょ?」
「いったあ……。まあねー、もうオーパーツには戻れなくなっちゃった。わりと居心地良かったんだけどなあ、あそこ」
目に涙を浮かべながら額を抑える弦子を眺めながら、律花は丸椅子からベッドの端に移る。
「……結局、あなたは何がしたかったの?」
ずっと律花が気になっていたことだった。別にオーパーツの活動に準じるつもりもなく、レーベル脱退にも素直に応じた彼女は、今回一体何を得たのだろう。
尋ねられて、弦子はうーん、と低う唸り、やがて口を開くと、プライベート・キングダム、と言った。
「プライベートキングダム?」
「聞いたこと無い? 当たり前の噂過ぎて最近はあまり話題に出ないから仕方ないのか」
弦子は肩を竦める。
「最強、最凶、最恐。オーディエンスを従える権利と、一振りで相手をたやすくなぎ払う力を持つ唯一無二の、王の名を冠するにふさわしい【伝説の】プレイヤーが存在している。私達が必死で戦うあの場所も、王にとっては遊び場でしかない。そんなたった一人の王が座る、モッシュピットの最奥にあると噂される空間。プレイヤー達はその伝説上の場所をこう呼んでいる。|深淵の遊び場《プライベート・キングダム》と……」
「ちょっと待ってよ、最強って、ラスト・ホリデイじゃないの?」
「もちろん、彼は最強よ。ただ、彼の名乗る最強はあくまでモッシュピット限定よ。そして彼がどうして最強を名乗るかといえば、プライベート・キングダムに至るためにそれが必要だと考えているからであり、そこへの到達を目的としているからよ」
「目、的……?」
弦子は不敵な笑みを浮かべる。それは、無邪気な少女のそれとは違う、血に飢えているような、獣性を帯びた獰猛なものに思えて、律花は緊張する。
彼女は、ただのプレイヤーじゃ、ない。
律花の本能が、そう言っていた。
「ラスト・ホリデイは、唯一無二の王座を奪い取るつもりなのよ。このモッシュピットを内側から消し去るために、ね……」
「消し去る……?」
弦子は起き上がると、唖然とする律花の横をすり抜けるようにして立ち上がり、保健室の扉に手をかける。
「ねえ、待って。そんなことを知っているって、あなたは一体……?」
律花の言葉に弦子は微笑む。
「私ね、欲しいものがあるの。ちょっとやそっとじゃ手にはいらないおっきいやつ。私はそのためならなんだってやるつもりで、その道筋に君と鳴海クンがいたから、利用しただけ。ごめんね、律花ちゃん」
そしてありがとう、と彼女は続けて言った。
「今回はとても大きな収穫だった。これからも期待してるよ。週末のロストマンとムーンマーガレットには、ね」
扉がぴしゃり、と閉じられる。
たった一人取り残された律花は、呆けた顔のまま、弦子の出て行った扉を見つめることしか出来なかった。
「さよなら律花ちゃん」
それから数日して、弦子は学校をやめた。
彼女の机に残った棒付きのキャンディ。そこに貼ってあった付箋の言葉を眺め、やがて握りつぶすと包み紙を破いて律花はキャンディを口に含む。
「……酸っぱ」
濃厚なレモンの味が口いっぱいに広がる。
この味が大好きだった彼女はもういない。
律花が始めて友達になれると思えた彼女は、もういない。
・
「今日は遅いのか、律花?」
朝食のトーストを口にしながら父は律花にそう尋ねる。律花は欠伸を一つしてから、焼きたてのトーストに苺のジャムを塗って齧りつく。
「うん、でも晩御飯までには帰ってくるつもり」
「そうか、なるべく暗くならないうちに帰ってきなさい」
律花は頷くと、トーストの最後を飲み込み、椅子の横にかけてあった肩提げ鞄を手にリビングを出て行く。
出て行ってから、思い出したように戻ってくると、律花は顔だけを廊下側から覗かせる。
「行ってきます、パパ、ママ」
「ああ」
「いってらっしゃい、律花」
変わらず憮然としたままの父と、にっこりと笑って手を振る母の姿を見てから、律花は玄関へと向かう。玄関側の洗面所に立ち寄り、用意しておいた花束を手に取って、萎れていないか確認して抱えた。
「律花、もう行くのか?」
振り返ると、丁度寝巻き姿の奏汰が階段から降りてきたところだった。大きく欠伸をしながら頭を掻く彼の姿を見て、律花はうん、と頷く。
「うん、お兄ちゃんも来る気になった?」
「いや、遠慮しておく。やり合って思ったけど、俺ちょっとアイツ苦手だ」
苦虫を噛み潰したような顔を浮かべる奏汰を見て律花はくすくす笑った。玄関前に腰を下ろして、おろしたての靴に足を通してから再び立ち上がると、ドアノブに手をかけた。
手をかけてから、もう一度振り返ると、奏汰の姿を見て言った。
「じゃあ、行ってきます」
「ああ、いってらっしゃい」
飛び出した扉の先は、晴天だった。曇り一つない青空を眺めながら、大分寒くなってきたな、と律花は首元に巻いたマフラーを巻き直しながら白い息を吐いた。唇は青くないだろうかと手鏡で確認しながら、律花は少し歩いた先にある停留所のベンチに座った。
運行案内を見て行程を確認して、おそらく三十分もあれば着くだろうと踏んで、律花はバスを待つ。
あれから律花達は長い話をした。今までのこと、そしてこれからのこと。
そこに解決はなかったし、未だに白部家はちぐはぐで、不器用な生活を続けている。四人それぞれにそれぞれの考え方があって、それはこれから度々話し合わなくてはいけないもので、簡単に答えを出せるものではなかったのだ。
けれどその会話が、家族をまたあの頃の食卓に引き戻してくれたように、律花は感じていた。
果てしない会話の末、律花は、これからも父と母の自慢の娘であろうと決めた。しかしそれは家族のためではなく、自分のための決断だった。
この先も多く求められることがきっとあるだろう。時には理不尽な障害だって出てくるかもしれない。それらを乗り越えるために、少なくともタフさは必要だと思った。
ただ、それでも自分ではどうしようもないことに突き当たってしまうことがあるかもしれない。そんな、途方に暮れてしまうような躓き方をしてしまった時は、我慢せず誰かに頼ってみようと思った。
そして最後に、これは単なる思いつきからだったのだが、家族の呼び方を、昔に戻してみた。自分を含めた四人ともそう呼ばれる度にどこか気恥ずかしさを感じるようだが、それで良いと思った。
「……コツさえ掴めば、宇宙も飛べる、か」
律花は顔を上げる。道路を挟んで向かいに住宅街が見える。視線を少し上にずらすと、青々とした雲一つ無い空が広がっていて、そこに飛行機が横に長い白線を引いていた。
「飛べるかな」
飛べるさ、と彼なら言うのだろう。脳裏で聞こえたその声に、律花はくすりと笑みをこぼした。
――私も、彼のように世界を一度壊してみようと思うのだ。
――小さくて構わない。私なりの|破壊《小さな一歩》を。
やがてバスがやってきた。
『○○病院行き』
律花は表示された電光板の文字を確認してから、バスステップに足をかける。
今日は鳴海に会いに行くつもりだ。
週末限定のあの|小さな破壊者《ロストマン》に、宣戦布告をするために。