プロローグ2 ある幼女の一日

朝起きると、家はいつもがらんどう。ちょっとだけ寂しいなって、髪をとかしながら思う。お風呂場は静かで、滴が落ちる以外には何も聞こえない。
毎朝同じ時間に起きて、慌ただしく登校の準備をするのがわたしの日課。目覚ましを止めて、歯を磨いて、朝ご飯を食べて、また歯を磨いて、髪の毛やお洋服を整える。その間には家の中を何度も、行ったり来たりしなくちゃいけない。広い家を歩き回っているのに誰の顔も見ないのは、自分が一人なんだってことをつきつけられるから嫌い。
わたしには、パパとママがいる。弁護士をしているパパと、デザイン関係の社長をしているママ。周りの大人の人たちは皆、パパとママのことを立派だって言ってくれる。二人の子どもに生まれたわたしは絶対、幸せ者だって。わたしも頭ではわかってる。家に居るとき、二人は優しくしてくれるし、欲しいものをネダれば買ってくれる。でもたまに、優しくなくてもいい、プレゼントをくれなくてもいいから、いつも一緒にいてほしいと思うときがある。おばあちゃんが生きていたころは寂しくなかったけれど、最近は……。
こんなに贅沢なこと、本当は思っちゃいけないんだ。わたしは反省する。身支度の仕上げに、髪を後ろで二つにまとめた。昨日、ママに買ってもらったヘアゴムを付ける。フリルがついたかわいいデザイン。うん、似合ってるよね。わたしは鏡の前で笑顔を作った。
毎朝同じ時間に起きて、慌ただしく登校の準備をするのがわたしの日課。目覚ましを止めて、歯を磨いて、朝ご飯を食べて、また歯を磨いて、髪の毛やお洋服を整える。その間には家の中を何度も、行ったり来たりしなくちゃいけない。広い家を歩き回っているのに誰の顔も見ないのは、自分が一人なんだってことをつきつけられるから嫌い。
わたしには、パパとママがいる。弁護士をしているパパと、デザイン関係の社長をしているママ。周りの大人の人たちは皆、パパとママのことを立派だって言ってくれる。二人の子どもに生まれたわたしは絶対、幸せ者だって。わたしも頭ではわかってる。家に居るとき、二人は優しくしてくれるし、欲しいものをネダれば買ってくれる。でもたまに、優しくなくてもいい、プレゼントをくれなくてもいいから、いつも一緒にいてほしいと思うときがある。おばあちゃんが生きていたころは寂しくなかったけれど、最近は……。
こんなに贅沢なこと、本当は思っちゃいけないんだ。わたしは反省する。身支度の仕上げに、髪を後ろで二つにまとめた。昨日、ママに買ってもらったヘアゴムを付ける。フリルがついたかわいいデザイン。うん、似合ってるよね。わたしは鏡の前で笑顔を作った。
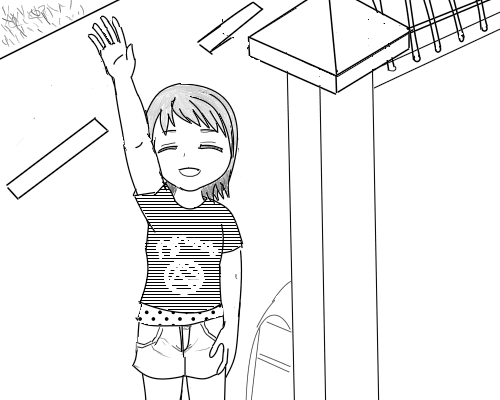
玄関を開けると、門の外には空ちゃんがいた。

「穂波ちゃん、おはよー」
「うん、おはよう」
悩みなんて一つもなさそうな空ちゃんの笑顔。自然とわたしにも元気が湧いてくる。あいさつを交わしたあとは、二人並んで学校に向かう。
通学路を歩き始めると、空ちゃんはすぐにわたしの顔を見て声を上げた。
「あ、穂波ちゃん、新しいゴム付けてるね」
首の後ろを指さして言う。
「うん、お母さんに買ってもらったの」
「すっごくかわいいね。羨ましいなー」
「ありがと。わたしも気に入ってるの」
ママから貰ったものを褒められると、わたしはとても嬉しくなる。心が軽くなって、なんでもできちゃうような、そんな気持ち。
空ちゃんはわたしの親友だ。幼稚園の頃から家が近くで、いつも一緒に遊んでいた。小学校に上がって、お互いの友達がそれぞれ変わっていっても、空ちゃんとの関係だけは続いている。だからきっと、私たちは大人になっても親友のままでいられるんだと思う。仲の良い友達は大切にしなさいって、おばあちゃんもよく教えてくれた。
「空ちゃん、肌焼けたね」
焼けてすぐの、赤くなった顔と腕を見て、わたしは言った。ちょっと痛そう。
「うん、お風呂入るの痛いんだよー」
空ちゃんは、はにかんで答える。
年齢が上がるにつれて、わたしは女の子とばかり遊ぶようになった。空ちゃんはちがって、今でも男子に混じってスポーツをしている。だから毎年、夏が近づくと肌が黒くなっていく。
「日焼け止めクリームとか塗らないの?」
「ひやけどめくりーむ? 目はやけどしてないよ?」
とんちんかんなことを言っている。
「肌が黒くならないように塗る薬のこと。日焼け跡って嫌じゃない?」
空ちゃんは「うーん」と考え込んでいる。
「あんまり考えたことないなあ……あ、ほら、あたしは穂波ちゃんみたいにかわいくないし、気にする必要ないかなって」
「そんなことないよ。空ちゃんかわいいよ」
自覚のない空ちゃんの顔を、両手で挟んだ。丸い、くりくりした目を見つめる。
「あ、あう……。穂波ちゃん、いひゃいよ」
「あ、ごめんね」
慌てて手を離す。
確かに空ちゃんは髪が短くて、男の子っぽいところがあるけれど、すごくかわいいと思う。きっともう少し大人になったら、一緒に遊んでいる男子たちがびっくりするくらい、美人になるはず。
「でも、そうだね、空ちゃんはそのままのほうが似合ってるかも」
ある日突然、空ちゃんが「あたし、オシャレに目覚めたの」なんて言って、お化粧してきたら怖いもの。妄想していると、空ちゃんがわたしの手を握る。
「ね、穂波ちゃん、今日の放課後、山田くんたちにサッカー誘われてるんだ。穂波ちゃんもやらない?」
大きい瞳をきらきら輝かせて、顔を近づけてくる。わたしはひるんでしまった。
「ごめん、わたし読みかけの本があるから」
つい断ってしまう。本当は、本を読むのなんていつでもよかった。ただ、この年になって男子と仲良くするのは抵抗がある。それに、他の友達に何を言われるかもわからない。
「そっかあ……じゃあ、あたしもやめとこうかな」
「え、なんで? 空ちゃんはサッカーしたいんでしょ、好きにしなよ」
「だって、穂波ちゃんと遊びたかったんだもん」
そんなことを言われてしまうと、悪い気がしてくる。わたしのせいで――なんて、思われてはいないんだろうけど。空ちゃんには悪いけど、男子に混ざるのはなあ……。
悩むわたしに、空ちゃんは語りかける。
「ねぇじゃあ、図書室で一緒に本読もうよ」
「本を一緒に?」
「うん、おすすめの本教えてね。穂波ちゃんの隣で読みたいから」
「隣で読んでるだけでいいの? つまらなくない?」
「大丈夫、もしかしたら途中で寝ちゃうかもしれないけど」
空ちゃんは恥ずかしそうに笑った。空ちゃんは、いつもこう。わがままなわたしに合わせようとしてくれる。わたしからも、なにかお返しはできないかと考えて、思いついた。ランドセルの中にある小物入れを引っ張り出して、ヘアゴムを一つ摘まむ。
「空ちゃん、これあげる」
腕を取って、日焼けに囲まれた手の平に乗せる。
「え、ダメだよ。穂波ちゃんが買ってもらったやつでしょ?」
「わたしはいいの。新しいの買ってもらったもん。これは、だから、お礼。友達でいてくれてありがとうって」
わたしはなんだか恥ずかしくて、うつむいてしまう。空ちゃんは顔が溶けたみたいに、にへらと笑って、抱きついてきた。
「穂波ちゃん、大好きっ」
「う、うん。どういたしまして」
いつからだろう。わたしは空ちゃんのことを『素直な子』だなって思うようになった。でもきっと、それは空ちゃんが素直になったんじゃなくて、わたしが素直じゃなくなっちゃったってことなんだろうな。昔のように簡単に笑えなくなった自分が、少しだけ悲しい。
学校に着くと、担任の先生が朝の連絡をする。白髪が混じった先生はいつもより険しい顔をしていた。
「あー、皆、静かに聞きなさい。実は昨日の夜、このあたりに不審者が出たそうだ」
『不審者』と先生が口にすると、とたんに教室が騒がしくなる。
「ふしんしゃだってよー」
「出たー、口裂け女だよ絶対」
「また泥棒かー?」
「きっと俺の父ちゃんだよ」
男子たちが好き勝手に言い合って、声が混ざり合う。
「おらー、お前ら静かにしろー」
先生が注意する。
朝の連絡のとき、このやり取りは毎回起こる。なんで先生が話してるのに、男子は静かにできないんだろう。
「あー、不審者情報をそのまま読み上げるぞー。昨日の夜7時ごろ、上山通り、は西門から出てすぐのところだ。そこで、コートを着た男が女子児童の前に立ち、『ワタクシは仮性なのか真性なのか、手で剥いて確かめて欲しい』と言って、コートを脱いだ。コートの下は全裸で、驚いた女子児童が逃げ出すと、全裸のままで追いかけられた、らしい。……これ、読み上げたらまずいやつだったのかな。まあ、お前らも気を付けろよー」
先生はなんでもないことのように言った。でも、教室の中は大騒ぎ。
「やべーよ露出魔だ!」
「包茎だっ、包茎男が出たっ」
「皆、やめなよ。包茎に罪はないよ」
「あー、こいつ包茎をかばってるぞ。自分も包茎なんだ絶対。やーい妖怪包茎男、ズル剥けがうらやましいか」
「でも実際、仮性か真性かで話はちがってくるよ」
「仮性だったら、僕は犯人に味方したいなあ。真性だったら救いようがないけど」
また、男子たちがうるさくしている。耳をふさいでいると、前の席に座っている空ちゃんが振り向いた。
「ねー穂波ちゃん、カセイとかシンセイとかってなにかな」
「わかんない」
その部分だけは正直、わたしも気になっていた。なんなんだろう。
「穂波ちゃんでも知らないんだ。難しいことなんだね、きっと」
二人で首をかしげていると、横から山下が割り込んできた。
「なんだお前ら、包茎を知らないのか」
えらそうな顔で、胸を張っている。山下はクラスでも勉強が全然できない男子。こいつが知っていてわたしが知らないなんて、くつじょく。
「なによ、悪いの」
思わず、腹を立てて言う。
「別に悪いなんて言ってないだろ、なーにムキになってんだよ」
「や、やめなよ二人ともぉ」
空ちゃんはおろおろしている。
「ふ、しょうがねぇな、気になるなら教えてやるよ」
山下はわたしの耳に口を近づけて小声で言う。
「ごにょごにょ」
その内容は、すごく恥ずかしくて、下品で、気持ち悪いことだった。
「サイッテー!」
わたしは席から立ち上がって叫ぶ。大声でみんなの視線が集まった。それすらも恥ずかしくて、席に座り直す。
「怒んなよ、本当のことを教えてやっただけじゃんか」
「もう知らない」
わたしは顔をそむける。山下はあきれて、今度は空ちゃんの方を向く。
「へへ、空にも教えてやるよ」
「やめなさいっ」
山下の服をつかんで、空ちゃんから引き離す。
「なんだよ、自分だけ知っておいて、友達はのけ者にするのかよ」
文句を言う山下の口をふさいで、遠くへほっぽりだしてやった。
「空ちゃんにはまだ、そういうのは早いの。変なこと吹き込まないで」
「ちぇー」
わたしが向き直ると、空ちゃんが興味津々な顔をしていた。
「穂波ちゃん、カセイとかシンセイとかってなんだったの?」
その言葉を聞いただけで、顔が熱くなってしまう。
「空ちゃん、もうこの話は終わり。あと、か、仮性とかって言葉もこれからは使っちゃダメ。わかった?」
「……はーい」
空ちゃんはしぶしぶ、あきらめてくれた。
5時間目が終わって、最後のチャイムが鳴った。
「穂波ちゃん、行こ行こ」
空ちゃんは一緒に読書をする約束を果たすため、わたしをせかす。忙しく教科書をランドセルにしまっていると、クラスの女の子たちが集まってきた。
「穂波さーん、勉強教えてもらってもいいかなあ」
教室には15人の女子がいるけれど、その半分くらいの人数が押し寄せてくる。
「うわわ」
空ちゃんは大群に押しのけられてしまった。
「明日からテストでしょ? わたしら全然勉強してなくて、穂波さんに教えて貰いたいなーって」
「ごめん、わたしこれから予定が――」
「お願いっ! 穂波さんしか頼れる人がいないの。穂波さんて頭いいから」
「教え方も上手っ」
「それに、顔もかわいいし」
「オシャレだし」
女の子たちは口々に言う。
「最後らへんのは関係ないような……」
「とにかくお願いっ」
大人数に頭を下げられると、心がしぼんでいく。どうしよう。
わたしはちらりと空ちゃんのほうを見た。すると、空ちゃんはにっこりと笑う。
「穂波ちゃん、教えてあげなよ。あたしは大丈夫、外で遊んでるから!」
ランドセルを背負って、走って行ってしまう。扉を出て、すぐに見えなくなった。わたしはずるい人間だな。自分で断ることもせずに、気を使わせるなんて。あとで謝っておかなくちゃ。
「穂波さんありがと~」
前を向くと、女の子たちはみんな、笑顔だった。
机をくっつけて、教科書とノートを広げる。輪になったあちこちからは楽しげな話し声が聞こえる。どうしてもお願いと言ってきた割に、みんなのんきだった。真剣にノートに向かっているのは半分くらいで、残りは友達とおしゃべりしてる。
「ねぇ、勉強しないの?」
「あ、ごめん、するする、するよ」
わたしが注意すると、仕方なしに勉強に戻る。さっきから、これを何回か繰り返している。ああ、やっぱり教えるのは断って、空ちゃんと遊びたかったな。いまになって、後悔のかたまりがわたしをチクチクと刺した。
「穂波さん、ここはどう解けばいいの?」
隣にいた子が聞いてくる。
「もう、そこはさっき教えたでしょ。だから、同じ式を使って……」
「あ、怒った? ごめんね。もういいから、一人でも大丈夫だと思う」
ノートが引っ込められる。怒ったわけじゃないんだけど。不機嫌にさせちゃったかな。なんだろう、わたし、すごくイライラしてる。ダメだ、こんなんじゃ。
「わたし、ちょっとお手洗いに行ってくるね」
言って、席を立つ。教室を出るあいだにも、女の子たちのはしゃぎ声はなくならなかった。
洗面台の前で、鏡を見る。手を洗いながら顔を見ると、眉の間にしわがよってる。空ちゃんは今、なにしてるかな。予定通り男子とサッカーしているならいいけど。そろそろ時間もたったし、勉強はお開きにするように言ってみようかな。そしたら空ちゃんを探そう。
廊下を歩いて教室に戻る。扉の前に立つと、女の子たちの会話が聞こえてきた。
「ちょっとみんな、穂波さん感じ悪くない?」
「うんうん」
「勉強教えてって、下手に出たらこれだもん」
「チョーシに乗ってるんじゃない、色んな人から褒められてさ」
「わたしら気ぃ使ってるだけなのにね」
壁に背をつけて、会話を聞き取る。心臓の音がものすごく早い。
「結局、親が金持ちってだけだもん」
「でも、うらやましいよねー、なんでも買ってもらえてさ」
やめて、それ以上言わないで。自分の陰口なんて聞きたくないのに、耳をふさぐこともできない。体が固まってしまう。頭の奥が熱くなって、背中は冷たくなる。
「あたしなんか、消しゴムも買ってもらえないもん。ほらみて、豆粒みたいに小さくなってる」
「あはは、それはヤバすぎ」
「穂波さんの髪留め見た? また新しくなってたよ」
「あんなのダサいよ。今どき二つ結びってイモすぎ」
「いーじゃん、あたしら凡人は、ひくつに生きましょー」
みんなが笑っている。わたしのことをバカにして。やっぱりさっき、冷たくしちゃったのが失敗だったんだ。ううん、本当はもっと前から失敗していたのかも。わたしは泣きだしそうになって、でも、いま泣いてしまったら教室に戻れなくなるから、じっとこらえた。
やっとわたしの話題が終わった頃に、教室に入った。
「あ、穂波さんおかえりー」
みんなは、勉強を聞きに来たときと同じ笑顔をしていた。
その後、勉強会は早めに切り上げた。空ちゃんを探すのは諦めて、まっすぐ家に帰る。
家の中に入るなり、わたしは自分の部屋に逃げ込んだ。ベッドに寝そべって、まくらに顔を押し付ける。下校中ずっと我慢していた涙が、次から次にあふれてきた。
「うん、おはよう」
悩みなんて一つもなさそうな空ちゃんの笑顔。自然とわたしにも元気が湧いてくる。あいさつを交わしたあとは、二人並んで学校に向かう。
通学路を歩き始めると、空ちゃんはすぐにわたしの顔を見て声を上げた。
「あ、穂波ちゃん、新しいゴム付けてるね」
首の後ろを指さして言う。
「うん、お母さんに買ってもらったの」
「すっごくかわいいね。羨ましいなー」
「ありがと。わたしも気に入ってるの」
ママから貰ったものを褒められると、わたしはとても嬉しくなる。心が軽くなって、なんでもできちゃうような、そんな気持ち。
空ちゃんはわたしの親友だ。幼稚園の頃から家が近くで、いつも一緒に遊んでいた。小学校に上がって、お互いの友達がそれぞれ変わっていっても、空ちゃんとの関係だけは続いている。だからきっと、私たちは大人になっても親友のままでいられるんだと思う。仲の良い友達は大切にしなさいって、おばあちゃんもよく教えてくれた。
「空ちゃん、肌焼けたね」
焼けてすぐの、赤くなった顔と腕を見て、わたしは言った。ちょっと痛そう。
「うん、お風呂入るの痛いんだよー」
空ちゃんは、はにかんで答える。
年齢が上がるにつれて、わたしは女の子とばかり遊ぶようになった。空ちゃんはちがって、今でも男子に混じってスポーツをしている。だから毎年、夏が近づくと肌が黒くなっていく。
「日焼け止めクリームとか塗らないの?」
「ひやけどめくりーむ? 目はやけどしてないよ?」
とんちんかんなことを言っている。
「肌が黒くならないように塗る薬のこと。日焼け跡って嫌じゃない?」
空ちゃんは「うーん」と考え込んでいる。
「あんまり考えたことないなあ……あ、ほら、あたしは穂波ちゃんみたいにかわいくないし、気にする必要ないかなって」
「そんなことないよ。空ちゃんかわいいよ」
自覚のない空ちゃんの顔を、両手で挟んだ。丸い、くりくりした目を見つめる。
「あ、あう……。穂波ちゃん、いひゃいよ」
「あ、ごめんね」
慌てて手を離す。
確かに空ちゃんは髪が短くて、男の子っぽいところがあるけれど、すごくかわいいと思う。きっともう少し大人になったら、一緒に遊んでいる男子たちがびっくりするくらい、美人になるはず。
「でも、そうだね、空ちゃんはそのままのほうが似合ってるかも」
ある日突然、空ちゃんが「あたし、オシャレに目覚めたの」なんて言って、お化粧してきたら怖いもの。妄想していると、空ちゃんがわたしの手を握る。
「ね、穂波ちゃん、今日の放課後、山田くんたちにサッカー誘われてるんだ。穂波ちゃんもやらない?」
大きい瞳をきらきら輝かせて、顔を近づけてくる。わたしはひるんでしまった。
「ごめん、わたし読みかけの本があるから」
つい断ってしまう。本当は、本を読むのなんていつでもよかった。ただ、この年になって男子と仲良くするのは抵抗がある。それに、他の友達に何を言われるかもわからない。
「そっかあ……じゃあ、あたしもやめとこうかな」
「え、なんで? 空ちゃんはサッカーしたいんでしょ、好きにしなよ」
「だって、穂波ちゃんと遊びたかったんだもん」
そんなことを言われてしまうと、悪い気がしてくる。わたしのせいで――なんて、思われてはいないんだろうけど。空ちゃんには悪いけど、男子に混ざるのはなあ……。
悩むわたしに、空ちゃんは語りかける。
「ねぇじゃあ、図書室で一緒に本読もうよ」
「本を一緒に?」
「うん、おすすめの本教えてね。穂波ちゃんの隣で読みたいから」
「隣で読んでるだけでいいの? つまらなくない?」
「大丈夫、もしかしたら途中で寝ちゃうかもしれないけど」
空ちゃんは恥ずかしそうに笑った。空ちゃんは、いつもこう。わがままなわたしに合わせようとしてくれる。わたしからも、なにかお返しはできないかと考えて、思いついた。ランドセルの中にある小物入れを引っ張り出して、ヘアゴムを一つ摘まむ。
「空ちゃん、これあげる」
腕を取って、日焼けに囲まれた手の平に乗せる。
「え、ダメだよ。穂波ちゃんが買ってもらったやつでしょ?」
「わたしはいいの。新しいの買ってもらったもん。これは、だから、お礼。友達でいてくれてありがとうって」
わたしはなんだか恥ずかしくて、うつむいてしまう。空ちゃんは顔が溶けたみたいに、にへらと笑って、抱きついてきた。
「穂波ちゃん、大好きっ」
「う、うん。どういたしまして」
いつからだろう。わたしは空ちゃんのことを『素直な子』だなって思うようになった。でもきっと、それは空ちゃんが素直になったんじゃなくて、わたしが素直じゃなくなっちゃったってことなんだろうな。昔のように簡単に笑えなくなった自分が、少しだけ悲しい。
学校に着くと、担任の先生が朝の連絡をする。白髪が混じった先生はいつもより険しい顔をしていた。
「あー、皆、静かに聞きなさい。実は昨日の夜、このあたりに不審者が出たそうだ」
『不審者』と先生が口にすると、とたんに教室が騒がしくなる。
「ふしんしゃだってよー」
「出たー、口裂け女だよ絶対」
「また泥棒かー?」
「きっと俺の父ちゃんだよ」
男子たちが好き勝手に言い合って、声が混ざり合う。
「おらー、お前ら静かにしろー」
先生が注意する。
朝の連絡のとき、このやり取りは毎回起こる。なんで先生が話してるのに、男子は静かにできないんだろう。
「あー、不審者情報をそのまま読み上げるぞー。昨日の夜7時ごろ、上山通り、は西門から出てすぐのところだ。そこで、コートを着た男が女子児童の前に立ち、『ワタクシは仮性なのか真性なのか、手で剥いて確かめて欲しい』と言って、コートを脱いだ。コートの下は全裸で、驚いた女子児童が逃げ出すと、全裸のままで追いかけられた、らしい。……これ、読み上げたらまずいやつだったのかな。まあ、お前らも気を付けろよー」
先生はなんでもないことのように言った。でも、教室の中は大騒ぎ。
「やべーよ露出魔だ!」
「包茎だっ、包茎男が出たっ」
「皆、やめなよ。包茎に罪はないよ」
「あー、こいつ包茎をかばってるぞ。自分も包茎なんだ絶対。やーい妖怪包茎男、ズル剥けがうらやましいか」
「でも実際、仮性か真性かで話はちがってくるよ」
「仮性だったら、僕は犯人に味方したいなあ。真性だったら救いようがないけど」
また、男子たちがうるさくしている。耳をふさいでいると、前の席に座っている空ちゃんが振り向いた。
「ねー穂波ちゃん、カセイとかシンセイとかってなにかな」
「わかんない」
その部分だけは正直、わたしも気になっていた。なんなんだろう。
「穂波ちゃんでも知らないんだ。難しいことなんだね、きっと」
二人で首をかしげていると、横から山下が割り込んできた。
「なんだお前ら、包茎を知らないのか」
えらそうな顔で、胸を張っている。山下はクラスでも勉強が全然できない男子。こいつが知っていてわたしが知らないなんて、くつじょく。
「なによ、悪いの」
思わず、腹を立てて言う。
「別に悪いなんて言ってないだろ、なーにムキになってんだよ」
「や、やめなよ二人ともぉ」
空ちゃんはおろおろしている。
「ふ、しょうがねぇな、気になるなら教えてやるよ」
山下はわたしの耳に口を近づけて小声で言う。
「ごにょごにょ」
その内容は、すごく恥ずかしくて、下品で、気持ち悪いことだった。
「サイッテー!」
わたしは席から立ち上がって叫ぶ。大声でみんなの視線が集まった。それすらも恥ずかしくて、席に座り直す。
「怒んなよ、本当のことを教えてやっただけじゃんか」
「もう知らない」
わたしは顔をそむける。山下はあきれて、今度は空ちゃんの方を向く。
「へへ、空にも教えてやるよ」
「やめなさいっ」
山下の服をつかんで、空ちゃんから引き離す。
「なんだよ、自分だけ知っておいて、友達はのけ者にするのかよ」
文句を言う山下の口をふさいで、遠くへほっぽりだしてやった。
「空ちゃんにはまだ、そういうのは早いの。変なこと吹き込まないで」
「ちぇー」
わたしが向き直ると、空ちゃんが興味津々な顔をしていた。
「穂波ちゃん、カセイとかシンセイとかってなんだったの?」
その言葉を聞いただけで、顔が熱くなってしまう。
「空ちゃん、もうこの話は終わり。あと、か、仮性とかって言葉もこれからは使っちゃダメ。わかった?」
「……はーい」
空ちゃんはしぶしぶ、あきらめてくれた。
5時間目が終わって、最後のチャイムが鳴った。
「穂波ちゃん、行こ行こ」
空ちゃんは一緒に読書をする約束を果たすため、わたしをせかす。忙しく教科書をランドセルにしまっていると、クラスの女の子たちが集まってきた。
「穂波さーん、勉強教えてもらってもいいかなあ」
教室には15人の女子がいるけれど、その半分くらいの人数が押し寄せてくる。
「うわわ」
空ちゃんは大群に押しのけられてしまった。
「明日からテストでしょ? わたしら全然勉強してなくて、穂波さんに教えて貰いたいなーって」
「ごめん、わたしこれから予定が――」
「お願いっ! 穂波さんしか頼れる人がいないの。穂波さんて頭いいから」
「教え方も上手っ」
「それに、顔もかわいいし」
「オシャレだし」
女の子たちは口々に言う。
「最後らへんのは関係ないような……」
「とにかくお願いっ」
大人数に頭を下げられると、心がしぼんでいく。どうしよう。
わたしはちらりと空ちゃんのほうを見た。すると、空ちゃんはにっこりと笑う。
「穂波ちゃん、教えてあげなよ。あたしは大丈夫、外で遊んでるから!」
ランドセルを背負って、走って行ってしまう。扉を出て、すぐに見えなくなった。わたしはずるい人間だな。自分で断ることもせずに、気を使わせるなんて。あとで謝っておかなくちゃ。
「穂波さんありがと~」
前を向くと、女の子たちはみんな、笑顔だった。
机をくっつけて、教科書とノートを広げる。輪になったあちこちからは楽しげな話し声が聞こえる。どうしてもお願いと言ってきた割に、みんなのんきだった。真剣にノートに向かっているのは半分くらいで、残りは友達とおしゃべりしてる。
「ねぇ、勉強しないの?」
「あ、ごめん、するする、するよ」
わたしが注意すると、仕方なしに勉強に戻る。さっきから、これを何回か繰り返している。ああ、やっぱり教えるのは断って、空ちゃんと遊びたかったな。いまになって、後悔のかたまりがわたしをチクチクと刺した。
「穂波さん、ここはどう解けばいいの?」
隣にいた子が聞いてくる。
「もう、そこはさっき教えたでしょ。だから、同じ式を使って……」
「あ、怒った? ごめんね。もういいから、一人でも大丈夫だと思う」
ノートが引っ込められる。怒ったわけじゃないんだけど。不機嫌にさせちゃったかな。なんだろう、わたし、すごくイライラしてる。ダメだ、こんなんじゃ。
「わたし、ちょっとお手洗いに行ってくるね」
言って、席を立つ。教室を出るあいだにも、女の子たちのはしゃぎ声はなくならなかった。
洗面台の前で、鏡を見る。手を洗いながら顔を見ると、眉の間にしわがよってる。空ちゃんは今、なにしてるかな。予定通り男子とサッカーしているならいいけど。そろそろ時間もたったし、勉強はお開きにするように言ってみようかな。そしたら空ちゃんを探そう。
廊下を歩いて教室に戻る。扉の前に立つと、女の子たちの会話が聞こえてきた。
「ちょっとみんな、穂波さん感じ悪くない?」
「うんうん」
「勉強教えてって、下手に出たらこれだもん」
「チョーシに乗ってるんじゃない、色んな人から褒められてさ」
「わたしら気ぃ使ってるだけなのにね」
壁に背をつけて、会話を聞き取る。心臓の音がものすごく早い。
「結局、親が金持ちってだけだもん」
「でも、うらやましいよねー、なんでも買ってもらえてさ」
やめて、それ以上言わないで。自分の陰口なんて聞きたくないのに、耳をふさぐこともできない。体が固まってしまう。頭の奥が熱くなって、背中は冷たくなる。
「あたしなんか、消しゴムも買ってもらえないもん。ほらみて、豆粒みたいに小さくなってる」
「あはは、それはヤバすぎ」
「穂波さんの髪留め見た? また新しくなってたよ」
「あんなのダサいよ。今どき二つ結びってイモすぎ」
「いーじゃん、あたしら凡人は、ひくつに生きましょー」
みんなが笑っている。わたしのことをバカにして。やっぱりさっき、冷たくしちゃったのが失敗だったんだ。ううん、本当はもっと前から失敗していたのかも。わたしは泣きだしそうになって、でも、いま泣いてしまったら教室に戻れなくなるから、じっとこらえた。
やっとわたしの話題が終わった頃に、教室に入った。
「あ、穂波さんおかえりー」
みんなは、勉強を聞きに来たときと同じ笑顔をしていた。
その後、勉強会は早めに切り上げた。空ちゃんを探すのは諦めて、まっすぐ家に帰る。
家の中に入るなり、わたしは自分の部屋に逃げ込んだ。ベッドに寝そべって、まくらに顔を押し付ける。下校中ずっと我慢していた涙が、次から次にあふれてきた。
「ふっ……うっ……うぅぅぅ」
家の中は静かで、わたしの泣き声だけがひびいている。大きな声を出したって、誰もなぐさめてくれない。
本当は、気にするほどのことじゃないのかもしれない。大勢で一緒にいれば、時々、誰かに腹が立つときだってある。陰口を言っていた子も、全員が全員、わたしを嫌っているわけではないのかも。ただ悪く言う子に合わせて、仕方なく言っていたのかもしれない。
そうやって自分に言い聞かせるのに、涙は止まってくれない。もしかしたら、わたしは友達みんなに嫌われているのじゃないかと、不安でたまらない。もしかしたら空ちゃんも、付き合いを断ってばかりのわたしに、あきれているかもしれない。もしかしたら、パパやママだって、産んでしまったからわたしを育てているだけなのかも。本当は、お仕事をもっと頑張りたいのかもしれない。わたしは誰からも愛想をつかされてる。嫌だ、そんなのは耐えられない。できることなら、周りの人たち全員に好かれていたい。でもきっと、それは無理なんだ。
「パパぁ、ママぁ、おばあちゃぁん……」
長いあいだ、わたしは泣き続けていた。
気持ちが落ち着いたのは、泣き疲れたころ。まくらから顔を起こすと、カバーが涙で濡れている。洗濯物が増えてしまった。なんだか自分が情けない。
仕方なく、鼻をすすって洗面台に行く。ついでに、腫れぼったい目と赤い鼻先を洗い流した。冷たい水を浴びて、気持ちが切り替わる。
へこんでばかりはいられない。つらいことがあるのはしょうがない。それでもわたしは、パパやママみたいな立派な大人になるんだ。さあ、今日も夜まで勉強しよう。
次の朝、玄関を出ると、空ちゃんは変わらない笑顔で迎えてくれた。
「おはよー……あれ?」
わたしの顔を見て、不思議そうにする。目が腫れてるのばれちゃったかな。昨日ちゃんと洗っておいたんだけど。
「今日は髪の毛むすんでないんだね」
解かしたままのロングヘアーを指さされる。
「あ、う、うん。気分転換。こういう髪型っていままでしたことなかったから」
わたしはうそをついた。本当は、怖くて結べなかったんだ。髪留めをしてきたらまた、バカにされるんじゃないかって。
「ふーん……そっかあ。でも、その髪型も似合ってるね。かわいい」
空ちゃんはわたしをほめると、今度は横を向いて、自分の頭を見せた。
「ほら、あたしは穂波ちゃんにもらったやつ付けてきたよ」
頭の片側だけに、小さなしっぽが結んである。空ちゃんが嬉しそうに跳ねるたびに、しっぽもフリフリと揺れる。かわいくて、元気で、空ちゃんにぴったり。
「空ちゃんも似合ってるよ。ありがとね、プレゼントしたのを付けてきてくれて」
「うんっ」
空ちゃんに手を引かれ、学校へ歩き出した。昨日はすぐ横に並んでいた二人の足。今日はほんの少し、わたしが遅れていた。
家の中は静かで、わたしの泣き声だけがひびいている。大きな声を出したって、誰もなぐさめてくれない。
本当は、気にするほどのことじゃないのかもしれない。大勢で一緒にいれば、時々、誰かに腹が立つときだってある。陰口を言っていた子も、全員が全員、わたしを嫌っているわけではないのかも。ただ悪く言う子に合わせて、仕方なく言っていたのかもしれない。
そうやって自分に言い聞かせるのに、涙は止まってくれない。もしかしたら、わたしは友達みんなに嫌われているのじゃないかと、不安でたまらない。もしかしたら空ちゃんも、付き合いを断ってばかりのわたしに、あきれているかもしれない。もしかしたら、パパやママだって、産んでしまったからわたしを育てているだけなのかも。本当は、お仕事をもっと頑張りたいのかもしれない。わたしは誰からも愛想をつかされてる。嫌だ、そんなのは耐えられない。できることなら、周りの人たち全員に好かれていたい。でもきっと、それは無理なんだ。
「パパぁ、ママぁ、おばあちゃぁん……」
長いあいだ、わたしは泣き続けていた。
気持ちが落ち着いたのは、泣き疲れたころ。まくらから顔を起こすと、カバーが涙で濡れている。洗濯物が増えてしまった。なんだか自分が情けない。
仕方なく、鼻をすすって洗面台に行く。ついでに、腫れぼったい目と赤い鼻先を洗い流した。冷たい水を浴びて、気持ちが切り替わる。
へこんでばかりはいられない。つらいことがあるのはしょうがない。それでもわたしは、パパやママみたいな立派な大人になるんだ。さあ、今日も夜まで勉強しよう。
次の朝、玄関を出ると、空ちゃんは変わらない笑顔で迎えてくれた。
「おはよー……あれ?」
わたしの顔を見て、不思議そうにする。目が腫れてるのばれちゃったかな。昨日ちゃんと洗っておいたんだけど。
「今日は髪の毛むすんでないんだね」
解かしたままのロングヘアーを指さされる。
「あ、う、うん。気分転換。こういう髪型っていままでしたことなかったから」
わたしはうそをついた。本当は、怖くて結べなかったんだ。髪留めをしてきたらまた、バカにされるんじゃないかって。
「ふーん……そっかあ。でも、その髪型も似合ってるね。かわいい」
空ちゃんはわたしをほめると、今度は横を向いて、自分の頭を見せた。
「ほら、あたしは穂波ちゃんにもらったやつ付けてきたよ」
頭の片側だけに、小さなしっぽが結んである。空ちゃんが嬉しそうに跳ねるたびに、しっぽもフリフリと揺れる。かわいくて、元気で、空ちゃんにぴったり。
「空ちゃんも似合ってるよ。ありがとね、プレゼントしたのを付けてきてくれて」
「うんっ」
空ちゃんに手を引かれ、学校へ歩き出した。昨日はすぐ横に並んでいた二人の足。今日はほんの少し、わたしが遅れていた。