20XX年、新都社大学は重大な危機に瀕していた。学生が登校しないのである。
学校経営は長らく安泰だった。明治初期から続く長い歴史と、趣のある校舎。権威によって学生たちは集い、学生たちは校外にて権威を証明した。滞りのない良循環。私立大学にとって冬と言われる時代においてさえ、勢いは衰えなかった。輝かしい実績が、いつしか“新都社神話”などと呼び表されるようになったのも必然である。
ところが近年、神話は崩壊しつつあった。
授業の集団ボイコット。人材に資する教育体制の、根幹を揺るがす事態である。
学生たちが大学に行かない理由は様々であった。自らの頭脳への驕り、日本的ムラ社会の崩壊、一部青年男性にとって極めて有意な電磁的脅威(エロゲー)、あるいは低血圧。とにかく、学生たちは大学を休んだ。
はじめ、|難治性学習拒否症候群《サボリグセ》に冒された学生は少数だった。彼ら初期感染者たちは皆、過激派である。一人は早々に卒業を諦め、社会の彼方へと消えた。一人は遠方の親を欺くため、成績資料を偽造・改竄した。一人は孤独の深淵に踏み入り、大学どころか人生から卒業した。やがて、校舎に姿を現す人数が減り始めると、変化は起こった。『大学に行かんでもよかろうもん♪』というミームは空気を介して伝染し、瞬く間に構内を席巻した。未曾有のバイオハザードである。
そして、今。がらんどうになった大教室の一角に、賢治はいた。
「はあ……またか」
最前列に座って黒板へ目を向けるなり、賢治はため息をつく。
チョークで書かれた文言はこうだ。
『教授不在により自習』
本日、自習を言い渡されたのは三度目だ。すなわち、講義に出席した回数でもある。驚くべきことに、ここ最近というもの、九割以上の授業が指導者を欠いている。
「まあ、無理もないことだが……」
聴衆なき選挙演説に価値がないように、読み手なき零細web小説に価値がないように。学生なき授業にもまた、価値はない。
教授たちの怠慢を咎める正義はなし。悪いのはひとえに学生側なのだ。
賢治は座ったまま振り返り、教室を見渡す。人っ子一人見当たらない。月曜の三限にこのような惨状があっていいものか。
「不良どもめ」
吐き捨てる。
怒りとは手が届かぬものにこそ、煮え滾るものだ。賢治にとっては、学友たちがその対象であった。今や姿を見かけることもない、堕落した者たち。彼らを生み出した怠惰という業。どちらも憎たらしかった。
現状、授業は形骸化しているのだから、大学に登校する意味も失われている。向学心を満たすためならば、自室で本を開けばよい。事実、幾人かは自宅学習の後、試験に出席して単位を獲得する者もいた。賢治がわざわざ教室に訪れるのは、自身の立場を確認し、同時に、敵を忘れぬためである。
厳めしい表情のまま、賢治は教科書を開く。講義されるはずだった該当範囲を探し当てると、すぐに取り掛かった。
「法哲学はわたしの得意分野だぞっ。どれ、哲学的難題をふっかけてみろっ、キヒッ、ヒャハハハハハァッ」
妄執は精神を蝕む。日に日に霊障チックな独り言が増していることに、彼は気が付いていない。
いつしか。改めて教科書と向き合えば、独り言も消えた。時おり挟まれる筆記音は静謐を害さない。
賢治の集中が頂点まで達したころ。教室の外から声がした。
…………――――あおおぉぉぉぉん――――うぉぉおおおおおん――――…………
聞きようによっては獣の遠吠えとも取れる。しかし、耳を傾ければ確かに人の肉声であった。
賢治は声の正体を知っている。珍しいものでもない。この大学に通う者であれば、一日に一度は耳にするであろう。それは、断末魔だ。大量に単位を落とした者の。あるいは、留年が確定した者の。
怠惰には必ず報いがある。内定取り消し、重い学費、両親からの勘当。安寧とした生活がデッドラインを踏み越えた瞬間から、莫大なツケがのしかかる。残酷な世の常。片隅に追いやっていた道理を眼前に突き付けられたとき、人は咽び泣くのだ。
賢治は手を止め、聞き入った。
「馬鹿なやつだ……。いっそ心が壊れてしまえば、楽になれるだろうに」
優越感と哀れみ、ない交ぜになった感情が起こる。打ち消すように、胸の前で十字を切った。
講義開始の時間からちょうど90分後。鐘の音とともに、賢治は立ち上がる。
そのとき――ふと、気配を感じて振り向いた。
学校へ行○う!
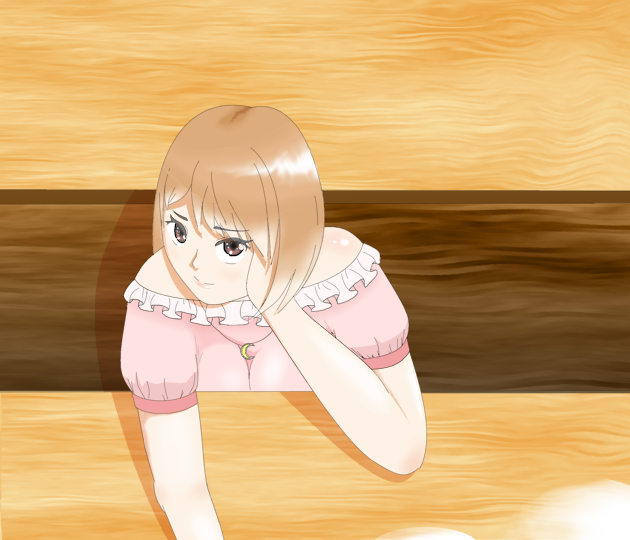
「なっ……いつの間にっ……!!」
程近く、斜め後ろの席。女が座っていた。
賢治は腰をそらしてのけ反った。知らぬ間に背後を取られた驚きもある。が、女の容姿がストライクゾーンの内角高めを抉ったことも無関係ではない。賢治はメガネっ子委員長最萌主義を掲げている。しかし、軽めのギャルまでならいけるクチだった。結婚してやってもいいとさえ考えていた。傲慢である。
「しばらく観察させてもらってたの。あなたって奇特な人ね」
女の声は外見に反して冷たかった。賢治は及び腰になるのをぐっとこらえ、毅然として言葉を返す。
「奇特? 大学生が大学で勉強するのは当然のことだと思うが」
「ふっ、大学で、ね」
皮肉の混じった響き。賢治は眉をひそめた。
「何が言いたい?」
「ここはもう、大学ではないわ。だって、そうでしょう? 教授も学生もいない大学なんてありえないもの。大学というのは建物を指すのではなく、人々の共同体を指すのよ」
「世迷言を。わたしは確かに新都社大学の学生だ。学生証も発行されている。学生は定められた時間に教室を訪ね、勉学に励む。それが規律。規律は絶対だ」
「規律も同じことよ。人のいないところで、規律はただの言葉に過ぎない」
嘲りは“歩く生徒手帳”と呼ばれた男を憤らせるに十分だった。
「では君はっ……誰だか知らないが……わたし以外の連中が正しいと? 学生としての本分を忘れ、腐りきった奴らが?」
両者はにらみ合う。剣呑な雰囲気が充満した。
緊張が破裂する直前。視線をはずしたのは女の方だった。わざとらしく肩をすくめ、ため息を吐いてみせる。
「一理はあると言ってるのよ。いいじゃない、単位なんて土下座で取れば。だって、法哲学よりは将来の役に立ちそうじゃない、土下座」
「サヴィニーは偉大だ」
「ええ、そうね。けれど無意味よ」
「憤怒ぅっ!!」賢治はTシャツを脱ぎ捨てた。「学問を愚弄するか貴様ぁっ!!」
上半身をこれでもかと言わんばかりに見せつける。筋骨を奮い立たせ、漢の威厳を誇示した。たったいま、賢治は全盛期ボ○・サップだった。自己解釈的に。
「貧相な身体ね」女は笑い、鼻息を漏らす。「虫みたい」
「おおぉぉぉぉ…………」
漢はあっさりとくずおれた。試合開始直後に膝をくらったボ○・サップのように。
罵倒に屈したわけではない。女の言葉が過去をよみがえらせたのだ。小学校時代、想い人に浴びせられたセリフは、未だに深く刻まれている。
『賢治くんって虫っぽい。多足類の』
「あああああああっ!! わたしは手足をあわせても四本だからっ!! 多足類の定義からは外れるんじゃないかなっ!? 愛梨ちゃんっ!!」
「……アイリちゃん?」
「はあ、はあ…………いや、いいんだ。こっちの話だから」
「汗すごいわよ。大丈夫?」
精神機能が正常を取り戻すまで、十数秒の時間を要した。
「ところで君」
賢治は襟を正して言った。
「なにかしら」
「君は勉学にひどく無頓着なようだ。国民の堕落は国家の堕落。日本の未来に君が影を落としている。わかるか? わからないやつには何時間でも説教する他ない。ちょっと来たまえ、わたしが指導してやる」
女の方へずかずかと歩み寄り、手首を掴む。……掴もうとして、失敗した。
「ん?」
もう一度掴もうとして、またも失敗する。不審に思い手元を見ると、奇異な光景が目に入った。
掴もうとした手のひらが、女の服を透過したのだ。いや、服どころか手首まで。何度握ってみても感触はなく、空を切るばかり。女の姿はそこにあるにもかかわらず。
「いくらやっても変わらないわよ。コレはホログラムだから」
「ホログラムっ!?」
賢治は仰天した。
にわかには信じられない。今度は女の胸に手を添えた。やはり、感触はない。
「本当なのか……」
「ねぇ、もしホログラムじゃなかったらセクハラよ。逮捕案件よ」
「ああ、それはそれとして。わたしが知らない間に、日本の科学技術はここまで進んでいたのか。いや、しかし、ホログラムということは、本物の君はどこに? 君は一体何者なんだ?」
「ふふん」
待っていましたとばかりに、女は胸(触れない)を張った。
「よくぞ聞いたわね。あたしは文部科○省に属する政府秘密組織の一つ、グローバルキャリアデザイン課(GCDD)の幹部よ」
「グローバルキャリアデザイン課?」
「ふふ、一般人のあなたが名前を聞けるだけでも光栄なことよ。なにせ、GCDDの機密性は折り紙付き。メンバーは全員、他部署からの転属で集まったにもかかわらず、元同僚でさえ我々の存在について口をつぐむわ」
「……それは」
『閑職に追いやられた事情を慮っているのでは?』と、賢治は口に出さなかった。
「あ、ちなみに、ホログラムの容姿は実際のあたしとは全く異なるわ。あたし四十代だし」
「おぉ……」
「そしてっ!」
落胆する間も与えず、女はまくしたてる。
「ここからが大事よ。あたしたちGCDDの提案で、政府はある政策方針を決定したの」
「政策方針?」
「ええ」
すぅ、と女は息を吸った。
「現代日本を取り巻く、行き過ぎた知性主義・学歴主義、中身を失った空虚な権威による支配構造、長期的な国益を重視すると言いつつ、その実、怠業を誤魔化す隠れ蓑に過ぎない教育施策、資本主義の成熟による格差社会、増える非正規、のさばるニート、諸々の問題を解決するための抜本的な改革こそが我々の使命。導き出されたのは、拝金主義の末に形骸化し、名ばかりとなった私立大学教育の解体・刷新よ。非効率な下等教養教育を全面的に撤廃し、浮動となった学生たちには、我々が提案する究極に先鋭的かつ実利的な訓練を受講してもらうわ。理不尽な社会にギヤソルジャーとして赴くための数々の能力、強いストレスに耐えうるためには電気椅子による拷問を、会社の人質たる扶養家族を獲得するためには野生味溢れる恋愛行動学を実技で会得、この訓練を受講すれば、いかな醜形男女であろうとも、三分で着床までの段階を経験できることを約束するわ。他にも、24時間戦うために前頭皮質周辺を切除、社内部署同士の緩衝材となるべく愛されキャラクターの確立、受ける菓子折りランキングの伝授、エトセトラエトセトラ、他にも数多の教育を予定しているわ。どう、素晴らしいでしょう」
言い切って、満足そうな笑顔。
「ほとんど聞き取れなかったが、つまり?」
「この学校は取り潰すわ」
「マイガッ(my god)」
賢治は頭を抱えた。
「嘆いても無駄よ。教育の神は死んだ」
「嘘だぁ……そんな暴挙が認められるはずがない」
幼児のように耳をふさぎ、イヤイヤと頭を振る。学生という自己証明を奪われた男は、いかにも惨めだ。
「さっき言ったでしょう、この計画は政府公認。しかも秘密裏に進められている。もはやあなたが打てる手立てはない、受け入れる以外にはね」
「では……秘密裏の計画をわたしに話した理由は?」
賢治はゆるゆると憔悴した顔を上げる。路上に置き去られた子犬のような様相が、女の胸を打ったか、どうか。彼女はゆっくりと語りだした。
「あたしはおよそ半年間、この大学を観察してきたわ。構内の監視カメラを通して、空っぽになった教室を見てきた。それが仕事とはいえ、退屈だった。だーれもいない空白の場所。つまらないから、明日にでも取り壊した方がいいと思った。だって、壊して困る人がいないんだもの。でもね――」
不意に、女の瞳が向けられた。ホログラムであるというのに、琥珀色の虹彩には慈悲が浮かんでいる。
「そんなある日、あなたを見つけたの。チャイムの通りに、規則正しく教室を行き来する人影。はじめは妖精か何かかと思ったわ。けれど、よく観察してみると、彼が人間であることがわかった。毎日毎日、真面目に勉強しながら、登校しない人間の愚痴を言ってる。ふふ、全部聞いてたのよ。だからわかった。こんなに愚かで人間らしい人が、妖精なわけないもの」
細い指が賢治の頬を撫でた。レーザー光の集積である虚像には、確かに温もりが。
「あなたはきっと、意固地になっていただけでしょうけど……少なくともあたしは、あなたのことを尊いと思うわ。あなたほど大学にこだわる人間が一人でもいるのなら、大学を取り潰さなくてもいいんじゃないかって。けれど、ごめんなさい。さすがに学生一名のためだけに例外は認められない。だから、同情するわ、賢治くん。あたしにできることはそれだけ。本当に、ごめんなさい」
多弁だった女の言葉が、それきり途絶えた。
語られた内容は希望を断つものだったが、賢治は取り乱さない。頭の中では、全く別のことを考えていた。
他人に名前を呼ばれることが、まるで何年振りかのようだ、と。
親元を離れて三年の間、賢治は独りだった。狷介な性格は友人を遠ざけ、生来の尊大さは家族に便りを送ることさえ許さなかった。学業にこだわり、怨嗟を吐き続けることで隠していた孤独が、背負いきれぬ質量を持つまで育っていたこと。
「ふっ……う……ぐぅっ………」
自覚したとき、賢治は大粒の涙を流していた。
「ううぅ~~……ひぃいいいいんっ…………わたしは、わたしにはもう、信じられるものなんて、一つもっ……!!」
「ナニも、シんジナクてイイのヨ」
「え?」
見上げると、女から表情が消えていた。顔には、安っぽいポリゴンのような無表情が張り付けられている。不自然な様子に、涙も引っ込む。混乱する賢治をよそに、女は続けた。
「ナニも、シんジナクてイイのヨ。だって、コレハ、ユめナンだから」
妙に、調子の外れた声。そのうえ、女との間に膜が張ったように、声は遠く聞こえた。すぐには意味を受け取れない。賢治は言葉を反芻した。
「ダッテ、コレハ、ユメナンダカラ……だって、これは、ゆめなんだから……だって、これは、夢なんだから」
一旦、息を飲み込む。
「夢っ!?」
「だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから」
壊れたラジカセのように、女から同じ台詞が繰り返される。
「ま、待て待て待てっ、夢って、全部が夢なのかっ!? こんなにダラダラと読ませておいてっ!! 夢オチは恥ずべき行為だぞっ、おいっ!!」
いくら問い詰めても、返ってくる言葉は変わらない。同じ台詞が繰り返される。
「だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから」
「うわあああああああああああああああああああああっ!!」
――――――――――――――――――――――――――――
「ハッ」
目を覚ましたとき、賢治は自室の床に転がっていた。直ちに、天敵を恐れる草食動物のごとく辺りを見回す。が、悪夢の気配は消え去っていた。
部屋の中は普段通りだ。ヤニが付いて黄ばんだ壁、絡まった配線、食べ残しの弁当。出不精特有の生活感が内部に満ちている。
ひとしきり検分すると、賢治は平静を取り戻した。鈍く痛む間接をさする。
「はて、どうして床に倒れていたんだろう?」
疑問に答える者はなかった。部屋には同棲する女の一人もいない。
「やかましい。ん? 女…………学校…………そうだっ」
電撃に打たれたように、賢治は顔を上げた。フローリングを踏み鳴らして窓際へ向かう。覚悟を決め、さあ来いとばかりにカーテンを開いた。
現れたのは――窓枠に切り取られる、一枚の風景。
整えられた高木。間を行きかう人々。そして、彼らが集う先。陽光に照らされ、堂々と鎮座する崇高なる学び舎、新都社大学。
夢にあったようながらんどうではない。大勢の学生が通い、活気をもたらす街の中心。現に今も、校門から出てきた学生たちがそれぞれの表情をしている。
「あれは全部、夢だったんだ」
もたらされた光景は、賢治の不安をすべて取り除いた。代わりに、愛校心がむくむくと起き上がる。忘れかけていた学生としての幸福。思い出させた悪夢に、感謝の念さえ浮かぶ。
「さて、大学に行くとするかっ」
校舎を背に、自室の玄関へ向かう。
その一歩目を踏み出した瞬間。足裏に何かが張り付いた。
「なんだ?」
拾い上げたのは、一枚の用紙。印刷のない白紙……ではなく、賢治には裏面が見えているようだった。表を見れば、何が書かれているのかすぐにわかる。しかし、賢治は硬直した。照明に透かされ、わずかに見える罫線と文言。唐突に、賢治は酷い頭痛を覚えた。そして、記憶が呼び起こされる。
今日、賢治はすでに大学へ行って、帰ってきた。今日、成績通知の配布がされた。さきほどは、眠っていたのではない、気絶していたのだ。
『ウーッ、ウーッ、ウーッ!』
賢治はサイレンの音を聞いた。音は彼自身の神経回路が発したのであるが、当人はそれに気が付かなかった。どうせ、何処ぞの酔っ払いが昼から暴れたのだろう、と決めつけ――皮肉なことに、本能的な警告がかえって賢治の背中を押した――無意識のうちに、用紙を返す。
畢竟、賢治は見てしまった。用紙のおもて面、ズラリと並ぶ『F(不可)』を。
…………――――あおおぉぉぉぉん――――うぉぉおおおおおん――――…………
慟哭は部屋を突き破り、大学構内にまで届いたという。
しばらくの後、賢治の意識機能は自壊し、その場で気を失った。
程近く、斜め後ろの席。女が座っていた。
賢治は腰をそらしてのけ反った。知らぬ間に背後を取られた驚きもある。が、女の容姿がストライクゾーンの内角高めを抉ったことも無関係ではない。賢治はメガネっ子委員長最萌主義を掲げている。しかし、軽めのギャルまでならいけるクチだった。結婚してやってもいいとさえ考えていた。傲慢である。
「しばらく観察させてもらってたの。あなたって奇特な人ね」
女の声は外見に反して冷たかった。賢治は及び腰になるのをぐっとこらえ、毅然として言葉を返す。
「奇特? 大学生が大学で勉強するのは当然のことだと思うが」
「ふっ、大学で、ね」
皮肉の混じった響き。賢治は眉をひそめた。
「何が言いたい?」
「ここはもう、大学ではないわ。だって、そうでしょう? 教授も学生もいない大学なんてありえないもの。大学というのは建物を指すのではなく、人々の共同体を指すのよ」
「世迷言を。わたしは確かに新都社大学の学生だ。学生証も発行されている。学生は定められた時間に教室を訪ね、勉学に励む。それが規律。規律は絶対だ」
「規律も同じことよ。人のいないところで、規律はただの言葉に過ぎない」
嘲りは“歩く生徒手帳”と呼ばれた男を憤らせるに十分だった。
「では君はっ……誰だか知らないが……わたし以外の連中が正しいと? 学生としての本分を忘れ、腐りきった奴らが?」
両者はにらみ合う。剣呑な雰囲気が充満した。
緊張が破裂する直前。視線をはずしたのは女の方だった。わざとらしく肩をすくめ、ため息を吐いてみせる。
「一理はあると言ってるのよ。いいじゃない、単位なんて土下座で取れば。だって、法哲学よりは将来の役に立ちそうじゃない、土下座」
「サヴィニーは偉大だ」
「ええ、そうね。けれど無意味よ」
「憤怒ぅっ!!」賢治はTシャツを脱ぎ捨てた。「学問を愚弄するか貴様ぁっ!!」
上半身をこれでもかと言わんばかりに見せつける。筋骨を奮い立たせ、漢の威厳を誇示した。たったいま、賢治は全盛期ボ○・サップだった。自己解釈的に。
「貧相な身体ね」女は笑い、鼻息を漏らす。「虫みたい」
「おおぉぉぉぉ…………」
漢はあっさりとくずおれた。試合開始直後に膝をくらったボ○・サップのように。
罵倒に屈したわけではない。女の言葉が過去をよみがえらせたのだ。小学校時代、想い人に浴びせられたセリフは、未だに深く刻まれている。
『賢治くんって虫っぽい。多足類の』
「あああああああっ!! わたしは手足をあわせても四本だからっ!! 多足類の定義からは外れるんじゃないかなっ!? 愛梨ちゃんっ!!」
「……アイリちゃん?」
「はあ、はあ…………いや、いいんだ。こっちの話だから」
「汗すごいわよ。大丈夫?」
精神機能が正常を取り戻すまで、十数秒の時間を要した。
「ところで君」
賢治は襟を正して言った。
「なにかしら」
「君は勉学にひどく無頓着なようだ。国民の堕落は国家の堕落。日本の未来に君が影を落としている。わかるか? わからないやつには何時間でも説教する他ない。ちょっと来たまえ、わたしが指導してやる」
女の方へずかずかと歩み寄り、手首を掴む。……掴もうとして、失敗した。
「ん?」
もう一度掴もうとして、またも失敗する。不審に思い手元を見ると、奇異な光景が目に入った。
掴もうとした手のひらが、女の服を透過したのだ。いや、服どころか手首まで。何度握ってみても感触はなく、空を切るばかり。女の姿はそこにあるにもかかわらず。
「いくらやっても変わらないわよ。コレはホログラムだから」
「ホログラムっ!?」
賢治は仰天した。
にわかには信じられない。今度は女の胸に手を添えた。やはり、感触はない。
「本当なのか……」
「ねぇ、もしホログラムじゃなかったらセクハラよ。逮捕案件よ」
「ああ、それはそれとして。わたしが知らない間に、日本の科学技術はここまで進んでいたのか。いや、しかし、ホログラムということは、本物の君はどこに? 君は一体何者なんだ?」
「ふふん」
待っていましたとばかりに、女は胸(触れない)を張った。
「よくぞ聞いたわね。あたしは文部科○省に属する政府秘密組織の一つ、グローバルキャリアデザイン課(GCDD)の幹部よ」
「グローバルキャリアデザイン課?」
「ふふ、一般人のあなたが名前を聞けるだけでも光栄なことよ。なにせ、GCDDの機密性は折り紙付き。メンバーは全員、他部署からの転属で集まったにもかかわらず、元同僚でさえ我々の存在について口をつぐむわ」
「……それは」
『閑職に追いやられた事情を慮っているのでは?』と、賢治は口に出さなかった。
「あ、ちなみに、ホログラムの容姿は実際のあたしとは全く異なるわ。あたし四十代だし」
「おぉ……」
「そしてっ!」
落胆する間も与えず、女はまくしたてる。
「ここからが大事よ。あたしたちGCDDの提案で、政府はある政策方針を決定したの」
「政策方針?」
「ええ」
すぅ、と女は息を吸った。
「現代日本を取り巻く、行き過ぎた知性主義・学歴主義、中身を失った空虚な権威による支配構造、長期的な国益を重視すると言いつつ、その実、怠業を誤魔化す隠れ蓑に過ぎない教育施策、資本主義の成熟による格差社会、増える非正規、のさばるニート、諸々の問題を解決するための抜本的な改革こそが我々の使命。導き出されたのは、拝金主義の末に形骸化し、名ばかりとなった私立大学教育の解体・刷新よ。非効率な下等教養教育を全面的に撤廃し、浮動となった学生たちには、我々が提案する究極に先鋭的かつ実利的な訓練を受講してもらうわ。理不尽な社会にギヤソルジャーとして赴くための数々の能力、強いストレスに耐えうるためには電気椅子による拷問を、会社の人質たる扶養家族を獲得するためには野生味溢れる恋愛行動学を実技で会得、この訓練を受講すれば、いかな醜形男女であろうとも、三分で着床までの段階を経験できることを約束するわ。他にも、24時間戦うために前頭皮質周辺を切除、社内部署同士の緩衝材となるべく愛されキャラクターの確立、受ける菓子折りランキングの伝授、エトセトラエトセトラ、他にも数多の教育を予定しているわ。どう、素晴らしいでしょう」
言い切って、満足そうな笑顔。
「ほとんど聞き取れなかったが、つまり?」
「この学校は取り潰すわ」
「マイガッ(my god)」
賢治は頭を抱えた。
「嘆いても無駄よ。教育の神は死んだ」
「嘘だぁ……そんな暴挙が認められるはずがない」
幼児のように耳をふさぎ、イヤイヤと頭を振る。学生という自己証明を奪われた男は、いかにも惨めだ。
「さっき言ったでしょう、この計画は政府公認。しかも秘密裏に進められている。もはやあなたが打てる手立てはない、受け入れる以外にはね」
「では……秘密裏の計画をわたしに話した理由は?」
賢治はゆるゆると憔悴した顔を上げる。路上に置き去られた子犬のような様相が、女の胸を打ったか、どうか。彼女はゆっくりと語りだした。
「あたしはおよそ半年間、この大学を観察してきたわ。構内の監視カメラを通して、空っぽになった教室を見てきた。それが仕事とはいえ、退屈だった。だーれもいない空白の場所。つまらないから、明日にでも取り壊した方がいいと思った。だって、壊して困る人がいないんだもの。でもね――」
不意に、女の瞳が向けられた。ホログラムであるというのに、琥珀色の虹彩には慈悲が浮かんでいる。
「そんなある日、あなたを見つけたの。チャイムの通りに、規則正しく教室を行き来する人影。はじめは妖精か何かかと思ったわ。けれど、よく観察してみると、彼が人間であることがわかった。毎日毎日、真面目に勉強しながら、登校しない人間の愚痴を言ってる。ふふ、全部聞いてたのよ。だからわかった。こんなに愚かで人間らしい人が、妖精なわけないもの」
細い指が賢治の頬を撫でた。レーザー光の集積である虚像には、確かに温もりが。
「あなたはきっと、意固地になっていただけでしょうけど……少なくともあたしは、あなたのことを尊いと思うわ。あなたほど大学にこだわる人間が一人でもいるのなら、大学を取り潰さなくてもいいんじゃないかって。けれど、ごめんなさい。さすがに学生一名のためだけに例外は認められない。だから、同情するわ、賢治くん。あたしにできることはそれだけ。本当に、ごめんなさい」
多弁だった女の言葉が、それきり途絶えた。
語られた内容は希望を断つものだったが、賢治は取り乱さない。頭の中では、全く別のことを考えていた。
他人に名前を呼ばれることが、まるで何年振りかのようだ、と。
親元を離れて三年の間、賢治は独りだった。狷介な性格は友人を遠ざけ、生来の尊大さは家族に便りを送ることさえ許さなかった。学業にこだわり、怨嗟を吐き続けることで隠していた孤独が、背負いきれぬ質量を持つまで育っていたこと。
「ふっ……う……ぐぅっ………」
自覚したとき、賢治は大粒の涙を流していた。
「ううぅ~~……ひぃいいいいんっ…………わたしは、わたしにはもう、信じられるものなんて、一つもっ……!!」
「ナニも、シんジナクてイイのヨ」
「え?」
見上げると、女から表情が消えていた。顔には、安っぽいポリゴンのような無表情が張り付けられている。不自然な様子に、涙も引っ込む。混乱する賢治をよそに、女は続けた。
「ナニも、シんジナクてイイのヨ。だって、コレハ、ユめナンだから」
妙に、調子の外れた声。そのうえ、女との間に膜が張ったように、声は遠く聞こえた。すぐには意味を受け取れない。賢治は言葉を反芻した。
「ダッテ、コレハ、ユメナンダカラ……だって、これは、ゆめなんだから……だって、これは、夢なんだから」
一旦、息を飲み込む。
「夢っ!?」
「だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから」
壊れたラジカセのように、女から同じ台詞が繰り返される。
「ま、待て待て待てっ、夢って、全部が夢なのかっ!? こんなにダラダラと読ませておいてっ!! 夢オチは恥ずべき行為だぞっ、おいっ!!」
いくら問い詰めても、返ってくる言葉は変わらない。同じ台詞が繰り返される。
「だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから。だって、コレハ、ユめナンだから」
「うわあああああああああああああああああああああっ!!」
――――――――――――――――――――――――――――
「ハッ」
目を覚ましたとき、賢治は自室の床に転がっていた。直ちに、天敵を恐れる草食動物のごとく辺りを見回す。が、悪夢の気配は消え去っていた。
部屋の中は普段通りだ。ヤニが付いて黄ばんだ壁、絡まった配線、食べ残しの弁当。出不精特有の生活感が内部に満ちている。
ひとしきり検分すると、賢治は平静を取り戻した。鈍く痛む間接をさする。
「はて、どうして床に倒れていたんだろう?」
疑問に答える者はなかった。部屋には同棲する女の一人もいない。
「やかましい。ん? 女…………学校…………そうだっ」
電撃に打たれたように、賢治は顔を上げた。フローリングを踏み鳴らして窓際へ向かう。覚悟を決め、さあ来いとばかりにカーテンを開いた。
現れたのは――窓枠に切り取られる、一枚の風景。
整えられた高木。間を行きかう人々。そして、彼らが集う先。陽光に照らされ、堂々と鎮座する崇高なる学び舎、新都社大学。
夢にあったようながらんどうではない。大勢の学生が通い、活気をもたらす街の中心。現に今も、校門から出てきた学生たちがそれぞれの表情をしている。
「あれは全部、夢だったんだ」
もたらされた光景は、賢治の不安をすべて取り除いた。代わりに、愛校心がむくむくと起き上がる。忘れかけていた学生としての幸福。思い出させた悪夢に、感謝の念さえ浮かぶ。
「さて、大学に行くとするかっ」
校舎を背に、自室の玄関へ向かう。
その一歩目を踏み出した瞬間。足裏に何かが張り付いた。
「なんだ?」
拾い上げたのは、一枚の用紙。印刷のない白紙……ではなく、賢治には裏面が見えているようだった。表を見れば、何が書かれているのかすぐにわかる。しかし、賢治は硬直した。照明に透かされ、わずかに見える罫線と文言。唐突に、賢治は酷い頭痛を覚えた。そして、記憶が呼び起こされる。
今日、賢治はすでに大学へ行って、帰ってきた。今日、成績通知の配布がされた。さきほどは、眠っていたのではない、気絶していたのだ。
『ウーッ、ウーッ、ウーッ!』
賢治はサイレンの音を聞いた。音は彼自身の神経回路が発したのであるが、当人はそれに気が付かなかった。どうせ、何処ぞの酔っ払いが昼から暴れたのだろう、と決めつけ――皮肉なことに、本能的な警告がかえって賢治の背中を押した――無意識のうちに、用紙を返す。
畢竟、賢治は見てしまった。用紙のおもて面、ズラリと並ぶ『F(不可)』を。
…………――――あおおぉぉぉぉん――――うぉぉおおおおおん――――…………
慟哭は部屋を突き破り、大学構内にまで届いたという。
しばらくの後、賢治の意識機能は自壊し、その場で気を失った。