薄暗い病院の中、僕はもうすぐ死ぬ。
息苦しくて息苦しくて仕方がない夜。
顔に張り付いた呼吸器が苦しい。
医者に余命宣告はされていた。
残り僅か1週間。
いつからだっただろうか、家族は来なくなっていた。
僕が死ぬ姿を見たくないからだそうだ。
ここ数十年で、排泄と人の死に関わることはとにかく隠されるようになった。
死に目に家族が立ち会うような時代ではない。
昔は家族に看取られるのが通例だった事が今では信じられない。
頬に涙が伝う。
僕は、たった1人で死に立ち向かわなければならない。
昔のアニメやドラマで見たような、幸せな死などない。
1日に何度か無機質なロボットのアームに点滴を施されることだけが僕の日常の全て。
人と接触する機会と言えば、ごく稀に医者が来る。ただそれだけだ。
会話はない。したくても息が苦しくて、出来ない。
心が寂しく、虚しい。
毎日白い天井を眺めては涙を垂らした。
きっと、いつか治る病気ならば退院して、その後のことを考えることが出来ただろう。
けれど僕はここで死ぬ恐怖と戦うことしか出来ない。
孤独で寂しい日々。
そんなある日、ふと僕の手を誰かが握った。
霞む視界の中、その手の主を見る。
医者ではない。華奢で儚げな女性。
彼女は綺麗な所作でお辞儀をして、僕に自己紹介した。
「私はノア。」
家族より派遣されたアンドロイドだと説明してくれた。
「あなたは一人じゃないよ。
私ね、あなたが死ぬまでずっと一緒にいる、そのために作られたアンドロイドなの。」
「……」
僕は何も答えなかった。いや、答えられなかった。
「御家族の意志なの。死に目に会うのは辛いけど、1人にするのも辛いからって、私を。
あなたが死んだらね、私もスクラップにかけられるの。そういう決まりだから。一緒に死ぬ人がいるって考えれば、怖くないでしょう?」
彼女は笑った。
僕ははっきりしない意識の中、微かな希望を感じた。
ノアの方舟。
限られた人数だけ死から逃れられるような、そんな希望を感じさせられる名前。
生きるという希望ではなく、死後の、知らない世界をこの子と過ごせるかもしれないという希望。
僕は彼女を見た。彼女も僕を見た。
ノアの手は暖かかった。
返答できない僕に、ノアはよく話してくれた。
心地いい声。楽しい話題。
ああ、この子と死ねるなんて、なんて幸せなことなんだろう。
苦しかった呼吸はやがて静かになり、
僕は全身の力を抜いた。
まとめて読む
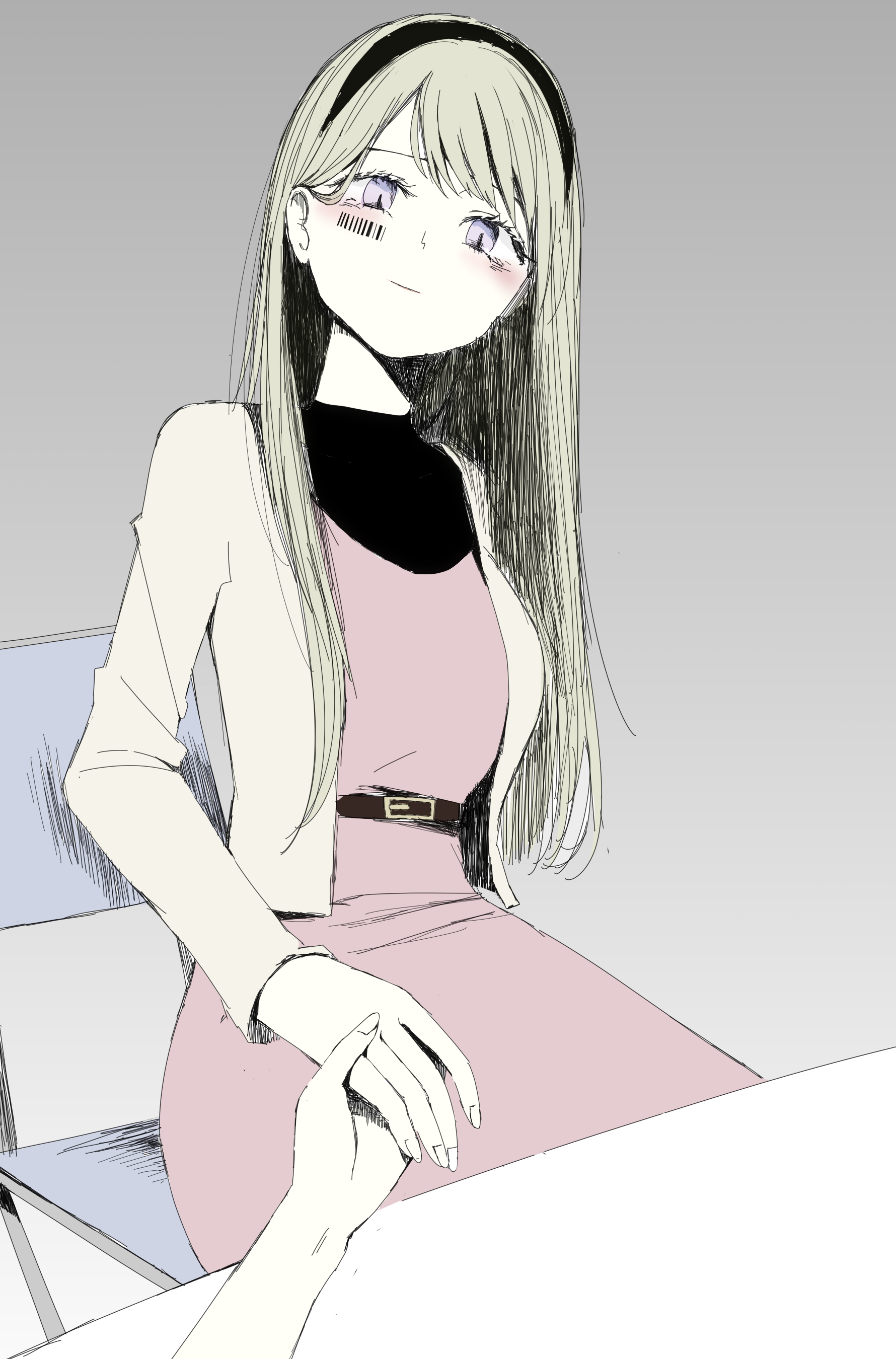
「ノア、今回もありがとう。ちゃんと録画は出来たかね?」
「はい。院長。御家族にもお見せできる品質かと思います」
「ありがとう。じゃあ次の現場に入ってくれ」