1.ラブレター
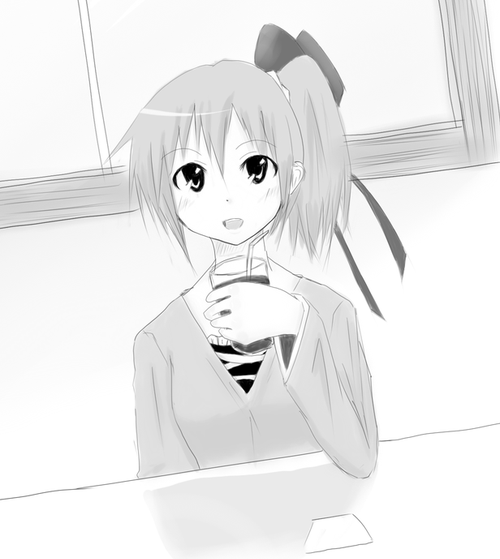
01.
あたしさ、馬場ってもっとヤなやつだと思ってた。
面と向かってそう言われて馬場天馬はひょいと眉を上げた。
「なんだかんだで間違ってないかもよ」
少なくとも善人と称されたことはない。
「またまたァ、そんなこと言っちゃってさ」
ミハネは愛猫を自慢する時のように顔をにやつかせて、
「実は結構、優しいくせに」と言ってきた。語尾をちょっと伸ばしていて油断しきった声。
思わず顔を背けた。恥ずかしくって顔なんかまともに見られたものじゃない。なんでそういうことを気安く口にできるのだ。
これだから女って生き物はよくわからない。
ミハネはストローからアイスコーヒーを吸い上げながら、窓の向こうの交通に目をやっている。大通りに面したコーヒーショップは繊細な冷房調節によって快適すぎるほどだった。
午後の日差しがグラスの中の氷に当たって乱れ散っている。
天国とはここのことではあるまいか、と天馬は夢見心地のまま思った。
「なァ」
ミハネが顔を上げる。
「なあに」
「おまえ、ホントに俺のこと好きなの?」
ぽかん、とミハネは一瞬なにを言われているのかわからなかったようだった。
「そうだけど。人の話、聞いてんの?」
聞いてたけど信じられません、とは言えなかった。
五月の半ば、昼下がり。
天馬は突然、告白された。
02.
その日も焼きそばパンだった。強く掴むと汁がこぼれてくるやつだ。屋上の給水塔の上に胡坐をかいて、ビニールを破る。
いじめられっ子としての壮絶な人生にピリオドが打たれたからと言って天馬の人生に劇的な向上は見られなかった。
相変わらず昼飯は一人きりだし授業はマジメに聞く以外にすることがない。
しかし放課後に幼馴染に暴行を受けることはなくなった。それだけでもマシだと思わねばなるまい、とパンをしゃぶりながら思うけれど、人間とは傲慢なもので、慣れてくると有り難味を感じないどころか不足を訴え始める。
ああ、会話がしたい。猛烈に。
学校に来てから帰るまで英語の教師に当てられた英文朗読でしか声帯を使う機会がないなんて人類が滅ぶことよりも悲しい。
ある意味――と天馬は思う。
(いじめられてたけど、雨宮たちはオレにとってたったひとつの接点だったのかもしれない)
虐待されてた頃を懐かしむなんてな、と自嘲気味に笑ってみせたところで胸の中を這いずり回る焦慮とも不安とも言いがたい孤独感は消えなかった。
今は誰も天馬を傷つけない代わり、相手にしようともしてくれない。
チャイムが鳴った。地上の騒々しいざわめきが緩やかに静まっていく。
オレはどこに行けばいい。
「――というわけで、体育祭が近いんだからな、おまえらちゃんと練習しとけよー」
かったるそうに担任の安野先生ことヤスポンが教壇に両手をついていた。
何人かが「ハーイ!」と元気よく返事した後にゲラゲラ笑っていた。
こいつらハシが転がっても面白いんだろうな、と天馬は頬杖をついて名前も知らぬクラスメイトを眺めている。個人の自由だけれど、髪を染めて何かいいことがあるんだろうか。
「まだ紅白どっちになるか分からないがな」とヤスポンがよく通る声を響かせた。彼は野球部の顧問であり、新婚ホヤホヤの二十九歳であり、ややイケメンであり、常日頃から独身貴族の古文教師、清田にいつか刺されるに違いないと噂されていた。動機は嫉妬。ぜひ実現するといい。
「もし勝ったら全員分のアイスを買ってやろう!」
えー現金くれよ、と不平を漏らした野球部セカンド門野の耳を引っ張りながらヤスポンは部活へと出かけていった。
ハァ、とため息がこぼれる。
アイスなら腐るほど妹のナギサが買ってくるが、友達は冷蔵庫に入ってやしないし、ヤスポンが配ってくれたりもしない。
(体育祭かぁ……)
カバンを背負いながら天馬は顔をしかめた。いい思い出が何一つない言葉だ。
過去、学校行事と名のつくものすべてをサボタージュし尽くしてきた天馬だったが、体育祭の練習に参加させられたことは何度かある。
生来、人と調和することが苦手だった。だからラジオ体操で一人だけリズムがズレているし、大縄跳びで三回以上飛べないし、二人三脚で相手ともつれ合ってグラウンドに鼻を打ちつける。
こんな行事を初めて考案したヤツは何が目的だったのだろう、ただ活発に動き回る少女が見たいだけの変態だったのではなかろうか。天馬は半ば本気でそう疑っていた。他のメリットが見当たらなかった。
(まァでも、ホントに楽しみと言ったらそれぐらいだよなァ――)
閑散とし始めた教室の中をちらりと盗み見る。
赤いスカーフ、紺のスカート、白いセーラー。
卒業したら毎日この制服が見られないというだけで死にたくなる。
特にあの加賀見空奈の姿が見られなくなるのはとても惜しい――
と、それまで友人らと談笑していたカガミが猛然と振り返って、長い黒髪が巻き上がった。視線と視線が交通事故を起こし、天馬の体を緊張が駆け抜けた。
幼い頃から鍛えられた鋭敏な彼女の感覚が自分に向けられている視線を受信したのだが、そんなこと天馬が知る由もなかった。
カガミが何か言おうとわずかに口を開きかける。
(……っ!)
それを待たずして天馬は引き戸から逃げ出した。
背中の向こうで、慌しく友人たちに別れの挨拶を交わすカガミの声が聞こえた。
(あのバカ……)
天馬は誰もいない旧校舎、四階の踊り場でようやく立ち止まった。
「話しかけるなって言っただろ」
「申し訳ありません」十七歳の少女がするに相応しくない丁寧さでカガミは謝罪した。
「挨拶くらいなら、よろしいかと思って」
「前から聞こうと思ってたんだけど」苛立たしげに爪先で床を叩きながら天馬は聞いた。「なんでオレにだけ敬語?」
「さあ」
カガミは教科書を見る学生と瓜二つの顔をしていた。表情がまったく読めない。
無口で愛想がないなんて転校生として不都合しそうな個性だったけれど、カガミはその人形じみた容姿から同級生に大層手厚く扱われている。一言で言うと、恐ろしいほど顔がよろしいから、何をしても大半は許されてしまう。
「だからこそ、いいか、だからこそなんだよ」天馬は口下手だ。
「おまえは学校に通ったことがないから分からないだろうけど、ここはとってもひどい場所なんだ。今は綺麗に見えるかもしれねえがな、ちょっとでも人と違うことをするとバシンと叩かれるんだ」
「腕に自信ならあります」
「……? いや、叩かれるってそういう意味じゃない。乱暴はよくない。叩かれるってのは、ハブられるってこと」
「わかってます」
「からかってるなオマエ」
「はい」いかにも楽しげなやり取りに思われるかもしれないがカガミの表情は先ほどから青写真のように固定されたままだ。
こいつラジカセなんじゃねえかな、と天馬はたまに思う。もしくはヒューマノイドインターフェースだ。
「おまえ、転校生だってこと自覚しろよ。今が一番大切な時期なんだ」
受験で一生が変わるんだぞ、と熱弁を振るう教師のような口調で天馬は拳をぶんぶん振った。
「ここでうまく溶け込めれば、後はもう大丈夫なんだけど、ところがどっこい転校生のカガミさんが」そこで自分の胸をバシッと叩く。
カガミの興味は床の染みの方に移りかけているが、天馬は気づかない。
「クラスでハブられ、昼休みは屋上で焼きそばパン食ってる馬場くんと友達だってことがバレてしまいました。わーカガミさんってそういう人だったんだーうわーひくわードン引きだわー。こうなります」
「だから、お昼ご飯は一緒に食べましょうって言ったじゃないですか」
「人の話聞いてた? オレといるだけで問題なの。クチ利いちゃダメなの。オレが一人メシかどうかは問題じゃねーってか前提だから。オーライ?」
「シャラップ」
「なんだとてめえコラ」
「私が誰と友達でいようと、私の勝手です」
カガミは小首を傾げて、不審そうに聞いた。
「いけませんか?」
「いや……まあ、オマエが正しいんだけど、世の中ってのは複雑なんだよ。うん。ああ、なんかオレって大人だなァ」
「これから部活見学に行くんですけど」カガミは抜群のスルースキルでポーズを決めている天馬を無視した。
「ついてきてくれませんか」
「だーかーら、オレがいると」
「弓道部にいくんです」
「弓道部? うちの学校にそんなのあったっけ」
「体育館の裏手でいつも練習していますから、目立たないんでしょう」
「へえ。あ、百円はやらないぜ」
「……?」
ほんのわずかに首が傾いでいるので、彼女が意味を理解していないことが判明した。
カガミってテレビ見ないのかなァ、と天馬はカガミの日常に思いを馳せた。窓辺で紅茶とか飲んでそう。ベッドは天蓋つきだな。
「あの、馬場様」
「呼び捨てでいいよ。おかしいだろ、様づけなんて。同級生だぜ?」
よく今まで人前で名前を呼ばれる機会に出くわさなかったものだ。今更ながら最悪の事態を想像するとぞっとした。
「じゃあ」カガミはスカーフの位置を直すために手を挙げ、天馬はいかがわしい想像をした。
「天馬」
「……」
「天馬?」
「呼び捨てって下の名前かい」
「ダメですか」
「いいよ、うん、いいよ、もう!」恥ずかしがってるこっちがバカみたいだ。
天馬は一飛びで三段駆け上がると、腰を下ろした。古い木材が苦しげに軋んだ。
「あの、体育館の裏って道路に面してるじゃないですか」
「ああ」確かにすぐ外に割りと交通の多い道路があった。渡るとファーストフード店やゲームセンターのあるショッピングモールがあり、放課後は制服姿の若者で一杯になる。
「そこから、弓道部の練習が見えるんです。植え込みがあるから、こっちからは見えにくいんですけど」
「ふうん」
「それで、もしお時間があったら、そこから練習を見ていてくれませんか」
「なんで?」
天馬はアホみたいに聞き返した。当然ながらカガミは黙り込むしかない。
「まあ時間はあるけど」
カガミが顔を上げた。
「でもダメだな」
「どうして」
「そんなことしてみ。オレ、見つかったら変態だろ、どっからどう見ても」
「……それは……確かに……」
「え、そこで確かにとか言うなよ。嘘でもいいからそんなことないよ!って言ってよ。え、嘘。マジかよ。泣きたい」
「どうぞ」
「どうぞじゃねーよ! ……とにかく、ダメったらダメ。オレとの接点はできるだけ少ない方がいい。
オレだってなァ、これでも少しは心配してんだからな。せっかく念願のジョシコーセーになれたんだろ。台無しになる前に危ない橋からは降りとけ」
矢継ぎ早に喋ったものだから息が切れた。ふう、とカガミを見ると心なしか目つきが鋭くなっている気がする。
「え、オレ悪いこと言ってなくね? なにその目つき怖い」
何か蓄えるかのような間を置いた後、カガミは
「弱虫」
と呟いて、去っていった。
後は追わなかった。
急ぎすぎたセミが、どこかで鳴いている。
(言われなくても、わかってるってんだよ)
誰もいない、この世界から忘れ去られた階段で、天馬は膝を抱えた。
(オレが苦しめばいい)
(オレでいい。おまえじゃなくていい)
(おまえを傷つけるより、ずっといい)
カガミとは先月、とある事件を通じて知り合った。その結果として彼女は天馬の通う私立武々羅学園に転校してきたのだ。
この学校という地獄の釜の底で、たった一人天馬が心を許している友達。
今頃、部活の見学でもしているのだろうか。
確かこの間、テニス部に体験入部して三年のレギュラーメンバーよりも鋭いスマッシュをぶちかまして先輩は一週間寝込んだらしい。超人はこれだから困る。
(まァアブナイ組織の一員なんだから、当たり前なんだけど……)
物語の登場人物のような彼女と知り合いであることを思うと誇らしい気分になってきて、表情が幾分か安らいだ。
そして、そんな無防備な天馬の下に、『それ』は爆撃されたのだった。
まず最初に見た。次に何らかの通知だと思った。
退学通知とかそういったもの。悪いことはしていないけれど、パトカーを見かけたら逃げるのと同じ心理だ。
しかしそれは否定された。なぜなら下駄箱から取り出した封筒には、個人の名が署名されていたからだ。
「これって」
今時いまだに、こんなものを送ってくるやつが生き残っているなんて!と天馬は驚愕した。
丸っこい字で差出人の名前が書かれている。
『鴉羽魅羽』
知らない名だった。
そして忘れられなくなる名だった。
03.
「もしもーし。生きてますかー?」
「へっ? あ、わ、悪い!」
いつの間にか物思いに沈んでしまっていたらしい。初対面の相手を前にして失礼すぎた、と慌てて平謝りするとミハネは気にした様子もなく手を振った。気さくな人物のようだ。
「緊張するよね、そりゃあさ、いきなりだもんね」
ミハネは飲み終わったグラスの氷を、ストローでかき混ぜる。
「でも、我慢できなくなっちゃって。下駄箱の前でだいぶ迷ったんだけど、ええい女は度胸!って思って入れちった」
「凄い……な。俺にはできない」
どんな口調にしたらいいのか分からず、語尾が濁ってしまった。
教科書はどこだ、学校は何をしてる。
ミハネは身を乗り出すようにして天馬の顔を見上げた。
「ラブレター書いたことない?」
「ない」
やばい無愛想だと思われたんじゃなかろうか、天馬は斜向かいでメニューを聞いているウェイトレスに念で助けを要請した。
ミハネは気にした様子はないが、それもコミュニケーション能力に長けた人間特有の隠蔽なのではないか、と疑えないこともない。
「告白したことも、ないし」
「じゃあ、今度ください」
「何を?」
「ラブレター」
ああ、こいつ苦手だ、と思った。
耳が熱くなるのを感じる。にやにや笑いを浮かべたウェイトレスが通り過ぎる。
ミハネは視線を逸らしてくれそうになかった。
その日も焼きそばパンだった。強く掴むと汁がこぼれてくるやつだ。屋上の給水塔の上に胡坐をかいて、ビニールを破る。
いじめられっ子としての壮絶な人生にピリオドが打たれたからと言って天馬の人生に劇的な向上は見られなかった。
相変わらず昼飯は一人きりだし授業はマジメに聞く以外にすることがない。
しかし放課後に幼馴染に暴行を受けることはなくなった。それだけでもマシだと思わねばなるまい、とパンをしゃぶりながら思うけれど、人間とは傲慢なもので、慣れてくると有り難味を感じないどころか不足を訴え始める。
ああ、会話がしたい。猛烈に。
学校に来てから帰るまで英語の教師に当てられた英文朗読でしか声帯を使う機会がないなんて人類が滅ぶことよりも悲しい。
ある意味――と天馬は思う。
(いじめられてたけど、雨宮たちはオレにとってたったひとつの接点だったのかもしれない)
虐待されてた頃を懐かしむなんてな、と自嘲気味に笑ってみせたところで胸の中を這いずり回る焦慮とも不安とも言いがたい孤独感は消えなかった。
今は誰も天馬を傷つけない代わり、相手にしようともしてくれない。
チャイムが鳴った。地上の騒々しいざわめきが緩やかに静まっていく。
オレはどこに行けばいい。
「――というわけで、体育祭が近いんだからな、おまえらちゃんと練習しとけよー」
かったるそうに担任の安野先生ことヤスポンが教壇に両手をついていた。
何人かが「ハーイ!」と元気よく返事した後にゲラゲラ笑っていた。
こいつらハシが転がっても面白いんだろうな、と天馬は頬杖をついて名前も知らぬクラスメイトを眺めている。個人の自由だけれど、髪を染めて何かいいことがあるんだろうか。
「まだ紅白どっちになるか分からないがな」とヤスポンがよく通る声を響かせた。彼は野球部の顧問であり、新婚ホヤホヤの二十九歳であり、ややイケメンであり、常日頃から独身貴族の古文教師、清田にいつか刺されるに違いないと噂されていた。動機は嫉妬。ぜひ実現するといい。
「もし勝ったら全員分のアイスを買ってやろう!」
えー現金くれよ、と不平を漏らした野球部セカンド門野の耳を引っ張りながらヤスポンは部活へと出かけていった。
ハァ、とため息がこぼれる。
アイスなら腐るほど妹のナギサが買ってくるが、友達は冷蔵庫に入ってやしないし、ヤスポンが配ってくれたりもしない。
(体育祭かぁ……)
カバンを背負いながら天馬は顔をしかめた。いい思い出が何一つない言葉だ。
過去、学校行事と名のつくものすべてをサボタージュし尽くしてきた天馬だったが、体育祭の練習に参加させられたことは何度かある。
生来、人と調和することが苦手だった。だからラジオ体操で一人だけリズムがズレているし、大縄跳びで三回以上飛べないし、二人三脚で相手ともつれ合ってグラウンドに鼻を打ちつける。
こんな行事を初めて考案したヤツは何が目的だったのだろう、ただ活発に動き回る少女が見たいだけの変態だったのではなかろうか。天馬は半ば本気でそう疑っていた。他のメリットが見当たらなかった。
(まァでも、ホントに楽しみと言ったらそれぐらいだよなァ――)
閑散とし始めた教室の中をちらりと盗み見る。
赤いスカーフ、紺のスカート、白いセーラー。
卒業したら毎日この制服が見られないというだけで死にたくなる。
特にあの加賀見空奈の姿が見られなくなるのはとても惜しい――
と、それまで友人らと談笑していたカガミが猛然と振り返って、長い黒髪が巻き上がった。視線と視線が交通事故を起こし、天馬の体を緊張が駆け抜けた。
幼い頃から鍛えられた鋭敏な彼女の感覚が自分に向けられている視線を受信したのだが、そんなこと天馬が知る由もなかった。
カガミが何か言おうとわずかに口を開きかける。
(……っ!)
それを待たずして天馬は引き戸から逃げ出した。
背中の向こうで、慌しく友人たちに別れの挨拶を交わすカガミの声が聞こえた。
(あのバカ……)
天馬は誰もいない旧校舎、四階の踊り場でようやく立ち止まった。
「話しかけるなって言っただろ」
「申し訳ありません」十七歳の少女がするに相応しくない丁寧さでカガミは謝罪した。
「挨拶くらいなら、よろしいかと思って」
「前から聞こうと思ってたんだけど」苛立たしげに爪先で床を叩きながら天馬は聞いた。「なんでオレにだけ敬語?」
「さあ」
カガミは教科書を見る学生と瓜二つの顔をしていた。表情がまったく読めない。
無口で愛想がないなんて転校生として不都合しそうな個性だったけれど、カガミはその人形じみた容姿から同級生に大層手厚く扱われている。一言で言うと、恐ろしいほど顔がよろしいから、何をしても大半は許されてしまう。
「だからこそ、いいか、だからこそなんだよ」天馬は口下手だ。
「おまえは学校に通ったことがないから分からないだろうけど、ここはとってもひどい場所なんだ。今は綺麗に見えるかもしれねえがな、ちょっとでも人と違うことをするとバシンと叩かれるんだ」
「腕に自信ならあります」
「……? いや、叩かれるってそういう意味じゃない。乱暴はよくない。叩かれるってのは、ハブられるってこと」
「わかってます」
「からかってるなオマエ」
「はい」いかにも楽しげなやり取りに思われるかもしれないがカガミの表情は先ほどから青写真のように固定されたままだ。
こいつラジカセなんじゃねえかな、と天馬はたまに思う。もしくはヒューマノイドインターフェースだ。
「おまえ、転校生だってこと自覚しろよ。今が一番大切な時期なんだ」
受験で一生が変わるんだぞ、と熱弁を振るう教師のような口調で天馬は拳をぶんぶん振った。
「ここでうまく溶け込めれば、後はもう大丈夫なんだけど、ところがどっこい転校生のカガミさんが」そこで自分の胸をバシッと叩く。
カガミの興味は床の染みの方に移りかけているが、天馬は気づかない。
「クラスでハブられ、昼休みは屋上で焼きそばパン食ってる馬場くんと友達だってことがバレてしまいました。わーカガミさんってそういう人だったんだーうわーひくわードン引きだわー。こうなります」
「だから、お昼ご飯は一緒に食べましょうって言ったじゃないですか」
「人の話聞いてた? オレといるだけで問題なの。クチ利いちゃダメなの。オレが一人メシかどうかは問題じゃねーってか前提だから。オーライ?」
「シャラップ」
「なんだとてめえコラ」
「私が誰と友達でいようと、私の勝手です」
カガミは小首を傾げて、不審そうに聞いた。
「いけませんか?」
「いや……まあ、オマエが正しいんだけど、世の中ってのは複雑なんだよ。うん。ああ、なんかオレって大人だなァ」
「これから部活見学に行くんですけど」カガミは抜群のスルースキルでポーズを決めている天馬を無視した。
「ついてきてくれませんか」
「だーかーら、オレがいると」
「弓道部にいくんです」
「弓道部? うちの学校にそんなのあったっけ」
「体育館の裏手でいつも練習していますから、目立たないんでしょう」
「へえ。あ、百円はやらないぜ」
「……?」
ほんのわずかに首が傾いでいるので、彼女が意味を理解していないことが判明した。
カガミってテレビ見ないのかなァ、と天馬はカガミの日常に思いを馳せた。窓辺で紅茶とか飲んでそう。ベッドは天蓋つきだな。
「あの、馬場様」
「呼び捨てでいいよ。おかしいだろ、様づけなんて。同級生だぜ?」
よく今まで人前で名前を呼ばれる機会に出くわさなかったものだ。今更ながら最悪の事態を想像するとぞっとした。
「じゃあ」カガミはスカーフの位置を直すために手を挙げ、天馬はいかがわしい想像をした。
「天馬」
「……」
「天馬?」
「呼び捨てって下の名前かい」
「ダメですか」
「いいよ、うん、いいよ、もう!」恥ずかしがってるこっちがバカみたいだ。
天馬は一飛びで三段駆け上がると、腰を下ろした。古い木材が苦しげに軋んだ。
「あの、体育館の裏って道路に面してるじゃないですか」
「ああ」確かにすぐ外に割りと交通の多い道路があった。渡るとファーストフード店やゲームセンターのあるショッピングモールがあり、放課後は制服姿の若者で一杯になる。
「そこから、弓道部の練習が見えるんです。植え込みがあるから、こっちからは見えにくいんですけど」
「ふうん」
「それで、もしお時間があったら、そこから練習を見ていてくれませんか」
「なんで?」
天馬はアホみたいに聞き返した。当然ながらカガミは黙り込むしかない。
「まあ時間はあるけど」
カガミが顔を上げた。
「でもダメだな」
「どうして」
「そんなことしてみ。オレ、見つかったら変態だろ、どっからどう見ても」
「……それは……確かに……」
「え、そこで確かにとか言うなよ。嘘でもいいからそんなことないよ!って言ってよ。え、嘘。マジかよ。泣きたい」
「どうぞ」
「どうぞじゃねーよ! ……とにかく、ダメったらダメ。オレとの接点はできるだけ少ない方がいい。
オレだってなァ、これでも少しは心配してんだからな。せっかく念願のジョシコーセーになれたんだろ。台無しになる前に危ない橋からは降りとけ」
矢継ぎ早に喋ったものだから息が切れた。ふう、とカガミを見ると心なしか目つきが鋭くなっている気がする。
「え、オレ悪いこと言ってなくね? なにその目つき怖い」
何か蓄えるかのような間を置いた後、カガミは
「弱虫」
と呟いて、去っていった。
後は追わなかった。
急ぎすぎたセミが、どこかで鳴いている。
(言われなくても、わかってるってんだよ)
誰もいない、この世界から忘れ去られた階段で、天馬は膝を抱えた。
(オレが苦しめばいい)
(オレでいい。おまえじゃなくていい)
(おまえを傷つけるより、ずっといい)
カガミとは先月、とある事件を通じて知り合った。その結果として彼女は天馬の通う私立武々羅学園に転校してきたのだ。
この学校という地獄の釜の底で、たった一人天馬が心を許している友達。
今頃、部活の見学でもしているのだろうか。
確かこの間、テニス部に体験入部して三年のレギュラーメンバーよりも鋭いスマッシュをぶちかまして先輩は一週間寝込んだらしい。超人はこれだから困る。
(まァアブナイ組織の一員なんだから、当たり前なんだけど……)
物語の登場人物のような彼女と知り合いであることを思うと誇らしい気分になってきて、表情が幾分か安らいだ。
そして、そんな無防備な天馬の下に、『それ』は爆撃されたのだった。
まず最初に見た。次に何らかの通知だと思った。
退学通知とかそういったもの。悪いことはしていないけれど、パトカーを見かけたら逃げるのと同じ心理だ。
しかしそれは否定された。なぜなら下駄箱から取り出した封筒には、個人の名が署名されていたからだ。
「これって」
今時いまだに、こんなものを送ってくるやつが生き残っているなんて!と天馬は驚愕した。
丸っこい字で差出人の名前が書かれている。
『鴉羽魅羽』
知らない名だった。
そして忘れられなくなる名だった。
03.
「もしもーし。生きてますかー?」
「へっ? あ、わ、悪い!」
いつの間にか物思いに沈んでしまっていたらしい。初対面の相手を前にして失礼すぎた、と慌てて平謝りするとミハネは気にした様子もなく手を振った。気さくな人物のようだ。
「緊張するよね、そりゃあさ、いきなりだもんね」
ミハネは飲み終わったグラスの氷を、ストローでかき混ぜる。
「でも、我慢できなくなっちゃって。下駄箱の前でだいぶ迷ったんだけど、ええい女は度胸!って思って入れちった」
「凄い……な。俺にはできない」
どんな口調にしたらいいのか分からず、語尾が濁ってしまった。
教科書はどこだ、学校は何をしてる。
ミハネは身を乗り出すようにして天馬の顔を見上げた。
「ラブレター書いたことない?」
「ない」
やばい無愛想だと思われたんじゃなかろうか、天馬は斜向かいでメニューを聞いているウェイトレスに念で助けを要請した。
ミハネは気にした様子はないが、それもコミュニケーション能力に長けた人間特有の隠蔽なのではないか、と疑えないこともない。
「告白したことも、ないし」
「じゃあ、今度ください」
「何を?」
「ラブレター」
ああ、こいつ苦手だ、と思った。
耳が熱くなるのを感じる。にやにや笑いを浮かべたウェイトレスが通り過ぎる。
ミハネは視線を逸らしてくれそうになかった。