11.偽者の戦士

持ち点二千九百。そこに天馬の命運がすべて乗っかっていた。
軽い点棒を指で弄びながら、すっかり戦意喪失してしまった天馬に話しかけるものはもういない。
南二局、親は烈香。
着々と進んでいく局を、真剣な三人を、天馬は遠い気持ちで眺めた。
心が死んでいる天馬にとって、三人は光輝いているようだ。
親の懐中を当てにしているだけ、と内心で下に見ていた白垣でさえ、今は戦士と呼ぶに相応しい。
そう、戦士だ――と天馬は思った。
俺も戦士になりたかった。だが、自分は所詮、偽者だった。
だから、いい。こいつらが勝てばいい。俺が負ければいいんだろう。
それが世の中ってやつの願いなんだろう。そうら、雨宮がリーチをかけてきやがった。へっ、持っていきやがれ、こんな命、くれてやらァ。
が、次の雨宮のツモを待たずして、烈香が五本オールをツモってしまった。
「ちぇっ、邪魔しやがって。野郎にトドメを刺そうと思ったのにさ」
「おまえの思うとおりにはさせない。勝つのは私だ」
好きにしろよ、俺ァもう疲れたぜ。三日も打ち通しだったんだ。
もう十分だ。もう満足だ。打ち足りたよ。もういい、もういいから、俺を休ませてくれねえか……。
次局、天馬は国士狙いのバラ打ちをし、烈香に振った。
面前タンヤオのみ、二千点の一本場は二千三百。
天馬の手元には、ちょこんと百点棒が残ってるきりだった。とうとう笑い出した。
「見ろよ。百点しかない。もう降参だよ。もうやめよう。好きにしてくれよ。もう、打ちたくねえ――」
三人ともなんともいわなかった。
(これでいいんだ、こんな風にみっともない生き様が俺には相応しいんだ。とっとと死ねばいいんだ、俺なんぞは――。
雨宮も、白垣も、烈香も、きっとあのシマだって、今の俺を見たら死ねばいいと思うのさ。
それが普通なんだ。俺にもわかる正しい道理なんだ。
死ね、馬場天馬。
――たった一度の勝利を奇跡のまま、腐らせちまったこれがおまえの結末なんだよ)
もしかしたら、と天馬は対面を見やった。
(俺はやっぱり、雨宮に生き残っててほしかったのかもな。俺よりも、あいつの方が、生きてるのに相応しいって内心では思ってたのかもしれねえ。
ざまァねえや。結局、俺の言葉なんて、なにもかも嘘っぱちだったんだな。はっ、ホントに、最悪だなァ……。
ま、今まで、この数ヶ月がおかしかったんだ。元に戻った。それだけだ――)
すげえよ、と天馬は再び雨宮に頭を垂れた。
力が湧いてこない。気合も糞もない。
手牌とツモがテンパイに届かずしてどう闘えというのだ。もう勝負は終わったのだ。
ロン、と白垣が手を倒した。
「ピンフのみ、千点の二本場は千六百」
雨宮がじっとその手を見ている。
「何かおかしいかい」
「おまえ、一巡前の天馬の牌でアガってるな」
「え? なんのことかな」白垣は口をすぼめた。
「今テンパイしたばかりさ。言いがかりはやめてくれよ。それに、トップを取らなきゃ意味がないじゃないか。責められるいわれはないよ」
「ふん、喰えないやつだぜ。おまえが金のことなんか考えてるもんか」
雨宮が無表情に点棒を払う。天馬は苦笑した。
(なんだ、ここまできて俺に情けをかけるのか、白垣。それとも退屈だっただけか?
悪いけど、俺にはもう牙はねえよ。シマウマは、大人しく食われることにする)
そうして天馬は、ふいに自分の気持ちに納得した。
俺は、負けたいのだ。
勝っても何も得られない。負けても何も失わない。
だから負けたい、終わらせたい。
勝負事にほとほと嫌気が差していたのだ、本当は。
ただ、かつての奇跡の名残だけが胸の中で疼いていて、諦め切れなかっただけだ。
敵を探して歩き回った。それにも飽きた。そうして辿り着いた相手は、やはり始まりの相手だけだった。
勝っても何も得られない。負けても何も失わない。
だから負かしてくれ、雨宮。俺を楽にしてくれよ。
すべて終わらせてしまおうぜ。
おまえが俺に、ケリってやつをつけてくんなァ。
それでいいのかよ。
本当にそれでいいのか。
このまま負けて後悔しねえっていうのか。
(いいとも。勝手にしやがれ。こいつァ俺の本心さ。
俺は勝負師にゃあなれなかった。偽者だ。偽者は、死ぬが道理だ。
自分でそう言いふらかして生きてきたんだ。
それが自分の身に降りかかったからって手の平返しをするのも、なんかな。
せめて本物の手で始末されるだけ、俺は幸せもんだぜ)
南三局、流局。
天馬は万感の思いを籠めて、手牌を伏せた。張れなかったのだ。
窓から差し込む朝の光が天馬の顔を優しく照らした。
(さ、終わりにしよう。ノーテン罰符を払って、ハコテンだ。
――これでようやく、楽になれる。
べつにおかしなことなんかじゃない、俺はずっとシマの真似事をしていただけで、本当はこうして楽になりたがっていたんだから)
白垣が手牌を伏せ、烈香も伏せた。
雨宮も、伏せた。
にやりと笑う。
「ふふふ、首の皮一枚のくせに、しぶとい野郎だぜ」
「早く終わりにしてくれよ、もう帰りてえんだ」
「おまえに帰る場所なんかねえよ」
そういえば、そうだった。家には居場所なんてものはない。天馬は自らの手でそれらを破壊したのだ。
じゃあ自分は、いったいどこに帰ろうとしていたのだろう。
闘わねば。そう思う。だが身体が言うことを聞いてくれない。
牌が鉛になったように重かった。喉元に胃酸が昇ってきては降りていく。
(身体が拒否してるんだな、闘うことを。
おかしな話だぜ、闘わなきゃ死ぬってのに、この身体、バカなんじゃねえかな。
もっとシャキっとしろよ。このままじゃ、死んじゃうぜ?)
そう呼びかけてきても、一層頭痛がひどくなるばかりだった。
徹夜特有の、芯が痺れるような、どこか遠い痛みが天馬を苛んだ。
(ああ、くそ、そうだったな、俺に味方なんかいやしなかった。
この身体だって、俺にとっては敵みてえなもんだ。
肝心なときに邪魔ばかりしくさりやがって、宿主ごと死にてえのかよ。
………………………。
どいつも――こいつも――!)
ぎり、と歯が軋んだ。両肩に何かが乗っている。死神の手かもしれない。
(俺は――戦士にはなれない。この土壇場で、ここまで崩れるなんて、俺もびっくりしたが、うだうだ言ってても始まらねえ。
所詮、これまでのやつなんだよな。
シマの真似事をして、勝負の真似事をして、博打をしったような顔をしてただけだ。ホント、ざまァねえな。
ホント――)
卓の下で、拳を膨れ上がるほど強く握りこむ。
カガミの顔が浮かんだ。
今でも俺は、やつと一緒にいることに罪悪感を覚える。やつの穏やかさに触れるたびに、胸がひりひり痛むんだよ。
俺はおまえが思ってるようなやつじゃないんだ。
もっとドス黒いやつなんだよ。つまらないやつなんだよ。
それはやっぱり、何があっても変わらねえことなんだ。
俺は俺をやめられない。
どうしてなんだろうな。
おまえはきっと、俺がいなくてもやっていけるよ。前にも言ったっけ?
おまえは強いからな。俺が保障するよ。
なァ、カガミ。
俺は、俺のためにだけ闘うって言ったけどさ。
どうもそれじゃあ、ダメみてえなんだ。力がぜんぜん出ないんだよ。
ふにゃふにゃのへちょへちょだ。身体がタコみてーになってんだ。
結局、その差なんだろうな。
俺はやっぱり、この土壇場で、甘さが出ちまった。
自分のために、自分だけのために、どこどこまでも修羅ではいられなかった。
わかった。
わかったよ。認めるよ。はっきりさせる。
俺、おまえのために、おまえんとこ帰るために。
もう一局だけ、がんばってみるよ。
オーラス。東一局の流れ一本場。親番は白垣。
俺の持ち点は100。雨宮は55000。その差、55400。
役満直撃のみ、逆転。
手牌に顔を向けたまま、ひょいと雨宮が視線を上げた。
「ん、ようやくエンジンがかかったかな」
俺は腕をまくって、滴る冷や汗を払った。
言葉はいらない。
手牌を起こし――
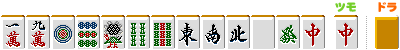
頭を抱えた。
この手から直撃できる役満は、おおよそ四暗刻と国士無双の二点に絞られる。あまりに遠いが字一色チートイツもあるだろうか。
だが、条件としては雨宮からの直撃を取らなければならない。
国士無双なら、ヤオチュウ牌は押さえられてしまうだろう。
四暗刻なら、単騎まで持っていかなければならない。
役満をツモっても逆転にはならない。
俺は長考した末に、胃の痛みに耐えながら初打を放った。
五筒。その次も五筒。五筒。
暗刻落としだ。
雨宮が無闇にカンに触る笑顔を浮かべる。
「国士決め打ちか。ま、がんばれよ。おまえなら引けるよ。嘘だが」
うるせえ。俺は無視してやった。
雨宮にとって無反応が一番堪えるのは誰よりも俺が知ってる。案の定そわそわし始めた。少しは落ち着きやがれ。
雨宮が俺の手を国士決め打ちと言うのも無理はない。
マンズ、ソーズの九連も残っているが、やつもまさか俺が四暗刻を狙っているとは思えなかっただろう。
そう、俺は暗刻落としからの四暗刻を狙っていた。
都合がいいと笑うかい? だが想像してみろ。五筒暗刻落としの後、四暗刻単騎、そうだな、たとえば七筒待ち。
こいつァ雨宮でもかわせまい。もちろんテンパイできれば、の話だけど、できなきゃ死ぬだけだ。
勝った時のことだけ考えてりゃいい。もう、そうする他に道はねえ。
できれば何か裏技でショートカットしたいところだが、俺には技も知恵もねえ。
だが、闘うってのは何も特別なことじゃない。生きてりゃ誰だってそうしていくんだ。
俺は偽者の戦士だが、だからって闘えねえってのは道理が通らん。
本音を言えば闘いたくない。今すぐ逃げ出したい。今まで調子乗ってマジすいませんでしたと土下座して逃げれるならそうしたさ。でもそうしない。
俺の目の前にいるのは、雨宮秀一だからだ。
この手から直撃できる役満は、おおよそ四暗刻と国士無双の二点に絞られる。あまりに遠いが字一色チートイツもあるだろうか。
だが、条件としては雨宮からの直撃を取らなければならない。
国士無双なら、ヤオチュウ牌は押さえられてしまうだろう。
四暗刻なら、単騎まで持っていかなければならない。
役満をツモっても逆転にはならない。
俺は長考した末に、胃の痛みに耐えながら初打を放った。
五筒。その次も五筒。五筒。
暗刻落としだ。
雨宮が無闇にカンに触る笑顔を浮かべる。
「国士決め打ちか。ま、がんばれよ。おまえなら引けるよ。嘘だが」
うるせえ。俺は無視してやった。
雨宮にとって無反応が一番堪えるのは誰よりも俺が知ってる。案の定そわそわし始めた。少しは落ち着きやがれ。
雨宮が俺の手を国士決め打ちと言うのも無理はない。
マンズ、ソーズの九連も残っているが、やつもまさか俺が四暗刻を狙っているとは思えなかっただろう。
そう、俺は暗刻落としからの四暗刻を狙っていた。
都合がいいと笑うかい? だが想像してみろ。五筒暗刻落としの後、四暗刻単騎、そうだな、たとえば七筒待ち。
こいつァ雨宮でもかわせまい。もちろんテンパイできれば、の話だけど、できなきゃ死ぬだけだ。
勝った時のことだけ考えてりゃいい。もう、そうする他に道はねえ。
できれば何か裏技でショートカットしたいところだが、俺には技も知恵もねえ。
だが、闘うってのは何も特別なことじゃない。生きてりゃ誰だってそうしていくんだ。
俺は偽者の戦士だが、だからって闘えねえってのは道理が通らん。
本音を言えば闘いたくない。今すぐ逃げ出したい。今まで調子乗ってマジすいませんでしたと土下座して逃げれるならそうしたさ。でもそうしない。
俺の目の前にいるのは、雨宮秀一だからだ。
四暗刻ってなんだっけ。あっという間に国士無双がテンパった。俺も自分でもびっくりしてる。西待ち。
雨宮がいくら国士を見抜いているとはいえ、この順目なら出るのではなかろうか。出ないか。出ないな。
しかし、やつの手も国士傾向になってりゃあ話は別だ。手牌全部ヤオチュウ牌になれば、西がポロっと出てくるかもしれねえ。
俗に脂っこいといわれる456、このあたりが俺と雨宮の河にゴミみたいに捨てられてる。実際ゴミだ。俺の有効牌以外は全部割れろ。この世には西だけあればよろしい。
雨宮が少し、長考が増えてきた。そしてぽろっとソーズが零れてくる。無論、俺のソーズ九連を警戒して取っておいた牌だろう。
実際、こんな局面で九連なんてできるわけがない。だから、端から見てりゃあ何を無駄な心配を、バシバシ切ればいいじゃないか、そんな風に思えるかもしれねえ。
でも、そのまさかにビクビクしながら勝ちを目指すのが麻雀なんだよな。
そう、俺は怖かった。負けるのが怖かった。
今は、勝つのも面倒くせえ。勝負ってのが、ただただダルイ。歯が痛い。
不思議だな、負けたらそれこそ腕をもぎ取られるかもしれねえのに、俺は麻雀なんか打ってる。さっきに比べりゃ、体調まで少しよくなってる。
なぜだろう。俺にもわからない。
身体の中にある芯が、ねじれて、よれて、まとまっていくような感覚がするんだ。
つまり、恐怖も焦りも苛立ちも一周して、俺にもよくわからんスパイラルに突入しちまったのかもしれん。
なァ雨宮。俺は心の中で澄ました対面に問いかけた。
おまえも今、こんな気持ちなのか。
「なァ、雨宮」
烈香も白垣も顔を上げない。雨宮だけが、ん? とこっちを見た。
「ちょっといまさらになるんだが……春先の勝負の金はまだかな」
雨宮は笑い出した。
「おまえ頭狂ったのか。シマが持ってったんだろ?」
「うん――だがよ」俺は次のセリフを考えながらしゃべった。
「俺はもらってないんだ」
「それは――おまえの責任だろ」
「どうかな。シマがあの後、おまえんとこに持っていったかもしれない」
「おまえ何言ってんの? 馬鹿なの?」
「ああ、馬鹿だぜ。――つまり、俺の手元に金がない状況、これだけでおまえに責任があるんだ」
「言いがかりも甚だしいな。俺は負けたおかげで、腕をなくしたんだぜ」
「知るかそんなこと」
「俺にどうしろって――」はたと雨宮が口を噤んだ。悟ったらしい。さすがだな。
ふっふっふ、と笑って、手牌を伏せた。
「俺が張ったのがなんでわかった」
「長い付き合いだからかな」
「ふうん――仕方ねえ、くれてやる。ほらよ、こいつがお望みなんだろ?」
千点棒が宙を舞った。
「リーチ――そら、がんばって国士を作りなよ。もっともその前に、俺が引きアガっちまうがなァ」
雨宮は腕を組んで、背筋を伸ばした。
まさか本当にリーチをかけてくれるとは。こいつ案外アホなのか。それとも――
とにかく、やつが西を掴んでくれりゃァ文句はない。
それで逆転。
頼むぜ神様。ケチケチすんなよ。
ここさえ凌いだら、俺、もう二度と麻雀は打たないからよ。
一生分のツキをよこしやがれ。
二順後、俺は西をツモった。
ツモった瞬間、全身が、びりっと痺れた。嘘じゃない。卓下で左手がわなわな震えちまって、びびった。暴走したかと思った。
そうして、口元を右手で覆って、笑いを必死にこらえた。目をぎゅうっと瞑って視界が赤くなる。
ツモっちゃったよ。
どうしよう。
雨宮がいくら国士を見抜いているとはいえ、この順目なら出るのではなかろうか。出ないか。出ないな。
しかし、やつの手も国士傾向になってりゃあ話は別だ。手牌全部ヤオチュウ牌になれば、西がポロっと出てくるかもしれねえ。
俗に脂っこいといわれる456、このあたりが俺と雨宮の河にゴミみたいに捨てられてる。実際ゴミだ。俺の有効牌以外は全部割れろ。この世には西だけあればよろしい。
雨宮が少し、長考が増えてきた。そしてぽろっとソーズが零れてくる。無論、俺のソーズ九連を警戒して取っておいた牌だろう。
実際、こんな局面で九連なんてできるわけがない。だから、端から見てりゃあ何を無駄な心配を、バシバシ切ればいいじゃないか、そんな風に思えるかもしれねえ。
でも、そのまさかにビクビクしながら勝ちを目指すのが麻雀なんだよな。
そう、俺は怖かった。負けるのが怖かった。
今は、勝つのも面倒くせえ。勝負ってのが、ただただダルイ。歯が痛い。
不思議だな、負けたらそれこそ腕をもぎ取られるかもしれねえのに、俺は麻雀なんか打ってる。さっきに比べりゃ、体調まで少しよくなってる。
なぜだろう。俺にもわからない。
身体の中にある芯が、ねじれて、よれて、まとまっていくような感覚がするんだ。
つまり、恐怖も焦りも苛立ちも一周して、俺にもよくわからんスパイラルに突入しちまったのかもしれん。
なァ雨宮。俺は心の中で澄ました対面に問いかけた。
おまえも今、こんな気持ちなのか。
「なァ、雨宮」
烈香も白垣も顔を上げない。雨宮だけが、ん? とこっちを見た。
「ちょっといまさらになるんだが……春先の勝負の金はまだかな」
雨宮は笑い出した。
「おまえ頭狂ったのか。シマが持ってったんだろ?」
「うん――だがよ」俺は次のセリフを考えながらしゃべった。
「俺はもらってないんだ」
「それは――おまえの責任だろ」
「どうかな。シマがあの後、おまえんとこに持っていったかもしれない」
「おまえ何言ってんの? 馬鹿なの?」
「ああ、馬鹿だぜ。――つまり、俺の手元に金がない状況、これだけでおまえに責任があるんだ」
「言いがかりも甚だしいな。俺は負けたおかげで、腕をなくしたんだぜ」
「知るかそんなこと」
「俺にどうしろって――」はたと雨宮が口を噤んだ。悟ったらしい。さすがだな。
ふっふっふ、と笑って、手牌を伏せた。
「俺が張ったのがなんでわかった」
「長い付き合いだからかな」
「ふうん――仕方ねえ、くれてやる。ほらよ、こいつがお望みなんだろ?」
千点棒が宙を舞った。
「リーチ――そら、がんばって国士を作りなよ。もっともその前に、俺が引きアガっちまうがなァ」
雨宮は腕を組んで、背筋を伸ばした。
まさか本当にリーチをかけてくれるとは。こいつ案外アホなのか。それとも――
とにかく、やつが西を掴んでくれりゃァ文句はない。
それで逆転。
頼むぜ神様。ケチケチすんなよ。
ここさえ凌いだら、俺、もう二度と麻雀は打たないからよ。
一生分のツキをよこしやがれ。
二順後、俺は西をツモった。
ツモった瞬間、全身が、びりっと痺れた。嘘じゃない。卓下で左手がわなわな震えちまって、びびった。暴走したかと思った。
そうして、口元を右手で覆って、笑いを必死にこらえた。目をぎゅうっと瞑って視界が赤くなる。
ツモっちゃったよ。
どうしよう。