06.奇襲そして奇襲
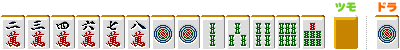
雨宮はすっかりこの関西娘を気に入っていた。
いくらか体型はシスターや烈香に比べると発育不良気味だが、そんなことは寛大な心でいくらでも許容できるというものだ。くりくりよく動く眼につられて、雨宮の首が揺れる。
うっとりとしてその手さばきを見つめていたものだから、雨宮はまたもやその事実にいち早く気づいた。
通常、麻雀は上ツモが東家西家、下ツモが南家北家である。
これはサイ二度振りだろうと関係ない。
ゆえに自分と対面のツモ筋に好牌を集め、上家下家にクズ牌を流し込む『うえ・した』と呼ばれるイカサマが発明されたのである。
このイカサマは精度さえ気にしなければ誰にでもできるのでご存知の方も多いだろう。
今、仮にさくみがツモるときに一牌多く牌を持ってきたとしよう。
おそらくいの一番に気づくのは麻雀マニアこと十六夜烈香であろう。さくみの多牌を指摘し、関西娘はチョンボ代を払う羽目になる。
ところが、三枚同時ツモならどうだろう。
ヤマは一トン短くなるが、うえ・したの関係は変わらない。
さくみの太ももの間に、二枚の牌が転がっていた(一枚は通常のツモとして手牌に紛れ込んでいる)。
麻雀はツモ一回の差で決着がつく。
さくみは多牌によって手牌十五枚で闘っているのだ。数の理が、彼女に味方する。
雨宮はすっかりシマのことなど眼中になく、さくみの一投一打にしきりに頷いていた。
「ちょっとー。応援が聞こえないんですけどー?」
「ん? ああ、ガンバレー。マケルナー。ツモルナー」
「うわぁ……腹立つ……」
拳を握り締めぷるぷる震えるシマに、挑発するようにさくみが言った。
「悪いなァ、彼氏を取ってしもて。ま、にいちゃんにはウチの凄味ってのがわか――」
何かを喉につっかえたような間のあと、さくみはヘラリと笑った。
「わかるんやろう」
「ああ、もちろん。そして俺ァ――」
雨宮もニヤァと笑った。
「好きな子には、意地悪したくなるタチでね」
薄気味悪い、と烈香が毒づくが蛙の面に小便である。さくみは頬を引きつらせた。苦笑したのだ。
「趣味悪いなァ、にいちゃん……。イケメンやけど、喰いたかないな。腹ァ壊すわ」
「そうかい――? どう思うよ、シマ?」
「毒を喰らわば鉄の胃を持て、だよ」
「おまえは長生きするだろうぜ、ホントに」
「あはは――ロン!」
さくみの指が、まだ牌から離れていなかった。
「また珍しい役だ――ピンフ、双竜争珠、ドラドラ。一二〇〇〇」
「待てや。動くな」
「ふぅ、やっと活躍できたよ。高めの八索ごちそうさま!」
「動くなゆうとるやろッ!」
バン、と卓を叩いてさくみが席からやおら立ち上がった。
「見えたで。おどれ多牌しとるな」
「何を根も葉もないことを――」シマがうそぶく。
さくみが指紋が見えるほどの近さで人差し指をシマに向かって突き出した。
「三枚一緒にツモったんやな、このアマ――こすいことをっ!」
悪びれもせずに自分の負い目を他人にかぶせるさくみに、また雨宮は陶酔しかけた。彼女は悪の魅力でぷんぷんだ。
ちらっとさくみは恨みがましい視線をにやける雨宮にぶつけ、またシマを殺さんばかりに睨みつける。
「出せや。身体検査や。丸裸にしたって暴いてやるで」
「やだよ。雨宮いるし。こいつに見られるのだけは死んでもヤ」
「遊びとちゃうぜ。男なんか摘みだせばいいんや。ガタガタぬかすな」
「ま、脱いでも晒してもいいけど……そんなに心配なら卓の牌の数を数えれば? 百三十六枚あれば、私は潔白ってわけだ」
「――――」
「動かないでいてあげるからさ、どうぞ?」
腕を組んだシマを横目に、三人はそれぞれ牌をあっという間に集め、数えてしまった。
「百三十六枚あるな」と烈香。
「これは早とちりのようですねえ」とシャガ。
さくみの頬がとうとうリンゴのように赤く膨れ上がった。
烈香、シャガともに、さくみが何の根拠もなく、ましてや見間違いで人を糾弾するような間抜けではないことは承知しているのだろう。
しかしせっかく沈んでくれたトップ者を助けてやることもない。
もしかするとこの場にいる者はみな、さくみの多牌、そしてその牌をシマが手にしてアガリを掠め取ったことに気づいているのかもしれない。
だとしたらこんなイザコザは続けるだけ茶番である。
シマがアガった時点で、誰もさくみの味方などしないのだから。
口汚く面子を罵ったさくみは、ぎろりと雨宮を睨んだ。
「おどれが何かしたんや」
「かわいいなぁ、負け犬がきゃんきゃん吠えてるよぅ。ハァハァくんかくんかスーハー」
「死にさらせ――!」
「はっはっは、悪いね――」
呪いの言葉も雨宮にとっては褒め言葉に聞こえるだけだ。
優雅に足を組み、王者の貫禄をもって雨宮は言ってのける。
「俺は、天邪鬼なんだ」
痛みにこらえるように顔をしかめたさくみが実に愉快である。
けれど彼女が雨宮の余剰牌盗みを察知できなかったのも、その後、シマの余剰牌をこっそり卓上に戻しておいたのも、無理からぬことである。
雨宮は、右腕でそっと左腕をさすった。
誰にも見えないその腕を。