10.陸咲シャガ
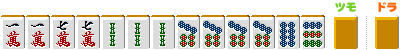
南一局三本場。
シャガは崖っぷちの際の際まで追い詰められていた。
残り点は一七〇〇点。
積み棒があるため中のみ千点にだって振り込むわけにはいかない。
この麻雀は赤ドラがないため打点が低くなりがちではあったが、この点数ではそれがネックとなって逆転は難しく、トドメを刺されるのはたやすい。
圧倒的なまでの、死の予感――。
琥珀色の月の光を浴びながら、シャガは祭られている巨像を見上げた。
その両眼は、かつて悪名を轟かせたある勝負師の墓石から作られている。シャガの父も、その信者たちも、みな彼を敬い崇めた。
巨像はただ遠くを見据えている――ここから動き出したいのだろうか。それまで無感動に見上げるだけだったその像に、赤い修道女はそのとき初めて親しみを覚えた。
陸咲シャガは愛されて育った。
父は苛烈な新興宗教の伝道師とは思えぬほど物静かで優しい人だった。子犬ほどに小さかった頃のシャガは、父から教わるゲームのどれもが好きで、時間なんていくらあっても足りなくて、眠っている暇なんてなかった。
厳しい面もあった。人を傷つけたこともあった。数え切れない罪を犯してきた。
でも、楽しかった。
それだけなんだ、とシャガは思う。
自分が生き延びてきたことに理由や理屈をつけるなら。
楽しかったから。
だから、死ぬときも、楽しんで死にたい。
たとえその考え方が、心も体も砕いたとしても。
人間らしい恐怖などない。
ただひたすらに――熱い。
シャガは崖っぷちの際の際まで追い詰められていた。
残り点は一七〇〇点。
積み棒があるため中のみ千点にだって振り込むわけにはいかない。
この麻雀は赤ドラがないため打点が低くなりがちではあったが、この点数ではそれがネックとなって逆転は難しく、トドメを刺されるのはたやすい。
圧倒的なまでの、死の予感――。
琥珀色の月の光を浴びながら、シャガは祭られている巨像を見上げた。
その両眼は、かつて悪名を轟かせたある勝負師の墓石から作られている。シャガの父も、その信者たちも、みな彼を敬い崇めた。
巨像はただ遠くを見据えている――ここから動き出したいのだろうか。それまで無感動に見上げるだけだったその像に、赤い修道女はそのとき初めて親しみを覚えた。
陸咲シャガは愛されて育った。
父は苛烈な新興宗教の伝道師とは思えぬほど物静かで優しい人だった。子犬ほどに小さかった頃のシャガは、父から教わるゲームのどれもが好きで、時間なんていくらあっても足りなくて、眠っている暇なんてなかった。
厳しい面もあった。人を傷つけたこともあった。数え切れない罪を犯してきた。
でも、楽しかった。
それだけなんだ、とシャガは思う。
自分が生き延びてきたことに理由や理屈をつけるなら。
楽しかったから。
だから、死ぬときも、楽しんで死にたい。
たとえその考え方が、心も体も砕いたとしても。
人間らしい恐怖などない。
ただひたすらに――熱い。
ドラも何もない、役は二暗刻の一飜のみ。ツモり三暗刻。
七筒をカンして四暗刻を目指すのが、いつものシャガの打ち方だった。親の先制リーチを喰らっていたとしても、だ。
けれど、今は何かが彼女に語りかける。感じさせる。
それはおまえの進むべき道ではない、と。
「――リーチ」
獲物を見つけた蛇のような手つきで、シャガはリーチ牌を打ち出す。
ハナからトイツ手を目指していたため、河の先頭には四萬が捨てられている。
待ち牌はダブル筋ひっかけだ。
そう、この手に理屈をつけるなら、四暗刻を狙うためには七筒を暗カンした後、八筒か九筒を暗刻にしない限り、一度アガリを逃すことになる。
それでも四暗刻テンパイの魅力の方が高いことなど重々承知。点数に余裕がないのも血反吐をぶちまけるほど理解している。
それでも、理屈ではないのだ。
南一局零本場での自分らしくない打ち筋は二度となぞらない。
愛されて勝ってきた。
だから愛されなくなったなら、
潔く、死ぬべきなんだ。
「この牌は――」
二順後、ぎろりとさくみが河を見渡す。
安全牌に窮しているらしかった。
「縁起が悪いねんけどな――!」
そうして打ち出された一萬は、
シャガにはとても輝いて見えたのだった。
「ロンっ!」
リーチ二暗刻。五十符二飜三本場は三千二百の四千四百。
受け取った点棒を引き出しに流し込み、シャガは、口元にこびりついた血痕を乱暴に拭い取った。
これでようやく手に入れた。
親番こそ自分の独壇場。
ただただツモり、ただただ勝つ。
勝利を愛し、麻雀に愛される。
陸咲シャガの辞書に座死はない。
南二局。
ここが正念場であろう。点数的に苦しいシャガはこの親番を活かさなければならない。
目標は三位浮上。トップを競る麻雀ではないため、ラスを回避することが重要となってくる。
ゆえに先ほどシマのぶっ飛び見逃しは異様であるのだが――シャガにはもうそんなことを思索する余裕はない。
体に馴染んだ麻雀動作と、理を超えたカン打ち。頭なんて使っていない。その必要もない。
ただ引き、ただ打つ。静かな表情、その一枚裏には狂気しか残っていない。
父の顔が浮かんだ。
「ロン!」
さくみが手を倒した。喰いタン、千点。振ったのは烈香。サシコミだったのかもしれない。
あっさり流されたシャガの親。シマの親を流し、これから返り咲くのでは、という期待を感じさせずにはいられない親。
その親が、流れた。
さくみが震える息を吐き、にやっと笑う。
しばらく、シャガは自分の手牌を崩さなかった。
崩せなかった。
続く南三局、烈香の親もシマが喰いタンをツモって三本五本。
場に流れる四位確定のまま半荘を終わらせようとする雰囲気。そして尽きていく体力。
シャガの顔はとうとう蝋のようになってしまった。
肘を膝にあてがって頬杖を突く雨宮はにたにたと笑いながらそれを眺める。
苦しんでいる人間の表情は言い知れぬ感動を脳に湧き起こらせるものだ。
ただ、このほぼ終わってしまった勝負で気がかりなことといえば。
ちらりと見やると、シマは顔をごしごしとハンカチで拭いていた。
おや、と手をポケットに突っ込むと雨宮のものが消えている。
「おまえそれさっき俺が顔拭いたやつだぞ」
「ぎゃっ!」
ざまぁざまぁと雨宮が笑い、シマが青い顔になっているのを鋭い視線で見つめるものがある。シャガだ。
彼女もまた例外なく四位の気持ちになっていた。
怒りの轟音が聞こえてきそうな憤激の念――
「浮かれてんじゃねえぞ、トップ家ァ」
というやつである。
そう、勝負はまだ終わっていない。
オーラスらしい陰と陽が幾何学模様に入り交ざった空気。
南四局。
親番は、霞野さくみ。
七筒をカンして四暗刻を目指すのが、いつものシャガの打ち方だった。親の先制リーチを喰らっていたとしても、だ。
けれど、今は何かが彼女に語りかける。感じさせる。
それはおまえの進むべき道ではない、と。
「――リーチ」
獲物を見つけた蛇のような手つきで、シャガはリーチ牌を打ち出す。
ハナからトイツ手を目指していたため、河の先頭には四萬が捨てられている。
待ち牌はダブル筋ひっかけだ。
そう、この手に理屈をつけるなら、四暗刻を狙うためには七筒を暗カンした後、八筒か九筒を暗刻にしない限り、一度アガリを逃すことになる。
それでも四暗刻テンパイの魅力の方が高いことなど重々承知。点数に余裕がないのも血反吐をぶちまけるほど理解している。
それでも、理屈ではないのだ。
南一局零本場での自分らしくない打ち筋は二度となぞらない。
愛されて勝ってきた。
だから愛されなくなったなら、
潔く、死ぬべきなんだ。
「この牌は――」
二順後、ぎろりとさくみが河を見渡す。
安全牌に窮しているらしかった。
「縁起が悪いねんけどな――!」
そうして打ち出された一萬は、
シャガにはとても輝いて見えたのだった。
「ロンっ!」
リーチ二暗刻。五十符二飜三本場は三千二百の四千四百。
受け取った点棒を引き出しに流し込み、シャガは、口元にこびりついた血痕を乱暴に拭い取った。
これでようやく手に入れた。
親番こそ自分の独壇場。
ただただツモり、ただただ勝つ。
勝利を愛し、麻雀に愛される。
陸咲シャガの辞書に座死はない。
南二局。
ここが正念場であろう。点数的に苦しいシャガはこの親番を活かさなければならない。
目標は三位浮上。トップを競る麻雀ではないため、ラスを回避することが重要となってくる。
ゆえに先ほどシマのぶっ飛び見逃しは異様であるのだが――シャガにはもうそんなことを思索する余裕はない。
体に馴染んだ麻雀動作と、理を超えたカン打ち。頭なんて使っていない。その必要もない。
ただ引き、ただ打つ。静かな表情、その一枚裏には狂気しか残っていない。
父の顔が浮かんだ。
「ロン!」
さくみが手を倒した。喰いタン、千点。振ったのは烈香。サシコミだったのかもしれない。
あっさり流されたシャガの親。シマの親を流し、これから返り咲くのでは、という期待を感じさせずにはいられない親。
その親が、流れた。
さくみが震える息を吐き、にやっと笑う。
しばらく、シャガは自分の手牌を崩さなかった。
崩せなかった。
続く南三局、烈香の親もシマが喰いタンをツモって三本五本。
場に流れる四位確定のまま半荘を終わらせようとする雰囲気。そして尽きていく体力。
シャガの顔はとうとう蝋のようになってしまった。
肘を膝にあてがって頬杖を突く雨宮はにたにたと笑いながらそれを眺める。
苦しんでいる人間の表情は言い知れぬ感動を脳に湧き起こらせるものだ。
ただ、このほぼ終わってしまった勝負で気がかりなことといえば。
ちらりと見やると、シマは顔をごしごしとハンカチで拭いていた。
おや、と手をポケットに突っ込むと雨宮のものが消えている。
「おまえそれさっき俺が顔拭いたやつだぞ」
「ぎゃっ!」
ざまぁざまぁと雨宮が笑い、シマが青い顔になっているのを鋭い視線で見つめるものがある。シャガだ。
彼女もまた例外なく四位の気持ちになっていた。
怒りの轟音が聞こえてきそうな憤激の念――
「浮かれてんじゃねえぞ、トップ家ァ」
というやつである。
そう、勝負はまだ終わっていない。
オーラスらしい陰と陽が幾何学模様に入り交ざった空気。
南四局。
親番は、霞野さくみ。