グロエリ本の感想文集
『セリエント』(2016)

目次
はじめに
1.見た目は大事(装丁・組版について)
2.「登坂車線」(ホドラー先生:「架旗透」名義)
3.クレーター(東京ニトロ先生)
閑話休題:『セリエント』kindle版が出たようです。
4.セリエント感想(上)(下)(クラック先生:「高倉創」名義)
5.Lovely Fairy with Me(いしまつ先生:「維嶋津」名義)
はじめに
1.見た目は大事(装丁・組版について)
2.「登坂車線」(ホドラー先生:「架旗透」名義)
3.クレーター(東京ニトロ先生)
閑話休題:『セリエント』kindle版が出たようです。
4.セリエント感想(上)(下)(クラック先生:「高倉創」名義)
5.Lovely Fairy with Me(いしまつ先生:「維嶋津」名義)
はじめに
2015年、文フリというイベントで、グローバルエリート(通称「グロエリ」)というサークルから、『セリエント』というSF短編集が頒布されました。一冊1500円。編者は、新都社SEであり、「鋼城都市」の作者でもあるクラック先生(「高座創」名義)です。技術のプロである同氏から溢れてくる人工知能論にかねてから関心のあったので、あらかじめ人づてに購入を依頼し、先日ようやく落手しました。
所収の短編は、いずれもなかなか面白く、総論としての感想は、「グロエリまじグロエリ」という畏怖とも嫉妬ともつかない言葉一つで終わってしまうのだけれど、より内容に立ち入って感想や考察を書き留めていくとなると、とても140字でまとまりそうもなかったので、このベータマガジンという場をお借りして、ぼちぼちと感想をあげていきたいと思います。
執筆陣は、クラック先生のほか、「夜の確率」ホドラー先生(「架旗透」名義)、「彼女のクオリア」「奥美濃ディストラクティブ」の東京ニトロ先生、「文学賞のための練習帳」いしまつ先生(「維嶋津」名義)、「夜のうつくし」の杏野丞先生です。
いずれも新都社作家であるので、この感想文集は一種のオフレポのようなものといえるかもしれず、また、感想者の常として読み込んだ作品については他の方の感想も気になるもの。そう思い、この文集はどなたでも編集できるものにしてみました。パスは「guroeri」。
私自身はというと、読むのも書くのも遅いので非常に遅い更新となります。
2015年、文フリというイベントで、グローバルエリート(通称「グロエリ」)というサークルから、『セリエント』というSF短編集が頒布されました。一冊1500円。編者は、新都社SEであり、「鋼城都市」の作者でもあるクラック先生(「高座創」名義)です。技術のプロである同氏から溢れてくる人工知能論にかねてから関心のあったので、あらかじめ人づてに購入を依頼し、先日ようやく落手しました。
所収の短編は、いずれもなかなか面白く、総論としての感想は、「グロエリまじグロエリ」という畏怖とも嫉妬ともつかない言葉一つで終わってしまうのだけれど、より内容に立ち入って感想や考察を書き留めていくとなると、とても140字でまとまりそうもなかったので、このベータマガジンという場をお借りして、ぼちぼちと感想をあげていきたいと思います。
執筆陣は、クラック先生のほか、「夜の確率」ホドラー先生(「架旗透」名義)、「彼女のクオリア」「奥美濃ディストラクティブ」の東京ニトロ先生、「文学賞のための練習帳」いしまつ先生(「維嶋津」名義)、「夜のうつくし」の杏野丞先生です。
いずれも新都社作家であるので、この感想文集は一種のオフレポのようなものといえるかもしれず、また、感想者の常として読み込んだ作品については他の方の感想も気になるもの。そう思い、この文集はどなたでも編集できるものにしてみました。パスは「guroeri」。
私自身はというと、読むのも書くのも遅いので非常に遅い更新となります。
1.見た目は大事 (装丁・組版について)
「これ、市販の文庫本じゃないですか?」
というのが、本書を手にとって最初の感想だった。
スタイリッシュな表紙デザイン、装丁、組版、どの点においても、一般書店に並んでいるものと遜色はない。もちろん、その道のプロからすれば、様々なアラを探すこともできるだろう。同席したSF愛好者の方は、一見してフチの余白について違和感を表明した。だが、履歴書の中でだけ「趣味:読書」などと嘯く私程度の人間では、その差を見破ることはできない。
表紙デザインの凝った同人誌は珍しくはないが、独自デザインかつ「市販の文庫本」に近づけることにここまで血道をあげたものはなかなかお目にかかることがない。あるいは、最近の文藝同人誌というのは、こういうものなのだろうか。ともあれ、1500円という価格設定も、この見た目だけで納得できる。
もちろん、書籍にとって大事なのは「見た目」ではなく「内容」だ。私は特にそう思う。漫画にせよ、文章にせよ、私は独力で「仕上がったもの」をつくるスキルがないから。主に創作活動を行っているWeb上では、落書きのような私の絵、文章でも概ね許される。それだけに体裁への注力については、言い訳したいという心の力学もあり、つい軽視しがちだ。しかし、本書を実際に手にとって読み始めて、その認識は大きく改められた。
すべての同人作家、特に文字媒体での作家に告げたい。
「体裁は徹底的に凝るべし。その効果は絶大」
実のところ、私はweb小説、同人小説は苦手である。特に、web小説は、よほど集中しないと目が滑る。
web小説は、web漫画とくらべて、手に取って読み始めるまでの心の壁はかなり高い。
率直に言って、最初に今回「グロエリ本」に関心を持ったのも、ネット上で絡みのある人の創作と極めて属人的な要素が大きい。
もともと文字媒体での創作物は、私にとって概して敷居が高く、どうしても身構え、襟を正す気持ちとなる。気軽に読み流せる漫画、ブログ記事であれば、ノンプロ的な甘さが際立っても、ネームや下書き的な未完成品であってさえ、その荒削りさ、また表現の意図をすくい取って楽しむということもできるのだけれど、「襟を正さして」向かい合わざるをえない小説においては、その心の余裕に乏しい。
(このことで、おそらく多くの傑作を見逃しているのだろうとは思う。)
「市販本と見紛う外見」は、「これは未完成品ではない」と読者に最も最も手っ取り早く伝える手段となる。
「プロ作家のものと『同じように読める』」ということは、同人誌を読むするとき特有の心の障壁を破壊する。
ついでにいえば、文庫本は読みやすさを追求してきた人間の英知の結晶であり、その模倣は合理的である。
電車、バス、飛行機、喫茶店、どこで広げても違和感なく読める。
優れた創作は、それに相応した「見た目」と「形」を得るべきである。
インターネットが隆盛しはじめた時期、「誰もが創作者に、誰もが発信者になれる」といった夢が語られていた。新都社は草創期からこの夢を体現してきた成功事例の一つであるものの、むしろそういうコミュニティは少数派で、一方では、「その夢はやはり安易ではなかったか」という現実を見せつけられることも多かった。やはり、プロの仕事はプロが作るものなのだ、と。
「見た目」こそ「誰もが創作者である」ための強力な条件の一つである。これは、私が「グロエリ本」から受けた最初の衝撃である。その仕上げが特殊なスキルによるものか、現在の印刷サービスから見れば、(労力次第で)誰もが獲得可能であるものなのか、そこの評価は、私自身の経験不足により、少し迷う。
「これ、市販の文庫本じゃないですか?」
というのが、本書を手にとって最初の感想だった。
スタイリッシュな表紙デザイン、装丁、組版、どの点においても、一般書店に並んでいるものと遜色はない。もちろん、その道のプロからすれば、様々なアラを探すこともできるだろう。同席したSF愛好者の方は、一見してフチの余白について違和感を表明した。だが、履歴書の中でだけ「趣味:読書」などと嘯く私程度の人間では、その差を見破ることはできない。
表紙デザインの凝った同人誌は珍しくはないが、独自デザインかつ「市販の文庫本」に近づけることにここまで血道をあげたものはなかなかお目にかかることがない。あるいは、最近の文藝同人誌というのは、こういうものなのだろうか。ともあれ、1500円という価格設定も、この見た目だけで納得できる。
もちろん、書籍にとって大事なのは「見た目」ではなく「内容」だ。私は特にそう思う。漫画にせよ、文章にせよ、私は独力で「仕上がったもの」をつくるスキルがないから。主に創作活動を行っているWeb上では、落書きのような私の絵、文章でも概ね許される。それだけに体裁への注力については、言い訳したいという心の力学もあり、つい軽視しがちだ。しかし、本書を実際に手にとって読み始めて、その認識は大きく改められた。
すべての同人作家、特に文字媒体での作家に告げたい。
「体裁は徹底的に凝るべし。その効果は絶大」
実のところ、私はweb小説、同人小説は苦手である。特に、web小説は、よほど集中しないと目が滑る。
web小説は、web漫画とくらべて、手に取って読み始めるまでの心の壁はかなり高い。
率直に言って、最初に今回「グロエリ本」に関心を持ったのも、ネット上で絡みのある人の創作と極めて属人的な要素が大きい。
もともと文字媒体での創作物は、私にとって概して敷居が高く、どうしても身構え、襟を正す気持ちとなる。気軽に読み流せる漫画、ブログ記事であれば、ノンプロ的な甘さが際立っても、ネームや下書き的な未完成品であってさえ、その荒削りさ、また表現の意図をすくい取って楽しむということもできるのだけれど、「襟を正さして」向かい合わざるをえない小説においては、その心の余裕に乏しい。
(このことで、おそらく多くの傑作を見逃しているのだろうとは思う。)
「市販本と見紛う外見」は、「これは未完成品ではない」と読者に最も最も手っ取り早く伝える手段となる。
「プロ作家のものと『同じように読める』」ということは、同人誌を読むするとき特有の心の障壁を破壊する。
ついでにいえば、文庫本は読みやすさを追求してきた人間の英知の結晶であり、その模倣は合理的である。
電車、バス、飛行機、喫茶店、どこで広げても違和感なく読める。
優れた創作は、それに相応した「見た目」と「形」を得るべきである。
インターネットが隆盛しはじめた時期、「誰もが創作者に、誰もが発信者になれる」といった夢が語られていた。新都社は草創期からこの夢を体現してきた成功事例の一つであるものの、むしろそういうコミュニティは少数派で、一方では、「その夢はやはり安易ではなかったか」という現実を見せつけられることも多かった。やはり、プロの仕事はプロが作るものなのだ、と。
「見た目」こそ「誰もが創作者である」ための強力な条件の一つである。これは、私が「グロエリ本」から受けた最初の衝撃である。その仕上げが特殊なスキルによるものか、現在の印刷サービスから見れば、(労力次第で)誰もが獲得可能であるものなのか、そこの評価は、私自身の経験不足により、少し迷う。
2.「登坂車線」(ホドラー先生:「架旗透」名義)
「小気味の良いミスマッチ小説」というのが読後の最初の印象だ。
結末部分に関わらない範囲で紹介するならば、本作は荒廃した近未来関西を舞台に、会社に疲れたサラリーマン2人が、衝動的に社長令嬢を誘拐することからはじまる逃避行の物語だ。社長令嬢に秘められた謎、「クラハ・モチーフ」が、メタファーとしても構造としても、ドラマ全体の軸となっている。
「ミスマッチ小説」と呼んだのは、本書を構成する要素の多様性にある。
作品分析など野暮ではあることは承知しているが、あえてその諸側面を列挙したい。
①ライトな活劇
本作の読み口は、非常に軽い。
設定の深刻さにもかかわらず、主人公たちは楽観的で、もっといえば呑気だ。
直情的に行動し、会社や社会、ヒロイン、敵役に遠慮なく毒づく明るさがあり、読者も、安心して状況を、いわば「ライト」に楽しめるようになっている。
敷居の高いSF短編集の冒頭を飾るに相応しい間口の広い作品と言える。
②本格的な知識に基づくバイオSF
すでに述べたように、物語の鍵となっているのは、ヒロイン「クラハ(シートゥー)」の持つ秘密だ。
それは、脳神経細胞、遺伝子操作、再生医療といった最先端技術をベースとしたSF設定だ。本作では、この分野に関する設定、知識が、サスペンス仕立ての構成で慎重に開示されていく。それは、物語の進展とともにプロットに組み込まれ、詩的に応用されることで、読者に知的充足感を、メインテーマに意味を与えていく。私は、この分野の専門家ではないので、本作設定のどこまでが現在のサイエンスでどこまでがフィクションかを厳密に考証することはできない。ただ、この厄介な素材をこれだけ縦横に振り回すことは、この領域に関する豊富な知識、経験の持ち主でなければ不可能であろう。
③ブラックな労働環境とその疲れを描く「お仕事」もの
この物語の主人公であり、語り部であるのは「逃げ出すおっさん(たち)」である。
それも積極的な逃避ではなく、仕事に疲れた男たちの日常からの衝動的な退避である。
ブラックな職場環境、つらい現実、虚しさは折に触れ回想される。ブラック自慢の創作は
今日ではもはや珍しくはなく、むしろ主人公達の労働環境は極端に劣悪ともいいがたいが、
ちょっとした描写、セリフのディティールが、仕事に圧殺される恐怖や不安よりも
人生の疲れに擦り切れていく感覚を浮かび上がらせている。
これらの要素は、そもそも相互に相性が悪く、並立困難である。
一歩間違えれば、目も当てられないバランスとなる。
脳科学、遺伝子、それらに素人が手を出せば、非常に浅薄なアクセサリーにしかならない。
といって、SF設定を重視するならば、ライトな人物描写や展開は読者にとりかえってノイズとなる。
サラリーマンの気だるさの描写は、リアルタイムの実体験か相応の空想力がなければ説得力を持たないが、そんな人の多くは、そもそも小説を書く時間も気力もない。
この点、本作は非常にバランスとまとまりがよい。
単なる「ミスマッチ小説」ではなく「小気味の良いミスマッチ小説」と呼んだ所以だ。
もちろん、細かいことをいえば、気になる点は皆無ではない。主人公コンビ、ヒロイン、敵役それぞれが「なぜそういう行動をとったのか」「そういう気になったのか」、その動機、行動原理について、もちろんそれぞれ説明はあるのだけれど、今一つつかめず、結末付近で「ん?」と感じた点もある。もっとも、私自身は「登場人物の気持ち」を問う国語問題でことごとく全滅してきた読解力の持つ主であるので、あまり参考にならない感想ではある。
構成要素の多様性にもかかわらず、本作は全体として一つの作品としてまとまっている。読後感は非常に爽やかである。物語に統一感を与えているのが、「エピジェネティク・ランドスケープの丘(を駆け上がる)」というモチーフだ。諸要素はここに結ばれ、ディティールの粗(のようなもの)は乗り越えられ、私は「こういう話だったか」と「納得」する。バラバラの諸要素を滑る、この構成力こそが、本作最大の武器といえよう。
察するに筆者は理系の技術者であろう。しかもかなりの手練れのようだ。文理で人間を区分するのは愚かである、というのは私の口癖のようなものであるが、それでも、これだけの小説が理系技術者によって編まれ描かれた、ということに私は嫉妬する。
あと、姫路を生きた街と表現するのは、とても素晴らしい。
荒廃した未来でも、輝くお城、輝く街、それが姫路。
「小気味の良いミスマッチ小説」というのが読後の最初の印象だ。
結末部分に関わらない範囲で紹介するならば、本作は荒廃した近未来関西を舞台に、会社に疲れたサラリーマン2人が、衝動的に社長令嬢を誘拐することからはじまる逃避行の物語だ。社長令嬢に秘められた謎、「クラハ・モチーフ」が、メタファーとしても構造としても、ドラマ全体の軸となっている。
「ミスマッチ小説」と呼んだのは、本書を構成する要素の多様性にある。
作品分析など野暮ではあることは承知しているが、あえてその諸側面を列挙したい。
①ライトな活劇
本作の読み口は、非常に軽い。
設定の深刻さにもかかわらず、主人公たちは楽観的で、もっといえば呑気だ。
直情的に行動し、会社や社会、ヒロイン、敵役に遠慮なく毒づく明るさがあり、読者も、安心して状況を、いわば「ライト」に楽しめるようになっている。
敷居の高いSF短編集の冒頭を飾るに相応しい間口の広い作品と言える。
②本格的な知識に基づくバイオSF
すでに述べたように、物語の鍵となっているのは、ヒロイン「クラハ(シートゥー)」の持つ秘密だ。
それは、脳神経細胞、遺伝子操作、再生医療といった最先端技術をベースとしたSF設定だ。本作では、この分野に関する設定、知識が、サスペンス仕立ての構成で慎重に開示されていく。それは、物語の進展とともにプロットに組み込まれ、詩的に応用されることで、読者に知的充足感を、メインテーマに意味を与えていく。私は、この分野の専門家ではないので、本作設定のどこまでが現在のサイエンスでどこまでがフィクションかを厳密に考証することはできない。ただ、この厄介な素材をこれだけ縦横に振り回すことは、この領域に関する豊富な知識、経験の持ち主でなければ不可能であろう。
③ブラックな労働環境とその疲れを描く「お仕事」もの
この物語の主人公であり、語り部であるのは「逃げ出すおっさん(たち)」である。
それも積極的な逃避ではなく、仕事に疲れた男たちの日常からの衝動的な退避である。
ブラックな職場環境、つらい現実、虚しさは折に触れ回想される。ブラック自慢の創作は
今日ではもはや珍しくはなく、むしろ主人公達の労働環境は極端に劣悪ともいいがたいが、
ちょっとした描写、セリフのディティールが、仕事に圧殺される恐怖や不安よりも
人生の疲れに擦り切れていく感覚を浮かび上がらせている。
これらの要素は、そもそも相互に相性が悪く、並立困難である。
一歩間違えれば、目も当てられないバランスとなる。
脳科学、遺伝子、それらに素人が手を出せば、非常に浅薄なアクセサリーにしかならない。
といって、SF設定を重視するならば、ライトな人物描写や展開は読者にとりかえってノイズとなる。
サラリーマンの気だるさの描写は、リアルタイムの実体験か相応の空想力がなければ説得力を持たないが、そんな人の多くは、そもそも小説を書く時間も気力もない。
この点、本作は非常にバランスとまとまりがよい。
単なる「ミスマッチ小説」ではなく「小気味の良いミスマッチ小説」と呼んだ所以だ。
もちろん、細かいことをいえば、気になる点は皆無ではない。主人公コンビ、ヒロイン、敵役それぞれが「なぜそういう行動をとったのか」「そういう気になったのか」、その動機、行動原理について、もちろんそれぞれ説明はあるのだけれど、今一つつかめず、結末付近で「ん?」と感じた点もある。もっとも、私自身は「登場人物の気持ち」を問う国語問題でことごとく全滅してきた読解力の持つ主であるので、あまり参考にならない感想ではある。
構成要素の多様性にもかかわらず、本作は全体として一つの作品としてまとまっている。読後感は非常に爽やかである。物語に統一感を与えているのが、「エピジェネティク・ランドスケープの丘(を駆け上がる)」というモチーフだ。諸要素はここに結ばれ、ディティールの粗(のようなもの)は乗り越えられ、私は「こういう話だったか」と「納得」する。バラバラの諸要素を滑る、この構成力こそが、本作最大の武器といえよう。
察するに筆者は理系の技術者であろう。しかもかなりの手練れのようだ。文理で人間を区分するのは愚かである、というのは私の口癖のようなものであるが、それでも、これだけの小説が理系技術者によって編まれ描かれた、ということに私は嫉妬する。
あと、姫路を生きた街と表現するのは、とても素晴らしい。
荒廃した未来でも、輝くお城、輝く街、それが姫路。
2.クレーター(東京ニトロ先生)
紹介文によれば、作者の東京ニトロ先生は「読む麻薬」「ラーメン二郎・文章版」と呼ばれているらしい。私は、そこに「パニック小説の村上春樹」を加えたい。
本作は、長野県の村に発生した正体不明の災害をめぐる物語だ。
故郷に落下した巨大隕石、そして謎の霧。
ふいに就活の現実から逃げだした「わたし」は、海外の放浪先でその「災害」を知る。
「かみさまに会いに行こうよ、ねえさん」
何もかも異様な事態の中、振りほどいたはずの過去と現在が交錯する。
警察、自衛隊を振り払い、たどり着いた災害の中心、「クレーター」で彼女が見たものは…。
私の稚拙な文章力で、本作のアオリを書くならば、このような感じだろうか。
誰もが一見してわかる本作の大きな特徴は、そのこってりした文体だ。
ひとつの段落、いやひとつの文の中さえ、細やかな情景描写、心象描写、そして言い直し、がこれでもかというぐらいに塗り重ねられ、かぶせられていく。そして、不意につきはなすように淡白な一人称「わたし」の所感が挿入される。
そのリズム、バランス、透明感は、素人目にも「村上春樹」を感じさせる。
一点、私にとって「村上春樹」をはるかに超えている点は、その明快さである。
「面白い」、「有名だ」、「海外でも著名」だと聞かされ、「村上春樹」に挑戦するたび、「何が伝えたいのか、何をやりたいのか」、「どうしてそんな持って回った書き方なのか」、「要するにオチはなにやねん」、あげく「頭で理解じゃなく肌で感じるもの?はあ?」と叫びたくなり、今や私の中では、「わからないのが村上春樹」が定説である。何冊も読んで印象に残っているシーン、作品は、ほぼない。しかし、本作は違う、その文章ごと、その段落ごと、シーンごと、そして全体として与える印象は鮮明である。くどくてこってりしていても、その味は確かにわかる。二郎系は食べたことはないが、そんな「天下一品」な印象だ。もっとも、「わからないのが村上春樹」であるならば、あるいは私なぞに明快と評されることは、ひょっとしたら失礼に聞こえるかもしれないけれども。
何しろ、本作は歴としたSFである。空想科学の世界であればこそ、幻想的、悪く言えば「韜晦」したような描写ではなく、確かな観察や論理性に基づく明快な記述がありがたい。パニック作品の醍醐味は、「現実にはない災害」、少なくともまだ経験も、まだ発生していない事態について、「起こりうること」「起こるはずのこと」が、その細部までシミュレートされることにある、と私は思う。本作は、この「こってりとしつつも明快な」文章で、その「まだない事態」の再現に成功しており、その知識、想像力に素直に脱帽する。個人的には、こういう思考の展開ができる人をすごく尊敬する。多くのパニック映画その他の作品、さらには関連書籍など、勉強し、この異常事態について考え続けてきたのだろうと。
そして意外にも、本作を貫くテーマはある種の成長劇である。「商品になれ」という就職活動の現実から逃げ出した「わたし」は、この異常事態の中、故郷の日々、旅先での出来事の回想、過去の恋人、家族との対話を通じ、自らを取り戻し、「選択をするという選択」に至る。ラスト数ページ、たたみかけるようなクライマックスは、この濃厚な文体と相まって、私をぐいぐいと引き込んだ。そして、唐突に迎える散文的な結末。そのギャップは、私を奈落に突き落とし、強烈な読後感を心に刻みつけた。
読み終わった時、私の心に浮かんだ感想。
「そうか。ラーメン二郎なのは文体だけではなかったのか。」
紹介文によれば、作者の東京ニトロ先生は「読む麻薬」「ラーメン二郎・文章版」と呼ばれているらしい。私は、そこに「パニック小説の村上春樹」を加えたい。
本作は、長野県の村に発生した正体不明の災害をめぐる物語だ。
故郷に落下した巨大隕石、そして謎の霧。
ふいに就活の現実から逃げだした「わたし」は、海外の放浪先でその「災害」を知る。
「かみさまに会いに行こうよ、ねえさん」
何もかも異様な事態の中、振りほどいたはずの過去と現在が交錯する。
警察、自衛隊を振り払い、たどり着いた災害の中心、「クレーター」で彼女が見たものは…。
私の稚拙な文章力で、本作のアオリを書くならば、このような感じだろうか。
誰もが一見してわかる本作の大きな特徴は、そのこってりした文体だ。
ひとつの段落、いやひとつの文の中さえ、細やかな情景描写、心象描写、そして言い直し、がこれでもかというぐらいに塗り重ねられ、かぶせられていく。そして、不意につきはなすように淡白な一人称「わたし」の所感が挿入される。
そのリズム、バランス、透明感は、素人目にも「村上春樹」を感じさせる。
一点、私にとって「村上春樹」をはるかに超えている点は、その明快さである。
「面白い」、「有名だ」、「海外でも著名」だと聞かされ、「村上春樹」に挑戦するたび、「何が伝えたいのか、何をやりたいのか」、「どうしてそんな持って回った書き方なのか」、「要するにオチはなにやねん」、あげく「頭で理解じゃなく肌で感じるもの?はあ?」と叫びたくなり、今や私の中では、「わからないのが村上春樹」が定説である。何冊も読んで印象に残っているシーン、作品は、ほぼない。しかし、本作は違う、その文章ごと、その段落ごと、シーンごと、そして全体として与える印象は鮮明である。くどくてこってりしていても、その味は確かにわかる。二郎系は食べたことはないが、そんな「天下一品」な印象だ。もっとも、「わからないのが村上春樹」であるならば、あるいは私なぞに明快と評されることは、ひょっとしたら失礼に聞こえるかもしれないけれども。
何しろ、本作は歴としたSFである。空想科学の世界であればこそ、幻想的、悪く言えば「韜晦」したような描写ではなく、確かな観察や論理性に基づく明快な記述がありがたい。パニック作品の醍醐味は、「現実にはない災害」、少なくともまだ経験も、まだ発生していない事態について、「起こりうること」「起こるはずのこと」が、その細部までシミュレートされることにある、と私は思う。本作は、この「こってりとしつつも明快な」文章で、その「まだない事態」の再現に成功しており、その知識、想像力に素直に脱帽する。個人的には、こういう思考の展開ができる人をすごく尊敬する。多くのパニック映画その他の作品、さらには関連書籍など、勉強し、この異常事態について考え続けてきたのだろうと。
そして意外にも、本作を貫くテーマはある種の成長劇である。「商品になれ」という就職活動の現実から逃げ出した「わたし」は、この異常事態の中、故郷の日々、旅先での出来事の回想、過去の恋人、家族との対話を通じ、自らを取り戻し、「選択をするという選択」に至る。ラスト数ページ、たたみかけるようなクライマックスは、この濃厚な文体と相まって、私をぐいぐいと引き込んだ。そして、唐突に迎える散文的な結末。そのギャップは、私を奈落に突き落とし、強烈な読後感を心に刻みつけた。
読み終わった時、私の心に浮かんだ感想。
「そうか。ラーメン二郎なのは文体だけではなかったのか。」
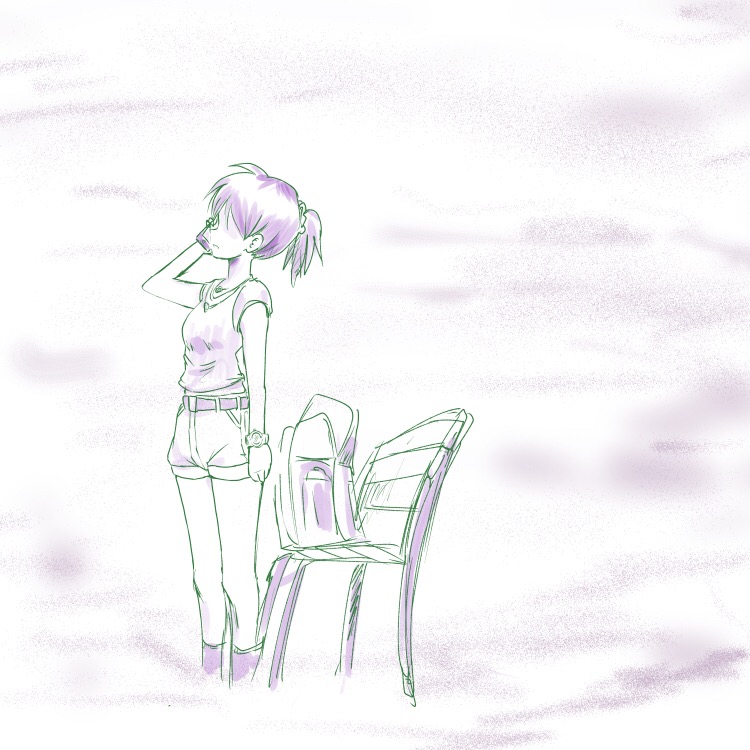
『セリエント』kindle版が出たようです。
おめでとうございます。
kindleにレビューを上げるべきですが、そのためのアカウントを持たないので、ここに記します。どなたか、レビューを書かれるときの参考にしてください。
ーーーーーー
☆☆☆☆☆ 開運間違いなし
投稿者 KATO Institute (トップ1000,000,000レビュアー) 投稿日2016/05/29
『私はサ ークル関係者でもないし作者の個人的な知り合いでもないただの通りすがりのユ ーザ ーなのですが 、ふと気まぐれで検索した結果出てきたこの本のタイトルが気になって思わず購入しました 。内容について結論から言うとただただ最高です !どれも個性豊かで面白く感動できる物語ばかりで 、時に横隔膜が破れるほど笑い 、また時に脱水症状を起こすほど大泣きして読了までに計四回入院しました !それに … …これはあまり他人に教えたくないのですが 、この本を読んでから 、なんだか身の回りでいいことばかり起きるようになったんです 。具体的に言うと昨日は宝くじで二億円が当たり庭から突如として温泉と油田が湧き思わず家を飛び出したら偶然ぶつかった人がたまたま好みド真ん中の人でしかも向こうから積極的にデ ートに誘ってきたしさらに激突した衝撃で身長が十センチ伸び体重が五キロ落ちたんです !この本のおかげで私の人生は変わりました 。親兄弟一族郎党恋人友人赤の他人に犬猫鳩カラスにも勧めようと思います !めざめよ地球人ども !』、とどなたかおっしゃってました。実際読んだ身としては、その内容の何割かは賛同できるので、ここに記します。
おめでとうございます。
kindleにレビューを上げるべきですが、そのためのアカウントを持たないので、ここに記します。どなたか、レビューを書かれるときの参考にしてください。
ーーーーーー
☆☆☆☆☆ 開運間違いなし
投稿者 KATO Institute (トップ1000,000,000レビュアー) 投稿日2016/05/29
『私はサ ークル関係者でもないし作者の個人的な知り合いでもないただの通りすがりのユ ーザ ーなのですが 、ふと気まぐれで検索した結果出てきたこの本のタイトルが気になって思わず購入しました 。内容について結論から言うとただただ最高です !どれも個性豊かで面白く感動できる物語ばかりで 、時に横隔膜が破れるほど笑い 、また時に脱水症状を起こすほど大泣きして読了までに計四回入院しました !それに … …これはあまり他人に教えたくないのですが 、この本を読んでから 、なんだか身の回りでいいことばかり起きるようになったんです 。具体的に言うと昨日は宝くじで二億円が当たり庭から突如として温泉と油田が湧き思わず家を飛び出したら偶然ぶつかった人がたまたま好みド真ん中の人でしかも向こうから積極的にデ ートに誘ってきたしさらに激突した衝撃で身長が十センチ伸び体重が五キロ落ちたんです !この本のおかげで私の人生は変わりました 。親兄弟一族郎党恋人友人赤の他人に犬猫鳩カラスにも勧めようと思います !めざめよ地球人ども !』、とどなたかおっしゃってました。実際読んだ身としては、その内容の何割かは賛同できるので、ここに記します。
セリエント感想(上)
人工知能が人間の知性を超える時。
シンギュラリティと呼ばれるその「時」は、一部の知的な人々の想像力を掻き立てる一方で、残りの多数に一種の恐怖を与えてきた。人工知能の暴走による人類滅亡といった筋立ては、『火の鳥』や『ターミネーター』に代表されるようにSFでは古典的な題材であるし、また機械が人間の雇用を奪っていく未来図は、産業革命以来から多くの凡庸な人たちを不安に陥れてきた。評者は後者に属する。対して作者のクラック先生は、その「時」を熱烈に待望する技術者の一人である。彼はいう。「その時、私は美少女になれる。」と。
なぜシンギュラリティによって、人は美少女になれるのか。私にはその理屈がさっぱりわからないけれども、とにかくも作者は、その待望者であり、しかもその道についてかなりのプロである。その彼はどのような未来を、その経路を展望しているのか。その興味こそ私が本書を手に取った直接の動機である。したがって、この感想もまた、エンターテインメントとしてではなく、未来予想図として、その可能性と不安について考察することが主な目的となる。果たして人工知能は人間を超えるか、それは人間を支配するか、それは人の仕事を奪うのか。
人工知能が人間の頭脳労働を代替する可能性について、私自身は次の2つの障壁があると考えている。第1に、パフォーマンスの客観化の技術的困難である。機械による判断が人間を代替する過程においては、目標となるパフォーマンスが数値化され、その上で優位が示されなければならないが、現在人間に残されている仕事にはそのような数値化がそもそも難しいものも少なくない。企業であれば、最終的には株主利益の最大化ということになるかもしれないが、その数値の決定要素はあまりにも大きい。第2は、その政治的困難である。パフォーマンスの数値化が仮に技術的に可能であるとしても、それは必ず一面的なものとなる。それについて、見落とされた安全性、不安について人間、とりわけ専門家が激しく抵抗し、最終的には必ず人間のチェックを挟むようになるだろう。医療や運転、人命、福祉に関わる分野において、機械と人間の判断が分かれた場合、どちらに従うべきか、機械の判断が人間の理解を超えた場合、それに従うことができるか。そのような不安を専門家は唱え続け、法制度を以って身を守るだろう。政治が最後に人間に残される仕事だと、私が考える所以である。
一例として、昨年少し話題になった「ハピネス指数」について見てみよう。あるデバイスを人間が身につけ、心拍数その他バイタルをとることで、人間の活発度、幸せさを観測し、それが高ければ会社のパフォーマンスを上げるという話だ。ハビネスちゅうにゅう。会社はオッケー。ハーバードビジネスレビュー(日本版)という品のない雑誌で取り上げられたこの記事は、明らかに開発会社のプロモーションの一環だが、このような話を誰が間に受けるだろうか。仮に、それが正しかったとして、会社のパフォーマンスのために、ハッピーでなければならないといわれ、そこに気持ち悪さは残らないだろうか。
「セリエント」では、この種の疑問に見事に答える形で、人工知能が普及する極めて説得力のある未来図を展開している。第1に、自動運転などは、それは現在の欧米圏ではなく、アフリカ等の国家諸制度、とりわけ人権に関わる制度が未整備な土地においてまず普及するであろうというものだ。政治的困難の壁を延辺において打ち破る、周辺変革説の一種とも言える。第2に、金融取引など、比較的パフォーマンスが明確な分野において、まず人間にとって変わるということだ。現実にも金融取引は、コンピューターへの代替は最も早くから進んできた分野で、古くは30年前の1987年にブラックマンデーは、機械が一斉に同じ判断をしたからこそ発生したという説もあるほどだ。第3に、既存の巨大IT企業の変質である。かつての通信会社が、「情報を運ぶ」ことを価値とし、今日のIT企業が「情報を集める」ことを価値としている。これらを踏まえた上で、「情報を理解する」AI企業が成立する。その際には、通信企業が今日でも重要なインフラ提供産業であるのと同様に、IT産業は情報の売却によって新しい産業基盤を提供するという。また、計算リソースもウェブ上で市場取引される(オープンデバイス財団)。このような重層的な産業理解は極めて説得的である。
また、その過程において、新しい技術が実現するたびに「それはAIではない」とみなされる現象、またその過程で日本はおそらく乗り遅れてしまうのではないか、という予見もまた、著者の現代日本の政治経済に対する洞察に裏打ちされたものであろう。特に「実現したものはAIではない」は至言。そうやって世界が漸進的に塗り変わっていく様を言い当てている気がする。これだけの世界観・シナリオを、既存の材料や技術の延長線上から、予見し、構築してみせる著者の見識には大いに唸らされた。政治経済オタもとい造詣の深いの本職技術者おそるべき。
(続く)
人工知能が人間の知性を超える時。
シンギュラリティと呼ばれるその「時」は、一部の知的な人々の想像力を掻き立てる一方で、残りの多数に一種の恐怖を与えてきた。人工知能の暴走による人類滅亡といった筋立ては、『火の鳥』や『ターミネーター』に代表されるようにSFでは古典的な題材であるし、また機械が人間の雇用を奪っていく未来図は、産業革命以来から多くの凡庸な人たちを不安に陥れてきた。評者は後者に属する。対して作者のクラック先生は、その「時」を熱烈に待望する技術者の一人である。彼はいう。「その時、私は美少女になれる。」と。
なぜシンギュラリティによって、人は美少女になれるのか。私にはその理屈がさっぱりわからないけれども、とにかくも作者は、その待望者であり、しかもその道についてかなりのプロである。その彼はどのような未来を、その経路を展望しているのか。その興味こそ私が本書を手に取った直接の動機である。したがって、この感想もまた、エンターテインメントとしてではなく、未来予想図として、その可能性と不安について考察することが主な目的となる。果たして人工知能は人間を超えるか、それは人間を支配するか、それは人の仕事を奪うのか。
人工知能が人間の頭脳労働を代替する可能性について、私自身は次の2つの障壁があると考えている。第1に、パフォーマンスの客観化の技術的困難である。機械による判断が人間を代替する過程においては、目標となるパフォーマンスが数値化され、その上で優位が示されなければならないが、現在人間に残されている仕事にはそのような数値化がそもそも難しいものも少なくない。企業であれば、最終的には株主利益の最大化ということになるかもしれないが、その数値の決定要素はあまりにも大きい。第2は、その政治的困難である。パフォーマンスの数値化が仮に技術的に可能であるとしても、それは必ず一面的なものとなる。それについて、見落とされた安全性、不安について人間、とりわけ専門家が激しく抵抗し、最終的には必ず人間のチェックを挟むようになるだろう。医療や運転、人命、福祉に関わる分野において、機械と人間の判断が分かれた場合、どちらに従うべきか、機械の判断が人間の理解を超えた場合、それに従うことができるか。そのような不安を専門家は唱え続け、法制度を以って身を守るだろう。政治が最後に人間に残される仕事だと、私が考える所以である。
一例として、昨年少し話題になった「ハピネス指数」について見てみよう。あるデバイスを人間が身につけ、心拍数その他バイタルをとることで、人間の活発度、幸せさを観測し、それが高ければ会社のパフォーマンスを上げるという話だ。ハビネスちゅうにゅう。会社はオッケー。ハーバードビジネスレビュー(日本版)という品のない雑誌で取り上げられたこの記事は、明らかに開発会社のプロモーションの一環だが、このような話を誰が間に受けるだろうか。仮に、それが正しかったとして、会社のパフォーマンスのために、ハッピーでなければならないといわれ、そこに気持ち悪さは残らないだろうか。
「セリエント」では、この種の疑問に見事に答える形で、人工知能が普及する極めて説得力のある未来図を展開している。第1に、自動運転などは、それは現在の欧米圏ではなく、アフリカ等の国家諸制度、とりわけ人権に関わる制度が未整備な土地においてまず普及するであろうというものだ。政治的困難の壁を延辺において打ち破る、周辺変革説の一種とも言える。第2に、金融取引など、比較的パフォーマンスが明確な分野において、まず人間にとって変わるということだ。現実にも金融取引は、コンピューターへの代替は最も早くから進んできた分野で、古くは30年前の1987年にブラックマンデーは、機械が一斉に同じ判断をしたからこそ発生したという説もあるほどだ。第3に、既存の巨大IT企業の変質である。かつての通信会社が、「情報を運ぶ」ことを価値とし、今日のIT企業が「情報を集める」ことを価値としている。これらを踏まえた上で、「情報を理解する」AI企業が成立する。その際には、通信企業が今日でも重要なインフラ提供産業であるのと同様に、IT産業は情報の売却によって新しい産業基盤を提供するという。また、計算リソースもウェブ上で市場取引される(オープンデバイス財団)。このような重層的な産業理解は極めて説得的である。
また、その過程において、新しい技術が実現するたびに「それはAIではない」とみなされる現象、またその過程で日本はおそらく乗り遅れてしまうのではないか、という予見もまた、著者の現代日本の政治経済に対する洞察に裏打ちされたものであろう。特に「実現したものはAIではない」は至言。そうやって世界が漸進的に塗り変わっていく様を言い当てている気がする。これだけの世界観・シナリオを、既存の材料や技術の延長線上から、予見し、構築してみせる著者の見識には大いに唸らされた。政治経済オタもとい造詣の深いの本職技術者おそるべき。
(続く)
セリエント感想(下)
一方、「代替可能性」という論点から見るならば、この説得力のあるシナリオは、その制約をも示している。上記の条件を裏返せば、先進諸国への浸透の遅れ、金融以外の産業への参入可能性、既存IT巨大企業の変質、住み分けに至る諸々の課題が浮かび上がる。また、本稿の活劇部分で描写される人工知能からも、筆者は「シンギュラリティ」の到来をそれほど容易に考えているわけではないことがわかる。
例えば、一つは、主人公リアがAIの改善のために戦地に来たという物語の舞台設定そのものであり。もう一つは主人公リアのアドリブによる巨大なAIとの対決。後者について、巨大なリソースと技術を持つ「敵」を少数の主人公の知恵と工夫で戦う構図は、エンターテインメントとしての本作の醍醐味である。また、本作ではそのような戦いが生じる技術的条件、互角以上に戦える条件についても主人公補正だけではなく、かなり慎重にぶ描写されている(ネタバレすると、敵との通信ラグ、計算リソースそのものが市場取引されている世界)。ただ、いずれにせよ、もし、このような対決がありえるならば、そこでは、確かに「人間」が必要とされる世界が描かれている。そこでは、人間によるチューニングと改善が確実に必要とされているのである。ただし、そこで必要なものとして生き残るのは「天才ヒロイン」に限るのだけれども。作者いわく「プログラミングのできない人間は皆死ぬ」。(評者こたえて「むしろ政治屋は死せず」)
その他、作中でキーワードになる標準人間行動モデルについて、未来のAIによる行動予測が本当に一つのモデルに帰結するのか、(あと、作品において「マンハントのためのモデル構築から対AIの読み合いによる戦い」という戦いの構図の移動(そこで、必要とされる技術がそもそもかなり違う気がする)は少し、私の理解力ではわかりにくかった)、その推計は簡単にアップデートされるか、試行回数が十分に少ないものでモデルの修正、評価は可能か、確率論的な提示について。これらは、現行予測し得る技術の限界点とともに、「計算量の爆発回避のためにモデルは常によりシンプルでなければならない(人間と同様の取捨選択が必要)」「つまり人間を上回る判断とともに、人間と同じように『ばか』にならなければならない」「一人の人間の行動予測が可能か」(歴史心理学では不可能とされた)とかとかの根本的な哲学的な問題もつきまとっているように思われる。
とにもかくにも、痛快軍事冒険活劇を読みながら、これほどに未来について刺激を受け、いろいろ考えさせられた本作は、SFとして大いに読むべき価値があるものといって間違いない。人工知能の展開についての次の作品が待ち遠しいものである。
最後に、娯楽小説という点から本作を評価したおきたい。本作は、上記の骨太な世界観と、娯楽との融合を図る試みである。それはミリタリー活劇であり、また美女ヒロインが活躍するライトノベルでもあるという。確かに、ヒロイン像は魅力的である。思わずFAを書くほどである。(次項参照)。なお、作者は冒頭で述べたように、シンギュラリティによる美少女転生の可能性に賭けている。そこで、作者に問いかけたいことは、いったい描きたいのは、「萌えるヒロイン」なのか「なりたいヒロイン」なのか。ということだ。各種スペックの高さ、飛び級で(幅広い見識獲得のための)留年といった像は、明らかに作者や作者の理想像を重ねているようであり、ヒーローとの絡み、お姫様扱いなどは、最後のほんのわずかな「デレ」。明らかにラノベの方法論に則っている。オチなどもラノベ的に非常に微笑ましい。「サイコパスに囲まれたお姫様」という評をどなたかが行っていたが、その二側面はどうも座りが悪い。
本作は、印刷、頒布した同人誌であり、「売り上げ」との関わりでどうしてもラノベとして、娯楽小説でなければならなかったのであろう。しかし、一読者として私は、リアは作者が「なりたいヒロイン像」で徹底してほしかったように思う。「デレ不要論者」の戯言だけれども。
以上
一方、「代替可能性」という論点から見るならば、この説得力のあるシナリオは、その制約をも示している。上記の条件を裏返せば、先進諸国への浸透の遅れ、金融以外の産業への参入可能性、既存IT巨大企業の変質、住み分けに至る諸々の課題が浮かび上がる。また、本稿の活劇部分で描写される人工知能からも、筆者は「シンギュラリティ」の到来をそれほど容易に考えているわけではないことがわかる。
例えば、一つは、主人公リアがAIの改善のために戦地に来たという物語の舞台設定そのものであり。もう一つは主人公リアのアドリブによる巨大なAIとの対決。後者について、巨大なリソースと技術を持つ「敵」を少数の主人公の知恵と工夫で戦う構図は、エンターテインメントとしての本作の醍醐味である。また、本作ではそのような戦いが生じる技術的条件、互角以上に戦える条件についても主人公補正だけではなく、かなり慎重にぶ描写されている(ネタバレすると、敵との通信ラグ、計算リソースそのものが市場取引されている世界)。ただ、いずれにせよ、もし、このような対決がありえるならば、そこでは、確かに「人間」が必要とされる世界が描かれている。そこでは、人間によるチューニングと改善が確実に必要とされているのである。ただし、そこで必要なものとして生き残るのは「天才ヒロイン」に限るのだけれども。作者いわく「プログラミングのできない人間は皆死ぬ」。(評者こたえて「むしろ政治屋は死せず」)
その他、作中でキーワードになる標準人間行動モデルについて、未来のAIによる行動予測が本当に一つのモデルに帰結するのか、(あと、作品において「マンハントのためのモデル構築から対AIの読み合いによる戦い」という戦いの構図の移動(そこで、必要とされる技術がそもそもかなり違う気がする)は少し、私の理解力ではわかりにくかった)、その推計は簡単にアップデートされるか、試行回数が十分に少ないものでモデルの修正、評価は可能か、確率論的な提示について。これらは、現行予測し得る技術の限界点とともに、「計算量の爆発回避のためにモデルは常によりシンプルでなければならない(人間と同様の取捨選択が必要)」「つまり人間を上回る判断とともに、人間と同じように『ばか』にならなければならない」「一人の人間の行動予測が可能か」(歴史心理学では不可能とされた)とかとかの根本的な哲学的な問題もつきまとっているように思われる。
とにもかくにも、痛快軍事冒険活劇を読みながら、これほどに未来について刺激を受け、いろいろ考えさせられた本作は、SFとして大いに読むべき価値があるものといって間違いない。人工知能の展開についての次の作品が待ち遠しいものである。
最後に、娯楽小説という点から本作を評価したおきたい。本作は、上記の骨太な世界観と、娯楽との融合を図る試みである。それはミリタリー活劇であり、また美女ヒロインが活躍するライトノベルでもあるという。確かに、ヒロイン像は魅力的である。思わずFAを書くほどである。(次項参照)。なお、作者は冒頭で述べたように、シンギュラリティによる美少女転生の可能性に賭けている。そこで、作者に問いかけたいことは、いったい描きたいのは、「萌えるヒロイン」なのか「なりたいヒロイン」なのか。ということだ。各種スペックの高さ、飛び級で(幅広い見識獲得のための)留年といった像は、明らかに作者や作者の理想像を重ねているようであり、ヒーローとの絡み、お姫様扱いなどは、最後のほんのわずかな「デレ」。明らかにラノベの方法論に則っている。オチなどもラノベ的に非常に微笑ましい。「サイコパスに囲まれたお姫様」という評をどなたかが行っていたが、その二側面はどうも座りが悪い。
本作は、印刷、頒布した同人誌であり、「売り上げ」との関わりでどうしてもラノベとして、娯楽小説でなければならなかったのであろう。しかし、一読者として私は、リアは作者が「なりたいヒロイン像」で徹底してほしかったように思う。「デレ不要論者」の戯言だけれども。
以上

Lovely Fairy with Me
(いしまつ先生:「維嶋津」名義)
最近聞きかじったことだけれども、
SFの面白さは「センスオブワンダー」であるという。
大雑把にいえば、それは「不思議」さへの感動や驚きといったものであるようだ。
しかし、『Lovely Fairy with Me』が私に強く与えた印象は、
不思議というよりはむしろ強烈なリアリティ、それも
「最凶のリアリティ」というべきものだ。
未来技術、SF要素はむしろそれを補強する道具として用いられている。
本作は、高度に発達した美少女育成アプリをテーマにした作品だ。
そこでは、様々な技術進化により、プレイヤーは美少女たちに「会う」ことができる。
物語は、このアプリに入れ込み、廃人となったある人物の末路の描写から始まる。
主人公は、地方都市から都心部の大学へ進学し、その後区役所に就職した公務員。
勤務3年にして帰省した彼は、高校時代の友人が廃人となって死んだことを知る。
その真相を探っていくのがこの作品の主な筋である。
本作が、私に感じさせる強烈なリアリティは次の二つである。
その一つは、「美少女アプリ」の内容である。
これは、今でもTVでCMされているような、スマホの美少女育成型アプリを土台に、脳波、血流測定と音声認識、脳電気刺激デバイスによる触覚等の再現、発達したAIによって、プレイヤーと美少女キャラクターとの、双方向的で高度なコミュニケーションを実現させたものである。
実のところ、私自身はこの種のゲームをやったことはほとんどないのだが、技術、設定、社会的反響その他に関するディティールが無理なく説明されており、「ありうる未来」としての説得力を高めている。また、試みにこのゲームをはじめる主人公が、いろいろ疑いながら、抵抗しながらも、このゲームに魅かれていく描写は、読む者にリアルタイムでゲームをプレイしているような臨場感のあるものだった。
もう一つ、私個人を揺さぶったリアリティは、主人公の心理描写である。本作のモチーフを、私なりの言葉で示すなら「置いてきた過去からの復讐」である。うまくいっていたはずのコミュニケーション。このことが、大きな仇となり、人を傷つけ、自らの心も閉ざす。
そこへ至る主人公は、その家庭事情、また転勤族子弟特有の「処世術」を備えた、非常に特殊な存在である。その「しっぺ返し」もやはり特殊である。しかし、彼が経験したこと、彼の悔悟、ミスには、非常にリアリティがある。生地を離れた、あるいは進学や就職を機に環境を変えたものには、こうした「置いてきた過去」は多かれ少なかれ身に覚えがあるように思われる。例えば「過去のいじめの復讐」が非常に古典的なホラーのテーマであるのは、この種の後ろめたさに呼びかけるものといえる。この作品の場合、「うまくいっていた」と主人公が思ってたところが、また一段の実感を、そして恐怖を誘う。「小さな違和感」「小さなすれ違い」は本当に小さなものであったか、と。
本作において、SF要素は、そうした人間ドラマの舞台装置として用いられてる。
そして、その試みは非常に成功している。
将来予想される魅力的なテクノロジーが、いかに人を導くか、傷を広げるか、昔の名作漫画のことばを借りれば「心のスキマ」をつくか。
ドラマとして完成度は非常に高い。
他方、このような魅力があるだけに、もう少し希望を述べるならば、
主人公が、ヒロインに魅かれていく過程をもう少し克明に、しつこく描いてほしかった。
主人公は、なぜこうなるのか、技術的な要因、主人公側の要因、環境、要素は揃っている。また上で述べたように、その技術の臨場感を描く筆力も素晴らしい。それは、私を「どきり」とさせるものだった。しかし、それだけに、物語の後半、結末に向けて変化していく主人公の心を、プロセスの描写
技術の限界を冷めたように観察する、あの態度はどこに消えたか、
ヒロインが担ったミステリ要素は、主人公の心にどう響いたか。
その過程の説明には確かに不足はない。けれども、その臨場感にもう少し酔いたかった。
要するに、「私ももっとこのゲームにはまっていたかった」のである。
(いしまつ先生:「維嶋津」名義)
最近聞きかじったことだけれども、
SFの面白さは「センスオブワンダー」であるという。
大雑把にいえば、それは「不思議」さへの感動や驚きといったものであるようだ。
しかし、『Lovely Fairy with Me』が私に強く与えた印象は、
不思議というよりはむしろ強烈なリアリティ、それも
「最凶のリアリティ」というべきものだ。
未来技術、SF要素はむしろそれを補強する道具として用いられている。
本作は、高度に発達した美少女育成アプリをテーマにした作品だ。
そこでは、様々な技術進化により、プレイヤーは美少女たちに「会う」ことができる。
物語は、このアプリに入れ込み、廃人となったある人物の末路の描写から始まる。
主人公は、地方都市から都心部の大学へ進学し、その後区役所に就職した公務員。
勤務3年にして帰省した彼は、高校時代の友人が廃人となって死んだことを知る。
その真相を探っていくのがこの作品の主な筋である。
本作が、私に感じさせる強烈なリアリティは次の二つである。
その一つは、「美少女アプリ」の内容である。
これは、今でもTVでCMされているような、スマホの美少女育成型アプリを土台に、脳波、血流測定と音声認識、脳電気刺激デバイスによる触覚等の再現、発達したAIによって、プレイヤーと美少女キャラクターとの、双方向的で高度なコミュニケーションを実現させたものである。
実のところ、私自身はこの種のゲームをやったことはほとんどないのだが、技術、設定、社会的反響その他に関するディティールが無理なく説明されており、「ありうる未来」としての説得力を高めている。また、試みにこのゲームをはじめる主人公が、いろいろ疑いながら、抵抗しながらも、このゲームに魅かれていく描写は、読む者にリアルタイムでゲームをプレイしているような臨場感のあるものだった。
もう一つ、私個人を揺さぶったリアリティは、主人公の心理描写である。本作のモチーフを、私なりの言葉で示すなら「置いてきた過去からの復讐」である。うまくいっていたはずのコミュニケーション。このことが、大きな仇となり、人を傷つけ、自らの心も閉ざす。
そこへ至る主人公は、その家庭事情、また転勤族子弟特有の「処世術」を備えた、非常に特殊な存在である。その「しっぺ返し」もやはり特殊である。しかし、彼が経験したこと、彼の悔悟、ミスには、非常にリアリティがある。生地を離れた、あるいは進学や就職を機に環境を変えたものには、こうした「置いてきた過去」は多かれ少なかれ身に覚えがあるように思われる。例えば「過去のいじめの復讐」が非常に古典的なホラーのテーマであるのは、この種の後ろめたさに呼びかけるものといえる。この作品の場合、「うまくいっていた」と主人公が思ってたところが、また一段の実感を、そして恐怖を誘う。「小さな違和感」「小さなすれ違い」は本当に小さなものであったか、と。
本作において、SF要素は、そうした人間ドラマの舞台装置として用いられてる。
そして、その試みは非常に成功している。
将来予想される魅力的なテクノロジーが、いかに人を導くか、傷を広げるか、昔の名作漫画のことばを借りれば「心のスキマ」をつくか。
ドラマとして完成度は非常に高い。
他方、このような魅力があるだけに、もう少し希望を述べるならば、
主人公が、ヒロインに魅かれていく過程をもう少し克明に、しつこく描いてほしかった。
主人公は、なぜこうなるのか、技術的な要因、主人公側の要因、環境、要素は揃っている。また上で述べたように、その技術の臨場感を描く筆力も素晴らしい。それは、私を「どきり」とさせるものだった。しかし、それだけに、物語の後半、結末に向けて変化していく主人公の心を、プロセスの描写
技術の限界を冷めたように観察する、あの態度はどこに消えたか、
ヒロインが担ったミステリ要素は、主人公の心にどう響いたか。
その過程の説明には確かに不足はない。けれども、その臨場感にもう少し酔いたかった。
要するに、「私ももっとこのゲームにはまっていたかった」のである。

「タクトくん」(アンノジョー先生:「杏野丞」(あんのじょう)名義)
人工知能が感情や自我を獲得する、というのはSFにおける王道のモチーフといえる。そのような作品は、手塚治虫や藤子不二雄の漫画にも幾つかあったし、到底SF愛好者とは自称できない私であっても、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』、『月は無慈悲な夜の女王』などのタイトルは挙げることができる。最近だとアニメ『楽園追放』も、やはり機械による自我の獲得が物語の軸であった。
本作は、「タクトくん」と呼ばれる多機能炊飯器の話である。物語は、自我を獲得した「彼」が、その持ち主の「人生を再び炊きたての白米のように熱く、かがやくものにしなければならない」と決意するところから始まる。「彼」は、どのようにして、彼女の人生を変えていくのか。
「道具が自我を獲得する」というお話は、(日本人に限定されるかどうかわからないけれども)八百万の神だとかフェティシズムがどうとか指摘するまでもなく、「道具に名前をつけること」がまったく珍しくない私たちの文化にとっては非常に馴染みやすい。「初音ミク」は、生まれた直後に、「自我を持つ機会の消滅の悲哀」を歌わされた。
しかし、本当に「機械が感情を持つ」ならば、まず問題となるのが、誰がどのようにそれを認識するのか、ということだ。それは、翻って「感情」「人間らしさ」の定義、「高度に発達した応答プログラムとの違いは?」といった面倒な問いを呼び起すものの、たいていの作品では、2、3の問答を通じて、感情の所在を確認することが通例となっている。本作では、この難所をむしろ逆手に、炊飯器の「人知れぬ決意」と、その努力、帰結が描かれる。
「人知れぬ」というところに、私は、あるいは私たちは弱い。竃炊きのような熱い情熱を持つ「タクトくん」の挑戦は、その行為の規模、インパクト、その影響力のどれをとっても薄く儚い。地味だ。持ち主を軸とした人間ドラマにおいて、「彼」は何かをなしえたのか、「彼視点」に立つ読者であってさえ、はっきりと「そうだ」とはいえないだろう。それだけに、この物語は、ほのかな寂しさ、小さな心の穴を穿つ。『セリエント』という不思議な作品集の最後を締めるにあたり、本作はちょうどいい具合の読書感をもたらしている。
「タクトくん」はまた、偶然ではあると思うけれども、『セリエント』という作品集の中でも、SF特有の技術や不思議と、登場する人物の物語との関わりという点で、独特の位置を占めている。「過去との対峙とSF」という軸から顧みるならば、「登坂車線」は、主人公たちは現在を含む過去から逃避する作品であり、SFはこのドラマの起点ではあり転機であるが、総じて中立である。「セリエント」では、そもそも「過去」をほぼまったく振り返らない圧倒的な未来志向の物語であり、強いて言うならば「過去」はモブとして未来の技術に蹂躙されている。これらに対し、「クレーター」「Lovely Fairy with Me」は、主人公が「過去に逆襲され、飲み込まれる」物語であり、SF要素は過去が主人公を覆い尽くす媒体となって現れている。「タクトくん」は、この2作とはまったく対照的に、主人公が過去と和解する話であり、SFはその和解を後押ししている。いわば、「人と過去」との対峙という普遍的なテーマとの関わりで、この作品だけが唯一「明るい未来」を提示している。このような構図、そして作品の配置は、おそらく意図したものではないだろうけれども、このことが、本作の「はかなさ」や後を引く読後感をよりいっそう強くしている。
とにもかくにも、この万能炊飯器。
もし実現したら、私は真っ先に買う。
お値段はボーナス2ヶ月分?
ボーナスなんて、はじめからないから平気。
なお、この作品を読むまで、私にとって「感情を持つ家電」といえば、島本和彦『ワンダービット』の「ポットちゃん」であった。作者がこの作品をご存知かどうか、もしご存知ならその感想などを聞いてみたいものである。
人工知能が感情や自我を獲得する、というのはSFにおける王道のモチーフといえる。そのような作品は、手塚治虫や藤子不二雄の漫画にも幾つかあったし、到底SF愛好者とは自称できない私であっても、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』、『月は無慈悲な夜の女王』などのタイトルは挙げることができる。最近だとアニメ『楽園追放』も、やはり機械による自我の獲得が物語の軸であった。
本作は、「タクトくん」と呼ばれる多機能炊飯器の話である。物語は、自我を獲得した「彼」が、その持ち主の「人生を再び炊きたての白米のように熱く、かがやくものにしなければならない」と決意するところから始まる。「彼」は、どのようにして、彼女の人生を変えていくのか。
「道具が自我を獲得する」というお話は、(日本人に限定されるかどうかわからないけれども)八百万の神だとかフェティシズムがどうとか指摘するまでもなく、「道具に名前をつけること」がまったく珍しくない私たちの文化にとっては非常に馴染みやすい。「初音ミク」は、生まれた直後に、「自我を持つ機会の消滅の悲哀」を歌わされた。
しかし、本当に「機械が感情を持つ」ならば、まず問題となるのが、誰がどのようにそれを認識するのか、ということだ。それは、翻って「感情」「人間らしさ」の定義、「高度に発達した応答プログラムとの違いは?」といった面倒な問いを呼び起すものの、たいていの作品では、2、3の問答を通じて、感情の所在を確認することが通例となっている。本作では、この難所をむしろ逆手に、炊飯器の「人知れぬ決意」と、その努力、帰結が描かれる。
「人知れぬ」というところに、私は、あるいは私たちは弱い。竃炊きのような熱い情熱を持つ「タクトくん」の挑戦は、その行為の規模、インパクト、その影響力のどれをとっても薄く儚い。地味だ。持ち主を軸とした人間ドラマにおいて、「彼」は何かをなしえたのか、「彼視点」に立つ読者であってさえ、はっきりと「そうだ」とはいえないだろう。それだけに、この物語は、ほのかな寂しさ、小さな心の穴を穿つ。『セリエント』という不思議な作品集の最後を締めるにあたり、本作はちょうどいい具合の読書感をもたらしている。
「タクトくん」はまた、偶然ではあると思うけれども、『セリエント』という作品集の中でも、SF特有の技術や不思議と、登場する人物の物語との関わりという点で、独特の位置を占めている。「過去との対峙とSF」という軸から顧みるならば、「登坂車線」は、主人公たちは現在を含む過去から逃避する作品であり、SFはこのドラマの起点ではあり転機であるが、総じて中立である。「セリエント」では、そもそも「過去」をほぼまったく振り返らない圧倒的な未来志向の物語であり、強いて言うならば「過去」はモブとして未来の技術に蹂躙されている。これらに対し、「クレーター」「Lovely Fairy with Me」は、主人公が「過去に逆襲され、飲み込まれる」物語であり、SF要素は過去が主人公を覆い尽くす媒体となって現れている。「タクトくん」は、この2作とはまったく対照的に、主人公が過去と和解する話であり、SFはその和解を後押ししている。いわば、「人と過去」との対峙という普遍的なテーマとの関わりで、この作品だけが唯一「明るい未来」を提示している。このような構図、そして作品の配置は、おそらく意図したものではないだろうけれども、このことが、本作の「はかなさ」や後を引く読後感をよりいっそう強くしている。
とにもかくにも、この万能炊飯器。
もし実現したら、私は真っ先に買う。
お値段はボーナス2ヶ月分?
ボーナスなんて、はじめからないから平気。
なお、この作品を読むまで、私にとって「感情を持つ家電」といえば、島本和彦『ワンダービット』の「ポットちゃん」であった。作者がこの作品をご存知かどうか、もしご存知ならその感想などを聞いてみたいものである。

