第二部 第一話 『幽霊賭博師』
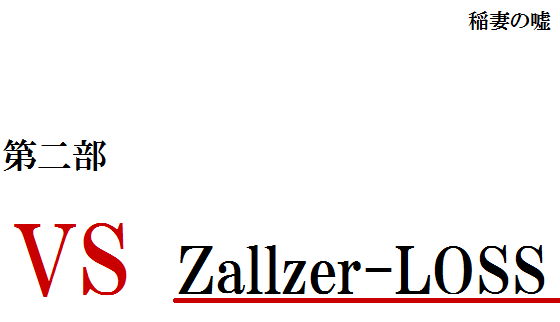
ヴェムコットがザルザロスに負けるのは、これで百度目だった。
盤面を見渡し、深呼吸して、己の敗北をヴェムコットは認めた。対面に座っているザルザロスを見る。
――緑色の猟師の服を着た青年だ。癖の強い金髪を長く伸ばし、時折あくびをしながら盤面を俯瞰している。石のように硬く思える瞳は深い紫電。組んだ腕を押さえた指で叩くのは考え事をするときの彼の癖。ヴェムコットはあらためて盤面を見下ろした。そこには黒と白の駒が入り乱れて、一三六の格子に区切られた戦場に陣を敷いている。お互いに十八から二十二の強弱硬軟の駒を握り取り、相手の王将を奪り合いするシンプルな戦争遊戯。この遊びが、ヴェムコットは好きだった。だから、ザルザロスにこの遊戯の手解きをしたのもヴェムコットだ。けれどただの一度も、ヴェムコットはザルザロスに勝てなかった。それがもう、百度も続いている。
なお不思議なのは、この賭博師あがりの<フーファイター>が、すでにこの勝負が『詰み』に入っているのに気づいていない、ということ。当然のようにザルザロスは頬をかき、目を瞬かせながら、次の一手について考え続けている。いつもなら、ヴェムコットは完成王手をかけられた段階で自らの王を転がす。だが、ふと思い立って、続行してみよう、と思った。自軍の白駒の中から鎧を着けた獣頭人を指の背中でわずかに動かした。続いて猫悪魔、鳥弓兵と動かし――この遊びは一度に三つまで駒を動かしていいのだ――ザルザロスの出方を見る。
ザルザロスは軽く鼻を鳴らして、それぞれ三つの自軍を動かした。陣が分かれ、盤面の中央に空隙が生まれた。詰みを見逃しておきながら、それは王手へと至る道――可愛げのないやつだ、とヴェムコットは思った。わざわざ負け戦を続行させてしまったことに不貞腐れながら、口火を切った。
「知ってるか、ザルザロス。今度の〈新人〉のこと?」
「さあ、俺のところには来てないな――弓兵いただき」
指をしゃくって駒を拾っていくザルザロスに、ヴェムコットは顔をしかめた。
「気にならないのか? やつは強いぞ、たぶん」
「強かろうと弱かろうと、挑んで来るなら受けるだけだし――それに俺に会うまで強かったなんてやつは、いくらでもいるしな」
ヴェムコットが三手放つと、それをかき消すようにザルザロスが陣を敷き直してきた。この〈フーファイター〉は、定石なんてろくに知りもしないくせに、ここぞという勝負所で失策を打つことがほとんどない。なぜだろう――ヴェムコットはもうずいぶん永く、その疑問に心を奪われている。奪われながら、言葉を重ねた。
「確かに〈収穫期〉のすぐ後は、いくらか〈リターナー〉が出る。出るが、その中から〈フーファイター〉を倒して来るやつなんて数期に一度だ。そうだろ?」
「そうだな」
「それがもう、やつは三機も〈フーファイター〉を落としてる」
ヴェムコットは指を三つ立てて、それが畏怖されるべき紋章かのようにザルザロスの顔に突きつけた。
「尋常じゃない勝負速さだ。セルディム、ランキリフ、ノスヴァイス。一番経験が浅かったのはセルディムだったが、一番強かったのもセルディムだ。やつは、この蒸気船に乗り込んですぐ、セルディムに仕掛けたらしい」
「セルディム? ああ、絵描きのあいつか。そういえばいたな、そんなの」
「このままの速さでいけば、やつは次の〈収穫期〉が来る前に達成するかもしれない」
この幽霊蒸気船〈アリューシャン・ゼロ〉は、船内に積み込んだ〈バラストグール〉の数が少なくなってくると、〈陸〉に接岸して新しい乗客を待つ。――走り続けるために。そのことを、〈収穫〉する、という。
ザルザロスがひょいと自軍の黒駒を持ち上げて眺めがら、尋ねた。
「達成するって、何を?」
「だから――全部位奪還」
「それはないよ」
「なぜ」
「俺がいるから」
軽く手首が翻り、象牙で出来た黒駒をザルザロスは敵陣深く、ヴェムコットの手元のそばの一点に押し込んだ。切り込んだ先には、無防備の白駒がある。王将だった。
「終わりだな。面白かった」
「――そうかい、それはよかったよ、いや、ほんとの話」
「そうむくれるなよ」ザルザロスは笑った。
「自信を持てよ。お前の方が、この遊びは強いんだから」
「完膚なきまでやっつけておいて、よく言うな」
「いや、本当だよ。お前は俺より上手だ。だが、俺はお前を観てる」
「観てる?」
「お前を観ながら、次にお前がどう動くか、限定された思考と盤面を読んでいく。それだけで、お前の攻撃、その矛先を逸らすことくらいわけはない」
「――ふうん」
「怒ったか? やめてもいいよ」
「かなり腹立つが、後学のために聞かせてもらおうかな」
「そうかい、じゃ、続けるか――そう、ここぞって正念場で攻撃が上手く炸裂しなかった時、お前は自分がしくじったと感じてる。大変なことをしてしまったと慌てふためく。自分でも、言われてみれば分かるだろ。それはこの百戦で共通してる。せっかく築いた戦線を作り直そうと、土台に手をかけて自ら努力の盃をひっくり返す。問題なのはそこだよ。落ち着いて冷静になれば、覚えたての俺ごとき、お前の腕ならどうにでもできる。それができないのは、ヴェムコット、お前が己自身に負けてるからだ。俺はなんにもしちゃいない」
「――慰めなんかいらないね。己自身に負けてるって、そんなことない、俺にはさっぱり分からんよ。お前は不思議なことを言うやつだ、ザルザロス」
「そうか?」
「お前は、己自身とやらに負けてないっていうのか」
「さあな、だが、手前を見失わなければ、不得手な遊びでも勝ちくらいは拾える」
「不得手?」
「俺は苦手だからな、将棋は」
ザルザロスは、パタンと黒駒を転がした。
「さっきのやつ、名前、なんだっけ」
「え?」
「新入りの〈バラストグール〉だよ」
「ああ、やつか」
真嶋慶だよ、とヴェムコットが答えると、ザルザロスはふうん、と軽く鼻を鳴らしただけだった。――だが、
彼は、その名前を知っていた。