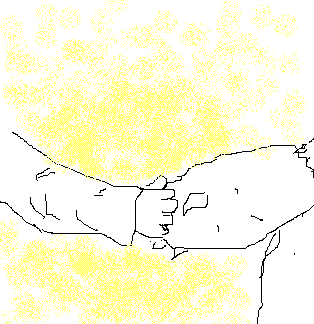第一話 少女と白兎

ズドドドド
ズズ…ン
最近続く良い天気のせいで太陽が頑張って雪が溶けたせいなのか、遠くで小さな雪崩が起きたらしい。
このごろは頻繁に雪崩が起きる。
遠くからやってきたであろうその音で今朝は早く目が覚めた。
「んん…ん、おはよう。」
答えてくれないのはわかっているがとりあえず友達にあいさつをする。
「友達」はいつも眠っている。
「しょうがないわ、冬の雪山で爬虫類を飼うなんてね。あたし、どうかしてるかも。フフフ。」
そうつぶやいた私の独り言はすぐに静寂の中へと霧散していく。
一年間通して雪が降り積もる国ホワイトランド、
その雪山のふもとにポツンと立った小さなレンガ造りの家。
それが私の生活の場である。周囲には音を立てるものは何もない。
そして友達というのは海外から取り寄せたコブラとトカゲだ。
一応部屋の中は暖かいはずなのだが、この2匹にとっては冬眠するほどの気温であるらしい。
ちなみにトカゲはファイアサラマンダー Salamandra salamandraは、ヨーロッパに生息する陸生有尾類。
古来サラマンダー(火蜥蜴)と称されてきたのは本種である。
Salamandra はギリシャ語の「火のトカゲ」または毒を発射するという意味の(ファイアー)が語源。
コブラはキングコブラ(Ophiophagus hannah)は、爬虫綱有鱗目コブラ科に分類されるヘビ。
本種のみでキングコブラ属を形成する。特定動物。
「勉強になったかしら?」
トカゲの方は突然変異とのことで体がやたらでかいのだけれど…。
私は爬虫類が好きなのだ。
写真を見てるだけなのは飽きてしまった。
お金もなぜか家に腐るほどあったので大枚はたいて無理やり手に入れた。
でもたまにもぞもぞと餌を食べるために起き出すくらいでほとんど私に構ってくれない。
「一応友達という役割を与えてやってるのだからたまには私に構いなさいよ。」
ほとんど独り言だが、私が住む家は音という音がなさ過ぎる。
たまに吹く山からの風のほかには何も聞こえない。
小さい家とはいえこんな麗しい幼女が一人住むのには広すぎよ。
「別にさみしくなんかないけどね。」
誰に言うまでもなく…言い聞かせる。
一度に色々なことを考えながら台所に行く。
朝の日課である食料の確認。この地方では何日も吹雪が止まないことがある。そんなときに食料や火種やまきが尽きたら終わりだ。
「もう小麦がないな、また買いに行かないと。」
どうせ家にいても読書をして時間を使うことくらいしかすることがない。
簡単な食事をすませてから今日はすぐに行動に移すことにした。
服を幾重にも着こんで玄関の扉を開ける。
―――――――――――――
私の名前はエヴォル・エキル。エイヴィーと呼んでくれてもいい。
年はわからない。外見から見て10歳くらいだと思う。
いつの頃からか。町から少し離れたところにある雪山のふもとの小さな家に住んでいる。
雪崩が頻繁に起きるこの地域で雪山のふもとに住み続けているのは自殺行為であろう。
しかし危険を避けるために移住するということは選択肢にはない。
他に行く当てがないというのも理由のひとつではあるが、最近はいつ死んでもよいと考えることが大きくなったからだ。
雪崩によって雪に埋もれてこの大地の一部になるのも悪くないのではないか、と。
いつの頃からか、と言ったが細かい記憶はない。物心がついたときにはその小さな家に一人で暮らしていた。親は誰だとか育ててもらったのは誰だとか、全くわからない。
俗に言う記憶喪失というやつだろうか?
最初から頭の中にあった知識については説明できない。
「まぁ、そんなことは気にはならないわ。天才は理屈じゃないのよ。」
私にとっては毎日を生き抜くことのほうが大事だもの。
家にはなぜか大量にお金もあったし、生活に必要な道具もあった。更にはいつ身についたのかわからない生き抜くための知恵もあった。
「まぁ、私は天才で、この雪国で暮らしていて、これからもずっとそれは変わらない、ただし死なない限りの条件付きでみたいなっ、って所ね。」
大事なのは過程ではなく結果だ。親が誰なのかがわかっても何も変わりはしない。事実は『今はいない』ということだけ。
現実が全てだ。
そんなことを小1時間程考えながら歩き続けるといつの間にか町の入り口についていた。
――――――――――――――――――
ズズ…ン
最近続く良い天気のせいで太陽が頑張って雪が溶けたせいなのか、遠くで小さな雪崩が起きたらしい。
このごろは頻繁に雪崩が起きる。
遠くからやってきたであろうその音で今朝は早く目が覚めた。
「んん…ん、おはよう。」
答えてくれないのはわかっているがとりあえず友達にあいさつをする。
「友達」はいつも眠っている。
「しょうがないわ、冬の雪山で爬虫類を飼うなんてね。あたし、どうかしてるかも。フフフ。」
そうつぶやいた私の独り言はすぐに静寂の中へと霧散していく。
一年間通して雪が降り積もる国ホワイトランド、
その雪山のふもとにポツンと立った小さなレンガ造りの家。
それが私の生活の場である。周囲には音を立てるものは何もない。
そして友達というのは海外から取り寄せたコブラとトカゲだ。
一応部屋の中は暖かいはずなのだが、この2匹にとっては冬眠するほどの気温であるらしい。
ちなみにトカゲはファイアサラマンダー Salamandra salamandraは、ヨーロッパに生息する陸生有尾類。
古来サラマンダー(火蜥蜴)と称されてきたのは本種である。
Salamandra はギリシャ語の「火のトカゲ」または毒を発射するという意味の(ファイアー)が語源。
コブラはキングコブラ(Ophiophagus hannah)は、爬虫綱有鱗目コブラ科に分類されるヘビ。
本種のみでキングコブラ属を形成する。特定動物。
「勉強になったかしら?」
トカゲの方は突然変異とのことで体がやたらでかいのだけれど…。
私は爬虫類が好きなのだ。
写真を見てるだけなのは飽きてしまった。
お金もなぜか家に腐るほどあったので大枚はたいて無理やり手に入れた。
でもたまにもぞもぞと餌を食べるために起き出すくらいでほとんど私に構ってくれない。
「一応友達という役割を与えてやってるのだからたまには私に構いなさいよ。」
ほとんど独り言だが、私が住む家は音という音がなさ過ぎる。
たまに吹く山からの風のほかには何も聞こえない。
小さい家とはいえこんな麗しい幼女が一人住むのには広すぎよ。
「別にさみしくなんかないけどね。」
誰に言うまでもなく…言い聞かせる。
一度に色々なことを考えながら台所に行く。
朝の日課である食料の確認。この地方では何日も吹雪が止まないことがある。そんなときに食料や火種やまきが尽きたら終わりだ。
「もう小麦がないな、また買いに行かないと。」
どうせ家にいても読書をして時間を使うことくらいしかすることがない。
簡単な食事をすませてから今日はすぐに行動に移すことにした。
服を幾重にも着こんで玄関の扉を開ける。
―――――――――――――
私の名前はエヴォル・エキル。エイヴィーと呼んでくれてもいい。
年はわからない。外見から見て10歳くらいだと思う。
いつの頃からか。町から少し離れたところにある雪山のふもとの小さな家に住んでいる。
雪崩が頻繁に起きるこの地域で雪山のふもとに住み続けているのは自殺行為であろう。
しかし危険を避けるために移住するということは選択肢にはない。
他に行く当てがないというのも理由のひとつではあるが、最近はいつ死んでもよいと考えることが大きくなったからだ。
雪崩によって雪に埋もれてこの大地の一部になるのも悪くないのではないか、と。
いつの頃からか、と言ったが細かい記憶はない。物心がついたときにはその小さな家に一人で暮らしていた。親は誰だとか育ててもらったのは誰だとか、全くわからない。
俗に言う記憶喪失というやつだろうか?
最初から頭の中にあった知識については説明できない。
「まぁ、そんなことは気にはならないわ。天才は理屈じゃないのよ。」
私にとっては毎日を生き抜くことのほうが大事だもの。
家にはなぜか大量にお金もあったし、生活に必要な道具もあった。更にはいつ身についたのかわからない生き抜くための知恵もあった。
「まぁ、私は天才で、この雪国で暮らしていて、これからもずっとそれは変わらない、ただし死なない限りの条件付きでみたいなっ、って所ね。」
大事なのは過程ではなく結果だ。親が誰なのかがわかっても何も変わりはしない。事実は『今はいない』ということだけ。
現実が全てだ。
そんなことを小1時間程考えながら歩き続けるといつの間にか町の入り口についていた。
――――――――――――――――――
-小さな町~スイミヤ~-
町の目当てのお店を見つけるのにはそう時間がかからない。
町自体が小さいし、小麦がそのまま売っているパン屋は一軒だけだからだ。
足取りが重い、毎度のこと町に来るのは気が進まない。
パン屋のドアを開けて入ろうとした瞬間、
バンッ!
「うっ!いつつつ…」
店の主人らしき人物がドアを勢いよく閉め、突き飛ばされた。
地面にしりもちをつき派手に雪のマットに跡が付いた。
冷たい。
「勝手に店に入るんじゃないよ!雪女の子どもが!店が呪われちまう!」
そして突然の怒号。それに物怖じすることなく言葉を返す。
「すいません、小麦を分けてください。お金ならありますから。」
「へぇ、妖怪が人間様の食べ物を食べるのかい。」
「次の吹雪が来たら耐えられません、どうかお願いします。」
ペコリと頭を下げる。こんな人間に頭を下げるのは癪だが、仕方がない。
「1キロ150ルーブだよ。さっさともって帰りな!」
相場の何倍もの値だ。でもそのことには気付いてないように振舞わなくてはならない。
下手に出なくてはならない。
売ってもらえないなんてことになったら私の物語はそこでおしまいだから。
「あ、ありがとうございます。5キロお願いします。」
100ルーブ札を8枚、渡す。
ドサッと投げ捨てるようにして小麦の入った袋が出てきた。
当然のようにお釣りはもらえなかった。
背を向けると、いつもいつも馬鹿なやつだ、といった話し声と笑い声。
やつらが私のお金目当てにいつも小麦を用意しているのは知っている。
私を見て嫌そうな顔をしているが、巻き上げるお金のことを考えて内心はほくそえんでいるのだ。
でも私は馬鹿の振りをし続けなければいけない。
このときほど惨めな気持ちになるときはない。
「フン、いちいち下等な人間の言うことを気にしていたらキリがないわ。」
5キロの小麦袋を担いで来た道を戻る。
負け惜しみもすぐに静かな町へ吸い込まれていく。
仄かに光る街灯がとても煩わしく感じられた。
帰り道にすれ違う人々も私を避けるように道を譲る。
そして背後から聞こえるヒソヒソ話。
(あぁ、また来てるぜあの雪女…最近よく起こる雪崩もあいつが起こしてるらしいぜ…。)
(なんであんなにお金持ってるのよ、絶対に危ないお金だわ…。)
(関わるな、関わると呪われるぞ…。)
帰り道、担いだ袋は重たかった。
―――――――――――――――――――――
雪山のふもとに建つ今どき珍しいレンガ造りの古く小さな家。
近くに家は立っておらず、町までは少し距離があり、交流の機会というものはない。
それはエヴォルの家のすぐ近くにそびえる雪山がこの国~ホワイトランド~では霊山とされておりこの近辺に家を建てるのは畏れ多いことなのであるというのも理由のひとつではあるのだが。
もちろん他の人たちと交流を絶っている当の本人には知る由もないわけで。
学校にも行っていない。学校に通って小学校の勉強をして何になるのか。
家族もいない。友達はヘビとトカゲだけ。
いつからあるのかわからない家にいつからか住み着いた女の子。
一人で雪山に暮らす少女を街の人たちは不思議に思い、いつしかその気持ちは畏怖の念に変わる。
気付いた頃には自然と敬遠されるようになっていた。
知識はあっても彼女は大人ではない。
少女は強がる、強がるが…。
(人は何かこの世で役割を果たすために生まれてくる、というけれど、この世に私が生まれた理由は何?人とろくな会話をしたこともなく差別され区別され侮蔑され侮辱され奇異の目を向けられ馬鹿の振りをし続けてこのまま一人で死んでいく私に役割なんてあるわけ?いっそ死んだ方が孤独から開放されるかもしれない。別に一人だからってさみしくなんかないけどね…。)
さみしさは次第に心を埋めていった。
…この国に降り積もる雪のように。
――――――――――――――――――――――
町の目当てのお店を見つけるのにはそう時間がかからない。
町自体が小さいし、小麦がそのまま売っているパン屋は一軒だけだからだ。
足取りが重い、毎度のこと町に来るのは気が進まない。
パン屋のドアを開けて入ろうとした瞬間、
バンッ!
「うっ!いつつつ…」
店の主人らしき人物がドアを勢いよく閉め、突き飛ばされた。
地面にしりもちをつき派手に雪のマットに跡が付いた。
冷たい。
「勝手に店に入るんじゃないよ!雪女の子どもが!店が呪われちまう!」
そして突然の怒号。それに物怖じすることなく言葉を返す。
「すいません、小麦を分けてください。お金ならありますから。」
「へぇ、妖怪が人間様の食べ物を食べるのかい。」
「次の吹雪が来たら耐えられません、どうかお願いします。」
ペコリと頭を下げる。こんな人間に頭を下げるのは癪だが、仕方がない。
「1キロ150ルーブだよ。さっさともって帰りな!」
相場の何倍もの値だ。でもそのことには気付いてないように振舞わなくてはならない。
下手に出なくてはならない。
売ってもらえないなんてことになったら私の物語はそこでおしまいだから。
「あ、ありがとうございます。5キロお願いします。」
100ルーブ札を8枚、渡す。
ドサッと投げ捨てるようにして小麦の入った袋が出てきた。
当然のようにお釣りはもらえなかった。
背を向けると、いつもいつも馬鹿なやつだ、といった話し声と笑い声。
やつらが私のお金目当てにいつも小麦を用意しているのは知っている。
私を見て嫌そうな顔をしているが、巻き上げるお金のことを考えて内心はほくそえんでいるのだ。
でも私は馬鹿の振りをし続けなければいけない。
このときほど惨めな気持ちになるときはない。
「フン、いちいち下等な人間の言うことを気にしていたらキリがないわ。」
5キロの小麦袋を担いで来た道を戻る。
負け惜しみもすぐに静かな町へ吸い込まれていく。
仄かに光る街灯がとても煩わしく感じられた。
帰り道にすれ違う人々も私を避けるように道を譲る。
そして背後から聞こえるヒソヒソ話。
(あぁ、また来てるぜあの雪女…最近よく起こる雪崩もあいつが起こしてるらしいぜ…。)
(なんであんなにお金持ってるのよ、絶対に危ないお金だわ…。)
(関わるな、関わると呪われるぞ…。)
帰り道、担いだ袋は重たかった。
―――――――――――――――――――――
雪山のふもとに建つ今どき珍しいレンガ造りの古く小さな家。
近くに家は立っておらず、町までは少し距離があり、交流の機会というものはない。
それはエヴォルの家のすぐ近くにそびえる雪山がこの国~ホワイトランド~では霊山とされておりこの近辺に家を建てるのは畏れ多いことなのであるというのも理由のひとつではあるのだが。
もちろん他の人たちと交流を絶っている当の本人には知る由もないわけで。
学校にも行っていない。学校に通って小学校の勉強をして何になるのか。
家族もいない。友達はヘビとトカゲだけ。
いつからあるのかわからない家にいつからか住み着いた女の子。
一人で雪山に暮らす少女を街の人たちは不思議に思い、いつしかその気持ちは畏怖の念に変わる。
気付いた頃には自然と敬遠されるようになっていた。
知識はあっても彼女は大人ではない。
少女は強がる、強がるが…。
(人は何かこの世で役割を果たすために生まれてくる、というけれど、この世に私が生まれた理由は何?人とろくな会話をしたこともなく差別され区別され侮蔑され侮辱され奇異の目を向けられ馬鹿の振りをし続けてこのまま一人で死んでいく私に役割なんてあるわけ?いっそ死んだ方が孤独から開放されるかもしれない。別に一人だからってさみしくなんかないけどね…。)
さみしさは次第に心を埋めていった。
…この国に降り積もる雪のように。
――――――――――――――――――――――
次の日
ドドドドドドドドドドドドドドド
「ひぇっ、な、何!?」
昨日とは違ってものすごい音と振動で目が覚めた。
最近は小規模な雪崩が本当に頻繁に起こるので、あまり気にはしていなかったのだが今回は違った。
外に出てみると丁度私の家を避けるようにして雪崩が起きた跡が残っていた。
「アハハ…。マンガみたいな光景ね…。…ん?」
不思議なものが目に留まった。
変な袋が雪の中に埋もれている。
「何かな、コレ? ん~、よいしょっ、と!」
掘り出して袋のひもを解く。中を見てみると不思議な模様が着いたカバーの、辞書のような厚みを持った本が入っていた。
「なんでこんなものが雪山からなだれ込んでくるのよ…。」
何かに文句を言いながらも少し嬉しい。
本を読むのは好きだし、家にあるものは全て読み尽しているし、町に買いに行くのも気が進まない。
一度好きなシリーズを買い占めたときから本屋の店主にはひどく煙たがられている。
店に入ることさえ禁じられた。以来、新しい本を読んでいない。
家にある本は何度も何度も読み返した。
他に読むものがなかったから。
新しい本を手に入れたという嬉しさが不思議な本を怪しく思うことを忘れさせ、家でゆっくり読んでみようと思いすぐに持ち帰った。
その本を読み終わるのには半日ほどかかった。
「何よコレ、笑っちゃうわ。」
その本には、
キマイラの作り方が図入りで生物学的観点から細かく説明されてるページ、
鉄から金を作るやさしい錬金術ただし鉄1tにつき金1gみたいなっ、
君だけのスタンド~幽波紋入門~、
コーク味の薬草エリクシルの精製法etc.…
そして最後のページにこう書かれてあった。
『コノ本ニ書カレタコトヲヤッテミタラモウ同ジ世界ニハイラレマセン。』
「こんな低レベルな本に夢中になるなんて、私もかわいいとこあるじゃない。」
子供向けのその手の本だがなかなかこった内容になっていておもしろかった。
でももう読むことはないだろう。一度読んだ内容はほとんど忘れないし。
だから、本を本棚の一番奥に閉まった。
―――――――――――――――――――
さて不思議な本を拾ってから1ヶ月ほどたったある日。
その日まで、私はその本の存在をすっかり忘れていた。
どこに閉まったのかや、内容も覚えてはいるのだろうけど気にならないから思いだすこともなく、私は何も変わらない日々を過ごしていた。
町に何かを買い求めに行けば人々はやはり私を忌み嫌い、家に帰っても、ヘビとトカゲを眺めては何も音のしない家の中で気が狂いそうになったり、そんな毎日。
これからも続くであろう永遠に退屈で閉鎖された真っ白な世界。
そして、
世界は白でこの世を埋め尽くさんとする―――
―――吹雪が来た。
「吹雪か。このまま世界が雪で埋もれちゃえばいいのに。」
思ったことをすぐに口に出すようになってしまったのは行き場のない気持ちを少しでも体外へ排出する保身のための行為だろうか。
吹雪はこの地域では珍しいことではない。今までにも何度かあったし、それを越えて生きてきた。
食料もあるし薪(まき)もある。
私は炎を絶やさないように暖炉を見守り、ときおりそっと炎に餌を与えれば良いだけだ。
「そう考えると炎もなかなかかわいいじゃない。」
暖炉の近くにイスを移動させ座る。
ここでぼーっと瞑想をしながら過ごすのが私なりの吹雪の越え方。吹雪は何もしないことに理由を与えてくれるからいい。
ぼんやりと目線を泳がせる。
窓から外を眺める。
ものすごい雪と風、白、白、白、そして赤い点…
…え?
雪原に赤い点?赤い点って何?ついに私も気が狂ったのか?
窓の外、赤い点である。
木の軋む音と共に凍りついたドアをどうにか開けるとものすごい風と雪を叩きつけられた。
家伝いに赤い点が見えたところに行く。
そこには小さな小さな血だまりがあった。
そして雪の上にいたら何も見えなくなるような、雪のように真っ白な兎が一匹。
このときは考えるより先に体が動いた。
すぐに、
私はソレを抱えて家に戻った。
その白兎は、
近くの山の雪崩に遭ったのか片耳は千切れ、片目と喉には長い枝が刺さっていた。手足もボロボロで、兎はすでに虫の息だった。
私の頭の中にある何千何億の知識が言っている。
(助からない。気管支からろくに呼吸もできてない。血も足りない。ここまで傷を負っているとまだ息があるだけで奇跡だ。)
その思考とともに体中の毛穴が開いていき体温が冷めていった。
背筋になにかヌラリとした冷たい物が這ったような感覚を覚え、ゾッとした。
一度目を閉じる。
まぶたに焼きついた死に掛けの兎。
真っ白な世界で独り真っ赤な液体を噴出させてなお生き永らている。
生きている意味も分からずに虫の息。
「コレは私だ…。」
助けたい。
兎も私も。
「いいえ、私を助けたいのね。」
このただ白いだけの世界から抜け出したい。
生 き た い。 活 き た い。
ズキンズキン!
胸が痛い。心臓をつかまれたような痛みが胸を締め付ける。
そしてそのまま引っ張られるように私は本棚の一番奥に閉まった『不思議な本』を引っ張り出していた。
開いたのは『キマイラの作り方が図入りで生物学的観点から細かく説明されてるページ』
生物のパーツをつなぎ合わせ、それぞれを機能させ、一体の生物として扱う方法。
体が勝手に動くということは私がそうしたいから動くのだ。
そう思わないとおかしいほど体が勝手に動いた。
現実に合成獣(キメラ)なんてできるはずがない、とは微塵も考えず行動に移す。
ここは仮想世界(ファンタジー)ではなく現実世界(リアル)だ。思考は冷静であろうとしたが動悸は激しく波打っていた。
本に目を向ける。
『合成にはまず最低でも2体の生物を用意すること。』
兎には傷が多かったので友達のヘビとトカゲと、そして部屋のお守りとして飾っておいた本物の熊の手を使うことにした。
この兎を救うのなら他に選択肢もない。
そして友達もこのまま冬眠し続けて人生のほとんどを眠って過ごすよりも新しい命となって雪原を走り回れる方が幸せだろう。
命を助けるためなら犠牲が出ても仕方ない、という考えを持っていたわけではなかった。
だがこの時ばかりはそうも言っていられなかった。ひとつの命のために複数の犠牲が出る。
しかし、犠牲となった者もその命の一部となって生きてゆく。
そうしたらまた友達になってもらおう。今度は一緒に遊ぼう。
「もし失敗したら私も死ぬことにするわ。約束よ。だからごめんね。」
生物を殺してつなげるなど、命をもて遊ぶ最低な行為だ。友達を殺すなんて、最悪な行為だ。この世の禁忌だ。
そして、この兎は私なのだから、兎が助からなければ私も助からない。真っ白な世界に埋もれて死のう。
でも、
「でも、全く失敗する気がしないの。」
約束というのは私が死ぬという約束ではない、必ず友達を救うという約束だ。死はそれに対する決意。
そういって私は、
眠っている『友達』にメスを入れ、
殺した。
思えば、このとき私は、狂っていたのかもしれない。
『キマイラの血液が足らない場合、主人となる者の血を雪に染みこませ切断部に当てる。』
私は雪を袋に詰めてきて左腕にメスで軽く皮膚を裂き、雪に染みこませた。痛みはない。
すぐに兎にコブラやトカゲを繋ぎ合わせていった。
「左右前後脚部切断、接合。腹部、陰部接合。右耳切断、コブラ接合。」
千切れた耳にコブラを、傷ついた足にトカゲを。血だらけの手には熊の手を。破壊された喉にはオオトカゲのものを代用し、腹部に同じくトカゲの口を埋め込んだ。
メスを置く。
「ふぅ…。」
頭がクラクラする。兎に傷が多かったため雪に染みこませるための血を流しすぎた。
だが体の合成はこれでいいはずだ。
『最後にあなたの僕となるキマイラに名前を付けること。』
ほっとした。狂気の時間がこれで終わる。。
「んと…。雪と私の血から造ったキメラ、雪のキメラ、ユキ、キメラ、ユキメラ…うん、ユキメラ、白兎のユキメラ、あなたの名前は、兎型愛玩系護衛奴隷ユキメラ!」
…
「私の名前はエヴォル・エキル。そうね、特別にあなたにはエイヴィーって呼ぶことを許してあげるわ!」
だが私の造った珍妙な生き物はピクリともしなかった。
「起きなさいよ!なんで起きないの!?私は書いてあるとおりにしたわよ!!」
…。
沈黙が私の姿をより滑稽にする。
駄目だった。
私はもう限界だった。
机の上のものに当り散らす。
わめきちらしてイスを蹴飛ばす。
「ぐっ」
悔しくて情けなくてわけがわからなくなったが、暴れまわった私の腕に突然ズキズキと鈍い痛みが走る。
そのことがなんとか私の脳に冷静さを取り戻させた。
「はぁはぁ、何が間違っていたのだろう?」
一度読んだ内容を思い出す。
そして素早く『本』の字の羅列に目を這わす。
!
急ぐあまり私はページをめくらなかった。
確か次のページには…
バッと本をめくるとそこには文字がただ1行、
『キマイラが目覚める時間にはムラがあります。2時間たっても起きない場合は体が腐り始めるので消毒用のお酒に漬けておくこと。』
私の家に酒なんかあるはずがない。
ここから町まで往復2時間ほど。
外は猛吹雪。
神様は残酷だ!神様なんて信じない!
どうやら神は禁忌に触れようとする人間を許そうとしないらしい。
「行くわよ!行けばいいんでしょ!」
お金を多めに握り締め、使い古したコートを羽織り、防寒具一式を身につけ、
再び凍り張り付いてしまった重い扉を無理やりこじ開けて、
町の方向に目星を付け、私は視界の悪い吹雪の中へと重い一歩を踏み出した。
――――――――――――――――
上から下から左右から無茶苦茶に吹き付ける雪は私をとにかく疲れさせた。
すでに1時間半が経過していた。
町へは比較的早く着いたのだが酒をもらうのに時間が掛かった。
どうやって酒を手に入れたのかは思い出したくない。
町の人達にはどうやっても相手にしてもらえなかったから無理やり知らない家に入ってわめきちらしてかっぱらってきた。
途方もなく疲れた。
今はこれから家に帰るところである。
あと30分で町から家までを歩くのは絶望的ともいえる時間であった。
視界は最悪。馬鹿げたように雪が積もっているから深みにはまったらそこで終わり、氷付けの少女が出来上がり。
しかし急がなければならない。
「なんで私…こんなにがんばってるのかしら…。」
貧血気味の疲弊しきった身体はまっすぐに足跡を刻む事さえも難しくさせた。
しかし足を動かすことだけはやめようとしない。
私の体が私のものではないかのように一歩、また一歩…歩くたびに体が重くなる。
一緒にどす黒い気持ちも大きくなる。
「人は何かこの世で役割を果たすために生まれてくるというけれどこの世に私が生まれた理由は何!?人とろくな会話をしたこともなく!差別され区別され侮蔑され侮辱され!奇異の目を向けられ!馬鹿の振りをし続けてこのまま一人で死んでいく私に役割なんてあるわけ!?」
目がかすんできた。朦朧としながらも前へと進む。
「いっそのこと…ここで雪に埋もれて死んだ方がどんなに楽か…」。
そのまま誰にも見つけられず白い世界の一部となる。
どうせもともと私の世界には何もなかったのだし。
でも足を動かすことだけはやめない。前へ…前へ…。
また一歩を踏み出そうと前を向く、目はぼやけているが私の家があるであろう方向を見る。
と、
突然目の前に広がる白い世界の一部が人型にグニャリと曲がったような気がした。
「グォォォオオオオオオオオオオ!」
少し遅れて鼓膜が破れるほどの轟音がやってきた。
吹雪の風の音を掻き消して近くで聞くもの全てを絶望させるほどの音。
降りしきる雪もその音の発信源を避けるように吹き飛ぶ。
「な、何なの!?」
全身に冷たい汗がじんわりとにじんだ。
ソレは距離にして私のたった5mほど前に突然現れた。
エヴォルの身長の3倍くらいの生物。
真っ白な、いや、真銀色といった色の毛皮を持った大熊であった。
あまりに真っ白だったのでこんなに近くに来るまで全く気付かなかったのだ。
「何で白熊がこの国にいるのよ…」
白熊とは一般にホッキョクグマのことであり、その名の通り北極に住む。こんなところにいるはずがないのだ。
だが目の前にいるのはまぎれもなく真銀の毛皮を持つホッキョクグマだった。白熊というよりは銀熊だ。
ソイツは体中の体毛を毛羽立たせ牙をむき、明らかな敵意を持ってこちらをにらんでいた。
熊に遭遇したときに絶対にやってはいけないこと。
1、死んだ振り
2、背を向けて逃げ出す
つまり熊から目を離す行為だ。
野生の熊も人間を恐れている。こちらから近寄らなければ向こうも危険を冒してまでこちらを攻撃してこない、というのが一般的な見方だ。
相手をにらんだまま後ろ向きにじりじりと距離を離そう。
少しでも隙を見せてはいけない。この距離だ、あの銀熊は一歩で間合いを詰め私を真っ二つにできるだろう。
私は冷静だった。嫌な汗はダラダラと止まらないが私の頭脳はこの状況において最適な行動を導き出した。
強い意志を持ち銀熊をにらみつけ後ろへと一歩を踏み出したその刹那、
「グウウウルアァアアアワアア!!」
熊がまるで「逃げるんじゃない!!」とでも叫んだかのようにその巨躯を駆って私の目の前へ。
そして同時に腕を振り下ろす。
「ひっ。」
巨大な熊が一瞬にして目の前にきたことにより私の身体は恐怖で動かなくなって、どしんとしりもちを着いた。
その行動が熊の振るった一撃をもろにくらわずにすんだのだが、
ジャッという鈍い音がしたかと思うと、両足から真っ赤な液体が噴出して近くの雪を赤く染めていた。
しりもちをつかなかったら私の胴はくしゃくしゃになっていただろう。
「に、逃げ…ぐっ。」
足を動かそうとしたが激痛が走る。ブルブルブルブルとひざが笑っていた。
もう身体は言うことを聞いてくれなかった。
あぁ、ここで私は死ぬんだ…
どうせいつかは死ぬんだと思っていたし…
それがちょっと早まっただけ。
どうせいつ死んでも同じ。
生きていても何もない白い世界が延々と続くだけ。
死のう…ここで潔く私は死ぬのだ…。
私の世界には何もない…
あれ
―――――――何もなかったっけ?
いいえ、エイヴィー、あなたは大事なものを残しているわ。
それは約束。
兎を救うのでしょう?
そして一人目の友達になってもらうのでしょう?
この真っ白な世界から抜け出したいのでしょう?――――――――
そうだ…
何も無くなんかない
兎を助けると決めたときから真っ白な世界にポツンとひとつ、初めて私が生まれ落ちたんだ
いやだ
このまま死にたくない
兎が、独りの兎が私を待っているのに
死 に た く な い
しかし眼前に迫る圧倒的な殺意
死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
嫌ダイヤだ嫌だイやダイヤダイヤだ嫌だいやだいやだいやだ嫌だ
イヤダイヤだ委やダイヤだ委やダイヤダ嫌ダイヤだ委やダイヤだ委やダイヤだ
「グォオオオオヲヲ!!」
目の前の獣が腕を振り上げる。
そのとき私は初めて泣いていた。
今までどんなにつらくてもひもじくても町の人に馬鹿にされて悔しくても泣くことはなかったのに。
ボロボロボロボロと涙がこぼれ落ちる。
「ひぐっ、いやだ!死にたくない!こんなところで独りで死にたくない!うっ、もう独りは嫌だ!嫌なの!助けなさい!助けて!誰か、私を、助けて!!あぁああああああ!!」
それは自分の本当の声、初めて出した心からの叫び、初めて出した自分の弱さ。
悲痛の叫びは獣には届かない。変わらず熊は大きく上げた銀色の腕を振り下ろそうとする。
私の物語はここでおしまいなんだ…。
私は覚悟を決めて目を閉じた。
…ヒュ
突然小さな風切り音が耳元で聞こえたと思ったら遅れて届く重厚な金属の音と衝撃が私の肌にぴぃっと鳥肌を走らせた。
これは私の頭蓋骨が砕けた音…
…。
…ではなかった。
振り下ろされた銀熊の腕は私の頭の上で止められていた。
まぶたを開くとそこにはー
――――――――――奇妙な後姿。
長い耳とコブラ、左腕には熊のかぎ爪、トカゲの脚、
ムクムクした真っ白な毛皮、
そしてその生物の声は、腹部から聞こえた。
「エヴォル・エキル、いやエイヴィーといったか…。それが貴様の望みか!?」
まるで地底のマグマがふつふつと煮えたぎるような汚い声。
聞くもの全てを地獄へおとさんとするかのような声だった。
すでに1時間半が経過していた。
町へは比較的早く着いたのだが酒をもらうのに時間が掛かった。
どうやって酒を手に入れたのかは思い出したくない。
町の人達にはどうやっても相手にしてもらえなかったから無理やり知らない家に入ってわめきちらしてかっぱらってきた。
途方もなく疲れた。
今はこれから家に帰るところである。
あと30分で町から家までを歩くのは絶望的ともいえる時間であった。
視界は最悪。馬鹿げたように雪が積もっているから深みにはまったらそこで終わり、氷付けの少女が出来上がり。
しかし急がなければならない。
「なんで私…こんなにがんばってるのかしら…。」
貧血気味の疲弊しきった身体はまっすぐに足跡を刻む事さえも難しくさせた。
しかし足を動かすことだけはやめようとしない。
私の体が私のものではないかのように一歩、また一歩…歩くたびに体が重くなる。
一緒にどす黒い気持ちも大きくなる。
「人は何かこの世で役割を果たすために生まれてくるというけれどこの世に私が生まれた理由は何!?人とろくな会話をしたこともなく!差別され区別され侮蔑され侮辱され!奇異の目を向けられ!馬鹿の振りをし続けてこのまま一人で死んでいく私に役割なんてあるわけ!?」
目がかすんできた。朦朧としながらも前へと進む。
「いっそのこと…ここで雪に埋もれて死んだ方がどんなに楽か…」。
そのまま誰にも見つけられず白い世界の一部となる。
どうせもともと私の世界には何もなかったのだし。
でも足を動かすことだけはやめない。前へ…前へ…。
また一歩を踏み出そうと前を向く、目はぼやけているが私の家があるであろう方向を見る。
と、
突然目の前に広がる白い世界の一部が人型にグニャリと曲がったような気がした。
「グォォォオオオオオオオオオオ!」
少し遅れて鼓膜が破れるほどの轟音がやってきた。
吹雪の風の音を掻き消して近くで聞くもの全てを絶望させるほどの音。
降りしきる雪もその音の発信源を避けるように吹き飛ぶ。
「な、何なの!?」
全身に冷たい汗がじんわりとにじんだ。
ソレは距離にして私のたった5mほど前に突然現れた。
エヴォルの身長の3倍くらいの生物。
真っ白な、いや、真銀色といった色の毛皮を持った大熊であった。
あまりに真っ白だったのでこんなに近くに来るまで全く気付かなかったのだ。
「何で白熊がこの国にいるのよ…」
白熊とは一般にホッキョクグマのことであり、その名の通り北極に住む。こんなところにいるはずがないのだ。
だが目の前にいるのはまぎれもなく真銀の毛皮を持つホッキョクグマだった。白熊というよりは銀熊だ。
ソイツは体中の体毛を毛羽立たせ牙をむき、明らかな敵意を持ってこちらをにらんでいた。
熊に遭遇したときに絶対にやってはいけないこと。
1、死んだ振り
2、背を向けて逃げ出す
つまり熊から目を離す行為だ。
野生の熊も人間を恐れている。こちらから近寄らなければ向こうも危険を冒してまでこちらを攻撃してこない、というのが一般的な見方だ。
相手をにらんだまま後ろ向きにじりじりと距離を離そう。
少しでも隙を見せてはいけない。この距離だ、あの銀熊は一歩で間合いを詰め私を真っ二つにできるだろう。
私は冷静だった。嫌な汗はダラダラと止まらないが私の頭脳はこの状況において最適な行動を導き出した。
強い意志を持ち銀熊をにらみつけ後ろへと一歩を踏み出したその刹那、
「グウウウルアァアアアワアア!!」
熊がまるで「逃げるんじゃない!!」とでも叫んだかのようにその巨躯を駆って私の目の前へ。
そして同時に腕を振り下ろす。
「ひっ。」
巨大な熊が一瞬にして目の前にきたことにより私の身体は恐怖で動かなくなって、どしんとしりもちを着いた。
その行動が熊の振るった一撃をもろにくらわずにすんだのだが、
ジャッという鈍い音がしたかと思うと、両足から真っ赤な液体が噴出して近くの雪を赤く染めていた。
しりもちをつかなかったら私の胴はくしゃくしゃになっていただろう。
「に、逃げ…ぐっ。」
足を動かそうとしたが激痛が走る。ブルブルブルブルとひざが笑っていた。
もう身体は言うことを聞いてくれなかった。
あぁ、ここで私は死ぬんだ…
どうせいつかは死ぬんだと思っていたし…
それがちょっと早まっただけ。
どうせいつ死んでも同じ。
生きていても何もない白い世界が延々と続くだけ。
死のう…ここで潔く私は死ぬのだ…。
私の世界には何もない…
あれ
―――――――何もなかったっけ?
いいえ、エイヴィー、あなたは大事なものを残しているわ。
それは約束。
兎を救うのでしょう?
そして一人目の友達になってもらうのでしょう?
この真っ白な世界から抜け出したいのでしょう?――――――――
そうだ…
何も無くなんかない
兎を助けると決めたときから真っ白な世界にポツンとひとつ、初めて私が生まれ落ちたんだ
いやだ
このまま死にたくない
兎が、独りの兎が私を待っているのに
死 に た く な い
しかし眼前に迫る圧倒的な殺意
死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死
嫌ダイヤだ嫌だイやダイヤダイヤだ嫌だいやだいやだいやだ嫌だ
イヤダイヤだ委やダイヤだ委やダイヤダ嫌ダイヤだ委やダイヤだ委やダイヤだ
「グォオオオオヲヲ!!」
目の前の獣が腕を振り上げる。
そのとき私は初めて泣いていた。
今までどんなにつらくてもひもじくても町の人に馬鹿にされて悔しくても泣くことはなかったのに。
ボロボロボロボロと涙がこぼれ落ちる。
「ひぐっ、いやだ!死にたくない!こんなところで独りで死にたくない!うっ、もう独りは嫌だ!嫌なの!助けなさい!助けて!誰か、私を、助けて!!あぁああああああ!!」
それは自分の本当の声、初めて出した心からの叫び、初めて出した自分の弱さ。
悲痛の叫びは獣には届かない。変わらず熊は大きく上げた銀色の腕を振り下ろそうとする。
私の物語はここでおしまいなんだ…。
私は覚悟を決めて目を閉じた。
…ヒュ
突然小さな風切り音が耳元で聞こえたと思ったら遅れて届く重厚な金属の音と衝撃が私の肌にぴぃっと鳥肌を走らせた。
これは私の頭蓋骨が砕けた音…
…。
…ではなかった。
振り下ろされた銀熊の腕は私の頭の上で止められていた。
まぶたを開くとそこにはー
――――――――――奇妙な後姿。
長い耳とコブラ、左腕には熊のかぎ爪、トカゲの脚、
ムクムクした真っ白な毛皮、
そしてその生物の声は、腹部から聞こえた。
「エヴォル・エキル、いやエイヴィーといったか…。それが貴様の望みか!?」
まるで地底のマグマがふつふつと煮えたぎるような汚い声。
聞くもの全てを地獄へおとさんとするかのような声だった。
私は瞳から涙がとぎれることはなく、喉はカラカラで痛くてしょうがなかった。
だから…動かない体を無理やり震わせ、コクンと首をたてに振る。
「それならば吾輩はそれに答えよう。貴様は約束を守ってくれた。」
喉から音を振り絞るようにして出す、なんとか喉から出た言葉は、
「ぐす…あなた…ユ…?」
「ふむ、そうだな、我輩の名はユキメラ。貴様が付けた名だ。」
ユキメラは受け止めた銀熊の腕をブンとはねのけた。
「グルル…」
明らかに小さい生き物が思いっきり振り下ろした一撃を軽々と受け止めたことは、明らかに銀熊を動揺させていた。少し間をおいて警戒し身を震わせる熊を無視してユキメラは話を進める。
「貴様に言っておくことがある。」
そう言って私を抱え一瞬にしてそこから10mほどの距離を跳んだ。
「エヴォル・エキル、貴様は我輩のことを兎型愛玩系護衛奴隷といったな。愛玩されるつもりもないし、奴隷も気に食わないが…フン」
「貴様を守ってやる。」
私は雪の上にそっと降ろされた。
ユキメラのモコモコの毛皮は私の鼻をくすぐった。
まだすぐ近くに恐ろしい存在がいるというのに、私は安心を覚えた。
まぶたが重い…
「それが吾輩がする約束だ。」
コクン
そしてまたひとっとび、銀の熊と白い兎が対峙する。
熊は目の前の白兎がただの雪山の生き物ではないことを感じ取ったようだ。
すぐにでも飛びかかれる体勢である。
「銀色の戦士よ!あのような小娘を殺したら貴公の名に傷がつくだけだろう!!」
「ここからは我輩がお相手しよう!」
「グァアアア!」
私には突然の強敵の出現に熊が喚起の雄叫びをあげたように見えた。
そう、熊は「のぞむところだ」と返事したのだ。
そして最初の一撃に全体重をかけるために、熊の脚の筋が膨れ上がるのが遠くからでも分かった。
それに対してユキメラは自然体のまま動こうとしない。
熊が先に動く。
獣の後ろ足が地面を噛み、雪を大きく巻き上げて蹴りあがる。
低空でユキメラに向けて弾けるように飛ぶ。
鋭い爪を持つ左腕を下から振り上げる。同時に甲高い音が届いた。
あまりに早くてその私には熊の一撃がほとんど見えなかったが、熊の腕が振り上がりきったのを視認したとき、ユキメラの身体は空中へ浮き上がっていた。
どうやらその一撃を避けずに受けたようだった。
しかし、金属音が聞こえたということは硬い爪で受けきったということなのだろう。
熊が吹っ飛ばした兎が落ちてきた瞬間にとどめの一撃を入れようと再度腕を振り上げる。
そして空から落ちてくる兎、
「ふむ、やはり質量の差か…。しかし貴公の全力の攻撃を避けるのは失礼であるよな。」
熊の腕の間合いに落ちてきた兎が入るとすかさず来る2撃目の振り下ろし。
その無骨ながら脅威をまとう重い攻撃はまたもやガキンと同じ音を響かせた。しかし先ほどと違うのは続いて聞こえた鈍い音。
それは兎が地面に叩きつけられた音であるらしかった。やはり彼は熊の攻撃を避けようとしていない。
だが立ち上がるユキメラに大きなダメージは残っていないようだ。
「フン!」
「お姫様が待っているのでな、ここからは手段を選ばずに行くぞ!」
そして今度は兎から熊へ向かっていく。それを待つほどに熊に余裕はなくもちろんお互いに距離を詰めあう形となった。
その後姿はとても力強かった。
だけど、フッと、突然視界が幕を引くように真っ暗になった。
ここが私の限界であるらしい。ユキメラの体液のために使った血。吹雪の中を歩き続けるために使った体力。
冷え切った体。そして今だ脚からドクドクと流れ続ける血。
ユキメラの言葉が嬉しくて安心してしまったからか、緊張の糸がきれてしまったのか、だんだんと意識が暗く沈んでいく。
でも、不安な気持ちはみじんもなかった。
「私の僕が…ただの熊なんかに…負けるもんですか…。」
ばた…。
私が覚えているのはここまで。
だから…動かない体を無理やり震わせ、コクンと首をたてに振る。
「それならば吾輩はそれに答えよう。貴様は約束を守ってくれた。」
喉から音を振り絞るようにして出す、なんとか喉から出た言葉は、
「ぐす…あなた…ユ…?」
「ふむ、そうだな、我輩の名はユキメラ。貴様が付けた名だ。」
ユキメラは受け止めた銀熊の腕をブンとはねのけた。
「グルル…」
明らかに小さい生き物が思いっきり振り下ろした一撃を軽々と受け止めたことは、明らかに銀熊を動揺させていた。少し間をおいて警戒し身を震わせる熊を無視してユキメラは話を進める。
「貴様に言っておくことがある。」
そう言って私を抱え一瞬にしてそこから10mほどの距離を跳んだ。
「エヴォル・エキル、貴様は我輩のことを兎型愛玩系護衛奴隷といったな。愛玩されるつもりもないし、奴隷も気に食わないが…フン」
「貴様を守ってやる。」
私は雪の上にそっと降ろされた。
ユキメラのモコモコの毛皮は私の鼻をくすぐった。
まだすぐ近くに恐ろしい存在がいるというのに、私は安心を覚えた。
まぶたが重い…
「それが吾輩がする約束だ。」
コクン
そしてまたひとっとび、銀の熊と白い兎が対峙する。
熊は目の前の白兎がただの雪山の生き物ではないことを感じ取ったようだ。
すぐにでも飛びかかれる体勢である。
「銀色の戦士よ!あのような小娘を殺したら貴公の名に傷がつくだけだろう!!」
「ここからは我輩がお相手しよう!」
「グァアアア!」
私には突然の強敵の出現に熊が喚起の雄叫びをあげたように見えた。
そう、熊は「のぞむところだ」と返事したのだ。
そして最初の一撃に全体重をかけるために、熊の脚の筋が膨れ上がるのが遠くからでも分かった。
それに対してユキメラは自然体のまま動こうとしない。
熊が先に動く。
獣の後ろ足が地面を噛み、雪を大きく巻き上げて蹴りあがる。
低空でユキメラに向けて弾けるように飛ぶ。
鋭い爪を持つ左腕を下から振り上げる。同時に甲高い音が届いた。
あまりに早くてその私には熊の一撃がほとんど見えなかったが、熊の腕が振り上がりきったのを視認したとき、ユキメラの身体は空中へ浮き上がっていた。
どうやらその一撃を避けずに受けたようだった。
しかし、金属音が聞こえたということは硬い爪で受けきったということなのだろう。
熊が吹っ飛ばした兎が落ちてきた瞬間にとどめの一撃を入れようと再度腕を振り上げる。
そして空から落ちてくる兎、
「ふむ、やはり質量の差か…。しかし貴公の全力の攻撃を避けるのは失礼であるよな。」
熊の腕の間合いに落ちてきた兎が入るとすかさず来る2撃目の振り下ろし。
その無骨ながら脅威をまとう重い攻撃はまたもやガキンと同じ音を響かせた。しかし先ほどと違うのは続いて聞こえた鈍い音。
それは兎が地面に叩きつけられた音であるらしかった。やはり彼は熊の攻撃を避けようとしていない。
だが立ち上がるユキメラに大きなダメージは残っていないようだ。
「フン!」
「お姫様が待っているのでな、ここからは手段を選ばずに行くぞ!」
そして今度は兎から熊へ向かっていく。それを待つほどに熊に余裕はなくもちろんお互いに距離を詰めあう形となった。
その後姿はとても力強かった。
だけど、フッと、突然視界が幕を引くように真っ暗になった。
ここが私の限界であるらしい。ユキメラの体液のために使った血。吹雪の中を歩き続けるために使った体力。
冷え切った体。そして今だ脚からドクドクと流れ続ける血。
ユキメラの言葉が嬉しくて安心してしまったからか、緊張の糸がきれてしまったのか、だんだんと意識が暗く沈んでいく。
でも、不安な気持ちはみじんもなかった。
「私の僕が…ただの熊なんかに…負けるもんですか…。」
ばた…。
私が覚えているのはここまで。
――――――――――――
――――――――――――
「んん…。」
目を開くとそこは私の家の小さなベッドの上だった。
頭が重い。全身が痛む。どうにかして上半身だけを起こす。
「いつっ、、、」
体の末端から鈍い痛みを感じ、そちらを見ると両足には包帯が雑に巻かれていた。
その傷を見て昨晩のことを思い出そうとする。しかし覚えているのは熊vs兎(?)の奇妙な構図のみ。
すると、ドアが開いてぬぅっと化け物うさぎが姿を現した。
「ぬ、気が付いたか?」
「あ…。あなた、体は普通に動くの…?」
「ふむ…エヴォル・エキル。それは吾輩の台詞だ。貴様、相当出血していたようだぞ。」
そう言われると頭がくらくらとする。急に頭が重くなって私はまたすぐさま横になった。続けて化け物うさぎが口を開く。
「吾輩の方は至って健康だ。どうやら貴様の血がうまく馴染んだ様だな。ただ、昨夜の衝突で接合部に少々ガタがきているようだ。」
そういって熊の腕がつながった左腕をプラプラと揺らす化け物。あまり見ていて気持ちのいいものじゃないわね。
「そう思うのなら早く繋げてくれ。」
どうやら声に出ていたようだ。失敗。
「ところで…昨日はあれからどうなったの?あの熊は殺したの?」
「フム…。」
~~~~~~~
「ここからは手段を選ばずに行くぞ!」
そういうと同時に近くで小さく人が倒れ込む音が聞こえた。
勿論この場所には今現在吾輩、熊、そして小娘の三人しかいないわけで吾輩は貴様が倒れたことをいち早く格好良く察知した。
「む?エヴォル・エキル、大丈夫か!?」
「グルルルルルル」
唸る熊はさながら「私を無視して話を進めないで頂戴」と嫉妬するバンビーナのようであった。
「すまない、ここは引かせてもらおう、私は貴様と戦うことが目的ではないのでな。」
丁寧に断る紳士な吾輩。
「グォオオオオオ」
名残惜しそうに別れを惜しむ恐ろしい形相な熊。
「そう急くな、いつかまた貴公とは合間見えることがあるだろう。」
しかし、その熊はただでは返してくれそうになかったので仕方がなく吾輩は実力行使に出たのだ。
「ぬぉおお!エラサムゥウボンバイエェエエエエエエー!」
そう言って大きく息を吸いこんだ。腹の口は火蜥蜴(サラマンドラ)の口。この口は地獄の業火を呼び起こす。
ぽっかり開いた大口の端がニンマリとゆがんだ瞬間、口腔のおくから炎が溢れ出す。
大きさこそ中規模なものであったが意外と銀熊は驚きたじろいでいたな。
まぁとにかく目くらましになったのだ。その隙にすぐにそこから姿を消すと銀熊は完全に吾輩を見失ったようだった。
バッと貴様を抱えて雪原を駆け、家に飛び込んだ。
~~~~~~~~
「…。」
「感謝しろ。」
「…うん。」
技のネーミングについて突っ込むべきかどうか。
「…というわけだ。無理して戦う理由はない、吾輩の目的は違うところにあった。だから銀色の熊とはほとんど戦っていない。」
「あなたの目的って。」
「貴様の護衛だ。」
「と、当然よね!あなたは私の奴隷なんだから!」
あらためて言われると照れる。こいつはあっさりと私を守る守るいいやがりまして…恥ずかしいったらありゃしない。
「奴隷は気に食わん。」
急にむすっとした化け物はなんだかおかしかった。
外はいい天気のようだ。わたしが寝ている間に吹雪は去ったのか。
「それとエヴォル・エキル、正確には熊と邂逅したのは昨晩ではない。貴様、あれから丸2日ほど寝ていたぞ。」
「エヴォル・エキルはやめて頂戴。なんだか禍々しくて嫌いなの。エイヴィーと呼びなさい。あと外が見たいわ、カーテンを開けなさい。」
「それが兎にものを頼む態度か。」
「開けてくれるかしら?足が痛くて動けないの。」
「それで譲歩しよう。」
注意するのもうざったいのか兎はすぐに折れてぺたぺたとカーテンの方へ歩いていった。
ただ久しぶりの太陽の光を浴びようと思っただけだった。窓からは白いだけの見飽きた景色が見えるはず…。
勢いよくカーテンが開いた。長らく感じなかった太陽の光に慣れるために虹彩が動くのを感じる。
「何よ、コレ…?」
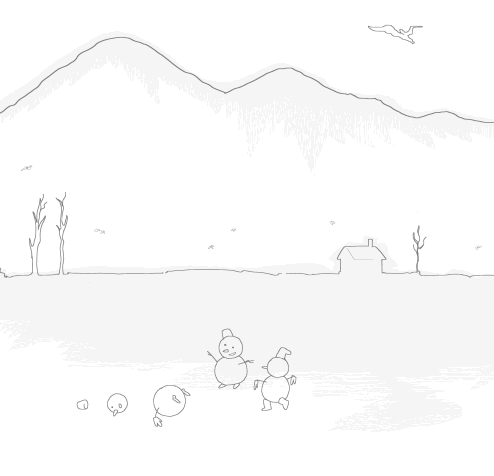
窓からまぶたに飛び込んできた景色は依然とはまったく違うものだった。
空にはスカイフィッシュが飛び、小さい妖精がじゃれあっていたり、雪だるまが列をなして行進していたり…。見慣れた景色はとんでもなくにぎやかになっていた。
「な、なにアレ!?なんで雪だるまが動いてるの!?あの小さな虫人間は何!?」
「雪妖精を見たことがないのか?」
冷静に返答する兎に少し苛立ちを覚える。
「ないわよ!!」
「では順番に質問に答えるとしよう、貴様が雪だるまと呼んだのはスノーマンという一族。虫人間と呼んだのは同じく雪妖精だ。付け加えると空を飛んでいる魚のようなものはアンノードという。」
「名前を聞いてるんじゃないわ!なんであんな生き物がこの世に…。」
しかしそれを言ってしまったらこの兎だってまったく非常識だ。
「雪原に住んでいるのに雪妖精を見たことがないはずがないだろう。」
「あんなもの普通の人間にはみえないわよ!」
「じゃあ貴様は普通ではないのか?」
「失礼ね!」
「雪山の動物達もみんな見えているぞ。人間だけが見えないのか?」
「そう、なのか…。」
兎は化け物とはいえもともと兎だったのだから雪山の動物には見えるというのは本当だろう。
じゃあなんで私は見えるようになったのだろう?
思考をめぐらすと急にまた足の傷が騒ぎ出した。
「いつっ。くぅ…。」
雑に巻かれた包帯を見ると少し血が滲んでいた。
「まだ痛むか?」
「痛いわよ、ところで、この足の包帯はあなたが?」
「ひどい傷だったのでな、勝手に消毒しておいた。」
「エッチなことしてないでしょうね?」
「クックック…」
「したの!?」
「心配するな、私は紳士なのでな。」
この馬鹿兎め、足が治ったら真っ先にこいつを踏んでやる。
「消毒の薬なんてあったかしら?」
「貴様が大事に抱えていた酒を使った。」
この兎のために取ってきたお酒が私の傷のために使われるなんてなんという皮肉だろう。
「フフフフフフフ…!」
生まれて初めて心の中から笑えた気がした。兎は私がなぜ大笑いしているのかよくわからないようだ。しかし私を見る目は暖かい。
「ふん、あなたが私を治療するのは当然よ。あなたは私の奴隷なんだから。」
照れ隠しにそんなことを言ってみる。
「奴隷は気に食わんといっている。」
やはりむす、とするウサギ。
「じゃぁ…」
「ふむ。」
奴隷なんか本当はほしくないのだ。
このあとに言う言葉はもう決めている。
生まれて初めて言うことば。
「じゃあ…、私と友達になりなさい。」
「喜んで。」
変な白い兎と友達になった日。
不思議な世界に一歩足を踏み入れた日。
その日、私の真っ白な世界に初めて色がついた。
第一話おわり