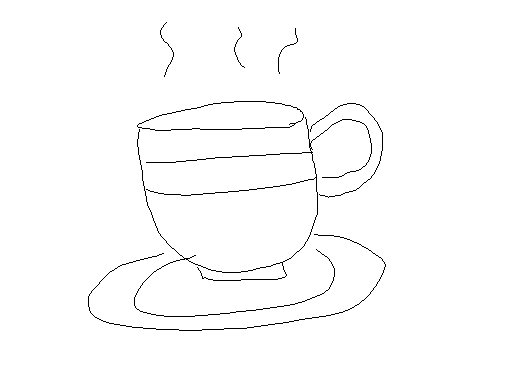ゐら<ゑ☆レま〃レヽω
T=〃レヽ±ωゎ
期待していたのは事実です。
ふらふらと、昔住んでいた―――いわば故郷である土地に、彼がまだ住んでいるであろうこの街に来てしまったのは、それはもう間違いなく、一目彼を見たかったから。
どうあっても繕えない。それは絶対にしてはならないこと。
だって、私はまだ彼を。
再会してしまったら、きっと気持ちを抑えることが出来なくなってしまう。そんな確信がありました。
だから来てはいけなかった。彼を探したりしてはいけなかった。彼とよく遊んだ公園で、思い出の木陰で、その姿を求めたりしてはいけなかった。
私は途方もない馬鹿でした。気付けば彼に声をかけ、彼の誘いに乗り、そしてまた会う約束まで受けてしまったのですから。
こんなことは許されないのに。あの日、彼に拒絶されたあの瞬間、彼への想いは断ち切るべきだったのです。
そうすればこんな愚かしい苦悩に苛まされることは無かった。素直に、喜んであの人と結婚できたでしょう。
私の婚約者は、決して悪い人ではありません。純朴で明朗で、とても素晴らしい人です。
何故あの人は私なんかを選んだのでしょう。今の時代に家柄などを気にするのは馬鹿げていますが、それでも気にしてしまう程の―――私のような女とはとても不釣合いな、良い家柄の息子。
あの人に不満はありません。きっと明るく優しさに満ち溢れた家庭を、あの人となら築けることでしょう。
問題があるとすればただ一つ。
私はあの人を愛していないのです。
待ち合わせの時刻まであと30分。
巳貴は迷っていた。
昨日見た梢の左薬指。そこには確かに、鈍く銀に輝く指輪がはめ込まれていた。それは恐らくエンゲージリングなのだろう。
だとすれば、もう梢に会ってはいけない。それは梢を困惑させるだけだ。自らを傷つけるだけだ。
不思議なものだ、と巳貴はつくづく思った。梢と再会する直前まで、彼女に対する愛情など心の奥でガチガチに凍り付いていたのに。
しかし梢の顔を認識した瞬間、氷は跡形も無く蒸発し、懐かしい、そして新たに生まれた得体のしれない感情が巳貴の身体を駆け抜けた。
あれは何だったのだろう。恋でもない、肉欲でもない。目の前に立つ梢の存在が、その境界線が薄れ巳貴と交じり合ったような。星が落ちるよりも短い時間、確かに感じたあの奇妙な一体感は。
洗面台の鏡に映った自分の顔を見て、巳貴の眉間に皺が寄る。
酷い格好だった。
プリントのカットソーに黒いベスト、細身のデニムパンツ。そして数種類のアクセサリー。それはあまりにも、「きめて」いた。
梢に会うという、そのために必死で服を選んでしまった。
(デート気取りか)
途端、とてつもない自己嫌悪が巳貴を襲う。
滑稽だった。梢にはもう心に決めた人がいるというのに、自分は一人浮かれて。
やはり行くのはやめよう。
そう思ったが、巳貴は梢の連絡先を知らなかった。
このまま家から出ずにいれば、梢を断ち切れるだろうか。しかし恐らく、彼女は巳貴の家まで来てしまうだろう。
たとえそうならなくとも、この炎天下の中、奇蹟のように白く透き通った梢の肌を日にさらし続けるというのは、申し訳ない気がした。
梢にも、そしてその婚約者にも。
日傘というのは、やけに目立つ。
純白に輝く傘と、黒いスモックのカーディガンのコントラストが目を引く。
「ごめんなさい。お待たせしました」
駆け寄り、巳貴は頭を下げた。
「待ってないよ」
涼やかに梢は微笑む。それは幼い頃とは全く違う、言ってみれば大人の笑みだった。
「それで、今日はどうするのかしら」
大きな木の下へ巳貴を誘いながら、梢は言った。
「えぇっと。実は何も考えてなかったんですけど」
何か見たいものはありますか。
巳貴の問いに、しばし彼女は考え「特に何も」と呟く。
梢にしてみれば巳貴に会うのが目的だったのだ。ましてや6年前まで住んでいた街。これといった名所が無いのも知っている。
巳貴は少々面食らったが、それでも頭を回し、目的を作り出す。
「最近できた喫茶店があるんですけど。そこ行きませんか?」
「喫茶店?」
「なんかお洒落っぽくて一人じゃなかなか入れなかったんです」
時刻は3時近い。お茶でくつろぐには丁度いい時間かもしれなかった。
「わかった。そこ行こう」
不意に、梢が巳貴の手をとった。それがあまりにも自然で、懐かしくて、巳貴は一瞬それがどういう意味なのか判断できなかった。
あなたは俺と手なんか繋いではいけない。
そう言おうとしたが、喉で引っ掛かって言葉にならなかった。
高鳴る胸の鼓動を覚られないように、静かに歩き出す。
その店は、公園に植えられた広葉樹林と街路樹の並木に挟まれた場所に、ぽつんと建っていた。
北欧の民家のような小ぢんまりとしたレンガ造り。建物自体は新しいはずだが、どこか年季の入った感じがする不思議な佇まいだった。
「素敵」
一目見て、梢は気に入ったようだ。
ちりん、とドアベルを鳴らしながら店に踏み入る。クラシックジャズとでもいうのだろうか。ピアノを基調とした、軽快ながらも静かな曲が流れていた。
窓際の席を選び、向かい合って座る。
「紅茶が美味しいらしいんです、ここ」
メニューを梢に渡しながら、巳貴は店内を見回してみる。
客は3組いた。こちらを気にしている様子は無い。
「私、ケーキセットとおすすめブレンド」
注文をとりに来たウェイトレスに梢が告げる。
「じゃあ僕はこの・・・ウバ・ハイランズ?でお願いします」
巳貴は紅茶の種類がずらりと並べられたメニューに戸惑いながらも、適当に目に付いたものを頼んだ。
元来コーヒーが苦手で、飲むのは専ら緑茶と紅茶の巳貴であったが、茶葉に関しては全くといって良いほど無知なのであった。
「ウバって何?美味しいの?」
早速興味津々、といった調子で梢が訊いてくる。巳貴は誤魔化してもすぐにボロが出ると踏み、正直に「いや、適当で」と言うしかなかった。
10分ほどで、ケーキセットと紅茶が運ばれてきた。
真夏にホットティーというのもなかなか悪くない。少し強めに効いた冷房はこのためなのだろうか。
「あ、香りがすごくいい」
オリジナルブレンドの紅茶は個人の好みで当たり外れがあるが、どうやら梢には当たりだったらしい。
巳貴の頼んだウバ茶も渋みがしかっりしている割に、ほんのりとした甘味と、抜けるような爽やかな香りが心地よく飲みやすかった。
「巳貴くんはケーキとか食べないの?」
ラズベリーのプチタルトを突付きつつ、梢が巳貴の顔を覗き込む。
「・・・お茶菓子とか、あまり好きじゃないんで」
「甘いの苦手ってこと?」
「甘いのは好きですよ。でも、お茶飲むときはお茶だけを飲みたいんです」
「ふーん」
変なの。
梢の呟きを聞き流しつつ、巳貴はどうしたものかと悩んでいた。
家を出てから梢に会うまでの時間ずっと考えていた。
梢に訊かなくてはならない。
指輪の意味。帰ってきた理由。そして今自分といるその心中を。
もしも全てが巳貴の想像通りだとしたら、今すぐここで梢に別れを告げなくてはならなかった。
だから、訊くのだ。
たとえその答えが、巳貴自身を粉々に打ち砕くものであったとしても。
「梢さん」
ティーカップをソーサーに戻し、巳貴は俯き加減に声を発する。
目を見なくては、梢の気持ちを察することなど叶わないだろう。
しかしどうしても、顔を上げることが出来なかった。
「訊いてもいいですか」
トーンを落とした巳貴の緊張が、一気に梢にも伝わった。
「なに?」
梢もフォークを皿に置く。
そして巳貴をまっすぐに見つめた。
すぐには言葉にならなかった。笑って誤魔化して、自ら作り出した緊迫しきった空気をぶち壊したかった。
だが、それでは駄目なのだ。
これはきっと、梢のためにも、はっきりとさせなくてはならない話―――
「昨日からずっと気になってはいたんです。でも、まだ梢さんは18だし、そんな年齢ではないと。そう自分に言い聞かせていました」
徐々に、指先が疼きだす。
「だけど、どうしてもそれ以外には考えられない。そしてきっと、そういうこともあるんだと、そう思いました」
やっぱりいけない。顔を上げなくては。彼女の顔を、目を見て話さなくては。
意を決し、正面から梢を見据えた。窓から差し込む光に淡く照らし出された梢は、本当に美しかった。
「梢さんは結婚するんですか」
梢は動かなかった。眉一つ動かさず、巳貴を見つめている。
「その指輪は、結婚指輪ですよね」
静かに目を閉じ、梢は小さく息を吐く。
一瞬の逡巡。そして何かを決心したように、再び目を開く。
「そうよ」
ああ、やはり。そうなのだな。
妙に落ち着いていた。もっと大きなショックがあると踏んでいた巳貴は、拍子抜けしたように手元を見た。
しかし。
「でもね―――」
ごめんなさい、と梢が言ったような気がした。声になど出してはいないのに。
「私が愛してるのは、あなたなのよ」
決して口にしてはいけない言葉。
それでも梢の瞳は澄んでいた。