賭博天空録バカラス
31.シマの魔雀 その5
それは、気ままな彼女らしい無軌道な発端だった。
五月の半ば、春が終わって夏の匂いがし始めた頃。
彼女――嶋あやめの目的地の中で、狗藤がオーナーを勤める地下カジノ『ダークメサイア』の優先順位は低かったはずだった。
ちょうど行き先を決めるため、愛車のホンダCBR1000RRを停めて考えた時、熱く盛っている場は二つほどあったのだ。
ひとつは関西方面の競馬場をウロついているという常勝無敗の少女。
野球帽を被っていて、売り子かと思っていると穴場の売り場にトコトコ歩いていって、いくらか増えた札束を持って戻ってくるという。
これは以前から噂を聞いていて、狙いをつけていたのだけれど、なかなか行方が掴めなかった。
その位置情報がようやっとシマまで流れてきたのだ。
もうひとつは、北の方で打ち歩いているという片腕の男。
右腕一本で、牌をあっという間にすり換えるという。その技も一目見てみたい。
そうして、行き先を北に定めようと顔を上げた時、ポケットで携帯が振動したのだった。
シマは二つ携帯を所持している。事務連絡のためのものと、知り合った一般人に見せても構わないデコイのもの。
着信したのは、無骨なシルバーの事務用のものだった。
画面に表示される、カジノの名前や規模、種目。
喰えそうな獲物のあれこれ。
しかし、なによりもシマの目に引いたのはそのカジノの住所だった。
見覚えのある地名。
けれど、このカジノはいつでも喰える。
優先するべきはいつ行方知れずともなりかねない二人のはぐれ者の方。
そんなことは、わかっていたのに。
ここからは山を挟んだ向こう側にある、自分がやってきた方角を振り返って。
メットをつけて膝がこすれるほどバイクを傾げ、弧を描いて反転疾走。
そう、今思えば、それはきっと。
心の隅に、こっそり隠れていたもの。
ほんの少しだけ生まれてしまった、同胞意識――。
【イブキ】
東を引いた鴉羽が右往左往した挙句に入り口側の席に着いた。
反時計回りに、南家シマ、西家狗藤、北家私(イブキ)と腰掛けていく。
先刻の河を卓へ流し込み、ガラガラとかき混ぜられる音に耳を傾けながら、私は対面の顔を窺った。敵情視察だ。
湯上りの頬は少し赤みを帯びていて、彼女の容姿を一層幼く見せていた。
鏡がないのでわからないが私も同じようなものだろう。
シマの謀略によってのぼせてしまったが、私とて博打でご飯を食べる身だ。
配牌を開ける頃にはいつものフォームを取り戻していた。
神経を集中させ、針のように研ぎ澄まされた感覚で彼らの理牌する音を捉える。
この時はまだ薄い靄がかかったように漠然としたイメージしか届いて来ない。
タン! と親の鴉羽が第一打を強く打つ。
その衝撃はほんのささやかなものだが、卓を渡ってヤマの牌へぶつかり跳ね返る。
それを繰り返してほぼ八、九順で私はすべての牌の正体を看破する。
しからば決して放銃しないし、ツモ和了は常にリーチ一発。
稀役、嶺上開花とてお手の物。
我ながら無敵の才能だ。
ツモった牌を手に入れ、不要牌を強く打ち出し、響かせる。
岩盤の中に埋もれる化石を発掘するように、私は一枚一枚の牌にかかった不明の土をどけていく。
東一局、鴉羽が四千オールを当然のようにツモあがり。
「鴉羽さん、四千オールじゃない時の方が珍しいね」と何が楽しいのかシマはヘラヘラ笑っている。
鴉羽も、ほっとしたように笑みを零して綺麗に揃えた点棒を大切そうに仕舞いこんだ。
「俺はいつも、いいところまではいくんだがね。それきりなんだ」
その鴉羽の呟きを聞いて、私と狗藤は肩をすくめ合った。
一本場はシマが喰いタンドラドラをツモあがって鴉羽の親を流した。
メンゼンで進めればいくらでも高くなりそうな手だったが、今の自分では後手を踏むという判断だろう。
私も彼女の立場だったらそうしていたはずだ。
こうして打ち始めてから私は、シマに対してずっと奇妙な親近感を覚えていた。
それは彼女の方からも同様であったのだろう。
時折、お互い敵同士でありながらふっと柔らかい視線を当てあうことがある。
その度に私は緩みかける自身の気を叱咤し、こっそり二の腕をつねって緊張感を取り戻していた。
どうも彼女は私のペースを狂わせる。
また、彼女もそれを自覚し楽しんでいる節があった。先の襲撃などはその典型だ。
なにを考えているのか分からないが、油断はできない。
シマは私の聴覚に感づいている。
彼女を確実にこの場で始末しなければならない。
秘密を知られるということは、そういうことだ。
東二局、狗藤がメンピンツモドラの一三、二六。
不調シマの親番は続かない。
東三局、私はこんな手だった。
五月の半ば、春が終わって夏の匂いがし始めた頃。
彼女――嶋あやめの目的地の中で、狗藤がオーナーを勤める地下カジノ『ダークメサイア』の優先順位は低かったはずだった。
ちょうど行き先を決めるため、愛車のホンダCBR1000RRを停めて考えた時、熱く盛っている場は二つほどあったのだ。
ひとつは関西方面の競馬場をウロついているという常勝無敗の少女。
野球帽を被っていて、売り子かと思っていると穴場の売り場にトコトコ歩いていって、いくらか増えた札束を持って戻ってくるという。
これは以前から噂を聞いていて、狙いをつけていたのだけれど、なかなか行方が掴めなかった。
その位置情報がようやっとシマまで流れてきたのだ。
もうひとつは、北の方で打ち歩いているという片腕の男。
右腕一本で、牌をあっという間にすり換えるという。その技も一目見てみたい。
そうして、行き先を北に定めようと顔を上げた時、ポケットで携帯が振動したのだった。
シマは二つ携帯を所持している。事務連絡のためのものと、知り合った一般人に見せても構わないデコイのもの。
着信したのは、無骨なシルバーの事務用のものだった。
画面に表示される、カジノの名前や規模、種目。
喰えそうな獲物のあれこれ。
しかし、なによりもシマの目に引いたのはそのカジノの住所だった。
見覚えのある地名。
けれど、このカジノはいつでも喰える。
優先するべきはいつ行方知れずともなりかねない二人のはぐれ者の方。
そんなことは、わかっていたのに。
ここからは山を挟んだ向こう側にある、自分がやってきた方角を振り返って。
メットをつけて膝がこすれるほどバイクを傾げ、弧を描いて反転疾走。
そう、今思えば、それはきっと。
心の隅に、こっそり隠れていたもの。
ほんの少しだけ生まれてしまった、同胞意識――。
【イブキ】
東を引いた鴉羽が右往左往した挙句に入り口側の席に着いた。
反時計回りに、南家シマ、西家狗藤、北家私(イブキ)と腰掛けていく。
先刻の河を卓へ流し込み、ガラガラとかき混ぜられる音に耳を傾けながら、私は対面の顔を窺った。敵情視察だ。
湯上りの頬は少し赤みを帯びていて、彼女の容姿を一層幼く見せていた。
鏡がないのでわからないが私も同じようなものだろう。
シマの謀略によってのぼせてしまったが、私とて博打でご飯を食べる身だ。
配牌を開ける頃にはいつものフォームを取り戻していた。
神経を集中させ、針のように研ぎ澄まされた感覚で彼らの理牌する音を捉える。
この時はまだ薄い靄がかかったように漠然としたイメージしか届いて来ない。
タン! と親の鴉羽が第一打を強く打つ。
その衝撃はほんのささやかなものだが、卓を渡ってヤマの牌へぶつかり跳ね返る。
それを繰り返してほぼ八、九順で私はすべての牌の正体を看破する。
しからば決して放銃しないし、ツモ和了は常にリーチ一発。
稀役、嶺上開花とてお手の物。
我ながら無敵の才能だ。
ツモった牌を手に入れ、不要牌を強く打ち出し、響かせる。
岩盤の中に埋もれる化石を発掘するように、私は一枚一枚の牌にかかった不明の土をどけていく。
東一局、鴉羽が四千オールを当然のようにツモあがり。
「鴉羽さん、四千オールじゃない時の方が珍しいね」と何が楽しいのかシマはヘラヘラ笑っている。
鴉羽も、ほっとしたように笑みを零して綺麗に揃えた点棒を大切そうに仕舞いこんだ。
「俺はいつも、いいところまではいくんだがね。それきりなんだ」
その鴉羽の呟きを聞いて、私と狗藤は肩をすくめ合った。
一本場はシマが喰いタンドラドラをツモあがって鴉羽の親を流した。
メンゼンで進めればいくらでも高くなりそうな手だったが、今の自分では後手を踏むという判断だろう。
私も彼女の立場だったらそうしていたはずだ。
こうして打ち始めてから私は、シマに対してずっと奇妙な親近感を覚えていた。
それは彼女の方からも同様であったのだろう。
時折、お互い敵同士でありながらふっと柔らかい視線を当てあうことがある。
その度に私は緩みかける自身の気を叱咤し、こっそり二の腕をつねって緊張感を取り戻していた。
どうも彼女は私のペースを狂わせる。
また、彼女もそれを自覚し楽しんでいる節があった。先の襲撃などはその典型だ。
なにを考えているのか分からないが、油断はできない。
シマは私の聴覚に感づいている。
彼女を確実にこの場で始末しなければならない。
秘密を知られるということは、そういうことだ。
東二局、狗藤がメンピンツモドラの一三、二六。
不調シマの親番は続かない。
東三局、私はこんな手だった。
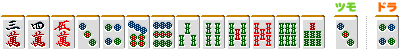
まだ八順だった。ドラは四筒。
通常なら焼き鳥のラス目であることも考え、九筒を落としてタンピン三色にまで伸ばしていきたいところだったが、私はノータイムで四筒を切り飛ばした。
狗藤がチラ、と打ち出された牌と私の顔を見比べた。
「それ、ドラだぜ」
「知っている」
その時、狗藤の手牌はこうだった。
通常なら焼き鳥のラス目であることも考え、九筒を落としてタンピン三色にまで伸ばしていきたいところだったが、私はノータイムで四筒を切り飛ばした。
狗藤がチラ、と打ち出された牌と私の顔を見比べた。
「それ、ドラだぜ」
「知っている」
その時、狗藤の手牌はこうだった。
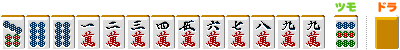
もちろん、私が知っていると言ったのは、彼の八筒のダブつきと九筒ツモのことで相違ない。
「ロン、八千」
「これだから――」苦りきった表情で狗藤は点棒を放った。
「赤ドラなんて嫌いなんだ」
「ここはあなたの店だと思ったが。ハウスルールくらい熟達しておいたらどうだ」
耳まで一気に赤く染め上げた狗藤は、深く息を吸い込むようでなんとか溜飲を下ろしたらしい。
ぴくぴくと目元が神経質に痙攣している。
彼に恨みはない。ただ博打はカッカと来たほうが負けであり、彼は金持ちだ。
男はプライドに拘るから、御し易い。
バカな生き物だが、彼らの大半はそれを認めぬままに死んでいく。
そう思わないか、シマ、と対面に心の中で呼びかける。
そうしてこうも付け加えた。
私の耳と同じことが、おまえにできるのか、と。
私はツキの波に乗っていた。
親番の東ラス、またしてもこんな手で、
「ロン、八千」
「これだから――」苦りきった表情で狗藤は点棒を放った。
「赤ドラなんて嫌いなんだ」
「ここはあなたの店だと思ったが。ハウスルールくらい熟達しておいたらどうだ」
耳まで一気に赤く染め上げた狗藤は、深く息を吸い込むようでなんとか溜飲を下ろしたらしい。
ぴくぴくと目元が神経質に痙攣している。
彼に恨みはない。ただ博打はカッカと来たほうが負けであり、彼は金持ちだ。
男はプライドに拘るから、御し易い。
バカな生き物だが、彼らの大半はそれを認めぬままに死んでいく。
そう思わないか、シマ、と対面に心の中で呼びかける。
そうしてこうも付け加えた。
私の耳と同じことが、おまえにできるのか、と。
私はツキの波に乗っていた。
親番の東ラス、またしてもこんな手で、
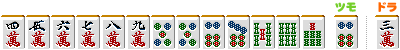
五筒切りリーチ。
シマが一瞬、目を煌かせて鴉羽の打牌に注目したが切られたのは通っている字牌。
一発喰い流しを狙ったのだろうが、鴉羽に他家との連携なんていうものを期待する方が愚かというもの。
私は丁寧に盲牌してから、ツモ牌を卓に叩きつけた。
「失礼、一発ツモ」
そして裏ドラを流れるようにめくった。
「――裏3。六千オール」
使われず王牌に沈んでいた赤五筒が、やれやれ出番に間に合った、とでも言いたそうに六筒の側に寄り添っていた。
「ふむ。切り間違えた時はどうなるかと思ったが、こういう時ほどツモってしまうものだな」
男二人はむっとしたまま何も答えない。可愛いやつらだ。
対面は私と目が合うと、手牌の端牌を二牌を倒して見せた。八九筒。
「どうせなら、七筒を切り間違えて欲しかったね」
「それは済まなかったな。文句は私の耳に言ってくれ」
「そりゃもう。ハラワタ煮えくり返ってるから、覚悟しといてよ――」
一本場。ここしばらく鳴きもリーチも見せず大人しくしていたシマが、長考の末にリーチをかけた。
すでに十二順。私は場の牌を完全に把握していたが、だからこそ焦らずにはいられなかった。
シマの待ち、北単騎はやつの次のツモなのだ。
やつがチートイツをテンパイしたのは九順目。それ以降テンパイは変わっていない。
なぜここでリーチをかけたのか、やつの身体から放たれる殺気じみた気配からイカサマやガン牌などの分かりきったツモではないことは確かだ。
つまり、これがやつの勝負強さ、ここぞという時にアガリ牌を引いてこれる強運――ということなのか。
あるいは、わざと他家の手が進行するのを待ち、回し打ちする余裕がない地点まで追い詰め、オリるなら手牌を壊さなければならなくなるまで待っていた……のか。
現に狗藤も鴉羽も苦しげに顔を歪めている。
両者ともにイーシャンテンだが、ゆえにオリても進める安全牌がないのだ。
狗藤はしばし黙考した末に、ため息をひとつ吐き出してメンツ中抜きで安全牌の四索を打った。
思わず、私はあ、と声を上げそうになった。
「――ポン!」
鴉羽が鳴きをいれ、タンヤオ手をテンパイ。
自らを鼓舞するようにして打ち出された油っこい中張牌をシマはスルーするしかない。
一発を消された上に、本来ならツモるはずだったアタリ牌が対面の私に流れてしまった。
引き結ばれた唇は無念の表れだろうか。
そうして、本当に僥倖なことに。
私もまた、シマのテンパイに合わせて北単騎に受けていたのだ。
「ツモ。チートイツ、一六オール」
この世に神がいるのなら、きっとシマはなにか怒らせるようなことをしでかしたのだろう。
私はせいぜい、媚びを売っておくことにしよう。そう固く誓った。
続く二本場は狗藤が鴉羽のヤミテンに振り込み、東場終了。
現在、私と鴉羽は一万九千点差だが、南場を丸々残している上に強運モード絶賛フィーバー中の鴉羽を突き放すには至らない。
次の南一局、鴉羽の親を流せるかどうか。
八千オールを喰らってしまえば残り六千九百の狗藤が飛んで終了してしまう。
麻雀はトップを取るゲームだ。
ツキ男ばかりにおいしいところを持っていかれてたまるものか。
そんな私の妄念が呼び寄せたのか、狗藤があっさり私のタンヤオ手に放銃した。
千三百点と安いが、私はダマ倍満をアガったような気持ちだった。
あとはゆっくりリードを保ちながら、終戦処理にもつれ込めばいい。
この半荘は次の局が最終コーナーだ。
見事、逃げ遂せてやろうじゃないか。
シマが一瞬、目を煌かせて鴉羽の打牌に注目したが切られたのは通っている字牌。
一発喰い流しを狙ったのだろうが、鴉羽に他家との連携なんていうものを期待する方が愚かというもの。
私は丁寧に盲牌してから、ツモ牌を卓に叩きつけた。
「失礼、一発ツモ」
そして裏ドラを流れるようにめくった。
「――裏3。六千オール」
使われず王牌に沈んでいた赤五筒が、やれやれ出番に間に合った、とでも言いたそうに六筒の側に寄り添っていた。
「ふむ。切り間違えた時はどうなるかと思ったが、こういう時ほどツモってしまうものだな」
男二人はむっとしたまま何も答えない。可愛いやつらだ。
対面は私と目が合うと、手牌の端牌を二牌を倒して見せた。八九筒。
「どうせなら、七筒を切り間違えて欲しかったね」
「それは済まなかったな。文句は私の耳に言ってくれ」
「そりゃもう。ハラワタ煮えくり返ってるから、覚悟しといてよ――」
一本場。ここしばらく鳴きもリーチも見せず大人しくしていたシマが、長考の末にリーチをかけた。
すでに十二順。私は場の牌を完全に把握していたが、だからこそ焦らずにはいられなかった。
シマの待ち、北単騎はやつの次のツモなのだ。
やつがチートイツをテンパイしたのは九順目。それ以降テンパイは変わっていない。
なぜここでリーチをかけたのか、やつの身体から放たれる殺気じみた気配からイカサマやガン牌などの分かりきったツモではないことは確かだ。
つまり、これがやつの勝負強さ、ここぞという時にアガリ牌を引いてこれる強運――ということなのか。
あるいは、わざと他家の手が進行するのを待ち、回し打ちする余裕がない地点まで追い詰め、オリるなら手牌を壊さなければならなくなるまで待っていた……のか。
現に狗藤も鴉羽も苦しげに顔を歪めている。
両者ともにイーシャンテンだが、ゆえにオリても進める安全牌がないのだ。
狗藤はしばし黙考した末に、ため息をひとつ吐き出してメンツ中抜きで安全牌の四索を打った。
思わず、私はあ、と声を上げそうになった。
「――ポン!」
鴉羽が鳴きをいれ、タンヤオ手をテンパイ。
自らを鼓舞するようにして打ち出された油っこい中張牌をシマはスルーするしかない。
一発を消された上に、本来ならツモるはずだったアタリ牌が対面の私に流れてしまった。
引き結ばれた唇は無念の表れだろうか。
そうして、本当に僥倖なことに。
私もまた、シマのテンパイに合わせて北単騎に受けていたのだ。
「ツモ。チートイツ、一六オール」
この世に神がいるのなら、きっとシマはなにか怒らせるようなことをしでかしたのだろう。
私はせいぜい、媚びを売っておくことにしよう。そう固く誓った。
続く二本場は狗藤が鴉羽のヤミテンに振り込み、東場終了。
現在、私と鴉羽は一万九千点差だが、南場を丸々残している上に強運モード絶賛フィーバー中の鴉羽を突き放すには至らない。
次の南一局、鴉羽の親を流せるかどうか。
八千オールを喰らってしまえば残り六千九百の狗藤が飛んで終了してしまう。
麻雀はトップを取るゲームだ。
ツキ男ばかりにおいしいところを持っていかれてたまるものか。
そんな私の妄念が呼び寄せたのか、狗藤があっさり私のタンヤオ手に放銃した。
千三百点と安いが、私はダマ倍満をアガったような気持ちだった。
あとはゆっくりリードを保ちながら、終戦処理にもつれ込めばいい。
この半荘は次の局が最終コーナーだ。
見事、逃げ遂せてやろうじゃないか。
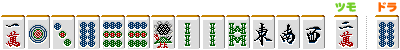
これが南二局、親番シマの配牌。河と聴き取った手牌から私が逆算したものだ。
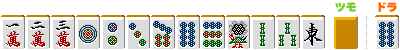
そしてこれが十二順目。九筒を残しての純チャンピンフに受けなかったのは六筒が残り一枚、九筒が枯れているためだ。
チャンタ三色ドラの親マンガン。
無論、私は放銃しないが疲労がたまっているのか頻繁に目を瞬いている鴉羽氏なら生牌の東でもひょっこり捨ててしまう可能性はある。
だからその前に、私は贈り物をしてやることにした。
次のツモでヤマから鴉羽が東を引く。そこで、
「チー」
私は狗藤の牌を喰い取った。
これで東はシマの元へいってしまう。
だがそれでいいのだ。
アガリ牌を引いてきた時のシマの顔は実に見ものだった。
手牌は倒されない。
そう、やつはアガれないのだ。
チャンタ三色ツモドラ一では、親のハネマン、六千オール。
残り五千三百の狗藤が飛ぶ。
本来なら三着から二着へ浮上し、ハコテン終了ならアガってもそうおかしなことではない。
だが、そう仕向けたのは他ならぬこの私だ。
その手をアガるということは、私のトップを確定させるということ。
この麻雀で常に私に対して奇妙な親密さと激しい敵愾心を燃やしていたシマは、この贈り物を拒否するだろう。
誰がおまえなんかの思惑に乗るものか。
そんな彼女の言葉を幻聴する。
そしてシマは突き放すように自らのアガリ牌を捨て去って。
「――ロン」
狗藤のヤミテンに、放銃した。
「チートイツドラドラ、六四だ。悪いな、シマ」
シマはなにも言わない。やはり放銃したとは思えぬほど穏やかに決められた点棒を渡すだけ。
それでいい。そうやって己の流儀とやらを守っていけばいい。
私は勝つ。白を黒に曲げても勝つ。
この世には守るべき戒律も、誇るべき価値も存在しない。
ただ在ること。それだけで十分なのだ。
おまえのように、情熱に生命を預けるなんて、夢物語に過ぎない。
もし、そんな夢を見続けるというのなら。
おまえの末路は、永劫に終わらぬ炎獄でしかない。
大勢は決した。南三局。狗藤の親番なんぞゴミと同じである。
私は悠々とした気分で鴉羽とシマを交互に見定める。
鴉羽とは二万とんで三百点の差。ハネツモでも倍ツモでもギリギリ耐え切れる。
そして私は決して振り込まない。
恐ろしいのはダブルリーチクラスの早熟手だが、早くて重い手がこんなところで都合よく来るわけはない。来たら泣いてやる。
よって、私の負けは九十九パーセントありえない。
だが不安要素は、六順目、唐突にやってくる死神のノックのように私の元にやってきた。
ドラの緑発がシマの手にトイツになっているのだ。
そうして聴こえてくる牌が増えてくる度に、少しずつ私の背筋を悪寒が走っていく。
赤ドラが二丁、入っている。ドラ四。
「ここまで我慢してきたんだから、そろそろ来てよっ……と」
チャンタ三色ドラの親マンガン。
無論、私は放銃しないが疲労がたまっているのか頻繁に目を瞬いている鴉羽氏なら生牌の東でもひょっこり捨ててしまう可能性はある。
だからその前に、私は贈り物をしてやることにした。
次のツモでヤマから鴉羽が東を引く。そこで、
「チー」
私は狗藤の牌を喰い取った。
これで東はシマの元へいってしまう。
だがそれでいいのだ。
アガリ牌を引いてきた時のシマの顔は実に見ものだった。
手牌は倒されない。
そう、やつはアガれないのだ。
チャンタ三色ツモドラ一では、親のハネマン、六千オール。
残り五千三百の狗藤が飛ぶ。
本来なら三着から二着へ浮上し、ハコテン終了ならアガってもそうおかしなことではない。
だが、そう仕向けたのは他ならぬこの私だ。
その手をアガるということは、私のトップを確定させるということ。
この麻雀で常に私に対して奇妙な親密さと激しい敵愾心を燃やしていたシマは、この贈り物を拒否するだろう。
誰がおまえなんかの思惑に乗るものか。
そんな彼女の言葉を幻聴する。
そしてシマは突き放すように自らのアガリ牌を捨て去って。
「――ロン」
狗藤のヤミテンに、放銃した。
「チートイツドラドラ、六四だ。悪いな、シマ」
シマはなにも言わない。やはり放銃したとは思えぬほど穏やかに決められた点棒を渡すだけ。
それでいい。そうやって己の流儀とやらを守っていけばいい。
私は勝つ。白を黒に曲げても勝つ。
この世には守るべき戒律も、誇るべき価値も存在しない。
ただ在ること。それだけで十分なのだ。
おまえのように、情熱に生命を預けるなんて、夢物語に過ぎない。
もし、そんな夢を見続けるというのなら。
おまえの末路は、永劫に終わらぬ炎獄でしかない。
大勢は決した。南三局。狗藤の親番なんぞゴミと同じである。
私は悠々とした気分で鴉羽とシマを交互に見定める。
鴉羽とは二万とんで三百点の差。ハネツモでも倍ツモでもギリギリ耐え切れる。
そして私は決して振り込まない。
恐ろしいのはダブルリーチクラスの早熟手だが、早くて重い手がこんなところで都合よく来るわけはない。来たら泣いてやる。
よって、私の負けは九十九パーセントありえない。
だが不安要素は、六順目、唐突にやってくる死神のノックのように私の元にやってきた。
ドラの緑発がシマの手にトイツになっているのだ。
そうして聴こえてくる牌が増えてくる度に、少しずつ私の背筋を悪寒が走っていく。
赤ドラが二丁、入っている。ドラ四。
「ここまで我慢してきたんだから、そろそろ来てよっ……と」
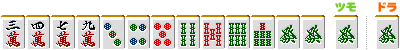
私は三枚目の緑発がやつの手に吸い込まれていくのを黙って見ているしかなかった。
そうしてこんな時に限って狗藤が鳴ける牌を打ってこない。
四五、とあるところに五を打ってくる有様で、私は叫びだしたくなった。
シマは目を瞑って、何かに耐えるように新たにツモった牌を卓に打ちつけ、
「カーン!」
カッと琥珀色の両眼を見開いた。晒される四枚のドラが、それを見る私たちの鼓動を否が応にも昂ぶらせる。
そしてシマが手を伸ばすはリンシャン牌。
つくづく、こいつは底が知れない。
四五六七、の形に七を見事引き入れたのだ。
そうしてこんな時に限って狗藤が鳴ける牌を打ってこない。
四五、とあるところに五を打ってくる有様で、私は叫びだしたくなった。
シマは目を瞑って、何かに耐えるように新たにツモった牌を卓に打ちつけ、
「カーン!」
カッと琥珀色の両眼を見開いた。晒される四枚のドラが、それを見る私たちの鼓動を否が応にも昂ぶらせる。
そしてシマが手を伸ばすはリンシャン牌。
つくづく、こいつは底が知れない。
四五六七、の形に七を見事引き入れたのだ。
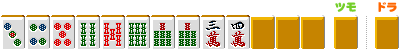
(緑発暗カンは省略)
テンパイ、二五萬。
しかもやつの次のツモは赤五萬。
「リーチッ!」
当然のようにその気配をかぎつけたのだろう。放たれた千点棒が河を舞った。
アガられれば、リーチ一発ツモ緑発、ドラ七……裏四。
カンしたことによってドラが増え、表のドラは一萬で無関係だが、その下に白が眠っている。
問答無用の数え役満だ。
親番の狗藤の点棒は一万二千。役満をツモられれば一万六千点払いでもちろんハコテン。
リー棒を抜いて七千九百のシマに対して私は四万七千五百。
引っくり返ってしまう。
――だが。
一手、私の方が速かった。
いや、正確には鴉羽の手、と言うべきか。
シマが四枚目の緑発を引く直前、神がかったタイミングで鴉羽はテンパイしていたのだ。
五七筒のカンチャンに八筒を引いてピンフのテンパイ。
そうして私の手牌には九筒がある。
これを差し込めばたったの千点で役満ツモを蹴れる。
嗚呼――この時ほど自らの勝利の確信に酔ったことはない。
悪いな、シマ。久々に、本当に久々にドキドキしたよ。
だが私は、そんなスリルなんていらない。
ツモった牌は偶然にも九筒で、そのままツモ切ろうとした時。
銃声が、鳴った。
本物でないことはすぐにわかった。
けれど私の身体は心の底の底に刻み込まれた恐怖によって反射的に振り向いてしまっていた。
私のベッドから連続してきた銃声は弾丸なんて発射せず、私たちを驚愕させただけだ。
そうして私はシマが先ほど、間違えて私のベッドで休んでいたことを思い出した。
恐らくその時、枕の下にでも仕込んだのだろう。
遠隔操作で音を鳴らせるもの。携帯電話だろうか。
そして、三人雁首並べて私たちは銃声の方をのんきに眺めていたわけだが、
ちゃっ……という音で私は首が千切れんばかりに卓を振り返った。
シマのヤマ、その右端。
確かに聴いた。
やつの手牌から、三四萬が置かれるのを。
ぶっこ抜きと呼ばれるイカサマがある。
自らの不要牌をヤマの片端につけ、反対側から同じ枚数を抜き取ってしまうという技だ。
手積みならば自分のヤマを積むのは自身なので、その方法で好きな牌を手に入れることができるというわけだ。
最も簡単なイカサマ。だが、これは自動卓だ。ヤマを好きなように積めるわけがない。
気づかれないうちに、好牌を左端に置いていて抜いたのか?
いや、そんな動きを私は見逃していないし、またやつの手牌の中身が著しく変化すればすぐに気づいたはずだ。
本来の左端の二牌は南と西。そのまま抜いてもテンパイはできない。
やつはなんのためにぶっこ抜きをしたのか。
テンパイしているのだから手を進める牌は必要ない。
そうだ、欲しかったのは私が見抜けない待ち。
やつは、待ちを変えたかったのだ。
だが、繰り返し私の思考は同じところに行き着く、左端にどうやってターツを置く?
そして私はひとつの仮説を立てた。
やつはぶっこ抜きなどしていない。
ただヤマの右端に三四萬をぶつけて音を立て(鴉羽や狗藤は聞き逃してしまうほど小さな音だったが)ぶっこ抜いたように見せかけ、待ちはその実、二五萬のまま。
そうして、ぶっこ抜きを警戒した私がアンパイに窮し、変化させたのならここはなかろう、そういう読みで二五萬を打つのを待っているのか。
どちらにせよそれなら一発ツモされて終了してしまう。
――ここまで私は振り向いてから一秒とかからずに考え終えた。
結局、やつがどんな策を弄していようと意味がないことに気づいたのだ。
鴉羽はテンパイしている。私はこの手の九筒をただ河に放てばいい。
幸い、先ほどまではダブロンルールだったが十半荘ごとに頭ハネルールに変更する取り決めが幸いした。この半荘は頭ハネだ。
仮になんらかの手段でシマが六九筒で待っていたとしても、その前に上家の鴉羽が頭ハネで和了する。
心配ない。私の勝ちだ。
波乱に満ちた南三局だったが、その結末は実にあっけない。あっけなさすぎるほどだ。
そうとも、これで終わりだ。
私は自らにまとわりつく何かを振り払うように、九筒を打った。
残念だが、シマあやめ。
私の耳に、おまえは一歩及ばなかった――!
「ロン」
テンパイ、二五萬。
しかもやつの次のツモは赤五萬。
「リーチッ!」
当然のようにその気配をかぎつけたのだろう。放たれた千点棒が河を舞った。
アガられれば、リーチ一発ツモ緑発、ドラ七……裏四。
カンしたことによってドラが増え、表のドラは一萬で無関係だが、その下に白が眠っている。
問答無用の数え役満だ。
親番の狗藤の点棒は一万二千。役満をツモられれば一万六千点払いでもちろんハコテン。
リー棒を抜いて七千九百のシマに対して私は四万七千五百。
引っくり返ってしまう。
――だが。
一手、私の方が速かった。
いや、正確には鴉羽の手、と言うべきか。
シマが四枚目の緑発を引く直前、神がかったタイミングで鴉羽はテンパイしていたのだ。
五七筒のカンチャンに八筒を引いてピンフのテンパイ。
そうして私の手牌には九筒がある。
これを差し込めばたったの千点で役満ツモを蹴れる。
嗚呼――この時ほど自らの勝利の確信に酔ったことはない。
悪いな、シマ。久々に、本当に久々にドキドキしたよ。
だが私は、そんなスリルなんていらない。
ツモった牌は偶然にも九筒で、そのままツモ切ろうとした時。
銃声が、鳴った。
本物でないことはすぐにわかった。
けれど私の身体は心の底の底に刻み込まれた恐怖によって反射的に振り向いてしまっていた。
私のベッドから連続してきた銃声は弾丸なんて発射せず、私たちを驚愕させただけだ。
そうして私はシマが先ほど、間違えて私のベッドで休んでいたことを思い出した。
恐らくその時、枕の下にでも仕込んだのだろう。
遠隔操作で音を鳴らせるもの。携帯電話だろうか。
そして、三人雁首並べて私たちは銃声の方をのんきに眺めていたわけだが、
ちゃっ……という音で私は首が千切れんばかりに卓を振り返った。
シマのヤマ、その右端。
確かに聴いた。
やつの手牌から、三四萬が置かれるのを。
ぶっこ抜きと呼ばれるイカサマがある。
自らの不要牌をヤマの片端につけ、反対側から同じ枚数を抜き取ってしまうという技だ。
手積みならば自分のヤマを積むのは自身なので、その方法で好きな牌を手に入れることができるというわけだ。
最も簡単なイカサマ。だが、これは自動卓だ。ヤマを好きなように積めるわけがない。
気づかれないうちに、好牌を左端に置いていて抜いたのか?
いや、そんな動きを私は見逃していないし、またやつの手牌の中身が著しく変化すればすぐに気づいたはずだ。
本来の左端の二牌は南と西。そのまま抜いてもテンパイはできない。
やつはなんのためにぶっこ抜きをしたのか。
テンパイしているのだから手を進める牌は必要ない。
そうだ、欲しかったのは私が見抜けない待ち。
やつは、待ちを変えたかったのだ。
だが、繰り返し私の思考は同じところに行き着く、左端にどうやってターツを置く?
そして私はひとつの仮説を立てた。
やつはぶっこ抜きなどしていない。
ただヤマの右端に三四萬をぶつけて音を立て(鴉羽や狗藤は聞き逃してしまうほど小さな音だったが)ぶっこ抜いたように見せかけ、待ちはその実、二五萬のまま。
そうして、ぶっこ抜きを警戒した私がアンパイに窮し、変化させたのならここはなかろう、そういう読みで二五萬を打つのを待っているのか。
どちらにせよそれなら一発ツモされて終了してしまう。
――ここまで私は振り向いてから一秒とかからずに考え終えた。
結局、やつがどんな策を弄していようと意味がないことに気づいたのだ。
鴉羽はテンパイしている。私はこの手の九筒をただ河に放てばいい。
幸い、先ほどまではダブロンルールだったが十半荘ごとに頭ハネルールに変更する取り決めが幸いした。この半荘は頭ハネだ。
仮になんらかの手段でシマが六九筒で待っていたとしても、その前に上家の鴉羽が頭ハネで和了する。
心配ない。私の勝ちだ。
波乱に満ちた南三局だったが、その結末は実にあっけない。あっけなさすぎるほどだ。
そうとも、これで終わりだ。
私は自らにまとわりつく何かを振り払うように、九筒を打った。
残念だが、シマあやめ。
私の耳に、おまえは一歩及ばなかった――!
「ロン」
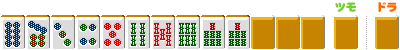
「リーチ一発緑発、ドラ六、裏四。
――――――三万二千ッ!」
あっと鴉羽が声をあげたが、もはや意味はない。
私はその時、脳裏に白熱した閃光が迸り、すべてのトリックを看破した。
あと一瞬、早く気づいていれば。
勝負はいつも、その後先で決まるのだ。
シマあやめも、鴉羽がテンパイした時に待ちターツを小手返しすることは気づいていたろう。
この局、最初にテンパイした鴉羽の待ちは穴六筒。もちろん役なしでリーチをかける価値もない愚手。
ゆえにアガる気がなかったため、この時彼は小手返しをしなかった。
彼の形式テンパイに気づいていたのは私だけだ。
次にシマが四枚目の緑発を引き込む直前の八筒ツモ。これで鴉羽はピンフを手に入れた。
しかし、まだ一手変わればタンヤオがつく可能性があったためリーチは保留。
しかし出ればアガる気だったのだろう。
一番右端、二枚の左側から出た牌が五筒。
ツモった牌を一番右に置いて、一度小手返し。
待ちが六九筒であることはシマにとって火を見るよりも容易かったはずだ。
そして緑発を引き入れリーチ。
さて、私にバレている二五萬リーチ。
一発ツモであることは私にしか分からないわけで、彼女は私からの直撃を欲し、そして求めた。
私が必ず差し込みに回るであろう七八筒を。
まず、携帯を鳴らして三人の注意を逸らす。
次に手牌右端の三四萬をヤマへ返す。
この時にあえて音を立て、私に幻のぶっこ抜きを警戒させる。
現実こそシマは一発ツモのはずであり、私は即差し込みに回れる状況であったが、そうではなくたとえばシマのツモ筋にアタリ牌がないと私が知っていて、私の手がアガれる可能性があれば、私は鴉羽に差し込まない可能性もあった。
それを避けるために、シマは私を下ろす必要があった。
そのための幻想のぶっこ抜き。
では次に七八筒をどこから持ってきたのか。
考えるまでもない。鴉羽の手牌からだ。
鴉羽の下家であるシマは、彼の右端の二牌を取る最適な位置にいる。
シマは、右手で三四萬をヤマに返すと同時に、ヤマの左端から二牌抜いた。
そして鴉羽の手牌にその二枚を残し、七八筒を自分の手の中に潜り込ませたのだ。
当然、待ちを奪われた鴉羽は手を倒せない。
シマは、あの悪魔は右手のぶっこ抜きで私の意識を盗み、同時に指先ひとつ震わせず、左手でヤマから粘りつくように二牌抜き取り、牌を沈黙させたまま、他家の待ち牌と交換した。
これが真相だ。わずか一瞬の出来事。
……もし少しでも音を立てていたら、私は気づいていただろう。
私の耳を欺くためにはほんの少したりとも牌を遊ばせてはならない。
死よりも静かな左手芸。
来る日も来る日も牌に溺れ続けた末、極限まで研磨された技。
それはもはや、千の年月を重ねた武術の奥義のごとき領域。
これが、シマあやめの魔雀。
天外魔境の三連盗――――――!
「牌がすべてわかる、か。本当にすごいよ。
わたしはどう頑張っても牌と牌がぶつかる音で、なんの牌が彫られているのか、生涯かけて努力してもきっとわからない。
でも、そういった才能と、誰が勝つかはべつだ。
君の聴き取る運命がわたしを救わないなら、この手で奇跡を造り出すまで。
わたしの勝ちだ、イブキ――!」
私は負けた、シマに――。
まだオーラスを残しているが、もはやこの半荘を制する運も力も私には残されていない。
牌を摘みながら、何かが身体から抜けていった。
力ではない。役満の直撃を受けたからといって戦意そのものを喪失する私ではない。
ただ、こいつと争うことは無駄だ。それが電撃的にわかってしまった。
私はシマに勝てない。
そして運命さえ捻じ曲げたシマはこれから嘘のような上昇の波に乗っていくだろう。
私には、そのさざめきが聴こえてくるのだ。
けれど決して悔しいわけではない。強いて言うなら仕事がやりづらくなっただけ。
そう、きっと私は初めから。
この魔物を本気で退治できるなどと、信じてはいなかったのだ。
【イブキ/】
シマはそれから人が変わったようにトップを爆走し始め、それに続いて鴉羽、イブキ、狗藤の着順が飽きるほど続いた。
狗藤も決してまずい打ち手ではない。ただ勝負所、と心を決めたところで踏み込んでは地雷に吹っ飛ばされていた。
先ほどのシマの濁りをそのまま引き受けたような形だ。
麻雀は忍耐だ。そう分かっていた彼であったが、それでも封じ込めた心から本音の水は零れてしまう。
その半荘が終わり、久々に鴉羽が一位を取った時に暗い表情で呟いた。
「ふん、もうあんた、自分の身体で返せるくらい稼いだね、おめでとう」
鴉羽は牌を流し込もうとしていた手を止めて、ひょいと顔を上げた。
「もう、そんなになったかね」
「ああ」
「なら、お終いだ」
「ああ。……ああ?」
鴉羽は席を立ち、壁にかけていた上着を手に取った。
後を追って狗藤が跳ね飛ばすように椅子から立ち上がった。
「ちょ、ちょっと待てよ。なに帰り支度してやがる。まだ完済したわけじゃないぞ」
「完済だよ。あんた、前に俺に言ったじゃないか。
いざとなれば人の命が緊急に入用なところはどこにでもあるんだ、ってな。そこに連れて行ってくれ。
残りは、死んで払うよ」
「なに言ってんだ。正気じゃないぜ。おい、おまえらもなんとか言ってくれよ! こいつ、あと一回のトップが取れないから帰るって言ってるぜ!」
「べつにおまえは困らんだろう、狗藤。借りた金をおまえに返す、と言ってるんだからな」
「しかし……」
「いいんだ。もう、いい。疲れたよ。死ぬような努力をしてまで生きていたくない。俺はそこまで、強くないんだ」
鴉羽は最後に卓の前に立ち、河を見下ろした。
喰い荒らされた動物の死骸のように、牌が散乱している。
その中から一牌つまんで、万感の思いを篭めるようにその表面を指で撫でた。
「俺は麻雀が好きだった。でも、麻雀は俺のことが大嫌いだったみたいだ。
ただ好きだというだけで愛されようなんて、ずうずうしかったかな」
そう言い残して、名残惜しむように卓の縁を撫でた後、彼は去った。
背中に、これまでの人生で重く積もった疲労を背負いながら。
狗藤はそれを釈然としない顔で見送り、イブキは一瞥しただけでなにも言わず、シマは相変わらず愉快げだった。
「不思議なものだね。一番勝っているやつが最初に死んだ」
「……理解できねえな。ここまでやって死ぬくらいなら、最初からどこかで楽に死ねばいいじゃねえか」
「これが彼なりの闘いだったんじゃないの。知らないけど。
さ、続けようか」
え? と狗藤が振り返ると、シマとイブキは当たり前のような顔をして新しく出てきたヤマを斜めにずらしていた。
「昔からひとり死んだらサンマア(三人麻雀)と相場は決まってるんだ。
よし、面倒だからマンズと北は全部抜きドラにしよう。すごいよ、一点いくらにしようか。ワクワクするなぁ」
「ちょ、おまえらなにを勝手なこと言ってやがる。そんなバカなこと……」
「まさか断らないだろうな、オーナー。
私たちは客だぞ? ああ、私ならディーラーはやめた。今やめた。
ここは上司の面が気に喰わん」
「さ、早く席に着いて。まだまだ遊び足りないよ」
二人の美少女が照明を浴びて紅い三日月の笑みを浮かべている。
それを見る狗藤の顔は月光に照らされたように、蒼かった。
――――――三万二千ッ!」
あっと鴉羽が声をあげたが、もはや意味はない。
私はその時、脳裏に白熱した閃光が迸り、すべてのトリックを看破した。
あと一瞬、早く気づいていれば。
勝負はいつも、その後先で決まるのだ。
シマあやめも、鴉羽がテンパイした時に待ちターツを小手返しすることは気づいていたろう。
この局、最初にテンパイした鴉羽の待ちは穴六筒。もちろん役なしでリーチをかける価値もない愚手。
ゆえにアガる気がなかったため、この時彼は小手返しをしなかった。
彼の形式テンパイに気づいていたのは私だけだ。
次にシマが四枚目の緑発を引き込む直前の八筒ツモ。これで鴉羽はピンフを手に入れた。
しかし、まだ一手変わればタンヤオがつく可能性があったためリーチは保留。
しかし出ればアガる気だったのだろう。
一番右端、二枚の左側から出た牌が五筒。
ツモった牌を一番右に置いて、一度小手返し。
待ちが六九筒であることはシマにとって火を見るよりも容易かったはずだ。
そして緑発を引き入れリーチ。
さて、私にバレている二五萬リーチ。
一発ツモであることは私にしか分からないわけで、彼女は私からの直撃を欲し、そして求めた。
私が必ず差し込みに回るであろう七八筒を。
まず、携帯を鳴らして三人の注意を逸らす。
次に手牌右端の三四萬をヤマへ返す。
この時にあえて音を立て、私に幻のぶっこ抜きを警戒させる。
現実こそシマは一発ツモのはずであり、私は即差し込みに回れる状況であったが、そうではなくたとえばシマのツモ筋にアタリ牌がないと私が知っていて、私の手がアガれる可能性があれば、私は鴉羽に差し込まない可能性もあった。
それを避けるために、シマは私を下ろす必要があった。
そのための幻想のぶっこ抜き。
では次に七八筒をどこから持ってきたのか。
考えるまでもない。鴉羽の手牌からだ。
鴉羽の下家であるシマは、彼の右端の二牌を取る最適な位置にいる。
シマは、右手で三四萬をヤマに返すと同時に、ヤマの左端から二牌抜いた。
そして鴉羽の手牌にその二枚を残し、七八筒を自分の手の中に潜り込ませたのだ。
当然、待ちを奪われた鴉羽は手を倒せない。
シマは、あの悪魔は右手のぶっこ抜きで私の意識を盗み、同時に指先ひとつ震わせず、左手でヤマから粘りつくように二牌抜き取り、牌を沈黙させたまま、他家の待ち牌と交換した。
これが真相だ。わずか一瞬の出来事。
……もし少しでも音を立てていたら、私は気づいていただろう。
私の耳を欺くためにはほんの少したりとも牌を遊ばせてはならない。
死よりも静かな左手芸。
来る日も来る日も牌に溺れ続けた末、極限まで研磨された技。
それはもはや、千の年月を重ねた武術の奥義のごとき領域。
これが、シマあやめの魔雀。
天外魔境の三連盗――――――!
「牌がすべてわかる、か。本当にすごいよ。
わたしはどう頑張っても牌と牌がぶつかる音で、なんの牌が彫られているのか、生涯かけて努力してもきっとわからない。
でも、そういった才能と、誰が勝つかはべつだ。
君の聴き取る運命がわたしを救わないなら、この手で奇跡を造り出すまで。
わたしの勝ちだ、イブキ――!」
私は負けた、シマに――。
まだオーラスを残しているが、もはやこの半荘を制する運も力も私には残されていない。
牌を摘みながら、何かが身体から抜けていった。
力ではない。役満の直撃を受けたからといって戦意そのものを喪失する私ではない。
ただ、こいつと争うことは無駄だ。それが電撃的にわかってしまった。
私はシマに勝てない。
そして運命さえ捻じ曲げたシマはこれから嘘のような上昇の波に乗っていくだろう。
私には、そのさざめきが聴こえてくるのだ。
けれど決して悔しいわけではない。強いて言うなら仕事がやりづらくなっただけ。
そう、きっと私は初めから。
この魔物を本気で退治できるなどと、信じてはいなかったのだ。
【イブキ/】
シマはそれから人が変わったようにトップを爆走し始め、それに続いて鴉羽、イブキ、狗藤の着順が飽きるほど続いた。
狗藤も決してまずい打ち手ではない。ただ勝負所、と心を決めたところで踏み込んでは地雷に吹っ飛ばされていた。
先ほどのシマの濁りをそのまま引き受けたような形だ。
麻雀は忍耐だ。そう分かっていた彼であったが、それでも封じ込めた心から本音の水は零れてしまう。
その半荘が終わり、久々に鴉羽が一位を取った時に暗い表情で呟いた。
「ふん、もうあんた、自分の身体で返せるくらい稼いだね、おめでとう」
鴉羽は牌を流し込もうとしていた手を止めて、ひょいと顔を上げた。
「もう、そんなになったかね」
「ああ」
「なら、お終いだ」
「ああ。……ああ?」
鴉羽は席を立ち、壁にかけていた上着を手に取った。
後を追って狗藤が跳ね飛ばすように椅子から立ち上がった。
「ちょ、ちょっと待てよ。なに帰り支度してやがる。まだ完済したわけじゃないぞ」
「完済だよ。あんた、前に俺に言ったじゃないか。
いざとなれば人の命が緊急に入用なところはどこにでもあるんだ、ってな。そこに連れて行ってくれ。
残りは、死んで払うよ」
「なに言ってんだ。正気じゃないぜ。おい、おまえらもなんとか言ってくれよ! こいつ、あと一回のトップが取れないから帰るって言ってるぜ!」
「べつにおまえは困らんだろう、狗藤。借りた金をおまえに返す、と言ってるんだからな」
「しかし……」
「いいんだ。もう、いい。疲れたよ。死ぬような努力をしてまで生きていたくない。俺はそこまで、強くないんだ」
鴉羽は最後に卓の前に立ち、河を見下ろした。
喰い荒らされた動物の死骸のように、牌が散乱している。
その中から一牌つまんで、万感の思いを篭めるようにその表面を指で撫でた。
「俺は麻雀が好きだった。でも、麻雀は俺のことが大嫌いだったみたいだ。
ただ好きだというだけで愛されようなんて、ずうずうしかったかな」
そう言い残して、名残惜しむように卓の縁を撫でた後、彼は去った。
背中に、これまでの人生で重く積もった疲労を背負いながら。
狗藤はそれを釈然としない顔で見送り、イブキは一瞥しただけでなにも言わず、シマは相変わらず愉快げだった。
「不思議なものだね。一番勝っているやつが最初に死んだ」
「……理解できねえな。ここまでやって死ぬくらいなら、最初からどこかで楽に死ねばいいじゃねえか」
「これが彼なりの闘いだったんじゃないの。知らないけど。
さ、続けようか」
え? と狗藤が振り返ると、シマとイブキは当たり前のような顔をして新しく出てきたヤマを斜めにずらしていた。
「昔からひとり死んだらサンマア(三人麻雀)と相場は決まってるんだ。
よし、面倒だからマンズと北は全部抜きドラにしよう。すごいよ、一点いくらにしようか。ワクワクするなぁ」
「ちょ、おまえらなにを勝手なこと言ってやがる。そんなバカなこと……」
「まさか断らないだろうな、オーナー。
私たちは客だぞ? ああ、私ならディーラーはやめた。今やめた。
ここは上司の面が気に喰わん」
「さ、早く席に着いて。まだまだ遊び足りないよ」
二人の美少女が照明を浴びて紅い三日月の笑みを浮かべている。
それを見る狗藤の顔は月光に照らされたように、蒼かった。

