天ノ雀――アマノジャク――
06.弱者は死すべし!
二日目の夕刻、冷房の効かなくなった和室は汗みずくの男たちでむせ返るようであった。室外機を破壊した当の天馬でさえ、顔面から多量の汗を滴らせて苦痛に耐えている。
よしくんの醜態は一座に一層の緊張を強いたようであった。冗談をいいあう会話の中にも不可視の棘が混ざっており、自分だけはああはならない、という思いに皆が駆られていた。
平然とした態度を続けていたのは白垣、天馬、烈香などのおなじみのメンバー。もっとも、白垣に関しては懐がこの場ではもっとも深く、払いを損なうことがないため気楽でいられたのだろう。レートが金を超えた時、彼がどんな表情をするのか、大柄な彼の背中を見るたびに天馬は興味を湧かした。
ひとり、またひとりとハコテンになったものたちが帰っていく。
白垣家のメイドたちが麦茶やそうめんを運んできてくれたり、また仮眠室で涼んでから戦場へ復帰することもできたが、それでも灼熱の部屋での闘牌は彼らの戦意を著しく消耗させた。そうして彼らは無意識のうちに身体の悲鳴に打ち負かされ、どんなに自分を叱咤しようともケアレスミスを演じてしまう。
あッと叫びたくなるような打牌の末に、ロン、といわれてしまうのだ。
天馬は卓に散らばった金をポケットにぞんざいに突っ込み、腰をあげた。周囲の彼を見る目が昨夜とはだいぶ異なっている。
白垣は烈香をダークホースと呼んだが、天馬の素性を知っているものたちは彼の活躍に対して驚いているようであった。三村とのいさかいを知らぬものは少なかったが、それでもまさかあの馬場天馬が、という思いがあったのであろう。
自分を見つめてくる視線の棘に、天馬はそれ以上の迫力をもって返した。
半分近くに減った参加者たちは、それぞれ脱落者たちが用意した金をそれぞれが握っている。彼らを完全に潰すのは難しい。
(絶対に痛み分けなんかにはさせねえぞ。勝つのはオレだ。オレだけが勝てばいいんだ。どいつもこいつも負けて死ね!)
そう強く思うと決まっていつも、烈香がこちらを見ているのだった。
彼女は、すでに昨夜のうちに大勝し懐に余裕のある相手を引き摺り下ろしていた。
そうして弱った獲物を、死肉喰らいの獣のように天馬がやってきてトドメを刺す。
どちらから申し出たわけでもないが、一種の共闘関係を構成しているようでもあった。もっとも二人とも、最終的には相手を潰してしまう腹積もりだったのだが。
一度も仮眠室へいかず、抜け番の時は他人の打ち筋をじっと素早い眼差しで追っている烈香の疲労は相当なものであったろう。眼の縁に濃いクマを浮かび上がらせた彼女の姿は亡霊のようだった。
上半身裸になった白垣たち男衆を不愉快そうに睨んでいる。彼女は上着を脱いでブラウス姿になっており、ぴちっと衣服が汗で肌に張り付いてしまっていた。時折ぱたぱたと指で風を入れ込む度に男たちの視線が集まったが、彼女は気づいていたのかいないのか。
天馬が座っていた席に収まった烈香の対面にすっと三村が座った。ピアスの輪がきらりと光る。
「さて、そろそろ思い上がったお嬢さんに格の違いを教えてやるかな」
「黙って打て、ウスノロ」
三村は拳を振り上げ卓に打ち下ろそうとしたが、にやにや笑いを浮かべた白垣と眼が合って引っ込めた。卓を壊したら勝ち負け以前に弁償である。
そうして綺麗に並べた手牌をかつてない真剣さで眺めた。この女だけには負けられないとでも思っていたろう。
天馬はまた、隣にいた進藤に外ウマを吹っかけた。
眼鏡を外して目頭を揉んでいた進藤は大人しそうに見えて烈しい一面があるのか、懲りずに乗ってきた。
しかし二人とも、三村には乗らなかった。
センチメンタリティで自分の発揮する能力の度合いを上下させる人間は麻雀であろうと他の勝負事であろうと弱者である。そのことを、この二人はよく知っていた。
天馬は三年生のマッキーに、進藤は黒縁眼鏡のノッポに乗った。烈香に乗るのは禁じ手にしよう、と進藤が言い出したためだ。
その半荘、終始三村は即リーチに打って出ていた。安い手ではあったが両面以上、先手であることが多かったからツモれると踏んでいたのであろう。
奇妙なほど、他家が彼のリーチにオリなかった。ばすばすと危険牌を振るくせに、振り込まない。新しい筋やドラを通されるたびに三村の頬が怒りで赤く染まった。
南三局、親番で三村は三順でリーチをかけた。チートイツの北単騎。一発で出てもおかしくない。心持ち彼の身が前傾になった。
「ふむ――そんな早いんじゃわからねえな」と三年のマッキーがぼやき「堂々といくか、それ、ドラだ!」
「おまえらもう少し――」三村が沈痛な声を出した。「まじめに麻雀をしろよ」
「ふうん、なるほど」といったのは烈香だ。彼女が戦闘中にしゃべるのは珍しい。
天馬は初めて、彼女が笑うのを見た。名前に相応しい烈しい顔つきだった。
「まじめに麻雀すると出る牌が当たりってことか」
「――――」
「みんな、字牌と二順目に切った五萬の筋は打つなよ」
そこでポーカーフェイスを作れたら、あるいはもっとうまく裏がありそうな悔しがり方ができていたら、三村にもまだ勝機はあったかもしれない。
彼は瞬きをしながらツモ切りを繰り返した末、烈香のタンピンドラドラに振込み、ハコテンを割った。
彼は手牌を開いて、皆にそれを晒した。
よしくんの醜態は一座に一層の緊張を強いたようであった。冗談をいいあう会話の中にも不可視の棘が混ざっており、自分だけはああはならない、という思いに皆が駆られていた。
平然とした態度を続けていたのは白垣、天馬、烈香などのおなじみのメンバー。もっとも、白垣に関しては懐がこの場ではもっとも深く、払いを損なうことがないため気楽でいられたのだろう。レートが金を超えた時、彼がどんな表情をするのか、大柄な彼の背中を見るたびに天馬は興味を湧かした。
ひとり、またひとりとハコテンになったものたちが帰っていく。
白垣家のメイドたちが麦茶やそうめんを運んできてくれたり、また仮眠室で涼んでから戦場へ復帰することもできたが、それでも灼熱の部屋での闘牌は彼らの戦意を著しく消耗させた。そうして彼らは無意識のうちに身体の悲鳴に打ち負かされ、どんなに自分を叱咤しようともケアレスミスを演じてしまう。
あッと叫びたくなるような打牌の末に、ロン、といわれてしまうのだ。
天馬は卓に散らばった金をポケットにぞんざいに突っ込み、腰をあげた。周囲の彼を見る目が昨夜とはだいぶ異なっている。
白垣は烈香をダークホースと呼んだが、天馬の素性を知っているものたちは彼の活躍に対して驚いているようであった。三村とのいさかいを知らぬものは少なかったが、それでもまさかあの馬場天馬が、という思いがあったのであろう。
自分を見つめてくる視線の棘に、天馬はそれ以上の迫力をもって返した。
半分近くに減った参加者たちは、それぞれ脱落者たちが用意した金をそれぞれが握っている。彼らを完全に潰すのは難しい。
(絶対に痛み分けなんかにはさせねえぞ。勝つのはオレだ。オレだけが勝てばいいんだ。どいつもこいつも負けて死ね!)
そう強く思うと決まっていつも、烈香がこちらを見ているのだった。
彼女は、すでに昨夜のうちに大勝し懐に余裕のある相手を引き摺り下ろしていた。
そうして弱った獲物を、死肉喰らいの獣のように天馬がやってきてトドメを刺す。
どちらから申し出たわけでもないが、一種の共闘関係を構成しているようでもあった。もっとも二人とも、最終的には相手を潰してしまう腹積もりだったのだが。
一度も仮眠室へいかず、抜け番の時は他人の打ち筋をじっと素早い眼差しで追っている烈香の疲労は相当なものであったろう。眼の縁に濃いクマを浮かび上がらせた彼女の姿は亡霊のようだった。
上半身裸になった白垣たち男衆を不愉快そうに睨んでいる。彼女は上着を脱いでブラウス姿になっており、ぴちっと衣服が汗で肌に張り付いてしまっていた。時折ぱたぱたと指で風を入れ込む度に男たちの視線が集まったが、彼女は気づいていたのかいないのか。
天馬が座っていた席に収まった烈香の対面にすっと三村が座った。ピアスの輪がきらりと光る。
「さて、そろそろ思い上がったお嬢さんに格の違いを教えてやるかな」
「黙って打て、ウスノロ」
三村は拳を振り上げ卓に打ち下ろそうとしたが、にやにや笑いを浮かべた白垣と眼が合って引っ込めた。卓を壊したら勝ち負け以前に弁償である。
そうして綺麗に並べた手牌をかつてない真剣さで眺めた。この女だけには負けられないとでも思っていたろう。
天馬はまた、隣にいた進藤に外ウマを吹っかけた。
眼鏡を外して目頭を揉んでいた進藤は大人しそうに見えて烈しい一面があるのか、懲りずに乗ってきた。
しかし二人とも、三村には乗らなかった。
センチメンタリティで自分の発揮する能力の度合いを上下させる人間は麻雀であろうと他の勝負事であろうと弱者である。そのことを、この二人はよく知っていた。
天馬は三年生のマッキーに、進藤は黒縁眼鏡のノッポに乗った。烈香に乗るのは禁じ手にしよう、と進藤が言い出したためだ。
その半荘、終始三村は即リーチに打って出ていた。安い手ではあったが両面以上、先手であることが多かったからツモれると踏んでいたのであろう。
奇妙なほど、他家が彼のリーチにオリなかった。ばすばすと危険牌を振るくせに、振り込まない。新しい筋やドラを通されるたびに三村の頬が怒りで赤く染まった。
南三局、親番で三村は三順でリーチをかけた。チートイツの北単騎。一発で出てもおかしくない。心持ち彼の身が前傾になった。
「ふむ――そんな早いんじゃわからねえな」と三年のマッキーがぼやき「堂々といくか、それ、ドラだ!」
「おまえらもう少し――」三村が沈痛な声を出した。「まじめに麻雀をしろよ」
「ふうん、なるほど」といったのは烈香だ。彼女が戦闘中にしゃべるのは珍しい。
天馬は初めて、彼女が笑うのを見た。名前に相応しい烈しい顔つきだった。
「まじめに麻雀すると出る牌が当たりってことか」
「――――」
「みんな、字牌と二順目に切った五萬の筋は打つなよ」
そこでポーカーフェイスを作れたら、あるいはもっとうまく裏がありそうな悔しがり方ができていたら、三村にもまだ勝機はあったかもしれない。
彼は瞬きをしながらツモ切りを繰り返した末、烈香のタンピンドラドラに振込み、ハコテンを割った。
彼は手牌を開いて、皆にそれを晒した。
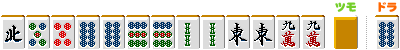
「答えろよ。俺の何が間違っていたっていうんだ。俺は正しい、ただツイてなかっただけだ。自分が強いなんて、てめえら勘違いするんじゃねえぞ」
「いいや、おまえは弱い」と烈香は言い切った。
「弱くって、みじめで、その上に情けない最低最悪の打ち手だ」
ばっと伸びてきた三村の手をあっさりかわし、烈香は侮蔑の視線を三村に当てた。
「さっき財布の中を覗いていたな。どうせ持ち金もハコったんだろ。忘れてやるからとっとと失せろ」
「おまえみたいなやつは」と烈香は言い残して部屋を出ていった。
「麻雀を打つ資格なんてないんだ――」
耳が痛くなるような沈黙の末に、三村の背中が襖の向こうに消えた。
天馬の目の前に進藤の手が差し出された。
「さ、払ってもらおう。千点棒一本差だったが、近藤の勝ちだ」
「あいつ近藤っていうのか」と天馬はノッポ眼鏡を見やった。「使えねえやつだぜ」
「よくいうよ。おまえは誰の使いにもならねえくせに」
ポケットから抜いた札束を進藤の胸に乱暴に押し付け、天馬は立ち上がった。
先ほどはトップを取ったが、今回の外ウマで台無し。少し息を抜くべきだ、と判断した。トップの記憶が新しいからといって、それにすがるべきではない。それまでの五半荘ほど、三位と四位のジグザグ走行が続いていたのだ、用心してしかるべき時。負け目のツラは滝のごとく険しい。
そして天馬は、烈香が初めて和室から出て行ったことに気づいた。それまでトイレにだって一度も立たず、麦茶一杯口にしているのを見た以外は食事もしていなかった。
窓の外から、白垣邸の外を窺った。誰もいない。街灯がアスファルトに横たわった野良猫の死骸にスポットライトを当てている。
天馬は襖を蹴破る勢いで飛び出していった。
まさか襖にまで防音機能が備わっているとは思えなかったが、白垣の父親の物好きは有名だったので妙な仕掛けでもあるのかもしれない、とにかく廊下は静まり返っていた。住み込みのメイドたちは階下で待機している。白垣が呼ばない限りは上がってこない。
天馬は裸足の足をそおっと滑らせて進んでいった。足裏の汗で転びそうになり、慌てて手すりを掴んだ。
シャワー室はこの階にあった。天馬も二度ほど使用している。タオルと代えの下着や肌着が用意されていたが、なぜか派手な柄のものばかりだったことを思い出す。
突き当たりの壁に、細長い人影が映っていた。何か言い争うような声が聞こえ、そのすぐ後に肉を打つ烈しい音がした。誰かがドサッと床に倒れこんだ気配。
天馬はL字型の廊下の曲がり角から、わずかに顔を出した。
飴のように磨き上げられ艶々している床に烈香が倒れこみ、その上に三村が覆いかぶさっていた。右手にはナイフ、左手には彼女の膨れた財布が握られている。彼はそれをポケットに突っ込むと、左手で烈香の首を掴んだ。
苦悶に歪む少女の顔をナイフでぺちぺちと叩く。
「もう一度、いってみな。誰が、麻雀を打つ資格がねえって?」
烈香の瞳から強い輝きが失われないのを見て、三村がそのナイフを彼女の眼前にかざし、指でつまんでぷらぷらと揺らした。
ちょっとした衝撃で落ちてしまいそうだ。烈香がごくっと唾を飲んだ。
「バカが、調子に乗りやがって。おまえも、あの馬場もだ。麻雀が強いからってなんだってんだ。結局、こうすりゃ、おまえらただ震えてるだけじゃねえか」
くるりと手首を返してナイフを握り、三村は刃先を烈香の白い首筋に当てた。そのまますうっと血の線を描いていき、彼女のブラウスを一息で切り裂いた。ボタンが弾け、白い下着が晒される。烈香は遮二無二抵抗したが、首を抑えられてはどうにもならない。
廊下に倒れこんだ二人を、もがく烈香の素足を眺めながら、天馬はこのままにしておこうかと思った。
自分は誰の味方でもない。仮に天馬が三村に襲われていたとしても烈香は助けに入らないだろう。
それが普通なのだ、助けというのは利害関係によってもたらされるもので、素寒貧に差し伸べられる手など本来はありえない。
弱肉強食の法則に従って生きていくつもりなら、そう覚悟し身を守る術を用意しておくべきだったのだ。
喰う以上は喰われることもありうる。ただ喰うだけでござる、というのは通るまい。
天馬の視線の先で、ますます状況が悪化していった。
「いいや、おまえは弱い」と烈香は言い切った。
「弱くって、みじめで、その上に情けない最低最悪の打ち手だ」
ばっと伸びてきた三村の手をあっさりかわし、烈香は侮蔑の視線を三村に当てた。
「さっき財布の中を覗いていたな。どうせ持ち金もハコったんだろ。忘れてやるからとっとと失せろ」
「おまえみたいなやつは」と烈香は言い残して部屋を出ていった。
「麻雀を打つ資格なんてないんだ――」
耳が痛くなるような沈黙の末に、三村の背中が襖の向こうに消えた。
天馬の目の前に進藤の手が差し出された。
「さ、払ってもらおう。千点棒一本差だったが、近藤の勝ちだ」
「あいつ近藤っていうのか」と天馬はノッポ眼鏡を見やった。「使えねえやつだぜ」
「よくいうよ。おまえは誰の使いにもならねえくせに」
ポケットから抜いた札束を進藤の胸に乱暴に押し付け、天馬は立ち上がった。
先ほどはトップを取ったが、今回の外ウマで台無し。少し息を抜くべきだ、と判断した。トップの記憶が新しいからといって、それにすがるべきではない。それまでの五半荘ほど、三位と四位のジグザグ走行が続いていたのだ、用心してしかるべき時。負け目のツラは滝のごとく険しい。
そして天馬は、烈香が初めて和室から出て行ったことに気づいた。それまでトイレにだって一度も立たず、麦茶一杯口にしているのを見た以外は食事もしていなかった。
窓の外から、白垣邸の外を窺った。誰もいない。街灯がアスファルトに横たわった野良猫の死骸にスポットライトを当てている。
天馬は襖を蹴破る勢いで飛び出していった。
まさか襖にまで防音機能が備わっているとは思えなかったが、白垣の父親の物好きは有名だったので妙な仕掛けでもあるのかもしれない、とにかく廊下は静まり返っていた。住み込みのメイドたちは階下で待機している。白垣が呼ばない限りは上がってこない。
天馬は裸足の足をそおっと滑らせて進んでいった。足裏の汗で転びそうになり、慌てて手すりを掴んだ。
シャワー室はこの階にあった。天馬も二度ほど使用している。タオルと代えの下着や肌着が用意されていたが、なぜか派手な柄のものばかりだったことを思い出す。
突き当たりの壁に、細長い人影が映っていた。何か言い争うような声が聞こえ、そのすぐ後に肉を打つ烈しい音がした。誰かがドサッと床に倒れこんだ気配。
天馬はL字型の廊下の曲がり角から、わずかに顔を出した。
飴のように磨き上げられ艶々している床に烈香が倒れこみ、その上に三村が覆いかぶさっていた。右手にはナイフ、左手には彼女の膨れた財布が握られている。彼はそれをポケットに突っ込むと、左手で烈香の首を掴んだ。
苦悶に歪む少女の顔をナイフでぺちぺちと叩く。
「もう一度、いってみな。誰が、麻雀を打つ資格がねえって?」
烈香の瞳から強い輝きが失われないのを見て、三村がそのナイフを彼女の眼前にかざし、指でつまんでぷらぷらと揺らした。
ちょっとした衝撃で落ちてしまいそうだ。烈香がごくっと唾を飲んだ。
「バカが、調子に乗りやがって。おまえも、あの馬場もだ。麻雀が強いからってなんだってんだ。結局、こうすりゃ、おまえらただ震えてるだけじゃねえか」
くるりと手首を返してナイフを握り、三村は刃先を烈香の白い首筋に当てた。そのまますうっと血の線を描いていき、彼女のブラウスを一息で切り裂いた。ボタンが弾け、白い下着が晒される。烈香は遮二無二抵抗したが、首を抑えられてはどうにもならない。
廊下に倒れこんだ二人を、もがく烈香の素足を眺めながら、天馬はこのままにしておこうかと思った。
自分は誰の味方でもない。仮に天馬が三村に襲われていたとしても烈香は助けに入らないだろう。
それが普通なのだ、助けというのは利害関係によってもたらされるもので、素寒貧に差し伸べられる手など本来はありえない。
弱肉強食の法則に従って生きていくつもりなら、そう覚悟し身を守る術を用意しておくべきだったのだ。
喰う以上は喰われることもありうる。ただ喰うだけでござる、というのは通るまい。
天馬の視線の先で、ますます状況が悪化していった。

