賭博神話ゼブライト
05.吼え猛る虎は西よりいずる
東三局。
リーチ、と親の烈香が牌を曲げた。
七順目。けん制の安手か、刺々しい打点か。
雨宮は部外者特有の気楽な気持ちで場を眺めた。
ううん、と烈香の下家のさくみが唸る。野球帽をかぶった頭に手を突っ込んでほつれた髪をかき回した。
「ああくそ、チーや。これでツモられたらウチ耐えられんわァ」
こういう時の発言は現実になりやすいものである。
烈香は次のツモを卓縁に勢いよく叩きつけた。
「ツモッ! リーヅモ裏……」
その時、雨宮には烈香の唇が、しゅっと抜ける音を出したように思えた。
「――3。四一〇〇オール」
ツモ山も、ドラ表示も、烈香の牌山だった。
オール伏せ牌の二度振りである。麻雀牌は全員で事前に点検済み、どこにでも売っているポピュラーなものだ。
雨宮は一月ほどぶりに見るこの少女を、いとおしげに見やった。
いつの間にやら成長していたらしい。これだから人生はわからない。
果たして誰が彼女に火をつけたのか。
クククッ、と笑うと、シマに足を蹴られた。
四千点を失って機嫌がよろしくないらしい。
肩をすくめてやると、ぷいっと前を向いてしまった。
シャガがツキの申し子だとするならば、烈香は玄人の生き残りだ。
烈香のヤマはいつも他人に不要牌を、自らに好牌をもたらした。
この面子を相手にして、流れるように山を仕込む。
他の三人ともなんとか彼女のヤマを配牌で使い切ってしまいたいところだったが、サイを振るのは烈香なのだ。
彼女は最初に五を出し、決して他人にサイを渡さなかった。
サイは転がることなく、卓のリンクを滑ったまま、望まれた数字を弾き出す。
雨宮はちらりとシマを見やった。
果たして積み込み、サイ振りの技術、烈香とこの悪華がまともに競い合ったらどちらが上か。なかなかの好カードである。
天馬ならどちらに張るかな、と雨宮はふいに思った。
そんな他愛なことを考えるほどに、少々気を抜いていたため、その手つきに雨宮が気づいたのはまったくの偶然だった。
イカサマを仕込む時は、同時に仕込まれやすい。
さくみは、対面のシャガのヤマから取ってきた配牌を自分のヤマの右端に一瞬つけた。
それだけの動作のように見えるが、実はこのとき右端に二枚置いてきており、自分のヤマの左端から二牌持ってきている。
初心者におなじみのお手ごろイカサマ、我らがぶっこ抜きである。
それでも、この三人の視線をかいくぐっただけあって、直視していた雨宮でさえ見逃しかけたほどの手際のよさ、淀みのなさ。
さすがだな――と雨宮はぷかあっとドーナツ型の煙を吐き出し、その輪の中に収まるさくみの横顔を眺めた。
関西を拠点とする負けなしの勝負師――霞野さくみ。
地理的事情から今までシマたちとはぶつからなかった異邦人が、風清会の清風を食い尽くしにやってきたというわけだ。
メインギャンブルは競馬だったはずだが、麻雀もいけるクチらしい。
泥を喰おうと破滅を拒む筋金いりの守銭奴で、負ける勝負からは恥も外聞もなく逃げ出す、という噂だったが、実際に負けたことも負けかけたこともないそうだから、真実はわからない。
シマと同じくいまだ活躍の時を得ていない彼女が持ってきた六牌、それは、九萬が四枚、それに八萬が二枚だった。
雨宮の眉がもぞもぞとうごめく。
(四暗刻とチンイツ……いや、九連との両テンビンってわけか? 効率悪いと思うけどな……大三元の方が手ごろだ)
ちなみに雨宮はネット麻雀を打つと役満しか出ないので感覚が麻痺している。今朝も純正九連宝燈をアガったばかりだ。
(ところがどっこい、現実は素直にいかないぜ……?)
だが現実を見えていなかったのは誰あろう雨宮だった。
それを彼はもうまもなく目の当たりにすることになる。
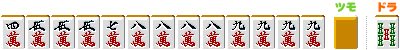
合成樹脂のつるつるしたさくみの手牌が、月光を受けて骨のように輝いていた。
(へぇ、大したもんだな……三四六萬待ち。四萬高め三暗刻か)
その時、ひょこっと親の烈香から四萬がこぼれ出た。
(来たッ。三暗刻チンイツ、倍満――!)
だが、さくみはそれをちらっと見たきり、何も言い出さなかった。
雨宮は喉の寸前までかかった声をなんとか飲み込んだ。
何を考えているのか――
次のツモで七萬をさくみは持ってきた。
まさか四暗刻を目指してカンはしないだろうな、と雨宮はざわざわしたが、あっけなくツモ切り。
(いったいこいつは何がしてぇんだ? アガりたくないのか?
誰かと組んでいて、そう、この状況だと烈香しかいない。
あいつに勝たせて、勝ちを折半すると?
だがビケを引けば引き金を引くのは自分なんだ。
そんな悠長な真似はしていられないはず……)
その時だった。
「ロン。
――三二○〇〇の二本場は、三二六〇〇の二十枚」
烈香の河に、曲げられた六萬が転がっていた。
「リーチ宣言牌でアガりか、ツバメ返しやけど、役満やからなァ――」
ばさっと扇子を広げて、さくみは笑顔の花を咲かせた。
和紙の上で虎が吼えている。
「すまへんなァ堪忍してや。
ウチ――金勘定しか取り得がなくってな」
真の高めは四萬ではなく六萬。
守銭攻命――百万石。
一転してトップに躍り出たのは霞野さくみ。
烈香はぐっと息を詰めてそれまでかけていたサングラスを外した。
「かっこつけてっから百万石に当たるのさ」
両手を枕にして、雨宮はうそぶく。
「うるさい、外野は黙ってろッ!」
カッと烈香は顔を赤く染める。無論雨宮にデレているわけではない。
ひょっとすると、彼女はこの自殺麻雀で、いまだ一度も引き金を引いていないのかもしれない。
かすかに震え始めた彼女の指先から、雨宮はそんな推理を立てた。
誰だって死ぬのは怖い。震えもするだろう。
その震えを武者震いにできたやつが真の強者となれる。
彼女ははたしてどちらだろうか。雨宮にはわからない。
「さーて麻雀の神様、ウチの親番や。もういっぺん百万石、頼んます!」
触れなば切れるような場の中で、さくみの軽口が浮いている。
しかしそれでいいのだ。今、ペースは明らかにさくみが握っている。
みな、彼女の言動を第一に考えて行動する。
特に流れを意識するシャガはしょっぱなからさくみの安全牌を抱え込むことになるだろう。
こんな時、親を必要以上に恐れて連荘されることが真に恐ろしい。
理屈ではそうわかっていても、振り切れない。
ましてや多額の金銭や命が懸かっていればなおさらだ。
どんな迷信でも信じて助かるならいくらでも信じる――勝つためなら。
勝てば官軍、負ければ賊軍。弱肉強食の百鬼夜行。
何気なく横を見ると、シマの唇がほんのかすかに、緩んでいた。

