賭博神話ゼブライト
04.自殺麻雀2
まず最初にリードを掴んだのは、おそらくシャガだったのだろう。
東初、三本、五本をツモりシマの親を潰し(雨宮がうしろでごちゃごちゃ言うからだ! というクレームは華麗に流した)、次の自分の親も二千オール裏1でチップを集めた。
ここで雨宮は、チップが積もらないことを知ることになる。
この麻雀ではチップは増えない。各人とも減っていくばかりである。
五十枚始まりで誰も五十枚以上ではないのだからもっと早く気づくべきだったな、と雨宮は舌打ちした。沸き起こりかける劣等感をねじ伏せる。
三枚のチップを受け取ったシャガは、それを教会の奥へ放り投げた。
三つの黄金色の奇跡は放物線を描き、風清会が崇めているという雲を背負った巨人の額に当たって砕けて散らばった。脆いらしい。
その足元には小さな砂漠のように、チップの残骸が広がっている。
雨宮は顎を上げて、その巨像を見上げた。額から一本の角が生えていて、それが原因かどうか、神の偶像は苦痛に顔をゆがめていた。
「まァ見てる俺は退屈しないからいいけどよ、おまえらってさ、死にたいのか?」
外野の問いに反応は様々だ。
シマは含み笑いをしたきり。さくみと烈香は河しか見えないといった態度。
シャガが言う。
「こうしなければなりませんの」
「なぜ。――あんたは」雨宮はシスターの豊かに膨らんだ胸元を凝視しながら喋った。
「勝っても失った風清会の三分の一しか取り戻せないし、どの道、もう復興は無理だろう。もう終わってるじゃないか、あんたの夢は」
せやで、とっとと諦めときや、とさくみが嘲笑う。
雨宮の問いは、シャガの胸に重く響いたらしい。心の声に耳を澄ませるように、シャガはしばし眼を伏せた。
彼女の噂は聞いている。
熱心な信者である父親に五つのときからあらゆるギャンブルの英才教育を受け、その甲斐あって、最強の座についた若き天才。
だがその胸の中には、父親や周囲の期待に対する重責がいつものしかかっていたのだろう。
そもそもギャンブルに天才などあろうはずがない。
イカサマ師はそのイカサマが失敗しない限りギャンブラーではなく仕事師でしかない。
風清会はイカサマを禁じている。運に乗ることで、神と同化するのだという。
神に一番愛されしもの、すなわち救世主、神の力を受けるものなり。
アホか。
そんな抜けたことを言っているから負けるのだ――雨宮も、今回の話を仕入れてきた白垣も最初はそう思った。
だが風清会はこの三人の襲撃を受けるまで、無敵を誇った無頼集団だったのだ。
奇跡を体現する少女は、慈愛に満ちた手つきで、己の手牌を撫でた。
「なぜって――」
「――なぜってとっても、面白いでしょう?」
前言撤回。
こいつもキチガイ。
雨宮は心の底でちょっといいなと思っていた分、烈しい失望に駆られた。
とっとと帰りたい気分になった。
赤い信者の麻雀は一言で言えば簡単だった。
両カンチャンと両面のイーシャンテンで、そっとカンチャンを埋めてリーチ、そしてツモる。
安定した麻雀といえば聞こえはいいが、とどのつまりツキに頼っている。苦しい展開にならないだけ、誰でもそうなる打ち筋。
その証拠に下家の烈香の染め手にもほとんど無警戒で急所牌を打ち出す。鳴かれる。
だがアガりはシャガの方が一歩速い。
雨宮も己の太いツキに裏切られることのない稀有な人間のひとりであったから、その打ち筋に自分に近いものをいち早く察知していた。
だからこそ、その終わりもわかってしまった。彼女よりも速く。
「リーチ――」
綺麗な所作で打ち出されたシャガのリーチ牌、一萬を討ち取ったのは、
「ロン」
烈香だった。
一萬と北のシャンポン待ち。点棒を笑顔で払うシスター。
だが、その一萬は烈香のみに当たっていたのではない。
頭ハネであるがゆえに、手牌を倒すことなく伏せて壊したのは二人。
一四萬待ちのさくみ、一四七待ちのシマ。
この三人ほど冷静な相手でなければ、三家和で流れたかもしれない局――。
いつの間に取り出したのか、雨宮はハイライトの煙を上手そうに吸い――その煙越しに青ざめたシスターの顔を覗いた。
夏だというのに、五人をさらう風は、冷ややかだった。
シャガは慎重だった。
牌運が一気に衰えたのだろう、序盤から脂っこい数牌を叩き落してベタオリの姿勢。
牌効率や敵手推理よりもアガれる局かそうでない局かによって判断を下すシャガは気に食わない局は容赦なく捨て去る。
そうしてまた太いツキの流れはニコニコして彼女を甘やかす――
――今日までは。
「ロン」
またも手を倒したのは烈香。親番で打点も大きい。まだ三順だった。
東初、三本、五本をツモりシマの親を潰し(雨宮がうしろでごちゃごちゃ言うからだ! というクレームは華麗に流した)、次の自分の親も二千オール裏1でチップを集めた。
ここで雨宮は、チップが積もらないことを知ることになる。
この麻雀ではチップは増えない。各人とも減っていくばかりである。
五十枚始まりで誰も五十枚以上ではないのだからもっと早く気づくべきだったな、と雨宮は舌打ちした。沸き起こりかける劣等感をねじ伏せる。
三枚のチップを受け取ったシャガは、それを教会の奥へ放り投げた。
三つの黄金色の奇跡は放物線を描き、風清会が崇めているという雲を背負った巨人の額に当たって砕けて散らばった。脆いらしい。
その足元には小さな砂漠のように、チップの残骸が広がっている。
雨宮は顎を上げて、その巨像を見上げた。額から一本の角が生えていて、それが原因かどうか、神の偶像は苦痛に顔をゆがめていた。
「まァ見てる俺は退屈しないからいいけどよ、おまえらってさ、死にたいのか?」
外野の問いに反応は様々だ。
シマは含み笑いをしたきり。さくみと烈香は河しか見えないといった態度。
シャガが言う。
「こうしなければなりませんの」
「なぜ。――あんたは」雨宮はシスターの豊かに膨らんだ胸元を凝視しながら喋った。
「勝っても失った風清会の三分の一しか取り戻せないし、どの道、もう復興は無理だろう。もう終わってるじゃないか、あんたの夢は」
せやで、とっとと諦めときや、とさくみが嘲笑う。
雨宮の問いは、シャガの胸に重く響いたらしい。心の声に耳を澄ませるように、シャガはしばし眼を伏せた。
彼女の噂は聞いている。
熱心な信者である父親に五つのときからあらゆるギャンブルの英才教育を受け、その甲斐あって、最強の座についた若き天才。
だがその胸の中には、父親や周囲の期待に対する重責がいつものしかかっていたのだろう。
そもそもギャンブルに天才などあろうはずがない。
イカサマ師はそのイカサマが失敗しない限りギャンブラーではなく仕事師でしかない。
風清会はイカサマを禁じている。運に乗ることで、神と同化するのだという。
神に一番愛されしもの、すなわち救世主、神の力を受けるものなり。
アホか。
そんな抜けたことを言っているから負けるのだ――雨宮も、今回の話を仕入れてきた白垣も最初はそう思った。
だが風清会はこの三人の襲撃を受けるまで、無敵を誇った無頼集団だったのだ。
奇跡を体現する少女は、慈愛に満ちた手つきで、己の手牌を撫でた。
「なぜって――」
「――なぜってとっても、面白いでしょう?」
前言撤回。
こいつもキチガイ。
雨宮は心の底でちょっといいなと思っていた分、烈しい失望に駆られた。
とっとと帰りたい気分になった。
赤い信者の麻雀は一言で言えば簡単だった。
両カンチャンと両面のイーシャンテンで、そっとカンチャンを埋めてリーチ、そしてツモる。
安定した麻雀といえば聞こえはいいが、とどのつまりツキに頼っている。苦しい展開にならないだけ、誰でもそうなる打ち筋。
その証拠に下家の烈香の染め手にもほとんど無警戒で急所牌を打ち出す。鳴かれる。
だがアガりはシャガの方が一歩速い。
雨宮も己の太いツキに裏切られることのない稀有な人間のひとりであったから、その打ち筋に自分に近いものをいち早く察知していた。
だからこそ、その終わりもわかってしまった。彼女よりも速く。
「リーチ――」
綺麗な所作で打ち出されたシャガのリーチ牌、一萬を討ち取ったのは、
「ロン」
烈香だった。
一萬と北のシャンポン待ち。点棒を笑顔で払うシスター。
だが、その一萬は烈香のみに当たっていたのではない。
頭ハネであるがゆえに、手牌を倒すことなく伏せて壊したのは二人。
一四萬待ちのさくみ、一四七待ちのシマ。
この三人ほど冷静な相手でなければ、三家和で流れたかもしれない局――。
いつの間に取り出したのか、雨宮はハイライトの煙を上手そうに吸い――その煙越しに青ざめたシスターの顔を覗いた。
夏だというのに、五人をさらう風は、冷ややかだった。
シャガは慎重だった。
牌運が一気に衰えたのだろう、序盤から脂っこい数牌を叩き落してベタオリの姿勢。
牌効率や敵手推理よりもアガれる局かそうでない局かによって判断を下すシャガは気に食わない局は容赦なく捨て去る。
そうしてまた太いツキの流れはニコニコして彼女を甘やかす――
――今日までは。
「ロン」
またも手を倒したのは烈香。親番で打点も大きい。まだ三順だった。
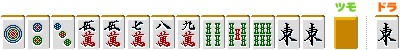
「三色通貫――」
「あんだと?」
雨宮の発した素っ頓狂な声がなぜかシマにウケた。げらげら笑い転げるシマの背中を容赦なく張り叩く。
「あいった! 何すんの!」
「うるせえ笑い声が頭に響くんだ。おいなんだよ三色通貫だと?」
「古役をちょっとだけ採用してるんだ――赤ドラの代わりに。烈火の提案でさ」
シマに指を指された烈香はぷいっと顔をそむけた。
採用されている古役は――
ツバメ返し(リーチ宣言牌で和了。一翻。面前役)
三色通貫(二翻、食い下がり一翻)
三連刻(二翻、面前)
二暗刻(一翻、面前)
双竜争珠、双竜闘蛇、双竜戯鳳(三翻、食い下がりなし)
一筒ラオユエ(一翻)
五筒カイホウ(一翻)
雪(白単騎)(一翻)
紅孔雀(役満)
大車輪(役満)
百万石(合計数百のみ)(役満)
「三色一通が二翻か。一翻でいいんじゃないか? あんまし綺麗じゃないもんな」
雨宮の問いかけに烈香はぶすっと答えた。
「一通、三色は九枚使いで二翻。三暗刻も。だから同じ九枚使いのサンツーが二翻で何が悪い――」
麻雀オタクらしい小ざかしい答えだ、雨宮は毒づいた。
「へっ。二暗刻はイーペーコーと同じ六枚使い、ツバメが面前なのも一発裏ドラのようなボーナス役として考えれば追加してもさほど問題ない――って考えてんだろ」
「うるさい、そうだよ。悪いか。やってみたかったんだ」
そりゃあこれだけわけの分からん古役が混ざった麻雀なんぞ、賭けでやりたがる物好きは金持ちだけだろう。しかもこのご時勢に地味な赤ドラ抜きときた。
雨宮はあきれたような尊敬したような、不思議な気持ちになった。
「赤ドラなんて無粋だ――」烈香は繰り返す。
「どうして赤五筒を役扱いさえするところがあるのに、古役がダメなんだろう」
「知るもんか、流行らんからだ」
「あはは、烈香はホントに麻雀が好きなんだね」
シマのやり方は烈香を黙らせるのに最高級の手段だった。
「あんだと?」
雨宮の発した素っ頓狂な声がなぜかシマにウケた。げらげら笑い転げるシマの背中を容赦なく張り叩く。
「あいった! 何すんの!」
「うるせえ笑い声が頭に響くんだ。おいなんだよ三色通貫だと?」
「古役をちょっとだけ採用してるんだ――赤ドラの代わりに。烈火の提案でさ」
シマに指を指された烈香はぷいっと顔をそむけた。
採用されている古役は――
ツバメ返し(リーチ宣言牌で和了。一翻。面前役)
三色通貫(二翻、食い下がり一翻)
三連刻(二翻、面前)
二暗刻(一翻、面前)
双竜争珠、双竜闘蛇、双竜戯鳳(三翻、食い下がりなし)
一筒ラオユエ(一翻)
五筒カイホウ(一翻)
雪(白単騎)(一翻)
紅孔雀(役満)
大車輪(役満)
百万石(合計数百のみ)(役満)
「三色一通が二翻か。一翻でいいんじゃないか? あんまし綺麗じゃないもんな」
雨宮の問いかけに烈香はぶすっと答えた。
「一通、三色は九枚使いで二翻。三暗刻も。だから同じ九枚使いのサンツーが二翻で何が悪い――」
麻雀オタクらしい小ざかしい答えだ、雨宮は毒づいた。
「へっ。二暗刻はイーペーコーと同じ六枚使い、ツバメが面前なのも一発裏ドラのようなボーナス役として考えれば追加してもさほど問題ない――って考えてんだろ」
「うるさい、そうだよ。悪いか。やってみたかったんだ」
そりゃあこれだけわけの分からん古役が混ざった麻雀なんぞ、賭けでやりたがる物好きは金持ちだけだろう。しかもこのご時勢に地味な赤ドラ抜きときた。
雨宮はあきれたような尊敬したような、不思議な気持ちになった。
「赤ドラなんて無粋だ――」烈香は繰り返す。
「どうして赤五筒を役扱いさえするところがあるのに、古役がダメなんだろう」
「知るもんか、流行らんからだ」
「あはは、烈香はホントに麻雀が好きなんだね」
シマのやり方は烈香を黙らせるのに最高級の手段だった。

