リボルヴァ⇔エフェクト>
<ブラック⇔エフェクト>
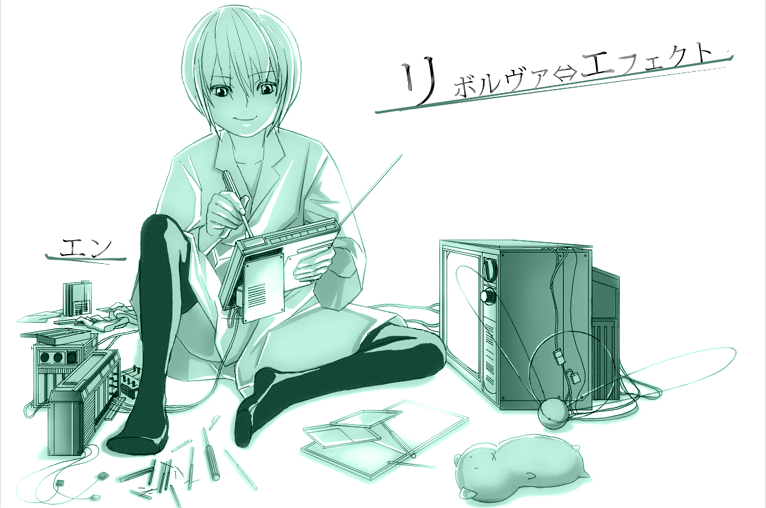
「一発でいいから! 一発で受精してみせるから!」
「おまえマジで死んでくんねェ? ドン引きなんですよ正直言って」
袖振り合うも他生の縁、ましてや我々は平行世界のパラレル・キャラクターであるにも関わらずクロは、ぼくに対してとても冷たい。それはもうひどいもので、口で済むなら良い方で、機嫌が悪いと髪を引っ張ってきたりスネを蹴ってきたりする。底抜けに機嫌が悪いと、ぼくを羽交い絞めにして、脇と首をあの繊細な指先でくすぐってくる。おいそこ、なにをクスクスしてるんだ。冗談事じゃない。くすぐりは立派な拷問なのだ。人間は暗闇のなかで額に長時間水滴を落とされただけで発狂してしまうのである。最近、ぼくの奇行が目立つようになってきたのはこの拷問のせいであるとぼくは睨んでいる。
ぼくは男女の区別なんて気にしないから、クロの非道の数々に対して、女の子だからどうこう、なんて言うつもりはない。ボディタッチおおいに結構である。減るものじゃないし。若い身体を道徳で縛りつけて持て余す方が、性欲をお与えになった造物主に対する反逆である。したい? しろ。それでいいじゃん、せっかく誰も見ていない満天の星空の下で五人も六人も紳士淑女が集まっているのだからヤッちまえばいいのだ。<向こう>でやったら即通報だけれど、ここでなら誰が困る? なにをしてよくて、なにがそうでないか、ここで決めるのは他ならぬ我々である。
この点に関して、クロはぼくと同意見のはずだ。彼がこっそり民家に忍び込んで即席の漫画喫茶として利用していることをぼくは知っているし、時々一緒に読みにいく。なのに彼は一向にぼくと性交してくれない。
もし二人の間に子どもができたら、それは時間と空間と運命のなかで、どんな性質を帯びて生まれる子なのだろう? ぼくはそれが気になって仕方ないのに、クロもカツミも聡志もリカもマナもわかってくれない。
天才はつらいよ。
○
今日もぼくとクロは漫画を読みに子どものいそうで金回りのよさそうな民家を探して街をうろつく。
子どもっぽく見られるのは本意ではないので少し補足しておこう。ぼくの楽しみは漫画だけではない。住居侵入は、その住民の性格や性質を探りながらやると格段に面白いものだ。男子高校生の部屋のベッド下を漁ってエロ本の代わりに少女漫画がドサッと転がり出てきたときは、これを発見した母上の心境を慮ると湧き起こる興奮を隠せなかったし、ふりふりピンクのレースのカーテンに閉ざされた女子生徒の勉強机でグフカスタムがガトリングシールドを蛍光灯めがけて構えていたときは感動した。ぜひ住人に握手を求めたかったけれど、いくら待っても不法侵入者を追い立てる家主の姿が現れることはなかった。
けれど、最近、どうも傷が目立つ。
クロはまったく気づいていない。彼は自分が興味関心を抱かないものは、まさしく眼中にないと語るに相応しいほどの無関心さを示す。だから、旅の途中でぼくたちが忍びこんだ住居のなかで、何軒も同じ構造の住宅があったことにも気づいていない。少女漫画好きの男子生徒の家はいままで三軒あったし、ガトリングシールドこそ武器と防具の完全なる融合であると信じているであろう女子生徒の家は五軒あった。
ぼくの知らないところで、あるいはこの世界で人間が消失する前に、そういうブームがあったのかもしれない。この世界では当然のことで、異世界からの来訪者であるぼくらの感性がずれているのかもしれない。
けれど、少女漫画はどのベッド下でもすべて同じ漫画が並んでおり、買い忘れたのか貸しているのか、欠けている巻まで同じだった。グフカスタムは机からひっかけて落としたのか、肩にひっかいたような傷があったのだけれど、それまで寸分違わず、五体のグフカスタムは同じだった。ぼくを疑わないでもらいたい、こう見えて記憶には自信がある方だ。
そして、いま、ぼくはまたべつの誰かの部屋にいる。
この部屋はシンプルで、パイプ椅子にパイプ机は買ってきたばかりのように真新しい。部屋の端には下駄箱みたいなプラスチックの洋服ケースが置かれている。ジャンルがバラバラの雑誌が突っ込まれたスチールラックの横の壁に一枚、J-POPのポスターが言い訳のように貼られている。殺風景な部屋だった。
クロはこの部屋を見た途端、「はずれ」と言って出て行ってしまった。彼のお目当ての漫画はこの部屋にはない。けれどぼくは、そこに留まった。ソックス越しでさえフローリングの床が冷たく感じるのは、この部屋に生活感がなく、ぼくが潜在的に恐怖を覚えているからだろうか。
誰かに見られている、気がした。
ベランダに続くガラス戸は閉じられて、無地のカーテンがわきにくくられている。外には誰もいない。パイプ机の上の窓からは銭湯の煙突が見えた。煙は出ていない。視力2.0のぼくの両眼は、その視界のどこにも人の姿がないことを確かめた。
けれど、ぼくが流しているこの汗は、暑いからでも疲れたからでもない。いやな汗だ。逃げ出したい。
逃げ出してしまえば、ラクなんだけれど。
ぼくは、黒いプラスチックケースの前に膝をついた。生唾を飲み込む。そろそろと壊れ物でも扱うように手を伸ばした。指が何度もケースのくぼみをひっかけ損ねて空を切った。動揺している。なのにわくわくしている自分がいた。
開けた。
なにもなかった。
底さえ、なかった。
○
ケースのなかには、真っ黒い闇が詰まっていた。なにかの生き物の口みたいだ。どこかへ通じている。開けたとき、空気が動いたのを感じた。
手を入れようとして、引っ込めた。念には念を、自分大事に。白衣のポケットからボールペンを取り出し、闇のなかに転がり落とした。
ボールペンは闇に落ちていき、耳をいくら澄ませても、底を叩く音が返ってくることはなかった。
限界だった。我ながら、口ほどにもないチャチな神経だと思う。
ぼくは逃げ出した。
家を飛び出して、まだ道の先をうろついているクロの背中に向かって駆け出した。いまほどあの背中が大きく見えたことはない。ぼくは大声で叫んだ。
「クロっ!」
ぼくが首根っこに飛びつくと、そのまま白衣の背中を掴まれて、アスファルトの上に叩きつけられた。勢いのわりには、衝撃は身体を通して虚空へ柔らかく散っていった。
青空を背景に、
クロの顔が、
「暑いんだよ。さわんな、バカ」
その途端、恐怖も焦燥も嘘みたいに消えていった。ぼくがそのとき、どんな表情を浮かべていたかはわからないけれど、どうもへんな顔をしていたらしい。クロが訝しそうに眉根を寄せた。いつもこれだ。粗暴に振る舞って、その後で心配そうにする。そんな生き方じゃ後悔ばかりしてきただろうに。不器用なヤツだ。
きっと、ぼくもそうなんだろう。
「おい、なんだよ。痛かったのか? 嘘だろ?」
「――心配、してくれるのかい? やさしいね」
「うるせえ。とっとと立てよ。めんどいから泣くなよ」
クロは歯をむき出しにして不機嫌さを顔中で表して、コツコツとローファーを道に踏みつけて歩いていく。助け起こしてくれさえしない。
ぼくはその場に座り込んだまま、その背中にいま起きたことを告げようかと思った。喉元まで、でかかった。
でも、やめた。
この世界がどうなっていて、どんな存在なのか。
ぼくは、それを求めるためにここにいる気がするから。
それに、どうせクロはなにを言っても興味がないことはあの耳を素通りするだけだし。
だったら、秘密はぼくの胸の中にだけ、あればいい。
そう思った。
ぼくは立ち上がって白衣についた汚れを振り払って、クロを追いかけた。やるべきことも知りたいことも、ぼくにはたくさんある。
立ち止まってなんかいられない。
今日こそはクロに、一年越しになるだろう実験の助手になってもらうのだ。
なにもわからないし、どうなるかもわからない。
でも、そんなに不幸だとは思わない。
少なくとも、この不思議なヤツに出会えたことが不幸だというなら、
ぼくは、不幸で結構だ。

