【星辰麻雀】
03.指を亡くして
清水京護は山の手線に乗っていた。
満員というほどでもないが、五時を過ぎ、日も暮れた宵の初め、周囲には気だるい不満と疲労の気配が立ち込めている。
しかし、閉じたドアにもたれかかった清水の側に近づく一般人はいない。
誰もが焦点をずらした目で、この薄汚れた、真っ青なスーツを着た金髪の男を見るともなく観察している。
一般常識の一覧には、金髪で裏商売風の格好をした唇とこめかみに喧嘩傷のある男と係わり合いになってはいけないという項目があるのだろう。
清水の周りのエア・ポケットに縮まる様子はない。
おまけに鼻ピアスとあっては、優先席に座る老婦人がじっと目を瞑ってうろ覚えのお経を唱えるのも無理はないというものだ。
清水は思う。
あの打、五萬は間違いではなかったと。
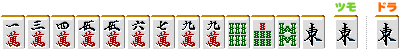
一三四五五六七九九678東東 ドラ:東
ピンク産業の顔役たちの、代打ちだった。
数年前、美境遠子という声優がいた。清水はテレビもサブカルチャーも断絶したところで寝起きする身だったので、よくはしらないが、なんでも有名なアニメに出ていたことでブレイクし、アイドルに転身したのだとか。
彼女のファンは金を湯水のように、CD、DVD、イベントなどに惜しげなく次ぎこみ、彼女の口座はゴクゴクとその金の雫を飲み込んだ。
大抵、トラブルはおとなしくしていればいいのに、それができなくて起こるものだ。
若手の芸人との熱愛報道、テレビでの暴言。遠子の声が作り上げた儚いイメージは脆くも崩れ去った。
元々、出演作が名作であったことが後押しになったというだけで、珍しい声質でもなく、遠子にしかできないと言われた声のポジションは同僚たちに掻っ攫われ、あとには雑草一本分の仕事も残らなかった。
その彼女がAVデビュー。
声を売る仕事に、いろいろオプションをつける気になったらしい。
かつての栄光の足元に及ばないにしても、一度掴んだ金の匂いはなかなか手から抜けきらない。
どの顔役が美境遠子を仕切るか。
それを決める、麻雀だった。
割れ東の東三局――
一萬を切ればテンパイなんてことは知っていた。
だが、九萬とドラ東のシャンポンでどこから出るというのだ?
ツモればいい。
なるほどそうかもしれない。幸いどちらもションパイだ。ひょっこりツモっておいしいね。
クソ喰らえ。
そんな夢と希望に満ちている運があるなら、誰もこんなところまで堕ちてきやしないのだ。
清水以外の代打ちたちは、皆一様に顔色が悪く、勝負前に覚せい剤を注射して、なんとか動くといった風のボロクズもいいところだった。
限界なんてスタートラインの後方五十メートルに引かれていて、逃げ場なんてどこにもない。
負ければ終わる。
勝てない代打ちは、終わったコンテンツなのだ。
だから、清水は、たったひとりヒロポンを打たなかった清水は、打五萬のテンパイ取らずに受けたのだ。
誇りを持って打った一打だった。
ここで一萬切りリーチを打つくらいなら、指を落とされる方がいい。
そう思った。
五萬切りのあと、すぐに九萬が下家から出た。
清水の頬筋はぴくりとも動かなかった。
次順、絶好の八萬ツモ。打、九萬。
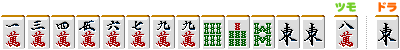
一三四五六七八九678東東 ドラ:東
勝利の美酒は、もうすぐそこに、たゆたっていた。
「リーチ」
一瞬の隙もない完璧なリーチ。二萬は一巡前の五萬のひっかけ。
一発で出ることさえある。上家の割れ目から出れば、打点は倍増。
いまにも血を吐いて死にそうな、四十過ぎの上家は、先制できなかった割れ目の常として、重苦しいため息を吐きながらツモった。
その牌を見て、泣きそうな顔になる。だが、誰も助けてはくれない。
京護は、無表情を崩さずに、鼻ピアスの感触を楽しむフリをして、全神経を上家のおやじに流し込んでいた。
頼む。
振ってくれ。
「わかったよ」
おやじが、ぼそっと呟いた。
「そんなに、おれを殺してえっていうんならな……」
そして手牌の中から一枚引っこ抜いて、真上から卓に叩きつけた。
東。
「リーチっ……!」
おやじの放ったリー棒が、笑うようにちゃららと転がる。
清水に、なすすべは、なかった。
おれは間違っていない。
敗北し、顔役にたっぷり痛めつけられ、小指を切断されるその間際も、清水はそう呟き続けた。
指は、こんなこともあろうかと、詰め物いりの手袋を用意していたので乗客にはわからないだろう。
そんな負けたときの用意なんてしていたから、負けたのかもしれない……夜の街を透かして見える自分のやつれた顔を見ながら、清水は思った。
だが、まだ死んだわけじゃない。
暗い倉庫で、死体のように長く這った清水に声をかけたのは、割れ目の清水から純チャン三色をアガって吹っ飛ばした、あのおやじだった。
「にいさん、悪かったな」
おやじは心底、気の毒そうには見えた。
「おれがアガって、にいさんの手が誤って手牌を倒したとき――おれは震えたよ。二萬があったら、迷わず捨てて、振ってただろう」
「……り前だ」
ぺっと血の混じったタンを吐くと、いくらかしゃべりやすくなった。
「出るようにして打ったリーチだ。それが、帳簿の赤黒しか見えねえやつらには、わからねえんだ」
「その通りだ、本当に」
生徒に自身の将来を嘆かれた教師のように、おやじはウンウン頷いた。
「長いこと打ってきたが、おれも今日で引退だ。今日の収益で、ヒロポン中毒のこの身体が動かなくなるまでは、どうにか暮らしていけるだろうから」
「そいつァよかったな。いますぐ金を抱いたまま、このおれの目の前でくたばってくれれば、あの手牌の見物代ぐらいにはなるだろう」
「残念ながら金はくれてやれない。だが、働き口を紹介してやる」
「働き口だと? いまさら――」
這いつくばった清水の顔の前に、にゅっと二枚の写真が突き出された。
「こいつ――」
清水の目は、太陽を一度も浴びたことがないような白い肌をした美少年に釘付けになった。
「おまえも知ってるだろう。雨宮秀一。ただの学生のこいつに、もう何人もスクラップにされちまった」
「おれも、一度、やられたことがある」
今夜は本当にヤな晩だ、と清水は思った。
あの、卓に座っているだけで運を吸い取られるのがじかにわかった麻雀を思い出させられるなんて。
あれは、もう勝負じゃなかった。
搾取だ。
「おれは雨宮とは打たない。もし、やつを倒して金を稼げなんて夢物語を言うつもりならな」
だが、おやじが放った一言は、清水の想像の範疇を超えていた。
「雨宮がやられた」
「――まったく冗談きついぜ。ひょっとしてこいつにか? このもう一枚目の、なんだ、この冴えない面は」
生徒手帳に貼られているものを拡大したのだろう、その写真の少年は学ランを着ているというより、学ランに支配されているといった方がよさそうな、覇気のない顔を清水にさらしていた。
輝くような笑顔の雨宮と比べると、まさに勝ち組と負け組の規範だ。
「名前は、馬場天馬。雨宮の幼馴染だったそうだ」
「ババ――」
とても信じられない。
この根暗そうで、反抗的な目つきをした陰険小僧が雨宮を。
「雨宮が倒されたのはだいぶ前だ……でも、あんた、ピンク産業の代打ちとして飼われてから、GGSはご無沙汰だったんだろう?」
「相手を探す必要も、なくなったからな」
「GGSじゃ、雨宮がやられたあとは、この話題で持ちきりだったんだぜ。巨星墜つってな」
まるで自分の自慢話のようにおやじはフンと鼻を鳴らした。
それこそ馬場天馬とかいうガキをそのまま中年にしたような男がパソコンに向かっている姿を想像すると、なんともばからしいというか、シュールだ。
「この馬場という少年には、いま、GGSから賞金がかけられている。倒せば、おまえもやり直せる。これが、おれのおまえの麻雀に対する、せめてもの餞だ」
――なにが餞だ、クズ野郎。
ポケットの中の写真を、傷ついていない方の手でぐしゃぐしゃに握りつぶす。
すぐに、本物の顔もそうしてやらなければならない。
そのためには、仲間がいる。
無一文になった後は、環状線に乗って考えをまとめる――いつものジンクスを終え、清水は電車を降りた。

