『雨ノ雀――廃校舎の怪麻雀』
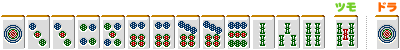
「廃校舎の……大ガモ?」
生徒会室でざるそばをすすりながら、雨宮秀一は聞き返した。
すぼめた口から冷麺が垂れ下がっている。
無論、昼休みに出前を取るなど校則違反甚だしいのだが、この男にそんな言葉は失われている。
革張りの椅子に座って眠りこけていた白垣真は隅の方にどけられて、そこには一人の少女が新たな主となっている。
組んだ足を机に乗せて、「生徒会長」と記された三角錐が蹴られて落ちた。
突然の君臨者――十六夜烈香は相変わらず涼しそうな軽装で、凛とした表情を浮かべ、雨宮の答えを待っている。
まだ子どもっぽさを残す顔は、やや目元がきつめに吊り上がっているため、どこか背伸びしたような愛らしさがある。
雨宮は片腕でざるそばをすすりながら、
「野生動物の異常繁殖は用務員のジジイに頼むべき仕事であって、一生徒にすぎない俺に言うことじゃない」
「誰が廃校舎がジャングルになってため池に化けガモが出たなんて話したんだよ。獲物だよ、え、も、の」
雨宮はけだるさをため息にして吐き出した。
首を残念そうに振り、
「俺はね、嫌いなものがいくつかある。麻雀を打つときに『ぶつ』って発音するくせに点数計算ができないやつと、ジャン卓のある友達んちを『雀荘』って呼ぶやつと、獲物だのカモだの言っておきながら言ってみれば小遣い銭しか持ってないやつのところに案内するやつだ。いまんとこ、おまえはすべてに該当する気がするけど俺の気のせいか?」
「気のせいだよ」
残念なことに雨宮の長口舌はすべて無駄になった。
烈香は足首をくいくいと動かして、
「あんた友達いないのか? もう下じゃ噂になってて、何人かの麻雀打ち――たしか進藤とかなんとか――が何回か狩りに出て、結構稼いでるらしいけど?」
夢いっぱいな話だろ、といわんばかりに烈香は顔を輝かせていたが、雨宮は気味悪そうに、「ざるそばとこいつの話は食い合わせが悪い」と言いたげに、回転椅子を滑らせて烈香からちょっと遠のいた。
狩り? 学生麻雀が?
中二病患者につける薬はないものか。
烈香はじれったそうにバタバタと踵を机に打ちつけ始めた。
授業中でなければ他の生徒会役員どもに叱咤されているところだ。
「と、に、か、く! おまえはあたしのオヒキ(手下、子分のこと)として、今晩打ちにいくの。いい?」
「いい、じゃねーよ。俺をどっかのヘタレと一緒にするなよ」
ちゅるん、とそばが露を跳ね散らかしながら雨宮の薄い唇に吸い込まれる。
たとえざるそばを食っているだけでもどこからともなく神聖さの加湿器が稼動してオーラを撒き散らし、結局は絵になる男なのだ。
欠片ほども取り合ってくれない雨宮に烈香は憮然とした表情を作って見せるが、雨宮の無関心さは崩れそうにない。
ざるそばを食い終わり次第、教室に逃げ込む算段だろう。
そうされてしまえば不法入校者の烈香は追跡できない。
「待ちなさいよ!」と教室のドアをバターンと開け放って周囲の空気を凍りつかせた後に通報されてお縄になるのも味なものかもしれないが、烈香はこれでも麻雀以外では一切の罪を犯していないつもりなので、こんなくだらないことで留置場にブチこまれるのは、彼女の玄人精神からすると許されざることである。
むむむ、と怒りと侮蔑と懇願を視線に梱包して送り続けるが効果なし。雨宮はおいしそうにそばをもぐもぐするばかりだ。
烈香は、一際大きく踵を生徒会会長卓にたたきつけた。
「そ。じゃあいいよ。あんたの気持ちはわかったよ、雨宮」
「わかってくれたか」雨宮はうんうんと頷いて両手を合わせた。「お祓いしとくからもう来るなよ」
「ものすごく腹立つ……。そーですよね、人気者の雨宮くんたら忙しくって麻雀なんか打てませんよねえ?」
「当たり前だ」
「帰宅部で、彼女もいなくて、学校と家の往復くらいしかやることのない雨宮くんたらさぞ忙しいんでしょう?」
「…………は?」
「いろいろあってから何もかもが面倒になっちゃった雨宮くんたら、ぶっちゃけ、うっすい人間関係とお山の猿大将ごっこにうんざりしちゃって、エンドレス五月病に囚われてるんですって? 忙しいことですわねえ」
しなを作って「およよよ」と袖で目元を拭う烈香の気持ち悪さもさることながら、なかなか痛いところを突かれて雨宮はぐっと言葉に詰まった。
確かに、自分は飽きている。
満たされていることに、飽きている。
だから自分からいろんなものにさよならして、またやる気が出るまでゆっくり過ごそうと思っていたのだが――
「それって」烈香が嗜虐感たっぷりの笑顔で、「準ひきこもりって感じだよねぇ?」
「ぐっ……」
「やだやだ、よくいるんだよねぇ、昔はよかったのに、とか、俺だって本気を出せば、とか終わってるくせにさ? ほざいちゃうヒト。雨宮もそーゆータイプだったんだ?」
「うぐぐ……」
一言一言に必殺の棘が絡みついている。雨宮はぐさぐさと切り傷だらけになっていく。心が。
こいつってこんなやつだったっけ? という思いがよぎるが、ヒトは成長するもの、確かに最近の自分はたるんでいると言えなくもなくて――
「老いた獅子の行く末は、餓死、ってね。」
がちゃん、と雨宮は空になった椀を置いた。残った右腕でぐしゃぐしゃと髪をかきむしる。
どうやら形勢不利らしい。
ならば流れを淀めることもない。
「わかったよ」
どうせ千点百円なんだろうなあ、と憂愁に煙る灰色の日差しを浴びながら、
「今晩だけは、おまえの下についてやろう」
「うんうん。最初からそういえばよかったのにさ。焦らしちゃって、メンドくさいやつ」
「おまえなあ……」
「じゃ、夕方に廃校舎で。作戦なんて造らなくってもどうせ勝てる相手だからさ、気楽に愉快にブッ潰そうぜ!」
とびきりの笑顔を残し、左手をひらひらと振って烈香は颯爽と出て行った。麻雀以外の話はする気が無いし興味も無いとばかりに。
今頃になってもぞもぞ目覚める気配を見せ始めた生徒会長を爪先で転がしながら、雨宮秀一は、ひとつ大きなあくびをこぼした。
世の中には廃墟愛好家というものがあって、雨宮たちの通う学園にある廃校舎もその筋では有名なスポットのひとつだった。
グーグル先生で廃墟、学校と検索すれば三十分とかからず無機質なイニシャルと無断で撮影されたモノクロ写真つきで紹介されているページに出くわすはずである。
そんなものは取り壊してしまえばよさそうなものだが、金持ちに道楽好きが多いのは世の常か、壊さないでくれと学園側に菓子折りを届ける輩がいるらしく(そしてその中身は食べられないものであって)、学校側もチェーンと立ち入り禁止の張り紙だけで済ませているだけで実質誰でも忍び込める。
だから怪談話やいじめの温床になることも多く、久々に夕暮れに染まる廃校舎前に立った雨宮は、短い時の流れの儚さをかみ締めるのであった。
この世の中、数秒先に何が起こるかわからない。役なしドラ3に振り込んでしまうように、読みもセオリーも、時には無力で、どれほどの力や幸福を溜め込んでも、それはただ刹那に映った陽炎だ。
空っぽの下駄履きに、十六夜烈香が腕を組んでもたれかかっていた。
一瞬、そこにいるのに存在感が不思議となくって見逃してしまいそうになる。けれど麻雀打ちとしては存在感が薄いというのも、便利といえばそうかもしれない。
「よう、おまた」
「なに、そのおっさんくさい言い回し?」
烈香が嫌そうな顔をする。女の子ならおじさんと言え、と雨宮は心の中で厳しくダメ出ししたが、仮に口に出しても十六夜烈香には無意味だったろう。
「準備はいい? じゃあ、いくけど」
「うむ」
ホコリとカビの臭いが充満する木製のトンネルを、烈香と共に進んでいく。
灯りが必要な暗さではないが、青い闇が一歩進むごとに深まっていく。
海の中を縦に降りていくように。
深く、深く、もう帰ってこれないほどに……。
烈香が立ち止まり、雨宮も足をとめた。
「ここだよ」と烈香が光で照らした先には、「宿直室」と書かれたプレート。
なるほど、確かに宿直室ならちょっとした畳敷きの座敷があって、麻雀にはちょうどいいだろう。
烈香が戸口に手をかける。
ふと雨宮の背筋を冷たい悪寒が走った。が、彼は強いて烈香にそれを告げることも、その手を止めることもしなかった。
不思議な気持ちだった。振り込むとわかっていながら牌を切ってしまうような、そんな不思議な、倒錯情動。
ガラリ、と烈香は戸を開けて中に入る。雨宮も続いた。
想像した通りの宿直室の畳の上に、ひとりの男がジャン卓に両肘をつけて、入ってきた二人のことを見上げている。
雨宮と同じ、黒い学生服を着た男だ。
どんよりと濁った目とその下にびっしりと染み付いたクマは、不健康そのもので、ただいま徹マン強行軍中と言われても不思議ではないが、他の面子の姿はない。
男は蓬髪をぐりぐりと指で絡め取りながら、烈香と雨宮を交互に見る。
「こんばんは」
咄嗟に、烈香も雨宮も言葉を返せなかった。ややあって、
「こ、こんばんは」
と引きつった笑みを浮かべて烈香が頷く。
男を騙せる笑顔じゃないな、と雨宮は思った。そのすぐ下に相手への嫌悪を無意識のうちに伝えてしまう笑顔は、女としては二流のシロモノだ。
あの嶋あやめなら、裏も表もなく笑って見せるのだろうが。
男に勧められるままに、烈香と雨宮はジャン卓へ腰かけた。
「えと……」と烈香が言葉に詰まり、あろうことか雨宮へ助けを求めるような視線を向けてきた。
冗談じゃない、と手を振ってやる。なぜ俺がこんな下賎な下男と下らない挨拶と段取りをしなくてはならないのだ。
そんなことは言いだしっぺのおまえがやることだろ、烈香、と睨んでやるが彼女は俯いてしまう。
(こいつ、ひょっとして……いままでギャンブルの舞台を整えるのは白垣に任せきりで、その下ごしらえをするのがまだ苦手なのか? ていうか、ひょっとして男がちょっと苦手だったりすんのか?)
おいおい大丈夫かよ、SSSランク麻雀打ったのホントにおまえか? などと雨宮はクドクドとお説教してやりたくなったが、まあ確かに二人と二等辺三角形を描く位置に座る男は、陰気で覇気がなく、とても心地よい関係を築けるとは思いがたい風格ではあったが。
男が黙りこくる二人に眉をひそめはじめたので、仕方なく雨宮はため息をつき、
「ここで面白い麻雀が打てるってんでね。こいつと遊びにきたんだ……えと、先輩かな?」
雨宮は振り返って、靴置きに目をやったが、男の上履きは見当たらなかった。本来ならそこに走るラインの色で、学年がわかるのだが。
男はぽりぽりとつむじを長く伸びた爪でひっかいて、
「ああ……三年の寺門だ。噂を聞いてここに来たのかな……いくらか高いレートで、あんたらのお好みのルールで打つ……一応、あんたたちの名前は?」
「へっ?」と烈香が素っ頓狂な声を出し、雨宮を見やる。
(ここの生徒じゃないってバレたらどうしよう)という顔だ。
雨宮はギロリと烈香を睨んでから、万人に親しまれやすい無敵の笑顔を寺門に向けて、
「ああ、俺は二年の雨宮。こっちもそう、ええと、馬場烈香」
「な、ちょっ……!」
またギロリ。
(十六夜なんて妙な名字、あとあと調べられても困る。馬場って名字なら、この学校には生徒で十三人、教師で二人いるからカモフラージュもいくらか効くだろ……恥ずかしがってんじゃねえタコ。カモる方がテンパっててどうすんだ?)
まったく、今の烈香の様子は大自然に解き放たれた動物園の豹のようだ。純粋培養されていた分、品があるが柔らかさと獰猛さに欠ける。それでは本物のハイエナたちに取り囲まれて終わりである。
「よし、じゃ、ルールの話といこうか。馬場?」
「……。あっ。そうそう、三人しかいないから、サンマ(三人麻雀)にしたいんですけど、いいですか、寺門先輩」
「いいよ」
即答だった。雨宮は、ふうん、と寺門に流し目を送る。これが女性に向けられていたら狙いを定めているのかと思われるところだろうが、あいにくといまの彼はいくらか戦士であって、市民ではない。
この寺門という男、腕に相当の自信があるのか、それともただの馬鹿か。
「サンマは、萬子の二から四、六から八までを抜く。一萬、五萬、九萬、北はガリ(抜きドラ)だ。抜いたら王牌から一枚持ってこれるのは知ってるよな? ドラは開門から十一枚目をめくる。点数計算はバンバンつきの一点、二点のあれ。チャンタは五点、純チャンタは十点。役満は五十点。ダブルは二百点。トリプルは千点。親は一点、連荘分は一点ずつ加算。チーなし。オーケイ?」
「何度かやってる」寺門の表情は変わらない。
「そいつは結構。いい打ち手と打てそうで俺も嬉しい。烈香から何かあるか?」
ふるふると烈香は首を振る。まるきり借りてきた猫状態だ。
ただ、その顔つきのすぐ裏に、麻雀打ちとしての若干の疑問符が浮かんでいることも雨宮にはすぐわかった。
そしてその回答は、卓の中で出すつもりだ。
ガラガラと寺門が牌をかき混ぜる。三人はそれぞれ引いて、位置についた。
起家、雨宮。南家、寺門。西家、烈香。
みんなが牌山を積んだところで、
「一点はおいくらかな?」
と雨宮はわざとらしく問いただした。雨宮はレートは烈香に任せるつもりだったので、視線を送る。
どうせ小金なので、いくらだろうと関係ない。
水を向けられた烈香はスッとそれまでの狼狽ぶりを消して、
「一万円」
ととんでもないことを言い出した。雨宮も思わず笑った。学生にそんな金があるものか。二五〇万円から始まる麻雀なんかバブル期のマンションクラスだ。
寺門はこけた頬をひと撫でして、
「一万か……」と苦しげな声を出した。
「ハハハ、先輩、じれったいマネはよそうぜ。そんな金持ってないだろ」
ところが、寺門は、「いや……」と意味深な呟きを残して背を向け、なにやら隅の方に転がっていたダンボール箱をごそごそし始めた。烈香と雨宮は顔を見合わせる。
「一万円札は十枚しかないが……こいつを担保にしてくれるなら、いいよ」
といって、ダンボール箱をジャン卓の真ん中にどんと置いた。
烈香と雨宮が額を揃えて覗き込むと、中には、金色に輝く板が折り重なって入っていた。
金ののべ棒。
ごくり、と烈香が生唾を飲み込み、雨宮の身体からは敵意が噴出した。
何かおかしい。
そんなことはわかっている。
「おい」
上級生に向けるとは思えないドスの効いた声音で、
「こいつはどういう冗談だ」
「冗談? 本物だが」
寺門は澄ましている。突然、その胸倉を雨宮は掴み、烈香が慌てふためく。
「学生がこんなアホみたいなモンもって麻雀するわけないだろ。てめえ常識あんのか? これはなんだ、演劇部から借りてきたのか? おい、この俺をなめると表も裏も出歩けないようにしてやるぜ」
「あ、雨宮、カ……寺門先輩から手ぇ離しなよ! 失礼だよ!」
カモといいかけたくせに、と内心で呟き、雨宮は取り合わない。
寺門は自分の運命にさえ興味がないといった口調で、
「これは裏山で見つけたんだ……徳川幕府の埋蔵金さ」
「どうやら指をツメられたいらしいな。いいぜ、血を見るのは嫌いじゃない」
「べつにそうしてもらっても構わんが……君らは麻雀しにきたんじゃないのか? だったら麻雀をしよう……もしこの金ピカがニセモノだったら、ちゃんと代わりのものを払うよ……本物だがね、繰り返すけど」
「いちいちカンに触るやつだ……だが、ま、いいか。麻雀しようか」
急にそれまでの怒気を蒸発させた雨宮は無表情になって、ダンボールをジャン卓からぽいっとどけた。
「ふん。北家がいないが、出目はヨンマと同じ風でいいかい?」
「ああ」
「じゃ、自五で俺の山から取り始めるぜ」
スッスッと何事もなかったかのように配牌を取り始めた男たちに烈香はしばし呆然としていたが、自分の手牌が完成する頃には、冷めた鉄ような雰囲気を回復させていた。『殺人麻雀』の名は伊達ではない、というところか。
自分の手牌をゴミでも見るような目つきで眺めながら、寺門が言う。
「君たちは俺の支払いを心配しているようだが……それはこっちのセリフでもあるんだぜ。俺は必ず払ってもらう……忘れないでくれよ」
「ああ」
「うん」
雨宮も烈香も、第一打牌する前に、そんなセリフは忘れてしまった。
サンマは、萬子がないためにヨンマよりも派手な手ができやすい。
生徒会室でざるそばをすすりながら、雨宮秀一は聞き返した。
すぼめた口から冷麺が垂れ下がっている。
無論、昼休みに出前を取るなど校則違反甚だしいのだが、この男にそんな言葉は失われている。
革張りの椅子に座って眠りこけていた白垣真は隅の方にどけられて、そこには一人の少女が新たな主となっている。
組んだ足を机に乗せて、「生徒会長」と記された三角錐が蹴られて落ちた。
突然の君臨者――十六夜烈香は相変わらず涼しそうな軽装で、凛とした表情を浮かべ、雨宮の答えを待っている。
まだ子どもっぽさを残す顔は、やや目元がきつめに吊り上がっているため、どこか背伸びしたような愛らしさがある。
雨宮は片腕でざるそばをすすりながら、
「野生動物の異常繁殖は用務員のジジイに頼むべき仕事であって、一生徒にすぎない俺に言うことじゃない」
「誰が廃校舎がジャングルになってため池に化けガモが出たなんて話したんだよ。獲物だよ、え、も、の」
雨宮はけだるさをため息にして吐き出した。
首を残念そうに振り、
「俺はね、嫌いなものがいくつかある。麻雀を打つときに『ぶつ』って発音するくせに点数計算ができないやつと、ジャン卓のある友達んちを『雀荘』って呼ぶやつと、獲物だのカモだの言っておきながら言ってみれば小遣い銭しか持ってないやつのところに案内するやつだ。いまんとこ、おまえはすべてに該当する気がするけど俺の気のせいか?」
「気のせいだよ」
残念なことに雨宮の長口舌はすべて無駄になった。
烈香は足首をくいくいと動かして、
「あんた友達いないのか? もう下じゃ噂になってて、何人かの麻雀打ち――たしか進藤とかなんとか――が何回か狩りに出て、結構稼いでるらしいけど?」
夢いっぱいな話だろ、といわんばかりに烈香は顔を輝かせていたが、雨宮は気味悪そうに、「ざるそばとこいつの話は食い合わせが悪い」と言いたげに、回転椅子を滑らせて烈香からちょっと遠のいた。
狩り? 学生麻雀が?
中二病患者につける薬はないものか。
烈香はじれったそうにバタバタと踵を机に打ちつけ始めた。
授業中でなければ他の生徒会役員どもに叱咤されているところだ。
「と、に、か、く! おまえはあたしのオヒキ(手下、子分のこと)として、今晩打ちにいくの。いい?」
「いい、じゃねーよ。俺をどっかのヘタレと一緒にするなよ」
ちゅるん、とそばが露を跳ね散らかしながら雨宮の薄い唇に吸い込まれる。
たとえざるそばを食っているだけでもどこからともなく神聖さの加湿器が稼動してオーラを撒き散らし、結局は絵になる男なのだ。
欠片ほども取り合ってくれない雨宮に烈香は憮然とした表情を作って見せるが、雨宮の無関心さは崩れそうにない。
ざるそばを食い終わり次第、教室に逃げ込む算段だろう。
そうされてしまえば不法入校者の烈香は追跡できない。
「待ちなさいよ!」と教室のドアをバターンと開け放って周囲の空気を凍りつかせた後に通報されてお縄になるのも味なものかもしれないが、烈香はこれでも麻雀以外では一切の罪を犯していないつもりなので、こんなくだらないことで留置場にブチこまれるのは、彼女の玄人精神からすると許されざることである。
むむむ、と怒りと侮蔑と懇願を視線に梱包して送り続けるが効果なし。雨宮はおいしそうにそばをもぐもぐするばかりだ。
烈香は、一際大きく踵を生徒会会長卓にたたきつけた。
「そ。じゃあいいよ。あんたの気持ちはわかったよ、雨宮」
「わかってくれたか」雨宮はうんうんと頷いて両手を合わせた。「お祓いしとくからもう来るなよ」
「ものすごく腹立つ……。そーですよね、人気者の雨宮くんたら忙しくって麻雀なんか打てませんよねえ?」
「当たり前だ」
「帰宅部で、彼女もいなくて、学校と家の往復くらいしかやることのない雨宮くんたらさぞ忙しいんでしょう?」
「…………は?」
「いろいろあってから何もかもが面倒になっちゃった雨宮くんたら、ぶっちゃけ、うっすい人間関係とお山の猿大将ごっこにうんざりしちゃって、エンドレス五月病に囚われてるんですって? 忙しいことですわねえ」
しなを作って「およよよ」と袖で目元を拭う烈香の気持ち悪さもさることながら、なかなか痛いところを突かれて雨宮はぐっと言葉に詰まった。
確かに、自分は飽きている。
満たされていることに、飽きている。
だから自分からいろんなものにさよならして、またやる気が出るまでゆっくり過ごそうと思っていたのだが――
「それって」烈香が嗜虐感たっぷりの笑顔で、「準ひきこもりって感じだよねぇ?」
「ぐっ……」
「やだやだ、よくいるんだよねぇ、昔はよかったのに、とか、俺だって本気を出せば、とか終わってるくせにさ? ほざいちゃうヒト。雨宮もそーゆータイプだったんだ?」
「うぐぐ……」
一言一言に必殺の棘が絡みついている。雨宮はぐさぐさと切り傷だらけになっていく。心が。
こいつってこんなやつだったっけ? という思いがよぎるが、ヒトは成長するもの、確かに最近の自分はたるんでいると言えなくもなくて――
「老いた獅子の行く末は、餓死、ってね。」
がちゃん、と雨宮は空になった椀を置いた。残った右腕でぐしゃぐしゃと髪をかきむしる。
どうやら形勢不利らしい。
ならば流れを淀めることもない。
「わかったよ」
どうせ千点百円なんだろうなあ、と憂愁に煙る灰色の日差しを浴びながら、
「今晩だけは、おまえの下についてやろう」
「うんうん。最初からそういえばよかったのにさ。焦らしちゃって、メンドくさいやつ」
「おまえなあ……」
「じゃ、夕方に廃校舎で。作戦なんて造らなくってもどうせ勝てる相手だからさ、気楽に愉快にブッ潰そうぜ!」
とびきりの笑顔を残し、左手をひらひらと振って烈香は颯爽と出て行った。麻雀以外の話はする気が無いし興味も無いとばかりに。
今頃になってもぞもぞ目覚める気配を見せ始めた生徒会長を爪先で転がしながら、雨宮秀一は、ひとつ大きなあくびをこぼした。
世の中には廃墟愛好家というものがあって、雨宮たちの通う学園にある廃校舎もその筋では有名なスポットのひとつだった。
グーグル先生で廃墟、学校と検索すれば三十分とかからず無機質なイニシャルと無断で撮影されたモノクロ写真つきで紹介されているページに出くわすはずである。
そんなものは取り壊してしまえばよさそうなものだが、金持ちに道楽好きが多いのは世の常か、壊さないでくれと学園側に菓子折りを届ける輩がいるらしく(そしてその中身は食べられないものであって)、学校側もチェーンと立ち入り禁止の張り紙だけで済ませているだけで実質誰でも忍び込める。
だから怪談話やいじめの温床になることも多く、久々に夕暮れに染まる廃校舎前に立った雨宮は、短い時の流れの儚さをかみ締めるのであった。
この世の中、数秒先に何が起こるかわからない。役なしドラ3に振り込んでしまうように、読みもセオリーも、時には無力で、どれほどの力や幸福を溜め込んでも、それはただ刹那に映った陽炎だ。
空っぽの下駄履きに、十六夜烈香が腕を組んでもたれかかっていた。
一瞬、そこにいるのに存在感が不思議となくって見逃してしまいそうになる。けれど麻雀打ちとしては存在感が薄いというのも、便利といえばそうかもしれない。
「よう、おまた」
「なに、そのおっさんくさい言い回し?」
烈香が嫌そうな顔をする。女の子ならおじさんと言え、と雨宮は心の中で厳しくダメ出ししたが、仮に口に出しても十六夜烈香には無意味だったろう。
「準備はいい? じゃあ、いくけど」
「うむ」
ホコリとカビの臭いが充満する木製のトンネルを、烈香と共に進んでいく。
灯りが必要な暗さではないが、青い闇が一歩進むごとに深まっていく。
海の中を縦に降りていくように。
深く、深く、もう帰ってこれないほどに……。
烈香が立ち止まり、雨宮も足をとめた。
「ここだよ」と烈香が光で照らした先には、「宿直室」と書かれたプレート。
なるほど、確かに宿直室ならちょっとした畳敷きの座敷があって、麻雀にはちょうどいいだろう。
烈香が戸口に手をかける。
ふと雨宮の背筋を冷たい悪寒が走った。が、彼は強いて烈香にそれを告げることも、その手を止めることもしなかった。
不思議な気持ちだった。振り込むとわかっていながら牌を切ってしまうような、そんな不思議な、倒錯情動。
ガラリ、と烈香は戸を開けて中に入る。雨宮も続いた。
想像した通りの宿直室の畳の上に、ひとりの男がジャン卓に両肘をつけて、入ってきた二人のことを見上げている。
雨宮と同じ、黒い学生服を着た男だ。
どんよりと濁った目とその下にびっしりと染み付いたクマは、不健康そのもので、ただいま徹マン強行軍中と言われても不思議ではないが、他の面子の姿はない。
男は蓬髪をぐりぐりと指で絡め取りながら、烈香と雨宮を交互に見る。
「こんばんは」
咄嗟に、烈香も雨宮も言葉を返せなかった。ややあって、
「こ、こんばんは」
と引きつった笑みを浮かべて烈香が頷く。
男を騙せる笑顔じゃないな、と雨宮は思った。そのすぐ下に相手への嫌悪を無意識のうちに伝えてしまう笑顔は、女としては二流のシロモノだ。
あの嶋あやめなら、裏も表もなく笑って見せるのだろうが。
男に勧められるままに、烈香と雨宮はジャン卓へ腰かけた。
「えと……」と烈香が言葉に詰まり、あろうことか雨宮へ助けを求めるような視線を向けてきた。
冗談じゃない、と手を振ってやる。なぜ俺がこんな下賎な下男と下らない挨拶と段取りをしなくてはならないのだ。
そんなことは言いだしっぺのおまえがやることだろ、烈香、と睨んでやるが彼女は俯いてしまう。
(こいつ、ひょっとして……いままでギャンブルの舞台を整えるのは白垣に任せきりで、その下ごしらえをするのがまだ苦手なのか? ていうか、ひょっとして男がちょっと苦手だったりすんのか?)
おいおい大丈夫かよ、SSSランク麻雀打ったのホントにおまえか? などと雨宮はクドクドとお説教してやりたくなったが、まあ確かに二人と二等辺三角形を描く位置に座る男は、陰気で覇気がなく、とても心地よい関係を築けるとは思いがたい風格ではあったが。
男が黙りこくる二人に眉をひそめはじめたので、仕方なく雨宮はため息をつき、
「ここで面白い麻雀が打てるってんでね。こいつと遊びにきたんだ……えと、先輩かな?」
雨宮は振り返って、靴置きに目をやったが、男の上履きは見当たらなかった。本来ならそこに走るラインの色で、学年がわかるのだが。
男はぽりぽりとつむじを長く伸びた爪でひっかいて、
「ああ……三年の寺門だ。噂を聞いてここに来たのかな……いくらか高いレートで、あんたらのお好みのルールで打つ……一応、あんたたちの名前は?」
「へっ?」と烈香が素っ頓狂な声を出し、雨宮を見やる。
(ここの生徒じゃないってバレたらどうしよう)という顔だ。
雨宮はギロリと烈香を睨んでから、万人に親しまれやすい無敵の笑顔を寺門に向けて、
「ああ、俺は二年の雨宮。こっちもそう、ええと、馬場烈香」
「な、ちょっ……!」
またギロリ。
(十六夜なんて妙な名字、あとあと調べられても困る。馬場って名字なら、この学校には生徒で十三人、教師で二人いるからカモフラージュもいくらか効くだろ……恥ずかしがってんじゃねえタコ。カモる方がテンパっててどうすんだ?)
まったく、今の烈香の様子は大自然に解き放たれた動物園の豹のようだ。純粋培養されていた分、品があるが柔らかさと獰猛さに欠ける。それでは本物のハイエナたちに取り囲まれて終わりである。
「よし、じゃ、ルールの話といこうか。馬場?」
「……。あっ。そうそう、三人しかいないから、サンマ(三人麻雀)にしたいんですけど、いいですか、寺門先輩」
「いいよ」
即答だった。雨宮は、ふうん、と寺門に流し目を送る。これが女性に向けられていたら狙いを定めているのかと思われるところだろうが、あいにくといまの彼はいくらか戦士であって、市民ではない。
この寺門という男、腕に相当の自信があるのか、それともただの馬鹿か。
「サンマは、萬子の二から四、六から八までを抜く。一萬、五萬、九萬、北はガリ(抜きドラ)だ。抜いたら王牌から一枚持ってこれるのは知ってるよな? ドラは開門から十一枚目をめくる。点数計算はバンバンつきの一点、二点のあれ。チャンタは五点、純チャンタは十点。役満は五十点。ダブルは二百点。トリプルは千点。親は一点、連荘分は一点ずつ加算。チーなし。オーケイ?」
「何度かやってる」寺門の表情は変わらない。
「そいつは結構。いい打ち手と打てそうで俺も嬉しい。烈香から何かあるか?」
ふるふると烈香は首を振る。まるきり借りてきた猫状態だ。
ただ、その顔つきのすぐ裏に、麻雀打ちとしての若干の疑問符が浮かんでいることも雨宮にはすぐわかった。
そしてその回答は、卓の中で出すつもりだ。
ガラガラと寺門が牌をかき混ぜる。三人はそれぞれ引いて、位置についた。
起家、雨宮。南家、寺門。西家、烈香。
みんなが牌山を積んだところで、
「一点はおいくらかな?」
と雨宮はわざとらしく問いただした。雨宮はレートは烈香に任せるつもりだったので、視線を送る。
どうせ小金なので、いくらだろうと関係ない。
水を向けられた烈香はスッとそれまでの狼狽ぶりを消して、
「一万円」
ととんでもないことを言い出した。雨宮も思わず笑った。学生にそんな金があるものか。二五〇万円から始まる麻雀なんかバブル期のマンションクラスだ。
寺門はこけた頬をひと撫でして、
「一万か……」と苦しげな声を出した。
「ハハハ、先輩、じれったいマネはよそうぜ。そんな金持ってないだろ」
ところが、寺門は、「いや……」と意味深な呟きを残して背を向け、なにやら隅の方に転がっていたダンボール箱をごそごそし始めた。烈香と雨宮は顔を見合わせる。
「一万円札は十枚しかないが……こいつを担保にしてくれるなら、いいよ」
といって、ダンボール箱をジャン卓の真ん中にどんと置いた。
烈香と雨宮が額を揃えて覗き込むと、中には、金色に輝く板が折り重なって入っていた。
金ののべ棒。
ごくり、と烈香が生唾を飲み込み、雨宮の身体からは敵意が噴出した。
何かおかしい。
そんなことはわかっている。
「おい」
上級生に向けるとは思えないドスの効いた声音で、
「こいつはどういう冗談だ」
「冗談? 本物だが」
寺門は澄ましている。突然、その胸倉を雨宮は掴み、烈香が慌てふためく。
「学生がこんなアホみたいなモンもって麻雀するわけないだろ。てめえ常識あんのか? これはなんだ、演劇部から借りてきたのか? おい、この俺をなめると表も裏も出歩けないようにしてやるぜ」
「あ、雨宮、カ……寺門先輩から手ぇ離しなよ! 失礼だよ!」
カモといいかけたくせに、と内心で呟き、雨宮は取り合わない。
寺門は自分の運命にさえ興味がないといった口調で、
「これは裏山で見つけたんだ……徳川幕府の埋蔵金さ」
「どうやら指をツメられたいらしいな。いいぜ、血を見るのは嫌いじゃない」
「べつにそうしてもらっても構わんが……君らは麻雀しにきたんじゃないのか? だったら麻雀をしよう……もしこの金ピカがニセモノだったら、ちゃんと代わりのものを払うよ……本物だがね、繰り返すけど」
「いちいちカンに触るやつだ……だが、ま、いいか。麻雀しようか」
急にそれまでの怒気を蒸発させた雨宮は無表情になって、ダンボールをジャン卓からぽいっとどけた。
「ふん。北家がいないが、出目はヨンマと同じ風でいいかい?」
「ああ」
「じゃ、自五で俺の山から取り始めるぜ」
スッスッと何事もなかったかのように配牌を取り始めた男たちに烈香はしばし呆然としていたが、自分の手牌が完成する頃には、冷めた鉄ような雰囲気を回復させていた。『殺人麻雀』の名は伊達ではない、というところか。
自分の手牌をゴミでも見るような目つきで眺めながら、寺門が言う。
「君たちは俺の支払いを心配しているようだが……それはこっちのセリフでもあるんだぜ。俺は必ず払ってもらう……忘れないでくれよ」
「ああ」
「うん」
雨宮も烈香も、第一打牌する前に、そんなセリフは忘れてしまった。
サンマは、萬子がないためにヨンマよりも派手な手ができやすい。
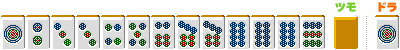
(1334566779)2345
こんな手から、雨宮は5sから切り出していった。
(この麻雀に三色同順はない……三色同刻ならあるがね。だからチャンタにも染め手にも複合しない5sなんかいらんのだ)
サンマはどんなゴミ手でもなんらかの手役ができるか、テンパイしてしまうことが多い。雨宮もその持ち前の強運を使うまでもなく、七順で牌を倒した。
こんな手から、雨宮は5sから切り出していった。
(この麻雀に三色同順はない……三色同刻ならあるがね。だからチャンタにも染め手にも複合しない5sなんかいらんのだ)
サンマはどんなゴミ手でもなんらかの手役ができるか、テンパイしてしまうことが多い。雨宮もその持ち前の強運を使うまでもなく、七順で牌を倒した。
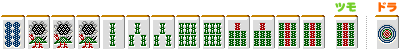
「ロン。メンゼンバンバン、チンイツピンフ、ドラ三(表一枚、ガリ二枚)、五が一枚、親で十四点」
寺門はうっと呻いてから点棒を惜しそうに払った。そこまでは、まあ擬態なんだろうと思っていた。
が、
「ツモなら二倍の点数になるのに……その三面張(雨宮は2-5-8p待ちだった)はツモる選択はなかったのか? それとも慣れてないのかな」
もちろん、雨宮と烈香のお財布は一緒なのでお互いの出入りは関係がない。
「ふん、アガリ見逃しするとツキが逃げると聞くんでね」
「そうか……」
雨宮はさらに驚くことになる。アガっておいて驚いたのは彼の雀史においても例がなかったかもしれない。
寺門は、バタッと自分の手を開けて、己の手牌を公開したのだ。
寺門はうっと呻いてから点棒を惜しそうに払った。そこまでは、まあ擬態なんだろうと思っていた。
が、
「ツモなら二倍の点数になるのに……その三面張(雨宮は2-5-8p待ちだった)はツモる選択はなかったのか? それとも慣れてないのかな」
もちろん、雨宮と烈香のお財布は一緒なのでお互いの出入りは関係がない。
「ふん、アガリ見逃しするとツキが逃げると聞くんでね」
「そうか……」
雨宮はさらに驚くことになる。アガっておいて驚いたのは彼の雀史においても例がなかったかもしれない。
寺門は、バタッと自分の手を開けて、己の手牌を公開したのだ。

唖然としてしまった。
「なあ、聞いてるのか、雨宮クン」
「え……いや、うん。その形からの打8pは仕方ないだろう。他のメンツとも繋がらないし、うん、しょうがないな!」
「そうか……ツイてなかったな。くそ、こっちだって索子のチンイツ一向聴だったんだ。どうしてこうなのかな、俺って……今ので十四万負けか。やってられないな……」
雨宮は烈香を見た。烈香は、その唇に押さえきれぬ笑みを浮かべていたが、その角度に反比例するように、雨宮の気持ちは沈んでいった。
悟ってしまった。
今宵の勝負が、勝負とも呼べない――正真正銘の、駄麻雀であることを。
寺門は、一点の疑いの余地もなく、ただのカモだった。
ただのカモとは、勝負ができない。
この時は、ただそれだけが、雨宮秀一には辛かった……。
最初の半荘を雨宮に飛ばされて、寺門はいつまでもブツクサ言っていた。
それを見かねて、烈香が視線を飛ばしてくる。
通しなどは決めていない二人だったが、その目の色だけである程度の意思は交わせる。
『ねえ、結構イラついてるみたいだし、もっと緩やかにカモらない?』
雨宮は視線を逸らして山作りに戻った。拒否の意味。
烈香が空咳をしたので、雨宮はまた顔を上げる。
寺門は、己の手元だけを見てガチャガチャと牌を几帳面に並べている。
『わかったよ。最初っから吹っ飛ばすつもりでいくんだね。じゃ、次はあたしがアガるよ』
これも拒否しようかと思ったが、面倒なのでやらせておく。
場所変えは面倒だったのでやらなかった。烈香は雨宮の対面、親番だ。
二つのサイをひねって落とす。転がらずにぶつかっただけのサイは、左四を示していた。
三人麻雀は北家がいないのでひとりの山が長くなる。烈香は丹精こめて造った山から、配牌十四枚をぜんぶぶっこ抜いた。
そんなことできるわけあるめえ、と思われるかもしれないが、本当に手元しか見ていないやつ相手になら、できる。
取ってきた手牌ブロックを立てずにそのままにしておき、自分の山の端にくっつけ押し出す。そして反対側から七トン十四枚の仕込み牌を持ってくる。
だから烈香は天和していたはずである。だが、烈香は普通に第一打を打った。
それもそのはず、烈香は八トン十六枚をぶっこ抜いていたのだ。手の平の親指から小指まで伸ばしてやっと、の量である。
そして二順後、
「ロン!」
「なあ、聞いてるのか、雨宮クン」
「え……いや、うん。その形からの打8pは仕方ないだろう。他のメンツとも繋がらないし、うん、しょうがないな!」
「そうか……ツイてなかったな。くそ、こっちだって索子のチンイツ一向聴だったんだ。どうしてこうなのかな、俺って……今ので十四万負けか。やってられないな……」
雨宮は烈香を見た。烈香は、その唇に押さえきれぬ笑みを浮かべていたが、その角度に反比例するように、雨宮の気持ちは沈んでいった。
悟ってしまった。
今宵の勝負が、勝負とも呼べない――正真正銘の、駄麻雀であることを。
寺門は、一点の疑いの余地もなく、ただのカモだった。
ただのカモとは、勝負ができない。
この時は、ただそれだけが、雨宮秀一には辛かった……。
最初の半荘を雨宮に飛ばされて、寺門はいつまでもブツクサ言っていた。
それを見かねて、烈香が視線を飛ばしてくる。
通しなどは決めていない二人だったが、その目の色だけである程度の意思は交わせる。
『ねえ、結構イラついてるみたいだし、もっと緩やかにカモらない?』
雨宮は視線を逸らして山作りに戻った。拒否の意味。
烈香が空咳をしたので、雨宮はまた顔を上げる。
寺門は、己の手元だけを見てガチャガチャと牌を几帳面に並べている。
『わかったよ。最初っから吹っ飛ばすつもりでいくんだね。じゃ、次はあたしがアガるよ』
これも拒否しようかと思ったが、面倒なのでやらせておく。
場所変えは面倒だったのでやらなかった。烈香は雨宮の対面、親番だ。
二つのサイをひねって落とす。転がらずにぶつかっただけのサイは、左四を示していた。
三人麻雀は北家がいないのでひとりの山が長くなる。烈香は丹精こめて造った山から、配牌十四枚をぜんぶぶっこ抜いた。
そんなことできるわけあるめえ、と思われるかもしれないが、本当に手元しか見ていないやつ相手になら、できる。
取ってきた手牌ブロックを立てずにそのままにしておき、自分の山の端にくっつけ押し出す。そして反対側から七トン十四枚の仕込み牌を持ってくる。
だから烈香は天和していたはずである。だが、烈香は普通に第一打を打った。
それもそのはず、烈香は八トン十六枚をぶっこ抜いていたのだ。手の平の親指から小指まで伸ばしてやっと、の量である。
そして二順後、
「ロン!」
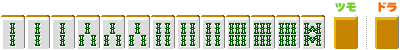
「いい手だな」
と雨宮が首を伸ばして手牌を覗き込む。
「双竜闘蛇か……役にはならんが」
「ふふふ、純チャンなんてツイてるなあ」
「そうだなあツイてるなあ」
「あはは」
「くくく」
寺門の顔だけが青い。
おそらく、烈香が握りこんでいた余分の二枚は、九萬と寺門のオタ風の南あたりであろう。
あえて不自然な天和にせず、ただの速いチャンタに見せかけたアガリ。
「出るよ。この巡目で一萬は出る」
寺門はぶつくさ言い募ったが、誰も聞いちゃいなかった。
不気味でさえあった。
五半荘連続トビ終了を喰らっているのに、寺門は一向に「イカサマ」ということを口には出さない。
確かに一度、親のダブリー一発ツモで(それでもサンマルールにしては小さなアガリだったが)勢いに乗ったような演出が偶発的に起こったのも、彼の暢気さに影響を与えていたかもしれないが、それでもここまで負けが続けば怪しみそうなものである。
それでも、寺門は自分の手牌しか見ない。
気づいていながら、黙っているのではないか? 何か策があるのではないか?
そんな固い疑念も雨宮の脳裏をよぎりはするものの、やはりそうとは思えない。
こいつはゴミだ。
やる気が出ない。
すっかり雨宮は気力を失って、アガリはほとんど烈香に集中していた。積み込みもぶっこ抜きも、してなんになる? 放っておいたって烈香がアガるのだ。
「ツモ!」
「やれやれ、ツイてないね……こんなとこ、来なけりゃよかった」
気だるげに点棒を渡す様も、寺門の曇った目には真実、負けがこんでいる者であるように映ったのかもしれない。
新しい局が始まる。
みなが牌を混ぜているとき、雨宮はちらっと烈香が積み込みをするそぶりを見せると有効牌をさりげなく送ってやっていた。そうしながら、それが目立たないように、
「寺門先輩って、麻雀歴はどんくらい?」
とか聞いて注意を引いたりする。寺門はハメられてるとも知らずにホイホイ答える。
「十年。子どものころ、じいちゃんに習った」
「へえ、いいじいちゃんだね。俺のじいちゃんは糞ジジイだったよ。ショタコンだったんだ」
「ショタってなんだ?」
「少年趣味。実の孫の俺を可愛がらずに他のガキばっか見てギンギンに興奮してたんだ。ひどい話だろ?」
無論、すべて雨宮の装飾過多の説明ではあったが、彼はやや本気でもあった。そうと思った方が、気が楽で、馬鹿にできたからだろう。
寺門が不憫そうな視線を送ってくるが、すぐに不憫になるのは彼の方である。
配牌をとり終えると、親番ゆえか、寺門は長考に入った。
この男、長考が異常に多く、有効牌だろうが無駄ツモだろうが(安全牌に見えるツモ切りパイでアタリ続けた雨宮と烈香にも責任があるが)すぐに牌理の迷宮に没頭する。隣の二人をほったらかして。
南場に入らずに終わる半荘がほとんどなのに、現在の経過時刻は通常の半荘勝負と変わらない。
雨宮と烈香が打牌に迷いがないのを差し引けば、およそ常人の四倍近い無駄な時間を浪費していることになる。
これだけでも万死に値するかもなァ、と雨宮はぼーっとしながら考えた。
もはやこれは勝負ではない。
搾取だ。
やがて、寺門は断腸の思いという感じで、8sを打った。
「ロン……」
烈香が薄笑いを浮かべて牌を倒した。

「緑一色、四暗刻単騎、人和――」
寺門が、顔中にしわをぐちゃっと集めて、歯の隙間から細い呻きをもらした。
雨宮の冷たい目が、それを広く捉えている。
片手でも、素早くやれば、ぶっこ抜きはできる。
「ロン。人和、チートイツ。ああ、一応サンマは役満に手役も加えて計算するからな――悪いね、先輩」
「この手で8s押さえられるかよ……7sが手にあれば俺だって考えた。考えたんだ。くそ、嫌な予感はしたのに、8s……」
「じゃあ切るなよ」
「うるさい、うるさい、ああ……」
寺門は完全に自分の世界に入って後悔に耽っている。
烈香はその様が愉快で仕方ないのか、自分の手をあっという間に牌山に突っ込んでぶち壊した。
雨宮の手元に、固められてあった7sが四枚転がってくる。
『ふふん、あたしがオールグリーンを積み込んでると見破って、同じ待ちにするなんて、粋なことするじゃん?』
雨宮はふっと笑ったきり、特になんの意思も伝えなかった。それが烈香には不思議だったのか、空せきをして、
『何? どうかしたの』
『べつに』
確かにカモだ。眠っていたって勝てる。それに、こいつが感じている苦しみも本物だろう。
それを取り除こうとするあらゆる努力を放棄しているのは雨宮からすれば謎だが……。
十六夜烈香は、嗜虐的な麻雀を打つ。
相手が苦しむことで、ようやく自分が麻雀をしていると実感できるのだろう。それをいいとか悪いとか言うつもりはない。弱いとも汚いとも思わない。
簡単な話。
雨宮秀一は、弱いものいじめに飽きていた。
それだけだったのだ。
烈香の気持ちもまるきりわからないわけじゃない。
自分の千点棒に、たかだか十円玉一枚さえも乗せられず、その十円玉で何を得るでもなくただ馬鹿なバクチで失いたくない、それだけの、そんな臆病者が平気な顔で、点数計算もできないままに麻雀を打ち、それどころか真剣に打つものを小バカにさえする。
そんな景色をずっと眺めてきたとしたら、この『苦痛の麻雀』は烈香を虜にしてやまないだろう。
そして幸か不幸かやつは、その苦痛を切り抜ける力を持っている。
だから、それについてこれないやつは死ねばいい。
シンプルで美しい情熱の回路。
それが十六夜烈香の根底にあるものだ。
だから、いい勝負である必要はない。麻雀を通して、敵を打ちのめせればいい。再起不能になるまで、苦痛のメーターが振り切れて戻って来なくなるまで。
自分は違う、と雨宮は思う。
自分は、それでは満たされない。
なァ烈香、と雨宮は、パンクに近づく寺門に熱の篭った視線を注ぐ烈香の横顔を見て、思う。
こんな麻雀、虚しくねえか。
こんな勝負、おまえ、自分の腕が可哀想じゃねえのか。
俺は可哀想でならねえよ。
違うか、烈香――。
烈香がトイレに立った頃、もう夜更けで、寺門はぼそぼそと「帰って欲しいな」とはっきりさせないまでも零し始めていた。
そして雨宮はじっと考え、やがて決めた。
「なあ寺門先輩」
「なに」
「あんた死んでるだろ」
寺門は、答えなかった。
「最初におかしいと思ったのは、あんたの上履きがどこにもなかったとき。そのはだしでここまできたのか? 汚れもせずにか? ガキじゃないんだぜ」
寺門は牌をいじっている。
「それに、この学校の生徒でこの俺を知らないってのもおかしい。俺、見かけ通りの超有名人なんだぜ。あんたの時代の卒業アルバムには載っていないだろうが……」
「俺が、幽霊だっていいたいのか」
「歯に着せた衣を剥げば、そういうことだ」
寺門は、ぽいっと牌を投げ出して、額を手で覆った。
「さあな、俺にもわからない。俺はただ、ずっと授業をサボってるだけだ。ここで……もう今が何時間目なのかも、わからないけど」
「ここが廃校舎になったのは、確か、火事があったからって聞いたな。その前から新校舎建設は進んでて、ちょうどいいからそのまま切り替えたらしい」
「俺は……」
「ふん、てめえの素性なんぞどうでもいいがな、いい手がアガりたくってこの世にしがみついてるんだったら、次の局、俺が天和をくれてやるよ。それを慰めにしてとっとと消えろ」
「そういうことじゃねえんだよ。そういうことじゃないんだ」
「じゃ、どういうことなんだよ。烈香がトイレから戻ってくる前に答えちまえよ」
寺門は、どこか遠くを見通すような、穴ぼこに似た目つきで虚空を見た。
「俺はずっと負け続けてきた……そのわけが知りたい。だからこうして打ち続けてきた。それだけだ。それだけわかったら、消えてやってもいい」
雨宮は迷わなかった。
「無理だ」
「無理? おまえや、馬場って子ならわかるんじゃないのか。散々ツキやがって」
「ツキ?」
愚、ここに極まれり。
「……やれやれ」
「なんだよ」
寺門は本当にわかっていないのだ。
雨宮は、ぐっとその端整な顔を、痩せた男に近づけた。お互いの息がかかる距離。
「あのな、おまえは愚にもつかないゴミ野郎だ。それはわかるか」
寺門は沈黙する。
「ふん。だが、それだけだったらまだ救いがあるんだ。
おまえに救いがないのは、いつか答えってやつが親鳥が雛にエサをやるみたいに降ってくると思ってるところなんだ。
死んでも治らないド馬鹿ってやつだ。
これ以上、てめえにかけてやる言葉も見せてやる打牌もない。
俺は帰る。
ここには火を放っておこう。
なにひとつない高さ二階の空中でいつまでも自縛霊やってろ」
そのとき初めて、雨宮は古い置時計が宿直室にはあって、カチコチと鳴っていることに気づいた。
寺門がふっと笑う。
「……ひどいやつだ。そこまで言うか、普通?」
「言うよ。言わなきゃ伝わらないだろ。言っても伝わらないなら陰陽師でも呼んでお祓いしてもらおう」
「みんなそうだな」
寺門は早口になっていく。耐え切れないとばかりに。
「みんな、俺のことが嫌いだという。言いながら、俺からは勝てるから、俺と麻雀を打つんだ。麻雀と、金のない俺なんて、意味がないというわけだ」
「その通りだ。自分の価値は自分で作って自分で認めてやるしかない。それができないおまえは黙って無意味に消えちまうのが似合いだぜ。
そしておせっかいにも付け加えておくが、ヒトから嫌われたからってなんだ? それが自分のあり方と関係すんのか?
そんなのどうでもいいことなんだって、俺は最近、知ったぜ」
もはや雨宮の言葉は、亡霊には届かない。
壊れた録音テープのように、寺門は呟き続ける。
「ツキがなかったんだ。みんなみたいに、俺は三半荘じっと粘ったってチャンスなんかこなかった。技術もなかった。テンパイの読みなんてどうしてできる……? 俺にはなにもわからない。そう、ツキと腕と……あとはなにが足りなかったんだろうな」
「そんなの全部関係ねーよ」
そう言う雨宮の目には、もう、悲しみしか残っていなかった。
「おまえはただ、生まれたときから……オトナだっただけだよ」
「……麻雀なんか、麻雀なんかやらなきゃよかった! ずうっと我慢して我慢して、その結果がこのザマか!」
「みんなそうだよ。いつか死ぬし、いつか負ける。だがね、俺はたとえトリプルハコを喰らって殺されたって、てめえみてえにブツクサ言って死んでいくのはゴメンこうむる」
「……祟ってやりたいところだが、その元気も、もうないや」
「祟るだと?」
魔少年は牙を剥いて、嗤う。
「たとえ神だろうが悪魔だろうが麻雀打ちを祟れるもんか。そんな真似してみろ、俺の魂がてめえの穢れた心をカスひとつ残さずフッ飛ばしてやるからよ」
その迫力に、その意気に、その情熱に。
すべてを得る前に失った亡霊は、なにひとつ言い返すことができなかった。
ただ、眩しいものから目をそむけるようにして俯き、
「まったく……恨めしいぜ、畜生」
名残惜しそうに呟いて、ふっと灯りを消すようにして、去っていった。
と、入れ替わるようにして烈香が戻ってきた。
「ふう、夜の学校のトイレってどうしてああ……あれ? 先輩は?」
「死んだ」
かなり真実に近いことを言ったはずなのに上履きで雨宮は頭をひっぱたかれた。
そんな無礼なマネをされた覚えのほとんどないこの欠落の王は、口をまん丸にして今にも笑い出しそうな、泣き出しそうな顔をした。
「な、何しやがる?」
「バカ言ってないでよ。まさか……」
烈香がジロリと雨宮に白銀の眼光をぶつける。
「逃がしたんじゃないでしょうね」
「逃がしたんじゃない。勝手に逃げたんだ」
成仏したんだろうが、結局、いなくなったやつは負けだろう。
面倒くさいので烈香には説明しないでおくが。
さて帰ろうか、と立ち上がったところでまたスパコーンとひっぱたかれた。首が斜めになって戻らない。
「だから何しやがるってんだよ!」
「バッカじゃないの! カモ帰らせてどうすんだよ! ハコテンにするつもりだったのに……」
「いいじゃねーか、金ののべ棒だったら、ほらそこに」
と指を伸ばしかけたところで、ぴたりと雨宮の動きが止まった。
ダンボール箱があった場所には、ただ読み捨てられたグラビア雑誌が積み重なっているだけだ。
「……あの野郎」
最後の最後に、味なマネしやがって。
だが、不思議と怒りよりも、呆れたような懐かしいような、そんな感情しか湧き上がってこない。
亡霊の最後の抵抗。
しっかり効いたぜ、こん畜生。
「ねえねえ何タソガレてんの? 勝手に?」
「痛いです痛い耳をひっぱらないで痛い痛い痛い」
烈香のこめかみに、ミミズが忍び込んだような青筋が浮き立っているのを見て、雨宮はぞっとした。殺されると思った。供養は丁寧にしてほしい。自縛霊なんて退屈なものは願い下げだ。
「オヒキのくせに、カモが金持って逃げるところをぼけーっと見てたわけ? ふ~んそ~なんだ~へ~ふ~んあっそ~」
「いやちげーんだって。あいつマジ足速かった。たぶん将来はマッハジジイ」
「そんなくだらねえジョークはお呼びじゃないんだよ!」
卓をスパーンと上履きを打ちつけ、ニヤリ、と烈香は笑った。
「取り憑いてやる」
「は?」
「あたしが今日勝った分の金、ぜんぶあんたにツケとくから」
「ちょっ」
一応、天涯孤独の身に落ちて、全財産をどこぞの若白髪に持っていかれた雨宮くん(17)は割と金欠の身である。
「そんなの白垣にツケろよ!」
「自分のミスを人に押し付ける気?!」それもそうである。
ぐい、っとシャツの襟を拳に巻き込んで、烈香は、
「あんたが耳揃えて払うまで、ずっと側にくっついててやる。おばけみたいに、枕元で、呪ってやる」
勘弁してくれ、と土下座までする雨宮を、きっと烈香は許しはしないだろう。
誰もいなくなった宿直室で、乱れた牌が、誰に触れられることもなく、散っている……。
「この手で8s押さえられるかよ……7sが手にあれば俺だって考えた。考えたんだ。くそ、嫌な予感はしたのに、8s……」
「じゃあ切るなよ」
「うるさい、うるさい、ああ……」
寺門は完全に自分の世界に入って後悔に耽っている。
烈香はその様が愉快で仕方ないのか、自分の手をあっという間に牌山に突っ込んでぶち壊した。
雨宮の手元に、固められてあった7sが四枚転がってくる。
『ふふん、あたしがオールグリーンを積み込んでると見破って、同じ待ちにするなんて、粋なことするじゃん?』
雨宮はふっと笑ったきり、特になんの意思も伝えなかった。それが烈香には不思議だったのか、空せきをして、
『何? どうかしたの』
『べつに』
確かにカモだ。眠っていたって勝てる。それに、こいつが感じている苦しみも本物だろう。
それを取り除こうとするあらゆる努力を放棄しているのは雨宮からすれば謎だが……。
十六夜烈香は、嗜虐的な麻雀を打つ。
相手が苦しむことで、ようやく自分が麻雀をしていると実感できるのだろう。それをいいとか悪いとか言うつもりはない。弱いとも汚いとも思わない。
簡単な話。
雨宮秀一は、弱いものいじめに飽きていた。
それだけだったのだ。
烈香の気持ちもまるきりわからないわけじゃない。
自分の千点棒に、たかだか十円玉一枚さえも乗せられず、その十円玉で何を得るでもなくただ馬鹿なバクチで失いたくない、それだけの、そんな臆病者が平気な顔で、点数計算もできないままに麻雀を打ち、それどころか真剣に打つものを小バカにさえする。
そんな景色をずっと眺めてきたとしたら、この『苦痛の麻雀』は烈香を虜にしてやまないだろう。
そして幸か不幸かやつは、その苦痛を切り抜ける力を持っている。
だから、それについてこれないやつは死ねばいい。
シンプルで美しい情熱の回路。
それが十六夜烈香の根底にあるものだ。
だから、いい勝負である必要はない。麻雀を通して、敵を打ちのめせればいい。再起不能になるまで、苦痛のメーターが振り切れて戻って来なくなるまで。
自分は違う、と雨宮は思う。
自分は、それでは満たされない。
なァ烈香、と雨宮は、パンクに近づく寺門に熱の篭った視線を注ぐ烈香の横顔を見て、思う。
こんな麻雀、虚しくねえか。
こんな勝負、おまえ、自分の腕が可哀想じゃねえのか。
俺は可哀想でならねえよ。
違うか、烈香――。
烈香がトイレに立った頃、もう夜更けで、寺門はぼそぼそと「帰って欲しいな」とはっきりさせないまでも零し始めていた。
そして雨宮はじっと考え、やがて決めた。
「なあ寺門先輩」
「なに」
「あんた死んでるだろ」
寺門は、答えなかった。
「最初におかしいと思ったのは、あんたの上履きがどこにもなかったとき。そのはだしでここまできたのか? 汚れもせずにか? ガキじゃないんだぜ」
寺門は牌をいじっている。
「それに、この学校の生徒でこの俺を知らないってのもおかしい。俺、見かけ通りの超有名人なんだぜ。あんたの時代の卒業アルバムには載っていないだろうが……」
「俺が、幽霊だっていいたいのか」
「歯に着せた衣を剥げば、そういうことだ」
寺門は、ぽいっと牌を投げ出して、額を手で覆った。
「さあな、俺にもわからない。俺はただ、ずっと授業をサボってるだけだ。ここで……もう今が何時間目なのかも、わからないけど」
「ここが廃校舎になったのは、確か、火事があったからって聞いたな。その前から新校舎建設は進んでて、ちょうどいいからそのまま切り替えたらしい」
「俺は……」
「ふん、てめえの素性なんぞどうでもいいがな、いい手がアガりたくってこの世にしがみついてるんだったら、次の局、俺が天和をくれてやるよ。それを慰めにしてとっとと消えろ」
「そういうことじゃねえんだよ。そういうことじゃないんだ」
「じゃ、どういうことなんだよ。烈香がトイレから戻ってくる前に答えちまえよ」
寺門は、どこか遠くを見通すような、穴ぼこに似た目つきで虚空を見た。
「俺はずっと負け続けてきた……そのわけが知りたい。だからこうして打ち続けてきた。それだけだ。それだけわかったら、消えてやってもいい」
雨宮は迷わなかった。
「無理だ」
「無理? おまえや、馬場って子ならわかるんじゃないのか。散々ツキやがって」
「ツキ?」
愚、ここに極まれり。
「……やれやれ」
「なんだよ」
寺門は本当にわかっていないのだ。
雨宮は、ぐっとその端整な顔を、痩せた男に近づけた。お互いの息がかかる距離。
「あのな、おまえは愚にもつかないゴミ野郎だ。それはわかるか」
寺門は沈黙する。
「ふん。だが、それだけだったらまだ救いがあるんだ。
おまえに救いがないのは、いつか答えってやつが親鳥が雛にエサをやるみたいに降ってくると思ってるところなんだ。
死んでも治らないド馬鹿ってやつだ。
これ以上、てめえにかけてやる言葉も見せてやる打牌もない。
俺は帰る。
ここには火を放っておこう。
なにひとつない高さ二階の空中でいつまでも自縛霊やってろ」
そのとき初めて、雨宮は古い置時計が宿直室にはあって、カチコチと鳴っていることに気づいた。
寺門がふっと笑う。
「……ひどいやつだ。そこまで言うか、普通?」
「言うよ。言わなきゃ伝わらないだろ。言っても伝わらないなら陰陽師でも呼んでお祓いしてもらおう」
「みんなそうだな」
寺門は早口になっていく。耐え切れないとばかりに。
「みんな、俺のことが嫌いだという。言いながら、俺からは勝てるから、俺と麻雀を打つんだ。麻雀と、金のない俺なんて、意味がないというわけだ」
「その通りだ。自分の価値は自分で作って自分で認めてやるしかない。それができないおまえは黙って無意味に消えちまうのが似合いだぜ。
そしておせっかいにも付け加えておくが、ヒトから嫌われたからってなんだ? それが自分のあり方と関係すんのか?
そんなのどうでもいいことなんだって、俺は最近、知ったぜ」
もはや雨宮の言葉は、亡霊には届かない。
壊れた録音テープのように、寺門は呟き続ける。
「ツキがなかったんだ。みんなみたいに、俺は三半荘じっと粘ったってチャンスなんかこなかった。技術もなかった。テンパイの読みなんてどうしてできる……? 俺にはなにもわからない。そう、ツキと腕と……あとはなにが足りなかったんだろうな」
「そんなの全部関係ねーよ」
そう言う雨宮の目には、もう、悲しみしか残っていなかった。
「おまえはただ、生まれたときから……オトナだっただけだよ」
「……麻雀なんか、麻雀なんかやらなきゃよかった! ずうっと我慢して我慢して、その結果がこのザマか!」
「みんなそうだよ。いつか死ぬし、いつか負ける。だがね、俺はたとえトリプルハコを喰らって殺されたって、てめえみてえにブツクサ言って死んでいくのはゴメンこうむる」
「……祟ってやりたいところだが、その元気も、もうないや」
「祟るだと?」
魔少年は牙を剥いて、嗤う。
「たとえ神だろうが悪魔だろうが麻雀打ちを祟れるもんか。そんな真似してみろ、俺の魂がてめえの穢れた心をカスひとつ残さずフッ飛ばしてやるからよ」
その迫力に、その意気に、その情熱に。
すべてを得る前に失った亡霊は、なにひとつ言い返すことができなかった。
ただ、眩しいものから目をそむけるようにして俯き、
「まったく……恨めしいぜ、畜生」
名残惜しそうに呟いて、ふっと灯りを消すようにして、去っていった。
と、入れ替わるようにして烈香が戻ってきた。
「ふう、夜の学校のトイレってどうしてああ……あれ? 先輩は?」
「死んだ」
かなり真実に近いことを言ったはずなのに上履きで雨宮は頭をひっぱたかれた。
そんな無礼なマネをされた覚えのほとんどないこの欠落の王は、口をまん丸にして今にも笑い出しそうな、泣き出しそうな顔をした。
「な、何しやがる?」
「バカ言ってないでよ。まさか……」
烈香がジロリと雨宮に白銀の眼光をぶつける。
「逃がしたんじゃないでしょうね」
「逃がしたんじゃない。勝手に逃げたんだ」
成仏したんだろうが、結局、いなくなったやつは負けだろう。
面倒くさいので烈香には説明しないでおくが。
さて帰ろうか、と立ち上がったところでまたスパコーンとひっぱたかれた。首が斜めになって戻らない。
「だから何しやがるってんだよ!」
「バッカじゃないの! カモ帰らせてどうすんだよ! ハコテンにするつもりだったのに……」
「いいじゃねーか、金ののべ棒だったら、ほらそこに」
と指を伸ばしかけたところで、ぴたりと雨宮の動きが止まった。
ダンボール箱があった場所には、ただ読み捨てられたグラビア雑誌が積み重なっているだけだ。
「……あの野郎」
最後の最後に、味なマネしやがって。
だが、不思議と怒りよりも、呆れたような懐かしいような、そんな感情しか湧き上がってこない。
亡霊の最後の抵抗。
しっかり効いたぜ、こん畜生。
「ねえねえ何タソガレてんの? 勝手に?」
「痛いです痛い耳をひっぱらないで痛い痛い痛い」
烈香のこめかみに、ミミズが忍び込んだような青筋が浮き立っているのを見て、雨宮はぞっとした。殺されると思った。供養は丁寧にしてほしい。自縛霊なんて退屈なものは願い下げだ。
「オヒキのくせに、カモが金持って逃げるところをぼけーっと見てたわけ? ふ~んそ~なんだ~へ~ふ~んあっそ~」
「いやちげーんだって。あいつマジ足速かった。たぶん将来はマッハジジイ」
「そんなくだらねえジョークはお呼びじゃないんだよ!」
卓をスパーンと上履きを打ちつけ、ニヤリ、と烈香は笑った。
「取り憑いてやる」
「は?」
「あたしが今日勝った分の金、ぜんぶあんたにツケとくから」
「ちょっ」
一応、天涯孤独の身に落ちて、全財産をどこぞの若白髪に持っていかれた雨宮くん(17)は割と金欠の身である。
「そんなの白垣にツケろよ!」
「自分のミスを人に押し付ける気?!」それもそうである。
ぐい、っとシャツの襟を拳に巻き込んで、烈香は、
「あんたが耳揃えて払うまで、ずっと側にくっついててやる。おばけみたいに、枕元で、呪ってやる」
勘弁してくれ、と土下座までする雨宮を、きっと烈香は許しはしないだろう。
誰もいなくなった宿直室で、乱れた牌が、誰に触れられることもなく、散っている……。