06.静かなる咆哮
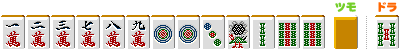
「――ロン。一発」
「――ツモ」
「――ロン。裏、3」
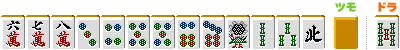
<南三局 天馬手牌>
一二三七八九(113)1299
天馬は点棒箱の中に手を泳がせた。点数は今のところ三万を越している。だが、天馬にはわかる。
じわり、じわりと。ツキが失せている。
麻雀はどんな偉そうなことを言ってみせたところでテンパイできなければ話にならない。アガリ以外の戦い方は牌を絞り大物手を匂わす河でプレッシャーをかけるくらいか。それもこの面子では、アガリ放棄の油切りなどやってみせたところで、こちらの手にある安全牌候補の単騎に受けられるまでだ。進んでも地獄オリても地獄。
だが、天馬の表情に焦りはない。手牌がこう良くては少々自信過剰になっても仕方もない。
純チャン三色のイーシャンテン。そこに清水からのリーチが入った。
現在清水はトップ目。ラス親を控えてのトップのリーチということは、ひょっとすると役なしか……それともツキが向いている自信か。
天馬の親番はこれが最後。ここで打点を稼ぐのが一番トップへの最短コース。全六回戦という長丁場のポイントマッチであることから考えてみても、親の重要度は通常の麻雀よりも高い。
稼げるときに稼がなければ。
リーチ第一発目、導師が打2p。これは清水の現物。
チーすれば純チャン三色で一万二千。十分打点だ。
導師の手が2pから離れる。天馬はそれを眼で追いつつ、スルーした。
(おれの河はピンズが安い。染め手じゃないことは詩織にも導師にもバレてる……同様に一通もない。チャンタ手であることがバレれば、おれのテンパイをかわすことは造作ない。そうなれば、詩織と導師が逆襲のテンパイを作ってくるかもしれん。いまのツキで三人四人でめくりあいはゴメンだぜ……)
ぎゅっと力をこめて牌を持ってくる。緊張の一瞬。
ツモったのは、1p。
三色ならずの安目……だが、構わない。
「リーチ……」
打3p、清水動かず。通り。
鳴いていても打点は変わらなかったが、ツモや裏で六千オールもある。
清水が顔をしかめた。
「陰気なツラでリーチをかける野郎だな。もっと元気よくいったらどうだ? せっかくのおっかけリーチなのによ」
「…………」
「チッ……暗いやつ。なんかうぜえぞ、おまえ」
ぶつくさ言っていたのが邪を呼んだのか。
清水はツモった牌を見て、うっと息を呑んだ。しかしリーチしている以上はカン材かアガリ牌以外はすべてツモ切らなくてはならない。
おそるおそる、その牌を河へ。
――白虎。
青白い顔をしたまま、天馬がむすっと押し黙っているので、清水は飛び上がらんばかりだった。
「ひゅう! 危ない危ない、獣牌で振ったら打点二倍だからな。どうだ、小僧、麻雀ってのはこうやって遊ぶもんなんだぜ」
天馬は清水の河を見ていた。だが、おもむろに視線を上げて清水の浅黒い顔を見た。その眼に宿る剣呑な光に、清水の笑いが苦くなる。
「なんだよ」
「もし、それがあんたのやり方なら、いますぐ宗旨替えした方がいい」
「――あ?」
「俺のバランスは、おまえの言葉ごときじゃ崩れない」
天馬は第一発目のツモを見もせずに河へ打ち放った。
赤5p。――通し。
清水が顔を引きつらせた。不敵に笑って見せたつもりだったのだろうが、かえって卑屈さを際立たせている。
「へっ。無理しちゃって」
「かもな」
だが、そこから先の展開で、詩織、導師、清水の三人は天馬の底知れない闇を垣間見ることになった。
まず、次のツモ牌が赤5m。――通し。
さらに次のツモ牌が赤5s。――これも通し。それどころか、5sは表ドラでさえあった。
天馬の顔は以前として微動だにしない。死人のように。
そんな闇は見慣れているとばかりに。
次のツモ牌も、軽く盲牌しただけで卓へ打ちはなった。
玄武。
一瞬ぼうっとした清水が、ハッとして手牌を倒した。
「ろ、ロン! 五二の二倍で、一万四百だ」
<清水手牌>
六七八(345567)123玄
天馬は無言で点棒を払う。それをかき集める清水の方が慌てふためき、失敗したよう。
天馬は、アガれなかった手牌に一瞥をくれてから、ガラガラと河と混ぜ合わせてしまった。
(俺にできることは、多くない)
(読みも、ツキも、こいつらを圧倒しているとは言えないだろう)
(ならせめて、できることだけは、ちゃんとしていたい)
(リーチ後は、アガるか、カンするか、それだけだ)
(迷う必要はどこにもない)
(俺は、迷わない)
(――オーラス)
詩織(青龍):22700
導師(朱雀):11900
天馬(白虎):21100
清水(玄武):44300