OY.どうか彼女に微笑みを
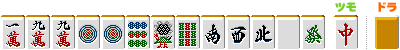
なんて、楽しそうな顔なんだろう。
詩織はぼうっとしながら、対面に座っている少年の顔を見つめる。
さっきまでの苦しそうな顔はどこへやら。すっかり笑顔になって、清水の肩を叩いて大声で笑っている。まるで、麻雀覚えたての粋がった不良少年のよう。
ああ、そうだ。麻雀はゲームなんだっけ。
ゲームって、楽しいものだったんだ。
そんな当たり前のことが、わからなかった。知らなかった。
笑顔なんて、ハッタリでしか使わない中途半端な武器だと思っていた。
こんな風に。
誰に見せるわけでもなく、心の底から笑っている人がいるなんて。
辛いことも悲しいこともたくさんあって、そっちの方がきっと多かったくせに。
こんな風に笑ってしまえるなんて。
なんて、馬鹿な人。
ああ、でも。
そんな馬鹿に、私もなりたかった。
私も、あんな風に……。
「リーチィッ!」
ダン、と天馬がリーチをかけてくる。
「かかってこいよ、紙島詩織。てめえからアガれば逆転だ」
「そう」
詩織は手牌を見た。
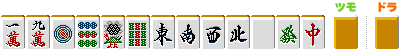
一九九(119)19朱虎玄白発中
国士テンパイ。奇跡のような手。
ああ、本当に起こったのだ、奇跡は。
なんて綺麗なんだろう。柔らかくて暖かくて、眩しい。
なにひとつ善いことなんてなかったけれど。
最後に、こんな気持ちになれたなら。
あたしの人生にも、小さい花丸くらいなら、あげてもいいかもしれない。
「リーチ」
「ロン」
「三万二千」
いつまでも続くように思えた粘っこい雨は、やんでいた。
戸から曙光が射しこみ、詩織には、天馬がどんな顔をしているのかわからなかった。
夜が明けて、今日もまた陽が昇る。
「……やってられねえや。帰ろうぜ導師の旦那」
「ああ」
立ち上がって、ふうやれやれと出て行こうとする清水と導師の背中に天馬の声が突き刺さった。
「待てよ。渡すもんがあるだろ」
「ちっ……抜け目ない野郎だぜ」
ほらよ、と出て行く二人から投げ渡されたカードを天馬はじっと見つめたあと、懐に仕舞った。カードにはまだ二人の体温が残っていた。
天馬は卓の向こうに目を向ける。そこには、仰向けにひっくり返った黒巫女が、喉をさらして虚空を見上げていた。
「おい、しっかりしろよ。べつに殺したりしねえよ。カードさえくれたら」
「バカじゃないの」
「なに?」
詩織は袂からカードを抜き出すと、それを歯で噛み、パキッと割ってしまった。あっと天馬が声をあげる暇もなかった。
ぷっと詩織は床にカードの残骸を吐き捨てる。
「ざまあみな」
「マジかよ……くあーっ」
天馬は額に手をやって、頭痛をこらえるように顔をしかめた。詩織はつつっと目を動かして、天上から天馬へと視線を変える。
「あの二人、追いかければ? カードがあっても完全な保証とはいえないし。いまならまだ捕まえられるよ」
「あー……それもそうなんだが」
「?」
「そうすると、おまえが一人になっちまうだろう」
ハッと詩織は嘲笑し、天馬など見たくもないとばかりに天上を見上げた。
「なに、やっぱりそういうこと?」
「そういうことってなんだよ」
「あたしをヤろうってんでしょ。好きにすれば? お金だけはかけた身体だけど、あんたあたしの昔の顔知ったら、きっと抱いた後に二度と起たなくなるよ」
天馬の声がしなくなった。見ると、天馬は、顔を赤くして、もごもごとなにか言っていた。
「は?」
「いや、だから、そういうこと言うなよ。おまえ女だろ。恥じらいってもんをさ」
「………………………………………………………………。死ねば?」
「よく言われる……」
がくっと天馬は肩を落とした。ああ、とか、うう、とか勝手に唸っている。詩織はとても付き合ってられない。
まあ、それも。
あと少しで関係なくなってしまうのだけれど。
詩織はそっと袂のなかに手を差し込んだ。細い柄の感触。
小ぶりなナイフだが、首筋をかき切るくらいならできるだろう。
天馬を殺して逃げることもできるかもしれない。
でも、やめた。
べつに天馬が惜しいわけじゃない。好きでもなんでもない。
ただ、そうして生き永らえても、もう無駄だと悟っただけ。
首筋にナイフを当てると、突然、卓を乗り越えて天馬が飛びかかってきた。
気づかれていないとばかり思っていた詩織はびっくりして固まった。
首筋にあてがわれたナイフの柄を、二人の手が握っている。
「やめろ」
そういう天馬の顔は、いまにも泣き出しそうだった。
組み伏せられた詩織は無感動にそれを見上げる。
「そっちこそやめてよ、せっかくあんたを殺してしまうこともできるのに、一人で消えてあげようっていうんだからさ。同情のつもり? それとも優越感かな? あ、わかった。死体を抱くのがいいんだ? いいよね、中がどんどん冷たくなっていくのがさ」
「紙島」
「ああ、そういう名前のときもあったね。いろいろ偽名使ってきたから本当の名前なんて忘れちゃった。どこの誰だったかも。いまどき山に住んでる仙人みたいなじいさんに拾われて、ペテンとイカサマを頼りにして生きてきたけど、ああ、身体を売れたらもっと楽に生きられたのになあ」
「そんなこと言うのはやめろ」
「いい気持ちでしょー? いまあたしは何もできない。何をされても文句を言えない。いいよねえ、善人にも悪人にもあんたはなれるんだから。それって最高の自由だよね。じゃ、時間ももったいないし、そろそろ本番に入ったら?」
天馬は呼吸を止めた。
そして、なにか難しい見慣れない文字を読み解くように真剣な顔で、詩織の瞳を覗き込んだ。
詩織の肩が強張る。
「――――なに」
「死にたいやつなんていねえ。俺はそう思う。でも、死にたいって気持ちが嘘じゃないってことも、わかる」
「――――――」
「死にたいってのは、生きたいってことだ。生きてるから死ぬってことがあるんだ。死にたいってのはいまの自分から遠く離れた、なにかに変わりたいってことなんだよ」
「ご高説どうも」
「俺はおまえになにもしてやれない。代わってやることもできない。おまえの問題はおまえが解決するしかないんだ」
「じゃ、手を放してもらいましょうか?」
「放さない」
詩織は顔を背けた。天馬はまっすぐに詩織の横顔を見つめ、続ける。
「なあ、きっと悪いことばかりじゃねえって。悪いことがあっても、それを俺たちは喰らっていける。そう思わないか」
「思わない」
「本当にそうか」
「思わないったら、思わないっ!」
「ぐあっ!」
詩織は天馬の腹を蹴り上げて、卓に向かって突き飛ばした。天馬が卓の上を滑って反対側に転がり落ち、牌が蜘蛛の子散らしたように飛散する。
ナイフは、立ち上がった詩織の手のなかにまだあった。
「あんたなんかにはわからない……一度救われたあんたには!」
「紙島……」
「この顔、この声、覚えがない? あたし、腕利きって評判のやつに頼んだんだけど、どうやらヤブだったみたいだね」
身体から牌をこぼしながら立ち上がった天馬が、ハタと目を見開いた。
「おまえ、それ」
「そ。あんたのよく知ってるやつの顔。あんたを救ったやつの顔。いいよねえ? あたしのところには本物なんてこなかった。だから、自分でなろうとしたけど、それもだめだった。どうすればいいの? あたしはどうすればよかったの?」
「紙島……」
「あんたたちみたいになりたかった。あたしだって、あんたたちみたいに、変わりたかったのに!」
詩織は涙を流しながら叫ぶ。その言葉ひとつひとつが天馬の胸を貫いて、痛んだ。
「あんたみたいなやつが一番嫌い。こっち側にいたくせに、救われたらそっち側のやつとすぐ同化する。あんたにはわからないよ。きっと、昔のあんたも、いまのあんたと会ったら同じことを言うだろうよ!」
詩織は目を瞑った。言いたいことはすべて言った。もう後悔はない。
言葉とは裏腹だけど、と詩織は心の中でつぶやく。
最後に、あたしの言葉を聞いてくれて、ありがとう。
それだけは、悔しいけど、ホントの気持ち。
じゃあね、馬場くん。名前、最後まで呼ばなかった。
「紙島、やめっ――――!」
ずぶり、と。
詩織のナイフが、天馬の手に突き刺さった。
「あ、あ……あんた……」
抱き寄せるようにしてナイフを生やした天馬が、額をつき合せるような距離から詩織を睨んだ。
痛みで潤んだ瞳、滴る鮮血が床に血だまりを広げていく。
「いいか……よく聞けよ、俺が昔の俺に会ったら、だと? 決まってる。殴り飛ばすよ。蹴りを叩きこむよ。だってそいつは、闘う前になにもかも諦めていたやつだからだ。人間のクズだからだ」
「だったら、あたしだって……!」
「違うんだよッ!!」
そのあまりの剣幕に、詩織は言葉を継げなかった。
いつの間にか、天馬も泣いている。怒りながら、泣いている。
「俺は確かにバカだった。臆病で、卑屈で、人を傷つけてばかりいた。でもな、そのときの俺ががんばったから、いまの俺がいんだよ。あいつが踏ん張らなきゃ、俺はいま、ここに立ってねえんだよ!
だから俺はぶん殴って渇を入れたら、そいつに感謝してもしきれねえんだよ。どんなに言葉を重ねたって、たりねえんだ!
だから、せめて、俺は生きていくんだ。昔の俺が、あの頃の俺が、消えないように、闘い続けるしかねえんだよ!!!!!!!!!!!」
「だから、」
「おまえも、死ぬなよ……」
なにも言えなかった。
ナイフが手から滑り落ちて、からん、と乾いた音が二人の間に響き渡った。
祝福のように。