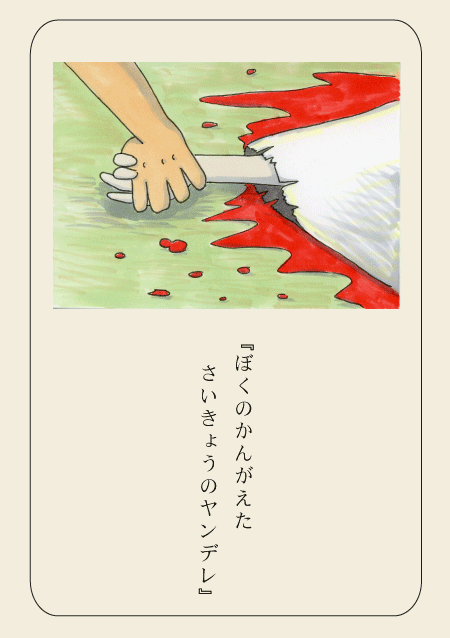境内に一歩足を踏み入れると、空気が一変した。
俺の周りを取りまいていた環境音――鬱々と茂る木々の葉ずれや鳥の囀り、風のさざめきといった、当たり前に感じすぎて気にも留めないような微かな音――が、いっせいに消える。
風が止まった?
いや違う。
欝蒼と茂る木々は強い風に吹かれ、変わらず枝を揺らし続けている。
音だけが――消えたのだ。
奇妙な静寂に包まれた境内で、俺はぐるりとあたりを見回す。
それほど広くはない、荒れ放題の敷地。手水を汲むための小さなあばら家があるが、水を受ける甕には一滴の水も入っていない。その横にある小さな井戸は、おそらく枯れているのだろう。
足元の苔むした石畳は、朽ちかけた正面の社に続いている。
その屋根の上に、血の色をした満月を背にして《ヤツ》はいた。
「やあ。ずいぶんと、遅かったじゃあないか」
よく通る声が親しげに俺を呼び、胡坐をかいて坐っていたシルエットが陽炎のように立ち上がる。着物に身を包む、すらりと細身の女性。だが、その全身から放たれるプレッシャーは、包み・塞ぎ・潰すように、あるいは刺し・抉り・削ぐように、俺の体を圧迫する。
――やはり、別格。
全身をつたう、嫌な汗を自覚した。それを知ってか知らずか、《ヤツ》は静かに笑う。
「しかし、ずいぶんと奇妙な縁よな。浄源武久。今まで何度となく殺し合い、そのくせ、成り行き上助け合ったことも何度となくあった」
「ああ」
「ふふふ。何故だろうな。今日はいつになく、妙な気分だ。最後に殺し合うのが貴様であってよかったと、そんなことさえ思う」
「……」
俺は口をついて出そうになった言葉を飲み込んだ。
分かっていたはずだ。
信仰を失い、地脈の供給を絶たれた神は、人に災禍をもたらす存在だと。
ヒトの形を憑代にしたところで、時間稼ぎに過ぎないと。
唇を噛み締める。
《ヤツ》は……罪であり、罰なのだ。
情が移る前に、殺してしまわなかった自分への。
だから俺は、言葉を伝える代わりに……殺す。
「――神呪・退威ノ法。参拾弐式【血煙】」
俺は呟き、呪力を込める。全身から、暗褐色の煙が、滲むように立ち昇った。神を汚し、威を削る力。ヒトに仇なすカミを落とし、滅するために作られた、「浄源」の血族が持つ忌まわしき力。
《ヤツ》は目を細め、そんな俺を見下ろした。
「……交わす言葉はすでにない、か。そうだな。我々はそうだったな。そういう間柄だったな。ふふふ。そんなことさえ忘れていた。良かろう、我もその殺意に応じよう」
俺を見下ろす眼が、みるみる赤く染まっていく。月の光を背にして影になったシルエットに、真紅の瞳が二つ、炯々と輝いた。
「来い、下賎なヒトよ。我が威に平伏し、塵と消えよ」
《ヤツ》が前のめりに構える。それだけで、発する圧力が暴風のように全身を叩いた。
――殺す。
俺はもう一度、確かめるように呟き、地を蹴った。
―。
――。
――――。
ごぼっ、という音が、静寂を破った。
俺たち二人は、同時に後方に飛び退き、距離を取る。
ぱた、ぱたん。
血が地面に滴り、奇妙に捻くれた線を描いた。
体が熱い。緊張していた体の力が、一気に抜けていく。
「勝負、あったな」
「……ああ」
答えると同時に、俺は地面に膝をつき、そのまま崩れ落ちる。
呼吸が早くなる。まるで肺がすぐ喉元にあるようだ。腹から全身に、痺れがゆっくりと広がりはじめた。
「長くはもつまい」
《ヤツ》は、しなやかな指でゆっくりと乱れた髪を整える。体についた傷は、はやくも塞がり始めているようだった。
「……そうだな」
やはり、強い。
ヒトの身では、到底届かないほどに。
「愚か者め。本来の威を取り戻した私に、貴様ごときが敵うはずもないのだ。……前々から、そう言っていただろうが」
「そうだな。どうやら俺の見立ては、想像以上に甘かったらしい」
俺は苦笑する。
「……何がおかしいのだ」
そういう《ヤツ》の眼は、哀しみで満ちていた。
奇妙な構図だ。
敗者が笑い。
勝者が哀しむ。
「お前こそ、なんてツラしてるんだよ。ようやく宿敵を倒し、晴れて自由の身になれるっていうのに」
「……うるさい、馬鹿者が」
《ヤツ》は、苛立つように首を振り……そして、ふっ、と息だけ出して微笑した。
「私の勝ちだな」
「ああ」
「これで私は晴れて、《アラガミ》となれる」
「そうだな」
「辛そうだな。とどめが欲しいか?」
「余計なお世話だ……っていいたいところだが、正直、確かに辛い。頼んでもいいか」
「ああ」
《ヤツ》は微笑み、俺の方へゆっくりと近付いてくる。
腹の傷を押さえている手に力を込めた。体の火照りは、すでに凍えるほどの寒さに変わっている。
もうすぐだ。
もうすぐ、全てが終わる――。
だが、《ヤツ》は俺の少し手前で足を止めた。
何だ? 何を考えている?
俺の混乱をよそに、やつはのんびりと空を見上げ、呟く。
「なあ、武久。今日がなんの日か、知っているか」
「はあ? 一体何を……」
釣られた見上げた夜空を見て、俺は目を見開いた。
空を白い流星が、幾筋も流れている。
それは不思議な光景だった。
《ヤツ》の結界の中は、時間の流れが外界よりも遅くなっている。だから、結界の内側から見る外の流星は、まるで飛行機雲のように悠々と光の尾を引いて、夜空を横切っていくのだ。いくつも、いくつも……。
奇跡のような光景に俺が思わず言葉を失っていると、《ヤツ》がぽつりと言った。
「あのうちのいくつかが、今宵、ここに落ちる」
何……何だって?
言っている意味が理解できなかった、何を、という言葉を言おうとしたが、声が出ない。
《ヤツ》はだが、俺を無視して言葉を続ける。夢見るように、夜空を見上げながら。
「奥の本殿に、そういう陣を組んだ。星降りの呪だ。その威は地を穿ち、木々を薙ぎ、この街に大きな災禍をもたらす。まあ……数万人が死ぬだろう」
「馬鹿な……嘘だろ?」
俺がようやく搾り出した声に、《ヤツ》は振り返る。
ゾッとするほど妖艶な笑みが、そこにあった。
「本当だ。死ぬ。大勢が死ぬ。我はその死者の魂と、生き残ったヒトどもの畏れを食らって、《アラガミ》となる」
「待て。俺は……俺はそんなもので死にたくなんかない。殺すならお前が、お前が直接殺せよ」
必死に訴える俺に、やつは首を振って答えた。
「ならぬ。……貴様、我と刺し違えるつもりであろう。その右手に集まる呪力。必死で隠そうとしたのだろうが……我が気付かぬとでも思うたか」
クソ……クソッ!
俺は重たい体に必死に活を入れ、立ち上がろうともがいた。同時に、腹をおさえていない左手で、ポケットを必死に探る。
取り出した携帯電話。待ち受けには「圏外」と表示されていた。
「無駄だ。分かっておろう。我を殺さねば、我の結界からは出れぬ。いかなる方法を使おうと、外界と連絡も取れぬ」
万策が、尽きた。
「何で……何でだよ!」
俺は、我を忘れて叫んでいた。
「何故? 《アラガミ》がヒトを殺すのに、なんの訳があるというのだ?」
「てめぇ、俺と決着をつけたいんじゃなかったのか。《アラガミ》になるのは、今日この立会いで、俺を殺してからだと、そう言っていたんじゃなかったのか」
「……」
《ヤツ》の表情が曇った。
「ヒトが自分に対する畏れさえ取り戻せばいいって、そう言っていたのもウソだったのか。こんな星クズで街を壊し、お前が愛し、守った土地を汚すのが、お前の望んだ終わり方か!」
「黙れ」
「何故だ! 何故最後になって、こんな裏切り方をする! ヒトとの約束を違えて、何がカミだ! ふざけるな!」
「黙れ!」
俺の体に、眼に見えない縄がびしりと巻きついた。縛りの呪。息がつまり、声を失う。今の俺に、これほどの力を破る呪力はもうない。
それでも俺は、唇を噛み締め、《ヤツ》を睨みつける。その視線を真っ向から受け止めた《ヤツ》は――。しばらくして、目を逸らした。
「惜しくなったのだ」
ぽつりと、言葉を漏らす。
「力を取り戻して、気付いた。我はもう、止められぬ。貴様とやり合えば、殺してしまう。だが、貴様は《浄源》の血族として、決して退かぬだろう。我も同じだ。カミとしての本能は、仇なすものを滅するまで止まらぬ」
《ヤツ》はゆっくりと近付き、俺を見下ろす位置に立った。
「我が貴様を殺せば、その魂は消える。消えてしまう。だが貴様がヒトとして死ねば。我が災禍に巻き込まれて死ぬのならば、その魂は畏れと共に我に喰われ、我の血肉となる」
――ああ。
俺は、理解した。
《ヤツ》が約束を違えた、その理由を。
理解して、しまった。
「たかが……たかが数万人なのだ! 規模は限りなく小さくした。地脈も途切れまい。ヒトなどすぐ増える。土地もすぐ生き返る。そして貴様の魂は……我の一部として生きることができる」
《ヤツ》は屈み込み、俺の頭にそっと手を置く。その手は頭を滑り落ち、ひんやりとしなやかな指が、俺の頬を撫でた。
俺を見つめる《ヤツ》の表情は、もはや災禍をばらまく悪鬼のものでも、威光に溢れた神のものでもない。
「貴様だって……貴様だって、魂ごと滅するのは嫌だろう? 我と共に往こうではないか。魂となってしまえば、敵も味方もない。なあ?」
そこにあったのは、必死に偽りの希望へしがみつく、情けないヒトの女の顔、そのものだった。
「私は……私は貴様を殺したくないんだ……」
彼女は、街と俺を天秤にかけた。
ヒトとしての感情と、カミの理とを天秤にかけた。
そして選んだのだ。
ヒトでも、カミでもない。
《彼女》としての答えを。
「分かってくれ、武久」
頬を撫でた手が、俺の顎をそっと持ち上げる。抵抗できない俺に、彼女はゆっくりと唇を近づけた。
抵抗できない?
いや。
すでに、抵抗する気なんて、失せているのかもしれない。
「共に永遠を生きよう――」
――ああ。
《彼女》は……罪であり、罰なのだ。
情が移る前に、殺してしまわなかった自分への。
そして、ヒトに堕ち、ヒトを知ってしまった、《ヤツ》にとっての――。
どうせ、万策は尽きたのだ。
《浄源》の理も、カミの理も、今だけは関係ない。
このまま、全てを委ねてしまうのも、悪くないかもしれない。
俺は全身の力を抜いた。
だが。
「何だ?……どういうことだ!」
突然、そんな彼女の声と共に、彼女の手が俺から離れた。
「馬鹿な。私の呪が、こんな――」
何故だかわからないが、彼女は酷く焦っている。
全身の拘束が、わずかに緩む。
その瞬間、空っぽだった俺の頭に、ドス黒い本能がなだれ込んだ。
(コロセ)
「……あ」
(コロセ)
(コロセ)
「……うああ、あ」
(アシキカミヲ コロセ!)
「……あああああああああああああッ!」
気がつくと俺は、渾身の力を込めて跳ね起き、腹を抑えていた右手で、彼女の腹をを刺し貫いていた。
「く、くふふ。さっきと、まるで逆だな」
彼女が笑う。
「ああ、そうだな」
俺が答える。
彼女は仰向けに、大の字になって横たわっている。その腹に空いた穴は、もう塞がる様子はなかった。
それを見下ろす俺の傷は、すでに完治している。
「呪と共に、浄源の血そのものをカミに打ち込み、その威を取り込む……。なるほど、凄まじい業だ」
「……」
「だが、威は取り込めても、カミの魂までは取り込めなかった。アテが外れたな? 武久」
そう言って彼女はまた、愉快そうに笑う。
「カミの魂が、ヒトごときの器に収まるとでも思ったか、阿呆め」
「うるせえよ」
俺はそう言って、足元の土を蹴った。
「……何事も、そうそう上手くはいかぬものよな。我も、貴様も」
彼女の言葉を聞き流し、俺は社の裏手に広がる山を見上げる。その中腹に、大きな火の手が上がっていた。結界越しに見る炎は、巨人がゆっくり手を振っているようにも見える。
「まさか、山火事とはな」
ぽつりと呟く。
タバコのポイ捨てか、あるいは焚き火の不始末か――。とにかく、その炎は山の中腹にあった本殿近くを焼き、彼女が張っていた星降りの陣を崩した。
この街は、救われたのだ。
「偶然に助けられたな、武久」
「神様は見てんのさ」
「くくっ、カミに向かってそれを言うか」
彼女はまた笑うと、少し苦しそうに顔を歪めた。俺はそれを……見ないようにする。
「だが……。そうもしれんな。かくて悪しきカミの野望は絶たれ、正義は成った、というところか」
「やめろよ」
「思えばどうもここ六十年ほどは……くく、世俗の言い方をすれば、まったくツいておらぬ。ヒトどもはどんどん我を忘れ、自我は薄まり、苦し紛れにヒトを憑代にしてみれば、世俗の暮らしに馴染めず苦労続き……」
「やめろって」
「おまけに貴様のような疫病神に狙われるわ、ヒトに堕ちたせいで、雑音のような瑣末な感情に悩まされるわ。ようやくこの面倒から解放されると思えば、いっそせいせいするかもしれんな」
「だから、やめろって。神様が卑屈になってんじゃねえよ」
俺は屈み込み、彼女の頬を撫でた。その手に、彼女は自分の手を重ね、微笑んだ。
「ずいぶん優しいな。我も奥の手を隠しているかもしれんぞ?」
「馬鹿言ってんじゃねえ。お前に余力がねえのは、俺が一番知ってる」
そうだ。
俺自身が一番分かっていた。
彼女にもう力は残っていない。
この世に留まり続ける力すら。
彼女の腹の傷がじわじわと広がり、彼女の体を飲み込んでいく。
彼女が、俺の手を強く握った。
俺も、強く握り返す。
「なあ、武久」
「なんだよ」
「ああは言ったが、我はこのヒトとしての人生、これでなかなか、満足だったぞ」
「……そうかよ」
彼女の足が消える。
「くくっ、俗世にも変わりものがいてな、我のような女に好意を向けてくれるやつもおったのだ。ちょうど貴様くらいの年齢だったかな。我のアパートに下宿しておるのだ」
「……へえ」
「ヤツには随分と月見酒に付き合わせてしまったな。何だかんだとついて来るから、アレでなんだか憎めなくてなあ。今日も貴様が来る前に、しこたま飲ませてやったわ」
「お前みたいな危険人物に付き合わされるほうも、たまったもんじゃねえだろうな」
「嫉妬か?」
「違ぇーよ」
彼女の腰が消える。
「ふふ。まあ確かに、貴様とは違う意味で、ヤツもまた我にとって特別だった。……そうだ。ヤツに合ったら伝言を頼めるか」
「……なんて伝えればいい?」
「『私の財産、全部譲る』」
「は?」
「『必要な書類は全部、管理人室の引き出しに入れてる』とも伝えてくれ」
「あのなあ……。そんなこと突然言われたって、向こうも混乱するだけだろうが」
「そこは何とか、上手く言いくるめておいてくれ」
「随分と無茶振りだな」
「貴様は我の婚約者でも名乗るとよかろう」
「アホか」
「なんだ、つれない男だな」
彼女の胸が消える。
「……なあ」
「なんだよ」
「お互いに、同じことを考えていたのだな。我は貴様の魂を食らおうとし、貴様は我の魂を取り込もうとした」
「……そうだな」
「貴様も我に、消えてほしくなかったのか?」
「違ぇーよ。ただ……ほら、付き合いも何だかんだで長いし、単に滅するにはもったいって、そう思っただけだ」
「くくっ、あの業、正統なものではなかった。カミの魂を取り込むことはできないと知っていて、改良を加えたのだろう」
「……」
「違うか? 武久」
「……」
「武久。答えてくれ」
握り合った手が、消え落ちる。
「ああ、そうだよ」
「何故だ?」
「……チッ。そうだよ。俺も、お前に消えてほしくなかった」
「そうか」
彼女は笑った。
「それを知れただけで満足だ」
「お前が言わせたようなもんだろ」
「何だ、嘘なのか?」
「……そういうわけじゃねえけど」
「武久」
「何だよ」
「ヒトというのは良いものだな」
「そうかよ」
「感情というものを、分け合える。相手が想ってくれるという事実だけで、こんなに幸せな気持ちになれる」
「……」
「それを知れただけで、我は満足だ」
「……だからやめろよ、そういうの」
「だから武久」
「何だよ」
「泣くのを止めろ。別れが辛くなる」
「うるせえな」
俺は拳を握り締める
「止めたくたって止められねえんだよ、バカ野郎」
「……そうか」
彼女の肩が消える。
「……そういうのもまた、嬉しいものだな」
彼女の眼が閉じられる。
消えるな。
いかないでくれ。
思わずそう叫びそうになって、俺は必死で自制する。
俺が彼女を殺しておいて、どの口がそれを言えるんだ。
崩れていく彼女の口が、微かに動いた。
「名前を……名前を、呼んでくれ」
俺は鼻水を啜り上げ、裏返りそうになる声を必死に抑えながら、声を絞り出す。
カミでもなく、ヒトでもない。その狭間に生きた《彼女》の名前。
「小雪」
彼女は微笑んだ。
「なぁに?」
一陣の風が吹く。
そして――全てが終わった。
俺は目を拭い、呼吸を必死で整える。
もうすぐ、彼女が作った結界も解けるだろう。
俺は胸の中で自問する。
これでよかったのか。
彼女を救うことは、結局出来なかった。
共に生きることも。
それどころか、俺が今までしてきたことは、結果として守るはずの街を危機に晒すことになった。
街が救えたのは、ただの偶然だ。
俺は間違ったことをした。客観的に見れば、そうなんだろう。
でも……。
『我は満足だ』
彼女の声が蘇る。
「俺も満足だ」
俺も呟く。
それで充分だといったら、勝手すぎるだろうか。
そのくらいの我侭は、許してもらえないだろうか。
もう、涙は止まった。
これで終わりじゃない。また新たな戦いの日々が始まるのだ。
俺は境内の入口に向かって歩き出し……。
そして足を止めた。
誰かが立っている。
俺は素早くあたりを見回した。まだ結界は解けていない。
人影は、結界のちょうど境界に立っているようだ。
結界は、招かれたもの以外には入れず、また見えない。
結界の外から見たところで、そこには誰もいない境内があるだけだ。
だが……。
俺の背筋に寒気が走る。
こいつ……見えてないか?
それは少女のような《モノ》だった。
歳は十四、五歳といったところだろうか。なんというか、和風の顔立ちをしている。
黒焦げのボロを身をまとい、裸足だった。
だが、明らかな異様を放っているのは、その眼だ。
限界まで見開かれた眼球は、おおよそヒトのサイズを超えている。そこから放たれる視線は《邪視》と呼ぶに相応しい、強烈な禍々しさを持っていた。
その視線が今、はっきりとした意志を持って、俺に向けられている。
先に彼女と対峙したときとは明らかに質の異なる圧力が、俺を襲った。
例えるなら、全身の毛穴に入り込んで、内臓を食い荒らされるような。
皮膚からしみこみ、神経を冒されるような……。
「ミツケタ」
少女が甲高い声で呟いた。
……すべての音を遮断するはずの、結界を越えて。
「ミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタミツケタ」
ビシィ。
限界が来たのか、あるいは、彼女の邪視が砕いたのか、ひび割れ消えていく結界を見ながら、俺は思わず臨戦態勢を取っていた。
ヒトではない。
だが、カミでもない。
妖でも、精霊でも、幽霊でもない。
……なんだ?
……なんなんだ? コイツは。
「アタシノコイ ミツケタ」
ゆらゆらと、踊りのような奇妙な動きを混ぜつつ、《ソレ》は近付いていくる。
連戦。それも得体の知れない相手。だが俺は、不思議と落ち着いていた。
体に満ちるこの力。彼女から……小雪から受けついだもの。
「悪いが今は、誰にも負ける気がしねぇな」
俺は不敵に笑ってみせる。《ソレ》は気分を害したのか、顔を紅潮させて突っ込んできた。
時の流れが戻った夜空を、幾筋もの流星群が駆けて行く。
「――神呪・退威ノ法。参拾弐式【血煙】」
俺の体から、真紅の煙が滲み出す。
――共に行こう。
俺は胸の中に浮かぶ笑顔に向けて呟き、強く地を蹴った。
210 ~シェアワールドアンソロジー~
9.「ぼくのかんがえたさいきょうのヤンデレ」