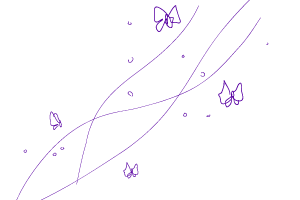オピオイドの繭
二章「キングス・オブ・ニューイングランド」
プスン、プススン、プススプスン。
「エンジンが、プスンプススン、プススプスン」
字余りだしこれじゃ季語がないな、とおどけていられるほど、武藤少年の置かれている状況は甘くなかった。
「雨は降れども、メーターの針は振れず」
途中から考えるのをやめた下の句を吐き出し、武藤は溜め息を一つ吐く。
空は曇天、雨は猛烈。
終わる世界へお遍路の旅に出た二人を運ぶ命の綱、原動機付き自転車が早くも音を上げた。どれだけエンジンをかけてもプスプス笑うだけで、マフラーを震わせて駆動することはない。かれこれ小一時間は粘っているが一向に事態は進展せず、少年の精神だけがごりごり削られていた。
「参ったな……まさかこんなに早く壊れてしまうだなんて」
この原付は旅に出る少し前、繭化してしまいそうだったのを武藤が見つけ、なんとか動くまでに回復させた代物だ。古いものには見えなかったのでしばらくは持つだろうと考えていたが、甘かった。繭化こそしていなかったが、内部の機構が恐らく異常をきたしている。素人の武藤では到底直せるとは思えなかった。
顔を油で黒く汚したまま、はあ、と武藤は転がった一斗缶に腰掛ける。
ガレージを出てから、三日が経つ。
男が蓄えていた食料のおかげで、二人は衣食住のうち食はそれなりに満足のいく生活を送っていたが、残りの二つに関しては当然不満が残る。衣服の替えは一日分しかなく、寝泊りも手ごろなベンチを探してその上に寝るしかない。四日目の今夜に至ってはあいにくの土砂降りで、なんとか公園らしきものを見つけて、そこの東屋で一休みしていた。恐らく今日の宿は、ここになるだろう。
雨か、と武藤は呟く。
「僕らの旅において、雨は天敵なんだよなあ」
服は濡れる、その所為で風邪は引く、焚き火がおこしにくければ、散歩も出来ない。挙句の果てに原付はすっかり機嫌を損ねてしまった。明日の朝もこの雨の調子だともはやお手上げ状態だ。
懊悩する武藤を余所に、明穂はベンチの上で寝息を立てている。
珍しく文句を言わず寝ている明穂も、武藤の懸念事項の一つだった。
雨が降り出したのは東屋に着く三〇分程前だったので、それまでは雨を全身に受けながら原付を飛ばしたわけである。武藤は服が濡れる程度で大した被害はなかったのだが、問題は明穂だった。
武藤は、少し苦しそうに息をする明穂の額に手を当てる。
「……うーん、思わしくないな」
微熱を感じ、明穂の毛布をキチンと掛け直す。
ここにきて明穂が、体調を崩してしまったのだ。
明穂の性格上、雨が降っても構わず原付を走らせろと武藤を煽りそうなものだったが、今日はどこかで休みたいと武藤の背中に告げていた。鈍感な武藤でもさすがにこの異変にはすぐに気付き、同時に原付の異変も覚えながら東屋に何とか辿り着いたというわけだった。
天候、相棒、移動手段。
全てが最悪の状況の中、武藤は必死に思考を巡らせていた。
「大丈夫だ。地図を信用するなら、あと少し南に向かえば集落があるはず。そこへ行けば薬もあるだろうし、原付を直す手段だってあるかもしれない。そこへ行ければ……きっとなんとかなる」
明穂を見遣る。苦しそうにうなされていて、連れて行けそうにない。ならば、ここに明穂を置いて自分だけで集落まで走ろうか。そうも考えたが、病人を放置してどれくらいかかるかも分からない旅路を走る勇気はない。
ならば、このままじっと待機するか。
しかし、明穂の容体が自然と良くなる保障はなく、雨が止む可能性も高いとは言えず、原付が息を吹き返す未来も今のところ見えてこない。可能性を探る度、詰将棋のようにどんどん選択肢が削られていって、終には考えが尽きてしまった。
どうすれば、どうすればいい。
騒がしい雨のノイズが思考回路をかき乱す。
妙案が全く思い浮かばず、思わず武藤はがしゃがしゃと頭を掻いた。
まさかこんなところで旅を諦めたくはない。自分の唱える、繭化の原因とその予防法。それを一人でも多くの人に知らせたい武藤としては、限界まで旅を続けていたかった。何よりも、明穂と共に旅をしていたかった。
だって明穂は、武藤の――――
「……ダメだ、こんなことを考えている場合じゃない」
状況は刻一刻と悪くなっているのだ。
武藤は両頬をペチペチ叩き、己を叱咤激励する。今出来る最低限のことで、生き繋いでいくしかない。そう考えた武藤はとりあえずリュックの中身を整理しようと、リュックを縛り付けてある原付に目を遣った。
そして。
「あ――――――」
その瞬間武藤は、明穂以外のヒトの存在に、気が付いた。
雨音に紛れて、完全に気配を消していた、その影。
「それ」は、リュックが紐で縛りつけられている原付に忍び寄って、何かをまさぐっていた。
「やべっ…………!」
目線に気付いたのか、影は小さく呻き、公園の茂みへと消える。
それを見て、反射的に武藤は立ち上がった。
「こ、んの野郎!」
怒声を聞き、ガサガサと音を立てて雨の降る公園の雑木林に消えていく影。
武藤はその後を追おうとしたが、横目に明穂の姿が入って、東屋から飛び出すという所で留まった。
忌々しげに舌打つ武藤。急いでリュックを確認する。
「……くそ、因果応報って奴なのか?」
リュックは僅かであるが、被害に遭っていた。
食料品であったスパム缶が、三つほど無くなっている。
「ロクなこと考えてない奴が、ここにもいるってことか」
武藤は公園を見渡す。途端に背筋をなぞられるような、気味の悪い寒気が身体を走る。
この公園には、何者かが潜んでいるのだ。
武藤と明穂を付け狙う、何かが。
「エンジンが、プスンプススン、プススプスン」
字余りだしこれじゃ季語がないな、とおどけていられるほど、武藤少年の置かれている状況は甘くなかった。
「雨は降れども、メーターの針は振れず」
途中から考えるのをやめた下の句を吐き出し、武藤は溜め息を一つ吐く。
空は曇天、雨は猛烈。
終わる世界へお遍路の旅に出た二人を運ぶ命の綱、原動機付き自転車が早くも音を上げた。どれだけエンジンをかけてもプスプス笑うだけで、マフラーを震わせて駆動することはない。かれこれ小一時間は粘っているが一向に事態は進展せず、少年の精神だけがごりごり削られていた。
「参ったな……まさかこんなに早く壊れてしまうだなんて」
この原付は旅に出る少し前、繭化してしまいそうだったのを武藤が見つけ、なんとか動くまでに回復させた代物だ。古いものには見えなかったのでしばらくは持つだろうと考えていたが、甘かった。繭化こそしていなかったが、内部の機構が恐らく異常をきたしている。素人の武藤では到底直せるとは思えなかった。
顔を油で黒く汚したまま、はあ、と武藤は転がった一斗缶に腰掛ける。
ガレージを出てから、三日が経つ。
男が蓄えていた食料のおかげで、二人は衣食住のうち食はそれなりに満足のいく生活を送っていたが、残りの二つに関しては当然不満が残る。衣服の替えは一日分しかなく、寝泊りも手ごろなベンチを探してその上に寝るしかない。四日目の今夜に至ってはあいにくの土砂降りで、なんとか公園らしきものを見つけて、そこの東屋で一休みしていた。恐らく今日の宿は、ここになるだろう。
雨か、と武藤は呟く。
「僕らの旅において、雨は天敵なんだよなあ」
服は濡れる、その所為で風邪は引く、焚き火がおこしにくければ、散歩も出来ない。挙句の果てに原付はすっかり機嫌を損ねてしまった。明日の朝もこの雨の調子だともはやお手上げ状態だ。
懊悩する武藤を余所に、明穂はベンチの上で寝息を立てている。
珍しく文句を言わず寝ている明穂も、武藤の懸念事項の一つだった。
雨が降り出したのは東屋に着く三〇分程前だったので、それまでは雨を全身に受けながら原付を飛ばしたわけである。武藤は服が濡れる程度で大した被害はなかったのだが、問題は明穂だった。
武藤は、少し苦しそうに息をする明穂の額に手を当てる。
「……うーん、思わしくないな」
微熱を感じ、明穂の毛布をキチンと掛け直す。
ここにきて明穂が、体調を崩してしまったのだ。
明穂の性格上、雨が降っても構わず原付を走らせろと武藤を煽りそうなものだったが、今日はどこかで休みたいと武藤の背中に告げていた。鈍感な武藤でもさすがにこの異変にはすぐに気付き、同時に原付の異変も覚えながら東屋に何とか辿り着いたというわけだった。
天候、相棒、移動手段。
全てが最悪の状況の中、武藤は必死に思考を巡らせていた。
「大丈夫だ。地図を信用するなら、あと少し南に向かえば集落があるはず。そこへ行けば薬もあるだろうし、原付を直す手段だってあるかもしれない。そこへ行ければ……きっとなんとかなる」
明穂を見遣る。苦しそうにうなされていて、連れて行けそうにない。ならば、ここに明穂を置いて自分だけで集落まで走ろうか。そうも考えたが、病人を放置してどれくらいかかるかも分からない旅路を走る勇気はない。
ならば、このままじっと待機するか。
しかし、明穂の容体が自然と良くなる保障はなく、雨が止む可能性も高いとは言えず、原付が息を吹き返す未来も今のところ見えてこない。可能性を探る度、詰将棋のようにどんどん選択肢が削られていって、終には考えが尽きてしまった。
どうすれば、どうすればいい。
騒がしい雨のノイズが思考回路をかき乱す。
妙案が全く思い浮かばず、思わず武藤はがしゃがしゃと頭を掻いた。
まさかこんなところで旅を諦めたくはない。自分の唱える、繭化の原因とその予防法。それを一人でも多くの人に知らせたい武藤としては、限界まで旅を続けていたかった。何よりも、明穂と共に旅をしていたかった。
だって明穂は、武藤の――――
「……ダメだ、こんなことを考えている場合じゃない」
状況は刻一刻と悪くなっているのだ。
武藤は両頬をペチペチ叩き、己を叱咤激励する。今出来る最低限のことで、生き繋いでいくしかない。そう考えた武藤はとりあえずリュックの中身を整理しようと、リュックを縛り付けてある原付に目を遣った。
そして。
「あ――――――」
その瞬間武藤は、明穂以外のヒトの存在に、気が付いた。
雨音に紛れて、完全に気配を消していた、その影。
「それ」は、リュックが紐で縛りつけられている原付に忍び寄って、何かをまさぐっていた。
「やべっ…………!」
目線に気付いたのか、影は小さく呻き、公園の茂みへと消える。
それを見て、反射的に武藤は立ち上がった。
「こ、んの野郎!」
怒声を聞き、ガサガサと音を立てて雨の降る公園の雑木林に消えていく影。
武藤はその後を追おうとしたが、横目に明穂の姿が入って、東屋から飛び出すという所で留まった。
忌々しげに舌打つ武藤。急いでリュックを確認する。
「……くそ、因果応報って奴なのか?」
リュックは僅かであるが、被害に遭っていた。
食料品であったスパム缶が、三つほど無くなっている。
「ロクなこと考えてない奴が、ここにもいるってことか」
武藤は公園を見渡す。途端に背筋をなぞられるような、気味の悪い寒気が身体を走る。
この公園には、何者かが潜んでいるのだ。
武藤と明穂を付け狙う、何かが。

夜になっても、雨はまだ静かに降り続いていた。
勢いは幾らか落ち着いたように見えるが、遠くがうすら曇る程度には降っていて、傘もなく彷徨けばきっとすぐにずぶ濡れになってしまうだろう。よっぽど身体が汚れていない限り、こんな中に飛び込む者などいない。
だから、雨降りの草叢というのは「少年」が身を隠すのにはうってつけだった。
少年は息を殺して、草叢の隙間から顔を出す。
東屋だ。目の前にはこの公園の東屋がある。
そしてその中にあるベンチには、誰かが毛布をかけて眠っている。男と女、二人いるようだった。傍には、荷物が括りつけられた原付が停められている。男の独り言を聞いていた少年は、その原付が故障していると分かっていたので、今更それを盗む気にはなれなかった。
再び狙っているのは、ロープで結わえ付けられているリュックサックの方だ。
先刻は男がまだ起きていたので、まともに盗みを働くことが出来なかったが、その男も今は寝息を立てている。少年にとって、これは稀に見るチャンスだ。
リュックの中には食料品が多く入っていた。あれを手に入れられれば、どれだけ幸福だろうか。
少年はゆっくりと深呼吸して、雨音が耳に入らなくなるほど集中する。
手元には錆びついたサバイバルナイフ。これでロープを切って、リュックごと荷物を盗む。もし男か女どちらかが目覚めたら、ナイフを使って脅しでもかければいい。そんな風に考えていた。
雨の勢いが少し強くなる。
今の内だ、と空が囁いた気がした。
直後、少年は疾駆した。
裸足で駆ける音は雨に打ち消され、さながら暗殺者のように少年は原付に向かって真っ直ぐに駆け抜けた。
一〇メートル、五メートル。その距離はみるみる縮まって行く。
そして、少年の持つナイフの刃が、荷物を括っているロープに向かって――――
「駄目だよ、味をしめてしまっては」
声が聞こえると同時に、少年は自分の身がふわりと宙に浮かぶのを感じた。
いや、違う。そう錯覚してしまっただけだ。どこからか男の声が聞こえたかと思うと、少年の身体は想定していた走路から大きく軸を外れて、原付の右斜め前に放り出された。
うわっ、と呻き声を上げて、少年の身は東屋の硬い石床を転がる。視界が転と揺らいだせいで、ぐわんぐわんと頭に痛みが走る。その逆かもしれない。少年の思考回路は、不意を突かれた所為で混乱していた。どこかに潜んでいた男に、思い切り突き飛ばされた。そう考えられるまでには、数秒ほど時間を要した。
ごろごろ転がった身体は、仰向けになって空を見る。
東屋の軒先から落ちる雨垂れが額を打った。それが微かに沁みた。額を擦りむいたようだった。
「他人の生命線を断りもなく奪うのは感心しないね」
視界の隅に、男の影が映る。
ああ、千載一遇のチャンスを逃してしまった。
少年はじくりと広がる痛みを感じながら、そんな風に考えた。
○
雨が止み始めて、世界に無音が戻りつつあった。
「生きるためには、奪うしかない」
少年は脱いだ衣服を乾かしながら言った。
湿気った薪では火をつけるのに幾分苦労したが、少年の手も借りて東屋には小さな明かりが灯った。
東屋の中には、田圃の地図記号を縦に並べたように四つのベンチがある。その一つには毛布を掛けられて明穂が眠っていて、武藤と少年は互いにベンチに座り、向かい合う形で火をおこした。
「こんな世界で生きていくためには、犯罪じみたことも平気で出来るようにならないといけないんだ」
「ほい。君も一つ食べるかい?」
武藤は蓋を開けたスパム缶を、少年に向かって差し出した。
このスパム缶は、少年が武藤から盗んだものだ。少年は眉をひそめる。
「それ、俺が盗んだものだろ。なんで」
「ああ。これは君が盗んだ物だ。返してもらったけど、盗んだ時点で所有権は君にある」
武藤はにっと笑う。
「そういう世界、なんだろ?」
「……変な人だな、アンタ」
「よく言われるよ」
互いに小さく笑い、武藤と少年はスパムを口にした。
武藤はあっという間に平らげたが、少年は何かに気を遣っているのか、半分ほどで手を止めた。
「なあ、アンタ」
「僕はアンタって名前じゃない。武藤だ」
「……武藤サン。この残ったスパム、貰ってもいいかな」
「貰うも何も、所有権は君だと言った筈だ」
雨水で缶を洗いながら、武藤は少年のことを見る。
その、何かを憂えているような表情には、幾らか心当たりがあった。
「さしずめ、腹を空かせている待ち人が居るってところだろ? 持って行ってあげなよ」
「! どうしてそれを……」
驚いて目を丸くする少年に、武藤は人の良い笑みを向けた。
「悲しいかな、人の機微には敏感になってしまってね。気まぐれ暴力少女と接してきた所為だとは思うけど」
「誰が気まぐれ暴力少女だって?」
「誰だなんてそんな無粋なことを言うなよ明穂。それはもちろん明……」
は、と武藤は口を止めて、ロボットのように顔を恐る恐る横に向けた。
瞬間、目を覚ました明穂のローリングソバットが武藤のこめかみにクリーンヒットして、武藤は「おふぅ」と情けない叫び声を上げながら漫画のように吹っ飛び、近くの草叢に頭から突っ込んだ。
「やあ明穂、その様子だと快復したみたいだね。良かった良かった」
「風邪なんて寝れば完治するわよ。あんまり私を甘く見ないで」
「ドラ○エの宿屋でも状態異常は治してくれないというのに、凄いね明穂は。ところで相談がある」
ふらつく意識で武藤は言う。
「逆に今度は僕のほうがダメージを負ったみたいなんだけど」
「クノー」
「さしずめ、『くたばれ無能な武藤』?」
「残念。正解は『クソ喰らえ無能な武藤』」
なんて酷い言われようなんだろう。
どくどく頭が脈打つのを感じながら、武藤は独りごちた。
「何なんだこの人達……」
少年は緊張感に欠ける二人を眺めながら呟いた。
それから少しだけ他愛のない話をして、少年は再び夜闇の中へ消えて行った。
武藤はその後ろ姿を追うことなく、焚き火を消す作業に取り掛かっていた。
「ねえ、武藤」
「何だい、明穂」
明穂は冗談なしに尋ねる。
「あの少年、何だか君に似てない? もちろん今じゃなくて、昔の」
「……悪い冗談だよ、明穂」
明かりが消える。
さああ、と鳴く止みかけの霧雨に、二人の会話は溶けていく。


一夜明けて少年が二人を案内したのは、公園に生い茂る雑木林。
かなり緑の多い公園のようで、少年の案内がなければ迷いそうなほど林の中は入り組んでいる。今朝は晴れているので視界は明瞭だったが、昨晩のような雨降りだとどう足掻いても迷うだろう。武藤はそんな感想を持った。
「試しに明穂を置いて行ってみようか。あの東屋まで戻ってこれたら明穂の勝ち」
「その傷口をもっと広げたいのならやってあげてもいいけど」
「わお、それは御免被りたいね」
臨戦態勢を取る明穂を見て、武藤は包帯を巻いた頭を擦る。これ以上傷めつけられては堪らない。
「それにしても自分でつけた傷に自分で包帯を巻くなんて、明穂のアメとムチには驚いたものだよ」
「そりゃ、馬車の馬がいなくなったら困るでしょ」
「ほっほー、そう来たかい明穂。今日は冗談が冴え渡ってるね」
頭を打って(蹴られて)若干ハイテンションな武藤。それを煽っていく明穂。
そんな二人を振り返りながら、少年は呆れて溜め息を吐いた。
「アンタら、本当に緊張感がないな……」
少年から見れば二人は異常だった。
今現在、『繭化』によって世界は間違いなく終焉に向かいつつある。恐らくは、誰もが絶望しか抱かないだろう世界だ。今更楽しい気分になろうとは思えず、少年は生きていくだけで精一杯だった。
しかし、武藤と明穂は違った。
この二人は明日死ぬかもしれない恐怖に怯えることなく、挙句の果てには昨晩から終始ふざけ合っている様子が見られた。例えるなら、戦争が始まっている中でのんびりとお茶でも飲んでいるかような印象。
「そういう君は、少し強張り過ぎだと思うよ」
武藤は手近にあった木の枝を手に取り、ぴっと少年を指す。
「世界が終わるみたいな懸命な判断ができるなら、その残りの時間を最大限に楽しむ程度の思考は持たないとやっていけないよ。小難しいことで悩んでいる間にも、刻々と時間は過ぎていくんだ。大事なのは遊び心だよ」
「遊び心」
「そう、遊び心だ」武藤は木の枝で地面をガリガリと削った。
「少年の事情は良く知らないけど、僕たちもそれなりにヘヴィな過去を抱えてる。だからこそ世界が終わるなんてことぐらいじゃ動じないし、生きることに対して躍起になることもない。ただ貪欲なだけだ」
「貪欲に、生きる」
「そう。貪欲に生きる」
木の枝がぽき、と折れる。
「そのうち少年にも分かってくることだと思うよ」
武藤はにっと微笑んだ。
少年は不思議そうに眉をひそめたが、何も言わずに前を向いて、歩き続けた。
「ここだ」
少年が二人を連れてきたのは、雑木林の奥にある開けた場所だった。
「へえ……こんな所があったとは」
武藤は感慨深そうに唸る。
さすがに公園自体よりは狭かったが、それでも十数人が囲って食事をしたりするには十分過ぎるほどの広さだ。
特別何かを設えられている様子は見られず、単に林の中にある空間と言った印象だが、その空き地の隅っこには大きなキャンピングカー、それもなかなか新し目のものが乗り捨てられていた。
少年はそれに近寄りながら言う。
「俺達の根城みたいなもんだ。他に連れてきたのはアンタ達ぐらいだよ」
「なるほど、ご招待にあずかり光栄です少年殿」
巫山戯た口調で言う武藤に、少年は返す言葉が見つからず、そのまま歩いて車に乗り込む。
「ちょっと待っててくれ」
少年はそうとだけ言って、付いていこうとする二人を手の平で制止した。
残された武藤と明穂は、キャンピングカーを睨めあげるように眺める。
武藤はキャンピングカーの質を見極められるほど目は肥えていなかったが、それにつけてもこのキャンピングカーは高価なものだとすぐに分かった。積載量もなかなか多そうで、食料もかなり備蓄できそうだ。さぞかし居心地は良いだろう。
「立派な車ね。さすがにガソリンがなければ暖房とかそういうのは使えなさそうだけど、ねぐらにはもってこいって言ったところかしら」
明穂が羨ましげに言う。武藤もこれには同意した。
「そうだね。それに車なら中から鍵もかけられるだろうから、安心して寝ることが出来そうだ」
「まあ、そんなの今更必要とも思わないけどね」
二人は旅に出てから、毎日野宿をしてきた。だから別に今更、安全な場所で寝ようとも思わなかった。
だが、より良い環境がそこにあるのなら話は別だ。
「……奪えないかしら」
「明穂はすぐ物騒な発言をするね。だからすぐにガサおぶぅ」
鳩尾に裏拳(1Hit)。
「ま、まだ何も言ってないじゃないか。これは不当な暴力だよ。控訴だ控訴」
「じゃあ、ガサの後はなんて言おうとしてたのかな。教えてくれるかしら?」
「え? あ、いや、それはだね……」
ウーン、と武藤は言葉に詰まる。「ガサツだ」と正直に言うと、もう一発鉄拳を喰らうのは確実だろう。
「……ガサ入れ、かな」
裏拳(2Hit)。逃げ道など無かった。
「待たせたな、二人とも」
武藤が下腹部を抑えて蹲っていると、少年が車のドアを開けた。
ちょっとタイミングが遅かったな、と思いながら武藤は俯いていた頭を上げる。
そして。
「初めまして。兄が、ご迷惑をお掛けしました」
両足のない少女が、車椅子に乗っているのを目の当たりにした。
かなり緑の多い公園のようで、少年の案内がなければ迷いそうなほど林の中は入り組んでいる。今朝は晴れているので視界は明瞭だったが、昨晩のような雨降りだとどう足掻いても迷うだろう。武藤はそんな感想を持った。
「試しに明穂を置いて行ってみようか。あの東屋まで戻ってこれたら明穂の勝ち」
「その傷口をもっと広げたいのならやってあげてもいいけど」
「わお、それは御免被りたいね」
臨戦態勢を取る明穂を見て、武藤は包帯を巻いた頭を擦る。これ以上傷めつけられては堪らない。
「それにしても自分でつけた傷に自分で包帯を巻くなんて、明穂のアメとムチには驚いたものだよ」
「そりゃ、馬車の馬がいなくなったら困るでしょ」
「ほっほー、そう来たかい明穂。今日は冗談が冴え渡ってるね」
頭を打って(蹴られて)若干ハイテンションな武藤。それを煽っていく明穂。
そんな二人を振り返りながら、少年は呆れて溜め息を吐いた。
「アンタら、本当に緊張感がないな……」
少年から見れば二人は異常だった。
今現在、『繭化』によって世界は間違いなく終焉に向かいつつある。恐らくは、誰もが絶望しか抱かないだろう世界だ。今更楽しい気分になろうとは思えず、少年は生きていくだけで精一杯だった。
しかし、武藤と明穂は違った。
この二人は明日死ぬかもしれない恐怖に怯えることなく、挙句の果てには昨晩から終始ふざけ合っている様子が見られた。例えるなら、戦争が始まっている中でのんびりとお茶でも飲んでいるかような印象。
「そういう君は、少し強張り過ぎだと思うよ」
武藤は手近にあった木の枝を手に取り、ぴっと少年を指す。
「世界が終わるみたいな懸命な判断ができるなら、その残りの時間を最大限に楽しむ程度の思考は持たないとやっていけないよ。小難しいことで悩んでいる間にも、刻々と時間は過ぎていくんだ。大事なのは遊び心だよ」
「遊び心」
「そう、遊び心だ」武藤は木の枝で地面をガリガリと削った。
「少年の事情は良く知らないけど、僕たちもそれなりにヘヴィな過去を抱えてる。だからこそ世界が終わるなんてことぐらいじゃ動じないし、生きることに対して躍起になることもない。ただ貪欲なだけだ」
「貪欲に、生きる」
「そう。貪欲に生きる」
木の枝がぽき、と折れる。
「そのうち少年にも分かってくることだと思うよ」
武藤はにっと微笑んだ。
少年は不思議そうに眉をひそめたが、何も言わずに前を向いて、歩き続けた。
「ここだ」
少年が二人を連れてきたのは、雑木林の奥にある開けた場所だった。
「へえ……こんな所があったとは」
武藤は感慨深そうに唸る。
さすがに公園自体よりは狭かったが、それでも十数人が囲って食事をしたりするには十分過ぎるほどの広さだ。
特別何かを設えられている様子は見られず、単に林の中にある空間と言った印象だが、その空き地の隅っこには大きなキャンピングカー、それもなかなか新し目のものが乗り捨てられていた。
少年はそれに近寄りながら言う。
「俺達の根城みたいなもんだ。他に連れてきたのはアンタ達ぐらいだよ」
「なるほど、ご招待にあずかり光栄です少年殿」
巫山戯た口調で言う武藤に、少年は返す言葉が見つからず、そのまま歩いて車に乗り込む。
「ちょっと待っててくれ」
少年はそうとだけ言って、付いていこうとする二人を手の平で制止した。
残された武藤と明穂は、キャンピングカーを睨めあげるように眺める。
武藤はキャンピングカーの質を見極められるほど目は肥えていなかったが、それにつけてもこのキャンピングカーは高価なものだとすぐに分かった。積載量もなかなか多そうで、食料もかなり備蓄できそうだ。さぞかし居心地は良いだろう。
「立派な車ね。さすがにガソリンがなければ暖房とかそういうのは使えなさそうだけど、ねぐらにはもってこいって言ったところかしら」
明穂が羨ましげに言う。武藤もこれには同意した。
「そうだね。それに車なら中から鍵もかけられるだろうから、安心して寝ることが出来そうだ」
「まあ、そんなの今更必要とも思わないけどね」
二人は旅に出てから、毎日野宿をしてきた。だから別に今更、安全な場所で寝ようとも思わなかった。
だが、より良い環境がそこにあるのなら話は別だ。
「……奪えないかしら」
「明穂はすぐ物騒な発言をするね。だからすぐにガサおぶぅ」
鳩尾に裏拳(1Hit)。
「ま、まだ何も言ってないじゃないか。これは不当な暴力だよ。控訴だ控訴」
「じゃあ、ガサの後はなんて言おうとしてたのかな。教えてくれるかしら?」
「え? あ、いや、それはだね……」
ウーン、と武藤は言葉に詰まる。「ガサツだ」と正直に言うと、もう一発鉄拳を喰らうのは確実だろう。
「……ガサ入れ、かな」
裏拳(2Hit)。逃げ道など無かった。
「待たせたな、二人とも」
武藤が下腹部を抑えて蹲っていると、少年が車のドアを開けた。
ちょっとタイミングが遅かったな、と思いながら武藤は俯いていた頭を上げる。
そして。
「初めまして。兄が、ご迷惑をお掛けしました」
両足のない少女が、車椅子に乗っているのを目の当たりにした。

○
少年は名を、ナオキと名乗った。
「ということはつまり」武藤はナオキが取り出した折りたたみ椅子に腰掛けながら言う。「君たち兄妹も、生まれ育った街が繭化によって壊滅状態に陥ったから、こうして世界の終わりに逃避行をしているわけだね」
「つっても、アンタらみたいに原付でひとっ走りすることは出来ないけどな」
自嘲気味に言うナオキ。それを聞いて、武藤の視線は少し離れた場所にいる少女に向いた。
少女は明穂に車椅子を押してもらいながら、何かを話しているようだった。
「妹さん、足を?」
「ああ。数年前に交通事故でな」
そうか、と武藤は呟く。
「実は足だけじゃ、ないんだよ」
ナオキは諦めたような笑いを浮かべながら、頭を掻く。
「あいつ、『 』って名前なんだけどさ」
ナオキの言葉の中には、聞き取れない音があった。
何も言わなかったわけではない。
ただナオキの放った言葉は声にならずに、一種のノイズとして聴覚へ飛び込んだ。
瞬間、武藤は理解する。
「まさか、君の妹は」
「そのまさかだ」ナオキは言う。「妹はもう、名前が『繭化』してしまっている。」
「名前が、繭化……」
不思議に思いながら、武藤はその言葉を反芻する。
武藤の導き出した理論で考えると、ナオキの妹の名前が繭化するということはほぼ考えられない。それはつまり、武藤理論が間違っていることを示している。武藤は打ちひしがれる思いになりながら、それでも平静を装って額に手を当てる。
「繭化で名前が奪われるなんてことは、今まで聞いたことがない」
「俺も繭化の事はよく分からん。武藤……って言ったか。アンタ、繭化について詳しいのか?」
「多少はね」武藤は答える。「ただ、詳しいと言っても全て憶測の域を出ない。繭化によって消えていく人たちを看取り続けてきた結果を、淡々と記憶しているだけだ」
「辛くは、ないのか」
「ないよ。元々家が葬儀屋だったから、人が消えることに抵抗はない。どちらかというと恐怖とか悲しみを覚えるのは、繭化のことを知らずに死んでいく人々が星の数ほどいる、という事実かな」
「……それで、アンタは繭化の治し方を知ってるのか」
ナオキのその言葉を予期していたのか、武藤の動きがぴたりと止まる。
「知ってるなら教えてくれ。頼む。俺は……俺はこのまま妹が繭化してしまうんじゃないか、怖いんだ」
武藤の前に跪き、ナオキは教えを請う。
「なあ、教えてくれよ! どうしたら妹を繭化から救えるんだ! 教えてくれ!」
「……僕も出来ることなら、そうしてあげたい」
遠くで明穂と話しているナオキの妹を、武藤は見遣る。
屈託で、純朴そうな少女だ。見たところ、兄であるナオキに逆らっている様子も見えない。明穂とすんなり相容れているところから、心が広く、とても寛大な性格であることは間違いない。
武藤は考えた。
あの子はきっと、何でもかんでも貪欲に欲しがるような、子じゃない。
“だからこそ繭化に陥ったのだ”。
「だけど、きっと無理だ。残酷な話になるけど、君の妹では恐らく繭化には抗えない」
「そんな……どうして、どうしてそんなふうに決め付けるんだよ!」
ナオキは思わず立ち上がって、武藤の襟首を引っ掴む。
「お前も、あの明穂っていう奴も! 繭化の蔓延する世界で、悠々と生きてるじゃねえか! それはつまり繭化を防ぐことが出来てるからだろ! その方法をちょっと教えてくれりゃあいいんだ、頼むよ」
「いいかい? そもそも繭化っていうのは、いわゆる自然界の淘汰作業みたいなものなんだ」
言葉を無視し、武藤は言う。
「白亜紀はいつか知らないけど、恐竜が氷河期になって滅びたように、人間も繭化によって滅びる。両者の違いは死滅させる現象だけだ。恐竜を殺すなら凍りつく寒さを、人間を殺すなら繭化をと、神が選択したんだよ」
「……じゃあ、繭化ってのは避けられない現象だって、言いたいのか」
「そういうことだ。僕も明穂も早かれ遅かれ、いずれは繭となって淘汰されていくだろう」
「だったら、完全に繭化するのを遅らせるだけでもいいんだ」
いつの間にか明穂と少女が戻って来て、二人のことを遠巻きに眺めていた。
それに気付いているのか、そうでないのか、ナオキは泣きそうになりながら言い募る。
「俺は少しでも長く、一秒でも妹の側に居てやりたいだけなんだ。頼むよ。この通りだ。頼む、頼む」
「お兄ちゃん。もう、いいんだよ」
土下座して懇願するナオキの元に、名前を失くした妹が近寄る。
「私、幸せだよ。お兄ちゃんがそう思ってくれるだけで、幸せだよ」
ナオキは武藤から、手を離す。
口がわずかに動いていた。
言葉にならない名前を、呼んでいた。
「お兄ちゃんがいてくれるなら、私もう何も、」
武藤は目を細めて、少女を見る。それだけは――――それだけは、絶対に。
「――――何も、要らないから」
言ってはいけない、言葉なのだ。
「子どもっていうのは、希望そのものだ」
林の中を歩きながら、うわ言のように武藤は言い続ける。
「昔のイギリスでは、子どもたち誰もが未来を支えることを祈って、寝る前の挨拶に『おやすみ、ニューイングランドの王たち』と言っていたらしい。誰もが国の王に、国を支える力になれることを願って」
「だから希望を捨てるな、って言いたいの?」
「僕は完成した人間じゃないから、そんな偉そうなことは言えない」
武藤は平板に言う。
「だけど、これで十分だ、これで満足だなんて感情を持ってはいけない。繭化を受け入れてはいけない。生きることを諦めてはいけない。君も分かってるだろう、明穂」
「……“理由を失ったものから、神は繭の糸を絡み付けていく”」
「そう。いつか君に教えたことだ」
「憶えてるよ。だから私はこうして立っていられる。それに」
明穂は、武藤の隣に並びながら。
「君がそう望んだから――――私は今、生きているんでしょう?」
遠く後ろのほうから、何かが羽撃く音が聞こえた。
■
ある時、僕は望んだ。
愛した少女との決別が出来ない僕は、強く望んだ。
世界は望みに応じた。
きっと誰にも分かることのない、かすかな代償とともに。
少年は名を、ナオキと名乗った。
「ということはつまり」武藤はナオキが取り出した折りたたみ椅子に腰掛けながら言う。「君たち兄妹も、生まれ育った街が繭化によって壊滅状態に陥ったから、こうして世界の終わりに逃避行をしているわけだね」
「つっても、アンタらみたいに原付でひとっ走りすることは出来ないけどな」
自嘲気味に言うナオキ。それを聞いて、武藤の視線は少し離れた場所にいる少女に向いた。
少女は明穂に車椅子を押してもらいながら、何かを話しているようだった。
「妹さん、足を?」
「ああ。数年前に交通事故でな」
そうか、と武藤は呟く。
「実は足だけじゃ、ないんだよ」
ナオキは諦めたような笑いを浮かべながら、頭を掻く。
「あいつ、『 』って名前なんだけどさ」
ナオキの言葉の中には、聞き取れない音があった。
何も言わなかったわけではない。
ただナオキの放った言葉は声にならずに、一種のノイズとして聴覚へ飛び込んだ。
瞬間、武藤は理解する。
「まさか、君の妹は」
「そのまさかだ」ナオキは言う。「妹はもう、名前が『繭化』してしまっている。」
「名前が、繭化……」
不思議に思いながら、武藤はその言葉を反芻する。
武藤の導き出した理論で考えると、ナオキの妹の名前が繭化するということはほぼ考えられない。それはつまり、武藤理論が間違っていることを示している。武藤は打ちひしがれる思いになりながら、それでも平静を装って額に手を当てる。
「繭化で名前が奪われるなんてことは、今まで聞いたことがない」
「俺も繭化の事はよく分からん。武藤……って言ったか。アンタ、繭化について詳しいのか?」
「多少はね」武藤は答える。「ただ、詳しいと言っても全て憶測の域を出ない。繭化によって消えていく人たちを看取り続けてきた結果を、淡々と記憶しているだけだ」
「辛くは、ないのか」
「ないよ。元々家が葬儀屋だったから、人が消えることに抵抗はない。どちらかというと恐怖とか悲しみを覚えるのは、繭化のことを知らずに死んでいく人々が星の数ほどいる、という事実かな」
「……それで、アンタは繭化の治し方を知ってるのか」
ナオキのその言葉を予期していたのか、武藤の動きがぴたりと止まる。
「知ってるなら教えてくれ。頼む。俺は……俺はこのまま妹が繭化してしまうんじゃないか、怖いんだ」
武藤の前に跪き、ナオキは教えを請う。
「なあ、教えてくれよ! どうしたら妹を繭化から救えるんだ! 教えてくれ!」
「……僕も出来ることなら、そうしてあげたい」
遠くで明穂と話しているナオキの妹を、武藤は見遣る。
屈託で、純朴そうな少女だ。見たところ、兄であるナオキに逆らっている様子も見えない。明穂とすんなり相容れているところから、心が広く、とても寛大な性格であることは間違いない。
武藤は考えた。
あの子はきっと、何でもかんでも貪欲に欲しがるような、子じゃない。
“だからこそ繭化に陥ったのだ”。
「だけど、きっと無理だ。残酷な話になるけど、君の妹では恐らく繭化には抗えない」
「そんな……どうして、どうしてそんなふうに決め付けるんだよ!」
ナオキは思わず立ち上がって、武藤の襟首を引っ掴む。
「お前も、あの明穂っていう奴も! 繭化の蔓延する世界で、悠々と生きてるじゃねえか! それはつまり繭化を防ぐことが出来てるからだろ! その方法をちょっと教えてくれりゃあいいんだ、頼むよ」
「いいかい? そもそも繭化っていうのは、いわゆる自然界の淘汰作業みたいなものなんだ」
言葉を無視し、武藤は言う。
「白亜紀はいつか知らないけど、恐竜が氷河期になって滅びたように、人間も繭化によって滅びる。両者の違いは死滅させる現象だけだ。恐竜を殺すなら凍りつく寒さを、人間を殺すなら繭化をと、神が選択したんだよ」
「……じゃあ、繭化ってのは避けられない現象だって、言いたいのか」
「そういうことだ。僕も明穂も早かれ遅かれ、いずれは繭となって淘汰されていくだろう」
「だったら、完全に繭化するのを遅らせるだけでもいいんだ」
いつの間にか明穂と少女が戻って来て、二人のことを遠巻きに眺めていた。
それに気付いているのか、そうでないのか、ナオキは泣きそうになりながら言い募る。
「俺は少しでも長く、一秒でも妹の側に居てやりたいだけなんだ。頼むよ。この通りだ。頼む、頼む」
「お兄ちゃん。もう、いいんだよ」
土下座して懇願するナオキの元に、名前を失くした妹が近寄る。
「私、幸せだよ。お兄ちゃんがそう思ってくれるだけで、幸せだよ」
ナオキは武藤から、手を離す。
口がわずかに動いていた。
言葉にならない名前を、呼んでいた。
「お兄ちゃんがいてくれるなら、私もう何も、」
武藤は目を細めて、少女を見る。それだけは――――それだけは、絶対に。
「――――何も、要らないから」
言ってはいけない、言葉なのだ。
「子どもっていうのは、希望そのものだ」
林の中を歩きながら、うわ言のように武藤は言い続ける。
「昔のイギリスでは、子どもたち誰もが未来を支えることを祈って、寝る前の挨拶に『おやすみ、ニューイングランドの王たち』と言っていたらしい。誰もが国の王に、国を支える力になれることを願って」
「だから希望を捨てるな、って言いたいの?」
「僕は完成した人間じゃないから、そんな偉そうなことは言えない」
武藤は平板に言う。
「だけど、これで十分だ、これで満足だなんて感情を持ってはいけない。繭化を受け入れてはいけない。生きることを諦めてはいけない。君も分かってるだろう、明穂」
「……“理由を失ったものから、神は繭の糸を絡み付けていく”」
「そう。いつか君に教えたことだ」
「憶えてるよ。だから私はこうして立っていられる。それに」
明穂は、武藤の隣に並びながら。
「君がそう望んだから――――私は今、生きているんでしょう?」
遠く後ろのほうから、何かが羽撃く音が聞こえた。
■
ある時、僕は望んだ。
愛した少女との決別が出来ない僕は、強く望んだ。
世界は望みに応じた。
きっと誰にも分かることのない、かすかな代償とともに。